2019.04.18

スイスの自殺ほう助の現状とさらなる自由化をめぐる議論
スイスでは、最初の自殺ほう助団体が設立されてから、すでに35年以上がたち、今日、自殺ほう助について話すことはもはやタブーではなくなりました。タブー視されなくなっただけでなく、2011年チューリヒ州の住民投票で、84.5%という圧倒的多数が自殺ほう助を支持(正確には、自殺ほう助の禁止案に反対)したことが端的に示すように、自殺ほう助はスイス社会において、今日、人生末期の選択肢の一つとして容認されています。その一方、2014年ごろから、高齢者の自殺ほう助をめぐり、新たな議論が巻き起こっています。
今回は、スイス社会において、現在、自殺ほう助がどのように位置づけられ、今後どこへ向かおうとしているのかについて、推進する人々やその主張だけでなく、自殺ほう助に対応・対処するという課題に直面している医師、介護施設、家族の対応や状況についても注視しながら、探ってみたいと思います。
自殺ほう助が認められているスイス
スイスでは、利己的な理由で人に自殺をうながしたり、自殺ほう助を行なった場合に処する法律がありますが(刑法115条)、利己的な目的ではない自殺ほう助は処罰の対象になっていません(ただし容認する法律がとくにあるわけではありません)。
このような状況下、1982年に、世界初の自殺ほう助団体「エグジットExit」が設立され、そのあと、スイス在住の人だけでなく自殺ほう助を希望する外国人のほう助も行う「ディグニタスDignitas」(1998年設立)など、ほかにも類似する自殺ほう助団体が設立されてきました。スイスでの自殺ほう助は、現在これらの自殺ほう助団体を通して行われています。
自殺ほう助についての詳細な法的規定がないため、医学アカデミーは2004年に「人生末期の患者の看護」という医療倫理指針(SAMW, 2004)を定め、2009年にはエグジットとチューリッヒ検察庁との間で自殺ほう助に関する協定がつくられました。これらは(医療倫理指針は現在までに主要でない部分が改正されてはいますが)今日まで、スイス全土の自殺ほう助の標準的な規定として採用されています(Wehrli, 2015, S.266)。
自殺ほう助を希望する場合、自殺ほう助団体の会員となったあと、改めて自殺ほう助を願いでます。これを受けて、担当スタッフや関連する専門家は緩和ケアなどの医療行為や治療、社会的な支援などで、自殺ほう助に変わる代替策がないかを検討し、これらの情報を会員に提供したり、相談にのります。
その後も願望に変化がない場合、二回医師の診断を受け、自分で判断できる状態(精神的な疾患や認知症などの症状があっても、自分で判断できるとされれば可能)か、自殺願望が一時的・衝動的なものでないか、病気などに起因する重い(耐え難い)苦しみがあるか等の項目から、自殺ほう助が可能かが審査されます。
医者が自殺ほう助が可能と判断した場合、薬剤(致死薬)であるペントバルビタールナトリウムが処方されます(ちなみに、医師が自ら致死薬を与える積極的安楽死はスイスでは違法行為です)。このあと自殺ほう助を本当に進めたい場合、団体スタッフと改めて連絡をとり、スタッフが医師の処方箋で入手した薬を服用する日時と場所を決定します(医者の診断結果は6ヶ月間有効)。
自殺ほう助団体はすべて非営利団体ですが、(スイス人より費用がかかる)外国人の受け入れ有無や、(スタッフの報酬の有無など)運営の仕方に違いがあり、自殺ほう助にかかる費用は異なります。もっとも負

自殺ほう助がもたらす自殺抑止力
スイスでは自殺ほう助団体の会員数も、自殺ほう助を介して命を断つ人の数も、年々増加の一途をたどっています。
連邦統計局の報告書(BfS, 2014)によると、スイスにおける(外国人で自殺ほう助を受けた人を除く)自殺ほう助で亡くなった人の数は、2008年から2014年の間で、253人から742人と約3倍に増加しています。2010年から2014年の期間に自殺ほう助を受けた人の圧倒的多数は、がん(42%)や神経変性疾患(14%)などの重篤な病気を患っており、うつ病患者(3%)や認知症の患者(0.8%)はわずかでした。
自殺ほう助が増える一方、首吊りや銃殺などの暴力的な自殺件数は、過去20年減り続けています。1980年代半ば、自殺者の数は年間1600人であったのに対し、1995年には1400人、2014年には1029人に減少しています。自殺の減少と自殺ほう助の増加の間の関係が明確になっているわけではありませんが、自殺願望者の一部が、自殺ほう助団体を通して自殺を実施していると推測されています。
また、自殺ほう助団体の会員となった人たちの間で、会員になったあとに自殺をとどまる、いわゆる「自殺抑制効果」と思われるケースも多数報告されています。
例えば、ディグニタスでは、二回の医者の診断で暫時的な許可がでることを、暫時的な「青信号」と呼びますが、この「青信号」がでたあと、70%の人からはその後一切連絡がこなくなり、16%の人は自殺ほう助の必要なくなった旨の連絡をしてくるといいます。そして最終的に自殺ほう助を望むのは、会員の3%に留まるといいます(Dignitas, Lektion)。
エグジットに登録した人の間でも、よく話し合いをした結果、自殺ほう助を受けるのをやめるケースが多く、全体の80%の人たちは、緩和ケアなど別の解決策を最終的に選択しています(Mijuk, 2016)。
老人ホームや介護施設(以後は、これらを合わせて「ホーム」と表記します)でも、居住者が自殺ほう助の会員になることは、実際に実行するためというより、むしろこれでなにかあったら頼めばいい、という安心感を得るための一種の「保険」のようなものとなっているようだ、という意見を聞きます。
このような状況をふまえて、ディグニタスの会長ミネリLudwig A. Minelliは、自分たちのやっていることが、「自殺ほう助よりもずっと広いもの」であり、自殺予防にもつながっていると強調します。「包括的に相談することができ、困難な状況でも選択肢があれば、人はプレッシャーやストレス、苦悩が減り、これによりよりよく長く生きることができる」(Stoffel, 2017)というのが持論です。
このため、外国人会員のそれぞれの祖国で自殺ほう助も受けられるようになり、「我々がしていることが、医療や社会システムに統合されるようになれば、ディグニタスやエグジット、ほかの同様の組織は安心して消え去ることができる」のであり、「ディグニタスの目標は、いつかなくなることだ」(Stoffel, 2017)とも言います。
ちなみに、2014年の時点で自殺ほう助による死亡は、全体の死亡の1.2%にすぎませんが、老年医学専門家ボスハルトGeorg Bosshardは、自殺ほう助が占める死因の割合はこのあとも上がり、10年後には(自殺ほう助も医師の積極的安楽死も認められている現在のベルギーのフランドル地方と同レベルの)5%程度になるのではないかと予想しています(Mijuk, 2016)。
キリスト教会の対応
社会に自殺ほう助を許容する雰囲気が広がっていくなかで、キリスト教会側はどのように対応してきたのでしょうか。
プロテスタント教会は自殺ほう助を直接支援こそしませんが、エグジットの共同設立者の一人ジクRolf Sigg はもともとプロテスタント教会の牧師でしたし、個人的に自殺ほう助への理解を示したり、退職後に関わる教会関係者が、これまで少なくありませんでした。
2016年以降は、ローザンヌを州都とするフランス語圏のヴォー州の教会を皮切りに(Rapin, 2017)、いくつかの州のプロテスタント教会で、牧師たちに、自殺ほう助を選択した人々に最後まで寄り添うことを薦める方針が打ち出されるようになりました(Reformierte Kirchen, 2018)。
そこでは、キリスト教の信仰上、生きることのほうが重要であり、自殺ほう助はあくまで「特別な場合であり、決して通常の死ではない」という基本見解を示しつつも、自殺ほう助を判断することに反対せず、そのような決意を尊重する立場が示されています。そして、牧師には、最後まで絆を大切にし、寄り添い、立ち会うことを推奨します。ただし、最終的な判断は牧師たち自身にまかせるとして、義務とはしていません。
これに対し、カトリック教会は自殺ほう助を容認する見解を公式に示していないどころか、反対する姿勢を当初から変えていません。2019年からスイス司教協議会会長に就任したゲミュア Felix Gemürも、「自殺ほう助はひとつのビジネスになりつつある」と強く批判します(Boss/ Rau, 2018, S.17)。
とはいえ、現代のスイス社会においては、このような教会側の見解はほとんど影響力がないとされます(Mijuk, 2016)。これは、自殺ほう助の問題に限ったことではなく、現在、スイスでは、宗教の影響力が社会全般で希薄になってことによるものと考えられます。
都市部では、キリスト教信者数が都市住民の半分以下となって久しく、毎年さらにスイス全体で約4万人がキリスト教会を脱退しています。2017年に欧米各国を対象にした比較調査では、スイスのキリスト教徒(プロテスタント教徒およびカトリック教徒)の間で、宗教が重要だと考える人や実際に祈祷などの宗教的な行為をする人が1割か、それ未満にとどまり、ほかの国と比べても非常に低い数値でした(穂鷹、2017年)。
自殺ほう助に関わる当事者以外の人々
ところで、自殺ほう助は、自殺ほう助を受ける人とそれを手助けする自殺ほう助団体だけで完結するものではありません。これらの人を言ってみれば当事者とすると、当事者以外の人たち、自分の意志に関係なく、自殺ほう助に関わるようになった人たちは、どのように気持ちを抱き、対応しているのでしょうか。
・医師
スイス医学アカデミーの2013年の調査(SAMW, 2014)によると、アンケートに回答した全体の4分の1にあたる1318人の医師の意見は、三つに分かれました。一番多かったのが基本的に自殺ほう助を許容でき、個人的に自殺をほう助するような状況を想定することができるという意見で、半分近い医師がこう回答しました。自殺ほう助を認めるが、自分ではしないと回答した人は4分の1、自殺ほう助を基本的に否定する人は5分の1でした。
一方、具体的な状況で自殺のほう助をする準備ができている、と答えたのは全体の4分の1にとどまりました。この一見矛盾しているようにもみえる回答から、多くの医師たちは、一般論として医師が自殺ほう助に関与する必要性を認めつつも、個人的には躊躇が強いことが伺われます。
このような医師の態度には、複数の理由があると思われますが、医療倫理指針はあっても、実際に自殺願望の患者を前にして、なにが「公平」で「中立」で「正しい」医師の立場や判断になるのかがいまだ明確とはいえないことが、最大の理由ではないかと思われます。
難しい立場に立たされている医師の現状は、医師自身の以下のような言葉からもうかがわれます。「今日医師は、ある種の「ダブルブラインド(二重盲検法)」に直面しているように感じている。一方で自分の意見を差し控えるべきであるとされ、他方で、「共同決定」という名目で患者たちが自律的に決定できるように、思いやりをもって積極的に関わり、それを容認いていく役割が期待されている。医者の権威は強く限定されたのと同時に、死が医療対象化したことによって、強化されたことになる。」(Zimmermann, 2017, S.731)
・家族
自殺ほう助団体の言動についてはメディアの注目度が高く、その主張を聞く機会も多いですが、自殺ほう助で家族をなくした人々の声を聞くことはまれです。
これは、家族の状況を考えると不思議ではありません。どんなかたちであれ家族を失った人の喪失感は大きく、公的に意見を述べるというエネルギーやモチベーションを持ち合わせている人は少ないでしょう。まして、故人の自殺ほう助に個人的に反対であった場合、故人の意志を尊重したい気持ちと自分の気持ちの間に葛藤も生まれ、それについて語る口はさらに重たくなることでしょう。
しかし、身内を自殺ほう助で失った家族の心境が軽視されていいわけではないでしょう。このため、自殺ほう助の家族への影響について調べた数少ない研究として、チューリヒ大学の臨床心理学者ヴァグナーBrigit Wagnerの調査結果は示唆に富みます(Wagner, 2012)。
ヴァグナーは、調査時点から遡って14〜24ヶ月前に、家族や近しい友人の自殺ほう助に立ち会った人を対象に調査をし、85人の回答内容を分析しました。この結果、13%がPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状、6.5%がその前段階の症状を示し、うつ病の症状と判断された人は16%でした。自殺ほう助で家族を無くして2年近くたっても、PTSDやうつ病に苦しんでいる家族が4割近くいることになります。
この調査の回答率が51%と低かったため、これだけで全体像を判断するは難しいものの、自殺ほう助が立会った人にとって心理的に長く重い負担になっていると著者は指摘します。
これに対し、エグジットで長く自殺ほう助に関わってきたフォークとHeidi Vogtは、協会としては早い段階で家族と連絡をとるよう会員にうながすなど、家族への一定の配慮をしており、亡くなって2〜4週間したあとにも家族に連絡をとっている。現実に、半分以上の家族は協会とのコンタクトを受け入れており、うつ病やトラウマになるケースは自分たちのところではほとんどない、と反論します。また、自然死で家族がなくなった場合の同様の調査がないため、この研究だけで内容を評価することは難しいとします(Freuler, 2016, Exit wehrt sich, 2016)。
デグニタスでも、自殺ほう助を願う人たちに、家族や友人の承認をできるだけ求めるようにうながしたり、自殺ほう助の日程を知らせ、家族や友人に最後まで立ち会ってもらうことで、喪失を受け入れやすくしたり、別れを可能にするなど対処をしています。
自殺ほう助団体が家族への配慮をし、支援活動も行なっているのは確かでしょう(柴嵜、59−60頁)。とはいえ、自殺ほう助団体側から提供されるそのような配慮や救済事業が、実際にどれだけ自殺ほう助による死を家族が受け入れる助けになっているかは、別問題として残ると思われます。
・ホーム
現在、スイスにはホームが約1600施設あり、全国で約10万人の収容が可能な状況が整っています。以前は、70歳を過ぎたくらいで、健康でもホームに入ってくるような人がかなりいましたが、今日は、在宅が不可能になってから施設に入ってくる人がほとんどであるため、ホーム居住者の高齢化が進んでいます。現在、スイスのホーム入居時の年齢は平均して84から86歳です。つまり、多くの入居者にとって、ホームは事実上終の住処となっています。
ホームでの自殺ほう助事情は州によって異なります。自殺ほう助を権利としてみとめ、居住者が希望すればホームでの実行を拒否できないとする州もあれば、各施設に許可するか否かの決断を委ねている州もあります。ホームでの自殺ほう助を全面禁止にしている州も少ないですがあります。2014年、エグジットによる自殺ほう助583件のうち60件がホームで行われました。
大勢の人が共同で暮らし、同室に複数で住んでいることも多いホームでは、自殺ほう助がまわりに与える影響も大きくなりがちです。
自殺ほう助後に検察官や警察が現場検証に訪れるため、普段の穏やかな雰囲気が乱れるだけでなく、自分が生きる意味を感じられなかったり、ほかの人に迷惑をかけているといった気持ちをもつ居住者に、不要な圧力や不安が生じないように、通常以上に気遣いが必要となります。自然死でなくなる居住者と異なり、自殺ほう助で亡くなった居住者については、居住者への通知を最小限にとどめる処置をしているところもあります。
検察官の現場検証に立会うなど、通常業務以外の負担を強いられるだけでなく、担当する居住者が自殺ほう助したことで個人的に責任を感じてしまう場合もある介護スタッフにも配慮が必要です。
国内に2600ヶ所の老人ホームと介護施設をもつ統括組織クラヴィヴァCuravivaが行なったルツェルン州の匿名のアンケートでは、ホームの3分の1が自殺ほう助に反対、それについて話す準備がまだできていないと回答しています。ほかの3分の1は社会の圧力のため、このことについて話すようになったと答え、残りの3分の1はすでに自殺ほう助を行なった実績がありました(Odermatt, 2018)。

自殺ほう助の自由化を求める動き
・新たな議論
2014年ごろから、自殺ほう助の話題は問題領域を移して、新たな議論をスイス社会に巻き起こしています。それを一言で言えば、現在の医療倫理指針では対象者を末期患者に限っていますが、健康上、とくに問題がなくても死にたいという強い願望がある人に対しても、自殺ほう助を公式に認めるべきだとする、自殺ほう助のさらなる自由化を求める動きと、それについての社会の反響です。
ここで、議論の中心になっているのは、一般の健康な(病気を患っていても末期と診断されていない)高齢者たちです。2014年5月のエグジットの総会では、高齢者が制限なく自由に死ぬことができる権利を擁護・促進することを規約にかかげることを、ほとんど満場一致で決めました(GV stimmt, 2014)。
エグジットは、これを「高齢の自由死Altersfreitod」の権利と位置づけ、その権利をより円滑に行使できるように、高齢者には、若い人の自殺ほう助の際に不可欠とみなされている必要な医学的な審査を簡略化することや、強い痛みについても厳しい証明を必要としないことも求めています。
・「高齢の自由死」議論を背後で支える人たち
「高齢の自由死」問題に自殺ほう助団体が積極的に取り組む背景には、そのような考えを支持し、強力に推し進めるようとする人々の存在があります。一体、誰なのでしょう。
結論を先に言うと、高齢者自身です。高齢者の自殺ほう助への関心の高さは、以下の統計結果からもうかがえます。スイス健康観測所(Obsan)が、2014年にスイスの三つの語学圏(ドイツ、フランス、イタリア語圏)の1812人の55歳以上の人を対象に電話で行なった調査によると、4%がすでに自殺ほう助団体の会員となっており、さらに今後会員になる意向の人たちは8.5%でした(Obsan, 2014)。また実際に、2014年に自殺ほう助を受けた742人の94%という圧倒的多数が55歳以上です。
とりわけ、「高齢の自由死」への関心が強いとされるのは、まだ比較的若い、通称「ベビーブーマー世代」と呼ばれる人たちです。この人たちは、1945〜65年ごろ、ようやくヨーロッパに平和がおとずれてまもない時代に生まれ育ち、右肩上がりに経済成長する社会で栄養状態もよく健康に育ち、1968年には若者として権威主義的な社会構造に対決し、そのあとも社会の改革を目指してきた世代です。
この世代は、それまでの高齢者たちと、健康状態や教育水準、家族との関係など、ライフスタイルのさまざまな側面において顕著な違いがあるとされます。発達心理学者で高齢者研究でも名高いペリック=ヒエロPasqualina Perrig-Chielloは、これまでの高齢者(現在約80歳以上の高齢者)がなにをしていいかを考える世代であるのとは対照的に、新しい高齢者たちは、どこまでなにができるかを追求する世代だ、と端的に表現しています(穂鷹、2016)。
今回のテーマに関連させて言うと、社会やだれかに意見を押し付けられるのを嫌い、自分で決めることに高い価値を置く、ということが重要であり、自分の死に方についても、自分で決められることを重視し、その一環として「高齢の自由死」という自殺ほう助の自由化を求めていると考えられます。

「高齢の自由死」を望む主要な理由
ところで、差し迫った健康上の理由がなくても死を選べる「高齢の自由死」の権利を主張する人たちは、具体的にどのようなことを理由にかかげ、自然な死に方ではなく「自由死」を選択したい、あるいは、それを自由化する必要性があると考えているのでしょうか。主要な理由として三つがあげられます。
・苦痛を避けるため
まず、これまでの自殺ほう助の理由でもあった、物理的な苦痛への忌避です。これまで、ほかの世代の同年齢の頃に比べ、良好な健康状態を保ってきたベビーブーマー世代であるだけに、健康状態の悪化を危惧する気持ちがことのほか強いのかもしれません。
しかしこれについては、2010年代以降、緩和ケアを行う施設も増えており、緩和ケアが有力な代替案になりつつあります。スイスのホームでは25%が、自分たちの核となる課題として、理想として緩和ケアを掲げ、実際にホームの40%が緩和ケアを実現か、するための取り組みを現在しています(Seifert, 2017, S.15)。ちなみにここでの緩和ケアとは、たんなる痛みの緩和だけでなく、医学、介護、社会的、宗教的、心理的なケアも含めた包括的なものをさします。
スイスよりも早くから緩和ケアに取り組んできたドイツで、国内の医師すべてに配布されている週刊誌『ドイツ医師報』に、三人の緩和ケア専門医師が自殺願望のある患者の気持ちやその対処についてまとめているので、以下、抜粋します。
「緩和ケアではあまりないが、患者が死にたいと言うことがある。しかしこれには慎重に対処すべきである。一方で、医者が患者よりもよくわかっていると考え、患者の苦悩や絶望をしっかり捉えていない危険があるので注意しないといけない。他方、重い病気をかかえる患者がそのようなことを伝えてきたからといって、必ずしもそれは死を切望しているのではなく、堪え難い状況を終えたいという希望である場合が多い。」
「ほかの人に迷惑をかけたくないという人もいる。そのようなテーマをタブーにしてはならず、医師や介護スタッフやほかの関係者でチームとして、そのような希望を聞き、取り組むべきである。死の願望の表明は、むしろ信頼のあらわれとみることもできる。そういうことを考えていい、話せる、ということだけで、患者の気持ちはずいぶん楽になり、緩和チームと患者との関係を豊かにするものともなりえる。」
「死の願望は、それだけを単独でみるのでなく、二つの相反する価値を同時に含んでいる状態を示しているとみることができる。そこから、二つの希望、もうすぐ人生を終えたいという希望と、もっと生きたいという希望が並存しているという状況が生まれるかもしれない。緩和ケアは死にゆく人々を最善のかたちで支援すること、同時に死ぬことを阻止するのではない。緩和ケアは直面する死における助けを提供するが、死への助けではない。」(Friedemann, 2014)
ちなみに、オランダでの研究によると、自殺ほう助の場合と異なり、緩和ケアが家族に与える悪い影響は見当たりませんでした(Freuler, 2016)。
・人生の総決算として
目前に迫る苦痛を回避するということよりも、「もう十分生きた」という人生への充足感や、将来予想される自分がのぞまない状況全般を回避したいといった思慮から、「自由死」を望む場合もあります。この場合、人生末期への悲観(希望がもてないこと)と、それを未然に防ぎたいという二つの強い考えが、とりわけ大きな影響を与えているようです。
雑誌『シュヴァイツァー・イルストリエルテ』が1004人を対象に電話で行ったアンケートで、自分が認知症になったら「自由死」(スイスの文脈でいうと「自殺ほう助」など意図的に死期を早めることを意味します)を選ぶことを想定できるとかという質問には、43%が「はい」と回答しています。また、認知症に対する悲観的な見方が、年齢が上がるほど強まっていました。認知症になっても生きる価値があるか、という質問に対して、価値があると回答した人が、55歳以上のスイス人で49%、若い世代(35歳から54歳が54%、15歳から34歳が69%)に比べ、最低の割合でした(Enggist, 2016)。
このアンケート結果をみると、認知症をのぞましくないものととらえ、それが進行する前に、自分で死を決断するのがよいと(少なくとも想定)する人が、とくに高齢者にかなりいることがわかります。このような志向は、「自由死」の同義語としてしばしば使われる「総決算の自殺Bilanzsuizid」という言葉にも表れているように思われます。この言葉には、人生を長い帳簿になぞらえ、総決算をマイナス決済で終わらせたくない、そのために、事前に自分で人生を終わらせる、というニュアンスが感じられます。
・経済的な配慮
チューリヒ大学の社会学者ヘプフリンガーFrançois Höpflingerは、健康、教育、経済状況にも恵まれてきたスイスの若い高齢者世代は、現在、経済的に自立しているのが一般的だが、今後、介護が必要になると、年金や貯蓄が十分ではなくなり、良好な状態が急激に悪化することもありうる。そして、実際にそのように高齢者にも認識されている。しかし、自分たちが病気や介護が必要になることで、これまではなかったような家族への財政的な重荷となることは避けたいと考える人は多く (Wacker, 2016)、そのような人たちにとって、自殺ほう助という考えがちらつくことは考えられる (Kobler, 2015.)、といいます。
個人の経済的な状況が要因となって、自殺ほう助に気持ちが傾く可能性があるというこの指摘について、自殺ほう助団体の中では意見が別れています。エグジットでは、自分たちの顧客には、経済的な考慮はまったくなんの役割も果たしておらず、自分たちの人生の最後を自分で決めたいという強い意思を本人や有しているかいなかが問題だ(Wacker, 2016)とするのに対し、デグニタスのミネリは、ホームで希望もなく長期滞在するのを回避し、それに必要な費用を孫の教育費用に当てたいという人がいれば、「それは分別があり賞賛に値する」と、むしろ肯定しています(Gute Arbeit, 2012)。
自殺ほう助の自由化に対する社会の反響
・分裂する医師の見解
「高齢の自由死」の議論を前に、医者たちはどう対応しているのでしょう。前述の2014年の医師を対象にした調査では、認知症の人に対して自殺ほう助を認める見解に対し、賛成は10%、どちらかといえば賛成が19%。反対は41%、どちらかといえば反対が24%でした。高齢の健康な人の自殺ほう助について賛成票はさらに少なく、賛成(8%)とどちらかと言えば賛成(12%)とあわせても2割にすぎず、逆に、反対(56%)、どちらかといえば反対(20%)としたのは8割近い人たちでした(SAMW; 2014, S.1768)。これをみると、「高齢の自由死」について医師の大多数が反対していることがわかります。
一方、2017年において自分たちが関わった自殺ほう助の4分の1が、すでに「高齢者の自由な死」に相当するものだったとエグジットが表明しているように、実際には終末期の患者だけではなく、健康上とくに問題のない自殺希望者にも自殺ほう助がすでに実施されています。厳密に医療倫理指針と協定で定められている標準規定を厳守していれば無理なはずですが、医師の審査・判断という部分がグレーゾーンとなって、倫理指針に背くことが実際には常態化していることになります。
このような倫理指針と現実が乖離する実情を前に、医学アカデミー(SAMW)は、重い腰をあげ、乖離を解消する方針に切り替えます。これまでの医療倫理指針を大きく見直し、終末期の患者に限らず「堪え難い苦悩」がある人全体を対象にするという、指針の緩和を2018年5月に打ち出しました。
しかし、医学アカデミーにとって予想しなかったことがおきます。医師の職業規定を作成し、スイスの全医師に通達する役割を果たすスイス医師会(FMH)が、同年10月、医療倫理指針の改定版を職業規定に組み入れることを拒否したのです。
スイス医学アカデミーとスイス医師会は、本来、対立する立場でなく、補い合うかたちで機能している組織であり、スイス医学アカデミーが定める医療倫理指針はこれまではなんの問題なく職業規定に組み入れられてきました。つまり、今回の事態はきわめて異例であり、医師の間でも、自殺ほう助をどこまで認め、なにを基準とするかについて、現在、意見が大きく割れていることを物語っているといえます(Brotschi, 2018)。
ちなみに、自殺ほう助団体は、自由化を拒んだスイス医師会の判断を批判していますが、これまでの医療倫理指針は現在でも有効であるため、これまでと同様のやり方で自分たちの活動を続けています。
一方、自殺ほう助でも緩和ケアでもなく、絶食死を別の選択肢として提唱する医者もでてきました。この方法で死に至るまでは通常三週間かかりますが、徐々に絶食死の事例は増えてきており、断食死をめぐる患者や家族について詳しいザンクトガレン応用科学大学教授フリガーAndré Fringerは、今後、絶食死は「社会の大きなテーマMegathema」になると予想しています(Müller, 2017)。
・新たな懸念
「高齢の自由死」をめぐる議論が続くなか、単なる個々人の決断の自由の問題におさまらず、社会のほかの人々にも見えないプレッシャーを与えたり、社会に望ましくない力学を生みだすなど、社会に波紋を広げる危険性も看過できないとして注視されています。
この点で先鋒に立つのはカトリック教会です。スイスのカトリックの頂点にたつゲミュアFelix Gemürは、現在の自殺ほう助の向かっている方向が、「わたしには、健康で、生産的で、スポーツができ、まだ自分ですべてできる人だけが生きるに値する、そんな風に言っているように思える。これは、我々の社会での、障害を持つ人や弱者、生産的でない人や貧しい人を締め出そうとするひとつの傾向だ」(Boss/ Rau, 2018, S.17)と、警鐘を鳴らします。
スイス医師会の医学雑誌『スイス・メディカル・フォーラム』でも、「経済的な理由で「死にたいと思うべき」圧力が並行して生じて、自殺ほう助が高齢化社会の政治的な装置になる危険性は否定できない」と認めます。そして、高齢者が急増する人口変動に並行して、今後、性急に別の提案をつめていかなくてはならないと提言しています(Zimmerman, 2017)。
いずれにせよ、自殺ほう助の「賛成者でも反対者でも誰もが、人が死ぬ意志にプレッシャーをかけてはいけないということでは、一致していることは確か」(Vollenwyder, 2015)です。ここを議論の起点にして、これまで「自殺ほう助に対してあまりにも肯定的なイメージが持たれ」(Bieler, 2016)、批判や検証が十分でなかったのだとしたら、「高齢の自由な死」の結論を出すことに終始せず、立ち止まり状況を再点検することが、今、スイスに必要なのかもしれません。
おわりにかえて
自殺ほう助をタブー視せず、社会にとって最良の方向を求め、異なる立場の人々が共同で模索しているようにみえるスイスの社会の現状は、一方で非常に真っ当にみえますが、他方、人々の死や高齢についての見解を聞くと、胸中に不穏な気持ちがわいてきます。
自由な死に方を追求するあまり、自分自身の考えに縛られ、自分の生き方や可能性を狭めている人もいるのではないか。そして最終的に自分にとって不自由だったり、不可解な選択肢を選んではいないだろうか、といった疑念がよぎります。
例えば、スイスでは55歳以上の人の約過半数が、認知症になったら生きる価値がないと感じていました。しかし、病気を患うことを「マイナス」とすることを思考の出発点にしなければ、違う結論にいたる人もいるのではないでしょうか。もちろん、高齢になったり認知症が進行することで苦悩や不安が深刻になることを過小評価はできませんが、それらを避けるために早期に自分の手で終焉を迎えるのが適切と考えるのも、ひとつの考えにすぎません。
「高齢の自由な死」とは対照的な考え方をもち、自ら実践している人たちも、同じスイスにはいます。ホームで人生末期の人々を夜に見守るボランティアの人たちはその一例です。介護スタッフが少ない夜から明け方までの約8時間、必要と思われる居住者のところに派遣され、ときには家族のかわりに最後を看取ることもあります。
ボランティアは、居住者たちの、早々に自分で切り上げて終わらせてしまわなかった人たちの人生の終焉を見守り、その時間をいっしょに過ごします。居住者たちが、見ず知らずの他者に付き添われながら臨終に近づいていくその時間を、ボランティアたちは虚しいことや、望ましくないことや、無意味なこととは思っていません。むしろ、死を前にした大切な過程であると考え、そこに自分が立ち会う意義も認めているからこそ、一晩寄り添うという任務を見返りも気にせず自ら買って出ているのでしょう。
このように、人生末期における意味や価値を見出すところやことが人によって違いがあり、自分たちが切り捨てたい負の部分と考えるところにも、違う価値を見出している人たちがいること。それらを意識することは、自分が自分自身の固定的な見解にしばられたり、結論を性急に出さないための、一助になるのではないかと思います。
一人で自分の死について考え込むより、むしろ外にでてほかの人と刺激・交流し合うことも有益でしょう。地域社会のほかの高齢者や世代の異なる住民との間で、助ける側と助けられる側の立場を互いに入れ替えながら考えていくことで、自分が納得するだけでなく周囲も受け入れやすい、人生の終え方がみえてくるかもしれません。
そうして最終的に、自分でどんな答えを出すことが目標で、必要なのでしょうか。倫理学者ビラー=アンドルノNikola Biller-Andornoは、自分の死を個人的に決定することは容認されるべきであるにせよ、ひとつの決まった答えがあるわけではなく、誰もが自分で人生末期を積極的にかたちづくる必要はない。自分で決めずに、医師や家族に委ねるのも可能だといいます。そして「人生末期においてもっとも重要なものは寛容さ」だと強調します(Biller-Andorno, 2015)。
ここでいわれる、人生末期における寛容さとはなんでしょう。緩和ケアや絶食死など、最近新たに注目されるようになった選択肢も含め、さまざまな死のかたちを認め合う社会全体の寛容さがまずあるでしょうが、それだけではないように思います。健康や精神面でアップダウンを繰り返しながら進む終焉までの道のりで、どう生き、どう死ぬべきか。自分のなかで意見が揺れ動いたり、自分の判断に自信がもてなかったり、自分で決めることができなかったりする、そんな(決してこれまでの自分と比べて「自分らしくない」かもしれない)自分自身の在り方を受け入れる寛容さでもあるのではないかと思います。

参考文献・サイト
・Abegg, Andreas, Zur Zulässigkeit der Zürcher Vereinbarung mit Exit. In: NZZ, 25.7.2009, 10:30 Uhr
https://www.nzz.ch/zur_zulssigkeit_der_zrcher_vereinbarung_mit_exit-1.3190195
・Bieler, Larissa M. (宇田薫訳)「死を巡る議論―自殺天国のスイス」、スイスインフォ、2016年07月11日11:00
・Biller-Andorno, Nikola, Torelanz am Lebensende ist das Wichtigste, Zeitlupe, 11/2015, S.17.
・Boss, Catherine / Rau Simone, “Das Zölibar ist kein Dogmat». Bischof Felix Gemür über sexuelle Übergriffen in der Kirchen und das Geschäft mit der Suizidhilfe. In: Sonntagszeitung, Fokus, 8.12.2018, S.15-17.
・Brotschi, Markus, Ärzte wollen Sterbehilfe nur bei Schwerstkranken leisten. In: Tages-Anzeiger, 26.10.2018, S.4.
・Bundesamt für Statistik (BfS), Todesursachenstatistik 2014. Assistierter Suizid (Sterbehilfe) und Suizid in der Schweiz, Neuchâtel, Oktober 2016.
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Themen/Fachthemen/BFS_2016_Suizide_Faktenblatt.pdf
・Dignitas, Lektion, DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben). Mein Weg. Mein Wille.(2018年12月4日閲覧)
https://www.dghs.de/wissen/lexikon-a-z.html?type=0&uid=11&cHash=f32f751ba85725cdef9946fc387aff16
・Exit wehrt sich gegen Vorwürfe,Das Gespräch führte Simone Fatzer, SRF, News, Schweiz, Mittwoch, 30.03.2016, 20:21 Uhr
https://www.srf.ch/news/schweiz/exit-wehrt-sich-gegen-vorwuerfe
・Enggist, Manuela, 43% wollen den Freitod. In: Schweizer Illustrierte, 22.04.2016.
・Fluck, Sarah, «Swiss Option» – Sterben in der Schweiz für 10’000 Franken. In: Der Bund, 4.6.2018.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/geschaeftsmodell-sterben/story/23845130
・Freuler, Regula, Das Leiden der Angehörigen. In: NZZ am Sonntag, 18.5.2016, 10:30 Uhr
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/sterbehilfe-das-leiden-der-angehoerigen-ld.83008
・Friedemann, Nauck et al., Ärztlich assistierter Suizid: Hilfe beim Sterben – keine Hilfe zum Sterben. Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2014; 111(3): A 67–71, arzteblatt.de (2018年11月30日閲覧)
https://www.aerzteblatt.de/archiv/treffer?mode=s&wo=1008&typ=16&aid=152921&autor=Radbruch%2C+Lukas
・“Gute Arbeit soll bezahlt werden“ (Das Interview mit Ludwig Minelli, führte Christian Rath). In: taz, 16.8.2012.
・GV stimmt pro Altersfreitod, Exit, 24.05.2014.
・Hehli, Simon, Warum die Schweiz eine Sterbehilfe-Hochburg ist. In: NZZ, 17.6.2017, 05:30 Uhr
・穂鷹知美「現代ヨーロッパの祖父母たち 〜スイスを中心にした新しい高齢者像」一般社団法人日本ネット輸出入協会、2016年4月8日
http://jneia.org/locale/switzerland/160408.html
・穂鷹知美「対立から融和へ 〜宗教改革から500年後に実現されたもの」一般社団法人日本ネット輸出入協会、2017年10月4日
http://jneia.org/locale/switzerland/171004.html
Kobler, Seraina, Selber entscheiden, «wann genug ist». In: NZZ, 11.3.2015.
https://www.nzz.ch/schweiz/der-tod-wird-gerne-verdraengt-1.18499919
・Mijuk, Gordana,Der Tod gehört mir. In: NZZ am Sonntag, 4.12.2016, 07:48 Uhr
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/zunahme-der-sterbehilfe-der-tod-gehoert-mir-ld.132410
・Müller, Mellisa, Fasten bis zum Tod. In: St. Galler Tagblatt, 15.3.2017, S.23.
http://afringer.ch/blog/fasten-bis-zum-tod
・Obsan(Schweizerisches Gesundheitsobservatoriumの略名) (hg.), Personen ab 55 Jahren im Gesundheitssystem: Schweiz und internationaler Vergleich 2014, Obsan Dossier 43, Neuchâtel 20.November 2014.
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2015/obsan_dossier_43.pdf
・Odermatt, Martina, Lebensende: Statt Sterbehilfe: Luzerner Heime bevorzugen palliative Pflege. In: Luzerner Zeitung, 29.1.2018, 05:00 Uhr
・Rapin, Noriane, VD: Pfarrer müssen beim Suizid nicht anwesend sein, ref.ch: Das Portal der Reformierten, 25. Januar 2017.
https://www.ref.ch/news/vd-pfarrer-muessen-beim-suizid-nicht-anwesend-sein/
・Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Solidarität bis zum Ende. Position des Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zu pastoralen Fragen rund um den assistierten Suizid, 7. Juni 2018.
・SAMW, Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende, Medizinisch-ethische Richtlinien der SAMW, Vom Senat der SAMW genehmigt am 25. November 2004.
https://www.samw.ch/dam/jcr:8b392d08-568d-4d1e-a8ba-55cbddf5bcc3/richtlinien_samw_lebensende.pdf.
・SAMW, SAMW-Studie «Haltung der Ärzteschaft zur Suizidhilfe» Zusammenfassung der Ergebnisse und Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission. In: Schweizerische Ärztezeitung | 2014;95: 47, S.1767-1769.
https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/view/article/saez/de/saez.2014.03112/SAEZ-03112.pdf/
・柴嵜 雅子「スイスにおける自死援助協会の活動と原理」『国際研究論叢』24(1)、2010年、51―62頁。
・Seifert, Elisabeth, Vom sorgsamen Umgag mit Ängsten, seelischer Unruhe und Schmerzen. Palliative Care macht Pflegeheime zu einem guten Lebens- und Sterbeort.In: CURAVIVA Schweiz, Ausgabe 11, 2017, S.12-15.
https://www.curaviva.ch/files/JNI2Q3T/fz_2017_november_sterbeort_pflegeheim.pdf
・Stoffel, Deborah, «Unser Ziel? Irgendwann zu verschwinden» In: Landbote, Inverview mit Ludwig A. Minelli, 09.05.2017, 06:30 Uhr
https://www.landbote.ch/front/unser-ziel-irgendwann-zu-verschwinden/story/25591753
・Vollenwyder, Usch, Jedem Menschen seinen eigenen Tod. In: Zeitlupe, 11/2015, S.11-15.
・Wacker, Gaudenz, Schweiz – Exit kommt fast nicht nach mit «Helfen», SRF, Dienstag, 01.03.2016, 14:14 UhrAktualisiert um 14:14 Uhr
https://www.srf.ch/news/schweiz/exit-kommt-fast-nicht-nach-mit-helfen
・Wagner, Brigit, et al., Death by request in Switzerland: Posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide, Abstract. In: Europian Psychiatry, October 2012, Vol. 27 Issue 7, Page 542-546.
https://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(10)00268-3/fulltext
・Wehrli, Hans et al. (hg.), Der organisierte Tod. Sterbehilfe und Selbstbestimmung am Lebensende. Pro und Contra, Zürich 2. überarbeitete Auflage 2015, Anhang: Vereinbarung über die organisierte Suizidhilfe zwischen der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und EXIT Deutsche Schweiz vom 7. Juli 2009, S.265-282.
・Zimmermann, Markus, In Ruhe sterben? Ambivalente Erwartungen an die Ärzteschaft bei der Behandlung von Patienten am Lebensende. Editorial. In: Swiss Medical Forum 2017;17(35):730-731.
http://www.unifr.ch/ethics/assets/files/Zimmermann%20SMF%202017.pdf
プロフィール
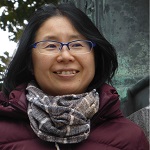
穂鷹知美


