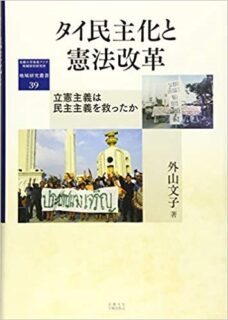2020.11.30
タイ政治混迷の背後にあるものは何か――『タイ民主化と憲法改革 立憲主義は民主主義を救ったか』(京都大学学術出版会)
2020年秋、タイ政治は混迷を極めている。7月下旬以降、バンコクのみならず地方都市でも学生を中心とした反政府デモが連日のように続いている。学生たちは、プラユット政権の非民主性や汚職体質を糾弾し、憲法改正やプラユット首相の辞任を要求している。しかし、学生たちの要求はそれらにとどまらない。8月以降は、タイ政治最大のタブーとされる王室批判が公然となされるようになった。学生たちは、国王が軍事クーデタを承認するという憲法外の権限行使を行ってきた点などについて激しく批判している。
しかし、タイ政治の混乱は2020年に始まったわけではない。タックシン・チナワット首相(2001年~2006年)を追放した2006年クーデタ後から2014年に再びクーデタが起こるまでの間、「黄シャツ」対「赤シャツ」の大衆デモ同士の衝突が路上で繰り返された。タックシン派とみなされることが多い「赤シャツ」は、クーデタによる民選政権の打倒、裁判所による非中立的な裁定(二重基準)について抗議した。「民主主義」「法の支配」といった原理・原則が中心的な争点であった。
両運動はいずれも、政治が民主主義の原則に則って行われていないこと、法の支配が損なわれている点について批判しており、理念において繋がりのある運動といえよう。では、なぜ長年に渡り大衆デモによる抗議運動が継続しているのだろうか。なぜこれら2点が争点となったのだろうか。そして、なぜ21世紀に入ってからタイ民主化が後退したのだろうか。背後には何が存在するのだろうか。
本書は、上記の問いを紐解く鍵の1つとして、タイ独特の政治体制である「国王を元首とする民主主義政体」に着目している。本書の出版は2020年1月であり、現在の反政府デモが興隆する以前に執筆したものである。しかし、本書のタイ政治に関する分析は、現在の政治的混乱を理解するための一助になると思われる。
「国王を元首とする民主主義政体」とは、1950年代末から1970年代の冷戦期にタイにおいて構築された政治体制である。
同政治体制の下では、主権は国王と国民が共同所有するとみなされる。憲法の文言では、主権は国民が所有するが、国王が国会、内閣、裁判所を通じて主権を行使するという玉虫色の表現がなされている。著名な保守派公法学者の説明によると、主権は国王と国民に存在する。タイは1932年立憲革命を契機に、絶対王政から立憲君主制となったが、法的には国王と国民がともに主権の保持者であるとされる。よって、クーデタが起こると主権が国王に戻ると説明される。このような法学者の解釈が明確になったのは1990年代以降のことであるが、1950年代末から軍部がクーデタを実行した際には、国王が裁可を下してクーデタに正当性を付与することが繰り返されてきた。
もう1つの特徴が、憲法に明記されているわけではないが、同体制では政治混乱が起きた場合、国王が介入および調停を行う(行える)ことが前提とされている点である。1973年10月と1992年5月にデモ隊と軍部・警察が衝突した際に、先代のプーミポン国王が政治介入を行ったことは、「国王神話」を支える重要なエピソードとなっている。
1992年5月流血事件の際に、プーミポン国王の権威は最高潮に達して「国王を元首とする民主主義政体」が完成したと評されることが多い。しかし本書では、このような解釈に対して疑問を呈する。本書の分析は、「国王を元首とする民主主義政体」は1992年5月事件の際に体制としての限界を迎えつつあった、という仮説から出発する。
まずこの点について検証するために、1992年5月事件後に興隆した政治改革運動や、政治改革運動の精神を受け継いで制定された1997年憲法と、2006年クーデタ後に軍事政権の下で制定された2007年憲法の起草資料について子細に検証を行う。加えて1992年5月流血事件の際のデモ参加者や、憲法起草に関わった法学者たちにインタビューを実施する。
一連の検証作業の結果、1992年5月事件の際には、市民社会の成長や大衆デモの変容を受けて、国王による政治介入が従前よりも危険を伴うものとなったこと、そして保守派知識人らが増幅する大衆の力に対して、大きな恐怖心を抱くようになったことが明らかとなった。
また起草資料の検証などから、限界に達しつつあった「国王を元首とする民主主義政体」を補完する役割を担わされたのが、憲法裁判所や国家汚職防止取締委員会などの独立機関をはじめとする司法機関であったことが浮かび上がった。
1997年憲法と2007年憲法においては、「立憲主義」の名のもとに司法権が強化された。本来は民主主義の「質」を向上させるために導入されるべき立憲主義の理念が、民意に基づく民主主義を制約するために機能することとなった。
国王による直接的な政治介入が困難となった時代に、司法が大衆を抑制するためにどのような制度設計がなされたのだろうか。本書では、憲法裁判所や独立機関の人事や権限のみならず、「何を汚職と規定するか」「何を選挙違反とするか」といった点に着目する。憲法および法律の規定内容について詳細な検証を行うことにより、タイ立憲主義の特徴を明らかにする。
本書の分析を通じて、1997年憲法および2007年憲法の起草および制定において、立憲主義や法の支配の原理が歪められていった過程と、その背後には、タイ社会の変化に伴い「国王を元首とする民主主義政体」の限界を感じとった保守派層の危機感や恐怖感が存在したことを明らかにしている。
保守派層が抱いた危機感、歪められた立憲主義と民主主義、憲法と関連法律の規定が民主化に与えた影響、本書で論じるこれらのポイントは、現在のタイ政治を眺めるうえでも重要な要素であると思われる。
プロフィール

外山文子
筑波大学人文社会系准教授、京都大学東南アジア地域研究研究所連携准教授。京都大学博士(地域研究)専門はタイ政治、比較政治学。早稲田大学政治経済学部卒政治学科卒、公務員を経て、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了(2013年)。主な論文に、「タイ立憲君主制とは何か―副署からの一考察」『年報 タイ研究』第16号、PP.61-80、日本タイ学会、2016年、「タイにおける体制変動―憲法、司法、クーデタに焦点をあてて」『体制転換/非転換の比較政治(日本比較政治学会年報第16号)』ミネルヴァ書房、PP. 155-178、2014年、「タイにおける汚職の創造:法規定を政治家批判」『東南アジア研究』51巻1号、PP. 109-138、京都大学東南アジア研究所、2013年など。