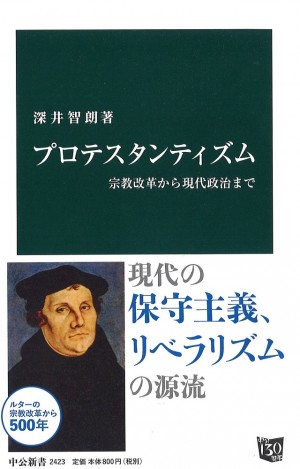2017.11.10

プロテスタンティズムと「共存の作法」
ルターの宗教改革から500年。プロテスタントを生み出したとされる宗教改革とはいったい何だったのか? ルターという人物は何を成し遂げようとしていたのか? ナショナリズム、保守主義、リベラリズムなど、多面的な顔を持つプロテスタンティズムについて、『プロテスタンティズム』の著者、深井智朗氏に話を伺った。(聞き手・構成 / 芹沢一也)
宗教改革前夜
――日本では「免罪符」とも訳される「贖宥状」ですが、「贖宥」とはどのような営為だったのでしょうか?
「免罪符」と言うよりは、「贖宥状」の方がよいと思います。
中世のキリスト教の教えの特徴は、人々に、どうすれば天国に行けるのかをわかりやすく説明したことにあったと思います。キリスト教は、人間が死後天国に行くことを妨げているものとして、ふたつの理由をあげていました。そして人間は生きている間に、それら妨げになっているものを取り除かねばならないとしたのです。
ひとつは「原罪」と呼ばれるもの。最初の人間とされるアダムが神との約束を破ったことで、その後の人類に遺伝し続けているものです。この「原罪」は洗礼によって消されるとされました。当時は乳幼児の死亡率がかなり高かったので、洗礼は死の直前ではなく、幼児期に行うことになりました。なにしろ洗礼を受けて罪を消さなければ、天国には行けません。そのため、死者の洗礼という制度があったほどです。
もうひとつは、洗礼を受けた後に犯した過ちです。これについては、司祭の前で過ちを告白し、悔い改める必要がありました。この過失を消すために、司祭は告白した人に必要な罰を与えます。罰はそれほど大げさなものではありませんでした。たとえば1ヶ月、毎朝教会の中庭を掃除する、というようなものです。
ところが人々はこう考え、不安になったのです。もし1ヶ月の前に死んでしまったらどうなるのか? そこでこの罰を代行するという習慣が生まれました。代行は、最初は修道士たちによる愛の行為でした。不安な人々に代わって、修道士がその罰を果たしたのです。そうしてもらえれば、万が一自分が死んでしまっても罰は行われ、天国に行くための障害は取り除かれるという理路です。これが贖宥という考え方です。
ところがこれは誰もが欲したことだったので、いつの間にか有料になり、贖宥状として売り出されました。また、売り手市場ですから高額となり、教皇の支配下にあり、教皇至上主義を主張するローマ主義者たちの資金源にもなったのです。
――当時の神聖ローマ帝国は、贖宥状の販売を通してローマ・カトリック教会に搾取されていたと言ってもよいと思うのですが、こうした関係性はなぜ生じたのでしょうか?
それについては、当時の神聖ローマ帝国の教会は、政治的支配者の所有物であったということが重要です。自らの政治的統治に正当性や権威を付与してくれるのは宗教でしたから、領民がみな同じひとつの宗教を信じるように、政治的支配者は教会を建てたのです。しかし当然のことながら、建物だけでは宗教はできません。儀式を取り仕切るのは聖職者です。その聖職者はローマから派遣してもらうか、ローマの許可を得た人たちのなかから選ばれます。
聖職者がいなければ宗教は成立しませんので、領主たちはローマに公然と歯向かうことはできません。逆に、ローマから派遣された聖職者たちは弱みにつけこんで、搾取を繰り返し、神聖ローマ帝国の領邦からローマにお金を流していたのです。当時の神聖ローマ帝国は300から400の領邦や自由都市の結合体ですが、領邦の領主たちのなかには、このようなローマとの不均衡な関係に不満をもっている者たちもいました。
これがルターの改革の前夜の状況だと言ってよいでしょう。
教会制度の「再形成」をめざしたルター
――そして、ルターの「宗教改革」が始まるわけですが、ご著書を読んでいると一般に流布しているイメージはだいぶ様子が異なりますね。ルターという人物は正確には何をしようとしたのでしょうか?
西ヨーロッパのキリスト教のことをカトリックと呼びますが、ルターは、その教会の修道士であり、聖書の教師でした。しかし彼は、先ほどお話しした贖宥状の有料化や高額化の問題、あるいはローマの教皇主義者たちの神聖ローマ帝国の教会の運営についての考えを知れば知るほど、教会が制度疲労を起こしていると感じるようになりました。そこでこの制度の「修復」(Reform)が必要だと考えたのです。
「宗教改革」と日本では訳されますが、ドイツ語ではReformationで、正確に訳せば「再形成」という意味です。ときに誤解がありますが、ルターはプロテスタントという宗派を生み出そうとしたのではなく、カトリックからの独立を考えたのでもありません。そうではなく、今ある教会制度の「再形成」を願い、それを強い意志と勇気をもって成し遂げようとしたのです。
教皇も人間ですし、教会の会議も人間が行うのですから間違えることもある。そこで彼は、キリスト教という宗教の正しさの判断基準として聖書のみが重要であると考えたのです。
聖書は教会が生み出したものですが、一度教会の正典(Canon)として受け入れられてからは、教会の教えや教会の宗教的な行為を規定することになりました。それまでの教会が聖書をまったく無視してきたわけではありません。教会の中で一番大切な基準は、聖書「と」教皇の判断、ということになっていたのです。ルターはそれにたいして、聖書「のみ」と言ったのです。
――ルターは新しい宗派をつくろうとしていたわけではないのですね。
ルター自身は生涯自分がカトリックであったと考えていたはずです。
最近、家のリフォーム番組というのが流行していますね。築後何年も経た、使い勝手の悪くなった古い家を、匠と呼ばれる設計者がリフォームするものです。全部壊さないで、土台や柱などは残して再生します。素人がみますと、いっそ建て直してしまった方が簡単だと思えるのですが、難しい条件のなかで、何とか住みやすい、そして前よりも素晴らしい建物に修復しようとする。ルターの「再形成」のイメージはこのようなものであったと思います。
ですから彼はカトリックの枠組みこだわったのです。先日も10月31日に、ドイツのアウクスブルクで行われた宗教改革500年の記念礼拝に出席しましたが、改めて思いますのは、バイエルン州のルター派の教会は建築構造の点でも、儀式の点でも、カトリックと似ているということです。あとで話に出るかと思いますが、「新プロテスタンティズム」とはその点で大きく違っています。
もうひとつ、ルターが新しい宗派として独立しようなどとは考えていなかったと思われる理由は、ルター自身がローマとの和解を試みようとしていたふしがあることです。たとえば、ルターは有名な『キリスト者の自由』(拙訳『宗教改革三大文章』に収録)をドイツ語で書いただけではなく、ラテン語でも書いています。ラテン語でも書いた理由は、それによってラテン語でものを考える教皇側と和解しようとしたからだと思います。ドイツ語版とは論じ方や内容が違っていて、明らかに教皇側が読むという前提のもとで自己弁護的な議論がなされています。
情報革命が可能にした改革
――ルターの改革にはヤン・フスのような先駆者がいます。しかしヤン・フスは教会に破門され、火刑に処されました。ルターの改革が成功した理由はどこにあったのでしょうか?
ルターの改革が成功したと言ってよいかは分かりませんが、ルターの考えは、当時の印刷技術の発展、また各都市の印刷所の成長などによって生み出された、当時の知識人である人文主義者たちの知的ネットワークを通して、またたく間にヨーロッパ中に広がりました。それはまさに情報革命で、詳しい内容はともかく、情報が瞬時に拡散されてしまったのです。
もちろんSNSなどが普及した現在とは比べものになりませんが、1517年に書かれたと言われている、いわゆる「95か条の提題」などは、数週間のあいだにヨーロッパ中に広がり、複製や海賊版がつくられています。そうしますとローマの教会が正式にその内容についてコメントしたり、判断する前に、知識人たちは内容を把握してしまっていました。
ルターはこの新しい仕組みをうまく利用しました。そして、さまざまな発言をしていったのです。彼は当時のベストセラー作家となり、もはやカトリック教会は自由に情報を発信するルターを止めることはできませんでした。
すると何が起こったか? 人々は以前と違って、教会によってコントロールされた情報だけではなく、ルターの考えを彼自身の声として聞くことができるようになったのです。そうしますと教会の側は、もはや都合のよい事実だけを公にしたり、事態を隠蔽したり、秘密裏に処理することができなくなった。つまりルターについて正義にかなわないことをすることがしにくくなったのです。
政治化する宗教改革
――そうしたなか、ルターの提起は信仰上、教義上の問題をこえて、世俗政治にも大きなインパクトを与えます。
先にもお話ししたように、それは領主たちの政治的統治とその安定のために教会が不可欠だったからです。ローマと繋がることで、自らの政治的統治に何らの利益を得ていた神聖ローマ帝国の領主たちは、ルターの主張に何も魅力を感じませんでした。
しかしローマとの関係に苦慮していた領主にとっては、これまで主張できなかったローマへの批判を代弁してくれるルターは重要な人物となりました。当時の帝国自由都市や領主のなかには、自らが手にした経済的成功にふさわしい政治的権利を主張したいと考える者たちがいたのです。
そのような領主たちは、従来通りローマと繋がることと、ルターの批判を支持するのと、どちらの選択が自らの統治に資することになるのかを計算しました。ルターたちの運動も、自らが政治的に使い勝手のよい宗教であることをアピールしたのです。
――政治にとっての使い勝手のよさと言いますと?
ルター派の特徴は、聖書のなかにあるローマの信徒への手紙13章にある「上に立つ権威」(die Obrigkeit)という考えに対する解釈にあると思います。そこにはこう書かれています。「すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。なぜなら、神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべて神によって立てられたものだからである。 したがって、権威に逆らう者は、神の定めにそむく者である。」
この箇所を「上に立つ権威」、つまりこの世の政治的支配者の権威は神によって与えられたものなのだから、それに従うべきだという考えだとしたのです。このことは従来のカトリック教会でも言われていたことですが、この世の政治的支配原理も、神によって建てられたのだから、政治性のみならず宗教性も持っているとまで言ったことがルター派の特徴です。
これが当時の領主たちへのセールスポイントでした。ですから、ルターの批判や「再形成」のプログラムは、宗教的な検討、議論ももちろんなされているのですが、むしろ政治的な枠組みの問題になったのです。
――バチカンの影響力と縁を切ることを望む領主にとっては、ルター派は格好の機会を与えてくれたわけですね。
ザムエル・フライヘル・フォン・プーフェンドルフ(生年没年不詳)という国法学者が、1667年に『ドイツ帝国の状況について』という書物を書いていますが、そこに次のような文章があります。「この宗派と同じように君主にとって都合の良いように広まった宗教を知らない」。
この宗派とはルター派のことで、プーフェンドルフは政治的に使い勝手のよい宗教として、ルター派を説明したのです。さらに彼は、ルター派の特徴は「内面化された宗教性による行政機関への忠誠にある」と述べています。つまり先ほど述べた「上に立つ権威」に従うことに対する解釈と同じで、政治的支配者に従うことは、神に従うことになるという考えで、人々は君主や国家に仕えることになっているというのです。
ルターの運動は最終的に、神聖ローマ帝国内の300以上の領邦の領主が、彼の改革を受け入れるのか、受入れないのかという政治的駆け引きとなりました。この騒動を沈静化させるために、ルターの死後、1555年に、アウクスブルクで帝国議会が開催されます。そこで「アウクスブルク宗教平和」と後に呼ばれることになる決議が出されますが、この決議によって「領主が自分の領邦の宗教を選択し、決定できる」ことになりました。領主たちが選択した教会が、その領邦における正統的な宗派となる、という合意が成立したのです。
このときルター派は、領主の政治的選択を促すように、政治的支配者に寄り添い、奉仕し、仕える宗教になりました。ルター派のこうした性格は、これ以降も変わりません。近代になってプロイセン主導でドイツ統一がなされた際も、ナチズムの時代も、そして戦後になっても、基本的には国家に寄り添う宗教であり続けました。宗教改革から引き出される宗教制度や社会の「改革」というイメージとは真逆に、ドイツのルター派は体制側に寄り添う保守的な勢力であり続けたのです。
ちなみに、「アウクスブルク宗教平和」において、ルター派の運動は「アウクスブルク信仰告白派」として、皇帝の「古い宗教」であるカトリックと並んで法的に認められるに至りました。当然、カトリックの側はこの決議の不法性を強く主張しましたので、ルター派の側では自らの宗派が「法的」な根拠を持つと主張します。そのとき、ルター派は法的にひとつの宗派になったのです。
ドイツ統一のための建国神話
――かくして、プロテスタントが新しい宗派として成立したということですね。しかし、宗教改革とプロテスタントには「近代的自由の思想の出発点」というイメージもあります。
それはいわゆる「伝統の創造」と言われるもので、政治的な創造物にすぎません。
「遅れていた大国」ドイツが1871年に悲願の統一を果たした際、新しく生まれた帝国は、統一国家としてのグランドデザイン、あるいは何よりも新たなナショナル・アイデンティティーを必要としていました。それは、なぜこの領土がドイツと呼ばれるのか、という国内の問いへの答えであり、同時にいち早く近代化を成し遂げていたフランスやイギリスに対抗できる、「偉大なるドイツ」を誇れるような理念でなければなりませんでした。
1871年の統一では、オーストリアは排除されました。そのためドイツ語という共通言語によるナショナル・アイデンティティーの形成は意味を持たなくなっていました。さらに統一を決定づけたのは長年の敵であるフランスに対する勝利でした。
だからこそ「ドイツ的なもの」の淵源は、16世紀にカトリックに対して戦い、近代的な自由の基礎をつくり上げたマルティン・ルターとその宗教改革に遡るという地政学的なイメージが浮上したのです。なぜならオーストリアはドイツ語圏ですがカトリックなので、統一からは排除されると説明できるし、長年の敵であるフランスもまたカトリックの地域だったのですから。
皇帝の正枢密顧問官で、ベルリン大学神学部教授であったアドルフ・フォン・ハルナック(1851 – 1930年)は、「17世紀のピューリタン革命より、18世紀のフランス革命よりも早く、近代的な自由を主張したマルティン・ルターの宗教改革」という地政学的な歴史解釈を提供しました。つまりこの時代、ルターとその宗教改革の精神は、宗教的にというよりは、政治的に再発見されたのです。
――そうしたイメージが、日本でも教科書的な知識として流布しているのですね。
宗教改革の政治的利用が主流であった統一後まもないドイツに、明治維新後の日本から、その後の国造りに貢献することになる多くの優秀な若者たちが留学し、ドイツ風の学問を持ち帰っています。
わが国のかつての世界史の教科書に、「1517年10月31日に修道士マルティン・ルターが、ヴィッテンベルク城の教会の入口に95箇条の提題を張り出したときに宗教改革が始まり、腐敗したカトリックを批判したルターによってプロテスタントが起こされ、プロテスタントはヨーロッパの近代化に寄与した」などと書かれていたとしても、決して不思議なことではなかったのです。それは歴史である前に、1871年のドイツ統一のための建国神話であったわけです。
二人のマルティン・ルター
――他方で、プロテスタントにはもうひとつの潮流もあるとのことです。
ヴィルヘルム期からヴァイマール期ドイツで活躍したエルンスト・トレルチ(1865 – 1923年)という、有名な神学者であった政治家がいます。ヴァイマール期には一時、大統領候補になったこともあります。マックス・ヴェーバー(1864 – 1920年)の数少ない友人で、またハイデルベルク時代は同じ家に住んでいました。
彼はその時代のドイツ・ルター派に責任を持とうとした神学者であり、政治家でしたが、だからこそドイツ・ルター派に批判的でもありました。そのトレルチがプロテスタントというのは、じつは一枚岩ではなく、カトリックと違って、世界中どこに行っても同一プロテスタントが存在しているのではない、ということを述べています。
そしてルターやジャン・カルヴァンなどの改革の流れを「古プロテスタンティズム」と呼び、この教会は制度的にはカトリックとそれほど変わらないと言いました。それに対して、ルターやカルヴァンの改革の不徹底を批判し、さらなる改革を主張したために、ルターやカルヴァンからはいじめ抜かれたグループから出てくる流れを「新プロテスタンティズム」と呼んでいます。
――改革派が保守化するなかで、さらなる改革派が出てくるわけですね。
ルターの改革はかなり早い段階で、大きく見渡すとふたつの、それぞれ性格の異なったプロテスタンティズムに区分されるようになっていました。
ひとつは「改革」という自らの立場を定着させ、自らが本来あるべき正統的なキリスト教だと主張するようになった勢力。それがドイツのルター派です。しかし社会におけるあらゆる改革勢力がそうであるように、「前衛」は戦いを経て「後衛」になります。改革を主張していた人々が、新たな改革に対して守りに徹するようになる。政治的勢力と結びつくことである程度安定したポディションを得たことで、さらなる改革や批判を受け容れられなくなるのです。それはいつの時代も同じです。
それに対してもうひとつの「改革」勢力は、従来の改革の不徹底さを嘆き、よりラディカルな改革を求めた人々の動きです。「改革の改革」を主張する人々が登場したのです。それは初期の宗教改革者たちの想定をこえた動きでした。ですから、このラディカルな改革を政治的支配者たちは治安の安定のために排除しますし、宗教改革者たちもそれに協力し、批判的になり、具体的には教会制度からの追い出しにかかったのです。
――「改革の改革」、あるいは「新プロテスタンティズム」とは、どのような特徴を持つものなのでしょうか?
私はこのことを説明するときに、しばしば「二人のマルティン・ルターを見るとよい」と言っています。マルティン・ルターはトレルチによれば「古プロテスタンティズム」に属しますが、もうひとり私たちは別のマルティン・ルターを知っています。
それはアメリカの公民権運動の指導者マーティン・ルーサー・キング牧師(1929 – 1968年)。その名はドイツ語読みをすれば、マルティン・ルターです。同名で、やはり牧師だった父から、16世紀の宗教改革者を意識して与えられた名前です。彼はバプテストと呼ばれるプロテスタントのグループの牧師でしたが、このバプテストは「改革の改革」の流れのなかから出てきた典型的な「新プロテスタンティズム」です。
彼らバプテストたちは体制化した宗教改革の運動とは違い、個々人が主体的に信じる自由、具体的には自由に宗教(あるいは教会)を設立し、その信者となる権利を要求しました。
今日では当然の権利として認められている信教の自由ですが、この時代の人々はまだ手にしていませんし、自由に教会をつくる権利などという考えは、社会の統一だけではなく、教会の一致をも破壊する恐ろしい考え方だとされました。だからこそ彼らは政治的な支配者だけではなく、宗教改革者たちからも批判され、排除されることになりました。
ルター派はこのような勢力を、社会秩序の基盤や、社会の統一を乱す厄介者として教会のみならず、社会から追い出しました。だからこそ、「改革の改革」を迫る勢力は政治的支配者に抵抗し、それとは明確に距離を取り、むしろ政府や統治者の過ちをはっきりと批判するようになりました。そこにバプテストの伝統があります。公民権運動の指導者となった方のアメリカのルターは、このバプテストの牧師なのです。
「新プロテスタンティズム」と近代世界
――近代、あるいは近代的な諸価値と結びついているのは、「新プロテスタンティズム」の方なのですね。
その通りです。近代世界の成立との関連で論じられ、また近代のさまざまな自由思想、人権、抵抗権、良心の自由、デモクラシーの形成に寄与し、あるいはその担い手となったと言われているのは、カトリックやルター派、そしてカルヴィニズムにいじめ抜かれ、排除され、迫害を受けてきた、「改革の改革」を主張した「新プロテスタンティズム」です。
このように、プロテスタントは一枚岩ではないのです。大きく見渡せばプロテスタントの流れはふたつあり、それがふたつの異なった政治的スタイルをも生み出しているのです。ひとつは政府の政策に寄り添う宗教としてのプロテスタンティズムであり、もうひとつは国家に依存するよりは、自活的結社としての教会の形成力に、社会の変革や改革に使命を見出すプロテスタンティズムです。
――公立と私立の小学校の違い、というたとえが分かりやすかったです。
「古プロテスタンティズム」のイメージは公立小学校ではないかと思います。その地域の行政の責任者が小学校をひとつ建て、そこで義務教育が行われるのです。その地域に住む住民はみなその学校に行きます。それを学校区と呼びます。「古プロテスタンティズム」の教会も同じで、教区というものがあり、その地域で生まれた者たちは、その地域の政治的支配者、あるいは行政が建てた教会に行くのです。授業料は無償で、税金で運営されます。
それに対して「新プロテスタンティズム」は、政治的指導者や行政が定める教会ではなく、自由に教会をつくらせろと言うのですから、私立の小学校のようなものです。公立の小学校があるにもかかわらず、あえて自分たちの教育の考えに合う小学校を選び、授業料を払い、入学資格を得るために試験を受けるのです。自発的結社です。
そういう意味では「新プロテスタンティズム」は、「古プロテスタンティズム」が独占していた宗教のマーケットを自由化したのです。もっと言えば、国営による独占を批判し、民営化し、自由化し、市場原理を持ち込むことで、自由な競争を可能にしたのです。
ここから近代の新しい社会システムが生まれたのではないでしょうか。民営化と「新プロテスタンティズム」が似ているのではなく、「新プロテスタンティズム」の人たちの宗教的行動が社会のシステムを最初に変えた。アメリカに渡ったピューリタンと呼ばれる「新プロテスタンティズム」の伝統を受け継いだ人々が意図的に、あるいは無意識のうちに生み出した社会の仕組みが、まさに民営化と自由化だったのです。
保守主義としてのプロテスタンティズムの真価
――他方で、保守主義としてのプロテスタンティズムにも、「共存の作法」という現代的な意義を認められていますね。メルケルの話はとても示唆的でした。
保守とは何か、ということなのですが、本来的な意味での保守というのは、その社会の本流や伝統を知っているということであり、「反動」ではありません。改革を拒否したり、変化を拒否する勢力でもありません。保守は社会の本流を知っているが故に、社会が本来あるべき姿から逸脱しようとするときには、否をいう勢力のことではないかと思うのです。
そのような意味でドイツ・ルター派の伝統とは何かということなのです。ドイツ社会が難民問題で揺れ動いたとき、それと並行して極右勢力の排他的で不寛容な政策が力を持つかに思えたときに、ルター派の牧師の娘であるアンゲラ・メルケル首相が、その動きを強く否定したことは、このことと深く関係していると思います。
プロテスタンティズムは、たしかに争いの宗教でした。その歴史は分裂と批判、戦争と排除の歴史です。それを忘れてはなりません。しかし他方でヨーロッパという地理的な条件のなかで、争っても、血を流しても、それでも争いが終われば、敵と憎しみの対象と共存してゆかねばならないのです。逃げられないのです。昼間取っ組み合いの喧嘩をした兄弟も、夕方になって母親が「夕御飯になります」と言えば、口を聞きたくなくても、まだ言いたいことはあっても、同じテーブルで食事をしなければならないのです。
それと同じように、プロテスタントの争いの歴史は、戦いの後に何とか共存の作法を見つけて生きて行こうという努力でもあったのです。1555年の「アウクスブルク宗教平和」、「寛容」という考え、「教会と国家の分離の原則」など、制度化されたり、思想として残されているもの以外にも、さまざまな努力があったわけです。
ドイツでルター派が保守であると言う場合には、プロテスタントであるとの意味を、他者を排除するという意味での宗派性に見ているのではありません。むしろ、宗教改革後の時代にやってきた宗派同士の終わることのないような政治的戦いのなかで、異なった宗派の共存のシステムをどのようにつくるかという努力の伝統として理解しているのです。そしてそこにこそ、保守主義としてのプロテスタンティズムの真価があると私は思います。
プロフィール
深井智朗
1964年生まれ。アウクスブルク大学哲学・社会学部博士課程修了。Dr.Phil.(アウクスブルク大学)、博士(文学)京都大学。聖学院大学教授、金城学院大学教授を経て、東洋英和女学院大学人間科学部教授。著書に『超越と認識』(創文社、2004年、中村元賞受賞)、『十九世紀のドイツ・プロテスタンティズム』(教文館、2009年、日本ドイツ学会奨励賞)がある。