2024.09.10
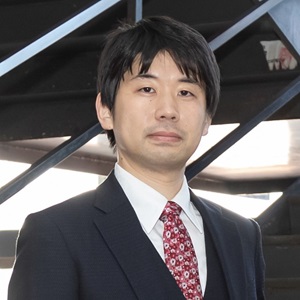
小国が超大国を揺り動かすメカニズム
強大な力を誇る「帝国」アメリカは、日本や西欧諸国と「非対称同盟」を結んでいる。だがアメリカは同盟国に圧力をかけるだけでなく、ときに同盟国に有利となる政策を自ら選択してきた。大国が小国にゆずる、という一見不可解な現象はなぜ起こるのか? 話題書『帝国アメリカがゆずるとき』著者で国際政治学者の玉置敦彦氏に、アメリカが「ゆずる」現象とその理論、史料収集・読解の裏話、揺れ動く現在の国際情勢について、お話を伺った。(聞き手:岩波書店編集部)
小国に「ゆずる」大国
――『帝国アメリカがゆずるとき』は、超大国であるアメリカが、対等ではない同盟国の側が明らかに有利になるような施策を取る現象について、そのメカニズムを明らかにした著作です。「犬が尾を振る」ならぬ「尾が犬を振る」という言葉で喩えられるこの現象について、まずはご説明いただけますでしょうか?
歴史的に、大国が小国に対して譲歩するという事例は数多く見られます。戦後の日本を例に取ると、第二次世界大戦後にアメリカの統治下にあった沖縄が1972年に返還されました。日本にとっては望ましい結果でしたが、当時はアメリカが膨大な労力を費やしていたベトナム戦争の最中で、在日米軍基地は非常に重要な存在でした。戦争中に権益を手放したこの行動は、一見不思議に見えるかもしれません。
このように、大国は小国の利益になるように譲歩することも、逆に圧力をかけ、内政に介入することもあります。こうした大きな力の差がある同盟を、国際政治学では「非対称同盟」と呼ぶのですが、なぜそのなかで尾(=小国、追随国)が犬(=大国、主導国)を振り回すようなことが起こるのか。本書では、ベトナム戦争の時代におけるアメリカと、同盟相手国である日本、韓国、フィリピンを対象として、アメリカがそれぞれの国に対しどのような見方や判断、そしてその結果として施策をとっていたのかを、アメリカ政府の一次史料を参照しつつ理論化しています。
同盟の条件
――基本的なことで恐縮ですが、そもそも同盟とは何をさすのでしょうか?
実は同盟という言葉自体が非常に多義的なのですが、国際政治学では、17・18世紀の近代ヨーロッパをその原型としています。オーストリア継承戦争や七年戦争などの多くの戦争が起こったこの戦乱の時代に、イギリス・フランス・プロイセン(ドイツ)・オーストリア・ロシアといった国々が、五年、十年単位で互いに手を組み、敵・味方を入れ替えて戦っていく。このように実際に肩を並べて戦い、あるいは「同盟相手とともに戦う」と宣言していることが、同盟の原義とされています。
これは対称同盟でも非対称同盟であっても、条約を結ぶ公式の同盟/そうでない非公式の同盟でも、基本的に同じです。条約は重要ですが、公式な同盟かどうかにこだわると齟齬をきたすこともあります。たとえば中国とソ連は1969年に珍宝島/ダマンスキー島事件で武力衝突をしているのですが、70年代末まで中ソ友好同盟相互援助条約が結ばれたままです。そうなると、武力衝突した後も同盟は残っている、ということになり、実態にそぐわない。そこで私は「相手の防衛や攻撃に参加するという公式/非公式の軍事的なコミットメントを有している」というのが、同盟と捉えるラインだと考えています。その意味では、たとえばアメリカとウクライナの軍事関係は、同盟とは言えないということになります。軍事援助をしてはいるものの、攻撃や防衛に参加すると明言されていないからです。
とはいえ、軍事援助や軍事協力をもって同盟と定義する著名な文献もありますし、逆に公式の条約を結んだ場合だけを同盟とする捉え方も有力です。こうした多岐にわたる同盟の理解の中で、私の定義は概ね中間点にあるといえるでしょう。
国際秩序形成と非対称な同盟
――そうした同盟を結ぶ国々のなかで起こる、非対称同盟での大国の譲歩について、もう少しご説明いただけますか?
戦後のアメリカは、ソ連を中心とする共産主義陣営に対して、自由主義陣営、現在では「リベラルな国際秩序」と呼ばれるブロックを形成しました。民主主義と自由貿易の拡大、そしてアメリカの優位を制度的に確立するという目論見によるものです。本書で中心的に論じているベトナム戦争期にも、そうした陣営間での緊張が生じていました。日本や韓国、フィリピンに対してアメリカは米軍基地の設置といった負担を求める一方で、制度や経済面などの援助も行っていきます。
そのときに重要なのが、同盟相手国との関係です。アメリカとしては、相手国から有利な条件を引き出したい。一方で派兵や米軍基地設置などの負担は、相手国の国民の不満をもたらし、それが募ると親米政権が維持できなくなる恐れが出てきます。先の沖縄返還を例にとると、1968年には、原子力空母の佐世保入港などの複数の出来事から、当時の佐藤栄作首相が日本国内で強い批判に直面していました。これを受けた駐日米大使らは、日本国内の政治状況が混乱し、アメリカに対する安定的な協力が見込まれなくなる可能性がある、といった報告を、アメリカ本国側に対して行っています。
詳しくは本書をお読みいただきたいと思いますが、こうした同盟相手国の政治状況や信頼の度合い、現地に駐在する大使らとアメリカ本国との見解の一致点と相違点、等々の様々な要素から、相手国をどう拘束し負担分担を求めるか、いかに譲歩し、あるいはいかに圧力をかけるか、といった政策が実行に移されることになります。これまでの国際政治学の理論の蓄積をもとに、非対称同盟における譲歩と圧力を理論化し、また日本・韓国・フィリピンを事例としてそのメカニズムを示したことが本書の特色だといえるでしょう。
なお、この構造はアメリカに限りません。おなじ超大国であったソ連からも、同じ図式が見て取れます。たとえば、1968年のプラハの春では、ソ連が同盟国であるチェコスロバキアに介入し、一方的に弾圧をおこなったかのようにも見えます。ですが実は、政変が波及することを恐れた他の同盟諸国、ポーランドや東ドイツといった国々が、むしろソ連に介入を要望したという側面もある。本書で検討したアメリカと同じく、「東欧諸国の共産党政権を維持しないといけない、そのためには相手の要望を聞いて支援する、つまり譲歩をせざるを得ない」といったメカニズムが働いていた。ソ連が東欧諸国に対して一方的に命令できたわけではなく、他の国に言うことを聞かせ、あるいはその政権を支えるために行動せざるをえない、という間接統治としての構造的な問題なんですね。
政権そのものを揺るがす介入も
――今のお話は、「アメとムチ」ということとはまた違うのですか?
たとえば政治学者の泉川泰博先生はreward とcoercionという言葉を用いて議論されており、日本語ではアメとムチと訳されています。私もこの議論から非常に多くを学んでいて、本書をまとめるうえでも大きな刺激となりました。とはいえ、私がアメとムチではなく、譲歩と圧力という概念を選択したのには理由があります。
というのは、アメとムチとは「なにかをさせるためにアメをあげて、聞かなかったらムチで打つ」というように、直接相手に言うことを聞かせるための方法ですよね。ところがそれでは、同盟国の政権が崩れかねないときに援助・譲歩するという現象は説明できない。それは、「同盟国が言うことを聞かないからアメをあげて誘導する」という話とは、また異なる論理を含む行動です。
他方ムチといっても、言うことを聞かないからその政権に懲罰を与えるケースに限りません。場合によっては、アメリカは信頼できないと判断した政権そのものを排除します。イラン、フィリピンやグアテマラ、パナマなどに対して、実際にそういった行動を取っているんですね。このように相手を動かすだけではなく、場合によっては相手を支えたり、取り替えたりすることも視野に入れている点では、譲歩と圧力という概念は、「アメとムチを含む、だがそれだけではない」ということになるでしょう。
大国が追随国を「信頼する」とは?
――アメリカの信頼の度合いがファクターの一つ、というご説明がありましたが、この場合の「アメリカの信頼」とは何を意味するのでしょうか?
同盟国からすれば、「アメリカがこれだけやってくれるんだから、もっとつけこんでやろう」というインセンティブもありえます。それに対し、同盟国がそういう判断をしないだろうとアメリカが考えるということです。
たとえば、1984年から86年にかけては、ニュージーランドとアメリカが米艦船への核兵器の搭載の有無をめぐって対立し、同盟が壊れるのですが、最近の研究によれば、この背景には、アメリカが当初はニュージーランド政府の立場に配慮する姿勢をみせたところ、これに勢いをえたニュージーランドがさらに強く出てきてしまった、という事情があったようです。主導国が譲歩したら、追随国がこれにつけこんでさらに要求を吊り上げたわけですね。
こうした政権に配慮してもアメリカは利益を失うだけで、状況を改善することはできません。アメリカからすると状況は悪化するだけです。そうではなく、アメリカがこうしてほしいと思って支援をしたら、それに応える意思がある。そして、意思があるだけではなく、その約束を実行できる能力があることが必要です。権力闘争に破れそうだったり、支持率が低かったりすれば、そのつもりがあっても政権そのものが倒れて実現できないかもしれない。つまりアメリカのような主導国から見れば、譲歩したとして、その見返りを期待できる相手かどうかが重要となります。
また、若干矛盾するかもしれませんが、信頼するからこそ配慮しなければいけない状況が生じることもあります。単に不安定だけど親米だから譲歩する、という話ではなくて、信頼できる相手に配慮する、という構図です。戦後、吉田茂はアメリカに対してずっと協力的な政権運営でしたが、政権末期には今後の復権が難しいとして信頼を失ったことで、容赦なく配慮の対象から外れます。
公式の同盟ではありませんが、台湾とアメリカの関係もその観点から検討できます。台湾は民主主義国家で半導体産業もありますので、アメリカは台湾を支援しています。ですが台湾がアメリカの支援を頼みに大々的に独立宣言を行ってしまったら、中国との間に大変な緊張関係が生じ、アメリカはこれに巻き込まれることになります。だからアメリカはそうした行動を台湾にとってほしくない。そうした「アメリカの意に反する行動をとるかどうか」も信頼性の一つです。
台湾は陳水扁政権の民進党の時代、アメリカからは警戒されていたんですね。突然独立を言い出しかねない、それは困る、と思われていたわけです。これに対して蔡英文政権になってからは、着実にアメリカの信頼を獲得していく。それゆえに「この政権を支援しても大丈夫だ」と判断されていくわけです。
膨大な史料の撮影と読解
――少し内容からそれますが、ここまでおっしゃったようなメカニズムは、どのような研究の過程から見えてくるのでしょうか。
基本的にはアメリカ外交の一次史料の読解です。アメリカ外交の場合、The Foreign Relations of the United States (FRUS)などはインターネット上で見ることが可能です。対象となる国によって異なりますが、日米関係はこれ以外にも資料集が充実していて、70年代ぐらいまでのものはある程度日本でも見ることができて、それ以上となると直接史料を収集する必要が出てきます。ですがたとえば、私の研究室には米・イタリア関係で修士論文を執筆した院生が所属していましたが、このケースでは日本で読める資料がほとんどないんです。なので最初から「史料収集に行きましょう」となってしまいます。
史料収集については、アメリカの国立公文書館や大統領図書館であれば史料のボックス単位で請求し、撮影室でひたすら三脚を使って撮り続けます。だいたい、2週間かければ2万枚強ほどは撮影できます。手元にある史料は、15万枚を超えています。
私の場合はできるだけ網羅的に、関係する史料を全て撮影してくるスタイルです。その場で読んで判断する方もいらっしゃるそうですが、私は読んでいる時間がもったいないですし、もし議論が変わったら、必要な史料が変わってしまいます。後になって「あのときあそこに史料があったのに」となるのは嫌ですから。指導する学生に対しても、「撮れる史料は全て撮ってきなさい」と伝えています(笑)。
史料の充実がもたらした研究の変化
デジカメで史料を撮影できるようになる前後では、史料状況、そして研究の精度も変わります。昔の優れた研究は多くあり、私自身も多くを学んできましたが、あらたな史料で見解を修正せざるを得ないこともたくさんあります。
一つ例をあげると、1964年の韓国では、ソウルで起こった数万人規模のデモが大統領府の青瓦台を包囲し、それに対して朴正煕大統領が戒厳令を施行する「六・三事態」が起こるのですが、これについて、アメリカ側の英語史料はほとんど出てなかったんですね。この六・三事態について、アメリカ側は韓国の戒厳令施行をはじめから支持していたと言われていたのですが、史料を見ていくと、駐韓米大使は戒厳令への賛否を表明しておらず、むしろ牽制するような発言をしていたことがわかってきます。当時の朴政治が不安定化していたため、アメリカ側は政権を保たせるべく支援していましたが、戒厳令についてはむしろ政権が崩壊する可能性を予測して、肩入れをしない対応だったわけです。
そうした箇所は、史料を読んでいて「え? そうだったの?」と驚きましたし、非常に面白かったです。アメリカ側の思惑、そしてどのように施策が行われていったのかは、ぜひ本書をお読みいただきたいですね。
理論枠組みでみえる国際情勢の裏側
――本書で示した非対称同盟の理論からは、現在の国際情勢の理解にどのような示唆を与えるのでしょうか?
一つの例が、ロシア・ウクライナおよびイスラエル・パレスチナの二つの戦争をどう読み解くかです。それは、いずれにも非対称同盟に類似した事象が存在しているからです。ウクライナについては、先ほど申し上げたようにアメリカと同盟関係にあるとは言えませんが、議論としては援用可能です。少し前にまとめた論稿「同盟論からみるウクライナ戦争」 で詳しく論じているので、ぜひお読みいただければと思います。
イスラエル・パレスチナについては、ガザ紛争勃発前後、当初アメリカはイスラエルに寄り添い譲歩することでこれをコントロールしようとしました。ですがその譲歩に対して、イスラエル側はアメリカの言うことを全く聞かない。とはいっても、イスラエルを見捨てることは戦略的にも国内政治的にもできない。そこでアメリカは一旦武器を送るのをやめてみたり、やはり再開したり、といった行動を繰り返しています。そしてイスラエル政府に対する信頼が揺らいでいくと、極右勢力の影響力排除を求めるなど、場合によってはネタニヤフ政権に介入することも視野にいれていく――そういった構図も見えてきます。2024年夏の時点では、アメリカはイスラエルの統制には失敗し続けているというべきでしょうが、そうした主導国の追随国の政権、そしてその内政への認識の変化に注目することが、この二つの戦争の分析には不可欠でしょう。
それ以外の国々との関係も見えてきます。たとえば、バイデン大統領は以前サウジアラビアに対し、圧力をかける非常に厳しい対応をしていましたが、ウクライナ戦争が始まると石油の増産を求めて近づいていく。一度断られるものの、一気に距離は近くなり、同盟条約を結ぶとの報道もありました。はじめ強い圧力をかけていたのが、どんどんバックダウンしている状況が読み解けます。これが本書における議論の面白いところで、戦略的な問題と国内の状況が絡みあいながら、圧力から譲歩へ転じていく過程がみえる。譲歩に至ったのも、その時々のアメリカの政権の性格のみならず、構造的な問題が大きいことがポイントで、それをもとに分析することが可能です。
弱体化する帝国アメリカ
一方、アメリカの国際秩序構想が、いまどれだけ同盟国を引きつける力があるのか、その点にも注目する必要があります。
現在アメリカは大統領選を控えていますが、同時に国際情勢は揺らいでいます。東アジア、欧州、中東の三正面で深刻な対立と紛争に直面し、しかもウクライナでは戦況は思わしくなく、ガザでは規範の観点からも紛争解決という意味でも、深刻なリーダーシップの欠如をあらわにしています。そして米中対立をめぐっては、同盟国に対して半導体等をはじめとした対中貿易に関する制約を課そうとする一方で、これを補うための経済秩序構想を打ち出すことはできておらず、そもそもそのような動きすらない。対中貿易を制約することで同盟国が何を得られるのか、あるいはいかに損失を抑えられるのか、見通しを提示できていないと言わざるを得ません。
これまで日本は日米同盟の中にあることで、アメリカ主導の国際秩序による自由な貿易関係と安定した国際環境を享受することができました。ですがいまや、バイデン政権率いる民主党政権の下でこれまでお話ししたような状況が生じていますし、ハリス副大統領が当選したとしてもこれが大きく変化するとはいまのところ考えられません。共和党のトランプ候補の場合は、ここで論じたような国際秩序構想や、同盟国との関係のヴィジョンそのものを持っていないでしょう(もちろん周囲の高官は別ですが)。
日本外交の行く末は?
もはや安全保障以外の分野では、アメリカ主導の国際秩序が日本に恩恵をもたらすかどうか、その保証はないのです。ならば、日本はいかに振る舞うべきなのでしょうか。
戦後の日本外交は、アメリカの外圧に反応するだけの受動的な外交、あるいは眼前の利益を追うのみの実利的外交とも言われてきました。ですが、私はそうではないと考えています。冷戦期以来、アジア・太平洋を舞台にその国際秩序の一部を改変する、あるいは国際秩序自体も、経済を中心に日本の理念と利益を反映するように修正を試みてきた、長い伝統があるからです。
いま、アメリカという主導国の提供する国際秩序に参入する追随国の立場から、日本は否応なく脱却を迫られていると言えます。強大な中国という現実を受け止めつつ、アメリカとの同盟関係を利用しながら、自らにとって望ましい国際秩序を創り出していく。そのような創造的な外交と、これを支える理性的な世論が、今ほど必要とされているときはありません。
プロフィール
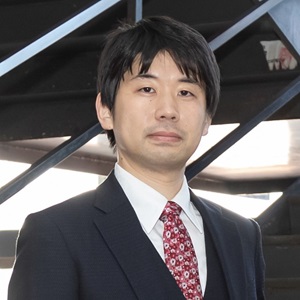
玉置敦彦
1983年生。中央大学法学部准教授(国際政治学)。東京大学法学部卒業、Boston University(フルブライト奨学生)及び Yale University(Department of History)留学を経て、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、博士(法学)。著書に『帝国アメリカがゆずるとき――譲歩と圧力の非対称同盟』(岩波書店)、主な論文に“Japan’s Quest for a Rules-based International Order: The Japan-US alliance and the decline of US liberal hegemony,” Contemporary Politics, Vol. 26, No. 4; “Japan and International Organizations,” (with Phillip Y. Lipscy) in Robert J. Pekkanen and Saadia M. Pekkanen eds., The Oxford Handbook of Japanese Politics (Oxford University Press); “Like-Minded Allies? Indo-Pacific Partners’ Views on Possible Changes in the U.S. Relationship with Taiwan,” with Jeffrey W. Hornung, Miranda Priebe, Bryan Rooney, M. Patrick Hulme, and Yu Inagaki (RAND Corporation). 「ジャパン・ハンズ──変容する日米関係と米政権日本専門家の視線,1965─68年」『思想』第1017号,「ベトナム戦争をめぐる米比関係──非対称同盟と「力のパラドックス」」『国際政治』第188号,「同盟論からみるウクライナ戦争」『思想』第1201号、他多数。



