2016.11.02

憲法論議を「法律家共同体」から取り戻せ――武器としての『「憲法改正」の比較政治学』
文化の日。「国民の祝日に関する法律」第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とする。それでは、それがなぜ11月3日でなくてはならないのだろうか。実は、70年前、1946年(昭和21年)のこの日、日本国憲法が公布されたのである(なお、5月3日の憲法記念日は、翌47年(昭和22年)に憲法が施行された日である)。日本国憲法が自由や平和、文化といった理念を重視していることにちなんで、この日は祝日とされた。
その日本国憲法をめぐる情勢は、いまや新たなステージに入りつつある観がある。改憲を志向する勢力が、国会において憲法改正発議に必要な「3分の2」を獲得し、憲法審査会での審議がまもなく再開するからである。改正を視野に入れた憲法論議は今後、ますますホット・イシューとなってくるだろう。
2016年7月に刊行された駒村圭吾=待鳥聡史(編)『「憲法改正」の比較政治学』(弘文堂)は、そんな今こそ注目されるべき多くの問題提起をなしている。そもそも、一体「憲法改正」とは具体的にどのような営みなのであろうか。主要各国の「憲法改正」の事例をつぶさに眺めてみることで、改正経験の有無や回数といった表層的な事柄にとどまらない、「憲法改正」の多様な見方が浮かび上がるのではないか。
本書が試みたのは、憲法学×政治学という、これまであまり交わることのなかった分野どうしのコラボレーション。これからの憲法論議のあるべきベースラインと新たな可能性を静かに、しかし力強く示唆している本書の「使い方」について、政治学者であり本書の共著者の一人である浅羽祐樹教授(新潟県立大学)と、気鋭の憲法学者である横大道聡准教授(慶應義塾大学)、そして政治記者の清水真人氏(日本経済新聞編集委員)を迎え、1990年代の政治改革から昨今の皇室典範をめぐる議論までを題材として、熱く語ってもらった。(弘文堂編集部)
「基幹的政治制度」として憲法をみるということ
浅羽 憲法や憲法改正をめぐる議論はこれまで、結論ありきになりがちでした。そこで『「憲法改正」の比較政治学』(以下、「本書」)は、特定の条項について変わったか変わっていないか、改めるべきか護るべきかという議論のされ方に対する違和感から出発しました。学問的に一歩引いて、憲法改正に対する態度をとりあえずカッコに入れたうえで議論するには、どういう道具立てを準備すればよいのか。どうすれば冷静に、他国との比較や歴史的な先例との比較の中で、日本の事例を考えることができるのか。こういった問題意識が、本書全体を貫く指針、構成原理、いわばコンスティチューションになりました。つまり、「憲法」や「憲法改正」についてどのように観念するのか、そしてそれをどうやってそれぞれの事例に当てはめて分析していくのか、という部分でイノベーションを試みたというわけです。
本書で提示した視座は、「基幹的政治制度」です。憲法典――憲法という名の付いているテクスト――が改正されるかどうかが、これまで憲法改正の有無を測る基準だったわけですが、もう少し視座を広げて「政治制度」に着目をする。その中でも、国の政治の仕組みの根幹を定める「基幹的政治制度」について、「憲法体制」として捉えて、その制度が変われば、憲法典の改正がなくても、憲法体制が変わった、とみなすことができるという視座を打ち出しました。
それでは、何が「基幹的政治制度」に入るのか。これは多少論争的ですけれども、基本的にはやはり、権力をまず構成し、そのうえで、その構成された権力をいかに各部門に任せて相互に牽制し均衡をはかるのか、という2つの契機があります。前者に該当するのは選挙制度ですし、後者は執政制度で、両方で「基幹的政治制度」を成している、と本書ではみなしています。この2つが「憲法体制」の中でどう配置されているのか、にはさまざまなパターンがあり、国によっては両方とも憲法典に置かれている場合もありますし、選挙制度の部分は憲法典ではなく法律で詳細が決まっている場合もあります。そもそも、何を憲法典で規定し、何を法律に回すのかは一様ではありません。
日本の場合、選挙制度は公職選挙法という法律マターです。これが1990年代に公選法を改正することで中選挙区制から小選挙区比例代表並立制へと変わったわけですが、選挙制度という「基幹的政治制度」が大きく変化したという意味では「憲法体制」が変わったと言えるのではないか、ということです。「憲法」や「憲法改正」を別様に観念することで、戦後日本政治においても、日本国憲法という憲法「典」の改正はなかったけれども、選挙制度改革という「基幹的政治制度の変化」があったので、実質的には「憲法体制の変化」があったという見方が可能になります。
本書では、この「憲法典の改正なき憲法体制の変化」について、良いとか悪いとかという論者の規範的あるいは政治的な判断が示されているのではなくて、観念を変えるとその実証の部分――いつ、どこで、何が、どのように変わったとか変わっていないとか――をこれまでとは違うかたちで提示することができるのではないか、という呼びかけにもなっているわけです。明示されているわけではありませんが、今のアクチュアルな政治課題に取り組むうえでも、そのほうがダイナミズムを捉えることができ、かつレレバンシー(妥当性)も確保できるのではないでしょうか。
横大道 本書で駒村圭吾先生(慶應義塾大学教授)が書かれていますけれども、一般的な憲法の教科書は、最初に「憲法とは何か」という項目を立てて、「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」の区別とか、「立憲的意味の憲法」といった概念を出して、憲法「典」だけが憲法学の対象ではないということを最初に述べます。そのように言っておきながら、憲法改正の項目のところになると、一転して憲法「典」の改正に関する解説しかしていません。実は、「基幹的政治制度」とか「実質的意味の憲法」が重要であってそれも憲法だ、という視点を憲法学はもともと持っていたはずなのに、それがいつの間にか消えていたというのが、これまでの一般的な教科書だったのではないかなと思います。
そうした状況に対して、「実質的意味の憲法」の改正も含めて憲法改正のところまできちんと憲法学の対象であるということを非常に明瞭に出してきたのが本書であり、憲法学にとっても意味があるという感想をまず持ちました。
なお、本書では導入部分に引き続いて、イギリスについて近藤康史先生(筑波大学准教授)と上田健介先生(近畿大学教授)の議論が収録されています。そこでは、イギリスは成文憲法典を持たないがゆえに、「憲法とは何か」「憲法改正とは何か」を常に自覚的に論じていることが明瞭に示されており、本書全体の企図との関係で大変周到な配置となっていますね。
浅羽 構成をお褒めいただき恐縮です。いわば本書の「憲法」がよくデザインされていたということですね(汗)。
横大道 憲法典の「改正」というのは非常に特別な瞬間で、日常と切り離された局面であると理解されるのが一般的であると思います。しかし、「実質的意味の憲法」の改正を視野に入れた場合、憲法に関わる政治というものが日常の政治からまったく切り離された別物なのではなくて、同一線上に並んだプロセスという視点から見ることができるようになるのではないか。
要するに本書は、「憲法の改正は、主権者が立ち現れて制憲権が行使されるという、非常に特別な瞬間である」というような、そういう固定化された「憲法改正」の見方を変える、非常に良いきっかけになるという印象を持ちました。
清水 昨年来、集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更問題を取材してきたんですけれども、内容においても、プロセスにおいても、あれは、はたして是とすべきことだったのか、非とすべきことであったのか、未だに自分の中で回答が出せません。自分なりの評価が定まらないモヤモヤしたものがあります。
なぜか。まず、安倍晋三首相が内閣法制局長官を代えて憲法解釈の変更の閣議決定に動いた。その後、それに沿った安全保障関連法案を国会に提出して審議するという手順を取りました。その出発点となった首相官邸の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」には政治学者や国際法学者が何人も関わって解釈変更を容認しました。半面、外側にいた多くの憲法学者からは、この解釈変更のプロセス自体にも猛反発が起きましたね。アカデミズムも割れたとなると、我々は一体どう受け止めればよいのか、戸惑いました。
次に、今度は憲法典の改正プロセスが始まるかもしれないという政治状況にあります。ではそれをどう捉えるのか、今度は何が起きるのか、という課題に直面しています。もちろん憲法改正手続法、いわゆる国民投票法という法律はあるんですけれども、まず国会のどこでどういう議論をしてどういうプロセスで改正案の発議に至るのか。そのあとの国民投票も、現実にどんな流れを経て行われていくのか。誰も経験がない。実は政治家たちもまったく手探りです。どうプロセスを創っていくのか。
そう思案しているときに、本書が出たというわけです。本書は、「憲法改正」というものの捉え方についても形式・実質の両方がありうるよ、と議論の射程を大きく広げてくれています。現実にどういうことが起こるのかという政治プロセスについても、改正の是非などは別問題として、ひとまず比較研究をしてみようということで、欧米主要国や韓国について非常に多様なパターンの知見が得られる。もちろん日本についても明治憲法下を題材に歴史的な考察を展開していますけれども、さしあたり各国の経験に学べる。
この手の研究で、憲法学と政治学がコラボレーションする例は、今まで必ずしも多くなかったのではないでしょうか。率直に申し上げて、憲法学者と政治学者はなぜこんなに仲が悪いのか、と不思議に思う場面がしばしばあったものですから。本書の内容以前に、両者の協働というこの出版企画自体がひとつのニュースではないかと。アカデミズムの変化の胎動みたいなものを、手に取ったときに非常に感じた次第です。
浅羽 アカデミズムの怠慢とタコツボの問題をご指摘いただき、耳が痛いです。政治学はどうしても、すでに起きたことについて経験的に分析することを第一義的な課題とするものですから、政策提言や制度の改革に向けてまとまって何かをするということは、なかなかありません。
しかも、90年代以降に日本では選挙制度改革があって、これはもちろん憲法「典」の改正ではないですが、ゲームのルールもプレイの仕方も実質的に大きく変わったので、そこに分析を集中させたわけです。いわば広い意味での「憲法体制の変化」の部分を明らかにしてきたことの代償だったのか、憲法「典」の改正それ自体を正面に据えて取り組んでこなかった。
そもそも政治学、特にポリサイ(政治科学)は経験分析が主眼ですし、日本には憲法改正の事例がなかったという事情もあります。だからこそ、すでに起きた他国の事例を盛り込んでいるというのは本書の特徴です。ともかく、清水さんのご指摘に対しては、反省が半分、残りの半分は政治学の学問的性格によるところが大きいと言えそうです。
横大道 憲法学としては、これまで政治学とまったく没交渉であったというわけでは当然なくて、いろいろなところで参考にしてきたとは思います。政治哲学は当然のこととして、そのほかにも、たとえば、議会研究であればレイプハルトなんかは憲法学者も当然読んでいますし、政党であればサルトーリの研究であるとか、そういう政治学の研究成果を参考にしてきました。しかし、それは必ずしも体系的でも包括的でもありませんでした。それを包括的にまとめるような役割を果たしたのが、今回の「実質的意味の憲法」とか「基幹的政治制度」という視座の設定です。本書ではこれを視座として設定し、共通の議論の土台を設定したために、政治学とのコラボレーションが成功したのでしょう。
浅羽 そうですね。政治学では近年「合理的選択新制度論」という観点が一般的で、これは制度が各アクターの戦略や相互作用を規定するという見方です。同時に、アクターの相互作用によって制度そのものが変わるという逆のベクトルもあって、制度が生まれ、維持され、変わっていくダイナミズムも射程に捉えます。そうした制度のうちのひとつが憲法であるわけですが、必ずしも憲法ですべてをカバーしているわけではありません。ゲームのルールとして、選挙制度も同じくらい重要です。憲法「典」だけ見ていては、制度の効果や起源の全容をつかめないというわけです。
たとえば、選挙制度が中選挙区制から小選挙区比例代表並立制になった結果、政党間の関係(政治システム)、政党(執行部)と政治家の関係(政党組織)がどう変わったのか、そもそもなぜ変わったのかについて、政治学は経験的知見を積み重ねてきました。しかし――極めて重要ではありますが――選挙制度改革の効果や帰結に分析が集中しすぎたきらいがあります。そこで本書が、議会制度や司法制度など他の政治制度も含めてトータルで「基幹的政治制度」として概念化し、それが憲法学で言われてきた「実質的意味での憲法」と実は同じものなんだということを、今回、もしかしたら初めて示したのかもしれません。そうすることで、政治学と憲法学との間に橋が架かって、前よりも見晴らしがよくなった、見通しが立つようになったのだとしたら、とても嬉しいですね。
90年代選挙制度改革で「憲法体制」が変わった
清水 本書は政治ジャーナリズムにも問いを突き付けるところがあります。反省の告白をしなければならないのですが、90年代からまず選挙制度が変わって小選挙区制が衆議院に導入されたことは、極めて大きなインパクトがあった。自民党の派閥は急速に衰え、首相(総裁)や幹事長ら党執行部に権力が集中した。野党陣営は自民党に対抗する政党を創る力学が働いてガラガラと再編されました。政権が交代しうる、実際に政権交代が起こったということで、まったく政党政治のゲームのルールが変わってしまった。
この政治改革を追うかたちで橋本行革が行われて、首相のリーダーシップを強化する補佐体制であるとか、官邸主導などとざっくりとした言葉を使っていますけれども、官邸の強化が図られた。この2つで政治ゲームのルールが2000年代に入って一変してしまった。私は小泉純一郎首相の取材を至近距離でしていましたので、それを痛感させられました。
指導者一人ひとりの個性が政治を動かすのも事実ですが、その前提として、法律などの制度の改革がこれだけ大きな現実の変革につながる。このことを、いろいろと書いてきたつもりなんですけれども、それはジャーナリズムの中でも決して――大石眞先生(京都大学)などが「憲法改革」というような言葉を使われていたと思うんですけれども――そこまでの重みをもった主流の議論ではなくて、政治家の個性であるとか人間模様、あるいは派閥力学みたいなもので分析する根強い伝統がありました。制度改革でゲームが変わる、みたいなことはなかなか十分に理解がされず、小泉内閣が5年5か月続いた後でもむしろ「変人宰相が異常な政治を行った異常な時代だった」という総括のほうがむしろ主流だったように思うんですね。
ですから、あの一連の統治機構改革について、本書がここに至ってひとつのケリをつけてくれたようにも思えます。《「基幹的政治制度」が変わることは「実質的意味の憲法」の変化を意味する》という枠組みをもって捉えるということが、今まで私が感じてきた90年代からの統治機構改革の重みと平仄(ひょうそく)が合ってきたと受け止めています。
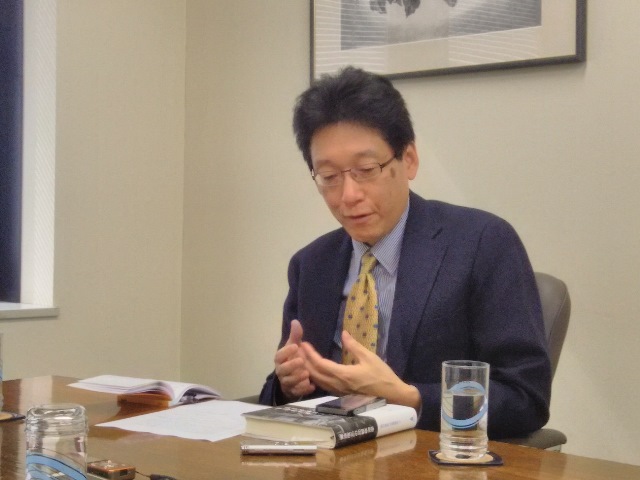
浅羽 統治機構改革はまさに「憲法体制の変化」だったわけですが、その全容がなかなか理解しにくかったのは、方向性がバラバラだったからなんですよね。こと選挙制度改革に絞っても、衆議院は政党システムとしては二大政党間の競争、政党組織としては党執行部への権力の集中を促す小選挙区制(中心の並立制)に変えたのに対して、2000年代に入って手を付けた参議院はむしろ、比例代表制はそのままで非拘束名簿式を導入して、小政党の存続や各議員の自律性を担保する制度に改めたりと、トータルで何を目指しているのかがよくわからない。
さらに、内閣機能の強化であるとか、裁判員制度の導入など、いろいろな制度が大きく変わったんですが、その時々でベクトルが整序されていたわけではありません。そのため、ここ20年で、「この国のかたち」は確かに変わったんだけれども、全体として一体何だったのか、つかみきれていないし、そもそもうまくデザインできたのかどうかがわかりにくい。
清水 あの統治機構改革に誰か特定の設計者がいたわけでもなく、その時々の現実政治の流れの中でいろいろと修正されたり、改革が不十分だったりということは多々あるかと思います。ただ、知的な底流がなかったわけではありません。橋本行革では、憲法学者の佐藤幸治先生(京都大学名誉教授)は多大な貢献をされました。佐藤先生が同様に取り組まれた司法制度改革は「行政による事前規制から、司法による事後チェックの社会へ」ということで、橋本行革とセットで出てきたものです。
政治改革・選挙制度改革は政治学者の佐々木毅先生、地方分権改革は西尾勝先生(ともに東京大学名誉教授)が深くコミットされました。「司法制度改革もまた、政治改革の一環である」と喝破された三谷太一郎先生(東京大学名誉教授)も含めてですが、この4名はアカデミズムの横のつながりの中で諸改革に橋を架ける努力もされたと思いますので、やはり振り返ってみれば改革の一筋の航跡は見えるのではないかと思います。ただ、浅羽先生がおっしゃったように、それらが現実政治の中でもみくちゃになる中で、どこまで整合的なものになっているかという論点は大事だと思います。
浅羽 制度改革がひとつずつ進んだときに、アカデミズムの知見のインプットだとか人的な貢献がなかった、という意味では決してありません。ただ、諸制度が組み合わさって効果をもたらすということになかなか関心が向かず、こと選挙制度改革に限っても、当初から衆議院と参議院を合わせて改革しないといけないとか、あるいは2000年代に入って参議院に手をつけたときに、先の衆議院との整合性はどうするのかについてキチンと詰めたとはとても思えません。実際は政治的思惑が露骨で、業界団体がどれだけ票を集められるのかを確認するために拘束名簿から非拘束名簿に変えたと。それでやってみたところ、衆参はねじれるし、参院自民は幹事長によるコントロールが及びにくいという結果になった。
第2次安倍内閣までは、参議院がこんなに強くて、はて困った、という状況で、それぞれの制度を変えたときの「意図せざる帰結」が合わせ技で出てきて、ようやくトータルで考え始めたわけです。でも、変えてから時間が経っているし、いろんな経緯が重なっているので、今、衆参の権限配置に見合うように参議院の選挙制度を変えられるかとなると、なかなか難しい。逆に、参議院を都道府県代表にするならば、パッケージとして権限も見直さなければならない。このことが、日本において90年代以降「基幹的政治制度=憲法体制」が変わったことの一番大きな帰結であり、今日の政治的課題であると言えるのではないでしょうか。
なぜ、日本では憲法「典」の改正はなされないのか
浅羽 本書は、「憲法」や「憲法改正」を捉え直す視座を提供していますが、面白いのは、2名の編者の間で温度差が最後まで残っているところです。政治学側の編者である待鳥聡史先生(京都大学教授)はグラデーションのように考えていて、改正要件が3分の2の硬性憲法を変えるのと2分の1の通常の法律を変えるのは同一線上の差にすぎない――とはいえ、やはり2分の1と3分の2とでは違うので、変えやすさとか実際の改正の頻度は当然変わってきますが――というふうに基本的には捉えている。
これに対して――横大道先生も先ほど、日常政治と憲法政治というのは同一線上に並んだプロセスなんだ、とおっしゃいましたが――憲法学側の編者である駒村先生は、その質的な差、不連続性を強調しています。本書は、一方で待鳥先生のように「フラットに」捉える有効性を示しつつ、他方でやはり日本の場合は閾値(しきいち)として「2分の1」と「3分の2」とでは決定的に違うにもかかわらず、「一緒くたに」捉えることによってその差がぼやけてしまう怖さがあるということ――待鳥先生もそこに無頓着なわけではありませんが――については、自覚的でなければならないと警告しています。
横大道 駒村先生の「あとがき」にあった、それでも憲法学者としては憲法「典」の改正にこだわりたい、というあたりのことですね。
浅羽 本書でのアメリカのニューディールに関する分析もそのことを示唆しています。つまり、当時、実質的には憲法体制が変わったと言えるが、そこまで「憲法改正権力」、あるいは生身の「憲法制定権力」が立ち上がり、一種の昂奮した状態にあったのならば、テクストの改正につながってもよかったのではないか、という議論です。つながらなかったのにはそれなりに理由があり、その差はやはり決定的だろうというわけです。
横大道 今おっしゃられたアメリカの事例は、テクストが変わらず、しかし「実質的意味の憲法」が変わったという例の典型ですよね。本書では岡山裕先生(慶應義塾大学教授)が詳しく説明されていますが、非常に興味深かったのは、変化をうまく言語化できなかったからテクスト化されなかった、という説明です。そういう理由でテクスト化されないというのは、説得的な説明であると思います。
ただ、先ほどの浅羽先生のお話にも関わるのですが、そもそも憲法典の構造がテクストの改正を必要としないものになっているのではないかというところを、まずは見なければならないのではないかと思います。これは、日本国憲法との関連で言えば、本書で西村裕一先生(北海道大学准教授)とか瀧井一博先生(国際日本文化研究センター教授)が書かれていますけれども、要するに、日本国憲法は非常に簡素な憲法典であるということです。
浅羽 字数が短い、ということですか。
横大道 非常に短い。「比較憲法プロジェクト」というアメリカのウェブサイトがあって、各国の憲法を長い順に並べているんですね。日本は下から5番目で、ラオス、ラトビア、ミクロネシアあたりと下位争いをしており、その短さが際立っています。内容に目を向けてみても、「法律でこれを定める」などと書いてあるところが30か所以上あるわけですね。だから、憲法「典」に手を付けなくても、「実質的意味の憲法」の改正はできる、そういう憲法典であったというのが第1にあります。このあたりは、政治学者のケネス・盛・マッケルウェイン先生(東京大学准教授)が指摘されているところです。
第2に、これは戦後の憲法学あるいは憲法状況で、「なんだかんだ言っても最終的には9条だろう」という議論があって、これは「蟻の一穴(いっけつ)論」ということで本書でも田近肇先生(近畿大学教授)が言及されていましたけれども、つまり、憲法「典」には絶対に手を付けさせないという主張です。そこで、憲法「典」に手を付けようとすることは政治的にも非常にコストがかかると。
それで日本国憲法を見てみると、実は、法律の改正で「実質的意味の憲法」の改正ができる仕組みになっている。となれば、憲法「典」の改正に行かないというのは、日本国憲法の構造上ある意味必然的にそうなっていると言えるわけで、これを、政府が解釈改憲をするのはけしからんとか、安倍総理のパーソナリティの問題にするのではなくて、そういう「仕組み」になっているというところをまず見なければいけない。
他方、たとえば、ドイツでは、「実質的意味の憲法」の改正に際しては、憲法「典」を変えるべきであるということが比較的明瞭に意識されているようです。日本と同じ敗戦国でありながら非常に大きな違いを見せています。本書では赤坂幸一先生(九州大学准教授)と近藤正基先生(神戸大学准教授)が書かれていますけれども、60回近くの改正があったという事実の裏には、そもそも憲法でどういうふうに国を創っていくのかというところからの発想、考え方の違いがあります。要するに、何が憲法「典」の改正に至る場合で、何が至らない場合か、それもまた「制度」との関係を抜きにしては語れないのではないかという気がします。
浅羽先生と國分典子先生(名古屋大学教授)が担当された韓国についても、1987年憲法以前は頻繁な憲法典改正が見られた一方で、1987年以降は憲法典の改正が下火になる。イタリアはその逆ですが、それでは、そのような動向は「基幹的政治制度」の制度設計とどのような関係があるのか。本書ではそうした制度の視点が示されていますが、日本国憲法を考える際にも、そのような視点が必要でしょう。

浅羽 今のお話は、「特別な瞬間」も訪れず、憲法制定権力――剥き出しのままなのか、飼い馴らされたものなのかはともかく――も立ち現れなかったがゆえにテクスト改正がなされなかったのではなく、そもそも日本国憲法は字数が単に短く、ターゲットになりうる項目が全部法律マターとなっていたので、2分の1ですむ法改正で十分だったからだ、ということでしょうか。
横大道 そうですね。そしてさらに別の要素を言えば、「司法消極主義」があって――これもまた、制度的な要因が関わっているのですが――裁判所は憲法問題の判断を積極的に行わない。そうすると必然的に、政治部門に負荷がかかってくる。そういう中で、9条の解釈をはじめとした実践が積み重ねられてきたのが、日本の「国のありよう」であったわけです。まずはそこに目を向けないと、今回の安保法制の出来事を、単に小泉総理や安倍総理といった非常に特殊なパーソナリティをもった人に帰するような、あるいは、「政治の矩(のり)」といった政治家の心構えのように矮小化された議論になってしまうのではないか、と思います。
清水 そこはやはり政治ジャーナリズムの弱みなんです。「制度」論にとても弱い。55年体制下では、自民党の派閥とか親分・子分の人間関係で、本当にすべてが決まっていた。それはもう現実には雲散霧消しています。しかし、政治家の側にしろ取材する側にしろ、意識が変わりきらないものですから、どうしても指導者論、人格論を軸に政治を語りたがる。小泉氏が変人だと言う議論や、何でも安倍首相の人格に帰する議論だけでは本質を見失いかねないというのは、その通りだと思いますね。
横大道 かつての中選挙区制についても、1つの選挙区で同じ政党から複数の候補者を立てることが派閥化をもたらした、といったところを憲法学でももっと見なければいけなかった。その意味ではやはり、本来は政治学などの分野とコラボレーションしてやっていくべきだったわけです。一方で、限られた時間の中で日々の出来事を追うジャーナリズムにとっては、なかなかそういう視点というのは難しいのかもしれません。
浅羽 政治をアクターひとつひとつのミクロな観点、それらの戦略的相互作用から見るとき、ジャーナリズムだと政治家の個性やイデオロギーに注目する反面、社会科学だと、まず「(基幹的)政治制度」に由来するインセンティブ(動機/誘引)構造に注目します。それで不十分ならば――マクロな文化や個々のアイデンティティといった――特異な要素をさらに追加して検討するという順番になります。ただ、それだとキャラ立ちしないし、グッとくるエピソードも出てこないので、一般の読者にはアピールしにくいでしょうね。
清水 私自身は政治記者としては理屈っぽいほうかもしれませんが、平成政治史は制度改革抜きに論じられませんし、「制度」を遡れば憲法まで行き着くわけです。ただ、制度の重要性やその変革のインパクトを日々のニュース報道の中で伝えていくのはなかなか難しい。昨今は限界があるかな、と思ったりもするのですが、あきらめてはいけない、と教えられたのは、昨年亡くなられた経済学者の青木昌彦先生(スタンフォード大学名誉教授)の言葉です。比較制度分析がご専門で、やはり「制度」をとことん論じておられて、青木先生が最後に書き残されたものを読むと、「今の日本は移りゆく40年のさなかにある」とあるのです。
つまり、90年代初めぐらいから日本はいろいろな制度変化――統治機構だけでなく、経済社会全体も――があって、今はそれらが移りゆく40年の渦中にある、と。単に法律の条文や紙に書かれたルールが変わっただけで、人びとの意識までがすぐ変わるわけではない。そこまで含めての「制度」なんですね。意識変革には時間がかかる。世代がほぼ丸ごと入れ替わる時間が必要で、それが「40年」の意味です。それくらい時が経たないときちんとした結論は出ないんだ、と。それを読んでまた元気が出まして、統治機構改革の制度論を政治ジャーナリズムにどう組み込んでいくか、引き続き考えたいと思っています。
そこで本書ですが、各国の比較分析が中心で、ある意味では日本の憲法改正は中心課題ではないこともあってか――意外なまでにと言えば怒られるかもしれませんが――憲法学者の方々も非常に醒めた、冷徹な制度分析をされている。その意味で本書は、今後「憲法改正」の問題を捉えるときには、座右に置くべき一冊だと思います。
司法を政治学する――「司法政治論」の可能性
横大道 脱線して恐縮ですが、さっきの制度論の話にひきつけて一言。今、アメリカでどういう議論があるかと言うと、アメリカ憲法の改正というのは、本書にも川岸令和先生(早稲田大学教授)が書かれているように、結構厳しいんですね。特に、上院の権限に手を付けるような改正はほとんど不可能である、と指摘されています。そうするとどうなるか。そこで、これまで積極的に憲法判断をしてきた裁判所の憲法解釈で変更してもらおうということになる。そっちの方向に向かうわけです。
今、オバマ大統領が、亡くなったスカリア連邦最高裁判事の後任を任命しようとしていますけれども、それを上院がストップさせています。これはまさに、裁判官の任命過程が高度に政治化しているということです。自分と政治的立場の近い人物を最高裁に送り込めば「実質的意味の憲法」を変えることができる、と。それは「成文の憲法典」を変えるよりもはるかに有効で現実的だと。その意味では、アメリカはアメリカなりの病理がある。現実政治として憲法改正が難しい、不可能である、このことが裁判官の任命過程の政治化につながり、そこで政治的に任命された裁判官が任命者のイデオロギーに親和的な判決を下す。これに対して、「憲法を裁判所から取り戻す」という議論や「ポピュリスト立憲主義」といったような、憲法学の潮流が出てくる。そういう状況にアメリカはあるのです。
本書にはいろいろな国の「憲法改正」が書かれていますけれども、それぞれの国の「憲法改正」が理想的な姿であるわけでは当然なくて、そこでもまた、それなりの問題を抱えており、それへの対応に苦戦しているのです。本書に興味を持った読者は、その先のところまで勉強していってもらえればよいのではないかと思いました。
浅羽 日本でも安倍政権の下で内閣法制局の長官人事が問題になったわけですが、率直に言って、これまでも別に手を突っ込もうと思えばいくらでもできたのにそれをしなかっただけで、今さら何を驚いているんだ、という話です。そもそも(事実上)内閣(総理大臣個人)は最高裁判事を任意に任命できるわけで、すでに9名が自民党の政権復帰以降の任命で、総理総裁の任期延長が実現するとそのうち15名全員が安倍内閣による任命ということになります。それが国会承認マターですらないわけで、気にするんだったらそっちだろうと。
スカリア判事の件は日本の紙面でも大きく出るのに、法制局長官もそうですが、最高裁の人事となると関心が低い。私の研究している韓国では必ず新聞の1面トップ扱いになりますが、やはり、それだけ政治的に重要であるということです。どんな判事がとりわけ憲法裁判所に送り込まれるか、誰に任命されるかによって、判決動向が大きく左右されるということを考えると、任命過程は政治的関心事、もっと言えば理念的な対立の場になります。
一方、日本の場合は、幸か不幸か、関心がまったく向いていなくて、安倍政権に批判的な人も法制局長官の方は注目するけれども、最高裁判事はこの間5分の3も入れ替わっているのにそのことを正面から取り上げたりしません。
たとえば、2009年に政権交代が起き民主党政権になったことで、自民党時代の最高裁判事任命パターンと違いがあるのか。そしてそれによって判決に差が出るようになったのかどうか。目につきやすい大法廷の違憲判決だけでなく、小法廷や判事一人ひとりの個別意見に対する検証が必要です。最高裁判事の国民審査には、判断材料があまりに少なすぎます。
別の例を挙げると、この年(2009年)の衆院選の前に、自民党が相対的に若い高裁長官をいきなり最高裁長官に任命したんですよね。これは政権交代となることがほぼ確実な中で、野に下ったときの「保険」として、政治過程を外から拘束しようとするものだったのではないか。こういったことも、本来キチンと議論すべきです。
もうひとつ例を挙げて、ちょっと踏み込んで言うと、90年代に社会党が政権に就いたときに、村山富市総理よりも「土井たか子最高裁長官」を獲った方が社会党のレガシーを残し、後の自民単独政権による「行き過ぎ」を縛ることができたかもしれないという議論も、本来あって然るべきです。実際は、自社さ連立政権期に任命された判事は、それ以前の自民党単独政権期とまったく変わらないタイプのエリートだった、という分析結果があります。
とにかく、そもそも手を突っ込もうと思えば、国会承認マターですらないところでいかようにもできたし、これからもできるのです。こういう司法と政治の間の、本来「のっぴきならない関係」については、日本のジャーナリズムもアメリカの事例にそれだけ関心を向けるのであれば、もっと足下の話に関心を向けていただきたいところです。

清水 幸か不幸かとおっしゃいましたがまさにその通りで、こうした「司法政治」という視点は最近になって私も初めて知ったという状況です。政治ジャーナリズムではほとんどなじみがないでしょう。つまり、司法というのは政治からは非常に遠いものだ、という思い込みで今までずっと来ていると思うんです。
実は、そこは安倍首相自身もそうじゃないかなと思っています。というのは、安倍首相は2013年に法制局長官を代えたんですけれども、あの時、その前任者(山本庸幸元長官)を最高裁判事に任命しました。あれは左遷なのか栄転なのか何だかよくわからない話だったわけですけれども、あの瞬間は法制局長官を代えることのほうが大事だったわけですよね。我々もそこばかり注目しました。でも前任者は最高裁判事になっているんだから、実は気が付いてみたら、安倍さんにとって厄介な憲法解釈などを展開するかもしれない、なのにそこは手綱を放してしまったという、非常に面白い現象だったと思うんです。
それくらい、まだ「司法政治」はあまり意識されていないと思います。おそらく、自民党政権が長く続いてきたことと関係があるんじゃないか。もっと政権交代が頻繁に起きるようになると、いよいよ最高裁人事にも介入しようというようなことが、党派性をもって行われてくる可能性はあって、そうなると――良いか悪いかは別としても――司法政治のダイナミズムが日本にも来るのかもしれないな、と思います。今のところは、まだそこまで話が及んでいないという感じですが。
横大道 憲法学ですと、司法というのは法原理を担い、司(つかさど)る機関であって、清水さんもおっしゃった通り、政治的な動機では動かないと想定されます。法と論理に従って、憲法と法律に従って動く人々なんだから、基本的には誰が裁判官になってもそれ相応のことをやる。法社会学者のダニエル・フット先生(東京大学教授)が、『名もない顔もない司法』というタイトルの本を出していますけれども、そういう「司法観」の是非も含めて、「司法政治論(judicial politics)」――これは浅羽先生も岡山先生も、本書で書かれていますけれども――の研究が今後、もっと注目される場面があるという気がします。
また、先ほどの「制度」との関連で言えば、「憲法裁判所構想」を本当に実現しようとしたときに、間違いなくその手の議論をやっていくことになると思いますね。憲法について判断する専門機関を創るということによって、政治や関連アクターの行動が変わるわけですから、そこにどういう人を送り込むか、というのは政治にとって非常に関心の高いことになってくるわけです。だからそのあたりも、制度設計をする際には相当慎重にやらないと、悪い意味での「司法の政治化」の流れになってしまう危険性はあると思います。
浅羽 いろいろなかたちで――裁判員制度などはその一環でしょうが――司法の民主的な基盤を確保するということがされているわけじゃないですか。民主的正統性が薄いと、どうしても立法府などの政治部門に対して謙抑(けんよく)的になってしまうということの顕著な例が、いわゆる「一票の格差」の問題です。最高裁は、《憲法の予定する司法権と立法権との関係に鑑みると、違憲状態だけれども、どう是正するのかの裁量は国会にある》というわけですが、これがなんとも煮え切らない。他方、最高裁と国会の間で、違憲審査をめぐって「対話」を続けているという見方を佐々木雅寿先生(北海道大学教授)が提示されていて、その場合、この「違憲状態」というのが実に絶妙で、一方的に断罪せず、相互に間合いをはかりながら、ともに憲法価値の実現に向けて進もうとしている、ともみなすことができます。
つまり、司法のあり方が日本でこれまでほとんど争点化してこなかったのは、決して当たり前のことではなくて、むしろ、露骨に手を突っ込まなくても政治部門の意向に反するような判決が出ないようにするコントロールが別のかたちで効いていたからだ、というのが司法政治論の見方ですよね。身もふたもない話になってしまうわけですが。
横大道 憲法学だと、たとえば見平典先生(京都大学准教授)が「司法行動論」をやられています。今おっしゃったようなお話は、憲法学としても今、注目されている領域で、今後もっといろいろと出てくると思います。
皇室典範問題をめぐって――本書をいかに「武器」とするか
浅羽 昨今の憲法改正論議のみならず、天皇の「生前退位」のお気持ちが表明されて、皇室典範の見直し、あるいは特別立法といった議論が出ています。こうしたアクチュアルな政治状況を前に、本書が提示している視座というのはどこまで「使える」のか、そしてそれを当てはめたときに具体的にどう見えてくるのか、ということについてご高見をご披瀝いただければと思います。
清水 憲法改正のプロセスを考えたときに、国会による発議には衆参両院の3分の2以上の賛成というハードルがあります。それに取り組む構えとして、3分の2の数さえ集まれば積極的に改正に進んでいこうという、いわば「多数決型アプローチ」が一方にある。しかし他方で、いやいや、少なくとも最大野党には入ってもらう――「3分の2」とはただ数のことを言っているだけではなくて――とか、アプローチとして非常に幅広い合意形成をすべきなんだ、という考え方もある。参院選後は「最大野党も含めた幅広い党派での合意形成」論のほうが優勢かなという印象を受けています。
それを背景に皇室典範の見直し問題を見ていますと、法律改正の話なのに、どうも幅広い合意形成を当然視しているようですね。極端な話、3分の2どころではない、全会一致に近い状況が必要だというのが、今の永田町の雰囲気だという興味深い状況があります。憲法典の改正をも上回る極端な「合意形成型アプローチ」を取ろうとしている。
そこで本書を読んだときに、憲法改正には多数決型、合意形成型、どちらのアプローチでいくべきかと。比較研究ではこれまた多様であって、実はどちらもありうるということなんですね。ドイツなどにはもともと「交渉民主主義」の伝統があって、憲法改正は当然二大政党を含めた「合意形成型」で進めるべきだということになる。他方、イギリスは不文憲法で普通の法律と同じ扱いで「実質的意味の憲法」も変えられるといったことを見れば、いや、やはり「多数決型」でも構わないのではないかと。こうした憲法改正プロセスの多様さは目から鱗でした。
それからイタリアは、かつては合意形成に意を用いていたのが最近は必ずしもそうでもなく、多数決型で行く面もある、もっともそれが必ずしも成功しているとも限らないということです。なかなか簡単に結論は出ないんだと思うのですが、そういう多様な政治プロセスを各国見比べてみるのは、非常に有用ではないかと思いますね。

横大道 まさに皇室典範というのは「実質的意味の憲法」であって、それに手を付けるというのは、本書が提示している視点で言うところの「憲法改正」の、非常にわかりやすい例かなと思います。しかももうひとつ、この問題が非常に面白いのは、「実質的意味の憲法」だと政治アクターは間違いなく自覚していて、だからこそ、通常の法律の改正とは違ったものだと見ていること。「これはちょっと気をつけないといけない」という扱いをしています。どこまで意図的にやったかはわかりませんが、天皇の「おことば」というかたちで世論の動向を探るようなことをやったりとか、あるいは、いろいろな識者を集めた有識者会議をやって意見をまとめさせようとか、かなり慎重にやっていますよね。
これは、このようなかたちでの合意形成の仕方が――先ほど清水さんのお話にもありましたけれども――今後、将来起こるかもしれない憲法「典」の改正に際して、実は非常に大きなインパクトを持つ可能性がある。その意味で、皇室典範は要するに法律と同じように変えられるから多数決型でやってしまえ、という話がここで出てきてこない、ということが非常に面白いし、重要なことだろうと思います。
浅羽 戦後の皇室典範は通常の法律ですので、改正要件は2分の1であるにもかかわらず、3分の2どころか全会一致のようなかたちで、政治日程的に真っ先になされるかもしれないというわけですね。
清水 与野党を通じて「全会一致が望ましい」という「雰囲気」が形成されています。
浅羽 もし全会一致でなされるとすると、それは図らずも、憲法改正でも、3分の2という明示的な要件があるにもかかわらず、最大野党には必ず入ってもらおう、みたいな議論につながるかもしれないということですね。
清水 皇室典範問題では、内閣が法案提出前に国会に議論の模様を報告して、事前審査というか、事前の合意形成みたいなことを衆参両院議長の下に与野党代表を集めてやるという動きがあるようです。これは前例のない話だと思います。ひとつの「知恵」だとは思いますけれども。皮肉を言えば、なぜ安倍内閣は集団的自衛権の憲法解釈変更を閣議決定する前に、同じように事前に国会と対話する丁寧な手順を踏む選択肢をとらなかったのか。
集団的自衛権は政争の具と化していて、与野党合意の可能性はないと見切っていたのでしょうけれども、今回は明らかに、横大道先生がおっしゃったように、「これは実質的な意味での憲法改正だ」という意識が強い――あるいは無意識の領域かもしれません――ために、そういう手順につながっている。非常に興味深い現象ですね。
浅羽 今後、どうなるかわからないですが、もし、そういう全会一致でなされないといけない、という規範がこの過程を通じて現われて、その通りに実際なされると、新しい96条とも言うべき憲法改正の手続を生み出すことになるかもしれません。つまり、96条には「3分の2」と書かれているのに、これは幅広い総意の形成を要求するためのある種の例示である、というような理解です。
もちろん外国には、イギリスのように多数決型で1票でも超えればよい、というタイプで憲法改正を行う事例があるので、どういうかたちでなされるかはまだわかりません。ただ、この皇室典範という「実質的意味の憲法」に関しては、形式的には法律の改正あるいは制定にすぎないのに、ひょっとしたら憲法典に書いてあるよりも硬い基準が出てくるかもしれない、ということですよね。
清水 本書で待鳥先生が論じられていますが、90年代の選挙制度改革につながった法改正の際には、全会一致を目指すまでの前提はありませんでした。それでも、結果はともかく、できるだけ幅広い党派の合意形成を目指すべきだ、という「建前」はあったように記憶しています。いずれにせよ、今の皇室典範改正問題の慎重な取り扱いは際立っていると思います。
浅羽 考えたこともなかったですね。閾値が3分の2よりも高くなるという状況……。
清水 興味深い状況だと思いますね。
横大道 そう思います。
浅羽 ぜひ読者の方々には、このように、本書に提示されている枠組みをフルに使って、ほかにもアクチュアルな問題を考えていただけると嬉しいですね。
憲法学と政治学、アカデミズムとジャーナリズムの協働に向けて
浅羽 最後に、憲法学と政治学の共同研究や、アカデミズムとジャーナリズムの協働について展望してみたいと思います。「これまで必ずしも没交渉ではなかったけれども、ある種の断絶はあった」とか、「アカデミズムではごく当り前の知見がなかなかジャーナリズムに届きにくい」といったときに、そもそも本書はひとつの架橋の試みだったわけですが、架橋することが望ましいとすれば、今後どういったかたちがありうると、お二人はお考えでしょうか。
横大道 憲法というのはひとつの研究の「対象」であって、憲法学者の独占物では当然ありません。憲法というものに対して憲法学は、規範的な観点から分析をしているけれども、たとえば今回提示されたように、政治学は実証的に見ていく。あるいは社会学では日本人の憲法意識はどうなっているのかなどを見ていくこともあるでしょう。そのほかにも、経済学や財政学と憲法の関係とか、いろいろありうるわけです。
憲法というのは、その意味では、いろいろな学問に対して開かれています。まずは本書をきっかけに、そういう意識が広まればいいんじゃないかと思います。つまり、憲法の議論というのは必ずしも憲法学者だけがやる話じゃなくて、いろいろな学問分野からチャレンジできるような、そういう面白い研究対象だ、ということではないかと思います。憲法学者もこれまで政治学の成果をつまみ食いしたり、社会学の文献を参考にしたりと、いろいろとやってきましたけれども、はたして「法学」としての憲法学とは一体何なんだ、ということの自省を迫る、そういう契機にもなるのではないかと思います。
社会学という言葉が出ましたけれども、たとえばフランス人のシモン・サルブラン先生――今、慶應義塾大学で教鞭をとっておられます――が、「日本国憲法へのカリスマ的性質の付与に果たした憲法学者の役割」とか、そういう研究をなされています。他の国に較べると非常に特殊じゃないかと。これは、社会学的な分析としても非常に面白い話でして、そういう意味で、憲法をもっといろいろな角度から見ていくことで立体的に浮かび上がってくるものがあって、次の清水さんのお話につながるかもしれませんが、ジャーナリズムが提示するようなステレオタイプな憲法の扱われ方でないものを、アカデミズムの方からもやっていかなければならないな、と思いました。
浅羽 そもそも、少なくない政治学者は法学部出身で、「博士(法学)」ですからね(笑)。学際系学部に散らばっている私のような場合は別ですが、法学部所属だと、本来、もっとコラボしやすい環境のはずなんですが……。

清水 これも政治ジャーナリズムの自省が入るのですが、「護憲 vs 改憲」という非常に硬直的な議論の「土俵」があります。それが、昨年来の集団的自衛権論議を経てもう一度、新たなかたちでがっちりと構築されてしまったと。憲法典の改正をめぐっても、権力を持っている安倍自民党の側が、ろくに専門家の意見も聞かずに、あたかも現憲法を根底から否定するかのような全面改正草案を用意して、それで議論しよう、野党も対案を出せ、という姿勢できていたわけです。これに対してアカデミズムが身構えるのは、気持ちはわかる、という面もあるんです。
これはある憲法学者の印象的な言葉ですが、憲法改正の「土俵」そのものがすでに、権力によって歪められているじゃないかと。そのような「土俵」に乗って学会や研究室でやっているようなフラットな議論をしろと言われても、とてもできない。だから「土俵」に乗れないんだ、とおっしゃる。一義的には権力側に責任があるとは思いますが、「土俵」が歪んできた理由のひとつとして、権力の側の問題とは別に、護憲/改憲という不毛な二項対立を、助長してきた責任がマスメディアの側にもあることは否定できません。
本書の中でも最も印象的だったのは、田近先生がイタリアの状況を記述されている箇所です。イタリアで憲法改正がどう捉えられているか。《守るべきものは守る、しかし変えるべきところは変える。そういう柔軟性こそがその憲法体制を守る「憲法保障」につながる》。この考え方は新鮮でした。守るべきものは守って変えるべきものは変えるというのは中立的な命題で、一般社会では当たり前のことではないでしょうか。日本の憲法論議となるとなかなかそれが中庸とは見なされないところがある。
メディアの方も、護憲か改憲か、あなたはどっちなんですか、という二分法を憲法学者にも強引に当てはめてきたのではないか。そんな単純な話であるわけがない。「守るべきものは守るし、議論するべきものは議論する、さらに変えるべきものがあれば変える」といったしごく真っ当な議論を展開されている憲法学者の方々もたくさんおられる。相対的に若い年代の方からはもっと自由闊達に憲法論議がしたいという声なき声みたいなものも伝わってきます。今までそういう方たちにメディアは自由で幅広い多事争論の場を提供してきたのだろうかと。
第2次安倍政権になってから憲法学の取材を始めた私から見ますと、逆説的ですが、実はここに未開拓の沃野が広がっていて、取材者として大チャンスなのではないか、とも思うわけですね。ですから、個人的にはリアリズムとかバランス感覚といったキーワードはあるのですが、できる限り多事争論の「土俵」を提供するのが私の仕事かもしれないと思い、その方向でいくつかの紙面的な試みをさせていただいているという次第です。
横大道 清水さんが関わられた、本年6月9日、10日の日経新聞「経済教室」での企画「憲法改正を考える」に登場された、曽我部真裕先生(京都大学教授)、宍戸常寿先生(東京大学教授)の記事や、待鳥先生や片桐直人先生(大阪大学准教授)が登場された最近の「公布70年憲法を考える」(10月19日-21日)などは、そうした試みの一環ですね。非常に重要なお仕事として、興味深く拝読させていただきました。
浅羽 要は、既存の「土俵」に伸るか反るかではなく、議論の「地平」そのものを広げることで、憲法について自由に構想し、護るべきは護り、改めるべきは改めるということですね。憲法論議は政治家が説く道徳律でもなければ、「法律家共同体」の独占物でもなく、本来誰にでもオープンであるはずですので。
「憲法」や「憲法改正」の理解をイノベーションし、《実質的意味の憲法、あるいは基幹的政治制度が変わると、憲法体制が変化する》というふうに見たときに、戦後日本では憲法体制の変化があったのか、なかったのか。同時に、とはいえやはり「2分の1」ではなく「3分の2」の憲法「典」の改正というのは依然として重要な閾値なので、それをクリアすることでしか変えられないもの、変えてはいけないものとは、一体何なのか。本書が、「われら日本国民」をこえて、憲法を議論する地平や文法を見直すきっかけになれば、執筆者の一人として、編者や他の執筆者、それに実は一番の仕掛け人である登健太郎さん(弘文堂編集者)とともに喜びたいですね。
プロフィール

浅羽祐樹
新潟県立大学国際地域学部教授。北韓大学院大学校(韓国)招聘教授。早稲田大学韓国学研究所招聘研究員。専門は、比較政治学、韓国政治、国際関係論、日韓関係。1976年大阪府生まれ。立命館大学国際関係学部卒業。ソウル大学校社会科学大学政治学科博士課程修了。Ph. D(政治学)。九州大学韓国研究センター講師(研究機関研究員)、山口県立大学国際文化学部准教授などを経て現職。著書に、『戦後日韓関係史』(有斐閣、2017年、共著)、『だまされないための「韓国」』(講談社、2017年、共著)、『日韓政治制度比較』(慶應義塾大学出版会、2015年、共編著)、Japanese and Korean Politics: Alone and Apart from Each Other(Palgrave Macmillan, 2015, 共著)などがある。

横大道聡
1979年生まれ。青山学院大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士(法学、慶應義塾大学)。鹿児島大学教育学部准教授を経て、現在、慶應義塾大学法科大学院准教授。主著として、『憲法Ⅰ・Ⅱ』(共著、日本評論社・2016)、『現代国家における表現の自由』(弘文堂・2013)などがある。

清水真人
1964年生まれ。東京大学法学部卒業後、日本経済新聞社に入社。政治部、経済部、ジュネーブ支局長を経て、2004年より経済解説部編集委員。主著として、『官邸主導 小泉純一郎の革命』(日本経済新聞出版社・2005)、『財務省と政治 「最強官庁」の虚像と実像』(中央公論新社・2015)など。



