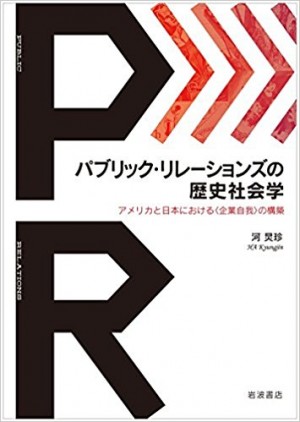2017.05.25

PRは悪なのか?――パブリック・リレーションズの歴史社会学
PR(パブリック・リレーションズ)、私たちが日常的に耳にするありふれた言葉だ。しかし、このPRこそが社会の形成に大きく影響を及ぼし、またその様相を鏡のように映し出す。『パブリック・リレーションズの歴史社会学――アメリカと日本における〈企業自我〉の構築』で、PRの基本構造を解き明かした河炅珍氏が、社会学者の開沼博氏とともに、PRという切り口から現代社会を解き明かす。(構成/服部美咲)
「HOW」の前に「WHAT」を考える
開沼 『パブリック・リレーションズの歴史社会学』は重厚でありながら、とても面白い本でした。河さんの長年の研究の対象であるPRというテーマですが、これは現代社会において、両義的な、興味深い存在だと思うんですね。
一方では、かつてのようにはモノが売れない、人も集まらない社会になっているなかで、例えば地方自治体が斬新な切り口でPRをおこなってインターネットで話題になるなど、最先端の明るい雰囲気を持っている。他方では、PRという概念には、企業や政府が秘密裏に意図を広めるような不純な、生臭いイメージもまとわりついている。ここを掘り起こしていくなかで、恐らく現代社会の根底に存在する、社会を動かす重要なメカニズムが見えてくるように思うんですね。
河さんは、なぜPRの研究をされているのでしょうか?
河 まず、個人的な理由から言えば、学部時代、私はPR・広告を学んでいました。卒業後は広告やPRの会社で働こうと思っていましたが、当時の私には「PRはそもそも何なのか」という問いに答えることができませんでした。そこで、まずはこの問いに答えてみたいと思い、研究の道に進みました。
本書の必要性をもう少し社会全体に広げてみると、近年、PRや広報、さらにCSR、ガバナンス、コンプライアンスなどの言葉が示すように、経済的主体・行政的主体の区分にかかわらず、ほぼ全ての組織にとってコミュニケーションはきわめて重要な問題になっています。でも、そのなかでも重要な位置を占めているはずのPRについて、「それはそもそも何なのか」という問いにはっきりと答えてくれる学術的な研究書はやはりありませんでした。
開沼 なるほど。PR自体は、社会に広く広がった概念だし、ビジネスのツールだし、研究の対象でもある。書店のビジネス書や経営学の棚には、すでにマーケティングやPRの本がたくさんありますね。でもそのなかには河さんが求める答えがなかったということですね。
河 そういえば新宿の紀伊国屋に行ってみたら、本書は経営学とマーケティングの隣の棚に並んでいました。おそらく「PR」とタイトルに入っているからだと思います。同じ棚には、PRのいわゆるハウツー本がズラリと並んでいました。もちろん、そのなかに、PRの理論的・歴史的な部分に触れている本が一冊もないわけではありません。でも、メインはあくまでも、「優れたPRが実践できる方法」を教えることが目的で、PRを「経営の実践に役立つ技術」として捉えている場合が多い。このような傾向は、アメリカのPR関連書籍に関しても言えることです。
これまでのPR研究は、その歴史から概念を抽出したり再構築したりすることよりも、むしろ、その手法における効果に焦点が置かれてきました。そのせいか、PRは、広告やプロパガンダと混同されてきました。手法だけなら、広告もプロパガンダもジャーナリズムも、とても近接していますから。
ただ、何かの概念を論じるとき、そもそも「WHAT」(これが何なのか)を理解せずに「HOW」(どのようにするか)を考えてもしかたがありません。従来の実践的・技術的な議論を超えたところで、「PRの概念とはそもそも何なのか」ということを、理論的・歴史的に議論してみたいと思いました。
開沼 言い換えると、PRについて、目的をもって何かを実現するために「どうするべきか」という方法として工学的・経営学的に研究する人はいたけど、そもそも「どうあるのか」という科学的・社会学的な研究が不足していたということですね。
河 そうです。研究者として、「人がまだやっていないことをやる」ということは重要ですね。それと同時に、研究を進めていくうちに、PRという現象やコミュニケーションの様式そのものが、現代社会の構造・メカニズムを理解するカギになることを確信するようにもなりました。企業や政府をはじめとするあらゆる組織は、なぜ必死にPRをするのか。なぜ彼らはPRを必要とするのか。
本書の見方でいえば、PRは、それを行う主体の〈自我=アイデンティティ〉に密接に関わるものです。すなわち、PRという概念は、現代社会の――厳密には、現代社会を構成するアクターたちの――非常に特徴的な問題を体現しています。ただし、そこにたどり着くためには、既存のPR研究や広告研究、プロパガンダ研究の視界を超えなければならないと思いました。また、それらを超えたときにもし新たに見えてくるものがあれば、それは「HOW」的な知識・技術にも役に立つのではないかと思っています。
経営学と社会学に橋をかける
開沼 にも関わらず、今回の本は、書店で書店員さんに、「役に立ちそうなPR」の本という棚に分類されてしまった。そうするしかなかったということなんでしょう。であれば、あえて聞きますが、実際のところ、この本は何かの役に立つのでしょうか?
河 本書の読者としては、まず、自分が携わる分野の専門知識を身につけようとしているPRの実務家たちが想定できます。彼らが顧客や同業者から「PRって何?」と訊かれたときに、狭い意味での「PRとは何か」だけでなく、その必要性や社会的な意味を、歴史的・理論的に語ることができるようになる。そういう意味で、本書は実用的な場面でも役立つと思います。
また、本書は、実務だけでなく、社会学の観点から現代社会を考えていく上でも役に立ちます。たとえば、本書は今までわりと分離されていた、しかし現代社会の顕著な特徴である、マネジメント研究(経営学)とマスコミ研究(社会学)という二つの領域を架橋します。
現代の資本主義社会を象徴する「企業」という組織体を中心に考えるマネジメント研究において、いままでPRは道具の一つとみなされてきました。一方で、マスコミ研究において、PRは商業的かつ企業から社会への一方向的なコミュニケーションとされ、周辺的なものとして扱われてきました。まったく別の系統で成立したこの二つの議論が、しかし、「PR」というフィルターをあてることで、緊密につながります。
本書で述べているように、現代社会において、企業などの組織は、〈自我=アイデンティティ〉を維持形成するためにPRを行います。そして読み進めると、マスコミ研究でいうところのオーディエンス、つまり〈他者=パブリック〉が、組織の〈自我=アイデンティティ〉とともに想像され、また創造されていく過程が浮かび上がってきます。
開沼 そこの接合をしているのが本書の大きな価値ということですね。今回の研究では、恐らくこれまでの経営学的、一般ビジネス書的な切り口として多用されてきた共時的な分析、つまり、PRの流行や成功事例の紹介ではなく、通時的に、PRが生まれたであろう19世紀のアメリカから、現代につながるPRの根本にあるメカニズムを見ようとしていますね。
まず、この「19世紀のアメリカがPRの起点である」ということ自体、PRの議論の初心者の私には「そうなんだ」といろんなことを考えさせられました。このことは、研究の初期から発見できていたのですか?
河 PRの原点をローマ帝国にまで遡って考える研究者もいますが、個人的には19世紀半ば以降の産業社会と大衆情報社会を背景にその成立を考えるのが自然だと思います。その一つの理由として、PRという概念やその技術的土台が、ジャーナリズムに根づいて出発していることが挙げられます。商業的で、かつニュースの生産・流布過程が制度化したジャーナリズムが成立する社会、すなわち情報社会がまず必要です。
このようなジャーナリズムの発達は、イギリスやドイツ、日本でも見受けられます。にもかかわらず、なぜアメリカなのか。19世紀半ば以降、アメリカでは、イギリスやドイツ、日本とは違う形で、社会全体をまとめる組織としての巨大企業が現れました。アメリカは移民社会であり、その爆発的な成長により、それらの巨大企業は自らの組織のなかに多様な人々を労働者・従業員として抱えるようになりました。PRは、このいわば内なる〈他者=パブリック〉である労働者・従業員を捉え、彼らを鏡として巨大組織の〈自我=アイデンティティ〉を生み出すところから出発しています。
このように、動機と目的を持つ組織が現れ、その動機と目的が実現する技術やメディアの状況が整えられたのが、19世紀末以降のアメリカ社会です。ここは研究を進めながら、ある程度歴史的状況を把握した上で、理論的な枠組みを設定したおかげで整理できた部分もあります。

トランプ現象の普遍性
開沼 まず、アメリカ社会の特徴がPRという非常に特異な社会現象を生んだという点が、とても面白いなと思いました。
イギリスのように、私的なものとして企業がある社会と、逆にドイツのように、法的なものとして企業や資本主義を発達させてきた社会とがあり、アメリカはその両者の間をとってやってきた。そこに、国民の多様さゆえに簡単にはまとめられない何かがあって、PRが生まれた。
現代の問題に引きつければ、トランプ政権誕生の背景を見てもわかるとおり、アメリカでは多様な国民をとりまとめる夢を見せるようなPRが効くし、ときにはそれが効きすぎてしまう。河さんの研究を見ると、あたかもトランプ現象が前代未聞の新しい現象のように語られているのが大嘘だと気付かされました。
PR研究者としては「普遍的な現象が起こっている」と、結構冷静に見ているのでは?
河 やっぱりそうだと思いますよ。トランプ現象は、政治学者が見るとありえないことなのかもしれないし、また世論調査の研究者からすると、いかに世論調査というものが当てにならないかということの証拠にもなりうる。もしくは、人がいかに自分の信じたいことだけを信じるのか、というような、否定されるべきであり、また否定しなくてはならない問題や現象も含んでいると思います。当然ながら民主主義の理念からも、トランプの今の言動には明らかに問題となる要素を含んでいることが指摘されます。
ですが一方で、この現象の基底にある、世論が形成されるプロセスに注目すれば、アメリカ社会で政府と市民の関わり方に対する基本的姿勢は、100年前にはすでに成立していたと言えると思います。それが徐々に洗練されていき、同時に調査技法も発達していく。本書の第4章で述べた、ニューディール政策を進めたルーズベルトのやり方を、現代ではトランプのそれと比較すれば、大統領と彼を支持する有権者との心理的な結びつけ方を歴史的に論じることもできます。
そう考えると、トランプ現象を、トランプという政治家の性質の良し悪しとは別の基準で、アメリカ社会の政治的コミュニケーションにおける特徴的な問題として捉えなおすことも可能だと思います。その上で、PRやジャーナリズムに対する大統領や政治家の関わり方についても改めて考えてみたいですね。
変遷する「忘れられた人々」
開沼 その4章がまた興味深い。書店で本書を手に取ったら、まず4章だけでも読むといいと思いますが、ここに「忘れられた人々」という言葉が出てきます。そもそもこの本はトランプ現象前に書かれているし、この言葉はトランプと直接関係ないところで出てきますよね。でも今、これがぴったり当てはまる。PRの本質を端的に表すキーワードだと思います。ニューディール政策がそうであったように、「忘れられた人々」の発見が進める社会の変化が、今起こっていることは間違いない。
河 ニューディールはきわめて成功した政治・経済的キャンペーンだと思います。アメリカだけじゃなく、第2次世界大戦後は、日本を含め、世界各国でニューディールは拡大再生産されてきました。もちろん、ルーズベルトはトランプに比べたらはるかに国民的尊敬をあつめ、愛され続けている大統領ですので、この二人を単純に比較するのは難しいでしょうけれど。
本書では「アメリカの大統領が、いったい『誰』に向かって語りかけるのか」を検討しています。ルーズベルトは「忘れられた人々」に向かって語りかけました。この「忘れられた人々」という言葉は、もともと中産階級の納税者を指していましたが、ルーズベルトは同じ言葉を使って、まったく違う階層である貧しい人々や農村地域の人々を捉え、彼らを自分が語りかけたい〈他者=パブリック〉として見出したのです。
そして、こう呼びかけました。「私こそがあなたたちを救うことができる」と。その上さらに、「私はあなたたちの友達なんだ」と言ったのです。支配者や権力者じゃなく、「友達」なんですね。この、有権者や支持者との間における「フレンドリーさ」は、アメリカ政治の特徴でもあります。ヒラリーが負けた原因の一つとして、彼女のエリート主義、大衆が近づきにくいという印象が弱点となったという指摘もありました。そういう意味でトランプは、皮肉にもアメリカ社会で歴史的にどういう戦略が成功してきたのかをよく理解していたとも言えますね。
PRは「悪」なのか?
開沼 そういうアメリカの社会像が見えるのも面白いですね。そしてこの本では、PRという言葉とあわせて、それに近い、広告やプロパガンダ、あるいはマーケティング、パブリシティといった、概念が整理されていきます。
そこで伺いたいと思ったのが、「PRって、不純で、社会正義の実現のためにあんまりない方がいい」という、今の社会でも少なからず共有されているだろう感覚についてです。つまり「これは実はPRなんだ、あいつはPRに加担しているんだ」って言われたら、例えば、この「PR」というところに「洗脳」とか「私利私欲の追求」とかを代入しても成立する文になるわけです。たしかにそういう側面もある。でも、本来のPRはそう単純な話でもないはずです。
この「PRは公共圏をゆがめるものである」という感覚は、以前から強くあるのかもしれないけれど、今はそれがますます強くなっているのではないか。welq問題やフェイクニュースもそうですが、実際に人の認知をゆがめるものが、いろんな意図で出てくる。それが政治的な意図ならプロパガンダになるし、経済的な意図なら広告になる。その総体として、「PR=悪」とされる現代社会の雰囲気がある。
でも、あらゆる経済行為も政治行為も、パブリックとリレーションシップを結ばなければ成立しないし、現にそのなかで経済活動、政治行動を私たちはしている。パブリックの側もまた、そのリレーションシップによって利益を得ている。でも、とにかく原理主義的に「PRは悪だ」という。
そこで何が起こるかといえば、既存のPRの手法らしくない手法を使うようになるわけです。最近のPR手法として、ステマ(ステルスマーケティング)という概念が社会問題になり、一般にも広く知られるようになりました。
この概念を使って言うならば、ひたすらステマ、それがダメならステマらしくないステマを開発して実践で使って目的達成を目指す、さらに、それもダメになるとステマらしくないステマらしくないステマの開発と実践で・・・という無限後退現象が起きている。こういうある種のPRの潔癖症のような状況に陥らざるを得ない。こういう現状の構図については、どう思われますか?
河 特にその傾向が顕著な例は「プロパガンダ」ですね。この言葉が負のイメージを持つようになったのはナチスドイツ以降です。今も、我々が日常生活で「プロパガンダ」と言うと、そこには強烈で、非倫理的行為を連想させるようなイメージが付随している。
このような傾向は、PRにおいてもある程度進んでいます。PRという言葉ももう古くなっていて、「政治家や企業経営者のためだけに役立つような活動ばかりではないか」という認識が既に形成されています。そのため、「コーポレート・コミュニケーション(CC)」をはじめ、新しい概念や言葉がどんどん作られる。
実態は同じことをしながら、それを指す言葉だけを変えていく。日本だけではなく、世界全体でそういう風潮があります。業界の人からすれば、クライアントを説得しなければなりませんから仕方がないのかもしれませんが、それではかえって問題となる概念をきちんと捉える道を閉ざしてしまうことになります。
研究者としては、一方では新しい言葉の流行に注目しながらも、他方では「それが代替しようとする現象が、そもそもなぜ『PR』と呼ばれてきたか」を問うていく必要があります。
それは、一部の研究者がいうような「PRは、組織と社会との間に双方向的・対称的関係を構築するものであるべきだ」という主張を鵜呑みにすることとは異なります。そういった「PRのあるべき姿」を論じることもときには重要かも知れませんが、個人的には「企業などの巨大組織が社会に向けて行うコミュニケーションが、なぜPRという言葉・概念で呼ばれてきたのか」を究明することに重点を置いています。
PR活動の結果として社会に害が与えられたり、あるいはPRコミュニケーションをなしていた情報が嘘であったりした場合には、その実態は厳しく批判される必要があります。しかし、かといって「PR」という言葉・概念そのものを否定し、死語にしてしまうと、つまり、「悪いからこの言葉は使わないようにしよう」ということになると、我々が直視し、分析しなければならない現象も言葉と共にどこかに消えてしまう。
PRは企業自我形成のためのコミュニケーション
開沼 そういうことですね。研究をする上では、起こっている現象について、「良い・悪い」というのは言えなくても、「どうあるべきなのか」というところまでは言えると思います。これまでの歴史的な経緯から、どういうPRが良いのでしょう。あるいは、それは公共圏をゆがめないところで成立するものなのかもしれない。どうでしょうか。
河 やや抽象的な議論になるかもしれませんが、「PRによって公共圏をゆがめられる」という問題に関しては、ハーバーマスやチョムスキーなど、厳しく批判する論者がたくさんいます。彼らは、哲学的、倫理的に重要な議論を形成していると思います。
本書では、そういった議論に真っ向から対抗するつもりも、また企業や政府のやり方を擁護するつもりもありません。むしろ、同じ現象を捉える上で異なる視点を提供することで、「市民社会がPRにいかに対応していくべきか」ということの方向性を示したいと思っています。本書の主な意義は、PRを、「企業や政府が〈自我=アイデンティティ〉を形成するためのコミュニケーション様式」として捉え直したところにあります。
批判的な論者にとって、PR活動が広範囲にわたり、その頻度やパワーがどんどん加速している状況は、公共圏をゆがめて市民社会の自然なコミュニケーションに害を為しているように見えると思います。しかし一方で、そういった状況を「PRはなぜ行われるのか」「組織は何を求めてPRをするのか」という側面から考えてみれば、PRが氾濫している社会では、組織のアイデンティティの形成や維持が厳しくなっている状況だということがわかります。
企業や政府が、なぜPRをやらざるを得ないのか。それは、組織が属している社会、そしてその社会を構成する〈他者=パブリック〉と深くかかわってきます。PRが盛んな社会とは、PRをしている政府や企業の社会的な〈自我=アイデンティティ〉の形成や修正をめぐって〈他者=パブリック〉からの圧力が増加している状況であるとも読み取ることができるのです。
公共圏に害を与えないために「PRはこうあるべき」というような、理想と理念に基づく議論も重要でしょう。ですが一方で、「PRの主体と〈他者=パブリック〉との関係性のなかで、主体の〈自我=アイデンティティ〉が形成される」という構造を理解すれば、そのメカニズムに沿って、「市民社会側がPRの担い手たちに対してどのような対応ができるのか」ということは、自ずから見えてくるのではないでしょうか。
本書で提示したかったのは、まさにこのような方向性と視点の転換です。単に「企業や政府のPRがいかに優れていたか」や、「ルーズベルトのニューディール政策がいかに成功したか」ということだけが語られているわけではありません。
戦後日本の姿をつくったPR
開沼 「政治にマーケティングを導入しよう」という議論を、大学入学前後の2000年代前半に、日本で目にするようになりました。その一方でインターネットの発達があった。それまでのように、自民党は農協のような地域の業界団体を押さえて、社会党は組合を押さえて、というような政治のやり方ではうまくいかなくなった。そこでまさに、「他者」を再設定しなければならなくなって、政治的なPRが主題になった、そういう現象だったんだな、ということを、この本を読みながら思い返していました。
共産党の「カクサン部」はじめ、今や右から左まで政治が皆PRをしているけれど、実は日本にPRが入ってきたのは戦後すぐなんだ、という系譜は、改めて面白かったです。日本に入ってきたPRが、戦後日本の姿かたちをかなり作ったんじゃないか、ということですよね。
河 そうですね。とくに、本書の後半で戦後日本の事例を扱ったのは、PRを通じてアメリカナイゼーションという問題を論じてみたかったからです。その意味でも、開沼さんの「日本に入ってきたPRが、戦後日本の姿かたちをかなり作ったんじゃないか」という指摘は的を射ています。
戦後の経済組織について言えば、経営者にとって労働者・従業員の意味合いが変わってしまった結果、アメリカ企業の労使管理に学んだ新しいPR=ヒューマン・リレーションズが導入されました。証券会社は、証券民主化に伴って株主や経営者に対するPR運動を実施し、電通などのマスコミ業界は、顧客をめぐる状況の変化に伴って事業体制をつくり、自ら進んでPRに取り組むようになりました。そしてこれらのそもそもの始まりには、「占領軍によって民主的コミュニケーション・モデルとしてPRを命じられた」という行政機関の事情もありました。
経済や行政の両面において、戦後日本のPRは、さまざまな動機と目的によって移植されたり導入されたりした。それが、朝鮮戦争が勃発し、占領政策そのものの性格が変わりはじめると、占領期に形成された戦後日本の経済的、政治的主体とその相手としての「パブリック=公衆」をめぐる関係性も再び変わっていきます。このような関係性の修正は、占領期から高度成長期へ、さらに1970年代以降も続いて何度も修正され、その都度、PRの特徴も変容していきます。
占領期にはそれまで〈他者=パブリック〉として認識されていなかった労働者、女性や子供、在日韓国・朝鮮人、革命家たちが、一時的に政府や企業と信頼しあう関係を構築すべき相手として設定されました。ところが、高度成長期になると、それらの相手は一斉に「お客様」になってしまい、高度成長に欠かせない存在だけが〈他者=パブリック〉として認識され、その層だけがどんどん膨らんでいきます。
詳しくは本書の6章と7章で論じていますが、〈他者=パブリック〉の再設定に伴い、PRを行う主体の自我も再定義されました。東京電力のような日本の企業は、〈他者=パブリック〉と信頼関係を構築するようなPR活動を掲げ、「他者の助力者」としての〈自我=アイデンティティ〉を構築しようとしましたが、それはあくまでも表象のレベルに留まり、1950年代半ばまでに試みられたような、「PRを通じて戦後日本社会を再形成する」という動きにはなっていなかったんです。結果的に1960年代半ば以降、PRは消費社会論に吸収され、マーケティング・プロモーションと見分けがつかなくなっていきます。
一度は消費社会論に吸収されていったPRが、ふたたび現れてくるのは、1970年代の反公害運動のときだと思います。公害という深刻な社会問題によって企業は、それまで「お客様」という自らにとって有意味な〈他者=パブリック〉だけを取り込んでいた関係を見直し、〈自我=アイデンティティ〉を修正した上で、新たなPR活動を行わざるを得なくなりました。
つまり、公害によって被害を受けた地域住民のような〈他者=パブリック〉が、日本企業のアイデンティティが形成・再形成される上で入ってくるわけです。企業のアイデンティティは、表象面でも大きく変わりました。「土下座して謝る経営者」とか「環境にやさしい企業」などのイメージですね。
そして20世紀末から21世紀にかけても、企業の〈自我=アイデンティティ〉に、またそれと連動して政府の〈自我=アイデンティティ〉にも何度かの修正があったはずです。開沼さんがおっしゃった2000年代の「マーケティングを政治に」という現象も、一方ではアメリカという強力な鏡に照らされながら、他方では変容する他者を通じて〈自我=アイデンティティ〉や関係性そのもののあり方を周期的に修正してきたという、戦後から続く歴史のなかに位置づけられるように思います。
想像され、創造される〈他者=パブリック〉
開沼 今のお話は、本の内容を前提にしつつ、その範囲も超える興味深い議論ですね。より現代に近づいてきました。
建築・土木分野だと、PI(パブリック・インボルブメント)という概念があって、それは今のお話と非常にリンクします。
1960年~70年代以降、まだ田中角栄的な土木関係の需要が社会を強く動かす力を持っていました。お金や夢をばらまいて、どんな田舎でも「ここが東京みたいになるぞ」と旗を降って人を動員し、社会的合意形成をとりながらやってこられた。
もちろん、成田空港の強制収用のような大きな問題も起こり、それが一つのトラウマになってはいるものの、多くの場合はそれで押し通せた。しかし、やがてそれではうまくいかない社会になった。ばらまくお金もないし、まして強制収用なんてやったらとんでもないことになるぞ、ということも学んだ。
そこで、1980年~90年代、そして現代に至るまでには、「公衆をいかに巻き込んでいくか」という議論がでてきた。PI、つまり、パブリックを巻き込むように、住民アンケートをとったり、ワークショップを丁寧に開いて、開発する側と住民とが未来図を一緒に策定したり。大きな方針の転換があったことをこのPIという概念は示しています。
しかしながら、一方で、3.11後の様々な問題や豊洲移転問題などを見てくれば、PI的なものは、あくまで社会の一部で成功したかもしれないし、大部分ではまだまだ成功事例が足りないものに過ぎないのかもしれないこともわかる。3.11後の被災地でもやたら「ワークショップだ」「ファシリテーションだ」ということが流行ってきましたが、それだけでうまくいったもの、具体的な成果に結びついたものばかりではない。
現代社会は、パブリックと関係を結びたい側がパブリックと関係を結ぶにはこれだ、というものがなかなか見えない時代なのではないかなと思います。
河 その問題を論じるために、まずはPR、つまり「パブリック・リレーションズ」を語るときにしばしば出てくる「パブリック」という概念が、日常的に我々が想定しているパブリック概念とは必ずしも一致しないということを指摘しておきたいです。
PRの主体にとっての「パブリック」とは、〈自我=アイデンティティ〉の形成・再形成に必要な存在としてイメージされるものです。本書では、PRでいう「パブリック」(=他者)が、PRの主体の〈自我=アイデンティティ〉形成のために、社会において識別・分離され、その〈自我=アイデンティティ〉を投影する鏡としてイメージ(想像)され、ときにクリエイト(創造)される過程を分析しました。
アメリカの歴史や、戦後日本の歴史を見ていく上で、この想像され、創造される〈パブリック=他者〉の範疇がどのように変容してきたのかということが重要だと思っています。例えば、1970年代の反公害運動で、多くの企業にとってPRの対象となる〈他者=パブリック〉は、一時的に「お客様」から「公害の被害を受けた地域住民」に移ったはずです。
でも、そうやって対象が変遷していけば、いずれは〈他者=パブリック〉の範囲が満遍なく広がるかというと、そうではないことも歴史から見えてきます。
今PR活動を行う上で重要な戦略的プロセスは、セグメンテーションです。PRを行う組織にとって、彼らが向きあうべき〈パブリック=他者〉が誰なのかということをまず明確にし、そして細分化し、かつ優先順位をつけることが、今やマーケティングをはじめ、企業のコミュニケーションにおいて基礎的な作業になっています。PRを行う主体にとって、どの〈他者=パブリック〉に自身を投影すれば、社会とより望ましい関係性を構築できるのかということは、重要な問題となっています。
開沼 本書のなかで重要な事例として、戦後から経済成長期に向かう東電のPRについて分析をしていらっしゃいますね。現在の東電はきわめて保守的な企業文化のなかで、ある種、時代遅れと言ってもよいような大きな枠組みのなかから大きく外れることなく、時には「なんでまたそんな逆効果な方法・態度をとるんだろう」と首を傾げるようなPRをいまだに続けています。
一方、小池都知事は小池都知事で、「ここに突っ込めば勝てる」という対象を上手に選び、「リスクはゼロではない」と言い続ければ勝てるゲームに持ち込むという野性的な直感がすごいといえばすごい。でも、ああいうPRで持続的ないい形が作れるとは思えない。
河 現状はかなり深刻ですが、これまでのPRによって持続的な形が作れていない状況が、批判と修正を経て改善される可能性は残っているように思います。ここでもやはり、PRというコミュニケーション様式をめぐる企業と社会、〈他者=パブリック〉との関係がポイントになります。
ある組織が過去に行ってきたPRは、一見そう見えても決して一方的なものではなく、社会からのなんらかの影響を受けてきました。そして今後行われるPRもまた、社会にどんな問題が伏在しているかということに影響されます。またそれによって、PRを行う組織と〈他者=パブリック〉との関係性も調整されることでしょう。このようなやりとりが、組織の〈自我=アイデンティティ〉の形成と修正を経ながら、PRというコミュニケーションのあり方を決めてきたことを歴史が示唆しています。
タコツボ化する公共圏
開沼 なるほど。企業や政府が、それぞれの時代の「忘れられた人々」のような〈パブリック=他者〉に光を当てることで社会を活性化してきたという見方は、本書でも重要な議論の枠組みですね。
しかし一方で、現代社会においては、公共圏そのものが非常に多極化していますね。近年、社会学では、その多極化した公共圏のなかで排除された人々が声をあげる手段として、デモとかパブリックコメント、国民投票などの方法が注目されました。今はそれが一周して、その声が望む通りには現実は変わらない、というかむしろ意図せざる結果に結実してすらいるような現実も見えてきている。
1970年代のように、現代と比較すれば公共圏が一極にまとまっていた時代には、例えば公害が起これば、社会が一つの方向を向いて戦うということにもなった。でも今はそうではなくて、公共圏が小さく分かれて、いわばタコツボ的になっている。そして、「私はPRの対象としての『他者』とは認められていない」という感覚が社会に充満している。
小池都知事やトランプみたいに、そのなかで偶然まとまっていたところを狙ってうまくいった、という場合もあるかもしれない。でも、そういう場合でもやっぱり、報われない不満や不安を抱えた人はずっと社会に残り続けるわけです。現代社会のこういう状況は、今までの歴史的なPRの枠組みでは解けない問題なのかもしれない。
河 その通りですね。20世紀と21世紀では、PRの行い方においてもかなり違う枠組みが示されています。アメリカでも日本でも、1980年~90年代までのPRは、どちらかというと組織の、単一で強い〈自我=アイデンティティ〉を形成する方向に焦点が絞られ、今はそれとは少し違う現象が起こっているように見えます。
昔のGMとかフォード、日本の東電などの巨大組織は、確固たる存在として社会のなかで自己を可視化させていて、その分、自らが想像=創造した〈パブリック=他者〉と強力に結びついてきました。しかし今は、組織は、ある〈パブリック=他者〉と常に緊密につながっているというより、多くの場合は可視化されない、細分化された〈パブリック=他者〉と、ケースバイケースで結びついている。訴訟とか、何か問題が起これば、組織はその瞬間だけある〈パブリック=他者〉と結びつく。しかしその後、そのまま強力な関係性が維持されるかというと、そうでもないのです。
本書の土台となった博士論文のタイトルは、「PRの20世紀史」でした。つまり、本書を書きながらすでに、「21世紀のPR史」を、また別の角度から理解する必要性を感じていたのです。もちろんその場合でも、本書で示した枠組みは有効です。
21世紀のPRを考えるためには、いま現在、アメリカや日本社会に起きている変化を見なければならない。PRというシンボリックなコミュニケーションの観点からいえば、企業や政府やその他の組織が、昔のような確固とした〈自我=アイデンティティ〉ではなく、もっと柔軟で、瞬間的な〈自我=アイデンティティ〉を求めているように見えるのはなぜか、という問いに答える必要がありますね。
開沼 今は、その状況を指す概念をそれぞれが探している段階かもしれませんね。
河 そうですね。インターネットが発達して、あらゆる社会運動が、かつてよりずっと活発に起こるようになりました。「社会運動が起こる」という状況は、20世紀PRの枠組みでいえば、何らかの問題的状況が活性化されていることを意味するので、PRする主体である企業や政府は、即時に体制や自らの組織の見せ方や見え方などを変える必要性を感じるはずです。
なのに、今、企業や政府の自己修正に対する言説は拡大しているにもかかわらず、実態としては、社会やメディアの変化に比べるとあまり変わっていないのかもしれません。社会運動は社会運動、組織は組織、という感じで、お互いが通じ合う瞬間は具体的な利害問題に限定されてしまう。
感情的であることを求められるPR
開沼 これらの状況のなかで今、「論理ではなく感情に訴えかける社会の風潮」があるのではないか、ということが、「ポピュリズム」「反知性主義」「Post Truth」など、手を変え品を変え次々に新たな概念で指摘されています。
そんななか、そもそもPRは論理ではなく感情、イメージや雰囲気を作る側面もありました。にも関わらず、この「感情に訴えかける」という風潮に、PRが追いついていないように見えるのはなぜでしょう?
河 PRの一部分を構成しているものとして、確かに感情に訴えかけるところもあるかもしれません。PRでは、他者と組織との関係性を、ビジュアルだったり、キャッチフレーズだったりを使って感情的に示すこともできる一方で、高度に論理的な議論をしながら提示することもできる。つまり、「PRというコミュニケーションそのものが、ロジカル(論理的)なのかエモーショナル(感情的)なのか」という問題ではなく、それを支えている関係性の問題なのです。
ではなぜ、PRは感情的なものに見えるのか。もしかしたら、PRとメディアの結びつきに原因があるのかもしれません。当然ながら、PRはメディアを介しますので、メディアの性質や社会的機能によって影響される部分があります。21世紀のメディア技術の変容とともに、今、社会から求められるPRが、より感情的なものへ変化している可能性がありますね。
「東電と福島」をめぐる二層構造
開沼 例えば現状を見ると、東電をはじめとする電力業界は、3.11後、本来の意味でのPR、つまり「パブリックとリレーションシップをもつこと」自体が社会的に許されない存在になっていますね。広告を出したくてもメディア内での考査が通らない。記者会見を頻繁にやってはいるけれど、専門的過ぎて社会全体には伝わらない。
メディア側もアジェンダセッティングが固定化して、「失敗しました」か「申し訳ありません」の2つを言わせたいし、それ以外の言葉を語りだしても、最終的にはつねにそこに持っていく。そしてそれに公衆が飽きる。結果的に全員が、儀礼的で表面的、かつ形式化したパブリックリレーションシップになっていないリレーションシップを続けるという構造になっています。
河 謝る以外の関係性が許されなくなった状態は、PRの失敗でもあります。そもそもPRは、それを行う主体が社会的に必要とされ、存在し続けるための〈自我=アイデンティティ〉と、それを成立させる上で重要な鏡となる〈他者=パブリック〉との間に関係を築くための活動ですから、そこで謝ることしかできないというのは、このような循環がもはや作動しない状況だということを意味しています。
これは、PRというコミュニケーションの失敗なのか、それとも東京電力という企業全体の経営・マネジメントの失敗なのか。おそらく両方の失敗かもしれません。
開沼 マスメディアはもはや、PRのツールとなりえなくなっている部分も拡大しているのでしょう。先に例をあげた東電のことで言えば、東電福島復興本社の石崎代表はマスメディアを通さない、SNSを使ったいわば1対1的な公衆とのコミュニケーションを実践している。そこでは、福島県民を中心に、毎回投稿に数百の「いいね」がつくような関係性が始まっていたりする。
社内では、始める際に「そんなイレギュラーなことはするな」という反発があったとも聞きます。このように、1対1の関係では、必ずしも東電の社員と福島県民がいがみ合っているというわけでもない。でもマスメディア上では、福島県民と東電は憎しみ合い、対抗しあって関係性が壊れている構図が「ロングラン公演」されているので、そういう側面しか見えていない人もいるでしょう。
東電と地域との交流については、地元メディアや共同通信など、一部でしか報道されてこなかった。結果として、マスメディアでは「福島県民と東電の関係性が壊れている」ことになっていて、その固定化したアジェンダセッティングが再生産されつづけ、一方インターネット上では、まったくなんの利権があるわけでもない福島県民が「今日もお疲れ様です。廃炉の情報発信ありがとうございます」と東電幹部と声をかけ合う。両者を観ている側からしてみれば、あたかもパラレルワールドがあるかのような、いわば二重構造、オルタナティブな関係性が生まれています。
この事例を見ても、河さんのご研究の先に何があるのか、色々な可能性があるように思わされます。

河 その二重構造は、いくつかの解釈ができると思います。まず、本書の第6章と7章でも分析したように、それまでの東京電力のPRがきわめて成功していたために、地域住民との間で強い関係性が築かれていて、それが今回の事態の収拾とともに復活してきているのか、という見方。もう一つは、今話題に出ているインターネット、SNSの影響であるという見方。
インターネット上では「1対1」になることができます。あるいは、実際には「1対多数」であっても、「1対1」という関係性を感じとることはできます。この、マスメディアよりはるかに高い親密度によって、インターネットは東電のPRの新しい次元を切り開いているのかもしれません。
マスメディアではいかなる関係性も許されないようなケースでも、SNS上では、組織と他者、社会の関係性は、従来のやり方とは全く異なる形から理解されなければならない。これは21世紀の、新しいPRについて考える上で欠かせない問題になりますね。
そういえば、最近SNS上で、企業がまるで生きた人間のように振舞っていますね。本書で私は「企業自我」という言葉を使いながら、企業をはじめとする巨大組織がいかにして「ひとりの社会構成員」になっていこうとしてきたかということを追跡しました。
そして今まさに、企業が比喩ではなく「ひとりの社会構成員」として存在することが、技術的にも可能となりました。これまでマスメディアを使って長年目指してきたことが、バーチャル空間で急速に現実味を帯びてきたのです。2000年以降、PR市場が爆発的に大きくなっているのも、インターネット、SNSの影響が大きいと聞きます。
社会は共通した問題を求めるのか?
開沼 かつてPRの原動力となった、戦争も貧しさも公害も、まだ残ってはいるものの、いずれも現代日本社会において大きな共通課題としての役割を持たなくなってきた。そういう現状において、今何が必要なのでしょうか。PRの原動力となるような問題って、1980年代以降はどうなってきているのでしょう。
河 その問題を特定できないまま、あてずっぽうでやっているから、今、皆うまくいかないんじゃないでしょうか。1970年代までは、社会にはずっと目に見える何かしらの問題があり、その問題に対応する形で企業や政府のPRがありました。
しかし、1980年代~90年代以降、社会問題がポカンと見えなくなり、あるいは問題の質が変わって、それと同時に、組織の対概念となる他者も見えなくなってしまったのではないかと思います。その結果、組織とその他者とのつながりが弱化した。こういう仮説が立てられます。
あるいは、市場や経済の変化により組織があえて他者との関係性を薄く保ち、先ほどいったようなケースバイケースの、条件付きの関係性を選ぶようになったのかもしれません。この辺はもう少し調べてみないと、どちらなのかはわかりませんが。
開沼 復興関係のことでいえば、被災地で俊敏かつ持続的に動いてきた企業は明確でした。ビール会社やタバコ、人材派遣に関連する企業、と、被災地で重要な貢献をしている姿を見ているので言うことを躊躇しつつ言うと、何か事件・事故などのきっかけがあれば、批判の対象になりかねない事業とつながっている企業です。
「いつパブリックから批判を受けるかわからない」という緊張感に晒されながら、長い時間をかけて事業を展開してきた企業、換言すると、いわばつねにPRに関する危機管理体制ができているような企業ですね。それらが3.11後に大きな活躍をして目立っている。ある意味では、彼らを活性化したのは、震災というわかりやすい問題の存在かもしれませんが。
河 1970年代までの日本では、PRする主体にとって問題がある社会状況は、共通の問題意識としてありました。戦争、経済成長、公害などですね。1980年代以降は、社会にこういった問題自体がなくなったのではなく、皆に「共通した」社会問題としての感覚が薄くなっている。震災は大きな社会問題ではあるけれど、いま現在もあらゆる企業が同じ深刻さで認識しているかというと、そうでもないと思います。
震災を大きな社会問題であると認識した企業は、素早く対応して、被災地域との関係性を着実に築く。でも同時に、そういう対応をあまりしない企業も存在する。2011年以降、震災は社会全体に共通の社会問題になりつつあるとは思いながらも、果たしてそれが21世紀社会の枠組みを変えるほどにまで広がっているのか。個人的には広がるべきだとは思うんですが…。
開沼 そこで、なんなら「問題をでっちあげる」という方向にいきますよね。
河 そうなんです。それが、今特に政治にわかりやすく出ていますね。
開沼 問題をでっちあげる、というのは、歴史的にもあったんですか?
河 「真実」と「真実らしさ」の問題ですね。もちろん、ありました。PRだけじゃなくて、メディアやマス・コミュニケーションの歴史のなかで、操作的な現実はよくある話です。ただ、これまでよりもはるかに深くメディアに依存している現代において、全面的に問題をでっちあげる、ということがあったら、我々はどう対応したらいいのでしょう。それは歴史の事例を超える大きな課題ですね。
開沼 共通の問題がないから、共通の問題をでっちあげることで社会を作ろうとしている。だったらもう社会は作らない、という方向にいくのか。つまり、「皆がつながっている感」をもう求めないのか。もしくは、でっちあげるならでっちあげるで、「メキシコに壁を作る」なんていうのよりは、もう少しマシな問題をでっちあげるとか。ある程度過激でないと共通の社会問題にならないなら、そこもきちんと考えて。
河 アメリカ社会の場合は、移民社会ですし、もともと異なる利害関係が当然に混在していて、それぞれの利害集団のせめぎあいによって社会がなんとなく動いてきたというところがあります。逆に日本社会は、近代国家を建設する上で社会構成員の皆に共通した問題意識があり、それによって社会が支えられてきた。
にもかかわらず、日本で今、その共通感覚こそが問題になっている。これは、潜在意識にあったはずの共通感覚が、もう潜在意識ではなくなってきているということですね。これまで、日本社会に共通の問題意識があったのは、さまざまな外的要因はあったにせよ、根本的にそれらを人々が共通感覚で受け止めていたからかもしれない。その個人と社会をつなぐ心理的な回線が変わってきたのかもしれません。
21世紀のPR史の仮説へ
開沼 もともとは、「社会に問題があって、政府や企業があって、そこから新しいものに昇華しましょう」というものだったはずなのに、今や社会と企業・政府とが、ある種の共依存関係になっています。問題解決を訴える社会と、それを聞く企業・政府という図式。そして、実際には問題は解決されず、されないがゆえに続く関係性が心地良い、という。誤解を恐れず言うならば、問題が問題であり続けてくれた方が、自己のアイデンティティを維持できるという構図こそ社会を動かす原動力になる。
河 面白いですね。問題が解決されないがゆえに続く関係性が心地よい。それが日本的なPRの特徴なのか、あるいは21世紀的PRの特徴なのか。
20世紀のPRは、どちらかといえば基本的な形をとっていました。20世紀初頭は、まだ巨大な企業の〈自我=アイデンティティ〉が固まっていなくて、そこを確固たるものにするためにPRが必要とされ、PRはすなわち巨大組織のアイデンティティを構築するコミュニケーションでした。組織の存続に影響を及ぼす社会の状況を、共通の問題として捉え、その問題を再定義しながら自らのアイデンティティを形成した。そして組織と他者が共存する社会のビジョンを掲げ、そのための他者を想像=創造していた、と。
これはきわめて単純な話ですね。本書でも援用したG・H・ミード(社会心理学者)の社会的自我論によると、人間の成長でいうところの成長期の子供でしょうか。だが、今の開沼さんのお話だと、むしろ今の状況は、成人の複雑な心理に似ています。「問題を解決する」と口では言いながら、実は解決されないままの方が目指す自我を構築できる、という。
開沼 まさにこの本の「人間の成長にたとえる」という部分の趣旨でいえば、今の考え方はスマートなのでは?
河 本書では「企業自我」の構築を説明する上で、ミードの議論を借りています。ミードは組織の社会的自我の形成を、子供の発達過程にたとえています。それに沿っていえば、20世紀の企業や政府は、子供が自我を形成するのと同じように、巨大な組織の〈自我=アイデンティティ〉の形成を目指していました。しかし、21世紀の企業や政府は、単に自我を形成するのとは別のものを目指しているようですね。〈他者=パブリック〉の再設定の方法も含めて、別のもの。
編集部 昨今、PRされる「他者」の側が、「忘れられた人々」にならないために、自分が属する社会問題を過大にPRしているような印象を受けます。
河 他者の「他者化」は、「自己PR」流の言説とも重なるところがありそうです。とにかく、「これは社会共通の問題だ」という意識が薄くなり、企業や政府のようなPRの主体が、昔のように確固たる〈自我=アイデンティティ〉に重点を置かなくなっています。そのため、〈他者=パブリック〉は組織や社会そのものとのつながりを保つために、互いに競争をしなければならなくなりました。他の対象に比べて自分の方がより多くの問題を抱えているように訴える(PRする)ことで差別化するという。
アメリカのような移民社会においては、とくにそういう現象はよく見られます。2つのマイノリティ・グループが、実質的にはほぼ同じ状況にあったとしても、補助金や支援を受けるために、自分のグループの問題がより大きいようなアピールをしていかなければならないという状況ですね。
この対談で、もう21世紀社会のPRについての仮説ができあがったような気がします。20世紀までは、社会を構成する巨大組織の〈自我=アイデンティティ〉の構築に重点がおかれていたとすると、21世紀は、その〈自我=アイデンティティ〉が必要とされるような、問題のある社会状況の生産と管理、維持に重点がおかれるようになった、ということです。
このため、PRの重点も、かつては目に見える確固たる〈自我=アイデンティティ〉の形成だったのが、〈自我=アイデンティティ〉はもはやどうでもよくなってしまい、むしろ〈自我=アイデンティティ〉の基盤となっている社会問題の方に移行していくという現象が起こっているのかもしれません。
この変化は、PRを行うあらゆる組織と、その対象となる社会構成員全てに広がっている。これは自分の研究にとって新しい観点となります。ありがとうございました。
開沼 とても興味深いですね。ありがとうございました。
プロフィール

河炅珍
1982年、韓国生まれ。韓国梨花女子大学卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。現在、東京大学大学院情報学環助教。専門は、社会学、メディア・コミュニケーション研究。主な論文に、「パブリック・リレーションズの条件――20世紀初頭のアメリカ社会を通じて」『思想』1070号(2013年)、「『公報』、あるPR(パブリック・リレーションズ)の類型――1960年代、韓国における政府コミュニケーションをめぐって」『マス・コミュニケーション研究』79号(2011年)など。

開沼博
1984年福島県いわき市生。立命館大学衣笠総合研究機構特別招聘准教授、東日本国際大学客員教授。東京大学文学部卒。同大学院学際情報学府博士課程在籍。専攻は社会学。著書に『はじめての福島学』(イースト・プレス)、『漂白される社会』(ダイヤモンド社)、『フクシマの正義 』(幻冬舎)、『「フクシマ」論』(青土社)など。共著に『地方の論理』(青土社)、『「原発避難」論』(明石書店)など。早稲田大学非常勤講師、読売新聞読書委員、復興庁東日本大震災生活復興プロジェクト委員、福島原発事故独立検証委員会(民間事故調)ワーキンググループメンバーなどを歴任。現在、福島大学客員研究員、Yahoo!基金評議委員、楢葉町放射線健康管理委員会副委員長、経済産業省資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会原子力小委員会委員などを務める。受賞歴に第65回毎日出版文化賞人文・社会部門、第32回エネルギーフォーラム賞特別賞、第36回同優秀賞、第6回地域社会学会賞選考委員会特別賞など。