2012.09.24

障害者介護保障運動から見た『ケアの社会学』 ―― 上野千鶴子さんの本について
『ケアの社会学』の評判と違和感
上野さんはフェミニストとして、もっとも有名な人だろう。著作を出すごとに論壇、文壇をにぎわしているし、テレビにもしばしば出演する。あまり学問とか研究に関心ない人でも、上野千鶴子という名前を聞いたことのある人は多いだろう。
その上野さんが、ここ10年余りの研究の成果として、『ケアの社会学』(太田出版、2011年)という大著を出された。
大きめサイズで約500ページの大著だから、普通の人はひいちゃうんじゃないかと思うけど、ぼくの知ってる介護関係の人々の間でも、この本は話題になっているようだ。残念ながら(?)読んだという人はあまり聞かないけど、読んでみたい、という人はけっこういるようだ。
論壇における評価は、かなり高い。中島岳志さんなどによって新聞各紙の書評でとりあげられているし、本田由紀さんなんかは、「震災後の日本の指針提示」の一冊として、この本を取り上げ、「フェミニズムと介護の問題に長く取り組んできた著者の集大成ともいうべき本書は、高齢化の進む日本にとって繰り返し参照される原点となるだろう」と述べている。
また、ケアに関心のある研究者たちもこぞってこの本を読んでいるようだ。知り合いの院生たちが、『ケアの社会学』の読書会を丁寧に各章ごとに開いている、なんて話も聞く。東京大学、ケアに関心のある研究者たちの集う研究会では、「新著『ケアの社会学』を手がかりに上野千鶴子とケアの社会科学をきわめる」という立派なタイトルのイベントも行われていた。「きわめる」はいいすぎだろう、と思った。
そして上野さん自身も、もはやアイドル的なひっぱりだこ状態。ある講演会では、フロントに上野さんへのお手紙ボックスがもうけられていたそうである。
ぼく自身といえば、上野さんのフェミニズム関係のものはほとんど読んでいなかったのだけど、『at』(太田出版)という雑誌に上野さんが連載していたころから「ケアの社会学」には関心をもっていた。数か月前に上野さんのケア研究がついにまとめられると聞き、これは重要な本になる、ケア関連の本の中では原典的な取り扱われ方をする本になるだろうと直感し、ぜひともまとめて読んでみたいと思っていた。
そして本を購入し、普段あんまり本は読まなくて大部な本は苦手なんだけど、わりと関心ある領域のことなので、なんとか最後まで読み通した。
しかし、読んでみた感想は、かんばしいものではなかった。読みながら「これではあかんのちゃうか」という思いがしばしば湧いた。
大著であり、ケアに関連する諸分野をほとんど網羅している。それなりに見事に整理している。これだけの仕事をやるのはやはり相当の才能と労力が必要だ。だけど、「ケアの社会学」というには、何か画竜点睛を欠いている。どこか大切な部分が見えてこない。
そして、この本がこのまま手放しに賞賛され、原典としての取り扱いを受けては困る、という思いにかられた。
どうしてそう思ったのか、違和感の所在はどこなのか、そこらへんのことについて、以下述べていく。その前に、ぼくが普段何をしていて、どういう立場からこの文章を書いているか、そうした自己紹介をしておこう。
『当事者主権』の物足りなさ
『ケアの社会学』は、「当事者主権の福祉社会へ」というサブタイトルがついている。この「当事者主権」という用語と思想は、上野さんが障害者自立生活運動から学んだものだ。2004年に『当事者主権』(岩波新書)という本を上野さんは、中西正司さんという障害者自立生活運動のリーダーと共著で出している。
ぼくは普段、この障害者自立生活運動の中で介助者、支援者として生息している。京都のJCILという自立生活センターで働き、また運動にもそれなりに活発に関わっている。とりわけ介護保障問題にはかなりの関心があり、行政交渉などにも積極的に顔を出している。障害者の介護保障を求めるかたわらで、介助者・支援者の生活保障も必要だと考えて、「かりん燈」という団体をつくって介助者の立場から自分たちの生活保障を行政に求める活動もしている。
介助をはじめてからは10年以上たち、自立生活センターに就職してからも7年くらいたっているから、それなりに現場経験も重ねてきた。
上野さんの礼賛する「当事者主権」の実践現場のわりと先端にいるんではないかな、と思っている。
そして自分の立場から上野さんの本を見るとき、これではものたりない、という思いを抱くのである。この本に書いてあることは、少なくとも障害者自立生活運動がすでに一通り経過してきたことのように思う。だから、自立生活運動の界隈にいる人たちに対しては、とりたてて新鮮なことはないから特に読む必要もないよ、などとも語っている。
さらに、これではまずい、と思うのは、上野さんが自立生活運動の表層のみをなぞり、深層にまで達していないと感じるからだ。一口に自立生活運動といっても一枚岩ではない。上野さんにはたぶん、運動のある一面しか見えていないのではないか(ぼく自身も、その深層はまだうまく語れないのだけど)。
もちろん『ケアの社会学』は革新的だ
しかしそういうと、上野さんの本に「批判的」だと聞こえるかもしれない。けれど、ほとんどの部分は全面同意だし、よくここまで整理して丁寧に書いてくれたなぁ、とも思う。
だから単に「批判的」にこの文章を書いていると思ってもらっては、とても困る。
むしろやはり、これまでケア領域に目を向けてこなかった人たち、目をそらしてきた人たちにはちゃんと読んでほしい。
今でも日本社会の市井では、家族介護こそが最良のものだと思われている向きは強い。
旧来のケアの価値観は、ざっと以下のような感じだろう。
家族のだれかが要介護者になったら家族が面倒をみる、そんなことは当然のことだ。男はやっぱり外で働く必要があるから、女がやっぱりその世話をする方がよい。介護保険とかの制度はやっぱり使わない方がいいし、もし利用するときがきたら、遠慮して感謝しながら利用しないといけない。ちょっと来てもらえるだけでもありがたいのだから、少々のことがあっても文句をいわない、要求はしない。「権利」なんて大それたこと、いえるわけがない。
ケアというのは立派な奉仕の行為。愛のたまもの。お金でやるものではない。たとえお金をもらったとしても、やりがいのある仕事なんだから、低賃金でも文句をいわない。文句をいうのは、きたならしい。
こうした既存の価値感、常識を次々と破壊していくためには、上野さんの本はやはり読まれた方がいい。
また、本書で採用される「当事者主権」という言葉にしても、ほとんどの人にとってなじみのないものであろう。「自立生活運動」もしかり。介護に携わっている人でも、特に高齢者介護分野の人々にとっては、「当事者主権」なんて、意味もよくわからない、その歴史的背景を知る機会もない言葉だと思う。
「当事者主権」ということで、上野さんは、あくまで「当事者」とはニーズの第一の帰属先である要介護者本人のことを指す、といっている。
けど、世間でもほとんどの福祉現場でも、普通に本人の思いは通用しないのが当たり前だ。介護保険では「利用者本位」なんて言葉もよく聞かれるけど、そんなのほとんど骨抜きだ。
本人の思いは、もっともらしい装いをまとって家族や介護職員の思いへと普通にすりかえられる。「こういう状態になったんでしたら、○○するのが、ご本人にとって一番いいんです。」「当事者主権」は耳触りがよいだけに、都合よく曲解されることに対しては、ぼくたちは慎重な見定めをしなければならない。
ぼくらは今でも、家族による介護殺人を目の前にしている。障害児も親に殺されるし、要介護の親も、息子、娘に殺される。ちょうど先日も、一日で三件、障害児殺しのニュースがとびこんできた。現在においても、要介護者は家族に押し付けられる。主として女性たちに押し付けられる。家族介護がいい、などという規範はたいがいにしておくべきだ。そうした社会規範は、暗黙のうちに「強制労働」へとつながっていることを認識すべきだ。
そしてまた、職員たちの虐待もなぜ起きるか。だれが福祉の介護現場を放置しているのか。なぜ現場はいつも手いっぱいなのか。そうしたことについて、もっと多くの人が真剣に悩んでいくべきだ。
旧来のケアに関わる社会常識を説得力あるかたちでつき崩し、新たな福祉社会へのビジョンを提示しようとするかぎりにおいては、上野さんの本は、多くの人にとって示唆に富み、革新的であろう。
『ケアの社会学』の要点
ちょいと先走ったところもあるけど、とりあえず『ケアの社会学』の要点を簡単に紹介しよう。
ケア——本書では高齢者介護、障害者介助、育児等の上位概念としてこの語が用いられているが、特に高齢者介護に焦点があてられている——については、すでに上野さんにとってはここ10年余りにわたる関心の対象となっていた。2000年代に入ってから、ケア領域に関する報告発表、発言が頻繁になされるようになる。
その途上で、先に述べたようにヒューマンケア協会代表の中西正司さんとの共著『当事者主権』が岩波新書から出されている。この本は、障害者自立生活運動とフェミニズムの運動の歴史がほぼ同様の歩みをたどっており、そして現在での共通の到達点が「当事者主権」というかたちでまとめることができるということ、そしてその当事者主権の内容と意義について書かれたものだ。
基本的には障害者当事者運動の歴史や主張・思想に沿って話が進められ、自立生活センターという運動体かつ事業体の成果や達成点について語られ、かつそれが「次世代型福祉の核心」とまで称されている。
上野さんの、障害者当事者運動への思い、肩入れはかなり強い。本書『ケアの社会学』の基本主張も、副題に「当事者主権の福祉社会へ」とある通り、障害者自立生活運動が達成してきたものが基礎となっている。
他方で、彼女にはフェミニストという彼女本来の立場からの問題意識もあり、その視点からも本書を書いている。『家父長制と資本制』という80年代に出た彼女の代表作があり、そこで彼女はマルクス主義フェミニズムという彼女の立場を鮮明に押し出し、家族問題、女の立場の問題、さらにそこに見られる育児、介護等の女性の不払い労働の問題が近代社会の社会構造(それがまさしく「資本制」と「家父長制」)に起因する問題であることを示したのだけれども、今回の『ケアの社会学』は、そのかつての作品の「直接の続編」である、といわれている。
『家父長制と資本制』の末尾では、「なぜ人間の生命を生み育て、その死をみとるという労働(再生産労働)が、その他すべての労働の下位におかれるのか、という根源的問題」について触れられ、そして「この問いが解かれるまでは、フェミニズムの課題は永遠に残るであろう」といわれる。
彼女はだから、『ケアの社会学』においても、ケアを「ケアワーク」「労働」として位置づける。ともすれば「愛」とか「奉仕」「やりがい」とかの言葉でごまかされる、そうしたケアの「労働」という側面、そして場合によっては、社会的圧力により女性におしつけられるケアの「強制労働」という側面も重視して論を進める。そうした観点から、(主として「嫁」、「娘」による)家族介護の自明視の問題点等をあばいていく。
だから『ケアの社会学』では、彼女は、「ケアされるもの」として当事者の視点、そして「ケアするもの」としての(特に女性の)当事者の視点のいずれも重視する。ケアは基本的に「ケアの与え手と受け手のあいだの相互行為」と定義される。
そして、ケアという「相互行為」が「のぞましい」のは、ケアの与え手と受け手双方が満足する場合、詳しくいえば、「1.ケアの与え手にとってケアしたいと思う人(と内容)をケアすることが選べ、ケアしたくない人のケアを避けることができるという条件と共に、2.ケアの受け手が、ケアを受けたい人からのケアを受け、ケアされたくない人のケアを避けることができるような条件のもとで、ケアが相互行為として成り立った」場合、とされる。
その際ベースにあるのは、ケアの人権アプローチという方法である。彼女は「ケアの人権」として、1.ケアする権利、2.ケアされる権利、3.ケアすることを強制されない権利、4ケアされることを強制されない権利の4つをあげる。それらのケアに関わる権利が各当事者間で適切に享受される場合が、最適なケアだ、ということになる。
他方で、「当事者主権」という概念の適切な理解のもとで、ケアの与え手と受け手のあいだに根本的な非対称があることも指摘する。つまりケアの与え手がケアからの退出・撤退が可能なのに対し、ケアの受け手はケアから逃れる事ができない。その意味で両者は非対称な力関係のバランスのもとにある、つまりありていにいえばケアの受け手の方が根本的に弱い立場にある。だから、彼女は、「当事者」という言葉を、純粋にニーズの帰属先としての本人に対してのみ使うべきだ、という。
そうした本人のニーズこそが一次的ニーズであり、それ以外の家族や介護者のニーズは、そこから派生する二次的ニーズにすぎない。そこははっきりわけて考えるべきだ、と考える。そして、第一次的なニーズの当事者こそ、制度や政策、サービスの最初で最後の判定者だ、と述べる。ここらへんは原則的な障害者当事者運動の主張の通りである。
彼女が本書『ケアの社会学』で根本にすえる規範は、上記の二つ、つまり「ケアの人権アプローチ」と「当事者主権」である。そして後者をより根源的な規範と考えている。ケアに対するこうした論点整理を行なった上で、彼女は高齢者介護分野の実践に、具体的に言及していく。
この実践編の中で上野さんが問おうとしているのは、「誰が介護を担うのがよいのか」という問いである。家族がいいのか、あるいは行政がいいのか(措置制度)、あるいは民間の営利企業がいいのか。彼女は、このどれでもなく、第4の領域として「協セクター」の優位を立証しようとする。
そこでとりあげられるのは、主として市民参加型の福祉サービス事業体としての生協福祉・福祉ワーカーズコレクティブである。彼女は、市民参加型のこうした福祉サービス事業体を「協セクター」として、高く評価する。
ケアに関しては、単なる市場も、単なる家族も、単なる国家も、どこにおいてもこれまで単体では限界につきあたっていた。
市場(民)の失敗(営利企業の論理の中では、ケアを必要とする人々は放置される)、家族(私)の失敗(市場の外部としてケアは家族領域にあてがわれてきたが、そこには女性の不払い労働があったし、また介護殺人に代表されるように家族介護には限界がある)、そして国家(公)の失敗(家族介護が限界に達した後、国の救済としての措置制度があったが、入所施設に代表されるように要介護者はきわめて劣等処遇のもとにおかれる、しかも費用も高くつきやすい)、それらを経て、彼女は協セクターに可能性を見る。
そして、先駆的な例として、ワーカーズコレクティブ等の市民事業体をとりあげ、そこで働く人々のフィールドワークを行なう。
全体としては、最初に述べたようなケアの理論的課題を前半で取り扱い、中盤以降、相当数のページを割いて、各地の先進的事例とされる市民事業体が取り上げられる。最後は、ケアの未来について語られて、おわる。ケア労働に関しては、ケアワークが階層の高い女性からより階層の低い女性たちに移転されていく「ケアチェーン」問題の難しさが述べられるが、次世代型福祉に関しては、当事者運動に夢が寄せられ、高齢者、障害者の連帯や、福祉サービスユニオンの構想が提案される。
以上が本書の結構である。ハードカバー上下二段組で500ページの大著である。理論面でも網羅的だし、またかなりのフィールドワークに基づき、先駆的実践例の紹介も豊富である。
ケアに関して、これだけ網羅的な書物はなかなかないわけだから、人それぞれで本書を読み進めていけば、ところどころに発見があるだろう。
しかし、まさに現在進行形の運動の真っただ中にいるぼくの立場からしたら、これだけでは物足りないのである。しかも上野さんの議論には大きな欠点があるようにも思う。
『ケアの社会学』の問題点
『ケアの社会学』の問題点について、いくつか思いあたったことを述べていこう。
まず一つ目、ごく簡単な点から。「当事者主権」を唱えるこの本では、第一次的なニーズの当事者こそ、制度や政策、サービスの最初で最後の判定者だ、と適切に述べられている。だからこそ、『ケアの社会学』においても、徹底して「ケアされる側」の声へと向かって踏み込んでいくべきなのである。けれども、上野さんはそれができなかった。
中盤以降で扱われるケアの実践紹介は、すべて提供者側、つまり「ケアする側」への調査である。「ケアされる側」の視点はほぼ完全に欠落する。もちろん高齢者には当事者運動がない、という彼女の嘆きはわかる(障害者の声は、7章で採用されている)。けれども、『ケアの社会学』という立派なタイトルをつける以上、要介護者本人の声に向かって上野さんはもっと進んでいくべきでなかったか。少なくとも、当事者団体に勤めるぼくとしては、これでは納得ができない。
ちなみに述べれば、上野さんがいうように、「当事者」とは、たしかに「当事者になる」ものである。けれども、ほっといて誰もが「当事者になる」わけではない。そこには陰に陽に、さまざまな支援や助けがあるのである。人が「当事者になる」ことに際しては、だれか他者にぐいっと踏み込まれてはじめて動き出すということも往々にしてある。だからこそ、本人の聞こえざる声に向かっての踏み込みが必要なのだ。そこへの踏み込みの足りない本書はやはり重要なポイントが欠落しているように思う。
また、そこに関係して、構成的にといっていいか、論理的にといっていいかわからないが、『ケアの社会学』の中でぼくがもっとも問題と感じるのは、意図してかどうかはしらないが、「当事者」概念のすりかえを上野さんが行っている部分である。
ケアの規範理論からいえば、「当事者」はニーズの帰属先としての本人に対してのみいわれる。しかし途中、ワーカーズコレクティブについて論じるあたりから、上野さんは、協セクターで活動する(主として女性の)経営者や組合員を「当事者」として立てている。
NPO法人等の協セクターでは、「自分たちがほしいサービスを自分たちの手で」供給する、そうした「当事者」性がある。さらにそうしたところで働く彼女たちは、みずから「家族介護の当事者」であったりもする、などと語られる。
またワーカーズコレクティブの調査研究のやり方は、女性自身による「当事者研究」であるともいわれる。上野さんは、こうした女性たちの「当事者性」を重視して、そこから高齢者介護の先進事例について語っている。
悲しいかな、ここで上野さんは「当事者主権」の原則を外してしまっている。そしてケアの与え手側を「当事者」と語る過ちをおかしてしまっている。
上野さんはそのことをわかっているだろうが、慣れていない読者たちはそこにころっとだまされるだろう。
あとにも振り返って述べるが、ここには、女性解放の立場と障害者当事者運動の立場の両方に立とうとする彼女の中での、無理が表れているのだと思う。女性自身が社会を切り開いていくことに期待するフェミニストとしての立場がここでは勝ってしまっていて、当事者原則からちょっと外れてしまっているのかもしれない。
また、彼女が思い入れしているというワーカーズコレクティブにおけるケアの内容が、おそらく貧弱であろう点も、気になるところである。この本の中で何度かいわれているが、障害者介護保障運動は在宅独居による24時間介護を実現しながら運動を進めてきた。そこの中心にはつねに、重度障害の当事者がいた。しかし、どう見ても、ワーカーズコレクティブの実践では、介護程度の軽い高齢者の要望にしか応えられていない。
ワーカーズコレクティブで提供されるサービスは、相対的に豊かな層の女性たちのための、ゆとりや生きがいの延長としての有償ボランティアでしかない、といわれている。そして「『自分で働き方を選べる』ワーカーズコレクティブは、その結果として利用の集中する朝や夕方の時間帯や休日・夜間のワークの引き受け手がいないという人手不足に悩まされる結果となった」そうである。
与え手の都合優先で考えていたら、受け手はつねに不利をこうむらざるをえない。自分の働きたいときにだけ働く、そんな気分で重度障害者の生活が支えられるわけがない。深夜の介助はだれが行うのか。つねに必要なときにそばにいてくれるのか。その介護がなければ重度障害者の自立生活など成り立つわけがないのに、今日はごめん、その時間はムリ、夜はムリ、で重度障害者の生活が支えられるだろうか。
与え手主導のサービス提供組織では、重度障害者はおいてきぼりにされる、そうしたことはすでに障害当事者運動が何十年も前から主張してきたことだ。ワーカーズコレクティブにおける、そしてまた介護保険における、介護保障の水準は、障害者福祉制度とは雲泥の差がある。いくら女性主体のワーカーズコレクティブ(高齢社会をよくする女性の会も含めて)に期待しようが、おそらく介護保障の水準が(少なくとも深さに関して)上がることはない。これは歴史が証明している。介護保障というのは、ケアされる当事者が中心となった運動によってはじめて深まっていくのである。
(なお、あまり知らない人のために。障害者福祉では、障害者運動が勝ち取った成果によってホームヘルプが一日24時間利用できるが、介護保険ではホームヘルプの利用時間は上限で一日あたりせいぜい3、4時間。提供者側からの運動によっては、これが5、6時間になったとしても、24時間になることはありえないだろう。入所施設を除いては。)
また、「協セクター」に期待を寄せる上野さんであるが、その「協セクター」は救貧や弱者救済に責任をもつ必要がない、と述べている点は気になるところである。
「ワーカーズコレクティブの有償サービスは、困っているが利用料金を負担する経済能力がない人たちには手が届かない。生協のような有償の介護事業体にとっては『公益性』といってもあくまで会員間の互助活動にとどまっており、救貧や弱者救済に責任がもてるわけでもないし、持つ必要があるともいえない。むしろこうした弱者救済こそ真の意味の公的福祉、すなわち官セクターの役割であり、協セクターとは役割分担すべきであろう。」(p300)
ここには若干の但し書きが必要であろう。上野さん自身は、ケアの市場化には反対で、ケア費用については国家化、ケア労働については協セクターへの分配が望ましいとする立場であり、つまり事業としては協セクターにまかせるが、費用面は公的責任において保障するのがよい、と考えている。それは現在の自立生活運動の主流の主張でもある。だから官と協の上記のような役割分担で何を指しているのか判然としない。まさか、生活保護水準の人たちには官セクターによる最低限の劣悪サービスでよい、と考えているわけでもないだろうが。
それはそれとして、基本発想として協セクターというのが、お上の力を頼らず、自分たちで互助的に支え合いながら事業をしていこうという側面があることはたしかである。
しかし、障害者自立生活運動の歴史に目を転じれば、こうした市民事業体が、重度障害者の生活を支えることができなかったことはすでに歴史が証明している。
自立生活運動でも、初期のヒューマンケア協会に代表されるように、住民参加型の有償介助派遣事業の試みはあった。しかしその弱点は早急に認識された。多くの障害者は購買力がないし、重度障害者の介護保障はその発想からは不十分だからである。自費による有償サービスで生きていけるのは、介護が一日あたり数時間程度ですむ障害者たちまでであり、重度障害者はそこからはこぼれる。
自立生活運動においてその弱点を補ったのは、それ以前からあった公的介護保障要求運動との連携である。そして、公的介護保障要求運動は徹底して公的責任を追及した。行政に、重度障害者の24時間介護を保障しろ、と迫ったのである。この運動こそ、現在成立している障害者の24時間介護制度の基礎をつくったものであるが、そのことはあまりに認識されていない。重度障害者の24時間介護制度は、行政の公的責任を強く問う中で成立したのである。
上野さんのように、協セクターの可能性に期待して、「弱者救済こそ真の意味での公的福祉の役割」で、協セクターと官セクターは役割分担したらよい、なんて甘いことをいっていたら、公的福祉はどんどん撤退するに決まっている。公的福祉が撤退した後でも、経済力のある人たちは、その購買力を武器に、介助・介護を利用できるかもしれない。しかし、それでいいのか(なお、障害者の介護保障運動の歴史については、拙著『介助者たちは、どう生きていくのか』生活書院 の4章に詳しく書いているので参照にされたい)。
また、経済力というところで、どうも上野さんには、セレブ的発想がある。たとえば、ヘルパーの指名制度を介護保険に導入できないものか、真剣に考えているようである。「利用者から人気の高いヘルパーに指名が集中すれば、指名料をとって報酬を増額すればよい」そうである。別にセレブ的発想が悪いというわけではない。
けれども、これでは貧乏人の反感を買うのは必至だ。金持ちは金を払ってよいケアを受けられる。貧乏人はだれがきても文句いわずがまんしなさい、といっているようなものだ。そういう嗜好は、それはそれで当然と思うが、それならば『ケアの社会学』は『(セレブの)ケアの社会学』という但し書きが必要ではないだろうか。
そういえば、上野さんは『おひとりさまの老後』という本では、金のある高齢シングル女性のサクセスストーリーのみを取り上げた、といっている(『現代思想』2011年12月臨時増刊号)。
そして最後に、上野さんは、なぜ「ケアワークは安いのか」という問題設定をするが、彼女にはどうも働く人たちへのまなざしがあまりないような気がする。彼女の視点は、まず基本は経営者に向かい、そしてサービス利用者として障害者にも向かう。けれども、もちろん働く人への言及はあるけれども、どうもその人たちへのまなざしがない。これはぼくが介助者であるゆえの感覚なのだろうか。
ワーカーズコレクティブの事例にしても、高経済階層の女性たちが「活動」の主力であり、「労働」して稼がねばならない低経済階層の女性たちはあまり登場しない。指名制の話にしたって、顔立ちがよくスキルの高い人たちは高い報酬をもらっていくであろうが、うだつの上がらない人たちはそこで格差をつけられる。
すべて一律がいいといっているわけではないが、ヘルパーの選別に対して多くのヘルパーの心理が動揺することは、彼女はご存じなのだろうか。彼女の視点は、基本的にケアワーカーを使用する側にあるように思う。経営者としてケアワーカーを使用する視点。利用者としてケアワーカーを使用する視点。
そして彼女には、自らがケアワーカーになるという視点があまりないのかもしれない。
「わたしたちの社会の女性のケア労働は、もっと条件の悪い他の女性たち(外国人、移民、高齢、低学歴、非熟練等々)の負担において『解決』される」(p451)
これは彼女自身の言葉であるが、彼女はこの課題に対しては十分な解決策を示していない。そして、ぼくが思うに、彼女の『ケアの社会学』からはこの課題は等閑視されざるをえない。上野さんの『ケアの社会学』は『ケアワーカー使用者の社会学』と言い替えられうる側面もあるように思う。
未完の『ケアの社会学』
前半で述べたように、この本は、大半の世の「常識人」にとっては革新的内容を含んでいる。彼女の家族破壊と女性解放の戦略は、やはり『家父長制と資本制』以来一貫している。
そして、育児と介助、介護をひっくるめたケアという人間の生命に関わる再生産様式に対する、彼女独特のまなざしも一貫している。生命の育みとその死の看取りへの深い関心が、戦闘的な彼女の思想の根っこにあるのだろう。それでも、本の構成、内容、論理上、ぼくが感じたところでは以上のような問題点があった。
「労働者性」の軽視と感じる部分に関しては、ここではこれ以上論究できない。むしろ彼女はその部分は論じずに突っ走っていけばいいように思う。それが時代を切り開いてきた先駆者の役割なのだろう。
もうひとつ、女性の立場と障害者の立場との間の溝について。問題点を論じる中で、障害当事者の視点に立つよりも、フェミニストとしての立場が勝ってしまっているのではないか、だから当事者主権の原則を外しているように見える、と述べた。残念ながら今回のこの本では、その二つの立場の間の溝については言及されていない。彼女もそこらへんを内省することは嫌がるかもしれない。
しかし、障害者運動の嚆矢が横塚晃一『母よ!殺すな』(生活書院)であったことは強調されていいように思う。70年代、福祉政策の欠如(=家族への押し付け)の中で母親による障害児殺しが多発したとき、母への同情は世間から多数あり、減刑嘆願運動まで起きたが、殺された障害児への同情の声は一切見られなかったという。それに脳性まひ者たちが抗議したことが、障害者自立生活運動のはじまりとされる。
もちろん、なぜ「父よ、殺すな!」でないのか、あるいは「母に、殺させるな!」でないのか、といった問いを考えてみるのは有意義である。けれども、障害者たちは、女としての母との格闘から、自分の道を切り開いてきた。自立生活運動はつねに、健常者社会、健常者文明一般を批判すると同時に、目前に立ちはだかった「母なるもの」と対決してきた。母はしばしば障害者にとって直接の抑圧者であった。「当事者主権」を本当に語るならば、そこらへんまで踏み込んで論じていってほしい。
上野さんの『ケアの社会学』の内容が深まるには、このあたりの格闘が書き込まれていかねばならない。それ抜きには、当事者主権の形式的追跡にとどまるであろうし、70年代と同じ過ち——ケアされる側の声は無視され、ケアする側への同情に終始する——が繰り返されないとも限らないのだ。「当事者主権」の論理も、「利用者本位」などと同様、現場では簡単にすり替えられるのだ。
じつは『家父長制と資本制』において、すでにそこらへんの格闘に対する示唆がある。その6章に「子供の叛乱」と題する節がある。以下、そこから引用するが、「子供」を「障害者」、ないし「要介護者」、「ケアされる者」に置き換えてほしい。ここに見られる抑圧の問題と取り組んでいくことなしには、『ケアの社会学』は完成しないであろう。
「子供の抑圧と叛乱は、フェミニズムとつながる重要な課題である。女性と子供は、家父長制の共通の被害者であるだけでなく、家父長制下で代理戦争を行なう、直接の加害——被害当事者にも転化しうるからである。家父長制の抑圧の、もう一つの当事者である子供の問題と、それに対して女性が抑圧者になりうる可能性への考察を欠いては、フェミニズムの家父長制理解は一面的なものになるだろう。」(p133、岩波現代文庫版より)
『ケアの社会学』はまだまだ未完成である。この本の読者は決してここで甘んじていてはいけないのだ。この本に書かれている内容に対して、別の視点、すなわち本来の「当事者」の視点で書かれたものが追加されることが切に待望される。そしてそれは掘り起こされていかなければならない。
ケアの課題に対しては、もっと重層的な立場からのやりとり、対話が必要である。その際つねに、自分がどこの立場からものを語っているのか、問われざるをえないし、自問せざるをえないだろう。この「大著」をこえて、ケアにまつわる議論を進めてゆくために。日々葛藤の中にありつつ、障害者の地域生活を支える介助者、支援者として生きている者として精いっぱい書かせてもらった。
プロフィール
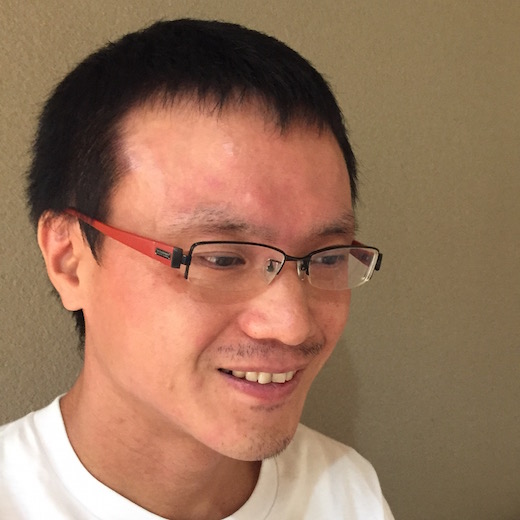
渡邉琢
日本自立生活センター事務局員、


