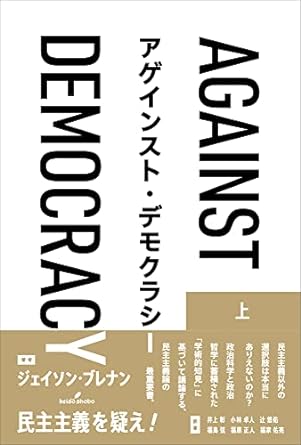2024.04.22

ジェイソン・ブレナン『アゲインスト・デモクラシー(上下)』
私たちは一定の年齢に達すれば選挙権が与えられる。しかし、政治的に無知な人々があまりに多く投票するために民主主義の危機が起こっている。そこで次の選挙からは政治的知識について共通テストを実施し、90点以上を取った者だけが投票できるようにしよう。――この提案は受け入れがたいだろうか。もしそう思うとすれば、それはなぜだろうか。
本書は現代の分析政治哲学の第一人者ジェイソン・ブレナンによる、包括的な反民主主義理論の書である。その主張によれば、民主主義は人々が思いこんでいるほどよいものではまったくなく、むしろ人々を敵対させるなど、有害な面さえ多くあるという。その克服のためには、人々をできるだけ政治から遠ざけ、政治への参加は知的に厳選された人々に限定しなければならない。そのようにして、民主主義(デモクラシー)に対する「知者支配(エピストクラシー)」の擁護を試みる(以下では本書の翻訳に合わせ、democracyを片仮名で「デモクラシー」、同様にepistocracyを「エピストクラシー」と表記する)。
この概要だけでも本書は危険な書であるかのように思われるかもしれない。現実のデモクラシーにはさまざまな欠陥があるだろうが、それはいまだ不完全な人間たちが非理想的な状況で行っているからではないか。一人一票の原則など、人々が歴史的に多くの血を流して勝ち取ってきた平等の理念を捨て去り、こともあろうに政治的知識についての投票者資格試験に合格した者のみに投票権を与えるとは何事か。エピストクラシーのこうした主張は反直観的、少なくとも論争含みである。しかし本書は、私たちがデモクラシーについてあまりにも自明に思っている諸々の価値には実のところそれほど盤石な基礎があるわけでもないことをひとつひとつ暴き立てていく。
分析的政治哲学の魅力
その論述からは――挑発的な表現に心を動かされないことが必要だが――、現代の分析政治哲学の魅力を存分に味わうことができる。いくつかの特徴を述べるならば、(1) デモクラシーに対するエピストクラシーの擁護という明確な目標のもと、(2) ありうる反論を丁寧に分節化しながら退けていく。そこでは (3) 多くの魅力的な仮想事例・思考実験やアナロジーが用いられ、また (4) 議論の成否を現実の各国の政治制度におけるパフォーマンスなど、検証に向けて開いていく。理論と実証といった非生産的な縦割りから逃れ、ときに突飛な仮想もまじえつつ、デモクラシーにこれでもかと不利な材料を与えていく論述はめまいがするほどだが、現代の分析的政治哲学の面白さが詰まっていることは確かである。
もちろん、ブレナンの主張をそのまま受け入れる必要はまったくない。その議論はときに露悪的であるし、意図的な飛躍を紛れ込ませているのではないかとさえ思える箇所も少なくない。それらはむしろ、そこで私たちのデモクラシーに対する価値観をじっくり問い直すための誘いであるかのようにも思える。
一例をあげよう。第5章「政治はポエムではない」(このタイトルも意地悪だが)では、政治的判断力について人々の間に優劣があるとすることは、そこで劣っているとされた人々を尊重しないことにつながるという「記号論的主張」が紹介される。これ自体は穏当な主張に見えるものの、それに対しブレナンは、たとえば医者が急病人を目の前にしたときに自分の医学的能力について謙遜するようなことはあってはならないし、自身の能力を表明したからといってそれが他者を尊重しないということにもならない。だとすると、政治的判断能力の優劣を認めたところで、それは同様に政治についてのことだけであって、人格的優劣とは無縁のことではないかという。
ブレナンはこの種のアナロジーによって直観に訴える議論を多用する。もし、この例で何か特別なことが見過ごされていると感じたならば、それは政治というものに必要以上の価値付けを行っているからではないか。あるいは、本来は社会的・経済的問題であるはずのこと(たとえば、低所得者層ほど政治的知識が乏しいといった状況)を政治的問題と不当にも思いこんでいるのではないか。ブレナンのこういった見方は、政治の領域をかなり狭く見た結果でもあるし、また、集合的問題を個人的問題へと還元することで解消を図る論法も多く用いられる(個人と集団の相互関係を軽視している点には批判もなされている。参照、Christiano 2017)。しかし「政治」や「デモクラシー」というものにしばしばどういった価値が付け加えられがちなのか、という問題に目を向けさせるための有効な議論であることは確かだろう。仮に、現代においてデモクラシーへの幻滅が広がっているとするならば、それはどのような価値がデモクラシーに付与された結果なのか、という問いが本書から得られるのである。
課題
本書はデモクラシーとその内在的価値とされるもののつながりを丁寧に解きほぐし、また別の可能性があるかもしれないと示すことにはある程度、成功しているといっていいだろう。しかし、エピストクラシーの積極的なヴィジョンを示す作業は道半ばであり、そのため、競合する立場との差別化にはいまだ課題が残っている。
ブレナンがエピストクラシーを支持するのは純粋に道具主義的な根拠によるとされている。つまり、正しい結果を生み出すがゆえに支持されるのであって、何らかの内在的価値ゆえではない。同様に道具主義をとる認識的デモクラシー論(特にエレーヌ・ランデモアによる、多様性を重視する主張)については、現実の市民は多くの系統的な誤りを犯すものであることを捉えていないと批判される(第7章)。もっとも、それはブレナンにも跳ね返り、政治的に有能な者はいかにして政治的知識を得るのか?と問われる(Eliot 2018)。よく機能するエピストクラシーにも相応の初期条件が必要である以上、道具主義‐認識主義内での差別化のハードルは高い(Vasic 2022)。しかし、エピストクラシーを支持するブレナンと、認識的デモクラシーを支持するランデモアとでの対話本も出版されるなど(Brennan & Landemore 2021)、この領域での論点は明確になりつつある。
翻訳の正確さ
最後に特筆すべきこととして、本書の翻訳がきわめて正確で読みやすいことをあげておきたい。筆頭訳者の井上彰はすでに国際的に活躍する分析政治哲学のトップランナーだが、他の小林・辻・福島・福原・福家は政治哲学を専攻する、優秀な大学院生・ポスドクであり、私などはもはやただ教えてもらうことばかりである。この分野の、とりわけこの20年ほどの進展にはおそろしいものがあるが、その集大成ともいうべき本書がこれだけ読みやすい日本語に翻訳されたことはこの強力な翻訳チームのおかげであることは想像に難くない。訳者たちによる解説(勁草書房ウェブサイトで公開されている)も過不足なく本書の背景や魅力を伝えている。本書の議論に関心をもった読者は、ブレナンやその批判者たちのさらなる議論を(できれば英語でそのまま)読んでもらいたいが、それに加えて、この若い訳者たち自身の論考もご覧になることをおすすめする。
読書案内
本書は一見したところ読みやすそうな筆致の裏に、近年の分析的政治哲学におけるデモクラシー論の膨大な蓄積がある。各論者の議論をすべて押さえる必要はないと思うが、一応の見取り図があったほうが読みやすいことは確かである。最初の一冊としては、デモクラシーの多様な論点を扱う、齋藤純一・田村哲樹 編『アクセス デモクラシー論』(日本経済評論社、2012年)がよいだろう。
デモクラシーへの懐疑的視点をブレナンとある程度共有するものとして、ブライアン・カプラン『選挙の経済学:投票者はなぜ愚策を選ぶのか』(長峯純一・奥井克美監訳、日経BP社、2009年)と、イリヤ・ソミン『民主主義と政治的無知:小さな政府の方が賢い理由』(森村進訳、信山社、2016年)がある。
文献
Brennan, J. and Landemore, H. (2021). Debating Democracy: Do We Need More or Less?, Oxford University Press.
Chrstiano, Th. (2017). “Against Democracy,” Notredame Philosophical Reviews: https://ndpr.nd.edu/reviews/against-democracy/
Elliott, K. (2018). “Against Democracy,” Contemporary Political Theory 17.
Vasic, M. (2022). “How Realistic Is the Modeling of Epistemic Democracy?,” Critical Review 34(2)
プロフィール

吉良貴之
法哲学専攻。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程満期退学。現在、愛知大学法学部准教授。研究テーマは世代間正義論、法の時間論、法と科学技術、およびそれらの公法上の含意について。主な論文として「世代間正義論」(『国家学会雑誌』119巻5-6号、2006 年)、「将来を適切に切り分けること」(『現代思想』2019 年8月号)。翻訳にキャス・サンスティーン『入門・行動科学と公共政策』(勁草書房、2021年)、エイドリアン・ヴァーミュール『リスクの立憲主義』(勁草書房、2019年)、シーラ・ジャサノフ『法廷に立つ科学』(監訳、勁草書房、2015 年)など。