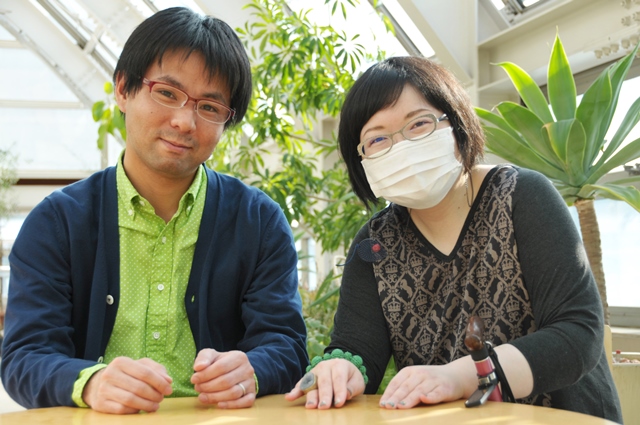2013.04.15

「倫理の溶ける瞬間」は誰にでもある。
「介護」の現場を真正面から描いた小説『ロスト・ケア』で第16回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した葉真中顕さん。自らの難病体験を綴った『困ってるひと』で2011年にデビューし、このほど2冊目の単行本となる『さらさらさん』を上梓した大野更紗さん。娯楽の体裁をとりながら、日本社会へ大きな問いを投げかける二人の新進作家が、初めて出会って、語った。
「ロスジェネ」世代の実感
大野 葉真中さんは、1976年生まれということで「ナナロク世代」とか「ロスジェネ」とか言われますよね。
葉真中 言われますね。
大野 『ロスト・ケア』の中にも、「ロスジェネ世代」という言葉が出てきます。
葉真中 今の30代半ばぐらいを中心とした世代のことですね。
大野 だんだん働き盛りになってきて、会社や組織の中堅になってくるような世代。いわゆる「フリーター」や「ニート」、そういう表現が世の中で一般的に使われ始めた時期に社会に出ていて、「氷河期世代」という言い方もされます。しかし、そのような言い方が出始めた10年前は、みんな20代だったわけで。……10年前というと、葉真中さんは何歳でしたか?
葉真中 今37なので、27歳です。
大野 27歳のときはそんなに気にならなかったことも、10年経てば、いろんなことが気になってくるんじゃないかなと。
葉真中 はいはいはいはい。
大野 当時は、その日1日を生きるのに精一杯で、非正規雇用でもいいと考えていたり、あるいは社会制度などが自分とは縁遠いものだったかもしれない。しかし今はなかなか切じつに、介護や医療についても悩むことがある。まずは、自分たちの親をどうしたらいいのかということに悩み始めているのではないでしょうか。そもそも葉真中さんが『ロスト・ケア』を書かれたのは、何かきっかけがあったんですか?
葉真中 まずは、不遜な言い方ですけれども、小説家になろうと。これまでもライター業みたいなことをやっていたんですが、ちゃんと文筆一本で食っていけるような作品を書こう、新人賞に出して勝負しようと思ったんです。そのときに、娯楽性の高いミステリー小説にしようというのは決めていたんですね。で、モチーフを選ぶときに、自分でも一番深刻に考えていることで、世の中の人にもっとも突き刺さるテーマを選ぼうと。
介護体験と「コムスン事件」
葉真中 さっき大野さんが言っていた、20代後半ぐらいまではまだ実感がなかったことが、だんだん当事者性を帯びてくるというのはまさにその通りで。私ちょうどその頃に結婚しているんです。結婚と同時に実家に戻って、祖父を介護して看取るところまでやりました。 これはもういろんなところで言われていることですが、介護とかってある日突然当事者になる。これだけ「高齢化、高齢化」と言われていて、それ自体は知っているわけですよ。
大野 日々のニュースに頻出する出来事として、頭ではわかっている。
葉真中 はい。でも実際、家族が要介護状態になったときにどうしたらいいか、たとえば介護保険制度の使い方なんかがぜんぜんわからない。自分が家族の中で一番若くて細かい字も読めるとか、そういう理由でいろいろな資料を集めたりして、やっと、随分おかしな制度だな、使いづらい、めんどくさいと思うわけですね。そうやって、身内の介護を通していろいろ感じた違和感というのが、何か書こうと思ったときに、モチーフ選択のとっかかりになったかなというのはありますね。
大野 なるほど。葉真中さんご自身はそのとき、どんなところでおかしな制度だなとか、使いづらいなと感じたか、今ぱっと思い浮かびますか?
葉真中 ぼんやりした記憶なんですが、祖父が要介護認定を受けるときに、たしか市役所の人が来ていろいろ質問をされたんですけれども、事前に「なるべく答えられないようにしたほうがいい」みたいなアドバイスをくれた方がいたんです。それが「要介護度」を上げるための知恵だというんですね。
同じようなことが『さらさらさん』の中で熊谷晋一郎さんとの対談で触れられていたと思うんですけれども、同じ人でも調子が良ければできるし、ダメなときはできないという、ものすごい振れ幅があるわけですよね。それを、「要介護」という数字に落とし込んでいくこと自体に違和感を覚えました。
そうやって「程度」で切っていかないと制度が回らないというのもわかるんですが、とにかく当事者として強い違和感があった。そのときの調子の良し悪しだったり、さらに言えばちょっと気をきかせてお芝居をするかどうかみたいなことで、その人の「要介護度」が違ってくる。すると、受けられる介護の時間が全然違ったりする。それが、その人の生活の質や、下手をすると寿命まで左右してしまう。「こういうものなのか」というのが、まず実感したことです。
大野 なるほどなるほど。
葉真中 その話でいくと、当時、立て続けに祖父の兄弟が次々と要介護状態になっていったんです。私は一回経験しているので、どうしたらいい? と聞かれるわけです。それで、いろいろ調べて、親戚の一人にコムスンのサービスを使ったら? というようなお手伝いをしたんですけれども、ちょうどそのときに「コムスン事件」が発生したんですよ。
(*「コムスン事件」とは……
2006~2007年にかけて、訪問介護最大手のコムスンによる介護報酬の不正請求や違法な指定申請が発覚し、厚生労働省の処分を受け、最終的に分割譲渡された事件)
大野 いわゆる「コムスンショック」ですね。
葉真中 『ロスト・ケア』の中でも、コムスン事件をモデルにした事件が発生するんですけれども、実際の事件が起きたときにも、マスコミを中心にコムスンに対する総バッシングみたいな状況が発生して、また別の違和感がありました。
大野 まるで、ガス抜きというか、お取り潰しのような状況がありましたね。
葉真中 ええ。そのへんの私の違和感はかなり作品の中に反映させていますが、構造的な問題のような気がしたし、現場の事務所に嫌がらせの電話がかかってきたりすることには「違うだろ」とストレートな怒りを感じました。
電話をかけた人は誰かわからないですが、やっぱりメディアの語られ方に問題があるのではないかと。「せっかく」なんて言ったら良くないかもしれませんが、せっかく大きな矛盾が噴出しているわけですから、なにか建設的な方向で、テレビなどの大きなメディアで議論が進めばいいのになって。
この問題はコムスンだけの問題じゃないということを言っている方たちがいらしたのは、書くにあたっていろいろ調べる中でわかったんですけれども、当時、普通にテレビを見て、普通に新聞を読んでいた私の生活感からすると、完全に一企業の、もっと言うとその会長という邪悪な人のせいでこうなったというひとつの物語として見えてしまっていた。それについては当時も強烈な違和感があったし、今もあれで良かったのかなと思っていますから。
大野 高齢者ケア領域のワーカーの友人の中に、当時ちょうどコムスンで働いていた人が何人かいます。コムスンの事業所のワーカーだというだけで、近隣の住民から聞こえるような声で非難されたりとか、自分たちは地道にケアをしているのに「極悪非道の悪人」みたいに言われることもあったそうです。
葉真中 そうですよね。
大野 「コムスン」という会社というか、組織が抱えている問題はもちろんあったのでしょうが。当時のワーカーの人たちに話を聞いていると、「アイツのせいだ!」っていうことにして、「私たちは悪くないんだ」と思いたかったのかなと考えるときがあります。
葉真中 コムスンの中の人でも、ということ?
大野 社会全体が、ということだと思います。「高齢者介護の社会化」が大きく謳われて、2000年から介護保険制度がスタートしたわけですが、介護にまつわることって「家の中」のことが多いから、親密圏の領域で、密室の中の人間の関係性がめちゃくちゃ歪みやすいんですよね。
葉真中 そうですよね。
大野 対人援助の領域は、援助者と被援助者の関係性は歪みやすくて、多くの方が悩みます。「虐待」が、親密圏内の暴力がリアルに自分の手に迫ってくる。私は当時難病と全然関係ないところにいたので、「コムスンショック」についてはリアルタイムでは何も知りません。後から、コムスンで働いていた経験があるワーカーの話を聞くというかたちで当時の状況を整理しているのですけれども。印象に過ぎませんが、やはり当時未熟だった制度の矛盾や構造的な問題について、「コムスンのせいだ」と思いたかったのかなという気はします。
葉真中 これはもしかしたら事業所にもよるのかもしれないですけれども、私の親戚が利用していて、直接話したり聞いたりした範囲では、そういう難しい時期にありながら、現場のワーカーさんたちは、「後ろ暗いようなことは少なくとも自分の事業所ではないし、私たちは求められている仕事なのだからしっかりやりたい」みたいなことをおっしゃっていたし、実際そのようにやってくれていたと思うんですね。
そういう現場の人たちに支えられてなんとか回している世界があるということは共有しなくてはいけないし、そのような現場に誹謗中傷が向かってしまうような世論の形成のされ方には問題があるんじゃないかと思っていました。そういうような当時の記憶を探りながら、今回の作品のモチーフとして援用させてもらったという経緯はあります。
小説だから書けること
大野 この小説はミステリーということで、「ネタバレ」になってしまうので内容については突っ込んでお話できないのですが……。
葉真中 後半の展開に触れなければ大丈夫です(笑)。
大野 じつは、私は自分が難病にかかってから、目の前で展開されている世界そのものが「壮絶」なので、小説を娯楽として読めなくなってしまった面があります。「読もう」と意識的に思わないと読めない、みたいなところがあったんです。でも『ロスト・ケア』は本当にするするするするするっと読めた。久しぶりに、ああ小説っていいな、小説にしかできないことってこういうことだな、と感慨深く読みました。
私も高齢者介護の現場の人たちに話を聞いたり、どういうことが起きているかを様々な方法で捉えようとするのですが、それを「外に出す」ことは非常に気を遣う難しいことなんです。もしかすると、介護職の人たちを危険にさらしたり、職を失わせてしまうかもしれない。これは自分の調査者としての最低限のモラルに関わることですが、何らかのかたちでご本人のお役に立てるならまだしも、同意も得ずに危険にさらすことはできない。ノンフィクションやルポでは、高齢者介護の問題を描ききるということはとても難しい仕事なんです。
「一番苦しいこと」を表現するのって、人はなかなかできない。それを小説という手法で、見事に書かれていると思いました。
日本社会が真剣勝負で考えなくてはいけないこと
大野 介護保険制度の高齢者介護と、若年の障害を持つ人たちに対するケアの歴史は、合流がありつつも、それぞれ違う文脈があります。高齢者介護は基本的に、「当事者不在」と言われて久しいんですよね。
葉真中 はいはい。
大野 政策形成の過程でも、事業者団体はいるんですけれど、高齢者「本人」は基本的にお客様で利用者で、全然関わらないですよね。一方で、障害のケアの領域というのは、1960~70年代から、世界的にラディカルな社会運動が盛り上がりました。それこそ一種一級最重度、脳性まひで、言語障害も強くて自分ひとりでは何もできないように、一見すれば見えるような人たちが、自ら運動して勝ち取ってきた歴史があります。家庭の中で主に女性たちが担ってきた介護労働という多大な負荷を、なんとか社会化しなくては社会の持続可能性が失われるということについて、先駆的に強く声をあげてきた人たちがいるわけです。
だから基本的に、障害の制度のほうは申請主義だし、本人が「こんなニーズがある」と言わなくてはいけない。もちろん障害の方でも、程度区分認定という、高齢者ケアの領域の要介護認定に当たるようなシステムがあって、それを受けないと支援は受けられないのですが。しかし大前提として、「本人の申請とニーズが第一」という精神が制度にも支援者にも最低限、共有されているところがあります。
でも高齢者ケアの領域は、国や事業所や会社によってある程度既存のものが用意されていて、利用者はそこから選ぶというかたちになっている。例えるなら、画一化されたファミレスがたくさんあって、食べるものは全部、そこにあるメニューから選んでね、というような印象を受けるところがあります。
葉真中 そうですね。
大野 もちろん、「今日はファミレスがいい」という日は人間あるわけですけど、24時間365日、3食全部ファミレスで食べろって言われているような、そういう印象が高齢者ケアにはあるような気がするんです。
葉真中 これは若干、自分の作品のことに引っぱっちゃいますけど、現代のミステリー小説では、「視点の吟味」というのがすごく重要視されています。とくに『ロスト・ケア』の場合は、三人称多視点という技法で視点人物が何人か入れ替わる。記述は三人称なんですけど、章ごとに視点人物が決まっていて、「視点人物が知らない情報は書かない」という原則で書かれているわけですね。
最後に推敲するとき、この「視点の吟味」は結構細かくやりました。で、そのときに気づいたのが、これは自分でも意図的なのか、そうでなかったのかわからないんですが、この小説は徹頭徹尾「介護する側の人間の物語」になっている。タイトルに「ケア」と付けておきながら、最後まで介護される人の感情心情っていうのは……。
大野 出てこないですよね。
葉真中 そうなんですよ。おそらく私がまだ30代で、どうしても「する側」という部分で書いているのがひとつと、こういう物言いが適切かわからないんですけれども、どこに向けて投げる小説かというと、主にこれから介護をする側の人に向けて書いている小説なので、というところはあると思うんですけど。
半ば無意識にそうなっているにしろ、この小説の中には介護される側の視点は出てこないんだなって、推敲の段階で自覚したんですね。それが悪いとか良いという話ではなく、私はそういうものを書いたことに、少なくとも自覚的であろうと思いました。
逆に言うと、私なりにバランスをとって、いろんな考え方、感じ方を詰め込んだつもりでも、被介護者の視点を落としてしまうということは、実際に高齢者介護の現場や制度づくりにおいても、当事者視点は落とされがちな要素なのかなというのは思いました。
大野 この小説の中で、かつては同じ家に暮らしていたはずの父親と息子が登場するのですが、とてもリアリティがあると思いました。息子は、父親のことはなかなか考えられなくて、ずーっと自分自身の人生のことを考えている。
葉真中 そのリアリティというのは、私自身も祖父を介護する中で感じました。とくに、認知症が進んでだんだんコミュニケーションが取りづらくなると、どんどん自分自身に意識が向いてしまう。たとえば、何かひとつ今までやっていたことをやめるとしますよね。それが良かったのか悪かったのかみたいな葛藤が、どうしても当事者の視点では入ってこない。自分が自分に対して倫理的に許せるのかどうかという葛藤になってしまう。
大野 私は基本的には当事者なんですけど、ときに支援者的な立場に立つこともあります。障害を持っている方たちや患者さんたちと付き合うというのは、なんというか、ダイナミズムがあるんですよね。その方が人として成長する瞬間とか、社会に参画していく物語みたいな瞬間を、垣間見ることがあったりする。
高齢者介護の領域を見て、相対的に難しいなと思うのは、とくに認知症の領域で顕著ですが、自分が非常に親しんできて、ある意味では権威性のようなもの感じていた「親」という存在が、どんどんできなくなることが増え、状態は落ちていくように見える。
落ちてゆくにしたがって、介護する側の自分は、やらなきゃいけないこともどんどん増えていく。「親はこうだったはずだ」というイメージから現実がどんどん逸脱していくのですが、その急速な変化に子どもがついていけなくなるときがある。「こんなはずじゃない」と、自分の親をゆるせなくなるような瞬間があるんです。誤解をおそれず言えば、必ずしもお子さんがその親御さんのよき代弁者だとは限らない。
葉真中 尊重しなきゃいけない自由意思みたいなモノが、認知症になるとほとんど見えなくなってしまうと私は思うんだけれども、そのときに相手の気持ちを忖度するのはどういうことなのかと。これを考え始めると、本当は私と父、私と祖父、私と相手の話のはずが、いつの間にか私と私の話になっていく。これは許されるだろうとか、いや、これは許されないからやっちゃダメだとか、どこかでスポーンと被介護者が抜け落ちる関係になる。これって、高齢者介護でとくに認知症を伴うような状況だと不可避になりやすい気がしています。こうなると本人の気持ちがよくわからなくなって、倫理的に溶けちゃう感じがある。
大野 わかります。溶けちゃうんですよね。
葉真中 この溶けちゃう感じを書きたいというのは、小説としてはありつつも、いや、溶かしていいのかよという気持ちもある。そこは自分でも考えたいし、読者にも問いたい。この先、われわれ日本人は本当に真剣勝負で考えていかないといけないことだと思う。そういう問題意識はあるんです。
最後の砦を、どう支えるか?
大野 『ロスト・ケア』の中に、聖書の引用で「自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい」というフレーズがたびたび出てきますよね。みんなが「どうしたらいいかわからない!」という状況の中で、そのときどきにこの黄金律をばっと思い出して、なんとか座標軸というのか、狂気と正気のぎりぎりの境をふっとつかむような場面だと思いました。
葉真中 はいはい。
大野 人口の比率として高齢人口はこれからさらに増えていきます。往々にして、「高齢者は金持ち」で「高齢者ケアはお金がかかって」……と言われます。それについてはわたしは非常に懐疑的ですが、その議論はまた別の機会にするとして。ともかく、介護保険や介護報酬を抑制したときに一番つらいのって、そこで働いている若年のワーカーの人たちなんですよね。
葉真中 そうですよね。
大野 人間の尊厳を支える最後の砦で働く人たちに、社会がちゃんとお金を出さなきゃいけないという意識が非常に希薄です。税やシステムでその人たちの労働をちゃんと支えなきゃいけないという合意が、いまだ持てていないんじゃないかなと感じるときがあります。
葉真中 ヘルパーさんの労働環境については、私も実際サービスを利用したときに愚痴っぽく聞いた限りですが、「お、これはブラック企業ではないか」という感触を持ちました。世の中には厳しい労働条件の職業は五万とありますけど、でも、これだけ必要だ必要だと言われて、国もいろんな仕組みだけは設けているわけじゃないですか。
大野 資格要件を整えたりすることは、必要なことですが、そもそも何のためなのか目的を見失っている部分もあります。肝心の財政的な部分はあんまり持ってこないのに、制度をむやみに複雑化・細分化して、ワーカーや事業所の過剰な自助努力を迫るようなことも多いような気もします。「大黒柱が食べていける職にしなければならない」という意識は最近になってようやく持たれ始めたかもしれません。
葉真中 そう。急に介護に関する新しい資格がパーっと出来たりとか。ところが、実際に社会と接続する最後の受け皿のところでこれかよっていう部分があって。大野さんが今まさにおっしゃった日本の保有資産のアンバランスは、俗に「世代間格差」と言われるもので、私は事実として不公平があるなら是正しなきゃいけないと思っています。でも、それがうまく均されて、下の世代にお金が回っていくというかたちにならずに、なぜか現場で働いている人たちの給与が絞られるみたいな矛盾というか、非常にいびつな構造になってしまっているんですよね。
世代論をバックボーンにした小説を自分で書いておいてなんですが、世代間格差があるということを指摘するのは必要なんですけれども、そこで世代間闘争を起こしても何にもならないと思います。
誰だって高齢者になるわけですから、高齢者が生きづらい世の中へと舵をとらせてしまうと、あとあと自分の首が締まることになる。そういう闘争とかバッシングというやり方でないところで、なんとか超えていけないのかなっていうのは考えます。そんな気持ちを持ちながら具体的なアイデアが何ひとつないのがもどかしいですが。
娯楽を通して、世に問う
大野 『ロスト・ケア』は、家族がいれば誰でも「こんなこと」を思うときがやってくるというか、きわめて鋭利で人を一気に追い詰める類の感情が、実際に身近になる時代なのだということを、鮮やかに描いている。
葉真中 そこの部分に関しては、ちょっと思うところありまして。うまくまとめて喋れるかわかりませんが……。
これだけ治安のいい国で、人が人を殺すということは誰でも非日常のことだと思って生活しているわけですよね。だけど、いわゆる「終末期」と呼ばれる状況においては、殺人と自然死が、ここでも溶けているような気がします。例えばがんになって、いわゆる「要介護状態」を経ない場合にも、やっぱり最後は溶けるような気が私はしている。
『ロスト・ケア』の中でも、主人公の父親が最後に胃ろうで延命するかどうかという話が出てくるんですけれども、現代医学で、わりとしっかりした病院がその気になると、どこで終わりにするかというのは意図的に決定できてしまうところがある。無限に伸ばすことはもちろんできないけれども、「少しでも長く」とか、「なるべく楽に」とかいろんな言葉があって、その言葉に従って、事実としての「死」が生まれる。
病院で死ぬということの中には、どこかに意図的に殺している瞬間が、私は訪れていると思う。ほとんどの家族は、選択をしているつもりはなくても、選択をしているのだと。私の祖母はがんで亡くなったのですが、その治療は、こんなにシステマチックなの? と感心してしまうくらいパッケージングされていました。「インフォームドコンセント」などといって、医者から家族に治療方針の確認があって、最後の迎え方という部分を説明されてそれに同意した瞬間に、じつは殺し方の選択をしていたんだと思うんです。
もちろん刃物でぶすっとやるのと、最後まで医療に委ねて死を迎えさせることはまったく違うことです。だけど、「人を殺す」ということを他人の寿命をコントロールすることだと考えると、その違いは程度問題ともいえる。
尊厳死や安楽死の問題も含めて、そこに私たちが普段考えないようにしている「倫理の溶ける瞬間」が誰にでもあるというふうに思っています。そういう部分をあえて象徴的に、小説というかたちで、誰にでも起こりうる「if」として提示するっていうのは、ひとつのやってみたい試みでした。誤解を恐れずに言ってしまえば、娯楽になると思っている。それは読む価値のあるものだと。そういう部分は自覚的に書いたかなと思うんですよね。
大野 こんな言い方をしていいのかわからないですけど、「文学的」ですね。
葉真中 何が「文学」かというのは非常に面倒くさい話で私もよくわかってないのですが(笑)、仮に小説に娯楽として楽しませる部分と、読者に考えさせる部分の二つの要素があるとして、とくに考えさせる方には、今回力を入れました。ちょっといやらしいですけど、そういうところがうまく娯楽と結びついた小説というのは、世に出る、世に出す価値があると私は考えているので。
大野 葉真中さん、見た目はほわんとしているけど、すごく熱いハートを持ってますね……!
プロフィール

大野更紗
専攻は医療社会学。難病の医療政策、

葉真中顕
1976年東京生まれ。2009年児童向け小説「ライバル」で角川学芸児童文学優秀賞受賞。コミックのシナリオなどを手がけながら、本作品でミステリー作家としてデビュー。