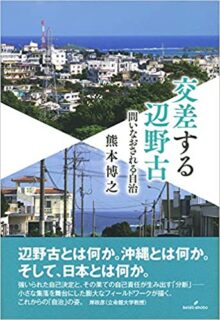2021.03.18
現代日本社会を読み解くための「報奨金化」というツール――『交差する辺野古 問いなおされる自治』(勁草書房)
意外な共通点
日本学術会議の会員任命見送り、秋田県へのイージス・アショア配備、そして普天間基地の名護市辺野古への移設。これらの問題には、当事者側が強く反発する一方で、世間一般の人たちの反応は鈍く、むしろ政府の方針を支持する人たちも少なくないという共通点がある。このうち、イージス・アショアの配備については、安全面での問題もあって白紙撤回となったが、残る2つは見直されることのないまま今に至っている。
なぜ当事者側の反発が世論を喚起できずにいるのか。それを、社会の報奨金化という観点から考察していきたい。
「報奨金化した社会」
報奨とは、ある人の功労や善行などに報い、それをさらに奨励することである。そして奨励は主にお金によってなされる。これが報奨金だ。つまりはインセンティブである。
ここでのポイントは、何が功労で、何が善行に当たるのかを決めるのは、報奨金を出す側だということである。そのため、報奨金をもらうためには出す側の意向に沿わなければならない。つまり報奨金は、人々を自発的に意向に沿わせることのできる、便利なツールなのである。
報奨金が一般の企業や学校で、社員や学生へのインセンティブとして用いられる分には、さほど問題にはならない。例えば私が勤めている明星大学には資格取得奨励奨学金制度があり、行政書士など指定された資格をとった学生に、重要度や難易度に応じた報奨金が出ることになっている。学生は資格を取得した上に「ご褒美」までもらえるし、大学は資格を取得する学生の増加による大学の評価向上を見込める。Win-Winである。
だが報奨金にはもう1つ、大事な側面がある。それは、「功労」や「善行」を為そうとしない者には、一円たりとももたらされないということだ。それは報奨金である限り、当たり前のことである。
だが、誰かからもらうお金が、すべて報奨金のような特徴を持つようになれば、話は変わってくる。なぜなら、お金をもらうことで、お金を出す側への貢献を義務づけられてしまい、しかも貢献ができないものはお金をもらうことができなくなってしまうからだ。これが「当たり前」になった社会のことを、「報奨金化した社会」と名付けよう。この報奨金化が、日本社会で近年、急速に高まっている。
なぜ日本学術会議任命拒否問題は内閣支持率を下げないのか
2020年9月に発足した菅政権が最初に強い批判を受けたのが、日本学術会議が推薦した会員名簿に載っていた、政権に批判的な見解を持つ6名の学者を首相が任命しなかった、任命拒否問題である。野党はもちろん、多くの学者が反発し、約500の学協会が抗議声明を発表するなど世論を大きく賑わせた。だが11月7日に毎日新聞が実施した世論調査では、任命拒否を「問題とは思わない」が44%を占め、「問題だ」とこたえた37%より多かった。そして内閣支持率も、発足直後から7ポイント下落したとはいえ57%の高水準を保っていた(『毎日新聞』2020年11月8日)。
こうした結果になった背景の1つと考えられるのが、日本学術会議に年間10億円の予算が投入されていることである。このことが報道されたことで、世論の趨勢が変わった。お金を出してくれている政府に批判的な学者は任命されなくて当然だという意見が急速に広まっていった。この世論調査では、菅政権が学術会議のあり方について見直しを検討していることについても聞いているが、58%が「適切だ」と答え、「適切ではない」は24%にとどまっている。このような意識が、菅内閣の支持率を支えていた一因なのである。
イージス・アショアの配備に反対した秋田への非難
この報奨金化を許容する世論の高まりは、政府からの再分配にあずかりたければ、それなりの貢献をせよと考える人たちの増加に繋がっている。その証左となっているのが、政府が秋田市に配備しようとしていた陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備計画に反対していた秋田県知事や秋田県民に対する激しい非難である。
佐藤敬久知事が配備に懸念を示したのは、防衛省がずさんな調査データに基づいて秋田を適地だとする報告書を出したこと、住民説明会で東北防衛局の職員が居眠りをして住民の怒りを買ったことなどを受けてのものであった。しかしこれに対して秋田県には、「秋田には原発もなく、日本の何の役に立っているのか」「秋田県は非国民だ」といった批判が殺到した(『毎日新聞』2019年6月24日)。
実際には、イージス・アショアが配備されても交付金が出るわけではない。だが、その誤解だけが秋田への「非国民」という激しい非難に繋がったわけではないだろう。秋田県のような地方の自治体が、再分配を多く受けていることは周知のことである。にもかかわらず国防への貢献を拒否するかのような知事の姿勢が、強く非難されたのだ。「日本の何の役に立っているのか」という声は象徴的である。
このように「報奨金化した社会」では、広く国民から徴収した税金を地方自治体に分配する「財の再分配」に対しても、厳しい目が向けられている。この流れの源流とも言えるのが、沖縄に対する振興事業の報奨金化である。
報奨金化した沖縄への振興事業① 米軍再編交付金
周知の通り、政府と沖縄県は米軍普天間飛行場(以下、普天間基地)の返還をめぐって対立している。1996年4月に日米両政府で合意した際、普天間基地の返還には、沖縄県内に代替施設を建設するという条件がつけられた。その代替施設は、名護市辺野古の沿岸部に建設されることになり、埋め立て工事が進められている。
政府は、この辺野古への建設を「普天間基地の危険性を除去するための唯一の選択肢」だとし、沖縄の基地負担の軽減につながると主張している。これに対して沖縄県は、辺野古に造られようとしている基地は恒久的に使用され続ける機能強化された新たな米軍基地であって、基地負担の軽減どころかむしろ強化であるとし、建設に反対している。
筆者はこの問題について、辺野古集落の住民の視点を重視しながら、10数年にわたる調査を続けている。その成果が2月に『交差する辺野古-問いなおされる自治』(勁草書房)として出版された。ここでは同書でも検討した、政府による沖縄への報奨金化した振興事業について記述していく。
さて、この問題の当初、政府は沖縄側の理解を得るために、補償金的な振興事業を沖縄に投下してきた。しかし次第に政府は、普天間代替施設/辺野古新基地の受け入れと振興事業の交付を結びつけるようになる。その象徴が米軍再編交付金である。
米軍再編交付金は、2007年4月に制定された米軍再編推進特措法に基づいて交付される交付金である。米軍再編計画への協力度に応じて地方自治体に交付されるこの交付金は、協力しようとしない自治体への交付はなされない「報奨金化した振興事業」である。
2005年10月に日米で合意された在日米軍再編の中間報告「日米同盟─未来のための変革と再編」に普天間基地の移設計画が明記されたことで、辺野古を抱えている名護市は、同交付金の交付対象自治体となった。これが名護市を翻弄していく。
制定当時、名護市の市長は辺野古への移設を容認していたため、名護市には(紆余曲折はあったのだが)米軍再編交付金が交付された。だが2010年1月に反対派の稲嶺進が市長に当選すると交付は停止し、2018年2月に事実上の容認派である渡具知武豊が市長に当選すると交付が再開する。政府は選挙期間中に、渡具知候補が当選すれば交付を再開する方針を示しており、それが渡具知市長の誕生の一因となっていたことは明らかである。
報奨金化した沖縄への振興事業② 沖縄関係予算
次に政府が手を出したのは、沖縄関係予算である。1972年5月15日、沖縄が日本に「復帰」したその日に施行された「沖縄振興開発特別措置法」(沖振法)を根拠法とする沖縄振興予算は、各省庁の直轄事業や補助事業など、他の都道府県ももらっている事業費を一括して計上したもの、つまり通常の再分配といっていい予算である。
この沖縄関係予算が2014年度、大幅に増加する。前年度から459億円増の3460億円が計上されたのだ。その背景には、政府が沖縄県に、建設予定海域の埋め立てを承認するよう申請していたことがある。大幅増が約されたのは、安倍晋三首相と仲井眞弘多県知事(いずれも当時)との会談がなされた2013年12月25日である。その2日後、仲井眞知事は、政府が申請していた辺野古沿岸域の埋め立てを承認する。増加した459億円は、沖縄の国策への貢献に対して支払われた報奨金だったのである。
そして報奨金である以上、貢献を拒否すると交付もなされなくなる。2014年11月、辺野古移設に反対する翁長雄志が仲井眞を破って沖縄県知事に当選すると、沖縄関係予算は一転して減額され、2018年度以降は3010億円で固定となっている。しかも2019年度からは、予算額のなかに、市町村に政府が直接交付することのできる「沖縄振興特定事業推進費」が組み込まれており、政府は意向に沿う市町村への恣意的な交付ができるようになっている。これもまた報奨金化した振興事業だといえよう。
このように政府は、通常の再分配というべき沖縄関係予算をも、報奨金的に交付するようになった。これは予算措置を通した沖縄の自治への介入である。2018年8月に逝去した翁長前知事の遺志を継ぎ、辺野古への基地建設反対を公約に掲げて当選した玉城デニー知事は、今も反対の立場を取り続けているが、知事の任期が終わる2022年は、沖振法の5回目の更新を迎える年でもある。更新に向けた議論は2021年度中になされるだろうが、政府が「更新しない」という選択肢も含めた交渉を進め、圧力をかけてくるであろうことは想像に難くない。
また沖縄県内では、2019年6月の八重瀬町議会を嚆矢として、4つの市町の議会が、普天間基地の辺野古移設を促進する意見書を可決している。その背景に、県は政府と対立しているけれども、自分たちはそうではないことを政府に向けてアピールしたいという意識があることは明らかだ。
辺野古住民のあきらめ
政府によるこのような沖縄の自治への介入による影響をもっとも強く受けているのが辺野古に住む人たちである。移設計画が立ち上がった当初、辺野古住民の多数派は移設に反対していた。だが次第に補償金や振興事業と引き換えに受け入れてもいいのではと考える容認派の住民が主流になっていく。そして「最低でも県外」に普天間基地を移設すると公言していた民主党鳩山政権が県外移設を断念した2010年5月、辺野古は条件つきで普天間代替施設の建設を受け入れることを決定した。
だが辺野古の住民の本音は「来ないに越したことはない」である。しかも2018年には個別の補償金を出すことはできないとの通達が防衛省から出されており、建設されても得るものはほとんどない。それでも辺野古は、集落の意思として「反対」を掲げることなく、政府との交渉を進めている。それは、反対しても止められないという諦めがあるからだ。
30代の男性住民は「父がウミンチュだからはじめは抵抗があった。でも国が『辺野古が唯一』といっている以上しょうがない。本音としては、できるかできないか、はやくどっちかにしてほしい。できないとは思っていないけど。どうせできるんだから、だったら早くつくれって思っている」と語ってくれた。海が埋め立てられるのは嫌だけれど、政府は絶対につくるといっている以上「しょうがない」。そして辺野古は、この問題に20年以上振り回されている。この現状にうんざりしているのである。
報奨金化した日本社会の行く末
政府が報奨金的に予算を使うことで意向通りに政策を遂行し、その政府を世論の多数派が支える。これが報奨金化した日本社会の現状である。沖縄に対してなされている振興事業の報奨金化は、ここまで日本社会を変えてきた。
このような社会で負担が集中するのは周辺部である。北海道の寿都町と神恵内村が高レベル放射性廃棄物最終処分場の文献調査に手を挙げたのは、迷惑施設を受け入れることで「貢献」を示し、再分配にあずかろうという思いからであろう。だが、生命の危険と引き換えにもたらされるお金は、もはやインセンティブではなく、補償金や賠償金というべきものだ。にもかかわらずインセンティブの顔をした再分配がなされることで、迷惑施設の受け入れは、受け入れた側の主体的な判断によって実現したことにされてしまう。
だから世論は政府を非難する方向には向かわない。政府にとって、これほど都合の良い国民もないだろう。政策によって一部の人たちが犠牲になることを国民が肯定しているのだから。
だが、このような社会では、いつ自分が「一部の人たち」の側にまわることになるのか、誰も予測できない。しかも犠牲者になったとしても、社会は助けてくれない。自業自得だとされ、自己責任だとして処理されてしまうからだ。
この「報奨金化した社会」では、誰もが不安を抱えながら生きていかなければならない。そして不安を直視したくない人たちは、自分たちがマジョリティ側に属しているという実感を持つことで、安心を得ようとする。それは時に、マイノリティへの非難や排除へと接続していく。だがそうやって得られるのは、束の間の安心でしかなく、こころからの安心感は得られない。
だから、本当に安心して暮らすことのできる社会をつくるためには、まずこの「報奨金化した社会」の論理を排し、否定していかなければならない。それは、「誰一人取り残さない」インクルーシブな社会を実現するための、とても大事な一歩なのである。
プロフィール
熊本博之
1975年生まれ。明星大学人文学部教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻修了。博士(文学)。専門は地域社会学、環境社会学。
著書に『交差する辺野古-問いなおされる自治』(勁草書房、2021年)。共著に『米軍基地文化』(新曜社、2014年)、『共生の社会学』(太郎次郎社エディタス、2016年)など。