2018.05.14
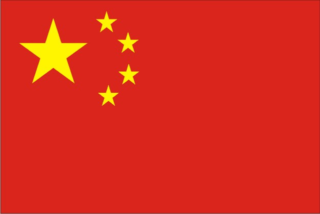
歴史のなかの日中関係――清末から現代までの120年間の歴史を振り返る
西洋列強や日本に蚕食されてきた19世紀半ばから、「恥辱」を受ける以前の「輝かしい過去」への回帰を目指してきた中国。そしていま、大国となった中国は「中華民族の偉大なる復興」を掲げている。『中国ナショナリズム』の著者、小野寺史郎氏に、清末から現代までの120年間の歴史を振り返っていただいた。(聞き手・構成/芹沢一也)
「中華」と西洋文明
――最初に、伝統的な中国王朝について教えてください。「中華」とはどう理解すればよいのでしょうか?
私が本来専門とする時代は19世紀末から戦前辺りまでなのですが、昨年出版した『中国ナショナリズム』で一番批判をいただいたのが、序章の「伝統中国の世界観」に関する説明でした。「伝統」と一口に言っても、実際には当然ながら、時代ごとに世界観も変化してきました。それをごく簡単にまとめると次のようになります。
儒教が国教となった漢の頃から、有徳の天子(皇帝)が「天の命」によって天下の統治を委ねられた、というのが統治を正当化するロジックとなります。そこで皇帝が実際に官吏を派遣して統治する範囲が「中華」、その外部が「夷狄」とみなされました。
ただ、この「中華」と「夷狄」の境界は、現実の政治状況の影響を受けるかなり曖昧・可変的なものです。ですので、ある政権が「中華」とみなされる条件としても、漢人のエスニック的な要素が強調される時代、あるいはエスニック的な出身にかかわりなく、儒教に代表される「文明」の受容度合いが重視される時代など、さまざまでした。
――「中華」の境界と内実は、近代的な国境によって画されるわけでも、また主権や国民のようなユニットによって実体化されているわけでもないということですね。
そうです。こうした世界観の下では、対外関係も、主権国家間の対等を前提とする近代西洋の国際関係とは異なるものでした。近隣の諸外国が中華の皇帝に使節を送り、臣従を示す儀礼を行うというもので、これが「朝貢」と呼ばれます。この朝貢によって、皇帝は自らの徳の高さを証明することができた。また諸外国の側も、中華との関係を安定させることができた。そうすることで、ともに統治の正当性を得ることができたわけです。
ただ臣従と言っても、これはあくまで形式上のものです。国家間関係を君臣関係に見立てたフィクションという面が強かったと言えます。また、中華の王朝と関係をもった国や地域がすべて朝貢の形式をとったわけではありません。たとえば、朝貢を伴わない貿易もあり、これは「互市」と呼ばれました。このように、中華の王朝と諸外国との関係にはさまざまな形式があり、まとまった一つの体制やシステムとして説明するのは難しいと言えます。
また、モンゴル人の元や満洲人の清をどのように理解するかも、非常に難しい問題です。現在では、これらの国は中央アジアの遊牧国家としての性格を強く持ち、いわゆる中華の王朝の原理では説明できないのではないか、という議論がなされています。
――アヘン戦争から義和団事件に至る事件を経験した清朝中国にとって、西洋文明とはいかなる意味をもったのでしょうか?
非常に大きくて難しい問題です。ただ、現在の歴史研究者のほとんどは、アヘン戦争(1840-1842年)によって清の体制や社会に何か大きな変化が起こり、中国の前近代と近代を画す契機となった、とは考えておりません。
また、かつては第二次アヘン戦争(1856-1860年)後に「洋務運動」(西洋の科学技術を導入して清の国力増強を目指す運動)が開始されたものの、体制は変えず西洋の技術のみを輸入するという「中体西用」思想のために失敗に終わった、という説明がなされていたのですが、こちらも現在では否定されています。
実際、かなり早い段階から議会など、西洋の政治制度の有用性を認識していた知識人もいましたし、受け手の置かれた状況や立場によって、西洋に対する理解や反応にはかなりの多様性があったようです。
――となると、何が中国が前近代から近代へと移行する契機となったのでしょうか?
この問題に関して一つの契機となったのは、1900年の義和団事件ではないかと考えています。西洋的な事物の排除を訴える宗教結社義和団が、既存の社会秩序や文化的慣習に帰属意識をもつ民衆の支持を得て勢力を拡大しました。列強がその取り締まりを要求すると、清政府はこれに反発して列強に宣戦しますが、8か国連合軍に大敗を喫しました。
これによって清政府と知識人層は、最終的に西洋に倣った近代化政策に転じます。しかしそれは民衆の世界観や伝統的習俗を置き去りにすることでもありました。そのためこれ以後長期にわたり、政府や知識人と民衆のあいだに乖離を生じる一因となったと考えています。
「中華民族」の起源
――清朝中国は多民族で構成され、近代的な国境観念もなかったなかで、どのようにしてネイションを構築していったのでしょうか?
1898年にドイツ、イギリス、ロシア、フランスが相継いで清国内に租借地(ある国が条約で一定期間、他国に貸し与えた土地のこと)を設けました。そして、租借地周辺の鉄道敷設権・鉱山開発権などを獲得して、そこを「勢力圏」と見なすようになります。
この勢力圏はそれ自体としては非常に曖昧なものだったのですが、列強の勢力圏に塗り分けられた清の地図が印刷メディアを通じて広まったことで、清が列強に分割されるという危機感が広まりました。
ここから逆説的に、元来はさまざまなエスニック集団や統治方式から成り立っていた清の領域を、一様かつ一体不可分の「領土」と見なす認識が生まれたという指摘がなされています。
――西洋列強に浸食されるというネガティブな経験を媒介に、一体のものとしての「領土」という観念が浮かび上がってくるんですね。そこからナショナリズムが生まれてくるのですか?
ナショナリズムの訳語である「民族主義」が、日本から中国に紹介されたのはその後になります。ただ、清の領域がさまざまなエスニック集団からなるものだったこと、清の統治者が人口で大多数を占める漢人ではなく、少数者の満洲人だったことから、深刻な問題が生じました。
孫文(注1)ら革命派は当初、清を打倒して漢人国家を建設することを主張しました。しかしその場合、清の領域のうち、漢人以外の満洲人、モンゴル人、チベット人、回民(テュルク系ムスリム)などが居住する地域はどうなるのかが問題となります。
(注1)1866~1925年。中国の政治家。反清武装蜂起の失敗後、亡命先の日本で中国同盟会を組織。辛亥革命に際して帰国し、中華民国臨時政府の臨時大総統に就任したが、直後に軍事実力者の袁世凱に政権を譲った。後、政権奪取を目指して広州に政府を組織し、中国国民党を結成。ソ連・中国共産党との提携方針を定めた。
そこで同じ漢人でも梁啓超(注2)ら立憲派は、先に述べた「領土」を前提として、その内部の複数のエスニック集団を融合し、一つのネイションにするという主張を行います。これが現在の中華人民共和国が主張する「中華民族」の考えの始まりです。
(注2)1873~1929年。中国の啓蒙思想家、ジャーナリスト、政治家。戊戌変法失敗後、亡命先の日本で雑誌『清議報』や『新民叢報』を出版。日本経由で得た西洋の知識を平易な文章で大量に紹介するとともに、清の立憲君主制改革を唱え、革命派機関誌『民報』と論争を展開した。
ただ問題は、こうした議論がほぼ漢人内部で行われたことです。モンゴル人、チベット人、回民などには共有されていませんでした。「外モンゴル」が1920年代に中国から独立して独自のネイション・ステイトを形成し、またチベットや「内モンゴル」、新疆などで、現在に至るまで、ネイションの範囲に関して中国政府と異なる認識が存在するのはそのためです。
中国ナショナリズムと日本
――中国ナショナリズムにおける日本の位置づけはどのようなものだったのでしょうか?
清末のナショナリズムにもとづく運動には、東三省(現在の中国東北部)に駐兵を続けたロシアに抗議する1903年の拒俄運動(俄はロシアの意味)、アメリカの排華移民法に反対する1905年の米製品ボイコット、1908年の第二辰丸事件(清政府が武器密輸の疑いで日本船籍の商船を拿捕したが、日本政府が謝罪と賠償を要求した)に反発して開かれた「国恥記念会」などがあります。そのため日本はあくまで清に利権を求める列強のうちの一つという位置づけでした。
一方、日清戦争の敗北以降、清では日本を近代化のモデルとする考えが生まれ、多くの留学生が来日し、日本を通じて西洋の知識を学ぼうとしました。そのためこの時期の人々にとって、韓国併合などに対する警戒感をもちつつも、日本には相対的に親近感を覚える部分もあったのではないかと思います。
――それが第一次大戦後の二十一か条要求によって変わるわけですね。
はい。それまで対中政策において、日本は他の列強との協調を重視してきました。ところが、第一次世界大戦で他の列強が東アジアに関与する余裕を失うなか、二十一か条要求によって単独で在華利権の拡大を図ろうとします。そのため中国側からは、日本は数ある列強の一つから、突出した「主要敵」と見なされるようになります。
その後に成立した段祺瑞(注3)政権に対し、日本が西原借款に代表される援助を行ったことも反発を生みました。1918年に日中共同防敵軍事協定が結ばれると、これに抗議して日本にいた多くの中国人留学生が帰国するという事件も起きています。
(注3)1865~1936年。中国の軍人・政治家。安徽派の領袖。袁世凱の死後、北京政府の実権を握る。日本の寺内正毅内閣の援助を受け、第一次世界大戦に参戦。1920年、直隷派との内戦に敗れ勢力を失った。
ただ、これ以後、日中関係がつねに悪化し続けたというわけではありません。とくに1920年代半ばには、対中不干渉・対英米協調を旨とする幣原外交の下で、中国の対日感情は相対的安定の時期を迎えます。1925年には空前のナショナリズム運動である五三〇運動が起きますが、その「主要敵」は日本よりイギリスでした。
こうした状況を大きく変えたのが1928年の済南事件です。
北京政府の打倒と中国統一を目指す、蒋介石(注4)率いる国民革命軍の北伐が進行すると、東三省利権への影響が及ぶことを危惧した田中義一内閣は第二次山東出兵を行います。そして、山東省の省都の済南で日本軍と国民革命軍の軍事衝突が起こりました。市民を含む多数の犠牲者が出たことで、ふたたび日本が中国ナショナリズムにとっての「主要敵」と位置づけられることになったのです。
(注4)1887~1975年。中国の軍人、政治家。国共合作の下で組織された国民革命軍の総司令に就任、中国統一を目指す北伐を実施。孫文の死後、実権を握り、クーデターで共産党を排除。南京国民政府を樹立した。最高指導者として対日抗戦を完遂したが、中国共産党との内戦に敗れ、中華民国を台湾に移転して存続させた。
――1930年代には、いわゆる「国恥図」が作成されています。
中国の学校の地理教科書などでは、1910年代から「失われた領域」を記した地図が掲載されています。ロシア領となった沿海州や中央アジア、かつて朝貢国だった朝鮮・琉球や、インドシナ半島、マレー半島、日清戦争で日本に割譲した台湾などです。
これは、先にお話ししたように、中国の領土認識自体が、列強に分割されるという危機感のなかで形成されたことに関わっています。とくに1931年の満洲事変以後、奪われた領土を回復するという意識は非常に強く表われるようになります。
ただし、このように現行領土を越えた範囲を「本来の領土」とみなす主張は中国にかぎったことではありません。たとえば同時期のタイなどでも、同様の「国恥図」が作成されていたことが知られます。
「二分論」と日中国交正常化
――戦後日中関係について伺っていきたいと思います。出発点として「以徳報怨」演説について教えていただけますか。
「以徳報怨」演説と呼ばれるものは、1945年8月15日に蔣介石が行ったラジオ演説です。翌日の新聞などにも掲載されました。後に翻訳されて日本にも紹介されています。
「以徳報怨」(徳をもって怨みに報いる)という言葉は、原文では使用していません。「もし暴行をもって敵の従前の暴行に答え、侮辱をもって彼らの従前の誤った優越感に答えるなら、互いに怨みに報いることが永遠に終わらない」といった内容になっています。「以徳報怨」という表現は、戦後の自民党内の親台(親国民党)派などが用いたもののようです。
――蒋介石は「以徳報怨」演説をするだけでなく、日本への賠償請求も放棄しています。
1951年に日本と連合国の講和会議が開かれ、対日講和条約が締結されます。ここで日本の賠償義務は免除されたのですが、例外規定があり、中国は賠償請求権を保留されました。ただよく知られるように、この会議には中華民国・中華人民共和国はともに招請されていません。日本はアメリカの影響の下、双方のうち中華民国との講和交渉を選びます。
しかし、中国国民党が政権を握る当時の中華民国は、中国共産党との内戦に敗れてほぼ台湾のみを実効支配するという非常に弱い立場に陥っていました。そのため当初は賠償請求を準備していた中華民国も、最終的にはサンフランシスコ講和条約に準じた賠償請求権放棄を受け入れ、日華平和条約が締結されました。
――中華人民共和国のスタンスはどうだったのでしょうか?
中国共産党が1949年に樹立した中華人民共和国は、サンフランシスコ講和条約・日華平和条約をともに認めず、強い抗議を行いました。
しかし一方で、アメリカや、台湾の中華民国と対峙する中華人民共和国は、日本への働きかけを重視しました。また、当時の日本にも、中国市場への期待が存在しました。そこで中国がとったのが、蔣介石と同じく、日本の中国侵略の原因は一部の軍国主義者にあり、一般国民にはないとする「二分論」でした。
中国政府はこれにもとづき、アメリカ・台湾と関係を結ぶ日本政府を批判しつつ、1952年に第一次日中民間貿易協定を締結しました。民間ベースの交流を徐々に拡大することで、政府間交渉に結びつけようとしたのです。
しかし日本政府が「政経分離」の立場を維持したこと、岸信介内閣の対米・対台政策に対する中国政府の反発があったことなどから、1958年の長崎国旗事件(長崎のデパートで開催されていた中国商品展示会場で、右翼青年が中華人民共和国国旗を引き下ろした事件)を契機にこの方式は頓挫しています。
――1972年の日中国交正常化交渉でも、中国は日本に妥協したと言われますね。
日中国交正常化に際し、日本政府にはいくつかの懸念がありました。日華平和条約との法的な整合性、とくに戦争状態の終了や賠償請求権の問題などです。
日本政府は「中国」との戦争は日華平和条約で終了しているという立場でした。そこで日中共同声明では、「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」が終了した、という表現が使われています。
賠償についても、中国側が賠償請求権を放棄すると表明しました。さらに、日本政府側が日華平和条約ですでに「賠償請求権」は放棄されているとの立場であったため、「賠償請求」を放棄したという表現になっています。日華平和条約についても日中共同声明では触れず、大平正芳外相が「存在意義を失い、終了したものと認められる」との見解を表明するかたちで処理されました。
交渉に際し中国側が一定の妥協を行っていることはたしかで、その背景には当時の中国にとっての「主要敵」であるソ連に対する警戒がありました。
――「主要敵」とは?
毛沢東時代の中国の外交の基本方針は、「主要敵」に対する統一戦線というものでした。
1960年代の中国は、冷戦下でのアメリカを含む西側諸国との対立に加え、ソ連やインドとの間にも紛争を抱えていました。こうしたなかでソ連を当面の「主要敵」とみなし、アメリカや日本との関係改善を求めたことが、1972年のニクソン訪中、日中国交正常化の原因です。
――このときの妥協が、後に禍根を残すことになるわけですね。
当時の中国社会にはなお日中戦争の記憶が鮮明でした。そのため、田中角栄首相の訪中に先立ち、中国政府は国民に対する説得キャンペーンを行いました。日中国交正常化が中国の国際戦略にとって、いかに有意義であるかが宣伝されたのです。
賠償請求の放棄についても、台湾の中華民国が放棄したのだから、中華人民共和国は同等以上の度量を見せる必要がある、また「二分論」の論理から、日本の一般国民に負担を課すべきではない、といった説明がなされました。賠償放棄について国共の共通点を挙げれば、道義にもとづく決断であることを強調している点でしょうか。
このようにして日中両政府は国交正常化を短期間で実現させました。しかしそれは、国民感情や歴史認識など、日中間のさまざまな困難な争点を解決するのではなく、双方が政治的に棚上げすることによってなされたものでした。また賠償請求の放棄は、日本社会の加害責任に対する認識を曖昧にすることにもつながりました。
以後の「日中友好」ブームの中で、双方の国民間でこれらの争点について議論が深められることなく、相互の認識のすれ違いが放置されたことが、1980年代以降の歴史認識問題の一因と考えられます。
中華民族の偉大なる復興
――80年代になると日中間に大きな摩擦が生じます。
1982年の歴史教科書問題や、1985年の靖国神社参拝問題が起きたことについては、いくつかの要因が指摘されています。
中国共産党は1978年に改革開放政策(注5)を開始し、経済発展を国家目標としました。他方で、西側の思想の流入や、社会に個人主義・自由主義的傾向が広がることを警戒しました。そこで国家統合の核としてナショナリズムが重視されるようになり、その構成要素として日中戦争の歴史が重視されることになりました。
(注5)中国で、1978年から鄧小平を中心として実施された経済政策。文化大革命後の経済を立て直すため、経済特別区の設置、人民公社の解体、海外資本の積極的な導入などが行われ、市場経済への移行が推進された。
また、台湾の国民党政権に対する働きかけの方針が、武力による統一から「和平統一」に転換したことで、日中戦争中の抗日民族統一戦線の歴史が重視されるようになったこともあります。国際的には、経済大国となった日本が政治大国となることへの警戒もあるでしょう。
とはいえ、日本のODAや円借款が中国にとって重要だったこともあり、基本的には1980年代の日中関係は非常に良好でした。日中関係が大きく転換するのは、やはり1990年代以降ではないかと思います。
――90年代の日中関係の転換について教えてください。
1989年の天安門事件が、日中関係に大きな影響を及ぼしました。事件が世界に大きく報道されたことで、日本社会の中国に対する親近感は急激に失われました。一方中国側でも、アメリカをはじめとする西側諸国の経済制裁、民主化への圧力は「和平演変」(非軍事的手段による体制転覆)の企てだとして反発が高まりました。
1996年には台湾で初の総統直接選挙が行われましたが、「台湾独立」を警戒する中国は軍事演習を実施してこれを牽制しました(台湾海峡危機)。この事件も日本社会の「中国脅威論」を高めることになりました。一方で中国側では、1997年に日米安全保障条約の再定義がなされたことで、「周辺事態」に台湾が含まれるのではないかとの警戒が強まりました。
このように、民主化や歴史認識の問題、台湾問題の影響で、1972年の国交正常化以来の日中関係が大きく変容し始めたのが1990年代だったと考えられます。
――天安門事件後、中国政府は「中華民族」という概念を前面に押し出し始めますね。
中華人民共和国で重要だったのは、階級概念にもとづく「人民」で、「民族」と言った場合は「漢族」「満族」「回族」
その一つは、冷戦の終結に伴う世界的なエスニック・ナショナリズムの噴出です。とくにソ連崩壊による中央アジア諸国の独立や、ユーゴスラヴィアの分裂と深刻な民族対立は、中国に強い危機感をもたらしました。実際に1989年の民主化運動の際には、チベットでも独立運動が起こっています。漢族と「少数民族」の上位概念として「中華民族」の一体性が強調されるようになったのはそのためだと考えられます。
――他方で、「列強に虐げられた」過去がふたたび強調されるようになりました。
毛沢東時代には、中国の歴史教科書の重点は「列強に虐げられてきた中国」よりも、「それを克服した中国共産党の偉大な勝利」に置かれていました。
天安門事件後の「愛国主義教育」のなかで、「列強に虐げられてきた」事例が強調されるようになった理由としては、やはり若い世代の西側の思想や事物への憧れを抑制し、警戒感を持たせるということ、また戦争を実際に体験した世代が社会から退場するなかで、それらを学校で歴史と教えなければならなくなったという事情も考えられます。
――そして現在、習近平主席は「中華民族の偉大なる復興」を掲げています。
「国恥図」の説明のなかでも触れましたが、近代以来の中国が、西洋列強から「恥辱」を受ける以前の「輝かしい過去」を想像し、そこへの回帰を目標の一つとして掲げてきたことは確かです。
ただ、やはり申し上げましたように、これはとくに中国に限ったことではなく、不利な状況で近代国家建設を迫られたあらゆる地域に共通する傾向なのではないかと思います。「中華民族」という概念自体が、清末に西洋式の国民国家を構想するなかで初めて生まれたものだったことも、先ほど述べたとおりです。
「中華民族の偉大なる復興」は胡錦濤前国家主席の時代から使用されてきた言葉ですが、表面的な華々しさの一方、それ自体としては内容が非常に曖昧な、如何様にも解釈可能なものです。そのためこの言葉が現在の中国の一般の人々にとってどれだけの意味をもつのかはよくわかりません。
――最後に読者へのメッセージをいただけますか。
現在、書籍にかぎらず、さまざまなメディアに中国に関する情報や議論が溢れています。情報の不足ではなく、むしろ情報の過多のために、中国というものの本来の姿が見えにくくなっているようにも感じます。そうしたなかで本書が、読者の方々が中国の歴史と現在について自分自身の見方をもつための、何らかの道しるべとなることができましたらうれしく思います。
プロフィール

小野寺史郎
1977年、岩手県生まれ。東北大学文学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター助教などを経て、現在、埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授。専門は中国近現代史。著書『国旗・国歌・国慶――ナショナリズムとシンボルの中国近代史』(東京大学出版会、2011年)ほか。


