2012.08.28

発達障害をめぐるQ&A
発達障害という言葉が日本で広まり、発達障害のある人への支援の重要性が認識されつつあります。支援の第一歩として、発達障害について正しい知識を持つことも極めて重要です。そこで今回はQ&A形式で、発達障害について整理してみます。
Q1 発達障害の定義を教えてください。
立場や国によってさまざまですが、2005年に施行された日本の発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害(*1)、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他のこれに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」と発達障害は定義されています。
より具体的には文部科学省・厚生労働省次官通知では、「法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその障害が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(<筆者注>WHO作成の国際的診断基準)における「心理的発達の障害(F80-89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-98)」に含まれる障害であること」と示されています。
(*1)広汎性発達障害の中核症状は以下の3つにまとめられます。1)社会的相互作用の質的異常、2)コミュニケーションの質的異常、3)反復的行動パターンと関心の著しい限局です。自閉症やアスペルガー症候群は広汎性発達障害の一部です。
Q2 ICDって何ですか?
ICDは診断基準ですが、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の略で、第一版は1893年に作成されています。WHOが採択した第六版(ICD-6)から、精神障害が独立した章となっています。ちなみにDSMという診断基準も有名です。こちらは米国精神医学会が作成した「精神疾患に関する診断・統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)」の略で、1952年に初版が作成され、現在はDSM-IV(4)-TRまで作成されています。
2013年を目途にDSM-5が出版される予定です。1992年に出版されたICD-10と1994年に出版されたDSM-IVでは、前者が「アスペルガー症候群」、後者が「アスペルガー障害」の語句を用いるなど、用語面などで差異もありますが、原則的には、それぞれの作成者の意見交換がなされ、両システム間の用語の一致を図り、無意味な相違点を減らす努力がなされたようです(*2)。
(*2)「診断基準の変遷と現状」小野次朗、p17-26、別冊[発達]31 ADHDの理解と援助、2011、ミネルヴァ書房
Q3 発達障害の診断の仕方を教えてください。
ADHD(注意欠如(陥)多動性障害)を例にあげて説明しましょう。前述したDSM-IV-TR(*3)では、個々の事例について医師が問診や把握できている情報、診察所見を踏まえ、基準A~Eを満たすと判断した場合、ADHDの診断が下されます。
基準Aでは、主要症状として不注意に関する9項目、多動性に関する6項目、衝動性に関する3項目が記載されています(*4)。それぞれの項目について医師が「6か月間持続したこと」があり、程度が「不適応的」で「発達の水準に相応しない」か否かを判断します。
不注意項目で6項目以上もしくはかつ多動性と衝動性の項目で6項目以上該当する場合、基準Aを満たすと判断します。基準Bでは、基準Aでみられた症状のいくつかが、7歳以前に存在し、「障害」を引き起こしていること、基準Cでは、症状による障害が複数場面で存在すること、基準Dでは、社会的、学業的、または職業的機能において、臨床的に著しい障害が存在するという証拠があることの判断が求められます。最後の基準Eでは、広汎性発達障害や統合失調症などの他の精神障害が除外されることが規定されています。
基準Cの判断では、たとえば事例が小学生の場合であれば、保護者の問診だけでなく、学校教師や塾講師など周囲の大人からの情報が重要になります。その他に重要なこととして皆さんに認識してほしいのは、基準B、Dに表現されているように、単に症状があるだけでは診断がつかず、症状によって障害が存在し、かつ社会適応上の問題があることが診断にとって必須だということです。
(*3)「DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引」高橋三郎・大野裕・染矢俊幸訳、2002、医学書院
(*4)不注意では「学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをおかす」など、多動性では「しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる」、衝動性では「しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう」などと表現されています。
Q4 診断基準が変わると聞いたのですが。
DSM が2013年を目途にDSM-5という新しいバージョンに変わることですね。DSMは定期的に見直され、修正されています。今回、DSM-5の細部については検討中のようですが、臨床的有用性や改定の根拠としての研究エビデンスなどが重視された改訂になる見込みです。発達障害に関する部分としては、「広汎性発達障害」の下位分類を廃止し、さらには下位分類を集合する上位概念の「広汎性発達障害」という用語が「自閉症スペクトラム障害」に変更される可能性が高いとされます。アスペルガー障害という用語がDSMの診断基準からなくなることになります。
また、ADHDについては、DSM-IV-TRの診断基準Eでは広汎性発達障害を除外することが明記されていましたが、この除外規定が廃止される可能性が高いとされます。したがって、ADHDと広汎性発達障害(DSM-5では自閉症スペクトラム障害?)の重複診断が生じうることになります。両障害の重複を認めてきた専門家も多く、臨床的感覚と診断基準が合致するといえましょう。ちなみに、2003年の文部科学省の「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」では、通常学級に所属するADHDの疑われる子どもの6分の1に広汎性発達障害の合併が疑われると報告されています。
Q5 CTやMRI、脳波検査で診断できないのですか?
発達障害の代表である広汎性発達障害、ADHD、学習障害の診断において、現在CT、MRI、脳波などの生物学的指標は使用されていませんので、CT、MRI、脳波検査は診断に必要不可欠ではありません。実際、現状においてはCT、MRIといった脳の形態が把握できる画像検査、脳神経細胞の電気活動が分かる脳波検査、身体状況が把握できる血液検査や尿検査において、広汎性発達障害、ADHDや学習障害の臨床診断に直結する異常所見はみつかっていません。しかしながら、発達障害と同等の行動特性を示す他の神経疾患(てんかん、脳腫瘍など)もありますので、臨床所見によっては、これらの検査の実施が考慮されます。
Q6 医師から子どもに薬物療法を勧められたのですが、飲ませてもいいのか迷っています。
発達障害の治療・援助では、お子さんの特性にあわせて学校や家庭で環境調整を図り、周囲が適切に関わることが最重要です。視覚的な情報処理が得意な子どもには、視覚情報を積極的に用いたり、刺激に敏感な子どもには教室で前のほうの席に座らせたりします。子どもに対して具体的・簡潔な指導・助言を行い、子どもなりの努力をきちんと評価して、自信を向上させることが周囲には求められます。このような取り組みを周囲が連携して一貫して行う中で、必要に応じて薬物療法が検討されます。つまり、薬物療法は発達障害の治療に必須ではありませんが、症状や状況に応じて医師は薬物療法の使用を考慮するわけです。
現在日本では、ADHDの症状を緩和する薬物は2種類認可され、使用されています。広汎性発達障害については、中核症状そのものに対する薬物は存在しません。不眠などの併発症状に対して薬物療法が考慮されます。薬物療法では、使用する目標・目的を明確にし、定期的に効果を判定し、副作用をきちんとモニターすることが不可欠です。
Q7 薬物療法では「依存」がこわいのですが。
Q6でも述べたように、全般的治療・援助の中に薬物療法を位置づけ、安易に薬物療法を行わないことは当然の姿勢です。しかしながら状況によっては、使用目標・目的を明確にして薬物療法を実施することが有効であることも事実です。
日本のADHD治療薬は、2007年に承認された中枢神経刺激剤の塩酸メチルフェニデート徐放剤、2009年に承認された選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤であるアトモキセチンの2種類があります。それぞれの特徴を生かした薬物治療を医師は行っています。ちなみに前者については、薬効成分が依存性のリスクがあるメチルフェニデートのため、適正流通委員会が設置され、処方医と調剤薬局の管理薬剤師には資格審査と適正使用についての講習への参加が求められています。
なお薬物依存形成には、脳内の報酬系回路が関与していて、メチルフェニデートのような中枢刺激薬による依存のリスクは、線条体におけるドパミン濃度の急激な増加と関連することが実証され、徐放剤のような緩やかに吸収される薬剤では、乱用や依存のリスクが少ないと考えられています(*5)。
(*5)「脳の発達段階と中枢刺激薬依存の関係」友田明美、p134-142、現代のエスプ51「ADHD薬物療法の新時代」、2010、(株)至文堂
Q8 ペアレント・トレーニングという言葉を聞いたことがあるのですが。
子どもの最も身近にいる親御さんが最良の理解者でかつ治療・支援者であるという発想を前提に、病院や支援機関などで実施される、主としてADHDの親御さんのための支援プログラムがペアレント・トレーニングです。徹底した行動観察と行動に応じた対応の技術を親が学び、実践することにより、子どもの適応行動を増やし、不適応行動を減らしていきます。親のストレス軽減効果もあります。
実施機関によりさまざまなやり方がありますが、筆者が2年前に始めたペアレント・トレーニングは計8回のセッションです。小2~小6のADHDの子どもがいる母親3~5人を対象とし、スタッフ2名で月2回のペースで行っています。第1回の「ADHDの誤解と理解」の講義に始まり、「子どもの行動の3つの分類と対応のコツ」「効果的な指示の出し方」「上手な無視の仕方」といったテーマでミニレクチャーやロールプレイ、ホームワークなどを取り混ぜて実施しています。成書としては、岩坂英巳医師らが編集した「AD/HDのペアレント・トレーニング ガイドブック(2004、じほう)」などがあります。
Q9 本人にいつ告げればいいのか迷っています。
周囲と自分の違いなどに悩み、思春期を中心に不安等を感じる発達障害の子どもは少なくありません。発達障害のある人への診断告知はデリケートですが、避けて通ることもできない問題です。吉田によれば(*6)、10%以上の子どもたちは、専門家や保護者が意図しない状況で診断名に気付いてしまうこと、またそのことを周囲に言えずに過ごしている場合もあることを報告しています。
どの年齢でどのように本人に伝えるかについての判断は、本人を良く知るご家族、医師、支援機関のスタッフなどが相談しながら、進めていくのがよいでしょう。ちなみに、診断告知の時期の判断材料として、吉田は、1)やりようがあるという実感、2)長所でもあるという実感、3)一定程度の言語理解力、4)診断の話題を安心して出せる場所があることなどとしています。
(*6)「本人への診断告知」吉田友子、p131-136、精神科治療学23(増刊号)、2008、星和書店
Q10 発達障害と診断され、今後が心配です。
発達障害の支援のキーワードは「連携」と「途切れない支援」です。これまで述べてきたように、発達障害の支援では、本人の特性にあった環境調整が極めて重要です。周囲が一貫して安定した支援を提供できるように、周囲の関係者や関係機関が連携することが大切です。即ち、一つ目のキーワード「連携」です。
さらに、本人の成長に合わせて年代ごとのニーズに合った支援が求められます。これが「途切れない支援」という二つ目のキーワードになります。独立行政法人日本学生支援機構が平成19年5月に行った「大学・短期大学・高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査」の結果では、高等教育機関に在籍する障害のある学生約5,000人のうち医師の診断がある発達障害学生が3%強であったとされるなど、種々の環境で発達障害の特性を持つ人々がいて、その中に支援を要する人々が存在していると思われます。乳幼児、義務教育年齢の子ども、義務教育後の若者、教育修了後の若者……。各世代で提供される支援が途切れずに引き継がれていくことが重要です。
わが国の発達障害の支援は発展途上です。まだまだ不十分な面もあります。しかしながら、地域ごとに様々な取組が芽生えているのも事実です。発達障害のある人とそのご家族のニーズと声を大切にして、このような取組が発展していけば、発達障害のある方にとって、社会がどんどんと暮らしやすいものになっていくに違いありません。
プロフィール
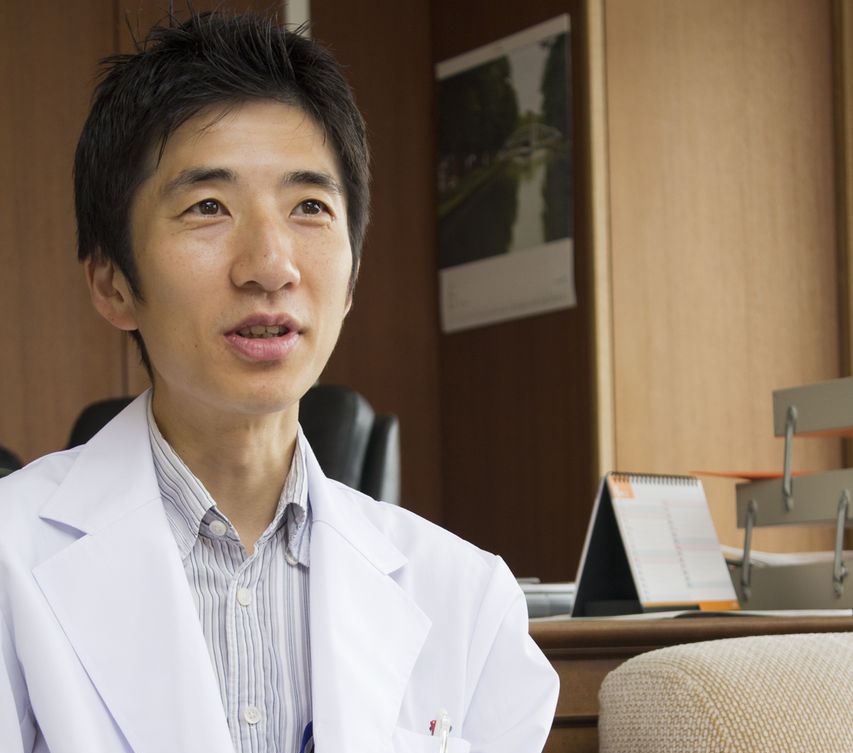
山本朗
1973年大阪府生まれ。和歌山大学保健管理センター准教授(精神科医)。専門は精神医学。効果的なひきこもり支援、動物介在活動の意義、困難を持つ子ども・若者への支援のあり方等をテーマに調査研究を行っている。


