2019.06.26

遙かなる未来を語ること――『予測がつくる社会』
第三千年紀
『2000年から3000年――31世紀からふり返る未来の歴史』は、英国のSF作家とサイエンス・ライターによって書かれた未来史の本である(以下『第三千年紀』、B.ステイブルフォードとD.ラングフォード、中山茂監訳、パーソナルメディア、1987年)。その内容は、タイトルにあるように、31世紀「現在」から、過去千年の科学技術社会史を回想したものである。
原著出版は1985年だが、その未来史は興味深い。国際政治では、オーストラリアが海洋大国になる一方、ブラジルとアルゼンチンが核戦争になり、最終的にブラジルが国連の管理下に入ることになってしまう(先日のテレビインタビューで、歴史人口学者のエマニュエル・トッドが、ブラジルは国家としては実質的に破綻していると発言していた)。他方、ソ連は31世紀まで生き長らえるが(実際のソ連崩壊は1991年)、中国の発展はそれほど強調されていない。日本は、23世紀に打ち続く大地震の連鎖により、領土のかなりが水没し、人口の多数がディアスポラ化するという(小松左京『日本沈没』の出版は1973年、ハリウッド映画版は1975年だから、その影響があるのかもしれない)。
だが国際政治についての歴史記述に加え、なんといっても『第三千年紀』でより印象に残るのは、科学技術の進歩と、それに伴う社会の変容である。たとえば23世紀に人体凍結技術が流行するが、停電による凍結中断や技術の未成熟で、結局失敗に終わる。他方、24世紀に開発が始まった核酸再生の技術で、寿命を飛躍的に延ばすことが可能になり、それは31世紀の今にも大きな影響を与えている、等々。
過去と未来
この「歴史記述」は結構リアルであるが、何か妙な印象ものこる。普通われわれが過去を回想する場合、自分がいる時点に近い過去の記述は詳細になり、遠い過去のそれはまばらになる。歴史年表では、現代史は月、日単位で事件の記述があるが、石器時代の歴史記述は万年単位である。歴史を実態視したサルトルに対して、レヴィ=ストロースが『野生の思考』の終章で「歴史記述は記号の体系」だと論争を吹っ掛けたのはこの事実による。その点からいうと、『第三千年紀』は31世紀からではなく、実際の執筆時を中心に歴史が記述されているという印象が拭えないのである。
実際第三千年紀が近づくにつれ、歴史記述は間延びし、個別の事件はより悠久の歴史的潮流にとって代わられる。もちろん、「文学作品」としてみると、その読後感は悪くない。31世紀に近づくにつれ、李白、杜甫といった漢詩の名作でも読んでいるような、茫洋たる感覚に襲われるからである。しかしそれは第三千年紀から歴史を展望したという設定とは食い違ってしまう。
予測がつくる社会
この『第三千年紀』の語り方、つまり本が刊行された1985年以前に予測したものを、ひとつの歴史的な事実として語ることというスタイルには、より深い含意がある。これが近年の科学技術社会学のテーマと密接に関わるからである。
『予測がつくる社会――「科学の言葉」の使われかた』(山口富子・福島真人編、東京大学出版会、2019年)というわれわれの論集の基本的な前提は、新しい科学やテクノロジーの成長には、未来を語る多様な予測の言説の働きが欠かせない、という点である。こうした期待の言説を含めて、未来についての語りは、人口、経済、技術動向等、社会のあらゆるところに繁茂している。
昨今AIの能力が人間のそれを超えるのは2045年ごろという「予測」が世間を賑わせているが、その学問的根拠についてはそれほど詳細には論じられていない。こうした予測の言説が広まるにつれ、社会のさまざまな部分がそれに反応して動きはじめ、結果としてその動きそのものが最初の予測そのものの実現に(部分的にせよ)加担する、それがこうした予測の力のひとつである。
こうした予測言説の中で、特に科学社会学で熱心に研究されているテーマのひとつに、「期待」の働きがある。期待とは、新たなプロジェクトが作り出す未来についての肯定的な見取り図である。期待は、「この技術によってこんなことが可能になる」という夢の言葉によって関係者を刺激し、その結果多くの人が共感すれば、期待は膨れあがり、プロジェクトの推進力になる。他方、現実は期待を下回ることが多いので、期待はすぼみ、「失望」に取って代わる。この複雑なメカニズムが科学技術の未来に大きな影響を与えるのである。
予測や期待が示す、複雑な働きを比較研究する立場からみると、『第三千年紀』はまさに絶好の事例である。「監訳者あとがき」にもあるように、この「歴史記述」は、技術予測でよく使われるデルファイ法といった方法と、SF的空想を組み合わせたものらしい。それゆえ、特に科学技術の歴史記述は非常にリアルに感じさせる一方、前述したソ連邦のケースのように、すでに現実の歴史との乖離があきらかな例も少なくない。前提である「第三千年紀からの回顧」という前提そのものが、ある意味予測言説の決定論的な雰囲気を示唆しているが、予測言説が現実の歴史から逸脱していく様子も同時に観察できるのが興味深いのである。
建築というメタファー
『第三千年紀』のトピックの中で最も印象的だったのは、新たな建築様式の誕生である。21世紀後半に、アメリカ人のレオン・ガンツが、バイオテクノロジーを 応⽤して考案した接着剤の技術は、コンクリートの代わりに、さまざまな有機物の使用を可能にした。これがガンツの「セメンテーション工法」、あるいは略して「ガンツ工法」とよばれる革命的な工法である。この技術を使うと、窓や戸の部分以外は土と草木に覆われたような、土塁か古墳のような建物をつくることが可能になる。

「ガンツ工法」(The Third Millennium, 1985, Knopfより)
柄谷行人の『隠喩としての建築』を引くまでもなく、建築に関わる多くの西洋語、たとえば「ストラクチャー」「コンストラクション」、あるいは「アーキテクチャー」といった用語には、多くの哲学的含意がある。ハイエクの有名な社会主義批判(『理性による反革命』)のように、未来を合理的に「設計」するといった観念を強く論難する主張もそうした含意と関係している。建築に関する思考は、潜在的に、論理や社会についてのメタフォリカル(隠喩的)な思考でもある。
建築業界の文脈では、近年〈建築と自然〉といったテーマがしばしば取り上げられるが、この「ガンツ工法」こそ、空想の産物とはいえ、まさにそうした未来の建築技法なのではないか。『予測がつくる社会』では、建築にかかわる事例は取り扱わなかったが、建築という技術が持つ隠喩としての働きには常に関心があったのである。
宇宙船と古墳
そんななか、「場所の記憶」の集中的リサーチを通じて設計を行ってきた建築家の田根剛の仕事、特に新国立競技場案として提案された通称「古墳スタジアム」案をみた時に感じたのは、ついに現実世界で「ガンツ工法」建築が誕生したという驚きである。この「古墳案」は採択されなかったし、田根が新「セメンテーション」工法を開発したわけでもないが、みたかぎりでいえば、まさにガンツ工法の成果そのものにみえた。しかもそれが、ザハ・ハディッドの、これまたアンビルトに終わった宇宙船のようなデザインと対比されていたのがまた一興であった。

田根剛「新国立競技場案」(Image courtesy of DGT)
この宇宙船か古墳か、という対比が面白いのは、『第三千年紀』が暗示する、未来の2つの方向性を具体的なデザインの違いとして示しているようにみえたからである。実際『第三千年紀』の将来像には、ある種の分裂がある。一方では核酸再生技術の発展で寿命が大きく伸びた人類の一部は、第三千年紀には、太陽系外に本格的に進出するとされている。彼らは宇宙船に適応した形に進化し、生物学的な形態も変わってしまうのだ。
しかし、本来なら直近の過去の話のはずなのに、その語りは、はるかな古代を思うように茫漠としている。他方、より近い未来においては、ガンツ工法による土塁や小型古墳のような建物が地表のかなりの部分を覆う光景が描かれる。これらは、第三千年紀からみれば、遠い過去のはずなのだが、逆にリアルなのである。
予測の役割を語るということは、言い換えれば過去と未来の関係を語ることでもある。 『予測がつくる社会』で取り上げた予測の内容は多岐にわたり、内容も多様である。他方、予測は科学的言語にもとづくのが普通だから、決定論的なニュアンスを帯びがちである。それゆえ、そうした予測が「つくる」未来社会の像は、堅牢で確実なものと信じられやすい。
しかしその細部を吟味してみると、それらは過去から借用してきた多くの仮定や仮説を外挿した結果として生まれるもので、開かれた未来に対する、可能なシナリオのひとつにすぎない。しかし予測という言説が発せられると、それは「言葉」としてそれ自身の物語を生きはじめる。結果として、そのように規定された未来が、希望と同時にわれわれを縛り上げ、息苦しさをもかもしだすのである。
空想建築
その意味で、建築は『予測がつくる社会』にとっても重要なメタファーなのである。この点で、さらにわれわれが参照したのは、野又穫(のまた・みのる)の諸作品であった。野又は、どこにも存在しないが、しかし何か懐かしい、空想上の建物を多く描いてきた。過去から未来をつなぐ予測(言葉)の働きを考えるという点で、野又の作品群にそのヒントを求めたのである。
いくつかの候補作が目に留まったが、そのひとつは、「遠景-3」というタイトルの、ブリューゲルの「バベルの塔」を思わせるような美しい作品である。もうひとつは、より最近の「ascending, descending-2」という、巨大な気球が上空をゆっくりと登っていく姿を描いた、野又のシリーズとしては珍しい作品である。
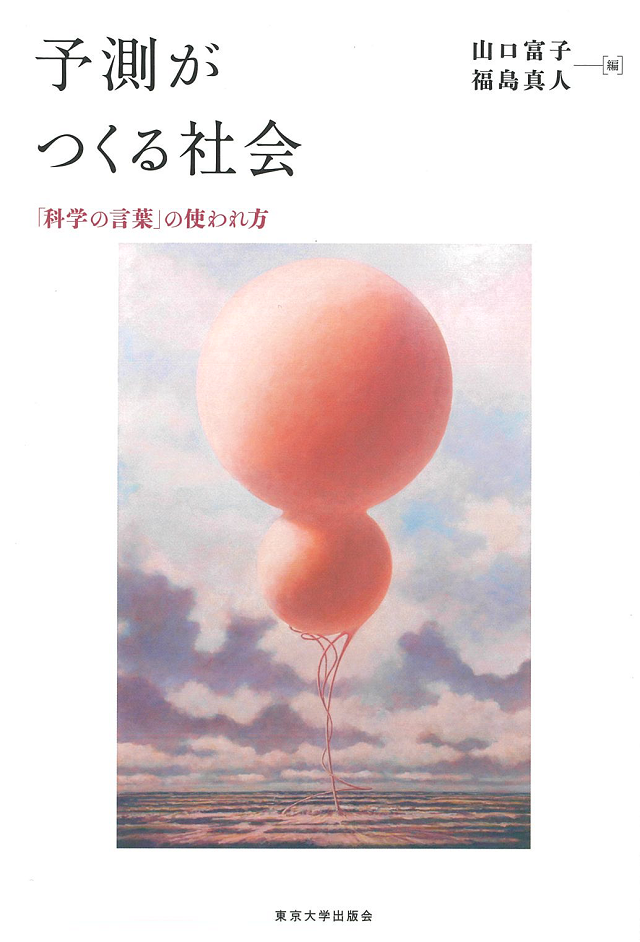
『予測がつくる社会』、装画は野又穫「ascending, descending-2」2018年
「遠景-3」は、まさに建設途中のバベルの塔が、未来に向かって完成に向かいつつある、というイメージをよく伝えている。これは過去から未来への連続性を示す、希望のメタファーともとれるし、またその完成により、段々と自由が拘束されていくという批判的なメッセージとも読めなくもない。「未来の植民地化」というアンソニー・ギデンスの言葉があるが、まさにそうした意味合いも読み込めるのである。
結果、この作品は荘厳で多義的だが、やや重いと感じられるようになった。実際、現在の多くの「予測」が語る未来社会も、ある種の息苦しさに満ちている。その息苦しさは、もちろん現状そのものにも由来するが、他方、予測への盲信がもたらす副作用でもありうる。
「ascending, descending-2」の気球が目に止まったのは、重厚な空想建築を多く描いてきた作者にしては珍しく、驚くほどの軽やかさがそこに感じられたからである。この空想の気球は何か偶然そこに打ち上げられ、そして気流に従って上空をゆっくりと漂っていく。 我々の未来もまた、そうした自由と偶然が積み重なってできるものなのだ、というメッセージが、そこに読み取れるのである。
『第三千年紀』の終章は、「31世紀の現在」にもかかわらず、茫漠とした印象しか残さないのは、所詮どんな予測もそこではとっくに息切れしているからである。現時点から遠く離れるほど、過去も未来もあいまいになっていく。その意味では、ザハの宇宙船形のデザインが未来を示し、田根の「古墳スタジアム」が過去の象徴とは、簡単には断定できないのである。
田根の案は、一見野又の「バベルの塔」のように、遠い過去のイメージによって未来を連続的につくる、という点だけが強調されそうだが、実は田根の「場所の記憶」では、過去は、未来を束縛する制約の集合――すなわち予測の負の側面――というよりも、潜在的な可能性の束と考えられている。その中に未来へのあらたな道筋を想像するのである。そしてその姿は、『第三千年紀』で未来の建築像として空想される工法に、驚くほど似ているのである。
全ての予測は、過去、現在のデータにもとづくが、過去の解釈が変われば、そこに挿入されるデータも変わってくる。そして未来には常に新たな要素が加わる。さまざまな架空の建物を描いてきた野又は、バベルの塔と気球が、実は同じ現象の2つの位相にすぎないということを、随分と前からとっくに気がついていたのである。
プロフィール
福島真人
東京大学大学院総合文化研究科教授。主要著書に『暗黙知の解剖』(金子書房、2001)、『ジャワの宗教と社会』(ひつじ書房、2002)、『学習の生態学』(東京大学出版会、2010)、『予測がつくる社会』(共編著、東京大学出版会、2019)、「病んだ体と政治の体-アピチャッポン・ウィーラセタクンの政治社会学 」夏目深雪、金子遊(編)『アピチャッポン・ウィーラセタクン光と記憶のアーティスト』(フィルムアート社、2016)、ほか。
HP:https://ssu-ast.weebly.com/


