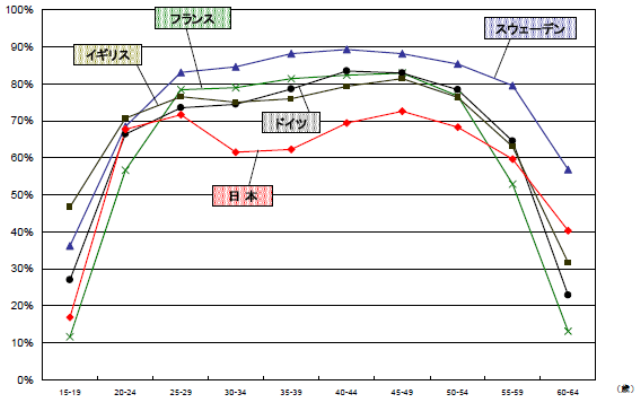2011.06.06

「新しい公共」の分岐点 ―― 震災復興のなかの社会保障改革
現在、「税と社会保障の一体改革」と称した、民主党政権による今後の社会保障政策全体を左右する改革案が取りまとめられつつある。官邸のHPで「社会保障改革に関する集中検討会議」の議事や資料は誰でも閲覧することができ、政府インターネットTVで過去の会議の動画を観ることもできる。
震災復興のさなか、どさくさ的に押し通されてしまった感がある改革案だが、その基本的な骨格は突如出現したものではない。菅政権の発足は2010年6月。直後の参議院選挙の際に掲げられたマニフェストには、はっきりとこう明示されている。―”私は「第三の道」を選択します”
変質する「新しい公共」
菅政権が示す「第三の道」の特徴は、「新しい公共」というアクターの強調である。「新しい公共」とは、80年~90年代に欧州の社会民主主義政策の議論のなかで盛んに登場したPPP<民間と行政による協働(Public Private Partnership)>の日本版のようなものであった、とわたし自身は認識している。
少子高齢化と財政制約による福祉国家の揺らぎの打開策として、生存権に関わるセーフティーネット以外の分野で、社会的企業や市民団体に福祉の機能の一部を委託することで効率化をはかる、というのがこれまでの「新しい公共」のイメージだったように思う。
「新しい公共」を積極的に採用する論者も、あくまでも人権のボトムラインは国家が維持するという前提と環境のもとで、日本のNPOや市民団体の財政基盤の脆弱性の解消、新たなコミュニティや社会資源創出の可能性などを模索してきたのではないだろうか。
しかし、震災をへて、「新しい公共」が担わされる役割が変質しつつある。社会保障改革案では「自助・共助・公助」という文言が明確に基本的方針として打ち出され、公の手前に「共助」がおかれたが、本来、人権として「公共」が保障するべきとされていた領域にも、「新しい公共」が立たされようとしているのだ。
NPOや各民間組織の力量の差、自治体による格差、制度設計の矛盾などによって、介護や医療、障害、教育、あらゆる福祉の現場が限界にあることは自明である。そうしたなか「共助」の安易な強調は、「公共」の力不足が人のQOLに不条理をもたらしている現実を、「新しい公共」を盾に容認させようとしているようにもみえる。
「脱家族化」の共振、だが揃わない足並み
高齢化が進行し、家族のケアを家族同士で担うのはもはや物理的に不可能であり、社会保障には「脱家族化」が必要だ、という感覚はおそらく世代や社会階層を問わず多くの人々が共有している。何らかの改革が必要であるというコンセンサスはある。しかしそれを現実にはたすためにどうするか、という具体性のある話になると、足並みが崩れ出す。
そもそも、女性の就労支援や男性の育児参加すらいまだ浸透には程遠い。今日「男女の機会均等」をあらたまって主張するなど、居心地の悪さすら感じる。しかし、女性の就労や社会権を中途半端に扱ってきたことの功罪は、再検討されるべきだと考えている。女性の社会的地位の実質的な向上は、「脱家族化」型福祉が機能しているかどうかという指標と表裏一体だからだ。
家族主義のなかで女性が担わされてきた福祉労働で、一般的にもっとも過酷な負荷は育児と介護であった。出生と老いのステージにおいては、人は無条件にケアされ福祉を受動する存在になる。
とくに、就学前の乳幼児期の子どもの保育は、保護者がもっている社会資源や経済力の差が、子どもの機会格差にダイレクトに影響する。それゆえ、福祉の「脱家族化」の停滞で、子どもは否応なしに不平等にさらされつづける。そして貧困は、次の世代に確実に引き継がれてゆく。
しかも、厳しい財政制約のなかでの再分配の議論は、「誰が誰に向かって要求するか」という形式になりがちである。そのような文脈では人は何らかの「弱者」として類型化・細分化され、互いのパイの取り合いに終始する羽目になる。「弱者」は互いにけん制し合い、対立し合う図式のなかで摩耗してゆく。
「家族主義」「企業主義」という日本型福祉の二本柱が崩れた後の亀裂に、現在進行形で多くの人が落ち込んでゆき、そこに「公共」ではなく「新しい公共」が矢面に立たされる。
動員の意味づけ
だが、国家や公的組織のみが社会保障の担い手であるべき、と主張したいわけでもない。現に、市場化や準民営化は多くの領域ですでに行われている。社会保障のアクセス権の公平性や質の維持を実現するために、現在の日本社会の状況のなかで、いったい何が現実的な対処なのかを考えなくてはいけない。
だが少なくとも、突然降ってきた「新しい公共」という抽象的なコミュニティ論が万能の処方箋であるわけはない。そして、「公共」の穴埋めのみを求められて、共助の執行者として「動員」されるというのでは、これまで地道に独自の事業を積み重ねてきた「新しい公共」自身、NPOや民間セクターにとってこそ、可能性を矮小化させられる傍迷惑な論理なのではないだろうか。
「今さら」なことを再考する
男女の機会均等や人権、「今さらこんなことを」と、この文章を書きながらわたし自身が躊躇を感じる。だが、なぜ躊躇を感じなければならないのか、ということも問いたい。過去10年間にわたる議論のなかで、行政の機能不全や福祉の崩壊といった事柄は、「古臭い」ものとして語り手に人気のない話題になってしまった。
社会学者の仁平典宏氏は、今回の震災後に執筆した論考 において、次のように述べている。
今回見えてきたのは、公的セクターと市民セクターの相補的な関係の重要さである。NPOや市民が限界まで活動しても、社会権の十全な回復を通してでないと避難状況から脱却できない。これは政府が―再分配という形の連帯を通して―責任もって行うべき役割である。そしてその基本ニーズが公的に保障されてこそ、創意に満ちた市民セクターの活動も輝きを増す。また、自発的なボランティア活動も、地域の公的セクターが円滑に機能してこそ、その力を存分に発揮できるという面があった。(POSSE vol.11掲載 「被災者支援から問い直す『新しい公共』」)
こう指摘したうえで、ゼロ年代の市民社会論・NPO論が、行政や公共セクターを非効率的なものとして批判することで、その脆弱化に結果的に加担してきてしまったのではないかと問うている。
少子高齢化と財政制約のなかで、何もしなくても、放っておいても、福祉の亀裂とQOLの低下は自然に広がってゆく。これから、社会保障改革案をもとに、各分野の法案や政策改変が行われる。その只中で、言論と生活者が協同してゆく術を、男女の機会均等や人権といった「古臭い」テーマをもう一度引き受けながら、いまこそ考えていきたいと思う。
推薦図書
この本も「今さら」かもしれないが、本書はブレア政権の社会保障政策の思想基盤そのものである。1990年代後半以降の欧州の社会民主主義政策の議論の流れのなかで、「イギリス型」をかたちづくった。菅政権の「税と社会保障の一体改革」の資料や政策案と並べて読んでみると、その類似点を実感する。本書がイギリスで発行されたのは1998年だが、当時のギデンズがとくに貧困対策に言及する際に展開した「コミュニティ」論に注目して読みたい。
プロフィール

大野更紗
専攻は医療社会学。難病の医療政策、