2013.04.17

アートで心を〈癒す〉―― 第4回「心のアート展」開催にあたって
2013年4月24日(水)~29日(月・祝)、東京芸術劇場5階〔ギャラリー1〕にて東京精神科病院協会(以下、東精協)主催による「第4回 心のアート展 ―― それぞれの感性との出会い」が開催される。開催に先立って、同アート展の実行委員をつとめる荒井裕樹氏にお話を伺った。「心の病」をかかえる人たちにとって、アートはどのような役割をはたすことができるのだろうか。(聞き手・構成/出口優夏)
「心のアート展」とは?
―― まず「心のアート展」についてご説明ください。
東精協に加盟している精神科病院(67病院)に、入院あるいは通院されている方たちの作品を展示するアート展です。東精協というのは東京都にある私立の精神科病院の連絡協議機関で、2009年から「心のアート展」を開催するようになりました。今回で4回目になります。
―― どのような作品が展示されているのでしょうか?
公募で集まった作品のなかから、2段階の審査を通過した作品を展示しています。前回の第3回展では19病院から300点ほどの作品が集まり、130点ほどの作品が展示されました。年々、参加病院・参加者の裾野はひろがっています。
原則的には東精協の加盟病院に入院・通院している方の作品が対象なのですが、このアート展の主旨にご賛同頂いたアーティストの作品を「特別展示」というかたちでご紹介することもあります。毎年協力してくださっているのは、『失踪日記』などで知られる漫画家の吾妻ひでおさん。吾妻さんは、ご自身も漫画化されていますが、アルコール依存症で医療機関にかかっており、自助グループにも通われているようです。
今回は、フランスから「アトリエ・ノン・フェール」の方々もお招きしています。「アトリエ・ノン・フェール」というのは、パリ郊外の精神科病院メゾン・ブランシェで活動をつづけてきたアーティスト集団です。現在はパリの街中を活動の舞台にしているようで、EU圏ではかなり頻繁に展示会が開かれて注目をあつめています。日本では、このアート展ではじめて実作品が展示されます。ほかにも、清貧の生活のなかで流行にとらわれず、孤高に描きつづけた画家・櫻井陽司氏の作品も紹介されます。
―― 審査はどのように行われているのですか?
「心のアート展」では、5人の先生方に審査をお願いしています。加賀乙彦氏(小説家・精神科医・審査員長)、仙波恒雄氏(日本精神科病院協会名誉会長)、齋藤章二氏(斉藤病院理事長・院長)、立川昭二氏(北里大学名誉教授・医学医療史)、安彦講平氏(〈造形教室〉主宰)です。どなたも、臨床現場と芸術分野の両面でゆたかな経験をお持ちの方です。
審査でむずかしいのは、「良い作品とはなにか」という点です。「良い」の基準をどこに置くのかというのは、とてもむずかしい。「技術的に上手い絵」をえらぶと普通のアート展との差異がなくなってしまいますし、「がんばって描いた絵」をえらぶとすれば応募されたすべての作品があてはまってしまいます。
審査会の現場では、審査員や実行委員の方が作品に試されているような緊張感があります。「この絵の価値があなたにわかるのか?」という感じですね。むずかしいことは重々承知の上で、可能な限り、作者の切実な思いや生命の息吹みたいなものが感じられる作品をえらびたいと思っています。
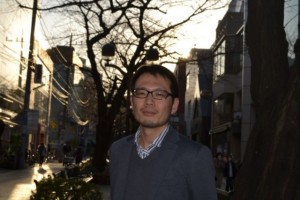
アート展を行う意味
―― このようなアート展を開催することに、どのような意義があるのでしょうか?
「障害者文化論」を研究するわたしの立場からの答えになりますが、いくつか意義があるように思います。
ひとつは啓発活動として。「心の病」という言葉がとても身近なものになってきた一方で、「精神科病院」や「精神障害者」にたいする偏見はまだまだ根強いです。「心の病」はボーダレスにこの社会にひろがっていますが、それをサポートする「精神科」への心理的なボーダーはとても高い。そのようななかで、アートは「心の敷居」を乗り越えるひとつの窓口になるのではないかと思っています。
ふたつめは、病院同士の情報交流の場として。精神科病院のアート活動は、基本的にはデイケアやOT(occupational therapy:作業療法)の現場で、医療スタッフの指導のもとに行われていることが多い。それぞれの病院が工夫をこらして活動をしていますが、ほかの病院の活動については、お互いに知らない部分も多いのではないでしょうか。ですから、さまざまな病院の作品を一堂に会することで、ほかの病院がどのような試みをしているのかを知る良い機会になると思います。
さいごは、病院という場で、とてもユニークで個性的で力強い作品をつくっている人たちがいる。そのことを社会に届けたい、知ってもらいたい、ということ。個人的には、これが一番おおきな理由だと思っています。なかには、この社会の閉塞感や生きにくさ、あるいは冷酷さなどを凝縮して映し出したような作品もあり、こちらが圧倒されることもあります。
研究者としての立場から言えば、このようなアート作品を社会に投げかけたら、人びとはそれをどのように受け止めるのか、という点にも関心があります。苦しんでいる人たちの心にこの社会はどのように映っているのか。アートはきっと「いつもとは違った角度から社会を見つめなおす」きっかけを与えてくれると思います。

「表現」が「表現者」を超える
―― 治療の一環としてアート活動を行うことにどのような効果があるのですか?
とてもむずかしい質問ですね。よく「絵を描くだけで病気は治るのですか?」と聞かれることがあります。わたしは医療者ではありませんから、医療的な観点からお答えすることはできません。ただ、このような研究に携わってきた経験の範囲内でお答えするならば、どうやらこの質問には、ふたつの答えを用意する必要がありそうです。
ひとつめは、「絵を描くだけでは治りません」という答え。一口に「心の病」といっても、さまざまな症状があり、それぞれに発症の経緯があり、一概に説明できるものではありません。しかしながら、心を病む人の周囲には、家庭・学校・職場など、生活の根幹にかかわる部分で、とても閉塞的で息苦しい(=生き苦しい)人間関係が存在する場合が多いということは、わたしの乏しい経験からでも事実だと言えそうです。
「心の病」というものは、その症状自体は個人の心身にあらわれたものなのですが、実際には、「その人を取り巻く人間関係自体が病んでいる」と表現した方がよい場合もあります。人間関係自体の「病み」が、「弱い立場に置かれた人」や「やさしい気づかいをしなければならない役回りを負わされた人」の心身を通じて噴出している、とかんがえたくなることさえあります。あたりまえのことですが、医療のサポートを必要とする人は決して自分で勝手に苦しんでいるわけではありません。必ず「苦しめられている」部分があるわけです。
ここで問題にしている「絵を描く」というのは、単に「紙に線を引いて色を塗る」ということではなく、「自分の気持ちをさらけ出す」という要素を含んだ行為を前提にしています。ですから、ひとつの作品が生まれるためには、自分の気持ちを表現しても受け止めてくれる人がいるという安心感が必要です。テーマについて相談したり、画材の使い方を一緒に考えたり、絵筆を動かしながらグチを聞いてもらったり、ときには率直に意見を言い合えるような、何気なくも温かな人間関係が大切なのです。そのような関係性の蓄積が、結果的に、病み疲れた心を良い方向へと導くのだと思います。
この点を踏まえて、先ほどの答えを表現しなおすと、「絵を描くだけでは治りませんが、安心して絵を描けるような環境がなければ治りません」ということになるかと思います。もちろん、適切な医療ケアは不可欠です。
ふたつめは、これはうまく説明しないと大きな誤解を招いてしまうのですが、「「治る」とはまた別の道を探すことも、場合によっては必要なのではないか」という答え。
「心の病」が「治る」という際、多くの人は、つらい症状が除去された状態をイメージするのではないでしょうか。しかしながら、いま申し上げたように、心を病む人の周囲には非常に生きづらい人間関係が存在する場合があります。
かりに、職場での激務や学校での人間関係に疲れ果てた人が医療機関を受診し、入院したり通院したりする必要が生じたとします。その後、薬などの効果によって際立った症状が出なくなった。でも、当人の周りで息苦しい環境が相変わらずつづいている場合、それは「治った」と言い切ることができるのでしょうか。「人間関係自体が病んでいる」ような場合、「個人の心の病が治る」というのは、どのような事態を意味しているのか、とてもむずかしいように思います。
医療や福祉の適切なサポートは必要ですが、それらは万能ではありませんから、すべての問題を解決できるわけではありません。多かれ少なかれ、つらい環境のなかをサバイバルしつづけなければならないわけです。だとしたら、医学的な処置によって症状を除去する「治す」とは別に、つらい状況を抱えつつも一息つきながら生き延びる〈癒す〉という考え方も必要になってくるのではないでしょうか。アートというのは、自分を〈癒す〉ことの手助けになるのではないかと思っています。
もちろん、これらはわたしの経験に基づく個人的な見解であって、医療者の方には医療者なりのお答えがあると思います。
―― 実行委員としてアート展にかかわってこられたなかで、印象的だったことはありますか?
わたしがとても興味深いと思っているのは、このようなアート展をやっていると、「表現が表現者を超える瞬間」に出会えることがあるという点です。
たとえば、こういうことがありました。ずっと親御さんと息苦しい関係で生きてきた方がいた。「お前はダメなやつなんだ、一人前じゃないんだ」と、一人の人間として認めてもらえなかったようなのです。その方が作品を出展することになり、勇気をだして会場に親御さんを呼んだ。そうしたら、多くの観覧者がこの方の作品に魅入っている。その様子を親御さんが見て、とてもおどろいたようです。
「あの子は自分がいなければダメなんだ」と思い込んできたのに、自分の知らないところで成長し、輝いている当人がいた。ずっと癒着してきた親子のあいだに、はじめて風が通ったというのでしょうか。これをきっかけに、親子の関係は少し改善されたそうです。この場合、この方の絵の前で足を止めていた観覧者も、知らず知らずのうちに、親子の「生き直し」をサポートしていたことになるのかもしれません。
また、こんなこともありました。「心のアート展」では、作品によっては実行委員がそれに似合った手作りの額を用意します。ある出展者が、額装された自分の絵を見て驚いていました。「自分はもっと暗くて陰鬱で救いようのない絵を描いたつもりだったのに、実際に額装された絵を見たら、思っていたより柔らかだった。もしかしたら、自分は捨てたものじゃないのかもしれない」とおっしゃっていました。
「表現」というのは、「表現者」の意図を超えた力を持つことがあります。最近よく思うのですが、「アーティスト」というのは「自分の思いを正確に表現できる技術を持った人」のことではなく、むしろ「自分の表現に自分自身が驚くことができる感受性を持った人」のことなのかもしれません。
さきほど、なにをもって「良い絵」とするかはむずかしいと言いましたが、もしかしたら「良い絵」というのは、展示したときに、描いた人にとっても観る人にとっても、予想外の出来事が起こる絵のことなのかもしれませんね。会場に足を運んでくれた方と出展者とのあいだで、なにか予想外の面白いことが起こるのを期待しています。
「大変さ」を表現できる社会へ
―― これまでアート展を見に来た人たちの反響はいかがでしたか?
おおむね好評をいただいたと思います。これまでのアート展では「心のハガキ」という企画を行っていました。来場者に一枚のハガキをお渡しし、「自分の心のイメージ」を描いてもらうというものです。絵を「見る‐見せる」という一方通行の関係ではなく、相互交流型のアート展にしたいという思いではじめた企画です。多くの方が好意的に描いてくださったのですが、そのなかで、いくらお願いしてもまったく描いてくれなかった方々がいた。40~50代の背広を着た男性たちです。もしかしたら「心を表現するのが恥ずかしい」「絵を描くなんて大の大人がやることではない」と思っていたのかもしれません。
「障害」というのは、わたしなりに定義すると、「ある文脈のなかで、みんなが普通にできることができないこと」です。だとしたら、あの文脈に合わせると、「心のイメージ」が描けなかった人たちは「自己表現障害者」になるのかもしれません。もちろん、少し皮肉を込め過ぎた言い方です。ただ、「心のイメージ」を描けなかった、描くことに抵抗感を覚えた、ということをきっかけに、「自分は本当に大変な時に、大切な人に助けを求められるだろうか」ということを考えてもらえたらいいですね。
「「だれかを励ます言葉」のバリエーションをいくつお持ちですか?」という質問をしたら、「頑張れ」とか「負けるな」と答える人が多いのではないでしょうか。きちんと統計を取っているわけではありませんが、おそらく両者ともトップ5には入ると思います。ただ、大変な思いをしている人はすでに十分頑張っていますし、勝ち負けの論理とは異なるところで困っていることもあります。そうすると、これらは「励まし表現」としては、あまりゆたかな表現ではないようです。
そもそも、「頑張れ」とか「負けるな」というのは、だれかを叱りつける際にも用いる言葉ですよね。つまりわたしたちは、純粋に人を励ます言葉の持ち合わせが少なくて、人を叱りつける言葉を文脈に合わせて援用しているわけです。「励まし表現」のバリエーションが少ないわけですね。3.11と昨今のいじめ問題などもあって、「一人じゃない」という言葉が「励まし表現」として社会的に共有されつつあるように思いますが、あれだけの惨事を経験して、ようやくひとつの新しい表現を生みだすことができたのかもしれません。
「励まし表現」のバリエーションが少ないということは、裏返すと、大変な思いをしている人たちが、その「大変さ」を表現するバリエーションも少ないということなのかもしれませんね。多くの人は、自分が抱えている「大変さ」を表現することが苦手だったり、あるいはそもそも表現してはいけないと思っているのではないでしょうか。「自分だけ大変だなんて言っちゃいけない」「大変って言ったらその時点で負けなんじゃないか」と思っているわけです。堂々と「大変さ」を表現する人がバッシングを受けるということも少なくありません。
生きにくい人、苦しい人、つらい人、弱い人、困っている人などなど、この社会のなかには、さまざまな「大変さ」を抱えた人たちがいます。そういった人たちもふくめて社会をゆたかにし、少しでも「生きやすい社会」をつくっていくためには、一人ひとりが抱えている「大変さ」に対する想像力や感受性を耕していくことが大切です。ちょっとおおげさですけれど、そのような想像力や感受性といったものを「社会資源」にまで育てていく必要があるわけですね。もしかしたら、アートにはそのような役割を果たせる可能性があるのではないでしょうか。そういった意味でも、「心のアート展」のような試みは意味があると思っています。
こんなことを言うと、「心のアート展」では、暗くて深刻な作品ばかり展示されているような印象を持たれる人もいるかもしれませんが、実際の会場では、可愛くてほほえましい作品も、ユニークな作品もあります。作者によるギャラリートークや座談会も企画されています。入場無料でやっておりますので、近くをお通りの際は、ぜひぜひ、お気軽に立ち寄ってみてください。

プロフィール

荒井裕樹
2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二松学舎大学文学部専任講師。東京精神科病院協会「心のアート展」実行委員会特別委員。専門は障害者文化論。著書『障害と文学』(現代書館)、『隔離の文学』(書肆アルス)、『生きていく絵』(亜紀書房)。


