2016.12.23
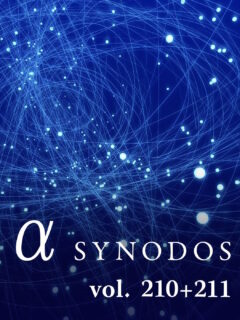
特集:宗教
1.木島泰三「現代の進化論と宗教――グールド、ドーキンス、デネットに即して」
副題に掲げた3人の内、グールド(Stephen Jay Gould: 1941-2002)とドーキンス(Richard Dawkins: 1941-)は進化生物学者、デネット(Daniel C. Dennett: 1942-)は哲学者であるが、いずれも、ダーウィンの進化論をベースにした科学的な世界観を広く一般向けに解き明かしてきた思想家であり、またいずれも「科学と宗教」の問題に切り込む著作を公刊している。本記事は彼らの宗教論をその歴史的、社会的な背景と関連づけて解説していく。(注1)
1.背景的歴史
1-1.初期近代の科学と宗教の蜜月関係
ヨーロッパで中世まで支配的だったアリストテレス(Ἀριστοτέλης (Alistotle): B.C. 384-322)の自然学によれば、どんな自然現象にも「何のために?」という問いへの答え、つまり「目的原因」があるとされた。
このような自然学は近代物理学の基礎が築かれた「17世紀科学革命」の時期に退けられ、代わりに自然現象は、自ら動くことがない物質が、他の、やはり自ら動くことがなく、他から動かされた物質によって動かされるだけの、法則的運動によって説明されるようになった。このような自然観を「機械論的自然観」という。
だが自然の中に目的原因を求める自然学の放棄は、「自然の目的」という思想(広い意味での「目的論的自然観」)を全面的に退けるわけではなかった。この時期以降、力を増した「偉大な時計技師としての神」という神学思想が、世界を導く神の善意や摂理を保証するようになったからである(注2)。この神学によれば、たしかに諸物体は単純な法則に従った機械的な運動しかしないが、そのような諸物体を巧みに配列した神がいて、その配列と自然法則が組み合わさって神のデザイン(これは「設計」とも「意図」とも訳せる)を実現する。
このように自然の中に神の働きを見いだす思想を「自然神学」というが、特にイギリスでは17世紀以降、自然の中に見いだされるデザインをもとに神の存在を導く「神の存在のデザインに基づく論証」を基礎にした自然神学が発展し、伝統的な宗教を妨げずに科学が発展できる状況ができあがって、19世紀の産業革命の時代に至るまで科学的な研究を導いた(松永1996、第1章)(注3)。そしてこの種の神学に主要な支えを提供してきたのは、脊椎動物の目やハタオリドリの巣作りのような、生物の環境への巧妙な「適応」の現象であった(注4)。
1-2.『種の起原』の出版から現代までのダーウィニズムの歴史
このように19世紀半ばまでのイギリスにおいて、科学と宗教の間(少なくとも多数派の穏健な科学者と開明的な神学者の間)には自然神学に基づく良好な蜜月関係が維持されていた。この状況を変えるきっかけになったのが、当初は自然神学の書として登場した、ダーウィン(Charles Darwin: 1809-1882)が1859年に公刊した『種の起原』[On The Origin of Species](Darwin 2006 (1959 / 1859))である。
ダーウィンはこの書で、当時なお認められ、デザイン論証の大きな支えとなっていた「種の個別創造」の説を退け、単一の祖先種から長い時間をかけて今のような無数の種が分化してきたという「変化を伴う由来」(=進化)の理論を、単なる空理空論ではなく(注5)、科学的手続きを踏んで提示される理論として提出し、同時にまた、進化のメカニズムとしての自然淘汰(自然選択)の仮説を提出した。
ダーウィンの著書によって、進化論を科学的仮説として受け入れるという動きが急激に進み、個別創造説の支持者は少数派になり、デザイン論証も大きな支えを失った。但し進化のメカニズムとしての自然淘汰説については、必ずしも幅広く支持されたわけではなく、むしろ19世紀終盤から20世紀初頭にかけては「ダーウィニズムの失墜」の時代が続いたと言われる(ボウラー1987 (1984)、第9章;ボウラー1992 (1988))。
宇宙や社会を含むすべての存在の進化論を提唱していたスペンサー(Herbert Spencer: 1820-1903)の思想がすでに登場していたことからも示されるように、ダーウィンに先立ち進化論を受け入れる土壌は整っていた。それは産業革命のような社会の急激な変化によって強く説得力を帯びた「進歩の思想」と軌を一にしていたのである。
自然淘汰は、有限な環境の中で生存や繁殖に有利な偶然の変異が生存競争の中で保存され数を増やすという、機械論、唯物論に反しないが、それゆえにまた緩慢で、運任せで、どこか残酷な過程である。例えばスペンサーのような、宇宙や生命、あるいは社会に内的な進歩への傾向のようなものがあるという見方が自明視されている限り、自然淘汰によって進化はおおむね説明されると考えるダーウィニズムの立場は、支持を得にくかったのではないかと思われる。キリスト教と進化を結びつける余地は十分にあったし(注6)、20世紀に入ってもベルクソン(Henri Bergson: 1859-1941)の「エラン・ヴィタル」のような反機械論的な思想が存在できたのである。
とはいえ、ダーウィニズムに対抗する諸理論は徐々に退潮し、また当初ダーウィニズムと対立するとされていたメンデル遺伝学が、1920-30年代にダーウィニズムと結びつき、集団遺伝学という新たな分野が確立するなどの経緯を経て、1940年代には「進化の総合説」ないし「ネオ・ダーウィニズム」と呼ばれる、現在まで正統説の地位を占める理論が登場した(ボウラー1987 (1984)、第11章など)。
総合説は生物学の各分野で浸透を続けていったが、特に重要な発展として1960年代以降の動物行動へのダーウィニズムの厳密な適用がある。この成果として、「自己犠牲」という見たところ自然淘汰に反する遺伝的行動を説明する「血縁淘汰」の理論が得られた(セーゲルストローレ2005 (2001)、第4章など)。この理論の創設者の1人であるハミルトンはしばしばこの理論を、個体にとっての自己犠牲の行為は「遺伝子からの視点」を取れば自然淘汰説に反しない、という仕方で説明した(ブラウン2001 (1999)、pp.38-39;セーゲルストローレ2005 (2001)、p.94)。
この遺伝子からの視点をダーウィン的進化全般の見取り図として拡張し、一般向けに解説したのがドーキンスの著書『利己的な遺伝子』(ドーキンス2006 (1976))である。この見方に従えば、自然淘汰は種でも群れでも生物個体でもなく、遺伝子の生き残りを最大化するように働く。要するに自己の生き残りを最大化するような表現型をコードしている遺伝子が最大に生き残るのであり、生物個体は進化の単位としての遺伝子を運ぶ「乗り物」として位置づけられる(注7)。
これら新しい進化生物学の成果は、1970年代の終わり頃から、ダーウィニズムないし総合説の影響力をより広い範囲に及ぼすようになった(注8)。動物行動学、進化生態学、社会生物学といった名で呼ばれる動物の(とりわけ社会的な)行動のダーウィニズムに基づく研究は、1990年代に入り認知科学、脳科学などの成果と結びついて、人間の心のダーウィニズムに基づく研究である進化心理学という新たな分野を生み出し、この観点から人間の道徳や宗教を研究する試みも始まる。この観点からの宗教論はドーキンスやデネットの宗教論に大きな基礎を提供するのであるが(注9)、それを見る前に、別の観点から同じ歴史をたどり直しておく必要がある。……つづきはα-Synodos vol.210+211で!
2.高橋典史「宗教組織による在日外国人支援――多文化共生社会の実現に求められるもの」
阪神大震災以降、ニューカマーの在日外国人に対する支援において宗教組織の活動が大きな役割を果たしてきたことは、あまり広く知られていません。カトリック教会などキリスト教団体によるインドシナ難民への支援、各地での在日外国人コミュニティの形成、在日ムスリムたちによる社会活動など、歴史の流れを追いながらわかりやすく解説していただきました。
◇日本における外国人労働者の受け入れ
1980年代以降、いわゆる「ニューカマー」と呼ばれる在日外国人の増加の波が続いている。2008年のリーマン・ショックの世界的な経済不況や2011年の東日本大震災による足踏みはあったものの、少子高齢化の深刻さが増しつつある日本社会にあっては、外国人労働者の大規模な受け入れの必要性が政財界でさかんに論じられてきた。そして、看護・介護分野における労働力の受け入れ、技能実習制度のさらなる拡大、「国家戦略特区」における家事労働者の受け入れの「解禁」など、さまざまな領域において実行に移されてきたことは周知の通りである。
しかしながら、これまで日本政府は正式なかたちでの「移民政策」は採用しては来なかった。そのため、「日系人」といった特定の出自を有する人びとに限定した就労可能なビザの発給や、技能実習制度という建前での実質的な外国人労働力の確保といったように、いわゆる「移民」を回避するかたちで、いかに労働力の受け入れるのかについて知恵を絞ってきた。
そういった経緯もあって、これまで国策レベルでは定住外国人の社会統合への取り組みは、それほど積極的ではなかったといえる。さらにいえば、多くの外国人住民を実際に抱えている地域社会の現場レベルでの多文化共生関連の取り組みも、地方自治体や各種のNGO等の努力に依存してきたといえる。
こうした社会統合政策が不在の、杜撰ともいえる海外からの労働力の受け入れ政策を進めてきた日本において、外国人労働者とその家族たちはさまざまな困難に直面してきた。そして、彼ら/彼女らを現場で支援してきた有力な民間セクターの1つが、宗教であった。もちろん、実際にそうした取り組みをしてきたのは、数ある宗教団体のうちごく一部にすぎない。とはいえ、外国人住民に向けた公的セーフティネットが脆弱である日本において、各種の専門的なNPOが未成熟な時期から、まさに草の根のレベルで支援を行ってきた宗教関係者や宗教組織の存在は貴重であった。……つづきはα-Synodos vol.210+211で!
3.吉田徹「「自己決定からの逃走」の先にあるもの――ウエルベック『服従』は何に服従したのか」
日本でも話題となった、フランスの作家ミシェル・ウエルベックによる『服従』。この作品では、イスラム原理主義_と世俗極右との対立が激化する近未来のフランスを舞台に、前近代的な宗教に染まりつつある社会の姿が描かれています。吉田さんは、すべてを自己決定しなければならない近代的自由主義の虚しさへの「服従」の帰結として、人間性への回復へと向かう主人公が描かれていると分析しています。
ミシェル・ウエルベック著『服従』は、2015年1月7日のパリ『シャルリ・エブド』襲撃事件当日に公刊されたこともあって、大きな注目を浴びた。シャルリ・エブド襲撃のみばかりか、同年末の地方選挙でFNの伸張もあって、本国のみならず日本でもベストセラーになった。
内容はといえば、時は2022年のフランス。圧倒的支持を誇る極右・国民戦線(FN)の大統領候補を落選させるため、既成政党がムスリム同砲団(これ自体はエジプト・ムルシー大統領も属していた実在のスンニ派宗教組織である)の候補者を担ぐ。欧州最大のムスリム・コミュニティを持つフランスで、産油国の支援もあって同胞団は勢いづく。かくしてフランス政治の対立軸は保革ではなく、世俗極右vs宗教原理主義へと転換していく。大統領選ではモアメド・ベン・アッベスが大統領に選出され、フランスは結果としてシャリア(イスラム法)を通じて統治されることになる――この間の出来事が、放蕩無頼を尽くす文学教授、フランソワの目線でもって語られる。
こうした内容を持った同作品は、フランスにおけるイスラム教の脅威を喧伝したものと誤解されがちだが、そんな単純な小説が評判になるはずがない。実際、翻訳される前からいち早くこの本の評判を書きとめた浅田彰は、「1968年以後の多文化主義の建前を露悪的にひっくり返す」のがウエルベックの十八番だとしつつ、「西洋の没落とイスラムへの服従を穏やかなニヒリズムをもって冷静に受けいれるという物語」でもあると高く評価していた。(http://realkyoto.jp/review/soumission_michel-houellebecq/)。
もっとも、この評価は半分しか正しくないように思われる。すなわち、理知的なヒューマニストたるウエルベックのメッセージは、もっと重層的なものではないか。……つづきはα-Synodos vol.210+211で!
4.平野直子「代替療法と『善なる自然』」
科学的根拠の乏しい健康・治療情報がネット上で広く出回る一方、専門家からのデマの検証、正しい知識の共有も進められています。なぜ、代替医療に惹かれる人々に対して、「科学的な根拠がない」という指摘が意味をなさないのか?「自然治癒力」「オーガニック」「マクロビオティック」というキーワードに通づる「自然=善」という考え方を手掛かりに、双方のコミュニケーションの食い違いの原因を指摘していただきました。
◇代替療法と「自然=善」のコード
インターネットの普及により、だれでも気軽に健康や病気の情報を探し、手に入れられるようになったが、同時に根拠の怪しい情報の氾濫という問題も大きくなる一方である。つい先日は、健康情報についてのまとめサイトが不確かな情報を垂れ流してサイト閲覧数を稼いでいたことが問題となった。客観的な情報を載せているように見えて特定の商品や施術の広告であるようなサイトも非常に多い。
こうした状況の中で、同じくネットを舞台に地道な啓蒙活動を行ってきた医師のNATROM氏や森戸やすみ氏、管理栄養士の成田崇信氏などが、近年次々と書籍を出し、広く読まれるようになったのは嬉しいことだ。彼らはネットにあふれる根拠の怪しい健康・治病の情報(NATROM氏などは「ニセ医学」と呼ぶ)を検証し、かわりに科学的に根拠のある、あるいは論理的に正しい(筋の通った)情報を提供すると同時に、読者に対しては「リテラシー」(ここでは「情報を適切に読み解き、取捨選択する力」ということ)を身につけ、あふれる情報から本当に必要なものを取り入れてほしいとしている。
言い換えると、「ニセ医学」が世にはびこる理由の一端は、非専門家である医療・健康情報の受け手に「リテラシー」、とくに科学的知識によって情報を読み解く力が欠如しているため、ということになる。また、「ニセ医学」グッズやサービスを提供する者は、根拠のない情報を流し、レトリックを駆使して知識のない消費者を「だましている」となる。
ネットに限らず巷にあふれる健康や医療に関する情報のうち、さも科学的な根拠があるようにうたいながら実はそうではない商品や施術に対し、専門家が正確な情報を示して批判するのは、たしかに非常に重要なことである。しかしそれだけではすまないものもある。ここで注目したいのは、しばしば通常の医療制度の枠外で行われる治病・健康法(以下、ここではそれらを「代替療法」と呼ぶ)のアピールポイントとなっている、「自然」の考え方である。
たとえばホメオパシーの指導者たちは、彼らが使う「くすり」(レメディ)は、日常世界で自分たちがよく見知っていて取り回せるものだけを使って作られている――「自然」なものである――と主張する。また、マクロビオティックのような食事法では、食品はできるだけ材料本来の姿のまま、つまり「自然」な状態で摂ることがよしとされ、玄米菜食や精製していない小麦粉や砂糖の使用が勧められる。
このほかにも代替療法の世界は「自然治癒力」「天然素材」「オーガニック」などの言葉にあふれており、他方で科学技術の産物である通常の医療や医薬品、または大量生産されて一般に流通する食品などは劣ったもの・有害なものと語られがちである。
ここでの「自然」のニュアンスには、「人工的ではない」「化学製品ではない」「生物本来のあり方に近い」などと幅があるが、大きくみればそれらはみな、「近代的なもの(あるいはそう見えるもの)=悪/非近代的なもの=自然なもの=善」という二項対立の、一方の項を表しているといえよう。この二項対立はさまざまな療法や健康法の実践者に共有されており、身体についての情報や経験を理解したりやり取りしたりするときの前提になっている。ここではこれを「自然=善のコード」と呼んでおこう。
「ニセ医学」を検証する人々は、主に個々の代替療法の効果や発信される情報が、論理的あるいは科学的に正しいかどうかに注目するが、現代の代替療法の実践について考えるときには、個々の療法の枠を超えて存在する自然=善のコードにも注目する必要がある。では、自然=善のコードとはどのようなもので、正しい情報を提供し「リテラシー」を高めるという「ニセ医学」批判の目的とはどのような関係にあるのだろうか。……つづきはα-Synodos vol.210+211で!
5.多ヶ谷有子「中世キリスト教と仏教における地獄の恐怖――死後の魂の救いの可能性をさぐる」
キリスト教世界における地獄と仏教における地獄との違いとは?それぞれの国の文学、絵画の中で生々しく表されてきた庶民の「地獄への恐怖」を読み解きながら、どちらにも共通する「死後の救いを求める」という普遍的な人間性を見出します。
※本稿は、『関東学院大学文学部 紀要 第128号(2013)』からの転載であり、2009年度および2010年度における関東学院大学文学部人文科学研究所の研究助成を受けた研究の一環として、発表されたものである。
1.はじめに―死後の魂の行方について
ヨーロッパ中世哲学の著名な学者の山田晶博士は、「日本の地獄は、キリスト教の煉獄に当たる」と語ったことがある(山田晶1986:66-81)。この言葉は、魂の救済(死後の魂の行方)の本質の一側面を表している。魂の救済とは、死後の魂の最終的な落ち着き場所が望ましい結末になり得るかどうかの問題である。
「魂の救済」という言い方は、「キリスト教の視点を前提にしている」、あるいはあまりに「抹香(まっこう)くさい」と受けとめられる恐れがないではない。しかし、「死後の行方」という問題についていえば、どのような言い方をしようが、言わんとすることの本質は同じである。死後の魂の行方は、いかなる宗教にとっても本質的な問題であり、宗教に関わらない立場の者にとっても、命を考える時には本質的な問題にならざるを得ない。
筆者は基本的には、死後の魂の行方の問題は、宗教に関わろうとそうでなかろうと、人間の本質的な問題であると受けとめている。問題の領域を広げると焦点が曖昧になるため、本章では魂の救済の視点にたち、キリスト教および日本仏教の天国あるいは極楽の対比にある地獄・煉獄観について考察し、山田氏の言葉の意味するところを明らかにしたい。
2.キリスト教世界に見られる地獄と煉獄
2-1.抒情詩が歌う死後の魂の行方
ヨーロッパ、中世後期、13世紀以降の宗教抒情詩は、特に、フランシスコ会の托鉢修道士による民衆教化に、大いに効果があったと言われる。宗教抒情詩は民衆の教化のために、キリスト教の基本的な教え(たとえばカテキズム)の内容を短詩の形にしたものである。歌うメロディは、しばしば当時の流行り歌に乗せたという。内容は、大きく、(1)キリストを讃美する歌、(2)マリアを崇敬し、日々、とりわけ臨終に際してとりなしを願う歌、(3)そしてやがて訪れる死に備え、この世の無常に心を向け、よく生き、死後の審判の後に天国に入れるよう心せよと教える死と無常の歌、の三つに分けられる。死と無常をうたう宗教抒情詩のテーマは、四終、すなわち死、審判、天国、地獄であり、死後の彼方にあるものを教える。
まず、宗教抒情詩が前提している死者の運命、つまり死者の魂がどこへ行くかの考え方を整理しておきたい。
旧約聖書によれば、元来死者は“sheol”(シェオール)と呼ばれる場所にくだると考えられていた。しかしバビロン捕囚(597-538B.C.)以後のヘブライ人には、善人と悪人は死後異なる場所に行き、悪人は死後も苦難を受けると信じられた。紀元前2世紀のころから、ダニエル書にあるように、死者の復活が信じられ、永遠の命と永遠の罰の思想が信じられるようになった(ダニエルXII:2)。古代イスラエルの時代に、エルサレムの南に「ヒノムの谷」と呼ばれる谷があり、その場所では生贄が焼かれた(エレミアVII:31,他)。そこは後に動物や犯罪者などの亡骸が焼かれる場所となり、終末のとき「地獄」の門が開かれるところとして知られていた。この谷はギリシア風に「ゲ・ヒノム」と発音され、新約聖書では“gehenna”(ゲヘンナ)と呼ばれ、永遠の罰の場所、「地獄」の意味になった(cf.『新カトリック大事典』1998:II,1182-84)。
地獄は、教義的にいえば、中世時代では、悔悛をせずに大罪を犯したままの状態でこの世を去った魂が永遠の罰を受ける場所と受けとめられていた。キリスト教では、審判は死後すぐにくだされる私審判と、世の終わりに行われる最終的な公審判がある。最後の公審判以後は、死者(すべての人類)の行き先は、天国と地獄の二ケ所である。しかし公審判以前において、死後の世界は、天国、地獄、煉獄に分かれ、暫定的な行き場としての煉獄が存在するとされた。……つづきはα-Synodos vol.210+211で!
プロフィール

シノドス編集部
シノドスは、ニュースサイトの運営、電子マガジンの配信、各種イベントの開催、出版活動や取材・研究活動、メディア・コンテンツ制作などを通じ、専門知に裏打ちされた言論を発信しています。気鋭の論者たちによる寄稿。研究者たちによる対話。第一線で活躍する起業家・活動家とのコラボレーション。政策を打ち出した政治家へのインタビュー。さまざまな当事者への取材。理性と信念のささやき声を拡大し、社会に届けるのがわたしたちの使命です。専門性と倫理に裏づけられた提案あふれるこの場に、そしていっときの遭遇から多くの触発を得られるこの場に、ぜひご参加ください。


