2015.11.05

日常に埋め込まれたエボラ出血熱――流行地ギニアに生きる人びとのリアリティ
シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「最前線のアフリカ」です。
はじめに
家族が死に行く姿を目にし、アフリカはいま悲しみに満ちている/病に伏した仲間に触れてはいけない/亡くなった家族や友達にも触れてはいけない/すべての人が危険にさらされている/若き者も年老いた者も、家族のために立ち上がろう/エボラ・・・それは見えない敵/エボラ・・・医者を信じよう
これは、2013年12月からはじまった西アフリカでのエボラ出血熱(Ebola Virus Disease、以下EVD)の流行を受け、翌年10月にリリースされたキャンペーンソング「Africa Stop Ebola」の冒頭である。この歌詞、特に最後の「医者を信じよう」の部分を見て、どのような感想を持つだろうか。「そんな基本的なところから訴えなければならないの?」と驚くだろうか。
だが、前半のやや感傷的な雰囲気を一蹴するかのようなインパクトを持つこの一言こそが、この歌の主旨だ。歌は、「もし具合が悪くなったら、医者たちが助けてくれる/医者はエボラを食い止める「希望の星」である/あなたたちを助けてくれることを保証する/だから、医者を信じよう」とつづく。
Tiken Jah Fakoly(コートジボワール)やSalif Keita(マリ)、Mory Kanté(ギニア)など、アフリカを代表する歌手が集まり、医療サービスへの信頼の重要性とEVD克服への希望を、フランス語やそれぞれの母語で歌い上げている。
プロデューサーの発表によれば、非公式のリリース直後に25万のコピーが出回ったという。しかし、流行地では、この歌の存在を知らないという人が少なくない。この歌を届けたいはずの相手に届いていない可能性がある。
2015年7月末、このキャンペーソングに携わったアーティストたちが主導した音楽イベントがギニアの首都コナクリで催された(中川, 2015)。それは、EVD撲滅をテーマにしたオリジナル曲のコンクールの決勝戦を兼ねていた。だが、会場へ足を運んだわたしの友人のギニア人たちは、「招待状がなければ入れない」と言われて入場できなかった。
わたしはその翌月、セネガルの首都ダカールのホテルで偶然、このコンサートの模様が特集されたテレビ番組を目にした。最後まで映らなかった客席には、誰が集まっていたのだろうか。EVDにかかわるできごとのはずなのに、現地の人びとの姿が見えてこない。
本稿では、今回のEVD流行の経緯を概説するとともに、一般的な報道からはこぼれておちてしまう、流行地ギニアに生きる人びとの反応と、そこから見えてくるEVDをめぐるリアリティの一片の提示を試みる(注)。
(注)本稿は、2008年から現在までギニアの人びと(国外に移住している者を含む)を対象としたフィールドワークで得られたデータに基づいている。
流行の規模と国際社会の反応
EVDの発生は1995年から2年ごとに確認されてきたが、1回の流行における最大感染者数は、2000年のウガンダでの425人だった。他方、今回の流行における感染者は2015年10月14日現在28,454人、死者は1万人を越え、史上最悪の事態となっている(WHO, 2015)。加えて、100万人以上が暮らす都市部での感染確認や流行期間の長期化は、過去に例を見ない。西アフリカでの発生もはじめてのことである。
2014年8月8日、WHOは「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)(注)」を宣言した。同時期、EVDの流行が国家の安全保障に対する脅威になると、各国政府から非常事態宣言が出された。ただし、各国政府の態度は一枚岩ではない。特にギニア政府は当初、他の二国と異なり、国境の閉鎖や軍の動員については難色を示し、人びとの動きを封じ込めることは逆効果だという見解を示していた。
(注)PHEIC、Public Health Emergency of International Concern:2015年10月1日に国際保健規約緊急委員会第7回会議が開催され、西アフリカにおけるEVDの流行が引き続きPHEICに該当すると結論付けた。
こうした動きに従って、日本の外務省も感染症危険情報を発出し、渡航計画者には不要不急の渡航の延期を、在留邦人には早期の退避の検討をそれぞれ勧告した(注)。その翌月には、同流行を国際の平和と安全に対する脅威と認定する国連安全保障理事会決議2177が採択され、国連エボラ緊急対応ミッション(UNMEER)が設置された。安保理が保健関連の緊急会合を開き、決議を採択したのははじめてのことだった。こうして、世界的な緊急課題としてEVDは認知された。
(注)2015年10月14日、感染症特有の注意事項として付記してきた在留邦人への退避の検討を促す文言が削除された。
ただし、2014年3月にギニア保健省が同国内でのEVD発生をWHOに報告した時点では、国際社会は事態を重くとらえていなかった。経済的影響を懸念したギニア政府による過小報告を批判する声もあるが、過去のケースと同様にアフリカでの局所的かつ一時的なものだと軽視した国際社会の責任も大きい。こうして対応が遅れるなか、EVDは地域をまたぎ国境を越え、生活のための移動を重ねる人びとを介して広がっていった。
わたしたちとEVD
遠く離れたアフリカでのできごとのリアリティがいよいよ日本(人)に突きつけられたのは、日本国内での疑い例が報じられたときだろう。それは、冒頭のキャンペーソングがリリースされた2014年10月のことである。
このとき、たとえばインターネット上には「エボラ!やばくない?」「うちに近いんだけど!」「日本も終わりだー」など、EVDの特徴を十分理解しているとは言いがたいコメントが溢れかえった。以後、日本国内ではこれまでに8つの疑い例が報告され、その度に出されるニュース速報が世間を騒がせた。過剰な報道とは裏腹に、結果はいずれも陰性だった。
こうしたことが8回繰り返されるうちに、世間の反応は、EVDに対する不安や恐怖よりも、「またか」「どうせ違うでしょ」という呆れや無視が優勢になっていった。日本では現在も、流行地域に21日以内に渡航した者の帰国・入国後の健康監視がつづけられているが、流行のピークが過ぎ、日本国内でのEVD関連の報道がすっかり減ったいま、EVDは再びわたしたちとは無縁のものとなりつつある。
見えにくさ、伝わりにくさのリアリティ
リベリアは、2014年8月から10月における感染者の急増とその後の急減を経験した(WHO, 2015)。ホットスポットは、人里離れた土地ではなく、総人口の約四分の一が暮らす、情報と人間の中心地である首都モンロビアだった。
治安部隊による地域の封鎖や外出禁止令などの強制的で暴力的な措置がとられると、住民たちは激しく抵抗し、それに対して更なる圧力がかけられた。道路に横たわり死にゆく人、家族の死を嘆く声などが町を覆った。あいさつ時の握手やハグは危険行為として認識され、それまでの習慣は一新されたという。こうした辛い経験と引き換えに、感染者の急減と2015年5月に一度目の終息宣言にたどり着いた。
他方、ギニアの感染者数の推移は、リベリアのようなはっきりとしたピークを示さず、横ばいがつづいている。人びとの習慣を一変させてしまうような鬼気迫る場面の経験は、リベリアに比べると少ない。首都コナクリに暮らす人びとからは、「またEVDの話か!それはもう飽きた!」と失笑されたこともあった。それはとても素直な反応だ。なぜなら、「身近なところに感染者がいない」からだ。
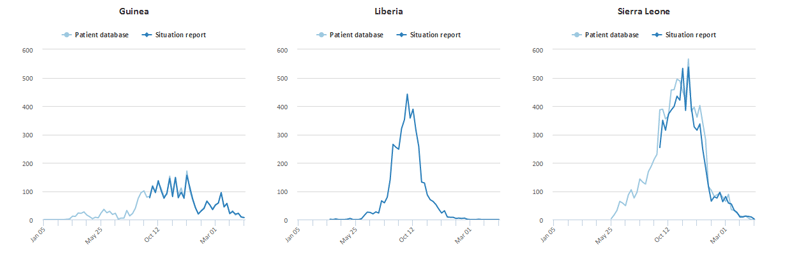
泥棒やケンカなどの噂は瞬く間に広がるのに対し、病気に関する情報は日頃から伏せられがちだ。万が一、感染者が身近に出たとしても、周囲からの批判や差別を想像すれば、死因を口にすることなどできるはずがない。
コナクリの貧困地域の一つで、人と家がひしめきあっているM地区では、通りに出れば必ず知り合いに会う。このM地区ではこれまでに少なくとも10人を越える感染者が出ている。直近の感染ルート源となった患者が出たR地区では、すでに千人規模が監視の対象となった。しかし、これらの地区では、住民が感染者を特定することは容易ではない。
カバクドゥという有名なコメディアンが出演するドラマのひとつに、息子をHIVで亡くした家族が、その死因を村の人に隠し叱責されるというエピソードがある。HIVを恥とし、周囲からの非難に怯えるがゆえについた嘘がストーリーの軸となる。カバクドゥは、「それはよくない!お前もあいつも、ドアも窓も椅子も全部がHIVになるぞ!」と怒鳴り散らす。このセリフが笑いを誘うという点はなかなか理解しづらいが、周囲の反応を危惧して物事を隠そうとするという態度や感覚は、わたしたち日本人にも通じるものだ。かれらに限ったものではない。

ギニア保健省やWHO、支援団体が啓発活動に注いだ努力は計り知れない。その一つに、携帯電話のSMSを利用した方法がある。
しかし、SMSは主に中高生などの識字率の高い若い世代のあいだで使われるコミュニケーションツールであり、「元気?」などと数単語だけのやりとりが一般的で、重要な情報伝達に使われるものではない。
そもそも「携帯会社からのプロモーションメッセージが多いから、メッセージをいちいちチェックしていない」という人も多い。指の色が変わるほど強く押さなければ反応しないニセiPhone、粉々、真っ黒、虹色の液晶画面のままのガラケー。かれらにとって携帯電話の文字情報はオプションにすぎず、音声通話や音楽再生機能が重要なのだ。
更新されつづける信頼関係
既存のコミュニティリーダーを頼った啓発活動に寄せられる期待は大きい。チーフなどの絶対的な存在を有するコミュニティでは、トップダウンの情報提供は効果的かもしれない。しかし、ギニアの場合、コミュニティ構造は単純ではなく、都市部のように複数のエスクニックグループが混住する地域となれば、さらに複雑さを増す。
トップダウン構造があったとしても、組織化されているのはそのトップ部分に限られ、一般の人びとはややこしく流動的な信頼関係によって構成されている。地縁、血縁、職縁を保ちつつも、日々より有利なコネクションを手繰り寄せていかなければ、生きていくことはできない。
一つの屋根の下に暮らしていたとしても、隣で寝ていたとしても、同じ石鹸を使っていたとしても、情報交換という意味でのコミュニケーションをあまりとらないということもしばしば見られる。
「かかりつけ医」のバリエーションが豊富であることは、想像できるだろうか。「病気や伝統的な薬による治療に詳しい人」の存在は、現地では一様一定ではない。その症状のみならず、症状が出た年齢や季節によって、頼る人は異なる。その基準は、同居/別居、親族/非親族、付き合いの長さなどから生まれるものというより、むしろ、それぞれの「暫定的な身近さ」が鍵となる。
たとえば、成人するまでは近親者内の目上の人(主に叔母や祖母)を頼る。生家を出た後も、近親者を頼ることもあれば、そのときにつきあいの深い友人を伝手にし薬を処方してくれる人を探すこともある。しかし、その友人とのつきあいが何らかの理由で断たれれば、また別の頼れる人を見つける。

道で知り合った気の合う人との会話から薬の情報を得ることもあるし、市場の一角に構えられた薬の材料を専門に扱う人のところに自ら赴き、相談しながら材料を揃えることもある。病院や診療所での診察や、薬局にあるフランス製の薬の購入を好むこともある。家の近くの商店、あるいは症状が出ているときに偶然目にした路上販売者から、中国やインドのものと思われる薬らしきものを1錠だけ買うということもある。
頼りたい相手が雨季になると冠水してしまう道路の近くにいるならば、乾季に限った「かかりつけ」となる。症状がひどく呪いが疑われた場合は、duléと呼ばれる呪医を呼び出し、儀礼を伴った治療をおこなうこともある。家族にも誰にも告げず、自分の判断で国をまたいで伝統的な治療を受けに行くこともある。
こうした入り組んでいて変化もしやすい人間関係の渦にある人びとに対して、「医者を信じよう」と訴えることの心もとなさを、アフリカ出身の歌手たちは忘れてしまったのだろうか。
プレ・エボラの視点
英医学雑誌『ザ・ランセット』(The Lancet)が2015年8月3日、WHO主導による新規EVDワクチンの臨床試験(医療従事者を中心に7651人が接種)の中間結果として、そのワクチンの有効性と安全性を発表した。このワクチンには、EVD終息へと向かう大きな一歩としての期待が寄せられている。
WHOの取り組みも第3フェーズへと入り、その目的も、感染防止をメインとしたものから、ワクチンを用いたコントロールや回復者へのケアなどへと移行している。また最近の報道では、EVDからの回復者の後遺症や差別問題、EVDがもたらした現地医療サービスへの影響などの扱いが中心となっている。
たとえば、マラリアやコレラといった死をもたらす可能性のある疾患がEVDの陰に潜んでしまっているという指摘(Khaddaj, S. and Forget, C., 2015)や、身体的な後遺症と同様に食欲不振などを伴う精神衛生上の負の影響についての報告などがある(Rettener, 2015)。
いまや、国際社会の関心は「ポスト・エボラ」へとシフトしている。しかし、ギニアのEVD流行はまだ終息していない。ポスト・エボラというEVDの流行から現地のできごとをとらえるのか、あるいは、現地の日常生活からEVDをとらえるのかによって、物事の見え方は異なる。
たとえば、2015年9月末、流行終息を祝うコンサートがギニアで開かれたことが報じられた。「エボラ流行終息へ秒読み、ギニアで一足早く「祝賀コンサート」」というニュースタイトルから、わたしたちは何を感じるだろうか。危機感がなく楽観的な人びとの姿に眉をひそめるだろうか。それとも、終息してよかったと安堵するのだろうか。
このコンサートは、EVDと同等あるいはそれ以上に、選挙という社会的イベントとの結びつきが強く、EVD撲滅や有名な歌手のステージを強調することによって集客をねらったものだったと言われている。開催を知っていたけれど行けなかった人にその理由をたずねると、野外コンサートの危険さや入場料をあげる。EVDというテーマを恐れたわけではない。
そのほかの例として、「エボラ、エボラ」と手を叩きながら踊りはしゃぐ子どもたちがいて、それを怒鳴りつける大人がいたとする。叱る理由は、EVDを話題に出すことではなく、電話しているそばで騒がしくすることにある。
EVD関連の報道のなかでは、EVDを前提とした社会や生活が描写される。他方、現場では日常を淡々と生きるなかの一片としてEVDは存在する。EVDと別のトピックが結びつきフォーカスされることはあるが、ギニアに暮らす人びとにとって、EVDは特別視するものではなく、日常に埋め込まれた不幸や不運の一つに過ぎない(中川 2015)。こうした現地社会の文脈を十分に把握することは、医療支援活動にも不可欠である。
ただし、問題が生じた後にはじめられた考察には、現地の論理を活動の疎外要因と位置づけてしまう危うさがある。そのうえ、EVDの流行という社会的危機に対して流行地の人びとが選んだ付き合い方、つまり、よりよい暮らしを営むために紡ぎだす日常の尊さとリアリティは、わたしたちに伝わりにくくなる。
ギニア政府が当初、他の国と足並みを揃えた国境封鎖や軍の介入を拒否したことは、EVDの封じ込めという点から考えれば、正しい判断だったかどうかはわからない。よって、この方針には賛否両論ある。しかし、強制的な措置は大きな混乱を呼ぶ可能性が非常に高く、効果的ではないと判断した所以は、現地のことを熟知していたからにほかならない。後に起こった啓発活動へのコミュニティ単位での激しい反発(道の封鎖や投石などによる意思表示)がそれを物語っている。
今後も当分のあいだ、流行地に対する地道な情報発信は間違いなく求められるだろう。それは、気が遠くなるような作業である。模索され試みられてきたさまざまな手段の「取りこぼし」への気づきはその一歩となる。また、日常生活におけるEVDの位置づけに迫ることは、現地の人びとのみに責任を負わせるような分析と、そこから生まれる対策の脆さや乱暴さを知る契機となる。
ポスト・エボラへと関心が向かういま、流行後の時間と空間にEVDの議論を閉じ込めることを避け、流行前からつづく日常のなかでEVDを問い直すこと、つまり「プレ・エボラ」の視点が、わたしたちに求められているのではないだろうか。
■参考文献
Khaddaj, S. and Forget, C., 2015, Ebola, malaria and cholera: Complicit killers that need to be fought simultaneously, ideas for development, Agence Française de Développement
(http://ideas4development.org/en/ebola-malaria-and-cholera-complicit-killers-that-need-to-be-fought-simultaneously/ 2015年10月15日アクセス)
Plucinski, M. et al. 2015. Effect of the Ebola-virus-disease epidemic on malaria case management in Guinea. The Lancet Infectious Diseases,
(http://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(15)00061-4.pdf, 2015年10月15日アクセス)
Rachael Rettner, 2015, Ebola’s Most Disturbing Impact On Survivors Is Social Rejection, HUFF POST HEALTH NEWS,
(http://www.huffingtonpost.com/2015/06/23/ebola-survivors-rejection_n_7644986.html 2015年10月22日アクセス)
WHO, 2015, Ebola Situation Reports
(http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports, 2015年10月15日アクセス)
WHO, 2015, Ebola data and statistics
(http://apps.who.int/gho/data/view.ebola-sitrep.ebola-country-LBR-20151014-graph?lang=en, 2015年10月25日アクセス)
中川千草, 2015a,「エボラがつなげるわたしとかれらの日常」, NPO法人アフリック・アフリカ『アフリカ便り』
(http://afric-africa.vis.ne.jp/essay/alphabet_e1.htm, 2015年5月1日アクセス).
中川千草, 2015b,「ギニアにおけるエボラ出血熱の流行をめぐる「知」の流通と滞留」, 『アフリカレポート』No.53、pp.57-61, 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所(http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Africa/2015_16.html , 2015年10月15日アクセス)
プロフィール

中川千草
博士(社会学)、龍谷大学農学部講師・NPO法人アフリック・アフリカ会員。これまでの研究テーマは資源管理と地域づくりで、ギニアでは塩づくりや魚の燻製に従事する人びとの生活に着目したフィールドワークを実施してきた。現地でのエボラ出血熱の流行を受け、エボラ出血熱をめぐる「知」の生産や流通、レジリエンス、さらには研究者としての応答責任についての研究をはじめた。


