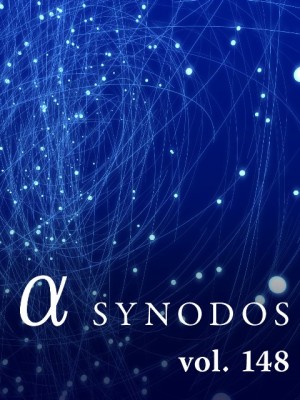2014.05.15
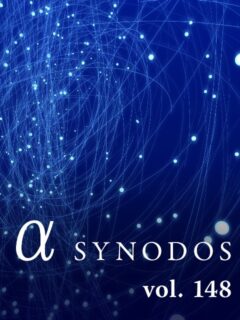
オウム真理教事件の真の犯人は「思想」だった
麻原彰晃は事件の真相を理解していない
一連のオウム事件の主犯が誰であったかについては、一時期、「麻原彰晃の独断」説と「弟子たちの暴走」説のあいだで論争が行われていました。
最近『文藝春秋』(2014年2月号)で公表された井上嘉浩氏の手記に見られるように、オウムにおいては、たとえ上層の幹部であっても、「麻原の意志に背けば殺される」ということが陰に陽にほのめかされていましたので、どちらかといえば前者の方が事実に近かったと思いますが、オウム問題を広い視野から捉えようとする場合、そのことは実は、さして重要ではありません。
事件のすべては麻原の独断によるものであり、また同時に、その「真相」のすべてを麻原が了解していたかといえば、とてもそうは考えられない。麻原の裁判は一審で打ち切られ、二審と三審が行われませんでした。言わば、「デュー・プロセス・オブ・ロー(法の適正手続)」が堅持されなかったわけで、そのことはやはり批判されなければなりません。
しかし、一審の経緯を見る限り、麻原はそもそも、現在の法制度によって自分が裁かれるということ自体を拒絶しており、審理の途中から妄想の世界に逃げ込んでしまった。もし裁判が継続されたとしても、その状況はおそらく変わらなかったでしょう。
また何より、オウム真理教とは何だったのか、教団の活動が何故あのようなお粗末な悲喜劇に終わってしまったのかということを、世界のなかで誰よりも理解していないのが、麻原彰晃という人間なのではないかと私は思います。彼の思考は濃密な幻想によって覆われており、ある意味で彼は、そうした幻想に突き動かされて行動した人間の一人にすぎなかったのです。
オウムの思想の根幹は「霊性進化論」
それでは、麻原彰晃やオウム真理教を動かしていた幻想とは、一体何だったのか。オウムの思想に対しては、私はすでに『オウム真理教の精神史』『現代オカルトの根源』という二著によって一通りの分析を終えていますので、ここではもう詳しくはお話ししませんが、現在の私は、オウムとは、「霊性進化論」という思想潮流から生まれた宗教団体の一つであったと考えています。
霊性進化論の源流を作り上げたのは、一九世紀後半に活躍したロシアの霊媒、ブラヴァツキー夫人という人物です。当時の世界では、ダーウィンの進化論が広範に普及し、その影響から、旧来のキリスト教信仰が大きな打撃を受けていました。こういう状況のなかでブラヴァツキーは、スピリチュアリズムと進化論を融合させることにより、「神智学」と呼ばれる新たな宗教運動を創始したのです。
それによれば、本当の意味での人間の進化とは、肉体のレベルではなく、霊性のレベルにおいて生じる。人間は地球において、七段階の進化を遂げることが予定されており、現在は物質的進化の極点に達しているが、今後は霊的進化への反転が生じることになる。簡単に言えば、「物質文明から精神文明への大転換」が起こることが予言されたのです。神智学の教えはその後、ニューエイジやポストモダンの諸思想に幅広い影響を与えていきました。
オウム真理教の最終目的もまさに、「物質文明から精神文明への大転換」を起こすことに置かれていました。オウムの内部でそれは、「種の入れ替え」という言葉によって表現されていた。現在の人間は物質的欲望に縛られて動物化しているため、これを粛清し、その後に霊性のレベルの高い神的人類から成るユートピアを建設する──それこそがオウムの目指していたことでした。オウムが起こしたあらゆる事件は、このような最終目的を実現するための布石として行われたのです。
なぜ裁判はオウム問題の本質に触れることができないのか
オウム真理教の本質を理解すれば、それによって引き起こされた数々の事件が、「思想犯」と呼ぶべきものであったことが分かります。ゆえに、オウム事件に対して裁定を下そうとすれば、本当は、その主要な原因となったオウムの思想自体の理非を問わなければならない。
ところがここで、大きな問題が現れます。それは、現行の日本の法制度においては、思想そのものの罪を問うことができない、ということです。
そんなことは当然だ、と思われるかもしれませんが、歴史を振り返ってみれば、思想の罪を問わないというのは、むしろ例外的な事態であることが分かります。人類の長い歴史のなかでは、社会を脅かす恐れのある「危険思想」に対しては、何らかの仕方で制裁が加えられるというのが普通でした。
ナザレのイエスが処刑されたのは、彼の説く「神の国」の思想がローマ帝国の統治にとって障害となると考えられたからでしょうし、中世のキリスト教社会では、「異端審問」がたびたび行われました。戦前の日本でも、治安警察法や治安維持法といった「治安立法」が存在していた。それらの法に基づき、「国体の変革」につながる恐れがあるという理由から、共産主義の他、数々の新興宗教団体に対する弾圧が行われてきたのです。
しかしながら、近代の社会が成熟するにつれ、「治安立法による思想犯の取り締まり」は、次第に行われなくなりました。それは、国家の安全よりもむしろ、信教の自由や思想・表現の自由を優先すべきだという見解が、大勢を占めるようになったからでしょう。
とはいえ、成熟した近代社会において、思想犯がまったく現れなくなったというわけではありません。戦後の日本の例で言えば、連合赤軍事件とオウム事件が、思想犯の典型であったと見ることができます。
連合赤軍やオウムは、それぞれの思想に基づき、現在の世界の体制を根本的に変革することを目指していた。ゆえに、これらの事件を裁こうとすれば、先ほど述べたように本当は、その思想の理非をまず問わなければならない。
しかし現行の法制度では、思想の罪を問うことはできず、法廷での議論はどうしても、武器をどうやって調達したか、犯行計画を事前にどこまで知っていたか等、あくまで即物的な内容に限定されてしまう。そのため、裁判に長い時間を費やしているにもかかわらず、いつまで経っても本質的な問題に話が及ばない、という不全感が残り続けることになるのです。
くれぐれも誤解しないでいただきたいのですが、だからといって私は、あらためて思想の罪を法廷で裁くべきだ、「異端審問」や「治安立法」を復活させるべきだ、と考えているわけではまったくありません。思想の罪を問わないということは、これまでの人類が長い試行錯誤を重ねた末にようやく獲得した原理であり、安易にこれを手放すことが、社会の改善につながるとは到底考えられないからです。
しかしながら、再び話を戻せば、法廷で裁かれないからといって、思想の罪自体が消えるわけではない。私たちはむしろ、思想の罪を法廷では裁かず、信教の自由や思想・表現の自由を最大限尊重するということに決めているのだから、そういった罪や責任は、国家権力が介在しない仕方で、市民社会の側からの自発的意志や見識に基づいて問うていく必要があります。私たちはそのことを、もっと明確に自覚しなければなりません。
オウム事件に対する思想的責任の範囲
オウム真理教事件に対する思想的責任や、道義的責任について考えてみると、問題の範囲は実に、オウムという団体やその信者のみに限定されなくなります。オウムの思想は、彼らがまったく独自に編み出し、彼らだけが主張していたという性質のものではないからです。
先に述べた霊性進化論というオカルト的な宗教思想、さらには、「物質文明から精神文明への大転換」といった類の空虚で粗雑な革命論は、一九世紀から現在に至るまで、世界中で蔓延し続けてきました。ここでは話を日本に限定すれば、オウム問題については、宗教団体の分野、アカデミズムの分野、メディアの分野のそれぞれにおいて、思想的・道義的責任が問われるべきではないかと思います。
まず、宗教団体の責任について。麻原彰晃はオウムを創始する以前、さまざまな新興宗教に関与し、それらの団体が公刊している著作を通して、霊性進化論の枠組みについて学んでいきました。特別な修行を積むことによって神に進化しうる、物質文明が遠からず破局を迎えるといった観念は、オウム以前にも多くの宗教団体によって主唱されていた。そして、日本の多くの人々は、それらの団体の教えを通して霊性進化論の思想に慣れ親しむようになり、そのなかで、よりラディカルな実践に身を投じたいと考えた一部の人間たちが、オウムに足を踏み入れていったのです。
私は昨年公刊した『現代オカルトの根源』において、霊性進化論の思想的系譜について具体的な考察を行ったのですが、それが原因でいくつかの宗教団体から抗議を受け、団体の広報担当者と長時間にわたって議論を交わすことになりました。結果的に、それは私にとって、教団の内実をうかがい知ることができるという点で、とても興味深い体験となりました。
とはいえ、その際にこちらから、団体の教義の性質について公開の場で議論させてほしい、あるいは、オウム事件に対する団体の見解を公にしてほしいという要望を出したのですが、残念ながらそれらには応じてもらえなかった。しかしオウムは、七〇年代以降に生じた「宗教ブーム」という大きな流れのなかから現れた存在であり、そうしたブームを同じくした他の教団が、完全に思想的責任を免れうるということにはならないはずです。
次に、アカデミズムの責任について。これに関しては、すでに多くの機会に言及してきましたので、詳しくは述べません。しかしながら、大学においてニューエイジやポストモダンの思想が蔓延していたことが、多くの大学生がオウムに入信した要因の一つとなったことは、疑うことができないでしょう。また、そうした種類の空言が未だに完全には消え去っていないことは、人文学の信頼性と生産性を大きく損なっていると考えます。
霊性進化論の関連で少し付言しておけば、人文系の研究者のなかには、神智学の代表的な思想家の一人であるルドルフ・シュタイナーの信奉者が、かなりの数で存在しています。一昔前に流行した「シュタイナー教育」の影響が、まだ残っているということなのでしょうが、しかし研究者であれば、シュタイナーの思想や世界観が全体としてどのような性質のものであったのか、もっと明確に認識しておくべきであると思います。
最後に、メディアの責任について。もう忘れられたことかもしれませんが、麻原彰晃はオカルト雑誌『ムー』の愛読者であり、一時期はそのライターとしても活動していました。彼の思想は『ムー』によって育まれ、また初期のオウムの活動は、『ムー』によって広く認知されていった。
しかしオウム事件以後も、同誌は編集方針をまったく変えることがなく、オウムの教義と同工異曲の「メシア論」や「陰謀論」を掲載し続けています。また、霊性進化論的なオカルト思想は、徳間書店の「超知ライブラリー」や「5次元文庫」といったシリーズの書物によって、今も広められている。大手出版社が堂々とオカルト本を売り捌いているというのは、世界的に見ても稀な現象でしょう。
二〇一二年にオウム最後の逃亡犯として逮捕された高橋克也被告の所持品のなかには、中沢新一氏の『三万年の死の教え──チベット『死者の書』の世界』(角川書店)という書物が含まれていました。この書物は、NHKが一九九三年に放映した、「チベット死者の書」というスペシャル番組をもとに作られています。
番組の内容は、一言で言えば、チベットの寒村における素朴な葬式の様子を描いたものにすぎないのですが、派手なCGや音響を随所に用いることにより、「死後の世界」をリアルに実感させるような演出が施されている。
この番組は当時、オウムが布教の手段の一つとして使用していたことが知られています。地下鉄サリン事件以前は、こうした番組が公共放送でも流されていたのです。今でもDVDが販売されていますので、一度視聴してみれば、オウムが日本社会で受容され、成長していった当時の雰囲気を実感できるかもしれません。
オウムとは直接的な関わりを持たなかったとしても、その背景となる思想を広めてしまったことで密かに良心を痛めている人は、今も日本社会のなかに沢山いるのではないかと思います。
来年は、地下鉄サリン事件から二〇年という節目を迎え、最後のオウム裁判となる高橋被告の裁判も始められるでしょう。本当にオウム事件を総括したいと思うのであれば、責任を感じつつも口ごもっている人々に勇気をもって発言してもらい、オウムの思想が日本全体にどこまで浸透していたかを明らかにすることが必要です。
※本稿を受けて、5月15日配信「α-synodos vol.148」に、大田氏へのインタビューを収録! ご購読はこちらから https://synodos.jp/a-synodos
特集:現代と宗教のあいだに
・大田俊寛「オウム真理教事件の真の犯人は「思想」だった」
・大田俊寛インタビュー「『空虚な幻想』から目を覚ますために――オウム真理教事件の根底にあるもの」
・宇都宮京子「呪術と合理性」
・猪瀬優理「宗教から離れるということ」
・岸政彦「もうひとつの沖縄戦後史(5)――ユタとイルカと近代化」
プロフィール
大田俊寛
1974年生まれ。一橋大学社会学部卒業、東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻宗教学宗教史学専門分野博士課程修了、博士(文学)。現在、埼玉大学非常勤講師。専攻は宗教学。著書に『グノーシス主義の思想――〈父〉というフィクション』(春秋社)、主な論文に「鏡像段階論とグノーシス主義」(『グノーシス 異端と近代』所収)、「コルブスとは何か」(『大航海』No.62)、「ユングとグノーシス主義 その共鳴と齟齬」(『宗教研究』三五四号)、「超人的ユートピアへの抵抗――『鋼の錬金術師』とナチズム」(『ユリイカ』No.589)など。