2015.12.01

人生の最期に聴きたい曲ってなんだろう?
死に直面している人って、自分がどういう人生を生きてきたか隠せないんです――アメリカで認定音楽療法士としてホスピスで活動し、昨年『ラストソング――人生の最期に聴く音楽』(ポプラ社)を上梓した佐藤由美子さんはそう言います。知っているようでぜんぜん知らない音楽療法。 演奏技術はどれだけ必要? 自分のために演奏することもあるの? そして、「佐藤由美子にしか弾けない音楽」ってなんですか? 荒井裕樹さん(障害者文化論)と語り合います。(構成/山本菜々子)
音楽の根っこ
荒井 『ラストソング――人生の最期に聴く音楽』(ポプラ社)の刊行から1年たちますけど、ご好評ですね。実はゲラの段階で読ませてもらっていたので、関係者以外ではぼくが最初の読者なんです(笑)。
ずっと佐藤さんとお話ししたいとおもっていて、でも、冷静にお話しするために少し時間が必要でした。ようやくお話できるかな……という気持ちになりました。それくらい力のある本です。
佐藤さんは、ずっとアメリカのホスピスで音楽療法士をされていて、今は日本で活動されていらっしゃるようですね。
佐藤 そうです。アメリカでは10年仕事をしていて、2013年に日本に帰ってきました。いまは、青森慈恵会病院の緩和ケア病棟で働いています。
荒井 この本を読んで面白いとおもったのは、音楽が人の記憶に寄り添っていくところです。死を前にした人たちが、音楽を聴いて人生を振り返りますよね。どんな人だって、自分の人生を振り返るのは大変なエネルギーが必要だとおもいます。その大変な作業を音楽が支えている。
やっぱりアメリカでは、信仰や文化に根をはる音楽がありますね。賛美歌だったり、移民の人がそれぞれの家族の中で伝えてきた祖国の民謡だったり。音楽が脈々と受け継がれている様子が本からもうかがえて、興味深かったです。
日本だと、そういった音楽って何でしょうね?
佐藤 日本でも、戦時中や戦後まもなくは音楽が娯楽として大きなウエイトをしめていて、ラジオから流れてきた音楽を家族みんなで歌ったり、そんな経験があったはずです。
荒井 ああ、美空ひばりとか?
佐藤 そうそう。みんなで歌って苦しい時代を乗り越えたように、音楽が重要な役割を果たした時代が日本にもあったんですよね。アメリカの場合はビッグバンドの曲を聴きながらみんなでダンスをして、そこで今の旦那さんや奥さんに出会った、ってことが昔は多かったんです。音楽にまつわる思い出もたくさんあったようです。
昨日も、藤山一郎の「長崎の鐘」(作詞・サトウハチロー 作曲・古関裕而 1949年)という曲を聴きたいという方がいらっしゃいました。なぜですか?と聞くと、「原爆の歌だから」っておっしゃって、やはりその年代の方にとっては意味深い歌だったりするんですね。
ですから、国の違いよりも、もしかしたら年代的なものなのかもしれません。アメリカでも感じていたんですが、私たちの年代が70歳、80歳になったとき、そういう音楽ってまだあるのかなっておもいます。いま流行って聴いていても1年後には誰も聴かない曲ばかりです。
荒井 音楽療法というと「音楽を聴いて気持ちよくなること」とおもわれがちですけど、そう単純な話ではないですね。音楽って文化や歴史に深く根を張っていて、それを生活の一部として生きてきた人がいる。
佐藤 そうですね。地域性もあります。青森あたりだと「津軽海峡・冬景色」(作詞・阿久悠 作曲・三木たかし 1977年)とか「北国の春」(作詞・いではく 作曲・遠藤実 1977年)とか。そういう歌に響くものがあるようです。
荒井 全然知らない曲をリクエストされることもあるわけですよね?
佐藤 はい。さっき言った「長崎の鐘」も知りませんでした。でも、知らない曲でも、その人を探るきっかけになるんですよね。なんでこの歌が聴きたいのか。
荒井 音楽療法士も人間ですから、得意・不得意とか、好き・嫌いはありますよね?
佐藤 そうですね。アメリカで活動していたときは、カントリーのリクエストも多かったんですけど、わたしはちょっと苦手で(笑)。カントリーって演歌と似てるんですよ。ストーリーなんですよね。失恋したり、悲しいことがあったり。歌詞に共感するところがあると、セラピーとしてはいいこともあるんですが。
荒井 アメリカだと、ロックン・ロールをリクエストされたりは?
佐藤 ありますよ(笑)。ジミ・ヘンドリックスが大好きな患者さんがいたんです。その方はALSで、全く動くことができず、話もできなかったのですが、ジミ・ヘンドリックスをずっと一日中聴いていて、できることがそれだけだったんです。
わたしははじめ、ハープを弾いたんですが、何を弾いても泣くんです。すごく辛かったんでしょうね。ジミ・ヘンドリックスが好きだから、わたしも一曲くらいとおもってギターの伴奏で歌いました。わたしがやっても、もちろんジミ・ヘンドリックスにはならないですが、彼は笑顔を見せてくれました。
音楽療法では必ずしも自分が演奏できないものもあり、その場合は録音したものを一緒に聞いたりしても良いわけです。彼は昔ロックバンドでドラムを弾いていた人だったので、彼の録音したCDを一緒に聴いたこともあります。それだけでも、彼のことを知ることができたし、貴重な経験でした。

セラピーってなに?
荒井 日本では「セラピー」という言葉が少し偏ったイメージをもっていますね。
佐藤 どういうイメージなんですか?
荒井 「受け身」で考えられているように思います。なにか気持ちの良いことを「してもらえる」「与えてもらえる」というイメージです。
ぼくは都内の精神科病院のアトリエをずっと応援していて、そのアトリエが毎年「“癒し”としての自己表現展」というアート展をやっているのですが、以前、来場者から「癒しと聞いて来てみたけど、観てもぜんぜん癒されませんでした」と言う感想が寄せられたそうです。
佐藤 ははは(笑)。確かにそういうイメージがあるのかもしれません。
でも、本当に苦しい過去があったり、病気があると、本来の意味で回復したり成長したりするためには、ものすごくエネルギーも時間もかかります。よく「音楽療法CD」などを見かけますが、聞くだけで「うつ病が治った」なんてことにはなりません。
結局は、本人が「良くなろう」という気持ちを持って、勇気を出して何かをやろうとする必要があります。私たちの仕事はあくまでもその環境をつくることだとおもうんですね。
荒井 「セラピー」とか「癒し」って、すごく能動的というか、困難を伴う主体的な行い……ちょっと言い方が固すぎるな。つまり「その人自身がやる」ことの比重が大きいんでしょうね。
佐藤 現代社会って、なんでも簡単に治そうとするじゃないですか。薬飲んで終わりとか、これを読めば結婚できるとか、これをやれば解決!みたいな。そういうことに飛びつきますよね。でもそんな簡単な話はないわけですよ。
もちろん簡単に治るにこしたことはない。でも、時間も努力も必要っていうのが本当なんです。でも、本当のことは人気がない。みんなお手軽な方にいってしまうんですね。
荒井 ちなみに、佐藤さんは現場に勤め始めてからどれくらいで「セラピストとしてやっていける!」って感じましたか?
佐藤 まだまだです(笑)。最初のインターンシップのときは、本当に頭がおかしくなっちゃったとおもいました。人が目の前で亡くなったり、今までそんな光景をみたことなかったので、音楽療法以前の問題でしたね。
でも、それをグリーフカウンセラーの人にいうと、「大丈夫、ぼくたちもクレイジーだよ」って言われて。それが普通だったんですね。でもすごく衝撃的なことでした。25歳で、そういうところに踏み込んでいくこと自体がすごくショックだったんです。
荒井 人が死ぬときって、静かにロウソクが消えるような感じではなくて、その周りでいろんなドラマが起こるじゃないですか。
佐藤 死に直面している人って、自分がどういう人生を生きてきたか隠せないんです。本の中では「死は人生を映し出す鏡だ」という言葉を引用しましたが、お金持ちであろうとなかろうと、学歴があろうとなかろうと、みんな同じような状態で死に直面している。もう何もつくろえないんですね。
今までどんな人生を歩んだのか、どんな風に愛されて、どんな風に嫌われてきたのか、その人の全てを見てしまうことになります。その場にウェルカムで迎えてもらえたときは、家族の一員としてものすごく貴重な時間を過ごすことになります。責任も感じます。

荒井 それを職業として続けるのは大変ですよね。途中でやめてしまう人もいるでしょう。
佐藤 「だいたい3年が平均だね」って教官に言われました。長く続けるのは難しい。今でも、たまに思うんですよね、これって一生できる仕事ではないのかなって。いまは、週に1回ほどしかやっていないんですが、それでもすごく疲れます。
荒井 人間関係って「物理的な近さ」とか「会っている回数」とか「血縁関係」とかを越えちゃう部分があるんですよね。
佐藤 ええ、そうなんです。不思議ですよね。もちろん長くかかわった人の方が、亡くなった時のグリーフ(悲しみ)は大きいとおもいますが、一回だけでもすごくインパクトがあったりする。
つい最近、夫とこんな話をしました。知り合いが自殺したのですが、夫は一回しか会ったことないらしいんですね。でも、「なんでこんなに気になるんだろう」って本人は不思議に思っていて。
でもそういうことじゃないんですよね。回数とか、自殺とか自然死のような死に方でもなく、死自体が人に与えるインパクトって大きいんです。
荒井 「近しい人の方がより悲しいだろう」とか、「一回しか会ってない人なんだから、亡くなってもそんなに辛くないでしょ」っておもわれがちですよね。
佐藤 こういう仕事をしている人は自分で言い聞かせている部分はありますよね。でも、それが積もり積もって疲れちゃって、辞めちゃったりとか、患者さんと距離を置くようになっちゃったりとか。
そういう意味では10年間フルタイムでやってきたから、この本を書いている時は休む時期だったのかなっておもいました。
技術はどれだけ必要?
荒井 音楽療法士にとって、演奏の技術ってどれくらい必要なのでしょうか?
佐藤 音楽療法士になるには、まずミュージシャンでなくてはいけないとおもっています。音楽をやらなくても、セラピーだったら他の方法がありますから。
音楽を使うからには、道具としていかに使うのかでセラピーの良し悪しが決まってきます。「えーっと、ギターのコードが……」って、演奏そのもので苦労していたらセラピーにならないわけです。
それから、クライアント(患者さんやご家族)の表情や状態を気にしながら演奏しなければならないので、演奏だけに集中できないんです。クライアントを気にしつつ、でも自然に楽器をこなせるだけの技術は必要ですね。
とはいえ、もちろんセラピストとしての勉強も必要です。ですので、音楽療法士になるにはピアノとギターと歌、それをやりながら心理学や音楽療法の理論などを勉強します。
荒井 資格を取るまでに何年くらいかかるのですか?
佐藤 音楽療法士の資格は国によって違いますが、アメリカの場合は少なくとも4年の大学のカリキュラムを終了する必要があります。それが終わればインターンシップが6ヶ月。その後試験があって、受かれば資格がもらえます。
荒井 佐藤さんは、いくつの楽器を演奏できるんですか?
佐藤 ピアノとギター、アイリッシュハープ、ウクレレ、ネイティヴアメリカンフルート。あと打楽器は基本的にやらないといけないので、西アフリカのドラムのジャンベもやります。もうちょっと上手くなりたいんですけどね。でも本当の意味で上手になろうとすると、一つの楽器だけでも一生かかりますから。
荒井 それは、セッションの中で必要に迫られて覚えていったんですか?
佐藤 そうですね。たとえばギターだとコードを弾いて歌うのが一般的です。もちろんテクニックがもっとあれば、歌いながらメロディーを弾いたりできるんですけど、そこまではできません。
でもハープの場合は、ピアノみたいにメロディーも弾きやすいんです。なので、演奏と同時に歌をやるためにはハープが必要でした。で、ウクレレをやり始めた理由も、音楽療法士の仕事って体力が必要で、楽器を背負っていくことが多いので、体が保たなかったんです。
荒井 そうか、持ち運びに便利かどうかもあるのか。
病院の中で絵を描いている人たちのことを見ていても、似た部分がありますね。絵を描きたい人を「支える側の人」も、やっぱり絵の技術は必要です。
作業療法でアートを取り入れている病院もありますけど、病院の職員さんは医療や福祉の学校を出ていますから、「油絵を描きたい」というリクエストが出ても応えられません。どうしても「水彩絵の具で我慢して」とか、悪意はなくても表現の幅を狭めてしまうことがある。
でも、その人が響くものって、色鉛筆かもしれないし、油絵かもしれないし、パステルかもしれない。やっぱり、ある程度の技術って必要なんだなっておもいます。
佐藤 そうですね。「自分が癒されるからハープが良いんだ」って思いこんでも、「ハープ=天国」だと感じるから嫌だって人もいます。「わたしがこの歌が好きだから」「この絵しか教えられないから」ではなく、その人にとって何が響くかですよね。そこを中心に考えた時、やっぱりこちらがいろんなものを提供できたほうがいい。
「良い支え手」とは?
佐藤 昨年、荒井さんから勧められて、さきほど話に出てきた「“癒し”としての自己表現展」に伺いましたよ(※「第21回“癒し”としての自己表現展」平川病院〈造形教室〉主催2014年12月2日~6日 八王子市芸術文化会館・いちょうホール)。そのとき、自分の精神障害の症状をそのまま絵に描かれている方にお会いする機会がありました。
「ものすごく勇気がいることだったのではないでしょうか」と聞くと、「自分ではそうはおもっていません。でも、よく言われるので考えてみたら、こんな表現をできる環境があったらからこそ、ぼくはできたんだとおもいます」っておっしゃったんです。
それがまさにセラピーだとおもいました。そういう環境があるからこそ、少し勇気を持ってやってみようとおもえる。でも、環境を作ることって簡単にできることではないんですよね。
荒井 表現って、自分以外の他人がいないと生まれないんですよね。だれか見てくれている人がいる。相談に乗ってくれる人がいる。でも干渉しないで良い具合に放っといてくれる。そういった人と人の「間」に働く力が大事なんでしょうね。
いくつかアート活動を取り入れている医療施設を見てきましたけど、「良い支え手」って草食動物みたいな人が多いような気がします(笑)。気配を消して空気に馴染んじゃう人。
そういう人と話をしていると、「障害のある人とない人」っていう区別の発想自体がないんですね。もちろん最初はあったんでしょうけど、長い現場経験の中で溶けてなくなっている。ほんとうに話していて面白いですよ。ただ、残念ながらそういう人は表に出てこない。草食動物なので(笑)。

佐藤 わたしもホスピスの仕事をやりながら、最初の1、2年は自閉症とか障害をもったお子さんとの音楽療法もやっていて、グループで障害のある子もない子も一緒にやっていたんです。
すると障害のない子たちが「なんでこの子はやらなくてもいいのに、ぼくはやらないといけないの」と言いだすことがあります。その時、この子は喋れないから歌わなくてもいい。その代わりこの子は手話ができるから手話をするし、君は歌えるんだから歌うんだよ。ただその違いがあるだけであって、それ以上のことではない。そういう違いを乗り越えて、どう付き合うかを子供のうちから教えることがすごく重要です。
大人になってからも同じで、コミュニティーミュージックセラピーのように、障害のある人もない人も同じバンドで演奏するようなことがすごく重要だとおもうんです。
荒井 「できること」の範囲がちがう人たちを一緒にすると必ず揉めます。でも、その揉め事を時間をかけて消化した先に豊かさがあります。
いま「障害のある人」と「アーティスト」のコラボレーションを謳ったアート展が盛り上がっていて、すごい規模で「お金と人」が動いているみたいです。自宅や作業所で細々と絵を描いていたのに、いきなり大きな美術館で展示されるようになって、注目のされ方も変わる。もちろん、それが励みになる人もいると思いますが、体調をくずす人が出てるという話も聞こえてきます。
この盛り上がりにはパラリンピックの影響もあって、確かにお祭りは大事だと思うんですけど、もっと大事なのは「祭りの後」です。ほんとうに、今までと同じ歩調で歩き続けることができるのか心配です。
佐藤 取り巻く人たちも長い目で見ているわけではなくて、その時の利益を考えてやっているのかもしれませんね。
荒井 アート業界を盛り上げたいのか。それとも日々の生活の中で絵を描く人を支えたいのか。やっぱり「良い支え手」って、10年とか20年とかのスパンで、同じ歩調で歩き続けることができる人なんだと思います。そうなると、きっと「支える・支えられる」の区別もなくなっていくでしょう。
以前、平川病院〈造形教室〉のことを本に書いたとき、素晴らしい活動を広く紹介したいけど、そのことで余計な雑音が入ってしまうんじゃないかと悩みました。幸か不幸か、ぜんぜん売れなかったので大丈夫みたいです(笑)。
佐藤 でも、本人にOKをもらって、名前をだしてやってらっしゃるから、そこに意義があるとおもいますよ。それだけでもすごく大きなステップですよ。自分の苦しみを絵に表現して、それが名前と一緒に本に載るってこと。そして彼らのアート展にいくとご本人に会えますからね。それがすごいです。
荒井 売れなかったですが(笑)。
佐藤 良い本が売れない時代ということにしましょう(笑)。
「押し付けない」こと
荒井 佐藤さんが考える「良い音楽療法士」の条件ってなんですか?
佐藤 当たりまえですが、人間として信頼できる人。わたしは一緒に仕事する人に対しても、自分の家族をこの人に安心して任せられるかどうか、という目でみています。
あと、「押しつけない」ことでしょうね。病院にいる人は立場的に嫌だって言えない場合もあるんですよね。もし嫌だって言ったら良い治療が受けられないんじゃないかとおもっていたり、言葉がしゃべれなくて気持ちを伝えられなかったりする場合もある。
そこで、セラピストが「自分はクラシック音楽がすごく癒されるから、他の人にも聞かせてあげよう」とおもったとします。でも、相手はそれが嫌かもしれない。だけど、なかなかそれが言えない。だから、「押し付けない」ってすごくセンシティブな問題だとおもうんですよ。
荒井 佐藤さんがなさっているホスピスでのセラピーだと、動けない患者さんを訪ねる形になりますからね。その分、「押し付けない」ことが大事なんですね。ちなみに、初めてお会いするクライアントの場合、一番気を使うのってどんなことですか?
佐藤 うーん、どうでしょうね……。わたしはやっぱりなるべく常に自分らしくいることがベストだとおもっています。もちろんセラピストによって手法は違うとおもいますが、わたしの場合はその人の本来の姿を知りたいのであれば、わたし自身も本来の姿を見せる必要があるとおもっているんです。
わたしは誰に対しても自分のことを話したいとおもうタイプじゃないので。逆に人の話しを聞いていたほうが楽なんですよね、自分のこと言わずに。ただ、それだと向こうも心開いてくれないから、わたしの性格上、常に気をつけていかないと、「うん、うん」ってどんどん聞くだけになっちゃう。
荒井 ちなみに、英語と日本語で困ることってありますか?
佐藤 ずっと困っていますよ(笑)。
荒井 アメリカのホスピスでお仕事をされていた時は、会話もメモも英語でされていたんですよね? でも『ラストソング』は日本語で書かれている。
佐藤 いざ日本語で出版するとなったとき、どういうふうに翻訳するのかかなり悩みました。全然日本語が出てこなくって。
荒井 具体的には、どのあたりが難しかったですか?
佐藤 たとえば、セラピストとして「being fully present」が一番難しいことであり、すごく重要なことだとおもうんです。英語で「present」って「ここにいる」って意味ですよね。「全部がここにいる」とか「自分の全てがあなたに集中している」とかって、日本語でどういうのかなってずっと考えていたんです。
直訳しても「完全にここにいます」になっちゃって、よくわからなくなってしまう。ある日、「心から寄り添う」って言葉を聞いてぴったりだなっておもいました。言われてしっくりくる言葉って、直訳してわかるものじゃなかったりします。

自分と他人との距離
荒井 音楽療法士って、自分のために演奏することもあるんですか?
佐藤 もちろんしますよ。わたしの恩師に、「仕事を続ける秘訣を教えてください」と聞いたら、「自分と音楽との関係を忘れないこと」っておっしゃったんです。自分のためだけに演奏することを忘れてはいけない。その関係を保っていないといけない。確かにその関係が薄れていると、セッションにもすごく影響が及ぶんですよね。
荒井 ぼくも忙しく仕事していたりすると、小説を読みながら「おもしろいな」っていうより先に「これ授業で使えるかも」って、そういった発想になっちゃうんですよね。
佐藤 そうなんですよ。音楽を聞いても、「あ、この曲セラピーにいいかも」とか「こういう風に演奏したらどうかな」って考えはじめてしまう。
だから、普段自分で聴いている音楽はインドの音楽とか、絶対にセッションでは使わないようなものが多いです。それだとあんまりセッションのことは考えないでいれる。それに津軽三味線とか、自分では演奏できないものだったりすると、素直に感激できたりしますよね。
わたしが一番好きなのは、山みたいに誰もいないところに行って、誰のためでもなく演奏することで、そういうことがもっとできればいいんですよね。
荒井 佐藤さんの本の中で一番気になったのは「セラピストは休みの日には患者さんに会いにいってはいけない」ってところです。目の前に心から寄り添うべき人がいる。でも近づきすぎてはいけない。難しい問題ですよね。
佐藤 そうですね。わたしは患者さんが亡くなったときにすごく落ち込んだことがあって、そのときに同僚が言ってくれたことがすごく印象に残っているんです。
「自分が心を開かなかったら相手も心を開いてくれない。あえて、もう亡くなるとわかっている人に対して深くて意味のある関係を作っていくことが私たちの仕事だ。そこが一番難しいところだ」って言われて。
本当にそうなんですよね。でもそこは大変なところで、患者さんはその人以外にもたくさんいたわけですから、その人に自分の全てを費やしてしまったら他の人にフェアじゃない。
やはり、自分の限界を認めるってことでしょうね。お葬式で演奏することも、できるときとできないときがあるんです。それをやってしまうと次の患者さんを看るエネルギーもないなというときは、あえて「できません」って言います。自分の限界を知るってことが境界を持つってことなんじゃないかなとおもいます。
あと、やっぱりクライアントは「友達」でもないんですよね。距離感がないとセラピーは成り立たないし、常にクライアントを中心に考えないといけないんです。その人にとって、何が必要かということを。
クライアントとの「距離」と言いましたが、もしかしたら「責任」なのかもしれません。音楽療法士には倫理(Ethic)というものがあります。たとえば、「take advantage」はしてはいけません。
クライアントは悩みがあったり、障がいや病気があったりして、だれかの支えを必要としています。そういった状態、英語だと「vulnerable」なのですが、日本語だとなんと言えばよいか、とてもむずかしいですね。とにかく、弱っていたり、困っていたりする人を前にして、セラピストは優位に立つようなことをしてはいけないし、そういった人から頼られて、自分の力を過信してはいけません。
これはセラピストの側が理解しておかなければいけません。距離というよりは、倫理的な面での、プロフェッショナルとしての責任の問題です。
「聞かせる歌」じゃダメ?
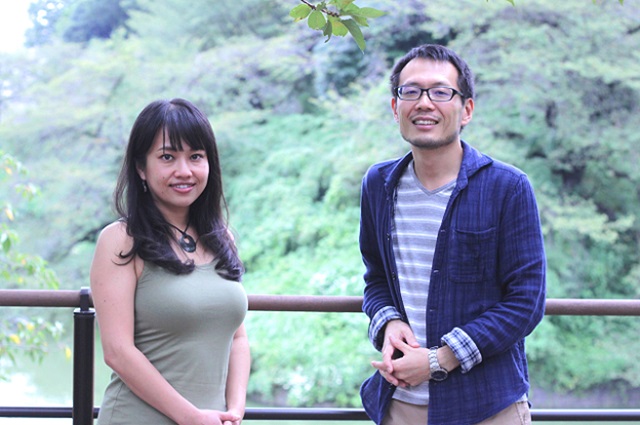
荒井 最後に、これはみなさんに聞いている質問です。「佐藤由美子にしか弾けない音楽」ってなんですか?
佐藤 さすがですね。こんな質問考えるなんて(笑)。わたしにしか弾けない音楽なんて、もちろん無いとおもっていますが、最近このことを考える機会がありました。
ユニバーサル・ミュージックから『ラストソング』を軸にしたCDが出ました。その中の一曲「浜辺の歌」はわたしが歌ったんです。
そのレコーディングの数日前に、プロデューサーが、実際にわたしのセッションを見に来たんです。すると、レコーディングでも「音楽療法をやっている時の雰囲気で、患者さんに歌ってるみたいにやってほしい」と言われました。
でも、実際にレコーディングしてみると、何十回もやっても「違う」と言われるんです。どうしても、セッションの時の声にはならないんです。最終的には「何回もやっていると歌手みたいな歌い方になってしまう」と言われて、レコーディングの最初の方に録ったものをつかいました。
荒井 歌手みたいになってしまう?
佐藤 はい。何回も歌っていると、「聞かせる歌」になってくるんです。セッションでやっているのは聞かせる歌ではなくて、セラピーとしての歌だった。客観的にプロの人に言われると、やっぱり違いってあるんだって初めておもいました。
確かに、患者さんに対して歌ったりしている時はその曲のことはあまり考えていないわけです。その人のことを見ているから。
荒井 「音楽療法士は歌手じゃない」って、おもしろいですね。
佐藤 歌手のように歌わないってことですよね。「わたしを見て」という歌手の歌い方だと、やっぱり心に響かない。プロデューサーはわたしに「(ハワイの)フラの歌い方だよね」と言いました。つまり心に響く歌い方だから、そのままレコーディングでやってほしい。でも、なかなかそこに近づいていかない。それは音楽と音楽療法の違いでもありますよね。
わたしはずっとパフォーマンスを専攻してやってきましたけど、音楽を極めようとしてやっている演奏家って、基本的には自分と音楽との関係なんですよね。いかに芸術としてやっていくかという問題で、それを見る人がどうこうではない。でも、音楽療法では自分と音楽の関係ではなくて、音楽とクライアントの関係なんです。
先日、初めてプロのカメラマンの方とお会いして、「最近、写真から『自分』がいなくなっていることに気づいて、少し上達したかなとおもうんです」とおっしゃったんです。それってすごく似ているなっておもって。あくまでも、音楽や写真などの媒体を道具として使うには、自分がなくならないといけない。ある意味セラピーと繋がるところがあって、いろいろ考えさせられました。
「わたしだけにできる音楽」という質問とは違うかもしれませんが……。
荒井 以前、この対談に出てくれた今野健太さんという彫刻家も、一番の理想は石が初めからそうなっていたようになること、という主旨のことを言っていました。自分が彫ったのではなくて、石が初めからそうなるべくそうなっていたようになるのが理想なんだと。
佐藤 アーティストなのに珍しいですよね。
荒井 表現って突き詰めるとそうなるのかもしれないですよね。世界で自分にしかできない表現を突き詰めていくと、自分がなくなってしまうのが一番良い表現になる。
佐藤さんのお話を伺っていて、音楽療法士って「その人の人生にとって、もっとも必要な音楽がそこにある状態」を作り出す人なんじゃないかと思いました。とても大変で、でも素敵な仕事ですね。
佐藤 ちなみに、荒井さんは最期に聴きたい曲ってありますか?
荒井 んー、なんだろう……いま選ぶとすれば『はらぺこあおむし』かな。よく子どもと歌っています。
たぶん、あちこちの家庭でも保育園でも歌われていると思うんですけど、ぼくにはぼくなりの思い出があるんですよね……って、なんだろう、なんか泣いてしまいそうだ(笑)。
プロフィール

佐藤由美子
ホスピス緩和ケアを専門とする米国認定音楽療法士。バージニア州立ラッドフォード大学大学院音楽科を卒業後、オハイオ州シンシナティのホスピスで10年間音楽療法を実践。2013年に帰国。帰国後は青森県在住。15年8月からは青森慈恵会病院の緩和ケア病棟で音楽療法士として働いている。著書に『ラスト・ソング』(ポプラ社)がある。ハフィントンポスト(日本版)でBlog「佐藤由美子の音楽療法日記」掲載中。

荒井裕樹
2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二松学舎大学文学部専任講師。東京精神科病院協会「心のアート展」実行委員会特別委員。専門は障害者文化論。著書『障害と文学』(現代書館)、『隔離の文学』(書肆アルス)、『生きていく絵』(亜紀書房)。


