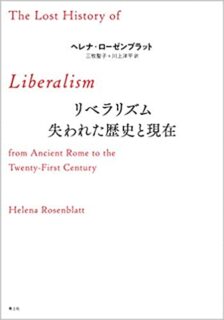2021.02.05
「リベラル」なリベラリズムの再生に向けて――『リベラリズム 失われた歴史と現在』ヘレナ・ローゼンブラット(青土社)
『リベラリズム 失われた歴史と現在』は、Helena Rosenblatt, The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-first Century, Princeton University Press, 2018の全訳である。著者ヘレナ・ローゼンブラットは、ジャン=ジャック・ルソーおよびバンジャマン・コンスタンの研究者として知られる。それらの個別研究を踏まえ、またフランス・リベラリズムについての共著の公刊も経て(注1)、より広い視点から政治思想としての「リベラリズム」の歴史そのものの見直しに正面から取り組んだのが本書である。
本書は、リベラリズムに対する攻撃でも擁護でもなく、古代ローマから今日に至るまでのリベラリズムの二千年の歴史の叙述である。今日、リベラリズムはその信頼を失い、非リベラルなデモクラシーの台頭は著しい。しかしリベラリズムを放棄したり、逆にひたすら擁護する前に、まずはリベラリズムとは本来的に何であったかを確認しようというのがその意図である。アプローチとしては、「リベラリズム」の定義を予め定めたうえで歴史を叙述するのではなく、「リベラル」ないし「リベラリズム」という言葉が歴史のなかでどのように捉えられたかという「言葉の歴史」が辿られていく。なぜなら、著者によれば、定義ありきの方法は必然的に時代錯誤(アナクロニズム)に陥るからである。
もっとも著者は、単にリベラリズムの歴史の概説を著そうとしたのではない。本書は、今日主流となっている英米系の個人主義的で権利基底的リベラリズムとは異なる主流のリベラリズムを、「失われた」リベラリズムとして再興しようとする。すなわちそれは、古代ローマに由来する道徳的価値である「リベラルさ(liberalitas)」を継承した大陸系のリベラリズムであり、「リベラル」の本義に基づくいわばリベラルなリベラリズム――著者の表現ではないが――である。
著者は、ロックやミルといった主要な思想家のみならず、知られざる思想家や、意図せずしてこの歴史に貢献した人々の存在に光を当て、また、英米のみならずフランスやドイツの思想家が重要であることを明らかにしていく。そして、最も論争的な点であるが、リベラリズムとは、今日そう見なされているような個人主義的で権利基底的な政治理論ではなく、むしろ共同体的でも宗教的でもあるような義務に基づく道徳性に満ちた立場であると示す。
著者はまず、一九世紀に生まれた「リベラリズム」ではなく、その元にある「リベラル」という言葉の起源を探り、それを古代ローマに見いだす。そこでリベラルとは、社会的紐帯の核心を表現する言葉であり、共通の事柄への献身や他者との助け合いを義務とする利他的な精神を意味していた。リベラルのこうした意味は、ヨーロッパ中世においても、愛、同情、慈善といったキリスト教的価値を加えつつ継承され、リベラルとは、神の人間への愛のごとくに、物惜しみなく与えることという含意をもつようになる。こうした社会的紐帯としてのリベラルという価値観は、ルネサンスと宗教改革、そして啓蒙主義の時代においても基本的に継承されていく。
この純粋に道徳的な価値としてのリベラルの意味が大きく変化するのが、フランス革命期である。本書においてフランス革命の意義は、リベラルを人物ではなく制度についての形容として用いた点に見いだされる。革命は、人間の平等な権利に基づいて、旧来の貴族の特権を廃止し、教会財産を没収した。従来の貴族主義的な「リベラル」の観点からすれば、これは「豚のような群衆」(バーク)によるリベラルな価値観の蹂躙である。だが、著者によれば、革命においては、その担い手たちの野蛮さとは別に、革命の樹立した政治制度そのものを形容する言葉として、リベラルという表現が用いられ始めたという。
もっとも、リベラリズムとデモクラシーとの間には、常に緊張関係があった。リベラルたちは、革命がもたらした人権の原理を肯定しながらも、人民主権が恐怖政治のような災禍に行き着いたことを踏まえて、いかにデモクラシーを適切に抑制するかを課題とした。その典型が、人間の境遇が平等化していくデモクラシーを不可避の趨勢と認めながらも、それをうまく飼い慣らすことを課題としたトクヴィルであった。
このようなある種のデモクラシー批判としてのリベラルの立場は、七月革命(一八三〇)以降、労働者階級が次第に階級意識をもち、貧困層の救済を政府に求めるようになるにつれ、挑戦を受けるようになっていく。一八四八年に革命が起こり(「二月革命」)、社会主義者を首班とする臨時政府が生まれ、周辺各国へも波及すると、ヨーロッパ中のリベラルは、この労働者階級の運動主義への恐れから、それを抑制するために、最終的にナポレオン三世やビスマルクなどの権威主義や教皇権と結託していくことになる。
リベラルたちは、社会主義革命を、社会制度の不正に対する正当な不満の発露として見ることはなく、社会主義という利己的で物質主義的な哲学に毒された労働者の、知的・道徳的退廃の帰結としてしか捉えなかったのである。それゆえにリベラルたちが事態の打開のために提唱したのは、社会制度の改革ではなく、民衆の道徳性の回復、そのための宗教の刷新、あるいは「人類教」という新たな宗教の構築であった。
リベラルたちの労働者への冷淡さには、古来のリベラルの徳化の理想が透けて見える。リベラリズムの唱道者は、広い意味では紛れもなく民主主義者ではあったが、彼らの民衆への信頼は、あるがままの民衆にではなく、彼らが道徳的になりうるという点に向けられていた。リベラルは、社会主義を、民衆の物質的な利己主義をそのまま肯定しているにすぎないと批判し、代わって彼らを道徳的にすることを追求したのである。著者によれば、「リベラル・デモクラシー」という言葉はこの文脈において誕生した。
こうしてヨーロッパで育まれてきたリベラリズムは、二〇世紀転換期に入るとアメリカへと導入されていく。このとき、リベラリズムの最先端にいたのはドイツであった。一九世紀後半、ドイツの経済学者たちは、悪化する貧困問題の解決を求めて、自由放任を批判して政府介入を志向した。自由放任(レッセフェール)が行き詰まりを迎える中、仏、英、米のリベラルたちは、こうしたドイツの知的実践に、新しいリベラリズムを見出していった。
しかし、その後、第二次世界大戦および冷戦という「全体主義」との戦いを背景に、リベラリズムは数世紀にわたってトランス・アトランティックな思想空間で育まれてきた意味内容を失い、とりわけ、ドイツの思想的な貢献は忘却され、個人の権利を中心とする教義へと転化していく。ドイツやソ連共産主義とのイデオロギー闘争を背景に、ニューディール・リベラリズムの唱導者は、肥大化した官僚機構の擁護者とみなされ、ファシズムや共産主義の類縁として批判すらされた。このような非難を避けようと、リベラルたちは、個人の権利の擁護をリベラリズムの中心命題として強調するようになったのである。
しかしこのことと引き換えにリベラルたちは、リベラリズムがその中心的基礎として歴史的に育んできた公共善への献身という道徳的価値を放棄することになった。著者は、リベラルたちが数世紀にわたって共同体や道徳のために戦ってきた事実、英米のみならず、フランスやドイツも多様なかたちでリベラリズムの発展に貢献してきた事実を呼び起こし、リベラリズムの「失われた歴史」を再発見し、リベラリズムは善や徳といったその中核的な価値観を回復していくべきだと結ぶ。このような結論には、現代の個人主義的リベラリズムに、本来の「寛大さ(リベラル)」を与え返すことで、リベラリズムそのものを救いだそうとする著者の切実な問題意識がうかがえる。
以上が本書の大筋だが、すべての章で、リベラリズムが女性、貧民、そして植民地に対する抑圧や差別を伴っていたことが繰り返し指摘されている点も、本書の特徴である。これは単純な補足ではない。リベラリズムが本来的に高貴さを求める道徳的価値であるからこそ、そのような基準に満たないとみなされた存在への抑圧を正当化してしまう危険をそもそもはらむことへの重要な指摘である。ただし同時に著者は、リベラルという原初的価値は、そのような抑圧そのものを自己批判する余地を備えているという点を強調し、リベラルの価値を信じるスタンスをあくまで貫いている。
(注1)French Liberalism from Montesquieu to the Present Day, ed. R. Geenens and H. Rosenblatt (Cambridge University Press, February 2012).
プロフィール

三牧聖子
同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科准教授。