2026.01.12
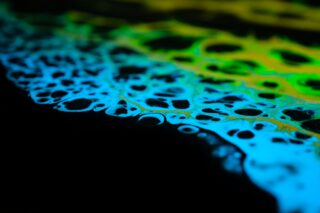
左右の全体主義を射抜く「矢」となれ――リベラリズムは「中道」ではなく「急進的」な戦う思想である
「リベラル」と聞くと、どのようなイメージをもつでしょうか。
右派と左派の間に立つ、優柔不断な「中道」?
それとも、少し古臭い現状維持の思想?
歴史が明らかにしているように、そうした認識は正しくありません。
本来のリベラリズムとは、そのような生ぬるい思想では決してありません。
それは、右からの排外主義であれ、左からの集団主義であれ、個人の自由を踏みにじる「すべての抑圧者」に対して、たった一人でも立ち向かうための鋭利な「矢」なのです。
今回紹介するのは、リベラル派のオンライン誌『Liberal Currents』に掲載された論考、「すべての反リベラルに対する矢(An Arrow Against All Illiberals)」です。
https://www.liberalcurrents.com/an-arrow-against-all-illiberals/
この記事は、私たちが忘れかけているリベラリズムの「野性」と「攻撃性」を思い出させてくれます。
リベラルは守りに入っている場合ではありません。
いまこそ「反リベラル(Illiberals)」たちに対して、反撃の狼煙を上げるときです。
1640年代からの「矢」
記事のタイトルにある「矢(Arrow)」という言葉は、17世紀のイギリス清教徒革命の時代に、リチャード・オーバートンという人物が書いたパンフレット『すべての暴君に対する矢(An Arrow Against All Tyrants)』から取られています。
当時、彼はこう叫びました。
「すべての個人には、誰にも侵されることのない自然の権利がある」
この叫びこそがリベラリズムの原点です。
王様だろうが、教会だろうが、あるいは「人民の代表」を自称する革命政府だろうが、個人の領域に土足で踏み込む奴は全員「敵」だ
――このシンプルで過激な思想こそが、リベラリズムの魂なのです。
記事は、イアン・ダントの著書『How To Be a Liberal』を読み解きながら、現代の私たちが直面している「二つの敵」を鮮やかに浮かび上がらせます。
右の「排外主義」、左の「集団主義」
現代のリベラルは、二つの巨大な力に挟撃されています。
一つは、右派による「他者(The Other)の排除」です。
移民や難民を「人間」としてではなく、統計上の数字や害悪として扱い、「我々の文化を守れ」と叫ぶ人々。
彼らは「国家」や「伝統」という集団のために、個人の尊厳を犠牲にします。
もう一つは、左派(レフト)による「アイデンティティ政治の暴走」です。
彼らは「正義」や「平等」を掲げますが、そこでも個人は軽視されがちです。
「あなたは〇〇属性だから、こう考えるべきだ」「〇〇属性の代表として発言せよ」といった圧力は、個人を固定化されたグループの中に閉じ込めてしまいます。
記事はこう指摘します。
集団内の一部の人々が、権力を持たない人々の「代弁者」として振る舞い始めたとき、危険が生じます。……左派においては、進歩的な学者や活動家が、他のすべての人々を代表して話す「異論を許さない道徳的権利」を確保してしまったのです。 (…the powerful within a group began speaking in the name of the powerless. … On the left, it meant that progressive academics and activists secured an unchallengeable moral right to speak on behalf of everyone else.)
右も左も、結局やっていることは同じです。
「集団(国家、人種、階級、ジェンダー)」を特権化し、そこからはみ出す「個人」を押しつぶそうとしているのです。
「個人」こそが最強の解毒剤である
では、リベラルはどう戦うべきか。
答えは、徹底的な「ラディカル・インディビジュアリズム(急進的個人主義)」への回帰です。
これは「自分勝手でいい」という意味ではありません。
「どんな崇高な目的(国家の栄光や社会正義)のためであっても、目の前にいる生身の一人の人間を手段として利用してはならない」という、絶対的な倫理的防波堤を築くことです。
フランス革命の際、ベンジャミン・コンスタンは気づきました。
恐怖政治(テロル)が起きたのは、個人主義が行き過ぎたからではない。
逆に、「個人主義があまりにも少なかった(too little individualism)」からこそ、あのような虐殺が起きたのだ、と。
「一般意志」や「人民の意志」という巨大な主語が暴走したとき、それを止められるのは「個人の権利」という杭だけです。
最も過激で、困難な戦いへ
この記事の優れた点は、左派的なテーマ(フェミニズムやクィア理論など)を否定せず、むしろそれをリベラリズムの文脈で「奪還」しようとしている点です。
ダントによれば、本来のフェミニズムやマイノリティの権利運動は、リベラリズムにとって脅威ではありません。
なぜなら、それらは「個人が、古い因習やカテゴリー(男らしさ/女らしさなど)から自由になり、自分らしく生きる」ための運動だからです。
リベラルは、こうした運動を「左派のもの」として遠ざけるのではなく、むしろ「個人の解放」というリベラルの本道として、積極的に取り込んでいくべきなのです。
リベラリズムは「どっちつかずの中間」ではありません。
それは、右の全体主義とも、左の全体主義とも妥協せず、たった一つの「個人の尊厳」という砦を守り抜く、もっとも過激で困難な戦いです。
私たちはもう一度、あの17世紀のパンフレットのように「矢」をつがえる必要があります。
群集心理に流されず、同調圧力に屈せず、「私は私である」と宣言すること。
その孤独で誇り高い態度こそが、憎悪と分断に満ちた現代社会を切り裂く、唯一の希望の光となるはずです。
プロフィール

芹沢一也
言論プラットフォーム SYNODOS の運営・編集を担い、現代社会における言葉の扱われ方を実践の場で扱っている。1968年東京都生まれ。アカデミズムとジャーナリズムのあいだに位置する場としてシノドスを立ち上げ、専門知を社会にひらくことを目的とした活動を続けてきた。
株式会社シノドス代表取締役。政治・社会・科学技術など複雑な問題を、どのような言葉で提示すれば議論が成立するのか、その条件を整えることを編集の役割として位置づけている。特定の思想や立場を前提とせず、論点が共有可能なかたちで提示されることを重視している。
この編集的な視点は、言語教育の分野にも接続されている。シノドス英会話 を主宰し、大人のための英語学習に取り組む。表現の暗記や会話テクニックではなく、日本語と英語における思考プロセスの違いに着目し、「分かっているのに話せない」という状態がどこで生じているのかを整理することを出発点としている。
言論という社会的な実践と、英会話という個人の実践を往復しながら、言葉が社会と個人をどのようにつないでいるのかを、具体的な場面で扱っている。


