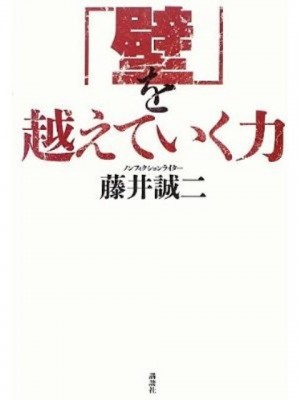2013.08.23

「いい質問」を考えない藤井誠二のインタビュー術
質問なんて重要じゃない!? 11人の半生を切り取った『「壁」を越えていく力』(講談社)著者であり、ノンフィクションライターの藤井誠二氏に聞く、インタビュー術とは。(聞き手・構成/山本菜々子)
「境界線」を走る
―― 『「壁」を越えていく力』では、11人の方を取材されています。この方達に共通する部分はどこなのでしょうか。
この本は10年間のぼくの取材の集大成で、インタビューをした11人はそれぞれ、医者であったり、俳優であったり、猿回し芸人であったり、映画監督であったりと、様々な職業についています。それぞれを繋ぐような共通点はありませんが、10年間の中で惹きつけられた人たちであることは間違いありません。
こうやって一冊の本になって、11人を並べて気がついたことは、ぼくは「境界線」を走っている人に惹かれているということです。たとえば、村崎太郎さんは猿回し芸人をしながら部落出身であることをカミングアウトしていますし、元朝鮮総聯幹部である洪敬義さんも愛国心ゆえに裁判を起こしました。性犯罪被害者である小林美佳さんも多くの人が寝泣き入りする中、名前と顔をさらして被害体験を語っています。自分の領域や場所から離れ、境界線上に生きて姿に、ぼくは引力を感じるんですよね。呼ばれている気がします。
―― 取材先を選ぶ際に、意識していたことはありますか。
ぼくが聞きたいとおもった人に行っているので、必ずしもタイムリーさを重視してはいませんでした。たとえば、「ナビィの恋」(1999)や「ホテル・ハイビスカス」(2002)で知られる映画監督の中江祐司さんを取材したのは2007年です。いわゆる「沖縄ブーム」よりも少し遅いので、あまり時事的とはいえないのかもしれません。
ぼくが中江さんに興味を持ったのは、彼と沖縄の距離感だったんです。当時の中江さんのインタビューを読むと沖縄賛美しかしていない。けれども好きの反面、警戒しているところがあって、それを聞くならこのタイミングだとおもったんです。
実は、ぼくは1ヶ月のうち10日は沖縄に住んでいます。沖縄というのは「人々はとても親切で、楽園のようだ」というメディアのイメージがありますが、一筋縄ではいかない強烈な共同体です。血縁を重視するところがあるというか。本土の人に対する風当たりが強い部分がある。
10日住んでいるだけでも大変なのに、中江さんは大学から沖縄に移住し活動を続けています。中江さんは沖縄を舞台にした映画を撮り、全国的に有名ですが「本土の人が撮っているから」とあんまり評価しない人もいるんです。閉館した桜坂劇場を復活させたりと、沖縄文化に大きく寄与しているともおもうのですが、これも評価されない。そんな中江さんが沖縄をどう見ているのか、ぼくは強く興味を持ちました。あまりタイムリーではなかったかもしれませんが、本人が封印していたものを少しずつ解き放ち語ってくれたとなぁと感じています。
カメレオンのように
―― インタビューはどんな方法でされているのでしょうか。
いろんな取材の方法があるけど、ぼくは取材相手と頻繁に会うことを大事にしています。ぼくの場合、相手を好きになりすぎるところがあって、夢にも出てくるくらいです(笑)。何度も会いにったり、ご飯を食べたり、お酒を飲んだり、旅に同行したりと、濃密にコミュニケーションをとります。でも、最初の二ヶ月くらいで、不思議なことに書きたいという気分が一気に落ちるんですよ。
相手のことをわかっちゃったから、もう書かなくてもいいかと、勝手に完結してしまう(笑)。でも、またしばらく経つと「やっぱり惹かれるなぁ」と思いなおしてくる。一度どん底に手をついてから、戻ってくるような感覚はあります。どんな人も同じようなプロセスを繰り返しながら、取材を続けています。だいたい、アポイントメントから含めると、媒体に掲載するまでに半年ほどかかります。
―― この本では、とてもナイーブな内容についても触れています。相手との信頼関係が大事だったとおもうのですが、どのように距離を詰めていったのでしょうか。
今回の場合は、相手にギャラを一切払っていません。ですから、ぼくのインタビューを受けることが面倒なのではなく、楽しいとおもってもらわないといけません。
ぼくと話すことで発見があったり、新たな自分に気づいてもらえるような関係性をつくることが重要です。そうなると、相手もぼくに聞いてくるんです「今こんなことを考えているんだけど、どうおもう?」と。その答えがぼくの中にあるとおもうから聞いてくるわけで、それは信頼されている証です。
こいつといると自分にとってプラスになり、自分でも知らなかった部分を引き出してくれる、どんなことでも受け止めてくれる、どこにも書かれていなかった自分の像を書いてくれる。そういう信頼関係を醸成していくために、11人それぞれに異なる仕掛けをしました。
職業や立場が違うので、どのようにアプローチしていくのか考えるのが一番大変だし、楽しいところでもあります。産婦人科医の宋美玄さんであれば、宋さんの本を手がけている編集者が長年の知り合いでしたので、そこから紹介してもらいました。やはり、信頼関係のある人から紹介してもらうのは重要です。それと、宋さんの場合は母方のおじいさんが韓皙曦(ハン・ソッキ)という、朝鮮史・キリスト教史研究者として有名な方なんです。
でも、宋さんはおじいさんの本を一冊も読んだことがない。だから、ぼくは韓さんの本を全部読みました。絶版のものも古本でそろえました。それを全部頭に入れていったので、孫よりもおじいさんに詳しくなってしまいました(笑)。「おじいさんのことはなんでも聞いてください」と自信を持って言え、宋さんの相談役になることもしばしばでした。
―― 知りたい情報を提供して、相談に乗ったということですね。
宋さんの場合はそうですね。海堂尊さんの場合は、Ai(Autopsy imaging、死後画像診断)の普及に取り組んでいたので、取材者という枠を超えて協力しました。当時の民主党政権時代の厚生労働省財務官だった足立信也議員の秘書が、仲のいい友人だったので、海堂さんを紹介したんです。その結果、足立議員と海堂さんがAiについて対談することになりました。その対談はぼくのブログだけにしか載っていません(*1)。足立議員はもともと問題意識が高かった方なので、その後、積極的にAiについて議会で発言して下さったようです。このように取り計らうことで、がっちり関係を組むことができます。
(*1)海堂尊氏と足立厚生労働大臣政務官との対話(2010.5.19) その1、海堂尊氏と足立厚生労働大臣政務官との対話(2010.5.19) その2
―― 取材すると共に協力して、関係性を築いていったんですね。
ぼく自身もAiの必要性を感じていたので、協力したんです。
俳優の宇梶剛士さんの場合は、インタビューをするまでにすごい時間がかかったんですよ。最初にやったのは彼と旅をすることと、酒を飲むことです。しかも、とことこんまで付き合う。周りにいる人が酔いつぶれても付き合う。朝まで付き合う。「行こう」という場所にはどこでも付き合いました。時には、飲み明かして朝8時になることもありました(笑)。
するとある日、宇梶さんにホテルのカフェに呼ばれて、「今日一日、時間があるからなんでも聞いてくれ」と言われたんです。やっぱり、ぼくが宇梶さんを観察しているように、聞く方も観られているんです。どのくらい自分に興味があるのか試されている。だからこそ徹底して付き合ってきました。
―― 宇梶さんの章は特に印象に残りました。身体に恵まれていて、「強い」からこその辛さがあるんだと、目から鱗が落ちましたね。
そうですね。強いから弱い、苦しいという気持ちと、その故に彼が背負っている自負も書くことができたとおもいます。そういう意味ではインタビュアーがよき理解者になれた瞬間でしたね。
このように、相手との距離を詰めていく方法は一人一人違いますし、毎回変えていきます。普遍的な技術はなく、いかにカメレオンのように色を変えられるのかという対応力が必要いなってくるんです。
質問はいらない
―― それぞれに違ったアプローチをしていくということですね。インタビューをする時に気をつけていることはなんですか。
よく、インタビューの時に「いい質問」を考えようとする人っているんですけど、あんまり質問って重要じゃない感じがするんです。だから、ぼくはインタビューの時に質問やメモをほとんど準備しません。
―― 質問を準備するのは鉄則だとおもっていました。
もちろん下調べとして、著作や関連する本は全部読んでいきますし、最大の準備はしていきます。なにを聞くのかも考えますし、世の中の現代性とどうこの人固有のものを結びつけていくのかも考えます。しかし、質問を考えていくと、それにとらわれてしまうところがあるとおもうんです。それよりも、ぼくと相手とでどんな科学反応が起こるのかを大事にしています。
人間って機嫌の良い日も悪い日もありますから、現場の空気や相手の出方を感じとりながら聞いていく。そのうちに、自分の中で聞きたい事が変わっていったり、明確になったり、自分の仮説や予想が外れていくといった動きが生まれてきます。その裏切られる過程がたまらなく面白いです。その結果、最後の最後になにを書いていいのか分からなくなるときもありますし、最初の興味からまったく違ったところに来ている場合もあります。
―― もっといいものが見つかるということですか。
いや、見つからないんですよ、それが(笑)。あれ、この人はもっと面白い人のはずなのにって。粘ったり切り口を変えてみることで、面白さが見えてくることもあります。自分が柔軟に対応するように追い込まれていくのも楽しいですね。
―― インタビュー中に、質問に詰まることもありますよね。普通は質問の準備がないと不安ですよね。
もちろん、これを聞きたいとおもうものはありますよ。でも、初回に聞くのではなく、二回目、三回目と何回も顔をあわせているうちに聞いています。なにかを深く聞けるのはある程度の関係性が醸成されてこそだとおもうんです。あいつにはなにしゃべってもいいなとか、安心して共有したいという風にならないと、大事なことや、きわどい質問には答えてくれません。関係性を築くのが先で、質問は後だとぼくはおもっています。
―― 特に、今回の本では出自や性暴力被害などのナイーブな話に踏み込むことが多かったとおもいます。自分の中で、「これは聞いてはだめだ」と線引きしていた部分はありますか。
それはないですね。そもそも世の中の人たちが普通は触れられないようことを書くことに意義があるわけですから、自分が遠慮して触れないというのはおかしいですよね。もちろん、初対面だったら怒られる質問もありますが、何度も会っていくうち答えてくれることが多いです。だから、自分の中で「これは聞いてはいけない」というのはないです。基本的には忌憚無く聞いています。
宋美玄さんと、彼女のオモニと焼肉を食べに行ったときに、酔っぱらって彼女の離婚話や男性遍歴を初めて聞いたんです。そのときは、酒の席だったこともあり、オモニもいっしょになってきわどい話も率直になって答えてもらったんですが、あとで「オモニの前でそれはないんじゃないの」とちょっと叱られてしまいましたが(笑)。
―― 深く関わるからこそ、本当のところを聞けると。相手に対して愛情がないとできないなと感じました。
そうですね。愛情ももちろんありますし、相手のことを好きになりすぎてしまいます。だけど、ぼくはそんなに人間が好きじゃないとこともあって(笑)。いやらしい意味も含めて人間に興味はあるんですけど、いわゆる「人間大好き」と賛美する気持ちはあまりないですね。そもそも、ライターという職業についているひとはだいたいそうだとおもいます。特に「人物モノ」を書く人は、意地悪な視点で人間を見ている部分があります。でも、相手のことは好きになると。その微妙なバランスがあります。
単に好きなだけなら、ミュージシャンが新曲を出したプロモーションにインタビューする御用ライターと代わらない仕事になってしまう。もちろん、その仕事を否定しているわけではないですが、ぼくはそういうインタビューはしたくないんです。だって、相手がなにを聞くのか分かっているインタビューなんて、答える側からしたら面白いはず無いじゃないですか。相手がどう答えていいのか分からないような質問をしたいし、分からなかったら次ぎ会うときまでに考えて聞かせて欲しいとおもっています。そんな付き合いをしたい。
ノンフィクションの書き手にも、いろんなタイプがいます。人物を追ったルポでも、大時代的なものを書きたい人は「○○はまさに昭和の妖怪だった」といった書き方をします。そういうのは読み物としてかっこいいとはおもうけど、あんまりピンとこなくて。時代とリンクさせるのは最小限にして、どちらかというと人物にスポットを当てたいんです。
「時代が生んだ申し子」の一言で説明したくないという気持ちがあります。だからこそ相手と深く付き合って、この人なら書いてもいいとおもってもらえるような関係性作りに力を入れていきたいし、自分なりに捉えてみたいという気持ちがあるんですよね。それこそがノンフィクションを書く原動力になっているのだとおもいます。
プロフィール

藤井誠二
1965年愛知県生まれ。ノンフィクションライター。当事者に併走しつつ、綿密な調査・取材をおこない、社会や制度の矛盾を突くノンフィクション作品を数多く発表。TBSラジオ「BATTLE TALK RADIO アクセス」のトークパーソナリティーや、大阪朝日放送「ムーブ!」で「事件後を行く」、インターネット放送で「ニコ生ノンフィクション論」などのコーナーを持つなど幅広い媒体で活動をつづけてきた。大学では「ノンフィクション論」や「インタビュー学」などの実験的授業をおこなう。著書に、『17歳の殺人者』、『少年に奪われた人生』『暴力の学校 倒錯の街』『この世からきれいに消えたい』(以上、朝日文庫)、『人を殺してみたかった』(双葉文庫)、『少年犯罪被害者遺族』(中公新書ラクレ)、『殺された側の論理』『少年をいかに罰するか』(講談社)、『大学生からの取材術』(講談社)、『コリアンサッカーブルース』(アートン)、『「悪いこと」したらどうなるの?』(理論社)、『体罰はなぜなくならないのか』(幻冬舎新書)など多数。