2014.02.17
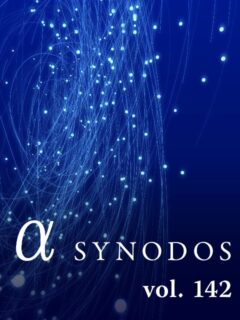
「大正デモクラシー」はどうして戦争を止められなかったのか
社会運動、政党政治、普通選挙――民主主義的な言論や運動が活発に行われた「大正デモクラシー」。しかし、その後日本は戦争の時代へと突入してしまう。なぜ大正デモクラシーは戦争を止められなかったのか。歴史学者の成田龍一氏に話を伺った。電子マガジンα-Synodos vol.142より、一部を転載。(聞き手・構成/山本菜々子)
「大正デモクラシー」とはなにか
―― 今回は、「大正デモクラシーはどうして戦争を止められなかったのか」というテーマでお話を伺えればとおもいます。まずは、「大正デモクラシー」はどのようなものだったのでしょうか。
まず、「大正デモクラシー」という言葉についてですが、これは同時代に使用された言葉でもなければ、歴史用語として定着しているわけではありません。論者によって「大正デモクラシー」といったときの時期や内容や評価が様々です。「大正」という元号と、「デモクラシー」というカタカナとが結びつけられた造語で、1950年代ころに登場しています。定着していない、といったとき、例えば、高等学校の教科書では、「大正デモクラシー」を重要なテーマの一つとして扱い、章のタイトルとして用いるものから、かんたんに註でしか触れていないものとがあるのです。「大正デモクラシー」が本当に「デモクラシー」だったのかと、根底的な疑問を投げかける人もいます。ことは、きょうの主題となっている、「大正デモクラシー」のあとに戦争の時代がやってきてしまったことの評価にかかわってきています。
一般的には、1905年(明治38年)~1931年(昭和6年)までを「大正デモクラシー」として把握し、政党政治が実現し、社会運動が活発であった時期として捉えられています。ここでも「大正デモクラシー」は、このように必ずしも、大正時代にすっぽりと収まる出来事として把握されているわけではありません。
また、大正デモクラシーは、1918年の米騒動を境に前半と後半に分かれます。それぞれで内容と担い手が変わってきます。
―― 前半はどのような人びとが担い手だったのでしょうか。
前半には大きくわけて二つの担い手がありました。一つは政党です。1900年代以降、すなわち明治の終わりから大正にかけて、政党が大きな力を持つようになりました。それまでは、明治維新を行ったとする旧薩摩藩と旧長州藩の出身者を中心とする藩閥内閣でしたが、民意を代表するものとしての政党に期待を寄せる動きがでてきました。そして、実際に政党が藩閥内閣を批判する運動を展開していくのですね。「閥族打破、憲政擁護」をスローガンとした第一次護憲運動は、政友会や国民党によって担われ、桂太郎内閣を倒す大正政変へと至りました。
より重要な、もう一つの動きは社会運動となって現われます。社会運動の担い手は二つの層に分かれます。一つは、「都市雑業層」と呼ばれる日雇いや人足・職人といった、都市における下層の人びとです。彼らは日露戦争後、暴動を起こします。1905年の「日比谷焼打ち事件」が「大正デモクラシー」の発端と言われていますが、この運動は、日露戦争後のポーツマス条約に賠償金が盛り込まれなかったことに対する不満から起された暴動でした。この時期は、東京のみならず、横浜、神戸、大阪など各地の大都市で、彼ら「都市雑業層」による暴動が起こりました。
もう一つの社会運動の担い手は「中間層」です。より厳密にいえば、旧中間層と呼ばれる「旦那層」で、家作を持ち、それを商売の元手にしている商家、あるいは中小の工場を経営し、「都市雑業層」を雇う立場の人びとです。彼ら「旧中間層」-「旦那層」も社会運動を起こしました。彼らはとくに地代や電気料金の値上げに対し、反対運動をしました。しばしば地域の名望家たちで、彼らが社会運動を起こしたため、「大正デモクラシー」は大きな潮流となったのですね。
社会運動の二つの担い手――その両者をつないでいたのが、新聞記者と弁護士でした。新聞記者は「都市雑業層」の暴動や「旦那衆」の運動の様子を記事にしたり、ときには自ら参加するなどして、社会運動を盛り上げていきました。また、弁護士は、逮捕され起訴された「都市雑業層」の弁護にあたりました。
―― 「旦那衆」が商売に不可欠な、地代や電気料金に対して運動をする理由は分かります。しかし、なぜ「都市雑業層」は、ポーツマス条約に対して暴動を起こしたのでしょうか。電気代や地代に比べ、生活の必要性からは遠いような気がするんですが。
むしろ、「都市雑業層」の方が切実な理由があって暴動を起こしたといえます。彼らは、都市のなかで単身で暮らしていて、「旦那衆」に雇われているような人たちですが、農民とともに、日露戦争のときにもっとも痛めつけられた階層といっていいでしょう。経済的な痛手が大きいのです。日露戦争の戦費の調達のため大増税がおこなわれますが、所得税ではなく間接税が上がりました。たばこや酒、砂糖といった、「都市雑業層」にとって仕事が終わった後の息抜きに不可欠なものに、税金がドーンとかかっていきました。彼らには、自分たちが戦費を負担している気持ちがあったわけです。日露戦争が終わって賠償金を取れば、自分たちの生活に還元されると思っていました。
ところが、ポーツマス会議では賠償金が取れませんでした。日本はかたちのうえでは「勝利」しましたが、実際には引き分けに近いギリギリの戦いだったので、ロシアに対し強い要求が出せなかったのです。「都市雑業層」からしたら、それは期待していたものが裏切られたということになります。「俺たちは弱腰の政府のもとで苦労していたのだ」という不満が残ります。さらに、彼らは選挙権を持っていないので、自分たちの意志表示をするためには、集会か運動しかありませんでした。そのようななか、日比谷公園で講和反対の集会が政府によって事前に禁止されてしまった。そこで、彼らの不満が爆発し暴動になってしまいました。

―― 訴える手段がないからこそ、暴動に走ってしまったのですね。当時の選挙というのは、どのようなものなのでしょうか。
1890年に、第一回の衆議院議員選挙が行われます。当時、選挙権を持っていたのは、直接国税を15円以上収める25歳以上の男性でした。全人口の1%くらいしか投票出来なかったのですね。現在の有権者率が80%ほどですから、当時の選挙権がいかに限られていたものか分かると思います。直接国税というのは地租が多くを占めていたので、有権者といったとき、基本的には地主が多かったのです。
普通選挙をめざせ
―― では、「大正デモクラシー」後半はどのようなものだったのですか。
近年では「大正デモクラシー」後半期は、「改造の時代」と呼ぶようになってきていますが、社会運動が活発になります。後半は、運動の組織化と普通選挙を目指す運動が活発になったことが特徴です。
まずは、組織化についてですが、米騒動以降、暴動型の社会運動が無くなっていきました。暴動は、瞬間には社会的に訴えることができ、参加者は日ごろの憤懣をはらすことができるのですが、さしたる成果を獲得できないことに気付きはじめたといえましょう。成果の獲得を目指し、社会運動の担い手たちは組織や団体をつくります。農民たちは農民組合をつくり、労働者は労働組合を、被差別部落は水平社を組織し、学生も「新人会」のような学生団体を結成しました。同時に、女性団体ができ、借家人組合や消費組合も結成されるように、運動自体も多様化していきましたが、大きな動きをみせた社会運動のひとつが普選運動です。選挙によって自分達の意見を反映させたいという思いから、普通選挙を政府に求めました。直接国税15円という規約を外し、財産による制限をなくすことを目標にしていました。政党と社会運動を媒介するとともに、前半と後半をつなぐ運動でもありました。
同時に、政府の側もいつまでも制限することは不可能だと感じていましたので、直接国税15円から10円、3円と減額する措置をとっていきます。しかし、財産による選挙権の制限自体の撤廃を求め、普選運動は盛り上がっていきました。
その結果、1925年に普通選挙法が成立します。衆議院議員選挙法を改正するという形で、すべての成人男子(25歳以上)に選挙権を与えるものになりました。ここで言ってみれば「国民」が成立し、日本の国民国家としての制度的な基盤―基礎が成立しました。近代国家として「国民」を制度的に誕生させたのですね。
しかし、女性は選挙権の対象外になりました。「普通」から外されてしまったわけです。女性の選挙権獲得には、敗戦まで時間がかかりました。このときまで、女性は正式な「国民」として認知されていないことになります。準「国民」とみなされ、そのように扱われていました。
同時に、憲法が適応されていなかった当時の植民地でも、選挙権は与えられていませんでした。植民地には大日本帝国憲法が適用されず、植民地の人びとも「普通」からは外されていたのです。したがって、選挙権があたえられないという点では、植民地にいる「日本人」に対しても同じ扱いでした。
他方で日本本土にいる植民地の人びとには、普選によって選挙権が与えられました。その結果、朝鮮人の代議士も誕生しました。ただし、普選は一定の居住地を有している人にしか適用されなかったので、植民地の人びとで、その条件を満たす人は少なかったのですが。
―― 普通選挙といえども、「普通」に全員が入れるわけでは無かったのですね。
そうですね。「国民」として権利が与えられるのですが、成年男子、それも「本国」の人間に限られました。そして、非常に大事な点ですが、普通選挙法の成立が、治安維持法とセットになっています。
繰り返し述べているように、普通選挙は「国民」を制度的につくりだしました。しかし、反面からいえば、このことは同時に、普選の枠のなかに人びとを囲い込んだと言えます。すなわち、その一方で、「普通」から外れた、あるいは外れようとする人たちを治安維持法で取り締まることにしたのです。言ってみれば、普通選挙により人びとを囲い込み、それに肯んじない人びとを治安維持法で排除するという体制を作り上げたのです。
当時の労働運動の活動家や社会主義者たちは、選挙にたいした期待を持っていませんでした。むしろ、選挙によって「国民」として捕えられてしまうことに反発していました。「大正デモクラシー」後半期には、そこまで認識が進んでいたのですね。ですので、普通選挙法が成立してからも、社会運動を活発に行っていました。社会主義がそのときの運動のひとつの指針となっていました。そのため、政府はその動きを治安維持法で抑えようとしたのです。善き「国民」は普選を与えるから選挙権を行使し、運動はするなというわけです。おりからロシア革命後のソ連とのあいだに国交を結ぶことになり、政府は共産主義に強い警戒心をもっていました。
普通選挙は、「大正デモクラシー」の一つのゴールでした。同時に、「国民」としての囲い込みと排除の体制が出来上がったわけです。「国民」としての囲いの中だけで行動することになってしまいました。権利が付与されたということとともに、そこからはみ出たばあいには排除されるという限界が提示されました。両義的ですね。
同じ問題が、政党政治に対しても言えます。1918年7月にはじまった米騒動に影響を受け、同年9月に原敬内閣が発足しました。従来までの藩閥政治に比べ、政党政治は人びとの意見をくみ取ることができるようになりました。しかし、その「意見」は、あくまで政党にパイプがある「中間層」―「旦那衆」のものでした。とくに政友会は、地域の名望家たちの利益誘導に熱心でした。これに対し、「都市雑業層」には政党に繋がる手段がなかったのです。
普選によって「国民」ができた一方で、それ以外を排除してしまうことになりましたし、政党政治によって社会運動を行っていた「都市雑業層」と「旦那衆」が分断されることになってしまいました。正確に言いなおせば、「旦那衆」は運動をする必然性がなくなりました。とはいえ普通選挙も実現し、人びとの運動によって内閣も倒れています。社会が変わっていったことは確かです。このあたりが「大正デモクラシー」の評価が分かれる点ですね。
なぜ戦争を止められなかったのか
―― ここから、「大正デモクラシーはなぜ、戦争を止められなかったのか」という本題に入っていきたいと思います。デモクラシーが盛り上がっているなかで、どうして戦争に向かっていったのでしょうか。
一般的には、「大正デモクラシー」が「帝国のデモクラシー」であったからといえます。「大正デモクラシー」は大日本帝国憲法下のデモクラシーであったが故に、弱さと限界があり、ファシズムや戦争を止められなかったということです。大日本帝国憲法のもとでは、主権は天皇にあり、議会は天皇を「協賛」し、内閣は天皇を「輔弼」するものとされています。「大正デモクラシー」の理念としての民本主義は、そのことを前提にした民衆による、民衆のための政治要求だったのです。いわば、解釈改憲のようにして、民衆に寄った大日本帝国憲法解釈が「大正デモクラシー」でした。そのため、日比谷焼打ち事件も排外的な要素をきっかけにしていますし、植民地朝鮮の独立を要求した3.1独立運動には民本主義者も批判的でした。いや、そもそも植民地の存在を自明のこととしており、そのもとでのデモクラシーでした。要のところが、弱いデモクラシーなのですね。
そうしたことのゆえに、多くの論者は、1931年の「満州事変」を「大正デモクラシー」の終りと捉えています。民衆意識が排外主義に向かい、侵略の動きがこれ以降始まったという認識です。実際、大正デモクラットの多くが(無産政党の人びとも含め)、この動きを支持していく事態となります。
このことを別の言い方をしてみると、1920年代と1930年代の間で断絶があるとする「断絶説」ということになります。「大正デモクラシー」が崩壊し、戦争の時代に突入したという認識ですね。これが歴史学のなかでも、一般的な把握だと思います。
しかし、私は別の説を考えています。いうなれば「連続説」です。1920年代と30年代は連続していると考えています。
どのようなことかというと、「大正デモクラシー」は確かに帝国のもとでのデモクラシーであり、その弱さを抱え込んでいました。しかし、この「大正デモクラシー」の時代に、前半期から後半期におよんで、基本的には「民衆」の意見を吸い上げなければ回っていかない仕組みを体制的に作り上げていきました。「民衆」を制度的に入れ込むシステムです。普選のもつ歴史的意義にさまざまに限定を付けましたが、しかし、「民衆」を「国民」として扱っていかなければならない時期がやってきたということです。秩序を保ちながら政治を遂行していくためには、あくまでも「国民」の意見を後ろ盾にしなくてはならない、というシステムの定着です。
このことは、デモクラシーの機運のなかで制度化されたのですが、いったん制度化されるや、「国民」の意向をないがしろにすることができなくなります。ありていにいえば、「国民」の意向が変わっていくと、当然、政治の方向も変わっていきます。1931年の「満州事変」によって、「国民」の意見や要求が排外的になった、そのゆえにあらたな方向に舵を取り、ファシズムという事態に入り込んでいった、というのが私の見解です。1920年代の「成果」が、1930年代の事態をつくりだしたという「連続説」です。
つまり、ファシズムが無理矢理に「国民」を引きずり込んだのではなく、人びとの考え方が排外主義に傾いて、「満州は自分達の領土だ」と思い、そのことをとりこむことによってファシズムが成立していく、ということです。「大正デモクラシー」の過程で成立し、人びとの意見を吸い上げるシステム(その制度化が、普選ですが)によって、戦争の時代になったと私は考えています。「大正デモクラシー」があったが故にファシズムに向かい、戦争の時代になったのです。
―― 「大正デモクラシー」は戦争を「止められなかった」のではなく、むしろ戦争を進めるのに加担していったわけですね。
「大正デモクラシー」を前提として、あるいは踏み台として、戦争に入り込んでいったということですね。「大正デモクラシー」を考える際に、象徴的な事例があります。「大正デモクラシー」の代表である吉野作造は、民本主義をとなえ、当時の言論をどんどんリードしていきました。吉野は民意を吸い上げ、政策に反映させることを目標とし、大日本帝国憲法の枠のなかで、ギリギリの解釈をしました。そして、後半になると吉野作造の教えを受けた「新人会」の人たちが、さらにラディカルな主張をしていきます。
そんな、「大正デモクラシーのチャンピオン」とも言える吉野作造には弟がいます。吉野信次です。吉野信次は、農商務省、さらにそこから分割された商工省の官僚として重要な働きをしますが、信次は民意を取り込まないと政策統治も上手くいかないと考えていきます。
つまり、兄・作造は「民衆」の側から民意をくみ上げる必要性を主張し、弟・信次は支配の側から民意を取り込むことを考えたのです。この両輪こそが「大正デモクラシー」の本質であると思います。この兄弟は仲が良かったと言われていますが、後世からみたとき、兄弟でお互いを補い合っている関係があったと言えるでしょう。
吉野信次らは、のちに「新官僚」と呼ばれ、さらに「革新官僚」へとつらなっていきますが、戦時の民衆動員の体制をつくりあげ、ファシズム体制を作り上げる担い手の重要な部分になっていきます。ファシズム体制―戦時総動員体制を担った革新官僚は、この文脈に引きつけていえば、吉野信次の系譜ということがいえます。ファシズムというのは、民意をいかに引き付け、主体的な営為をおこなわせ、コントロールすればいいのかということを、たっぷり学んだ人達によって行われていたということです。民意の重要性を知る人によってなされたのです。つまり、「大正デモクラシー」があったために、吉野信次や革新官僚が出てきて、戦争の体制が出来上がったということができるでしょう。
ですから、「なぜ大正デモクラシーは戦争を止められなかったのか」という問題の立て方自体を疑うことが必要ですね。
そう考えると、どこを「大正デモクラシー」の終りにするかが、あらためて問われることになります。難しい問いですが、私は、1933年に終了したと考えています。33年は、プロレタリア文学の代表的な作家である小林多喜二が拷問によって虐殺された年です。この年を境に、社会運動から転向する人が増えていきます。社会運動からの人びとの離脱、さらに転向する人びとの存在によって社会運動が衰退する以上に、その質が転換します。すなわち(体制への)抵抗の運動ではなく、(体制への)翼賛の運動になり、さきの新官僚・革新官僚がめざす方向と一致します。こうして体制の側も社会運動の側も変質し、背中合わせの調和のもとに総動員―体制の時代がやってきました。
(つづきは、α-Synodos vol.142号で! https://synodos.jp/a-synodos)
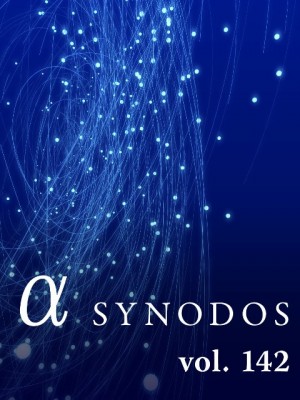
民主主義をとらえる
成田龍一インタビュー「『大正デモクラシー』はどうして戦争を止められなかったのか」
木村俊道「政治のアルス――デモクラシー以前の『文明』と『教養』」
重田園江インタビュー「熱烈な民主主義、冷静な社会契約論――社会契約論から見える民主主義の姿とは」
松尾隆佑「ステークホルダー・デモクラシーに何ができるか」
岸政彦「もうひとつの沖縄戦後史(2)──人口増加と『都市の暗い谷間』」
プロフィール

成田龍一
1951年、大阪市に生まれる。その後、小学校からは東京で暮らす。1970年、早稲田大学に入学し、歴史学―近現代日本史を学ぶ。1990年、日本女子大学で、教鞭をとる。主な著作に、『<歴史>はいかに語られるか』(NHKブックス、2001年、増補版、ちくま学芸文庫、2010年)『大正デモクラシー』(岩波新書、2007年)『「戦争経験」の戦後史』(岩波書店、2010年)『近現代日本史と歴史学』(中公新書、2012年)『戦後日本史の考え方・学び方』(河出書房新社、2013年)
などがある。


