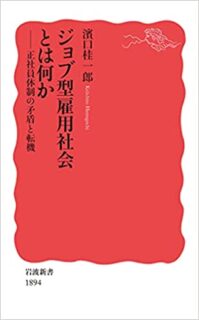2021.10.25
ジョブ型は成果主義にあらず――『ジョブ型雇用社会とは何か 正社員体制の矛盾と転機』(岩波新書)
ジョブ型は成果主義にあらず
2020年には突如として「ジョブ型」という言葉が流行し、ネット上で「ジョブ型」を検索するとほぼ毎日数十件の新しい記事がヒットするという状態が続きました。これは、同年1月経団連が公表した『2020年版 経営労働政策特別委員会報告』が大々的にジョブ型を打ち出したことによるものですが、記事の多くは一知半解で、間違いだらけのジョブ型論ばかりが世間にはびこっています。その中でも特に目に余るのが、「労働時間ではなく成果で評価する」のが「ジョブ型」だという議論です。あまりにも頻繁に紙面でお目にかかるため、そう思い込んでいる人が実に多いのですが、これは9割方ウソです。
そもそも、ジョブ型であれ、メンバーシップ型であれ、ハイエンドの仕事になればなるほど仕事ぶりを評価されますし、ミドルから下の方になればなるほど評価されなくなります。それは共通ですが、そのレベルが違います。多くの人の常識とは全く逆に、ジョブ型社会では一部の上澄み労働者を除けば仕事ぶりを評価されないのに対し、メンバーシップ型では末端のヒラ社員に至るまで評価の対象となります。そこが最大の違いです。
これは「ジョブ型」とはどういうことかを基礎に戻って考えればごく当たり前の話です。ジョブ型とは、まず最初に職務(ジョブ)があり、そこにそのジョブを遂行できるはずの人間をはめ込みます。人間の評価はジョブにはめ込む際に、事前に行うのです。後はそのジョブをきちんと遂行できているかを確認するだけです。圧倒的に多くのジョブは、その遂行の度合を細かく評価するようにはなっていません。ジョブディスクリプションに細々と書かれた任務を遂行できていれば、そのジョブにあらかじめ定められた価格(賃金)を払うだけです。これがジョブ型の大原則であって、そもそも普通のジョブに成果主義などはなじみません。例外的に、経営層に近いハイエンドのジョブになれば、ジョブディスクリプションが広範かつ曖昧なので、できているかできていないかの二分法では足らず、その成果を細かく評価されるようになります。
これに対し、日本のメンバーシップ型社会においては、欧米の同レベルの労働者が評価対象ではないのとまったく正反対に、末端のヒラ社員に至るまで事細かな評価の対象になります。ただし、入社時にも入社後もジョブのスキルではなく、特殊日本的意味における「能力」と「意欲」を評価されています。この「能力」とは、具体的なジョブのスキルではなく、潜在能力を意味します。また「意欲」の徴表は長時間労働です。
このように、ハイエンドではない多くの労働者層についてみれば、ジョブ型よりもメンバーシップ型の方が圧倒的に人を評価しているのですが、ただその評価の中身が、「能力」や「意欲」に偏り、「成果」による評価が乏しいのです。そして、この普通の労働者向けの評価スタイルが、経営者に近い管理する側の人々に対してもずるずると適用されてしまいがちです。ハイエンドの人々は厳しく成果で評価されるべきだとすれば、「9割方ウソ」の残り1割はウソではないと言えます。しかし、そういう人はジョブ型社会でも一握りの上澄みです。もし、ジョブ型社会ではみんな、日本で「能力」や「意欲」を評価されている末端のヒラ社員と同じレベルの労働者までがみんな、「成果主義」で厳しく査定されているという誤解をまき散らしているのであれば、それは明らかにウソであるといわなければなりません。
ジョブ型は新商品に非ず
さて、「ジョブ型」「メンバーシップ型」というのは、言葉自体は私が十数年前に作った言葉ですが、概念自体はそれ以前からあります。これは現実に存在する雇用システムを分類するための学術的概念であり、本来価値判断とは独立のものです。つまり、先験的にどちらが良い、悪いという話ではありません。
一方、商売目的の経営コンサルタントやそのおこぼれを狙う各種メディアは、もっぱら新商品として「これからはジョブ型だ! 乗り遅れるな」と売り込むネタとのみ心得ているようです。そのためジョブ型とは何か、メンバーシップ型とは何かという認識論的基礎が極めていい加減なまま、価値判断ばかりを振り回したがる傾向が見られます。
そもそもジョブ型は全然新しくありません。むしろ産業革命以来、先進産業社会の企業組織の基本構造は一貫してジョブ型だったのですから、戦後日本で拡大したメンバーシップ型の方がずっと新しいのです。
その日本でも、民法や労組法や労基法といった基本労働法制は全部ジョブ型でできています。それとメンバーシップ型でできている現実社会との落差を、さまざまな判例法理が埋めてきているのです。また、日本でも高度成長期の労働政策はジョブ型を志向していました。近代的労働市場礼賛期の1960年に策定された「国民所得倍増計画」では、「労務管理体制の変化は、賃金、雇用の企業別封鎖性を超えて、同一労働同一賃金原則の浸透、労働移動の円滑化をもたらし、労働組合の組織も産業別あるいは地域別のものとなる」と、ジョブ型社会への移行を展望していました。
ところが1970年代半ばから1990年代半ばまでのほんの20年間には、「新商品」としてメンバーシップ型礼賛論が溢れました。当時は、日本はME(マイクロエレクトロニクス)において最先進国だと言われていました。だから柔軟な日本型がいい、硬直的なジョブ型はだめだというのが常識だったのです。ところが21世紀になると、IT化の下では、AI化の下ではジョブ型がいいという議論ばかりです。MEもITもAIも、発展段階が違うだけで、情報通信技術の産業への応用という意味では何も変わりません。いつも同じように新商品をいかに売り込むかということばかりに熱中して、肝心の議論がどこかに消えてしまっているのです。
メンバーシップ型の真の問題点
1980年代には、世界的にもこの日本型雇用システムこそが日本の圧倒的な経済的競争力の源泉であるともてはやされていましたが、その時期においても、誰がそれで得をし、誰が損をしていたかを考えると、性と年齢でかなり差がありました。
日本型雇用で得をしていたのは若者です。ジョブ型社会というのは、「この仕事ができる」人が優先して雇われる社会です。若者というのは定義上中高年よりも経験が乏しく技能が劣ります。それゆえに労働市場で不利益を被り、卒業してもなかなか職に就けず、失業することが多いのです。ところが日本では、仕事の能力が劣っていることが明らかな若者ほど好んで採用されます。ところが一方、職安には中高年が長い列を作っていました。日本型雇用で損をするのは中高年です。いったん失業したら、技能も経験もあるのに嫌がられ、なかなか採用してもらえません。
若者といい中高年といい、暗黙のうちに想定されていたのは男性です。実のところ、日本型雇用システムにおいて一番割を食っていたのは女性です。男女均等法以前の日本企業においては、男性は新卒採用から定年退職までの長期雇用が前提であるのに対して、女性は新卒採用から結婚退職までの短期雇用が前提で、その仕事内容も男性社員の補助業務が主でした。結婚退職した後は、主婦パート以外に働く場はほとんどありませんでした。
1990年代半ば以降、日経連の『新時代の「日本的経営」』に示されるように、長期蓄積能力活用型という名で正社員を絞り込みつつ、雇用柔軟型という名の非正規雇用が拡大していきました。それまでのように若者は誰でも正社員になれる時代ではなくなり、正社員コースに入りこめなかった氷河期世代の若者は非正規労働に取り残されたまま今日中高年化しつつあります。この格差問題こそ、メンバーシップ型雇用社会が未だに解決できていない最大の矛盾です。また、若い男性を前提にした無限定な働き方と、家事育児負担を負った既婚女性との矛盾も大きくなっています。
こうして矛盾だらけになった(古びた新商品としての)柔軟すぎるメンバーシップ型を見直し、もっと硬直的なジョブ型の要素を持ち込もうというのが真の「働き方改革」であって、その意味ではこれは復古的改革というべきものなのです。
プロフィール

濱口桂一郎
1958年大阪府生まれ。1983年東京大学法学部卒業。同年労働省に入省。東京大学客員教授、政策研究大学院大学教授を経て、2017年4月より、労働政策研究・研修機構労働政策研究所長。
著作―『新しい労働社会――雇用システムの再構築へ』(岩波新書、2009年)、『日本の雇用終了――労働局あっせん事例から』(労働政策研究・研修機構、2012年)、『若者と労働――「入社」の仕組みから解きほぐす』(中公新書ラクレ、2013年)、『日本の雇用と中高年』(ちくま新書、2014年)、『働く女子の運命』(文春新書、2015年)、『働き方改革の世界史』(共著、ちくま新書、2020年)等多数。