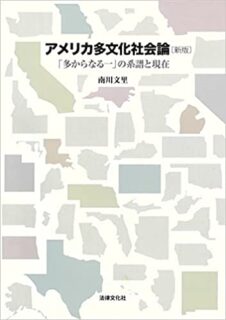2022.05.23
多文化社会を「きちんと」論じるために——『アメリカ多文化社会論[新版] 「多からなる一」の系譜と現在』(法律文化社)
多文化社会論のねらい
アメリカ合衆国には、「多からなる一(e pluribus unum)」という言葉があります。これは、1ドル札にも記される「国民的な標語」とされており、「多様なものによって作られる一つの国」というアメリカの特性をあらわす言葉として、広く知られています。当初は13の植民地に起源を持つ連邦制をあらわす語でしたが、アメリカが抱える文化的多様性とそのなかでの統合の模索という、広範な含意を持つ言葉になりました。
本書のねらいは、「多からなる一」という言葉を手がかりに、アメリカの歩みを一つの「多文化社会(multicultural society)」として論じることにあります。アメリカにおいて異なった文化的背景を持つ人びとが共存する社会は、どのように構想され、どのような具体的な取り組みに反映されてきたのか。それは現在、いかなる状態にあるのか。
「多文化社会」というのは、実はとても奇妙な言葉です。なぜなら、社会を構成する一人一人が異なった存在であるとするならば、あらゆる社会は「多文化社会」であると言えるからです。
バラク・オバマは、自身を一躍有名にした2004年民主党大会での演説で、「多からなる一」を「個々人がそれぞれの夢を追い求めながら、アメリカ人として一つの家族でもあること」を示す言葉であると語っています。オバマはそれをアメリカ特有の理想として語りますが、「人が個として生きながら、社会の一員となる」ことは、自由や民主主義を掲げる多くの社会にとっては、よりよい社会を考えるための大前提となる理念といえるでしょう。
それでも、あえて本書が「多文化社会論」を名乗っているのは、アメリカには、「多」であることと「一」であることの両立を自覚的に追求してきた歴史があるからです。とくに、20世紀以降のアメリカは、文化的な多様性の存在を認め、「多からなる一」の実現を模索してきました。
その歴史を追跡することで、日本を含む多文化社会で、人びとがよりよく生きるための制度や枠組のあり方を考えることができるのではないか。それが、本書が主題として掲げる多文化社会論です。
2016年11月9日
多文化社会としてのアメリカを論じた本書の初版は、2016年1月に出版されました。アメリカ研究界隈ではよくある話ですが、4年に一度の大統領選挙年は、アメリカへの一般的関心が高まるため、関連図書が多く刊行されます。初版もそのなかの一つで、アメリカの多文化社会論の基本的な概念や議論の枠組を提供し、世界の注目を集めるアメリカの「現在」への理解を助けることができればと出版されました。
ちょうど原稿執筆時にドナルド・トランプが大統領選挙への出馬を宣言して大きな話題となっていましたが、初版では、オバマ政権時代までの多文化社会としての歩みを体系的に捉えることを優先しました。それまで、黒人や先住民などの集団ごとの歴史を描いた書籍は多く刊行されていましたが、「同化」「文化多元主義」「多文化主義」などの包括的な社会構想を軸としたものは少なく、アメリカ研究分野の教科書や参考書として多くの大学で採用していただきました。
しかし、2016年11月9日、状況が大きく変化しました。メディアや専門家の予想を裏切って、トランプがヒラリー・クリントンを破り、第45代合衆国大統領に選出されました。紆余曲折はあれど、多様性を尊重する態度が定着しつつあると思えたアメリカで、白人中心の世界観を隠そうとしないトランプが大統領となることで、これまでの多文化社会論の前提がいくつか覆されました。
たとえば、トランプは、差別的言動は政治家にとって致命的であるという前提を破り、むしろ熱狂的な支持を集めました。また、マイノリティ人口の増加で政治的影響力が低下するとみられていた白人層、とくに白人労働者階級を、アメリカの人種政治の主役として再登場させました。
たしかに、初版では、多様性を推進するオバマ政権下にあって、黒人への警察暴力に抗議するブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動が始まったこと、人種主義に対する黒人と白人のあいだの認識ギャップが広がっていたことなどを指摘していました。しかし、トランプ時代以後の多文化社会を理解するための十分な材料を提供できているとはいえず、出版後1年が経過する前に、現状分析においては限界がある一冊となってしまいました。
トランプ以後の多文化社会論
トランプ現象は、多文化社会としてのアメリカを考える議論の磁場を揺るがしました。日本国内では、トランプ現象を「行き過ぎた多文化主義に対する反発」と捉える解説がテレビや新聞などでも繰り返されました。しかし、そのような議論は、多文化主義についての学術的な議論を反映していないばかりか、事実の誤認にもとづいている場合もありました。
アメリカにおける多文化主義は、20世紀末の「文化戦争」をもたらした政治的論争点として強調された結果、その内実がなかなか社会科学的な研究の対象となりませんでした。一方で、ウィル・キムリッカなどのカナダの研究者を中心に、多文化主義の国際比較研究の枠組が提案され、各国の多文化主義の政策を学術的に評価する取り組みが見られるようになりました。私は、後者の枠組を参照することで、アメリカにおける多文化主義の特徴を整理し、その展開を歴史的に捉える研究に着手しました。
そのような多文化主義研究の成果が、2021年に刊行された『未完の多文化主義——アメリカにおける人種、国家、多様性』(東京大学出版会)でした。同書のなかで、多文化主義が、1960年代の公民権改革のなかで反人種主義政策として制度化されたものの、反対派との折衝を通して変質を余儀なくされる過程を描きました。そして、多文化主義の変質によって反人種主義的な規範が後退したことが、トランプ現象を導いたと論じました。
さらに、本書の初版では扱えなかったトランプ現象とその後を射程として、『未完の多文化主義』での成果をより広範な多文化社会論の文脈に位置づけなおしたのが、今回の『アメリカ多文化社会論[新版]』でした。
新版では、多文化社会を論じる際に用いられる人種と人種主義、同化、エスニシティと文化多元主義、多文化主義、インターセクショナリティなどの概念が、アメリカの歴史的文脈のなかでどのように登場し、それがどのような社会構想や政策を導いてきたのかを論じています。
いずれの概念も、頻繁に使われるにもかかわらず、それぞれの歴史的背景や射程が十分に理解されているとはいえません。そのため、各分野の基本文献を紹介しながら、なぜそのような概念が必要とされ、多様な背景を持つ人びとの声がどのように反映され、政策や社会運動がどのように人びとの社会生活を変えたのかを、丁寧に論じたつもりです。
トランプ現象以後、人種や差別をめぐる議論の「分断」が強調されています。「どっちもどっち」と言わんばかりの「分断」論は、アメリカ史のなかで模索されてきた多文化社会論の蓄積を、政治的なイデオロギーにもとづく一面的な主張であるかのように語ります。そのような単純化を避け、多文化社会をめぐる議論を実のあるものにするには、さまざまな概念の文脈と射程について共通了解を作る必要があります。本書が目指したのは、多文化社会の課題とその可能性を「きちんと」論じるための土台を用意することでした。
多文化社会を「きちんと」論じる
「きちんと」論じるとは、どういうことでしょうか。本書のなかで、「文化戦争」を経て、アファーマティヴ・アクションや多文化教育などの反人種主義的な政策が、新自由主義的な「多様性」実現のための手段へと変質してきたことを論じています。
その結果、ビジネスや教育における効率やパフォーマンスにいかに寄与するかという観点から評価される「浅い多様性」が優位となり、人種的な排除の歴史をふまえた公民権や反差別への関心が後退するようになってしまいました。トランプ現象の背後にあったのも、彼の差別的な言動と「アウトサイダー」としての期待を天秤にかけ、後者を選ぶような態度でした。
しかし、反人種主義が「浅い多様性」に置き換えられた状況を鋭く問いかける議論も登場します。その代表的なものが、オバマ政権期の2013年に登場し、2020年ジョージ・フロイド氏殺害事件をきっかけに世界的に広がったBLM運動でした。新型コロナ・パンデミックのなかで、人種間の不平等が可視化されるなか、BLM運動は表面的な「多様性」の背後にある人種主義の問題を問い続けました。
本書では、BLM運動が描き出す次世代の多文化社会のあり方を、「インターセクショナルな多文化主義」として議論しています。それは、多様性のありかを、その歴史的文脈に位置づけ、人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティが相互作用する権力関係から掘り起こすものでした。多文化社会を「きちんと」論じるためには、その表面的な相違だけでなく、歴史的文脈と複合的な権力関係にもとづく「深い多様性」から考えることが必要です。そのことを、BLM運動があらためて示唆したのです。
以上のような「多からなる一」をめぐるアメリカ多文化社会論は、アメリカが置かれた歴史的文脈とその特性を明らかにするものです。そうすることではじめて、多文化であるのに多文化主義的な取り組みを忌避してきた日本においても、「きちんと」多文化社会について論じるための道具を提供できるのではないかと期待しています。
本書が、アメリカについての理解を深めるとともに、多文化社会日本の可能性を追求する議論を活性化することを願っています。
プロフィール

南川文里
同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。1973年愛知県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(社会学)。専門は、社会学・アメリカ研究。神戸市外国語大学専任講師、立命館大学国際関係学部教授などを経て、2022年4月から現職。主な著書に、『アメリカ多文化社会論[新版]——「多からなる一」の系譜と現在』(法律文化社、2022年)、『未完の多文化主義——アメリカにおける人種、国家、多様性』(東京大学出版会、2021年)、『「日系アメリカ人」の歴史社会学——エスニシティ、人種、ナショナリズム』(彩流社、2007年)など。