2016.06.03
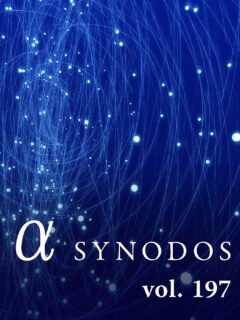
特集:家族
アラフォー世代に“家族”のことを訊いてみた
ブロガーのテラケイ氏が、さまざまな分野の専門家と「家族」について語り合う。
「結婚」「家庭」「つながり」「絆」――そんなことばを耳にする機会が、いつしか多くなっていた。それは、私が20代も半ばを過ぎ、そういったキーワードを気にするような年頃になったからなのかもしれない。けれど、ただそれだけではないような気がしていた。自分だけでなく、多くの人が、家族のあり方、ひいては、人と人との結びつきのあり方について、「迷い」や「不安」を抱えているのではないかという、漠然とした予感があった。
いま20代である私たちの世代は、「ゆとり世代」あるいは、ネットでは通俗的に「さとり世代」とも呼ばれ、大きな理想を持たず、身の丈にあった、無理のない人生を選びたいと望む傾向が強いとも言われている。しかし実際のところは、先行きの見えない不況のただなかを過ごし、自分の親世代が辿ってきたような将来像を描きたくでも描けないでいる者が多い。親世代が築いたような家庭の姿が、私たちにとっては、いつのまにか「普通」ではなくなっていた。
昔のようなビジョンを描けなくなった私たちの世代は、「家族」あるいは「人と人との結びつき」をどのように捉えればよいのか――そんな個人的な興味がきっかけとなり、幸運にも今回の対談が実現することとなった。奇しくも、私に語ってくれたお三方はみな「アラフォー」と呼ばれる年代の方々であり、バブル崩壊後の大不況のなかで社会に出ることを余儀なくされた「(初代)就職氷河期」と呼ばれる世代でもある。
今回の対談は、日本の「家族」の歴史を振り返りながら、その機能・構造・将来の問題点などをつまびらかにするものである。それと同時に、「親世代と同じ未来を描けない」という現実に私たちの世代よりも早くにぶち当たった先輩方の見てきた風景を交えつつ、「家族」「人との結びつき」をめぐる、少し不思議な旅の記録でもある。
第1回 テラケイ×久保田裕之(家族社会学)
テラケイ:この企画では、私がおこがましくも何名かの専門家の方にインタビューする形で、「家族」のことについて様々な角度から考えていく予定です。第1回では、家族制度の政治的・経済的な諸問題に深く立ち入っていく前に、「家族」や「家庭」とはそもそも何なのかという、もっとも基本的なところにフォーカスしていきます。
“「家族」が大事。「家庭」をもとう。少子化はよくないことだ。若者は結婚しよう”――私の世代のみならず、先生の世代、いわゆるアラフォー世代も、晩婚化・非婚化を背景にして世間からはいろいろいわれていますが、私たちがつくることをしばしば推奨される「家族」は、社会あるいは個人にとって、いったいどのような存在なのでしょうか。久保田先生に教えていただきたいと思います。
◇「家族」は意外と最近になって誕生した
久保田:家族の話をするときに、どうしても最初に確認しておかなければならないことがあるんですが、それはいったい「家族」とはいつごろからできたのかということです。
男女が性関係をもって子どもをもうけ、その子と両親を含めた社会的ユニットのなかで子どもを育てる――という構図は、人類が誕生して以来、というか人類が人類の形をとる前からある程度普遍的なものだったはずです。
ですが、その場合の社会的なユニットというのは、現在私たちが家族」の名の下にイメージするよりもずっと広く、親族共同体や、非親族を含む農業共同体や村落共同体全体にまで広がっていました。『<子ども>の誕生』という本を書いたフィリップ・アリエスという社会史家は、「家族の歴史を遡っていくと、共同体のなかに溶けてしまう」というようなことを書いています。
では、いつごろから父と母と子を基本構成とした、より小さなユニットが今のような「家族」として成立するようになったのかというと、西欧では産業革命よりも後だといわれています。というのも、産業革命以降になってはじめて「職住分離」、すなわち、仕事をする場所と寝起きする場所の区別が一般化してくるからです。
それ以前の農業を中心とした村落共同体では、寝起きする場所は同時に労働の場であっただけでなく、祖先祭祀など宗教の場であり、子どもに生活を教える教育の場でもありました。家族のなかの地位と役割は、村落全体の地位と役割のなかに埋め込まれていました。
ここから近代化のなかで、教育は学校に、宗教は宗教団体に、労働は雇用へと専門分化・外部化され、逆に、それぞれの家のなかに取り残されて消費と再生産(家事・育児)に特化したものを、私たちは家族と呼んでいるわけです。……つづきはα-Synodos vol.197で!
第2回 テラケイ×飯田泰之(経済学)
◇「マルサス的社会」からの離脱
テラケイ:前回の久保田先生のお話によりますと、日本において「家族」という社会的ユニットが名実ともに成立したのは産業革命以降であるということでした。経済学の側面からみると、「家族」がその時代に成立した背景にはどのようなものがあったのでしょうか。
飯田:家族あるいは人の暮らし方を規定する大きな要因のひとつが生産力です。かつて日本には、今日我々が考えるような「家族」とは異なる家族システムが適合的な社会がありました。非常に低い生産性の農地を人力で耕す、なおかつ代替的な生産活動が存在していない社会――いわゆる前近代社会のことです。
テラケイ:代替的な生産活動というのは、たとえば工業とか、そういった類のものですか。
飯田:そうです。このような社会では、人口の上限は食料の生産で規定されます。これを経済史では「マルサス的社会」と呼んだりします。
テラケイ:「マルサス的社会」とはどういうものでしょうか。
飯田:食料生産によって人口の増加が制限される社会です。有限の農地に対して労働力を投入していくと、一人当たりの生産性が労働人口の増加にともなって下がっていくことになります。人ばかり増やしても生産が増えない、または耕作に適した土地に限界がある――このとき総生産高はだんだんと頭打ちになっていくでしょう。
そして、一人あたりの生産高が、その農地をもつ社会のメンバーがギリギリ生きていくのに必要な生存維持水準にぶつかったところで人口の増加は完全に止まります。
というのも、生存維持水準よりも一人あたり生産高が下回ってしまうと、その社会の成員の誰かが飢えて死ぬことを意味するからです。限られた農地で生産すると、その農地の生産高で養える人間には限界がおのずと生じる。これはマルサス的社会の典型例でしょう。
テラケイ:人がどれだけ増えても生産する土地が増えなければ、それは一人当たりの生産性を下げるだけ。有限のリソースで人だけが増えていくと、やがてそれは人ひとりが生存するための生産高を下回るため、その時点で社会が停滞する……まさしくマルサスの「人口論」で示された構造ですね。
飯田:そのとおりです。前近代社会にあっても、新田開発が一部では行われていましたが、多くの場合は困難を極めました。というのも、多くのマルサス的社会では、その社会の生存維持水準と一人あたり生産高が非常に近い。つまり、貯蓄ができないということになるからです。……つづきはα-Synodos vol.197で!
第3回 テラケイ×赤木智弘(フリーライター)
◇生きていくため、家族を持つための「溜め」
テラケイ:前回まで、久保田先生と飯田先生に、家族(制度)の歴史や、社会学的・経済学的意義と現在の問題について、マクロ的な観点から考えてきました。そこで明らかになってきた、こんにちの日本の家族モデルが抱える問題は、格差問題や人口問題と地続きになっているように感じます。
このシリーズのひとまずの最終回として、これまでの議論を踏まえつつ、いま赤木さんご自身がみている光景に立脚した、ミクロの問題についてのお話をお伺いできればと思っています。
赤木:久保田先生、飯田先生のこれまでの議論のなかで一番重要だと感じたのは、家族の形態が生産の形態とシンクロしているのという側面です。
人類が集落を形成して狩猟採集をしていたころは、獲るところから食べるところまで自分たちで完結していた。その後、それぞれが必要とする物を交換するという仕組みが確立して経済が発達し、経済の発達にともなって分業が発達し、貨幣が誕生した。
分業が経済の根幹となっていくにつれ、個人個人の目に見える成果はよくわからないものになっていった。分業のもとそれぞれが行っていた単純作業はやがて機械にとって代わられ、人の労働はサービス化していった。大雑把ではありますが、こうした過程の中で、自分たちの労働と、最終的に与えられる報酬の関連性がよくわからなくなっていったわけです。
もう少し具体的に考えてみましょう。たとえばチェーン店では、下のレイヤーで従事する人がいないと仕事全体が回らないにもかかわらず、上のレイヤーの人はたくさん分配を受けて下は少ししかもらえない。全体としてひとつのことをなしているのだけど、メンバーの報酬には格差があると。
しかし、なぜ報酬に格差があるのか、その明確な理由はもはや多くの人にはわからなくなっている。「上の人がお金を貰えるのも、下がもらえないのも当然だろう」という認識がなんとなく広がってしまった。
つまり何がいいたいかというと、生産の形態が変化するにつれ、人は自分たちのやっている労働の責任と自分たちの受け取る報酬の関係がはっきりとはわからなくなっていったということです。
労働と報酬の関係性が見えにくくなり、大勢の人にとってよくわからないままに生じていった賃金の格差に適応する形で家族モデルが構築されていったわけです。「伝統的家族像」と呼ばれる家族モデル(正社員夫×専業主婦orパート妻)は、実際は高度経済成長期の特殊な条件下で成立した形であると、久保田先生が明確に指摘されていましたね。
現代の日本では、多くの人が正社員として働き、それに紐づいて家族を養っていた時代から、非正規労働者が家計の中心になる可能性を想定しなければならない時代となりました。こんにちにおいてもなお「伝統的家族像」をあるべき家族像として掲げることが、かえって社会に歪みを生じさせてしまうことになるのは、これまでのお話にあったとおりです。
ですがその一方で、法的あるいは社会保障的なメリットの観点から個人に最適な戦略だけを考えるのであれば、「伝統的家族像」の形態が最も有利であることは依然として変わっていません。
世帯に正社員がいて、その正社員に紐づいて養われるメンバーがいる――このモデルが、この国の社会にとってはいまだに代表的な「普通の家族像で、「真っ当な人生を送っている」と社会からみなされる証明にもなっているからです。……つづきはα-Synodos vol.197で!
片岡剛士 経済ニュースの基礎知識TOP5
日々大量に配信される経済ニュースから厳選して毎月5つのニュースを取り上げ、そのニュースをどう見ればいいかを紹介するコーナーです。
日差しが強い日が続きます。気象庁によると、南米ペルー沖で海面水温が高くなるエルニーニョ現象が5月中にも終息し、その後、海面水温が低くなるラニーニャ現象に推移するとみられるとのことです。ラニーニャが発生すると記録的猛暑になる可能性があるとのことですが、このところの日差しで日焼けしてしまい既に「一皮むけた」自分は今後どうなってしまうのかが心配なこの頃です。
今月はG7伊勢志摩サミット、2015年世帯貯蓄動向、2016年1-3月期GDP一次速報値、熊本地震被害額公表、消費税増税を巡る提案についてみていきたいと思います。
◇第5位 G7伊勢志摩サミット(2016年5月26日、27日)
今月の第5位のニュースは、G7伊勢志摩サミットについてです。
本稿の〆切が25日ですのでサミットの内容について詳しくふれることができませんが、経済政策の観点からはG7が財政出動や金融政策、構造改革でどのような協調姿勢を打ち出せるのかが焦点です。
安倍首相は世界経済の動向についてG7諸国の認識をすり合わせつつ、財政出動を協調して行うことを目標においていると報じられています。リーマン・ショック後の政策対応の結果として先進諸国の中央銀行は政策金利をゼロないしマイナスにし、合わせて量的緩和政策を実行するという「非伝統的」金融政策を行っています。
この結果、先進諸国の名目金利は大きく低下して、日本は長期名目金利がマイナスの現状です。世界経済が需要不足により低迷しており、かつ名目金利が中央銀行の金融政策によって低水準に抑制されている現状では、先進国が協調して財政支出を拡大することは世界経済の需要不足を抑制する大きな力になるでしょう。
筆者は安倍首相の「協調的な財政出動」という主張は正しいと考えます。ただし、協調的な財政出動への道のりは険しいことも予想されます。ドイツやイギリスは財政出動には反対姿勢を貫いている状況、フランス、イタリア、カナダは(各国間で温度差はあるとは言え)財政出動に前向きではあるもののこれらの国々の主張がG7としてのコンセンサスへと結びつくかは疑問符がつくこと、米国は大統領選を控えて明確な主張をしづらいこと、といった点が協調的な財政出動への障害となりえます。「協調的な財政出動」に合意することは最適解ですが、各国が自国の置かれている環境の下で総需要拡大に向けて政策対応を行う旨を確認・表明できれば良いのではないでしょうか。……つづきはα-Synodos vol.197で!
プロフィール

シノドス編集部
シノドスは、ニュースサイトの運営、電子マガジンの配信、各種イベントの開催、出版活動や取材・研究活動、メディア・コンテンツ制作などを通じ、専門知に裏打ちされた言論を発信しています。気鋭の論者たちによる寄稿。研究者たちによる対話。第一線で活躍する起業家・活動家とのコラボレーション。政策を打ち出した政治家へのインタビュー。さまざまな当事者への取材。理性と信念のささやき声を拡大し、社会に届けるのがわたしたちの使命です。専門性と倫理に裏づけられた提案あふれるこの場に、そしていっときの遭遇から多くの触発を得られるこの場に、ぜひご参加ください。


