2013.06.29

HIVと共に生まれる ―― Ekilooto of Uganda
2012年1月23日、特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS主催のトークイベント「Ekilooto of Uganda~HIVと共に生まれる~」が開催された。いまエイズ孤児支援ではなにが必要とされているのか。PLAS事務局長の小島美緒氏とフォトジャーナリスト安田菜津紀氏によるトークの模様をお送りする。(構成/出口優夏)
HIVを取り巻く現状
小島 本日は「Ekilooto of Uganda~HIVと共に生まれる~」と題しまして、フォトジャーナリストの安田菜津紀さんとともに、ウガンダやカンボジアにおけるHIVやエイズ孤児の現状をお話ししていきたいと思います。
安田さんはフォトジャーナリストとして、カンボジアやウガンダでHIVと共に生きる方たちの方を熱心に取材されていますね。彼らはいま、どのような状況におかれているのでしょうか?
安田 まず、カンボジアの現状からご説明させていただきます。カンボジアは東南アジアの真ん中に位置している小さな国で、90年代後半まで30年近く内戦がおこなわれていました。内戦によって医療システムの崩壊がおこり、また、貧困層では売買春が蔓延した。その影響で、2000年代初頭には東南アジアでもっともHIVの感染率が高い国になってしまったんですね。その後、HIV対策はかなり進んだのですが、すべての問題が解決したわけではありません。
たとえば、貧困層は病院に行くお金も手段も乏しいので、HIVによる病気が進行してもギリギリまで我慢せざるを得ません。そして、病院にいくときにはすでに手遅れになってしまっている。取材のなかで出会った40歳のチャムロンさんもそのひとりでした。
一人息子のペイくんが3日間寄り添ったかいもなく、入院4日目の朝にチャムロンさんは息を引き取ったのですが、火葬場からチャムロンさんのご遺骨が出てきたときに、おばあちゃんが「息子がこんなに小さくなってしまった」とわーって泣いていたのがとても印象的でした。エイズに蝕まれたチャムロンさんのご遺骨は片手にほんのわずか乗るくらいしか残らなかった。
なぜ、対策が進んできたにもかかわらず、こうした状況は起きてしまうのでしょうか。
現在、HIVの症状をおさえる薬は安く入手できるようになり、貧困層の方でも購入できるようになっています。チャムロンさんもその薬を受け取っていました。しかし、HIVの薬というのはとても時間に厳しい。薬の種類にも、あるいはウィルスの種類によっても異なるのですが、たとえば、薬を数回、飲み忘れてしまうと、体内で薬に対する耐性がついてしまい、薬が効かなくなってしまうこともあるんですね。チャムロンさんは時計の文字盤が読めなかったため、薬を時間通りに飲むことができませんでした。
この背景にはカンボジアの医療の現状があります。カンボジアでは内戦後、国内に生き残ったお医者さんが40人しかいなかったと言われています。お医者さんの数が少なければ、患者さん一人ひとりにかけられる時間が限られてしまう。だから、薬を渡すことができても、患者がしっかり時間通りに飲んでいるかどうかまでチェックすることは難しいんですね。
また、最新の薬が送り込まれてきても、お医者さんの知識不足のために処方できないこともあります。「最新の薬があっても使いこなせる人が育っていない」という医療の現状がカンボジアにおける一番の課題ではないでしょうか。わたしたちは支援の方法を考えていかなければなりませんね。
つぎにウガンダのことをお話ししていきたいと思います。ウガンダはカンボジアと同じく内戦がつづいており、政情がかなり不安定な国です。1990年代にはHIV感染率が18%に達するときもありました。その後、国をあげて対策に乗り出したこともあり、いまでは感染率が6%まで低下していますが、それでもまだまだ高水準と言えます。
ウガンダでは、国がマスメディアやNGOと連携してHIV予防の啓発活動をおこなっている一方で、海外からの支援金を政府が流用するという汚職事件も発生してしまっています。無料で処方されるはずの薬を、病院関係者や運送人などが転売しているという事例も多くある。そのせいで、病院で処方する薬が品切れになってしまうということも起こっているんですね。ウガンダにおける一番の課題はこうした汚職問題とのたたかいだと思います。
エイズ孤児の現実
小島 現在、全世界ではHIVと共に生きる人が3,400万人を超えると言われています。なかには小さなお子さんを持つ親御さんも多い。彼らがエイズを発症して、亡くなったときに取り残されてしまうのがエイズ孤児です。
エイズ孤児はさまざまなリスクを抱えています。たとえば、HIVは性交渉で感染するので、片親だけでなく、両親ともエイズで亡くしてしまう可能性が非常に高い。また、HIVの正しい知識が広まっていないため、エイズ孤児は差別され、村八分の状態にされてしまうことも多くあるんですね。このあとは、そういったエイズ孤児についてお話しをしていきたいと思います。
まず、プラスがウガンダで事業をおこなっていくなかで出会ったご家族の例を紹介させていただきます。このご家庭では、娘夫婦をエイズで亡くしてしまい、おばあちゃんがひとりで孫たちを養っています。
こういった家族構成は決して珍しいことではありません。ある家庭では13人の子どもをおばあちゃんひとりで育てていることもありました。また、家の前に置き去りにされていたエイズ孤児を引き取って、わが子同然に育てている家庭もあります。
このように、エイズ孤児の子どもたちは、それぞれが悲しみや苦しみを持ちつづけながらも、懸命に生きているわけです。
母子感染はなぜ起こるのか
小島 わたしたちNGOは現地の状況を数値やデータで分析し、より良い支援を探っていくというかたちでエイズ孤児に対するアプローチをおこなっています。一方で、安田さんはフォトジャーナリストという立場から、一人ひとりのエイズ孤児により深く向き合ってこられたのではないでしょうか。安田さんが出会ってきた子どもたちのエピソードをお教えください。
安田 そうですね。エイズ孤児のことだけでなく、母子感染のことも交えながらお話していきたいと思います。
最初に、トーイというカンボジアでわたしが一番親しくしている男の子の話をしたいと思います。トーイは、母子感染によって生まれながらにHIVに感染しています。
母子感染について少々説明させていただきます。「HIVの親から生まれた子どもはHIVである」という偏見がありますが、100%母子感染するとは限りません。むしろ適切な処置をおこなった場合の母子感染率は、わずか5%程に過ぎない。しかし、母親がなにも対策をしなければ、3~4割ほどの確率で母子感染がおこってしまいます。
トーイの場合も、お母さんは自分の感染にさえ気づかないままトーイを生んでしまいました。ある日、トーイが体調を崩して病院に行ったときにはじめて、トーイとその両親がHIVに感染していることがわかったのです。
こういったケースは珍しいことではありません。カンボジアは保険制度が未整備なので、病院に行けば行くほどお金がかかってしまう。だから、カンボジアの貧困層では母子医療が根付いていないんですね。
つぎに、ウガンダで親しくしているレーガンの話をしたいと思います。レーガンも母子感染で、生まれながらにHIV陽性者でした。彼の場合は薬の副作用による肌荒れが顕著に見受けられ、学校などで友達に差別されていた。
よくレーガンは「怖いのはHIVそのものではなくて、さまざまなことが重なって生きる希望を失うことだ」といいます。HIVにかかった子どもは病気そのものだけでなく、社会の目や偏見差別ともたたかわなければいけない。一度に何十もの苦を背負ってしまうのが母子感染の苦しいところですね。
小島 ありがとうございます。いま安田さんがおっしゃっていたように、母子感染は防げるものであり、適切な処置や治療がいくつもあります。ただ、現地の人々がそれを知らないことが一番大きな問題なんですね。
そこでわたしたちプラスは、母子感染予防啓発活動をおこなっています。「3年後までに妊産婦検診に通い安全に出産する妊産婦の数を2割増やす」ということを目標に、現地でボランティアの啓発リーダーを選出して、その方たちがHIVの正しい知識をほかの住民に教えていくというモデルを組んでいます。
昨年の3月に始まったのですが、1年間に約9,000人の地域住民の方々にHIVや母子感染に関する情報をお伝えしてきました。「教育」というのは、自分の命だけでなく、大切な人の命にもつながっていく非常に重要なことだと思います。
生きる原動力は家族の絆
小島 HIV感染率が高い地域では、大切な家族や自分自身の命がいつまでつづくかわからないという非常に過酷な状況を強いられています。しかし、そうしたなかでも希望を失わずに夢を持ちつづけている人が沢山いらっしゃるんですよね。彼らの生きる原動力はどういったところにあると安田さんはお考えでしょうか。
安田 わたしは家族の絆や支え合いではないかなと思っています。
たとえば、さきほどお話ししたレーガンはすでにエイズでお父さんを亡くしていて、お母さんと妹のジョフィアの3人で暮らしています。しかし、じつはジョフィアは妹ではなくて従兄妹なんですね。ジョフィアの両親はエイズですでに亡くなっているので、レーガンの家族が引き取ったんです。でも、レーガンは「自分はジョフィアのことを本当の妹と思いつづける」と言っていました。また、一緒に暮らしてはいませんが、レーガンのお兄ちゃんは中学を中退して出稼ぎに行き、なんとかレーガンを学校に通わせようとがんばっています。
たしかに彼らを取り巻く環境は過酷なものですが、そのなかでも家族の絆や支え合いは存在している。そして、彼らの命はそれらによってつながれているのではないかと思います。
ただ、その一方で当事者である彼らの声はなかなか外に出てきません。しかし、どうにかして外に伝えなければ、彼らの状況が改善されることはない。社会問題はたくさんの方が認識しない限り、そもそも問題として扱われないですから。そこで、わたしの場合は写真という手段で彼らの声を伝えていこうと思っています。どこまで力になれるかはわかりません。でもやはり写真の一枚一枚が彼らの拡声器であってほしい、彼らの声を写真が代弁して欲しいと思います。
小島 NGOとしてエイズ孤児というマイナーな問題に取り組んでいますと、「アフリカは遠いよね」とか、「エイズ孤児は自分に関係ないよね」という声をよく聞きます。そのたびに自分たちの力不足を実感してしまう。
安田 アフリカってすごく遠いし、行ったことがある人も少ないと思います。でも、日本のタコの6割はアフリカ西海岸から輸入されていますし、10円玉の銅はザンビア産のもの。自分が知らないだけで、じつはアフリカってわたしたちの生活に溶け込んでいる部分が結構あるんですよね。そういうことを知っていくだけでも、なんとなくアフリカとの距離が縮まっていく気がします。HIVの問題ももちろん知ってほしいですが、まずはタッチアフリカということで。

それぞれの立場に応じた役割を見つける
小島 HIVの問題に関わるお仕事をしているという意味では、安田さんとわたしたちには共通項がある。その一方で、問題に対する切り口はまったく異なっていますよね。
NGOの場合、地域に入るとき際は、気をつけなければいけないことがいくつかあります。たとえば地域住民から賄賂を要求されたりと、なにをするにもお金を要求されてしまいがち。また、わたしたちの事業が地域住民の理解を得られないこともあります。つねづね、地域で事業を展開する難しさを感じてきました。
そして、支援という名前でただお金を流すだけではなく、わたしたちの事業が終了したあとも現地の方だけで自立的な運営がおこなえるようにしなければならない。本日の安田さんのお話を聞いて、地域の人たちと向き合う姿勢を学ばせていただいた気がします。
安田 わたしにとってもNGOのみなさまと一緒になにかをやらせていただく機会というのはとても大事なものです。というのもジャーナリストって現場では、本当に無力なんですよね。写真を使って人の命は救うことはできない。しかし、そこは役割分担だと割り切っています。
カンボジアにいたとき、現地のNGOの方に、「NGOは現地で人に寄り添いながら活動することはできるけれど、ここでなにが起きているのかを世界に発信していくことはできない。菜津紀さん、あなたは通いつづけることはできるし、多くの人に伝えて欲しい」と言われたことがあります。きっと、多くの方が「なにかしたい」と思っている。一人ひとりがすべての役割を果たすことはできませんが、みなさんがそれぞれの立場に応じた役割をみつけてほしいなと思っています。
●エイズ孤児支援NGO・PLAS:http://www.plas-aids.org/
(2013年1月23日 目黒にて)
プロフィール
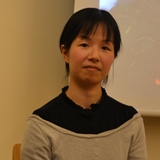
小島美緒
エイズ孤児支援NGO・PLAS事務局長。ICU卒。大学卒業後、ウガンダへボランティアに行ったことをきっかけにエイズ孤児支援に興味を持つ。帰国後は外資系証券会社勤務を経て現職。現在は国内での広報活動や、資金調達活動に携わっている。

安田菜津紀
studio AFTERMODE 所属/フォトジャーナリスト。上智大学卒。2003年8月、「国境なき子どもたち」の友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。2006年、写真と出会ったことを機に、カンボジアを中心に各地の取材を始める。現在、東南アジアの貧困問題や、中東の難民問題などを中心に取材を進める。2008年7月、青年版国民栄誉賞「人間力大賞」会頭特別賞を受賞。2009年、日本ドキュメンタリー写真ユースコンテスト大賞受賞。共著『アジア×カメラ「正解」のない旅へ』。




