2018.12.03

「働く上での障害」をなくしインクルーシブな職場づくりを
省庁・地方自治体の障害者雇用水増し問題は、多くの当事者や当事者家族、そして日々障害のある方に関わる支援者にとってショッキングな出来事であった。第三者検証委員会の報告によると、省庁33機関中28機関が3,700名、地方自治体は3,800名、合計7,500名が不適切に計上されていた。今後、法定雇用率を達成するためには、中央省庁では4,000名の採用が必要になるとのことである(注1)。
(注1)2018年10月22日・毎日新聞より
この問題は、「雇用すべき障害者を雇用していなかったため、不足分雇用したらそれでよい」という話でもないだろう。障害者雇用、雇用率の在り方について改めて整理をする必要性を感じる。そして、この問題は障害のある人を雇用する公的・民間企業におけるそもそもの働き方、職場の文化や組織の在り方にも示唆を与えている。
本稿では、障害のある人の就労支援と障害のある子どもの発達支援に携わる者として、就労支援の実情や具体的な事例を交えながら本件の背景にある問題を整理し、解決の方向性を提案したい。
何のための雇用率制度か
日本では1960年に身体障害のある人を対象とした「身体障害者雇用促進法」が制定され、その際に雇用率が義務付けられた(注2)。その後1987年にはその対象がすべての種類の障害者に拡大し、名称が「障害者雇用促進法」に変更されている。現在では民間機関は2.2%、国の機関は2.5%の雇用が義務付けられている(注3)。さらに今後それぞれ2.3%、2.6%と引き上げられる予定だ。
(注2)制定当時公的機関は義務、民間企業は努力目標。民間企業は1976年に義務化。
(注3)平成30年4月に義務付けられている雇用率。なお、都道府県の教育委員会は2.4%。
このように障害者雇用に関わる制度が整備されてきた背景には、「障害者の権利」に関する動きがある。国連ではこれまで一貫して障害者の「完全参加と平等」を謳い、各種宣言や条約が採択されてきた。近年の動向としては、日本も2014年に批准した「障害者の権利に関する条約」の第27条の「労働及び雇用」に、「障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利」との記述がある。
「障害のある人は障害のない人と同様に就労機会を提供されるべき」「労働環境は障害者を包容すべき」といった文言を聞き、異論を唱える人はおそらくいないであろう。本来、雇用率制度がなくても、障害のない人同様の就労機会を得られるべきだ。しかし、現実的には今の社会では雇用率の制度がないと、障害のある人の雇用は実現されづらい。それは、今の社会では多様な人を内包し活かすことがまだできていないからである。
「雇用率の達成」は最終目的ではない。本来の目的は、多様な人を内包・包摂する職場環境(インクルーシブな職場環境)を作り、障害のある人も障害のない人同様働く機会を得ることで、障害のある人の働く権利を守ること。今回の水増し問題の報告からは、「雇用率の達成」自体が目的化し、本来の雇用率制度の趣旨が薄れていってしまったようにも見える。そして、他にも同様な問題、つまり雇用率の達成自体が目的化してしまっている組織もあるかもしれない。
医学的な障害≠働く上での障害
ではどのようにして本来の目的を見失わずに、障害者雇用を推進していったらよいのか。障害者雇用を考えるとき、その難しさを障害当事者の医学的な診断としての「障害」そのものに置く人は多いだろう。現に雇用率も医学的な診断がベースになっている。
しかし、はたして働くことが難しい要因は本当に医学的な診断としての障害そのものにあるのだろうか。例えば車いすに乗っている、下肢に障害のある方がいるとする。その方の職務内容が移動のない内容だったら、その方は困難さをどこまで感じるだろうか。
もしくは、移動する仕事であっても、建物がすべてバリアフリーだったらどうだろう。職種や環境によっては、働く上での障害はほぼない状態もありえるかもしれない。このように障害を個人と社会環境との相互作用で捉える社会モデルで捉えると、その人の医学的な診断としての障害は「働く上での障害」とイコールではないと言える。
一方、現状の雇用率は医学的な診断をベースにカウントされるため、障害種と障害種ごとの雇用数や雇用率のみに焦点が当たりやすく、「働く上での障害」として捉えて雇用し職場での工夫を推進することを難しくしてしまっているとも考えられる。
合理的な調整で働く上での障害をなくす
つまり、障害者雇用を進める上では、その方の医学的な障害名や症状について知ることも重要だが、「その人」が「その職場」で「その職務内容」を実施するときに、どんな困難さがあるか?を明らかにすることの方がより必要な情報になる。この「働く上での障害」を明らかにしていき、その障害を最小限にしていくプロセスこそが、障害者雇用を実施する上でもっとも重要なポイントになる。そしてこのプロセスが2016年4月に施行された障害者差別解消法における合理的配慮提供のプロセスである。
「合理的配慮」と聞くと、配慮を「してもらう」「してあげる」という関係性を想起しがちだが、原語は“reasonable accommodation”であり、「合理的な調整」や「合理的な工夫」ともいえる。その人の働く上での障害を明らかにし、それをなくしたり減らしたりするためにどのような工夫ができるか、共に話し合い決定していく。障害者雇用においてはその合意形成のプロセスが欠かせない。合理的配慮の手順としては、以下のステップをおすすめする。
(1)働く上での困難さを明らかにする(例:通勤時、移動時、会議時、コミュニケーションの取り方、休憩の仕方、集中しやすい環境など)。
(2)困難さを減らすための工夫をなるべくたくさん考える。
(3)その中でお互いにとって無理のない工夫を選択する。
(4)実際に工夫を実施してみる。
(5)工夫をした結果どうだったかを定期に見直す。
同じ医学的な診断があってもその人の状態像や抱えている困りごとは一人ひとり違い、さらに職種や職場の環境によって働く上での障害がどのくらいあるかは大きく左右される。そのため、障害名で一括りにせず、ご本人と共に話し合いを通して決めていくプロセスを大切にしたい。
筆者が働いている株式会社LITALICOの就労移行支援事業「LITALICOワークス」では、まず就労移行支援事業所に通所している間に利用者自身が働く際に感じるであろう困難さをご本人と確認をする。就職の際は、人事担当の方のみでなく、必ず直属の上司も同席いただき、ご本人が想定している「働く上での障害」をお伝えし、それに対してその職場でできそうな工夫をともに検討することを基本としている。
発達障害のあるAさんの働く上での障害とそれを減らす合理的な工夫
例えば、発達障害のある方の場合はどうだろうか。発達障害と一言で言っても、その状態や抱える困難さは一人ひとり違う。私が就労支援に関わったAさんは自閉症スペクトラムの診断があった。独学で学んだプログラミングが得意でミスがとても少ないため、エンジニアの職種を探していた。
Aさんは聴覚に過敏さがあり、ガヤガヤした周りの音やエアコンなどの機器の音が聞こえすぎてしまい、そのような音が聞こえる環境だと集中することが難しい。また、急に音が聞こえると驚きパニックになる。例えば急な放送やいつ鳴るかわからない電話の音にも過敏に反応する。また、自分の疲れ具合を自ら把握し自ら休憩を取ることが難しく、食事をとることを忘れてしまうくらい、集中しすぎてしまう。そのように集中しているときに他者に急に話しかけられるとパニックになることもあった。
Aさんがエンジニアとして仕事をする場合、働く上での障害は何になるだろうか。また、どのような職場でどのような工夫があったら働く上での障害を最小限にすることができるだろうか。
まず、物理的な職場の環境としては、周りの人の声や電話が聞こえづらい場所がよいであろう。そのような個室や一角が用意できる職場があれば良いが、もしない場合はノイズキャンセリングのヘッドホンを活用するのも良いかもしれない。集中しすぎてしまうことについては、毎日作業内容を確認し、休憩をとるタイミングを事前に決めておくのもよいかもしれない。
もしくは、音はびっくりしてしまうためタイマーなどは使わず、PCのカレンダーに休憩時間を登録し、休憩時間になったらカレンダーがリマインドをしてくれる設定にできるとよいかもしれない。急に話しかけるとびっくりすることは事前に職場のメンバーに伝えておき、チャットなどのツールで話しかけるようにするのも一つだろう。
そして、職場の文化としては、ヘッドホンをすることや、Aさんの特性に応じて話しかけ方を工夫することができる、などを受け入れることのできる文化が必要であろう。
これらの工夫を、勝手に雇用主やAさんそれぞれが決めるのではなく、上記のステップの通り、共に話し合いを通して決めていく。
誰もが働きやすいインクルーシブな職場づくりとセットで推進する
障害者雇用は単独で進めるのではなく、インクルーシブな職場づくりとセットで計画し推進する必要がある。なぜなら、働く上での障害があるのは、医学的な障害のある方のみではない。読者ももしかしたら現在働いている職場にて「障害」を感じているかもしれない。「じつは自分は朝より夜のほうが集中できる」という人は、フレックス制度のある職場だったら障害を感じないが、シフトが決まっていてその時間通りに出勤をしなければならない職場だったら障害を感じるだろう。
育児中の方であったらリモートで働けたら働く上での障害を感じないかもしれない。多様な人が働くことを前提とした職場づくりがなされていると、障害のある方が働くことになっても、とくに働く上での障害を感じず、その職場では合理的な配慮はとくに必要なかったりすることもある。仮にAさんの職場がチャットやカレンダーが当然のように活用されていて、ほかの人もヘッドホンをしていることが当たり前の職場だったら、Aさんも安心して働けるであろう。
インクルーシブな職場づくりのためには、フレックスやリモートで働ける制度、パートナーシップに関する制度などの整備ももちろん重要であるが、どの社員であっても困難さを感じたときに相談がしやすかったり、お互いの得意不得意を自己開示しあい苦手を補い合ったりする仕組みづくりや文化づくりがかかせない。直属の上司には相談しづらいこともあるため、多様な相談先を仕組みとして用意しておくことと、誰もが気軽に困ったことを相談し合えることが当たり前であると、障害のある人も相談がしやすいし、助けも求めやすい。
そして、「完璧な仕事をすること」をお互いに求め合う職場文化では、なかなか多様な人は働きづらい。お互いの得意不得意、強み弱みを知り合い、苦手を補い合うチームづくりをしていく。「できないこと」よりも「できること」に着目し、どうしてもやらなければならない「できないこと」に対しては、できるための工夫を考える。障害の有無にかかわらず、お互いにこのような働きかけをすることがインクルーシブな文化をつくることにつながる。
さいごに
どんなに障害者雇用を推進したとしても、インクルーシブな職場づくりが根幹にないと、なかなかその職場で働き続けることは難しい。今回の問題を機に、民間企業も官公庁も障害者雇用を進めるのみでなく、誰もが働きやすいインクルーシブな職場づくりを社会全体で目指したい。
また、現状は、仮に働いている多様な人たちの働く上での障害が限りなく少ないインクルーシブな企業や組織があったとしてもなかなかそれが外からは見えづらいため、評価もされづらく、よい実践や仕組みが共有されづらい。個々についているラベルの多さのみでその組織の「インクルーシブ度」を測るのではなく、その組織がどれだけ多様な人の働く上での障害をなくしているか?によって「インクルーシブ度」を測れるような仕組みを考えていきたい。
参考
プロフィール
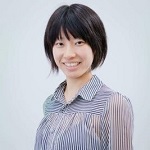
野口晃菜
1985年生まれ。小学校6年生の時にアメリカへ渡り、
高校卒業時に日本へ帰国、
共著に「インクルーシブ教育ってどんな教育?」や「


