2022.02.01
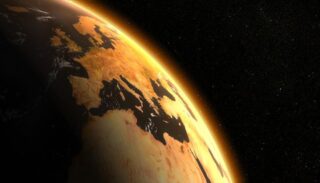
人新世と気候工学――経済思想と環境倫理学の対話
シリーズ「環境倫理学のフロンティア」では、環境倫理学の隣接分野の研究者との対話を行っています。今回は「経済思想×環境倫理学」として、『経済的思考の転回』(以文社、2014年)の著者である桑田学さんと対話を行います。桑田さんは、人新世と気候工学についても研究されており、『現代思想』の人新世特集や気候変動特集に原稿を寄せています。今回は、これらの内容をふまえて、狭義の環境経済学を超えた、人新世の経済思想についてお話しいただきます。
思想史研究と環境倫理学
吉永 2018年3月に私と福永真弓さんとの共編で勁草書房から『未来の環境倫理学』を出版しましたが、そのなかで桑田さんに、人新世と気候工学についての章を執筆していただきました。その後も朝日新聞(2018年8月20日)にインタビュー記事が掲載されるなど、人新世と気候工学の研究者としてご活躍されています。
他方で、『現代思想』2020年2月号の気候変動特集に寄稿された「思想史のなかの気候変動」のなかで、経済学者のジェヴォンズとラスキンについて論じられていることからもわかるように、もともとは経済思想がご専門ですよね。私からすると、経済思想のご専門の方が環境倫理学的なテーマについてアクチュアルに発言をされており、興味を惹かれます。思想史研究と環境倫理学とが見事に結合されているとように思います。この両者の位置づけについては、どのようにお考えでしょうか。
桑田 私のなかでは、両者は相補的な関係にあると考えています。環境倫理学は現在において問われるべき問題とは何であり、あるいはその際にいかなる観点が求められているのか、その先端を学ぶ領域といった感覚を持っています。たとえば気候危機や人新世をめぐる議論にかんしても、人文学や社会科学の視点から考えるべき問いを磨くうえで環境倫理学の研究成果は大事な視点を与えてくれます。思想史研究は、歴史的な言説やテクストを読み解くことがメインになりますが、その際に読み手(自分)の側に分析の視角や観点が十分に自覚されていなければ、アクチュアリティのある研究とはなりえませんが、私の場合にはそうした分析の視角や観点を練り上げる際に環境倫理学や環境思想の研究動向も参考にしています。
他方で、とくに英米圏の環境倫理学や規範理論は私にとってそのままでは抽象的すぎて、ときにリアルに問題が感じられないという感覚ももっています。それはたんに私が抽象的な思考が苦手というだけなのですが、自分としてはその点に思想史研究の重要な役割があるのではないかと思っています。つまり、現在の争われている問題の来歴・由来を探究したり、歴史的な文脈づけを行ったりすることで、現代の環境倫理学で問われている問題がよりリアルに迫ってくるという面も確かにあるということです。現代と歴史の両輪をうまく活かした研究を進めることができればと思っています。
人新世について
吉永 人新世と経済思想といえば、2020年に話題になった斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』(集英社新書)があります。とても読みやすく、また共感できる内容ですが、他方で目から鱗が落ちる話ではなく、どこか既視感のある話だと思いながら読みました。素人考えですが、結論部分の脱成長コミュニズムというのは、ラスキンとモリスの話ではないか、という気もするのです。國分功一郎さんと山崎亮さんの共著『僕らの社会主義』(ちくま新書、2017年)を思い出しました。また斎藤さんは、市場と経済の切りわけとか、経済の社会への埋め込みを説いているわけですが、これはカール・ポランニーの主張を連想させます。
そんな中で、桑田さんの著書『経済的思考の転回』を読み直したら、ここに同じことが書いてあることに気づいたのです。主な考察対象はオットー・ノイラートの経済思想ですが、176頁の「市場の形式に還元されない、人間の必要や欲求の多面性、そしてこれを充足する自然界の多様な構成要素を含む、人間の生のマテリアルな次元の再生産としての経済の意味」とか、198頁の「資源やエネルギー、あるいはそれらの支出によって作られるモノの使用価値を完全に引き出すこと、つまりは人間の幸福に十全に結びつけること」および「ニーズ充足を目的とした消費を規準に生産や労働時間を調整する必要性を指摘するとともに、生産される財の耐久性や生産技術の質を一定の科学的知見から評価し管理する科学者や技術者のアソシエイションが果たす役割」といった箇所は、言葉遣いから内容まで、斎藤さんの本からの抜き書きとして提示しても通用するほど酷似しています。
ノイラートはマルクス以後の経済学者なのだから、当然マルクスの影響を受けているのではないか、と思われるかもしれません。しかし、斎藤さんの論旨は、脱成長コミュニズムは、忘れられていた晩期マルクスの思想を掘り起こすことによって新しく導き出されたものだ、というものです。ところが桑田さんの本を読むと、晩期マルクスを持ち出さなくても、他の人が同種のことを主張していたことが分かります。ラスキン、モリス、ポランニー、ノイラート、これらの人々に依拠したほうが脱成長コミュニズムという言葉で言わんとしている内容をよりストレートに語れるのではないかと思います。長くなりましたが、桑田さんは『人新世の「資本論」』をどう読まれましたか。
桑田 『人新世の「資本論」』は私も刊行されてすぐに拝読しましたが、私自身かなり近い問題意識をもっており、また扱われている文献も自分の研究と重なるところがあって、本当にすらすらと内容が頭に入りました。斎藤さんはマルクスを対象としていますが、マルクスの新しい解釈それ自体だけでなく、マルクスと現代をつないでいく作法や「脱成長コミュニズム」のような具体的なヴィジョンの提示という点でも大いに勉強になりました。
人新世をめぐる問題は、本当に巨大かつ多面的であって、自然科学、社会科学、人文学を含むきわめて広範な視点・視座から読み解いていかなければ、解決の方向性はもちろん、問題の正しい理解にいたりつくことも困難です。さらには既存の科学や知識のあり方そのものが問い直されるべきものでもあると思います。そうしたなかで、経済思想や社会思想からアプローチする場合でも、マルクスはもちろん重要ですが、それ以外にも色々な知的資源や歴史的なコンテクストが動員できる方が当然ながら良いと思っています。特定の思想家から「これが解決策だ」などと安易に考えるのは危険ですから(もちろん斎藤さんはそのような乱暴な議論をしていません)。マルクスの眼によって浮かび上がってくる側面もあれば、そうでないものもまだ沢山あると思います。
「人新世」という概念を提唱したのは大気化学者のパウル・クルッツェンです。彼は人新世の始まりは蒸気機関を用いた石炭の大規模燃焼が始まった産業革命期だとしていますが、少なくとも19世紀には現在のシステムを特徴づける諸要素(階級対立、中核による周辺の資源・労働力の収奪、土壌の劣化や石炭枯渇の不安、水や大気の汚染等々)はすでに存在していました。ですから、マルクスだけでなく、これらの問題を資本主義的な産業社会の深刻な欠陥として受け止めていた他の思想家や科学者がいてもまったく不思議ではありません。そうした歴史に埋もれた人新世的問題をめぐる知や論争を掘り起こしてみたいと思っています。
気候工学について
吉永 なるほど、しかし私は斎藤さんのこの本には不満があるのです。この本では人新世についてあまり立ち入った考察がなされず、「人類が地球を破壊しつくす時代」として、もっぱら人類が気候を大規模に変化させた時代の名称として、人新世が用いられています。他方、斎藤さんが『現代思想』に寄稿された論文「人新世のマルクス主義と環境危機」では、人新世と、気候変動対策としての気候工学(ここでは地球工学と呼ばれています)との関連についてふれられています。この点は重要です。というのも、クルッツェンは気候工学を正当化するために人新世という概念を持ち出したという面があるからです。人間は地球環境を悪い方向に変えてしまった、だからもう一回良い方向に変えよう、という含みがあります。桑田さんも次のように書いています。
「クルッツェンにとって、人新世の到来を人類が自覚するということは、気候変動対策においても、テクノロジーによる気候システムの大規模な操作と改変という従来とは異次元の段階へと足を踏み入れていかざるを得ないことを意味していたといってよい」(「人新世と気候工学」『現代思想』2017年12月号、122-123頁)。
そして今では「「意図せざる地球の改変」から気候工学を軸とする「意識的な地球システムの技術的管理」への移行は、ときに「悪しき人新世Bad Anthropocene」から「善き人新世Bad Anthropocene」への転換として表象される」(同、124頁)こともあるわけです。
気候工学については斎藤さんも言及していますが、クルッツェンの意図について明確には記されていません。このあたりについて、桑田さんにあらためて解説していただければと思います。
桑田 クルッツェンが遅々として進まない気候変動対策の状況を受けて、気候工学の「研究」の必要性を訴えたのは確かですが、彼自身が気候工学の「実施」をどれだけ具体性をもって考えていたかは定かではありません。しかし、現代の気候危機を自然科学の観点からのみ捉えてしまうと、気候工学のような技術的解決が妥当であるかのように見えてしまう危険性があることには十分注意しておく必要があると思います。
今年出されたIPCCの第六次評価報告書も示すように、現在の気候変動は非常に危険な状態です。温室効果ガスの早急な削減なしにはかなり破局的な事態(気候の非常事態)が引き起こされるという予測は、しっかりと受け止めなければなりません。
とはいえ、斎藤さんも強調しておられるように、絶えざる成長や資本蓄積を求める資本主義的なシステムにおいて、果たして先進国の政府やその主要企業が、化石燃料の大量燃焼、核廃棄物、資源や安価な労働力の大規模な収奪といった深刻な問題について、きちんと自己批判して対処できるかどうかはたいへん疑わしい(実際クルッツェンは先進国の緩和策は失敗していると考えていました)。そうした現在のシステムを変更不可能なものと「諦念」してしまえば、彼のように、いまから(産業革命以前と比して)2度上昇へと突き進んでしまうような最悪のケースを考えて、本来は望ましくないとしても気候工学研究に着手すべきだと主張するのは、当然なこと、賢明な対応であるようにみえます。現にクルッツェンの提案以後、気候工学研究は飛躍的に進展しました。
そもそもこうした議論には、気候工学という技術を現在の国際社会が適切にガバナンスできるというあまりに甘い想定があるように思えてなりません。システムの脱炭素に向け国際社会がコスモポリタンな視点で協調・協働することが困難な社会状況があるとすれば、またそのような状況からグローバル・ノースが恩恵を享受し続けようとしているならば(倫理学者のステファン・ガーディナーはこうした状況を「道徳性の破局」と呼んでいます)、この構造を問わずして気候工学のような複雑な技術の運用について楽観することはあまりに危険です。
気候正義の運動が主張しているように、現在の気候危機はこれまでの成長と開発を何より重視してきた政治経済システムの帰結であり、さらにそのなかで膨大なコストを一方的に転嫁されてきた貧しい地域や人々がいることは明らかです。このシステムそれ自体を根本的に反省することなければ、気候工学の実施は問題の解決どころか、さらなる国際的な対立や紛争を招くだけのように思います。現在、気候工学の「ガバナンス」についても研究されてはいますが、気候変動の問題の背後にある資源収奪的な経済システムの問題にまで議論の射程が届いているかといえば、残念ながらそうとは思えません。
吉永 ありがとうございます。いま気候工学はどんどん進められていますが、そこにはたくさんの倫理的問題があり、それを桑田さんは『未来の環境倫理学』のなかでコンパクトにまとめられています。あらためて気候工学の倫理的問題についてお話しいただけますか。
桑田 気候工学にはいくつかのタイプがありますが、ここではそのなかでも実現可能性が期待されている「成層圏エアロゾル注入」(以下SAIと略記)に限定します。これは成層圏に粒子状物質を散布し、太陽入射光の反射率を高めることで全球平均気温の上昇を抑制する技術です。
まずこの手法の気象学的なリスクとして、アジアやアフリカのモンスーン地域における降雨量を減少させ旱魃を深刻化させる可能性や、全球規模の水循環を弱める効果をもつことが懸念されています。とくに南米やアフリカ、東南アジアでの降雨量の減少は、農業生産や飲み水の利用条件に大きな損害を与え、人びとの生存条件を著しく悪化させる恐れがあります。注意すべきは、これらの地域は、概してCO2排出に関していえば、加害者というよりむしろ被害者ということです。問題に最小限の責任しかない人びとが、気候変動の影響だけでなく、SAIに伴う危害をも被るとすれば、それは不正の上塗り(複合的不正義)になりかねません。つまりSAIの実施が新たな気候体制のもとで「勝者」と「敗者」をつくりだすことが十分に予想されますが、こうした事態の予期は、気候変動対策に不可欠な国境を超えた相互信頼や連帯、協力関係に新たに深刻な亀裂を生じかかねないということです。
第二に「モラルハザード」の問題です。気候工学研究が進むことで、それが気候変動に対する一つの「保険」とみなされ、CO2排出削減努力が、とくにより大きな排出削減義務をもつ先進国のあいだで著しく低下するのではないかと懸念されています。SAIが緩和策(排出削減)失敗の際の「保険」とみなされていけば、緩和への政治・社会的努力はいっそう後退しかねません。ましてや、大胆な緩和策が進まない背景に現状維持の趨勢(政治的惰性)や政治の機能不全が存在するとすれば、現状から大きな利益を得ている化石燃料・資源の大量消費国は、さらなる緩和努力の先送りという「道徳的腐敗」に陥る懸念があります。
第三に、経路依存性やロックインと呼ばれる問題があります。気候工学をめぐる議論では、研究、実験、実施はそれぞれ区別されていますが、しかし現実にそれらを厳密に区別することが可能かどうかはきわめて不透明です。研究であれば問題ないだろうと思われますが、研究と一口にいっても、気候モデルでのシミュレーションから本格的な屋外実験、さらには国家規模の「マンハッタン計画」のようなものまで、そのレベルはさまざまです。しかし一定規模の研究資金が継続的に投入されるようになれば、制度的な推進力が働いて研究と実施の区別は曖昧なものとなるおそれがあります。
もっとも、ここに挙げたのは倫理的な問題のごく一部だろうと思います。
吉永 ありがとうございます。これは本来、環境倫理学者がなすべき仕事です。桑田さんは、ご論考の中で気候工学に関してこう書いています。
「気候工学(太陽放射管理)は唯一、経済的に競争力の高いテクノロジーであるらしいが、当然そこで前提とされるコスト計算は考慮すべき問題の大部分を欠落させている。その意味でも、環境倫理(環境正義や未来世代への責任)といった規範的な視点から計算不可能なことがらを明るみにすることは大切だろうし、技術デザインの背後にある政治的意図や権力関係を暴く技術哲学的分析も重要であろう。そしておそらく同様に重要なのは、意図的な気候改変の実践や思考の系譜を遡り、歴史的なコンテクストに位置付けなおしてみることである」(「フレデリック・ソディと〈破局〉の経済思想」『現代思想』2015年9月号、188頁)。
狭義の経済的な視点だけでなく、環境倫理的、技術哲学的、歴史的な視点が必要だ、ということで、環境倫理学と思想史の役割を共に重視しているわけですが、ここで環境倫理学の仕事として「計算不可能なことがらを明るみにする」ことが挙げられているのに興味を惹かれました。環境倫理学の主要な仕事はコスト計算に収斂されない価値の提示にある、とのお考えでしょうか。というのも、私が研究していたマイケル・ウォルツァーの分配的正義論はまさにこれです。それから宇沢弘文先生の「自動車の社会的費用」や「社会的共通資本」の研究もこれですよね。この定義だとお二方も環境倫理学者になり、私にとってはうれしい限りです。
桑田 以前に市民も含めて、気候工学について検討されるべき40の課題を考えるというワークショップに参加させていただきました(その成果はSustainability Science誌に共著論文として掲載されています)。その作業のなかで、環境倫理学や技術哲学の知見がいかに実践的な意義をもっているか、という点を嫌というほど感じました。それは主に言葉や概念の定義、価値の優先順位、社会的文脈や意味に関わる問題です。「どのような背景で登場した技術なのか?」、「そもそもある技術を『研究する』とはどういうことか」、「評価されるべき『リスク』や『コスト』とはいかなる性質のものか?」、「定量化不可能なリスクはいかに評価されるべきか?」例えばこうしたさまざまな厄介な問いをたえず提起し、議論に揺さぶりをかけておかないと、あっという間に「技術-工学的な問題」あるいは「コスト・ベネフィット」の問題に還元されてしまいかねないように感じました。数値では割り切れない問題を浮かび上がらせるうえで、倫理学を含めて人文学的な知がもっと社会のなかで役割を発揮すべきなのだと思います。
吉永 同感です。そしてまさに今おっしゃったことを倫理学の視点から行っている人がいます。アメリカの環境倫理学者シュレーダー=フレチェットです。彼女は『環境リスクと合理的意志決定』(昭和堂、2007年)という本のなかで、リスクを評価する際に数値では割り切れない側面が存在することを的確に説明したうえで、それを数値で割り切れる評価とすり合わせる道を模索しています。技術哲学や科学技術社会論の論点をふまえた環境倫理学を展開しているといえるでしょう。日本では『環境の倫理』(晃洋書房、1993年)という本の編者として知られていましたが、実はリスク論や原発論、そして環境正義の研究が彼女の本領です。彼女のEnvironmental Justiceという本の翻訳が1月に出ます(奥田太郎・寺本剛・吉永明弘監訳『環境正義――平等とデモクラシーの倫理学』勁草書房)。これで彼女の仕事の全貌が明らかになります。
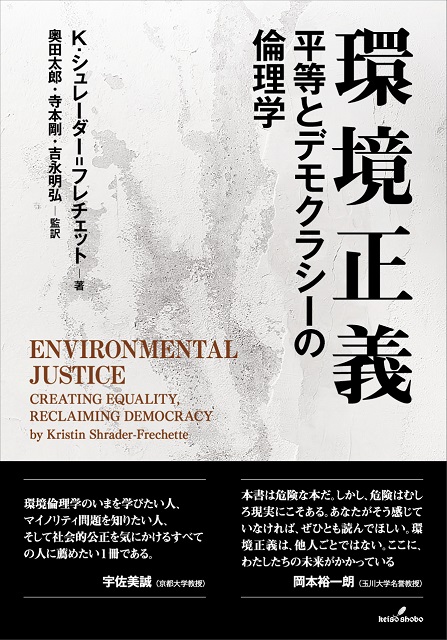
ラスキンの経済思想について
吉永 さて、ここから本来のご専門である経済思想についてうかがいます。桑田さんが研究されている思想家は、ノイラートだけでなく、ポランニー、ラスキン、モリスという、経済学としては異端のほうに位置する人々ですね。さらには物理化学者で経済学者のフレデリック・ソディ、生物学者かつ都市論者かつ経済学者のパトリック・ゲデスといった人たちの業績も検討されています。
私は特に「思想史のなかの気候変動」のなかで論じられているラスキンの思想に惹かれます。一言で言えば、劣化する世界のなかでいかに善く生きるのか、ということがテーマ化されていますが、これこそが人新世における環境倫理学の重要テーマだと思うのです。これまでは気候問題の「緩和」に関する倫理学がメインでした。つまりCO2排出の削減が必要だが、その負担をいかに公平に分配するかということが論じられてきました。他方で現在では、気候問題の「適応」が大きなテーマになっています。これは気候変動によって災害などが多発することが確実視されている世界においてどのように「善く」生き残っていくか、という問題です。今道友信先生が『エコエティカ』(講談社学術文庫、1990年)の中で書かれているように、我々は単に生き残るだけでなく、善く生きることが重要です。先ほどの「劣化する世界のなかでいかに善く生きるのか」というテーマは、適応の時代における環境倫理学の大きなテーマであり、その観点からラスキンは再評価されるべきだと思いました。
桑田 ラスキンの環境思想はこれまでロマン主義の系譜のなかで評価されるのが一般的であったと思います。しかし、彼の思想にはそれに留まらない意味があると思います。たとえば、晩年の『19世紀の嵐雲』(1884年)では、産業が膨大な廃物をつくりだし、環境を汚染するなかで、産業と自然との境界が曖昧となり、そのなかで自然と人間の生がともに劣化していくような破局的な世界が描かれています。まさに現代の人新世の言説を想起させるような内容です。そのなかでとくに重要だと思うのは、ラスキンが自然の破壊や汚染だけを問題にしているのではなく、つねにそれらを人間の労働や生の質の劣化との関係から考えているところです。言い換えれば、ラスキンにおいて、自然と人間との関係の回復は、産業社会において劣化している「労働」や「消費」の変革という問題と不可分に結びつけられていました。
そのような眼でラスキンの経済論を改めて読み直すと、そこでは資本主義や奢侈への道徳主義的な批判ばかりではなく、「人間のエコノミー」と「自然のエコノミー」を総合的に捉えるような問題の立て方がされていることが分かってきます。ラスキンは、同時代の自由主義経済学にとって代わるべき真の「ポリティカル・エコノミー」は、人間の生存にとって不可欠な「清浄な大気、水、土」をもたらすものでなければならず、したがってこの科学の根底には自然についての知(自然科学)が備わっていなければならないと論じています。これは人間の生の基底をなす自然の物質的条件を含めて「生命」と「富」の関係を解明する科学としてポリティカル・エコノミーを再建するという課題ですが、その点でゲデスやソディのような自然科学者にとってもラスキンは大変魅力的に映ったのだと思います。
ちなみに、ラスキン自身は社会主義者ではありませんでしたが、モリスばかりではなく、19世紀末や20世紀初頭のイギリス社会主義の思想に強い影響を与え、ゲデスやソディもそれと非常に近いところで経済学の研究に取り組んでいました。斎藤さんの晩期マルクス解釈は、社会主義とエコロジーの思想史的な連関を示していますが、ラスキンの継承者たちにも、同様の問題(つまり自然の破壊や収奪と人間の生の破壊や劣化との重層性)が強く意識されていました。このことは、現代の人新世や気候工学の問題を考えていくうえでも決して外せない視点だと思います。
これと関連して、歴史学や思想史の分野では、およそ16世紀に始まるヨーロッパの植民地収奪の問題が環境破壊の問題とも関係づけながら論じられていますが、環境倫理学の側ではこういった問題はどう扱われているのでしょうか。
吉永 植民地収奪は、先に挙げた「環境正義」の問題でもあります。最も有名なのはインドの思想家バンダナ・シバによる「バイオパイラシー」(生物学的な強盗)の指摘でしょう。これは先進国の科学者が途上国の生物の細胞や遺伝子を特許化することによって富を得る一方で、原産地である途上国では従来通りの利用が禁止されてしまうという「不正義」を指摘したものです。シヴァはこれを植民地支配の延長だと明言しています(バンダナ・シバ『バイオパイラシー』緑風出版、2002年)
また、日本で「ローカルな環境倫理」を提唱した鬼頭秀一先生は、同じくインドのラマチャンドラ・グーハの議論を引用しながら、先進国の自然保護観、特に米国のウィルダネス保存(人のいない自然を人の手から守る)という考えを「普遍的な環境保護」として途上国に持ち込むと、途上国の土壌流出、大気、水質汚染、食料の安定性、貧困等々のようなもっと解決しなければならないことが見逃されてしまう、と述べています(鬼頭秀一『自然保護を問いなおす』ちくま新書、1996年)。ここでも南北の問題が意識されています。
ついでに環境史と環境倫理学との連携について言えば、米国のなかで「ウィルダネス」と呼ばれていた地域には、かなりの数の先住民が暮らし、そこで耕作をしていたことが、環境史や考古学の研究から明らかにされています。環境倫理学者アンドリュー・ライトは、こうした研究を引用して、ウィルダネス保存から日常の自然(人の生活が絡んだ自然)の保全へという道筋を描いています。
桑田 なるほど、「ウェルダネス」という自然認識それ自体がもつ政治性は非常によくわかります。気候工学もそうなりかねませんが、ポストコロナの社会を考えていくうえで、先進国の「エコ」や「安全」の追求が外部や未来の他者を犠牲にし続けるかたちになることは絶対に避けなければなりません。環境倫理学と経済思想が互いに知恵を出し合ってこの問題を考えていければと思います。
吉永 ありがとうございました。今後もいろいろとご一緒できればと思っています。
プロフィール

吉永明弘
法政大学人間環境学部教授。専門は環境倫理学。著書『

桑田学
福山市立大学都市経営学部准教授。専門は経済思想史・環境思想。著書に『経済的思考の転回―世紀転換期の統治と科学をめぐる知の系譜』(以文社、2014年)、共著に『現代の経済思想』(勁草書房、2014年)、『科学技術社会論の挑戦2―科学技術と社会』(東京大学出版会、2020年)、A Genealogy of Self-Interest in Economics(Springer、2021年)など。


