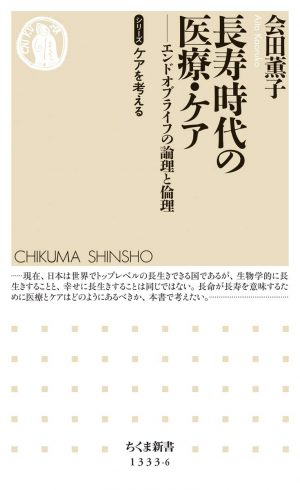2020.02.17

長寿時代の医療・ケア――エンドオブライフの論理と倫理
はじめに
平和と豊かさと長命は人間の希求するところであり、医学・医療が目指してきた生存期間の延長は寿命革命につながった。1947年に約50年だった日本人の平均寿命は、2018年に男性が81年、女性が87年となった。いまや日本は世界でトップレベルの長命国である。
一方、さまざまな加齢変性を抱えながら最期へ向かう過程において、医療のためにかえって本人の苦痛が増し、尊厳が損なわれる場面もみられるようになった。多くの人にとって人生は長くなったが、老衰の進んだ超高齢者に負担となる医療行為が行われ、穏やかな最終段階が阻害されることも多くなった。このジレンマにどのように対応すべきか。
これは臨床現場において「生き終わり」のあり方を考察する臨床死生学の中核のテーマであり、人生の最終段階の医療とケアに関して本人・家族側の意思決定を支援する医療・介護従事者にとっては、臨床倫理上の重要なテーマでもある。
また、これは20世紀後半以降に著しく進展した医療技術の光と影をめぐる問いでもある。そのため先進国特有の問題であるともいえ、日本よりも先に先進国となった米国をはじめとする西洋諸国においては、この問題は日本よりも早く社会的に顕在化した。
人工的水分・栄養補給法について
1)医学的知見と情緒的反応の乖離
医療に関わる事柄を議論する際には、それがどのような分野の議論であっても、その基礎として、時代に合った新しい医学的な知見を踏まえることが必要である。医学的に適切な判断が土台となることで、臨床倫理的に適切な判断も可能となる。医学的な知見は時代に沿って更新されるものであり、そのために学び続けることが必要となる。
しかし、医学的な新知見が語ることは、従来から「常識」とされてきた見解や一般的な情緒的印象から乖離していることもある。そうした場合に、臨床現場では意思決定上の問題が発生しやすい。
例えば、老衰の最終段階やアルツハイマー型認知症末期において摂食嚥下が困難になったとき、人工的に水分と栄養を補給することは医学的および倫理的にどのような意味をもつのだろうか。
この問題は人工的水分・栄養補給法(AHN:artificial hydration and nutrition)が存在しなかった時代には、当然ながら存在しなかった。
AHNには経鼻胃管あるいは胃ろうや腸ろうを経て栄養剤を投与する経腸栄養法と、中心静脈あるいは末梢静脈から栄養分を投与する静脈栄養法がある。経腸栄養法は管を使用するので経管栄養法とも呼ばれる。
AHNが一般的な医療行為となった1970年代以降、この技術は多くの症例にとって福音となった。何しろ、食べることができなくても生きられる時代となったのである。AHNは事故や腫瘍や神経疾患やその他の疾患や障がいのために摂食嚥下困難となった人たちにとって、生き続けることを可能にするための手段となった。大きな医学的進歩であった。
一方で、人生の最終段階に到り、生命体として終焉を迎えているために食べなくなっている超高齢者にまでAHNが行われ、それが本人にとって苦痛のある最期につながり、社会問題化した。米国ではPEG(ペグと読む)という術式を用いて胃ろうを造設して行う栄養法が汎用され始めた1980年代から、日本では2000年代に入ってから、次第に深刻な社会問題となった。
しかし、AHNが問題化した症例を見ても、医師を含め多くの人々の情緒は次のように反応した。
AHNが容易に手に入る時代に、AHNを行わずに看取ることは倫理的に許されるのか?
筆者が2004年に医師に対して実施したインタビュー調査では、多くの医師が次のように語った。
「水分と栄養を補給しないことはね、アフリカの子どもを餓死させるのと同じだから、絶対できませんよ、人間として。人工栄養は、基本的にはやめられないです。僕の考えでは、それは虐待だと思う。経管栄養をしないとか、それはある意味、死に直結することですよね。」(40代男性、脳外科医)
「とにかく餓死は、ウチでは餓死させろと言われても病院ですから、そういうことはできません」(50代男性、療養型病院院長)
ちなみに、このインタビュー調査において、筆者の側から「餓死」という言葉を用いたことはない。筆者はこの言葉を使用しないよう慎重にインタビューをすすめ、具体的な臨床像を示し、その患者においてAHNを差し控えることをどう捉えるかを問うた。そうしたら、多くの医師が自ら「餓死」という言葉を使い、「許されない」、「非倫理的」と述べたのである。
このインタビュー調査の詳細は、『延命医療と臨床現場――人工呼吸器と胃ろうの医療倫理学』(東京大学出版会、2011)にて報告し、次の段階として、この調査結果をもとに量的調査を実施した。
2)量的調査が示す医師の意識変化
前述のインタビュー調査は、先行研究が不在な領域においてブラックボックスを開け、変数を明らかにするための調査でもあった。そのようにして明らかになった変数によって仮説を組み、実施した縦断調査の結果、この問題に関する医師の意識が5年のインターバルで大きく変化したことが示された。その一部を以下に記す。
1回目の調査は2007年に、2回目は2012年に実施した。対象は療養病床勤務で高齢者を日常的に診ている医師720名。老衰の最終段階かつアルツハイマー型認知症末期で摂食しなくなった85歳の仮想症例を示し、いずれのAHNの方法を選択するか、あるいはいずれも選択しないかについて質問した。
その結果、2007年の調査(有効回答数277票)では、「胃ろう栄養法を導入する」ことが適切と回答した医師は33%、「末梢点滴を継続しつつ自然の経過に委ねる」も33%、「経鼻胃管栄養法を施行する」は31%、「すべてのAHNを差し控えて自然の経過へ委ねるのが適切」を選択したのは2%だった。
また、この症例について、「AHNを差し控えることは患者を餓死させることと同じであると思いますか」と質問したところ、「そう思う」という回答は47%、「そう思わない」は23%だった。
しかし、同じ母集団の医師を対象に同一の質問紙調査を2012年に実施(有効回答数273票)したところ、同一の仮想症例について、「末梢点滴を継続しつつ自然の経過に委ねる」を選択した医師は59%とほぼ倍増した。一方、「胃ろう栄養法を導入すること」が適切と回答した医師は11%と3分の1に減少し、「経鼻胃管栄養法を施行する」を選択した医師は15%と半減以下になった。また、「すべてのAHNを差し控えて自然の経過へ委ねるのが適切である」を選択した医師は10%になった。
そして、AHNの差し控えはAさんを餓死させることと同じであると思うと回答した医師は28%に大きく減少し、そう思わないと回答した医師は43%とほぼ倍増した。
これらの変化が起こった背景には、2012年に発表された、日本老年医学会ガイドラインの影響があると思われる。同ガイドラインについては後述する。
医師の認識は患者・家族の選択肢の幅に直結する。それは、医師が選択肢として認識していることのみが患者・家族に選択肢として提示されるからである。つまり、こうした医師側の意識変化は患者側に直接的かつ重大な影響を及ぼすのである。
医師がAHNを施行せずに看取ることを「餓死させること」と認識している限り、医師に「AHNを行わずに看取る」という選択肢はそもそも存在しないので、患者・家族側にもこの選択肢は提示されない。これは患者・家族側にとって、どのような意味をもつのだろうか。
3)AHNを行わないことは緩和ケア
アルツハイマー型認知症に関して日本よりも長い年月にわたって研究を進めてきた欧米諸国の医学会やアルツハイマー協会は、アルツハイマー型認知症では末期になるまで摂食可能なことが多いが、可能な限りの食事介助を工夫してもいよいよ食べることができなくなったら、それは本人の生命が生物学的に終焉の段階にあることを意味しているので、その後に胃ろう栄養法や経鼻胃管栄養法を行うと本人の身体にはかえって負担になるとしている。これは現代、胃ろうや経鼻胃管栄養法の適応に関する標準的な判断と考えられており、2000年頃から諸外国で相次いで発表されたガイドラインに記載されている。
この段階で摂食困難となった場合に胃ろう栄養法も経鼻胃管栄養法も行わないとなると、AHNに関してはどのようにすればよいのだろうか。
米国老年医学会は「適切な口腔ケアを行い、小さな氷のかけらを与えて水分補給する程度が望ましい。氷に味をつけるのもよい。死を間近にした患者は空腹やのどの渇きを覚えない」とし、オーストラリア政府は「高齢者介護施設における緩和医療ガイドライン」において、「アルツハイマー型認知症末期で摂食嚥下困難になった患者に対する最も適切なアプローチは、死へのプロセスを苦痛のないものにすることである。胃ろうや経鼻チューブによる経管栄養法も輸液も実施しないほうが最期の段階の苦痛が少なくて済む。死が迫った高齢者に胃ろう造設すべきでない」としている。
医学・生理学的にいえば、老衰やアルツハイマー型認知症末期にはAHNを行わずに看取るのが本人にとって最も苦痛の少ない最期につながる。その理由として、余分な輸液を行わないことによる気道内分泌物の減少と吸引回数の減少、気道閉塞リスクの低下や、肺と心臓への負担の低下、脳内麻薬と呼ばれるβエンドルフィンやケトン体の増加による鎮痛鎮静作用が挙げられる。つまり、AHNを行わないことは「餓死させること」ではなく緩和ケアであり、自然に委ねることで安らかな最期を実現することができるのである。
そのようなわけで、緩和ケアの観点からいえばAHNを行わないことが最も適切な選択肢となる。そして高齢者医療において最も重要なのは緩和ケアなのである。
もっとも、すべての症例において個々に検討することは重要なことであり、アルツハイマー型認知症末期と診断されていても、胃ろう栄養法等によって生存期間が延長される場合はゼロではないので、肺炎の罹患歴と本人・家族の希望などによっては、胃ろう栄養法を検討の対象とすることはありえるだろう。しかしその場合でも、医師はアルツハイマー型認知症末期患者に対し、胃ろう栄養法等の経管栄養法を積極的に勧めるべきではないといえる。
この領域で著名な石飛幸三医師や中村仁一医師が述べるように、「食べないから死ぬのではない。死ぬから食べないのだ」。
4)点滴信仰
上記の仮想症例に対するAHNとして、2012年の調査では末梢点滴を選んだ医師が多かった。筆者らが日本老年医学会の医師会員を対象に実施した同様の調査において、この仮想症例とほぼ同じ臨床像の患者に対して末梢点滴を選択した医師443名に対し、その理由を問うたところ、複数回答で、「すべてのAHNを差し控える場合に比べて家族の心理的負担が軽くなるから」が69%、「すべてのAHNを差し控える場合に比べて医療スタッフの心理的負担が軽くなるから」が57%であった。末梢点滴は医療行為であり、医療行為は医学的なニーズに応じて行われるべきものだが、この設問で「患者にとって医学的に必要だから」を選択した医師は38%だった。
つまり、この場合の末梢点滴は医学的なニーズではなく、家族や医療スタッフの心の負担軽減のために行われていることが示されたのである 。
何もせずに看取ると看取る側の心が痛むので、点滴ボトルの下がった風景をつくり、家族と医療スタッフの情緒をケアしているつもりになっているのである。
しかし、ここでケアされている周囲の人たちの情緒とは何なのか。そもそも誤解に基づいた認識なのではないだろうか。
人生の最終段階にある本人に繰り返し針を刺しながら、本人のためではない医療を周囲の情緒のために行っていることの意味を再考すべきである。日本では7割以上の人が病院で最期を迎えているが、その際に病院で広く行われている末梢点滴の多くが見直しの対象となると言えるだろう。
5)AHNの差し控えや終了も適切な選択肢
AHNを行わないという意思決定は、エンドオブライフ・ケアに関わる判断のなかでも特に難しいといわれている。それは、AHNは食事の代替であり、その提供はケアの象徴と認識されることが多いからである。上述の調査のように、その差し控えや終了は「餓死させること」に相当する非倫理的なことと認識している医療・介護関係者は少なくない。
医療者がこのような認識を有しているとき、家族に対し、AHNを差し控えて看取ることは選択肢として提示されず、胃ろう造設等が行われる。何らかの医療行為が行われるとき、その効果よりも医療行為を実施したという事実に重きが置かれることも少なくない。自然な経過の先にある死を受け入れることに対する心の抵抗が、医療行為の継続を呼び、患者の不利益に帰することが少なくないのが現代医療の特徴の1つである。
これらの課題への応答として、日本老年医学会は2012年、「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン――人工的水分・栄養補給法の導入を中心として」を発表した。このガイドラインにおいて、AHNも含め、本人の益にならない医療行為を差し控えたり、一旦開始したあとでもその医療行為を終了して看取ることは臨床上の適切な選択肢とされた。
また、同ガイドラインはAHN導入をめぐる意思決定に関して、「本人の人生をより豊かにする、少なくともより悪くしないことを目指す」、「AHNの導入・差し替え・導入後の減量・終了について、本人の人生にとっての益と害の観点で評価する」、「本人/家族らとスタッフが本人の最善をめぐってよりよいコミュニケーションを取り、納得できる合意形成/共同意思決定を目指す」ことを推奨している。
フレイル――老化の科学を臨床に活かす
1)高齢者医療における新たな視点
今世紀にはいってから、老化の科学の新展開にも注目が集まっている。今後、高齢者医療において、医学的および倫理的に過剰医療と過少医療を回避し、適切な医療を提供するためにきわめて重要な知見になると考えられている。具体的に検討するために下記に症例を挙げる。
A氏は82歳男性。軽度の認知症と軽度のうっ血性心不全および腎機能低下がみられた。妻と二人暮らし。杖を使用し一人で歩行可能で、日常生活動作(ADL)は自立。この1年間、転倒したことはなかった。歩くと多少の息切れはあるが、外出が好きだった。二人で子や孫に会いに行くのが一番の楽しみという日常を送っていた。
ある日、定期検査で胸部X線検査を受けたところ影が認められたので、精査を受けた。その結果、初期の肺がんと診断された。医師は標準治療は手術であり、治癒の可能性もある段階だとA氏と妻に説明した。A氏は「治せるのなら治そう」と思い、妻も賛成したので、手術を受けることとした。
手術そのものは成功し、肺がんは切除された。しかし、術後にせん妄と認知症の周辺症状が出現し、軽快しなかった。そのため自宅退院できず、療養病院に転院することとなった。認知症は急速に進行し、歩行もおぼつかなくなった。
これは世界的に著名な医療倫理の学術誌であるJournal of Medical Ethicsに掲載された英国の症例である。この症例ではA氏の肺がんは確かに切除された。しかし、A氏の生活の質(QOL:quality of life)は大きく低下してしまった。手術は成功したが、治療としては失敗してしまった。
この症例のように、高齢患者において、ある疾患を治療することが思わぬ結果に至ることは少なくない。若年や壮年の患者とは異なるこうした問題が起こるのはなぜなのだろうか。
2)フレイルとは何か
こうした問題が起こるのは患者がフレイルである場合がほとんどであるといわれている。
日本老年医学会の定義によると、フレイルは「高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態」である。
フレイルはfrailtyの日本における用語として日本老年医学会が2014年に採用した。frailtyは英語圏で形成された概念であり、今世紀に入ってから次第に知られるようになった。現在、老年学研究者が最も注目している概念であり、世界各地で盛んに研究が進められている。
この学会定義のなかの「ストレス」は心理的なストレスだけでなく、本人にストレスを与えるもの、つまりストレッサー(stressor)を指している。そして留意すべきは、医療やケアの行為もストレッサーになる場合があるということである。特に医療行為のなかで侵襲性が高く本人にとって負担の重いものは重大なストレッサーになる恐れがあるので注意を要する。
フレイルは、従来、年齢で判断されがちであった老年に特徴的な諸問題に関して、年齢とは独立した予測因子となることが次第に明らかにされ、注目されている。
2013年に発表された国際フレイル・コンセンサス会議の報告によると、フレイルは時間の経過に伴い悪化するが、初期の段階であれば改善もありうる動的な状態である。フレイルは今後のあらゆる高齢者医療分野にとって重要な概念になると考えられている。
3)エンドオブライフにおけるフレイルの有用性
フレイルの臨床上の有用性は大別すると2つあり、その1つは介護予防である。前述の国際コンセンサス会議でも、QOLの向上と介護サービスの社会的コスト削減のために、まだフレイルになっていない高齢者がフレイルになることを遅らせることの重要性が強調された。日本でも政府の健康寿命延伸政策のもと、多数の高齢者ケア関係者が地域住民に対しフレイルについて教育・啓発活動を展開し、介護予防を促進している。
しかし、もう1つのフレイルの臨床上の有用性については、日本では依然として研究が稀少である。それは、すでにフレイルが進行した高齢者への医療行為に関することである。
フレイルな高齢者はストレッサーに脆弱な状態である。そのため、侵襲性の高い医療行為は益ではなく害を及ぼすことが多くなる。この点では特に、放射線療法、化学療法、手術、透析療法、循環器関連の処置に注意が必要といわれている。
そして上術の国際会議は、本人のフレイルの程度を判断する尺度として「臨床フレイル・スケール」という9段階のスケールを紹介している。
世界の研究においては、フレイルになった高齢者に対しては、治癒を目指して侵襲性の高い治療を行うことよりも、苦痛の緩和とQOLの最適化を中核とした緩和ケアを行うべきとされている。
また、エンドオブライフ・ケアにおけるフレイルの知見の有用性についても言及されており、英国で国民皆保険制度を運営するナショナル・ヘルス・サービスは、「フレイルが進行した高齢者に対しては、今後の展開を予測しつつケア・プランを立てていくことと、エンドオブライフ・ケアを検討することが適切」としている。
フレイルが進行したら、人生の最終段階をも見据えたケア・プランを立てることが重要なのである。つまり、アドバンス・ケア・プランニング(ACP: advance care planning)の実施が必要ということである。ACPについては後述する。
4)重度フレイル高齢者に対する医療行為の問題
①心肺蘇生法
フレイルを組み込んだケア・プランとして、まず「重度のフレイル」と「非常に重度のフレイル」の場合の心肺蘇生法(CPR:cardiopulmonary resuscitation)の問題を考えてみたい。
CPRは①口対口人工呼吸、②AEDによる電気ショック、③胸骨圧迫の3点で構成されている。胸骨圧迫では両手を患者の胸に重ね、胸が5cm沈むくらい強度な圧迫を1分間に120回繰り返し、心拍の再開を目指す。胸骨圧迫の合言葉は、「強く、速く、絶え間なく」である。
日本ではフレイルが重度に進行した高齢者が自宅や介護施設等において心肺停止(CPA:cardiopulmonary arrest)状態で発見された場合に、救急搬送されることがしばしばみられる。
通常、CPAの患者にはCPRが行われる。しかし、CPRの中核である胸骨圧迫を重度フレイルの高齢者に行うと何が起こるか。多くの場合、胸骨も肋骨も折れ、出血もする。こうしてCPRを行い、その結果、患者は蘇生するのだろうか? 重度フレイルの高齢者が目撃のないCPAで発見された場合、CPRを行っても蘇生する人は限りなくゼロに近いことが報告されている。
「目撃」の有無とは、心肺停止したときにそれを誰かが見ていたか否かを意味する。「目撃がある」心肺停止であればすぐに救急車が呼ばれるだろうし、救急車の到着までの間、そばにいる人が胸骨圧迫する場合もあるだろう。つまり、蘇生可能性が高くなる。
しかし、「目撃がない」心肺停止の場合は、誰かが気づいたときにはすでに心肺停止状態だったということであり、それから救急車が呼ばれても到着までには時間が経過している。
このような対象へのCPRは救急医と救急隊員らに不全感をもたらしていることが近年の日本救急医学会学術集会等で多数報告されている。そこで、こうした状況への対応のため、総務省消防庁の検討部会は2019年11月、末期がんや老衰の最終段階にある高齢者が自宅等でCPAとなった場合には、連絡を受けたかかりつけ医がCPRを行わない判断や一旦開始したCPRを終了して看取る判断をすることが可能とする報告を発表した。CPRに関して国として考え方が示されたのはこれが最初である。
今後は、高齢者介護施設等や在宅医療の場では、重度フレイルの高齢者がCPAで発見された場合には、誰よりも本人のために救急搬送しないような話し合いを含めた準備が必要といえる。具体的には、医療・ケア従事者側が本人・家族側と相談し、DNAR(do not attempt resuscitation)に関する話し合いを含めたACPを進めることが大切であり、総務省消防庁の報告書にもその点が盛り込まれている。
②透析療法
透析療法が循環動態に負荷を与える治療行為であることは広く知られており、透析療法の導入によってADLが低下したり死亡率が上昇したりすることを示す研究は、この10年間、諸外国で数多く報告されている。「導入」とは「開始」を意味する。
例えば、米国で行われた研究では、ナーシング・ホームに入所していた要介護で高齢の末期腎不全患者3,702例に関して、透析療法の導入前後のADLを比較した。その結果、多くの患者で透析導入後の3ヶ月間でADLが著明に低下し、透析導入後6ヶ月でADLを維持していたのは30%、透析導入後12ヶ月でADLを維持していたのは13%のみで58%が死亡していた。これは2009年にNew England Journal of Medicineという世界のトップジャーナルで発表された。ナーシング・ホームは高齢者介護施設である。
慢性腎臓病とフレイルに関する総説論文によると、2013年3月までに国際的な学術誌に掲載された慢性腎臓病患者におけるフレイルを検討した論文は7篇あり、フレイルな慢性腎臓病患者はフレイルではない慢性腎臓病患者に比べて、原因を問わず死亡リスクが増大することが示された。つまり、透析療法も死亡リスクを増大させることが示唆されたのである。
最近では2018年にオランダの病院から報告された研究で、透析導入患者と非導入患者を比較すると、80歳未満では透析導入により生存率が上がるものの80歳以上では有意差がないこと、また、重度の合併症を有する患者群では70歳代でも生存率の有意な改善を認めないことが報告された。
日本における高齢者への透析療法の現状はどのようなものだろうか。
日本透析医学会がまとめている「わが国の慢性透析療法の現況」(2017年12月31日現在)によると、2017年に透析療法を導入した患者数は38,786名で、導入の年齢層で最も多かったのは女性では80歳以上85歳未満で、男性では75歳以上80歳未満であった。80歳以上で導入したのは女性では32.4%、男性では23.1%、85歳以上で導入したのは女性で14.8%、男性で9.4%であった。
要点は、これらの高齢者がフレイルでない場合は、暦年齢が高くても透析療法が本人に益をもたらす可能性は高いが、重度フレイルあるいは非常に重度のフレイルである場合は、透析療法によってかえってQOLが損なわれたり死亡したりする恐れが高いということである。
この点に関する国内の研究報告はまだ限定的だが、そのなかで、谷澤雅彦らの報告は注目に値する。谷澤らは日本透析医学会のデータを解析し、「80歳以上で日常生活障害度が高度の場合、37%が透析導入後の3ヶ月以内に死亡している」と報告し、「日常生活障害度が透析療法導入後の超早期死亡を予測する独立した危険因子である。透析非導入が極端に少ない本邦において、導入後の早期死亡が予想される超高齢者においては、保存的加療を選択することも考慮すべきである」と述べている。保存的加療とは透析療法以外の方法を用いるということであり、生活管理や食事内容の工夫と薬物療法によって、腎臓の機能をできるだけ長く保つようにすることを指す。
これらの報告で谷澤らが指摘している日常生活障害度の高さは、フレイルの程度を示している場合が多いと考えられ、重度フレイルおよび非常に重度のフレイルの場合は、透析療法を行うと早期死亡に至ることが少なくないことが示唆されているといえるだろう。
日本では透析療法のほとんどが公費で負担されている。この制度のもとで透析導入率は極めて高く、2017年現在で透析療法を受けている患者数は全国で33万人以上を数えている。これらの透析患者のうち、重度フレイルまたは非常に重度のフレイルの患者はどの程度なのだろうか。
5)年齢ではなくフレイルの程度で判断
フレイルには個人差が大きい。まだフレイルになっていない高齢者の場合は、年齢が高くても壮年者と同様の治療を行うことが適切といえる。この点には注意が必要である。それは従来、医療現場では、「まだ70歳だから積極的な治療をする」とか「もう90歳だから治療は控える」などと、年齢によって判断されることがしばしばみられたからである。
しかし、フレイルの科学が進展した現代では、このような判断は高齢者差別のそしりを免れない。侵襲性の高い治療行為の医学的な適否の判断は、年齢ではなくフレイルの程度によって行われるべきといえる。
アドバンス・ケア・プランニングの実施へ
人工的水分・栄養補給法やCPRや透析療法を含め、人生の最終段階における医療とケアについて、本人を中心に家族や医療・ケア従事者が予め話し合っておくことが必要である。そこでACP の重要性が叫ばれており、日本でも2018年に厚生労働省がACPの推進を開始した。
ACPはリビング・ウィルなどの事前指示(advance directives)の不足を補いつつ英語圏で発展してきたもので、そもそも輸入概念なので、日本におけるACPの実施には日本社会にあわせた配慮が必要である。
そこで、日本老年医学会は2019年6月、「ACP推進に関する提言」を発表し、国内の医療・ケア従事者に向けてACPの概念と要点を説明し、適切な実践を呼びかけた。
同提言では、ACPを「将来の医療・ケアについて、本人を人として尊重した意思決定の実現を支援するプロセスである」と定義し、ACPの目標を「本人の意向に沿った、本人らしい人生の最終段階における医療・ケアを実現し、本人が最期まで尊厳をもって人生をまっとうすることができるよう支援すること」としている。
そのために、「本人と家族等と医療・ケアチームは対話を通し、本人の価値観・意向・人生の目標などを共有し、理解した上で、意思決定のために協働することが求められる。ACPの実践によって、本人が人生の最終段階に至り意思決定が困難となった場合も、本人の意思をくみ取り、本人が望む医療・ケアを受けることができるようにする」ことが大切としている。
同提言の全文とACPの実践を具体的に示す事例集が日本老年医学会のホームページに掲載されているので、参考にして頂きたい(https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/proposal/acp.html)。
今後の高齢者医療に関しては、ACPのプロセスにフレイルの評価を組み込むことが重要である。それによって、医学的および倫理的に適切に医療とケアを提供することが可能となると考える。
おわりに――コミュニケーションの重要性
医療とケアに関する意思決定プロセスを倫理的に適切に進める際に必須なのは、医学的に適切な判断である。医学的な判断が不適切では、医療とケアに関するいかなる判断も倫理的に適切とはならない。その点でフレイルを含めた新知見は重要である。
厚生労働省の2018年の人口動態統計によると、日本人の死因は、がん、心疾患に次いで老衰が第3位となった。老衰と関連の深い肺炎による死亡も増加しており、死因の第5位となった。肺炎で死亡した人の97%が高齢者であった。
これらが示すことは、世界屈指の超高齢社会である日本において、致死的疾患ではなく身体の老化によって最期を迎えている高齢者が増加しているということである。逆に言えば、日本は多くの人がその状態まで生存することが可能な社会となったということである。
こうした日本社会において高齢者を人として尊重するために、まずフレイルの程度に合った適切な医療とケアを行うことを基本とし、さらに各人の人生の物語り(narrative)に沿った意思決定を支援することが求められている。つまり、医学的な意味を本人にとっての最善の実現という観点で捉えなおすということである。
そして、本人の価値観・死生観を反映した人生の物語りを尊重する臨床上の意思決定に至ろうとするときに肝心なのは、丁寧なコミュニケーションのプロセスである。本人側と医療側は相互に価値観・死生観を知り、本人が意思疎通困難な状態となった後も、医療側は本人の物語りを形成する上で重要な関わりをもつ人々とコミュニケーションを繰り返していくことが、本人にとっての最善を探索する道筋となるだろう。
臨床上の選択肢が増え、一人ひとりの価値観が多様化している現代、本人側と医療者側のコミュニケーションの重要性はますます高まっている。バランスのとれた意思決定に到達するためにコミュニケーションは必須であり、医療ケア従事者にはコミュニケーション・スキルの向上を望みたい。
エンドオブライフ・ケアの意思決定について話をするということは、多くの日本人にとって依然としてハードルが高い。しかし、人生の最終章を幸せなものにするために、最終段階の医療とケアのあり方について、まず本人と家族が話し合い、そして医療者側とも話し合いを繰り返すこと、それが標準的に行われる社会の実現を目指すことが重要であると考える。
プロフィール

会田薫子
東京大学大学院医学系研究科健康科学専攻博士課程修了、博士(保健学)。ハーバード大学メディカル・スクール医療倫理プログラム フェロー(フルブライト留学)、東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター上廣講座特任准教授を経て、現在、同講座特任教授。専門は、臨床倫理学、臨床死生学、医療社会学。研究分野は、 エンドオブライフ・ケア、延命医療、高齢者医療とケア、脳死、臓器移植など。
おもに人生の最終段階の医療とケア(エンドオブライフ・ケア)の分野において、調査・研究と実践活動を重ねてきました。長寿の時代に、一人ひとりの高齢者が自分らしく生きて、生き終わることを支援するための意思決定のあり方を、臨床現場の医療・ケア従事者とともに考えつつ、それを実現するための社会環境整備、看取り文化の再構築に取り組んでいます。
主要著書に、『長寿時代の医療・ケア ― エンドオブライフの論理と倫理』ちくま新書(2019)、
『延命医療と臨床現場:人工呼吸器と胃ろうの医療倫理学』東京大学出版会(2011)(2012年度日本医学哲学・倫理学会賞受賞、2012年度三井住友海上福祉財団賞受賞)、『医療・介護のための死生学入門』東京大学出版会(共編著、2017)、『医と人間』岩波書店(共著、2015)、『老い方上手』WAVE出版(共著、2014)、『高齢者ケアと人工透析を考える:本人・家族のための意思決定プロセスノート』医学と看護社(編、2015)、『高齢者ケアと人工栄養を考える:本人・家族のための意思決定プロセスノート』医学と看護社(共著、2013)、『シリーズ生命倫理学3 脳死・臓器移植』丸善出版(共著、2012)、『シリーズ生命倫理学4 終末期医療』丸善出版(共著、2012)、『シリーズ死生学5 医と法をめぐる生死の境界』東京大学出版会(共著、2008)など。