2015.12.15
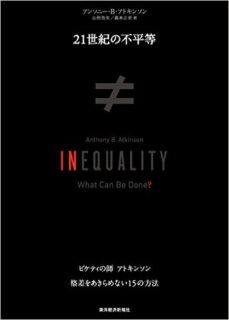
『21世紀の不平等』――グローバル化のせいで何もできないか?
昨年話題になった『21世紀の資本』の著者ピケティの師匠にあたり、「不平等研究の父」とも言われるアトキンソン。「ピケティ旋風」から1年経った今、ピケティが問題提起した格差拡大の研究を継承・発展させたのが『21世紀の不平等』である。ピケティいわく、「平等な社会に向けた現実的ビジョン」とされる本書から、「グローバル化のせいで何もできないか?」の一部を転載する。
本書で私はOECD諸国での不平等を減らすための提案をしている。すぐに思いつく反応は、「そいつは結構だが、いまいる世界ではそういう道筋を追い求めるわけにはいかないんだよ」というものだ。つまり、過去にはそういう野心もあったかもしれないが、今日では所得をもっと公平に分配するなどというのは、グローバル化した経済のなかで実現不可能な贅沢品となっているというわけだ。
どんな国でも、不平等低下を目指そうとすれば世界市場のなかでの競争力を失ってしまう。国内のパイが減らなくても、外部からの制約があるというのがその見方だ。この見方からすると、社会保障制度や累進課税、補助金政策の考え方や完全雇用目標はすべて歴史の遺物でしかない。21世紀にはそんなものが出る幕はないということになる。
実は、提案に対するこの反論には二つのバージョンがあって、相互に関連しているがこの両者は別物だ。一つはOECD諸国全体、あるいはもっと狭く欧州連合(EU)が全体として、新興工業国からの競争に直面したときに、概ね似たような政策を実施できるだろうか、という問題だ。もう一つは他のOECD諸国が現状のままの政策を何も変えずに進めているなかで、個別の国が再分配や社会支出増大の手段を単独で採用できるかどうかという懸念となる。
これは重要な懸念だし、私としても真面目に考えたい。この反論を無視するのは、確かに愚かなことだ。というのもこの世界がどう発展するのか、ほとんど何もわかっていないからだ。本書を10年前に書いていたなら、世界経済の見通しは2015年時点とはまるで違っていただろう。世界経済に影響しかねない大きな力のなかには─特に気候変動と、中国やロシアとの政治関係─私には評価しかねるものもある。
むしろ私としては、経済の見通しについて完全に悲観的ではない理由を三つ挙げよう。一つは、提案した各種手法の主な要素の一つ─社会保障制度─が19世紀におけるグローバル化の時期に起源を持つということだ。だから現在のグローバル化が正反対の反応を引き起こすというのは不思議なことだ─不平等の増大への対応として、ここで主張したように社会保障制度を強化するどころか、それを解体しなければならないと思ってしまうとは。今日のグローバル化の形は違っているかもしれないが、職や賃金への影響は似たようなものだ。
楽観論の第二の理由は、各国は世界の発展に直面したときに単なる受け身の主体ではないということだ。本書の中心的な主題は、今日の高い不平等を、どうしようもない力の産物として見るのは間違っている、ということだ。同じことがグローバル化についても言える。第三の理由は、私が国際協力の可能性について少しばかり楽観的だということだ。
歴史的に見た社会保障制度
グローバル化は目新しいことではない。ウィキペディアの記述を見ると「19世紀には現在の形に近いグローバル化の進展が見られた。工業化のおかげで家庭用品が、規模の経済により安く生産できるようにしてくれたし、急速な人口増は商品財に対する持続的な需要を作り出した」と教えてくれる。強調したいのは、同じ時期に今日のグローバル化で生存が脅かされているとされる重要な制度─ヨーロッパの社会保障制度─が台頭してきたということだ。
産業革命に伴い、現代的な雇用関係が発達してきたために社会保護の主要な制度を作り出す圧力が生じた。工業雇用のため、多くの労働者は失業、病気、退職が収入の完全喪失を意味するような状況に直面することとなった。これは19世紀終わりから20世紀初頭にかけて、失業保険や工業傷害給付、疾病保険、高齢年金の設立につながった。工業雇用に関わる労働者たちは、工業事故などの個人的な不運や全体的な景気下降のせいでいきなり食い扶持を失いかねなかったが、こうした新しい仕組みは労働者たちのためにそうしたリスクに保険をかけた。
この面で世界を主導したドイツでは、社会保険のビスマルク的な制度を導入する動機がいくつかあった。たとえば労働者組織台頭と社会主義的な考え方の広まりのなか、政治社会的な安定性を保つ必要なども挙げられる。でも大きな要因は、ヨーロッパが1840〜1914年の時期にグローバル化で大きな競争にさらされたことで、雇用が不安定となり、社会的な保護が必要となったということだった。
この初期の第一次世界大戦前のグローバル化時代にこそ現代の社会保障制度の起源があるという点は強調しておくべきだ。というのも、社会保障制度は両大戦のあいだの期間に生じたという説がときどき出てくるからだ。確かにアメリカで高齢生存者保険が始まったのは、第32代大統領フランクリン・ルーズベルトの下の1930年代であって、26代大統領セオドア・ルーズベルト(1901─1909)の下ではなかった。
確かに、ヨーロッパ各国の社会保障プログラムに対する支出が拡大したのは両大戦にはさまれた時期だった。でも多くの制度は、1914年以前に導入されている(表10─1)。あるアメリカの評論家が述べているように、「ヨーロッパでは社会保険に向けての複雑な法制度体系が急速に発達した(中略)ノルウェーの凍りついた岸辺から、イタリアの晴れ渡る風土まで、東の最果てからスペインまで、ヨーロッパ全土で、ゲルマン、サクソン、ラテン、スラブ、どこでも同じ道を進んでいる(中略)社会保険に向けた動きは、現代における最も重要な世界の動きなのだ」。これが書かれたのは1913年のことだ。
このタイミングを強調するのは、ヨーロッパでの社会保障制度プログラム導入が経済目標の実現と競合するものとは見なされず、むしろそれを補うものと考えられていたからだ。ヨーロッパ社会保障制度の初期には、社会政策と経済政策が同じ方向を向いていると思われていた。この見方は数十年にわたり続いた。イギリスで1942年にベヴァリッジが戦後社会保障の計画を書き上げたとき、ケインズと協力してマクロ経済政策と社会政策が確実にかみ合うようにした。特に社会移転が自動スタビライザーを提供することで両者が関連するようにしている。アメリカでは、モーゼス・アブラモヴィッツは「最低所得、ヘルスケア、社会保険など社会保障制度の各種要素の支持は(中略)生産性成長プロセスそのものの一部だった」と論じている。
支配的な見方が変化し、社会保護が経済パフォーマンスを補うものではなく邪魔するものだと思われるようになったのは、ずっと後の1980年代や1990年代になってからのことだった。失業給付が失業を引き起こしていると思われ、国の賦課方式(ペイゴー方式)年金は貯蓄率を引き下げ、成長率の足を引っ張っているとされた。アメリカのノーベル賞経済学者ジェームズ・ブキャナンが1998年に書いていたことだが「多くのヨーロッパ人たちが、他の地域に見られる少し限られた社会保障制度に比べて優位にあると思っている『社会モデル』は、21世紀では経済的に成り立つものではない」というわけだ。
この見方は国際機関からも述べられた。当時IMFの長官だったミシェル・カムドシュはこう述べている。「ヨーロッパの経済通貨連合の未来にとって、加盟国が十分な柔軟性を持ち、もはや現代世界にはふさわしくない、きわめて高コストの失業給付や社会保障レジームが財政に与えるインパクトを軽減させることが極度に重要であると我々は見ている」。
21世紀の社会保障制度
21世紀のグローバル経済では社会保障制度はまかなえないというのは本当なのだろうか? 社会保障制度がまかなえないという立場の核心にあるのは、グローバル化が社会保障制度の徴税能力を減らしたという主張だ。
この見方について、国民所得のうち税収として集められる部分には限界がある。アメリカの経済学者アーサー・ラッファーが一般に広めたように、総税収と総税率とを関連づける曲線があり、これは最初は上がるが、どこかで頂点に達してその後は下がる。この曲線を、ラッファーはワシントンのレストランのナプキンに描いて、ニクソン大統領の側近だったディック・チェイニーとドナルド・ラムズフェルドに示したという。この二人は後にそれぞれ副大統領と国防長官になった。
ラッファー自身も認めていたように、この「ラッファー曲線」は目新しい発想ではないが、今日でも広く引用されている。重要な点は、グローバル化と技術変化があわさってこの曲線を引き下げているので、どの税率でも政府が集められる税収は減ったということだ。
曲線の頂点は左にシフトした。なぜかといえば、インターネット取引の拡大で間接税が集めにくくなったからだ。世界的な労働市場の発達で、労働所得の課税は限られてしまう。そして国同士の税競争により、法人税や投資所得課税からの税収は下がってしまう。各国がこれまでは歳入最大化税率に近いところにいたとしても、いまや歳出を切り詰めねばならない。そしてこれまではまだ税収を増やせる余地があると思っていたにしても、その余裕はいまや存在しないというわけだ。
陰気な話ばかりだ。でもこの議論のもとになっている想定を受け入れたとしても、分析はもっと複雑だし、結論はそんなに明白ではない。そもそも、この限界は総政府支出に対するものであり、歳出の各種区分をどう削減するかの相対的な便益を比べる必要がある。社会移転は大きな費目だが、総額だけ見てある個別区分を削減する理由にはならない。あらゆる政府部局で歳出を何十億削減することから生じる費用便益を比較するべきだ。国防、公共インフラ、研究開発、農業、教育など、すべて社会移転と比べる必要がある。
これほど明らかではないが重要な点としては、直接的な政府支出と、「税支出」という形で税システムから間接的に行われる支出(第7章参照)を比べねばならないということだ。税支出をなくせば税収は増えるから、同じくらいしっかり検討する必要がある。一部のOECD諸国では、税支出はかなりの額に上る。2004年から2007年の時期での推移を見ると、税支出はイギリスではGDPの8パーセント、アメリカとカナダでは6〜7パーセントだ(ドイツ、韓国、オランダではもっと少ない)。
税支出がいまの議論のなかで重要なのは、社会保障制度が削減または現状維持となった場合に何が起こるかを考える必要があるからだ。一つの答えは、民間による福祉提供が増えるというものだ。国が助けないなら、個人は民間セクターに頼る。これが現在起きていることは、OECDによる総社会支出の国際比較からもわかる。
これは民間によるものと公共によるものの合計を見ている。社会支出は現金や現物などの給付や補助金として、人々の福祉を悪化させるような状況において公共と民間の機関が提供するものと定義されている。ここには社会保障、健康保険給付、住宅給付、労働市場プログラムなどが含まれる。図10─1で2011年の数字を示したが、公的な給付の水準(色の薄いグラフ)はOECD諸国のなかでもかなりばらつきがある。
アメリカでは、ほとんどのヨーロッパ諸国に比べれば国民所得に占める支出の割合は小さい。チェコ共和国よりわずかに多いくらいだ。でも民間支出を加えて総支出(色の濃いグラフ)を出すと、アメリカは俄然高くなる。唯一アメリカより高いのはフランスだけだ。デンマークとの対照ぶりは示唆的だろう。デンマークの公共支出はアメリカより3ポイント高いが、総支出は3ポイント低い。これは、社会支出のニーズは何らかの形で満たされるのであり、公的支出をやめれば民間支出で置き換わるということを示唆している。
この知見の重要性は二つある。もし公共支出の減少を相殺するために社会ニーズに対する民間支出が増えねばならないなら、この費用は雇い主か家計が負担することになる。雇い主が高い費用に直面したら、雇い主への税金と同じ形で彼らの競争力は下がる。従業員の医療保険負担は、雇い主への課税と同じように立地判断を左右する。支払うのが従業員なら、必要な支出は手取り賃金を減らし、これは賃上げ要求につながるだろう。福祉負担が国から民間に移転しても、経済的な影響に変化が出るのは両者の効率性が違う場合だけだ。
第二に、年金やヘルスケアなどで民間社会支出が増えればしばしば税支出も伴い、税金側にも影響が出てくる。この限りにおいて、グローバル化した社会での各国の財政問題を解決するには、社会支出を公共から民間部門に移転するだけではダメだとわかる。
社会保障制度はグローバル経済で競争できるのか?
予算費用への影響はどうだろう? 税金が高いと財がもっと高価になって、グローバルに競争できなくなるのだろうか? 雇い主はしばしば、税金や雇用に伴う社会費用負担のおかげで自分たちの財やサービスの競争力が下がると愚痴る。でも同じ影響は、従業員に課税しても起きかねない。従業員の負担が増えれば雇用費用へとそれが転嫁されかねないからだ。
ちょっと特殊な例を挙げると、イギリスのプレミアリーグのサッカー選手たちが税引き後の手取りをこの水準にしろと強固に要求した場合、最高税率を引き上げたらその所属クラブは選手の給料を上げるしかなく、これはたぶん試合のチケット価格の引き上げや、放映料の引き上げに転嫁されたりするわけだ。するとこれは、サッカー見物にイギリスにやってくる観光客数を減らしかねず、またテレビの観客もプレミアリーグの試合からブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエAの試合に流れてしまう。
もちろん賃金費用を左右する要因は税金だけではない。同僚のジョン・ミュルバウアーは、住宅費用の重要性を強調している。住宅ローンの負担が大きければ高賃金を得ようと交渉する。人々をロンドン、オックスフォード、ケンブリッジなどの都市に惹きつけるには高い給料が必要だ。住宅価格を引き下げるための行動には、本書で提案した地方議会税改革も含まれるが、それをやれば賃金圧力も下がるかもしれない。公共サービスの提供も重要であり、よい学校や医療サービスの有無も同じ方向に作用する要因だ。
高い税金が賃金費用を引き上げるにしても、それはイギリスの競争力を引き下げるだろうか? 私は昔から「国の競争力」という表現に首を傾げてきた。ある企業に競争力がないというならわかる。大学に競争力がないとか、あるいは産業全体として競争力がないというのだってわかる。でも国となるとわからない。だから数年前にノーベル賞国際貿易理論家のポール・クルーグマンが「競争力というのは国の経済に適用したら無意味な言葉だ」と述べているのを見てホッとした。
彼はまた「ぼくの本棚にある国際経済学の教科書は、一つとして競争力という言葉が索引に出てこない」と述べている。単一の企業とは違い、国には対外的な不均衡に対する調整プロセスがある。輸出が減って輸入が増えれば─為替レートが貿易収支に対してどこまで調整するかにもよるが─為替レートは下がり、輸出業者が財やサービスを、輸出市場と見合いの価格で売れるようになる。同じく、為替レートが下がると輸入財が国内価格で高価になり、その価格を適正な水準にする。
この調整はうまくいかないかもしれないし、それなりに費用もある。うまくいかないのは、為替レートは短期や長期の資本移動など他の要因にも左右されるからだ。あるいはユーロ圏のように為替レートが固定されているから機能しない場合もある。後者の理由の場合、ある通貨圏にいる単一の国は、その通貨圏外の国には当てはまらない制約に直面しかねない。だからこそ、質問のなかでこの2種類を区別するのが重要だ。ユーロ圏の単一のメンバー国は、ユーロ圏全体には当てはまらない形で制約されている場合があるのだ。
でもどんな水準であろうと、為替レートによる調整には費用が伴う。下落はその国の生活水準を減らすということだ。1967年の切り下げで、1ポンドが2・8ドルだったのが2・4ドルになったというのは、100ドルのアメリカ製品に対してイギリス人が支払う価格が、36ポンドだったのが42ドルに上がったということだ(四捨五入した値)。
ハロルド・ウィルソン首相は国民に対し、ポケットのなかの1ポンドはいまでも1ポンドの価値を持つのだと演説したが、実はその前にもっと正確な主張をつけていた。「いまから外国ではポンドは他の通貨で見た場合に14パーセントくらい価値が下がる」。これこそが実は本当の核心なのだ。人々が「競争力をつける」というとき、それは実際には国民の生活水準を維持すると言いたいのだ。
ここでの文脈で言うと、それは福祉国家と再分配増大のための財源を見つけねばならないということだ。提案したプログラムの費用は、人口のなかの裕福な集団の実質所得引き下げによりまかなわれねばならない。その意味で、この問題は総リソース一定の国が国内で直面する問題と何ら違いはない。
前章で述べた通り、再分配では得をする人だけでなく損をする人もいる、というのは再分配に反対するまともな反論ではない。政府が本気で不平等を減らしたければ、どうしてもトレードオフは生じる。これは容易なことではない。トーニーが論説『平等論』で述べたように「不平等は流れに身を任せる以上のことを要求しないので簡単だが、平等は流れに逆らうことなのでむずかしい。(中略)それには代償と負担が伴うのだ」。
そのむずかしさは二つの形をとる。個人のレベルでは、それは「一部の人には物質的な犠牲」をもたらす。税金が引き上げられることを受け入れてもらわねばならない。社会のレベルでは、難しい問題に取り組まねばならないということだ。市場プロセスの結果をあっさり受け入れるのではなく、「公平な」分配というのはどういう意味かを検討しなくてはならないのだ。
まとめ
再分配手法の範囲、特に社会支出の増大を伴うものの範囲は、一部で言われるほどグローバル競争に制約されてはいないと論じてきた。制約はある。でもだからといって何もできないということではない。これは予算を全体として眺め、あらゆる給付などとあらゆる社会支出を、公共と民間の両方について検討するとなおさらはっきりする。確かに財政問題はあるが、それは私たちが解決できる力の範疇にある問題であり、外部の力だけで結果が決まるような問題ではないのだ。
プロフィール

アンソニー・アトキンソン
オックスフォード大学ナフィールドカレッジ元学長。現在、オッスクフォード大学フェロー。所得分配論および福祉国家論の研究で知られ、国際経済学会、欧州経済学会、計量経済学会、王立経済学会会長を歴任。所得分配論の大御所と言われる。ノーベル経済学賞候補としても知られ、ノーベル賞を予測する「トムソン・ロイター引用栄誉賞」を2012年に受賞している。


