2016.08.25

食足りて、○○を知る?――鯨油とパーム油の見えざる関係
捕鯨”で”考える
ここ3年間ほど日本各地を訪問し、捕鯨産業に従事してきた人びとの個人史の採録をつづけている。誰がどのように問題視しているのかは別にして、わたしが、いわゆる「捕鯨問題」に関心をよせる理由は、以下の3つである。
まず、なんといっても鯨肉が好きだからである。統計上、日本人は、ひとりあたり年間に鯨肉を33グラムしか食べていない。しかし、わたしは、少なくともその50倍は食べているはずだ。大分県の盆地で生まれ育ったわたしは、なにも幼少期からクジラを食べてきた「筋金入り」の鯨肉愛好家ではない。1967(昭和42)年生まれということもあり、給食で食べた記憶も定かではない。クジラを好んで食べるようになったのは、「食と環境」に関心をもつようになった、この15年ほどのことである。
たしかに、わたしもクジラをかわいいと思う。しかし、「クジラが、かわいそう」との動物権や動物福祉といった動物愛護思想には、正直なところ、理解できないところがある。「正義」のためには暴力もやむなしとする主張など、もってのほかである。
とはいえ、グローバル社会においては、ことなる価値観をもつ人びととの意見にも耳を傾け、たがいの妥協点を見いだしていかねばならないことも自覚している(つもりだ)。このように、「捕鯨問題」は、現代社会における異文化理解の格好の題材でもあるし、今後、世界の食糧事情が逼迫することが予想されるなか、「食」の安全保障と水産資源の持続的利用に直結する課題でもある。これが、わたしがクジラに関心を寄せる第2の理由である。
むろん、捕鯨については生態学から江戸時代の捕鯨に関する歴史研究、現代の国際関係学にいたるまで、膨大な蓄積がある。そのようななか、わたしは、「日本の近代化における捕鯨の役割」について考えてみたいと思っている。
捕鯨は、北洋におけるサケ・マス漁、カニ漁や南洋におけるカツオ・マグロ漁同様に、日本の水産業の近代化を語るうえで無視できない産業である。北洋にしろ、南洋にしろ、南氷洋にしろ、それらはいわゆる手つかずの「フロンティア」漁場だったわけであり、そこに経済的要因と軍事的動機がかさなり、国策的に資本が投入され、大型漁船による進出が可能となった。その過程と結果を、「日本の近代化とわたしたちの生活変容」という視点から批判的に考察してみたいというのが、第3の理由である。
とはいえ、どこから手をつければよいのか・・・・・・その手はじめとして、捕鯨関係者へのインタビューに着手したというわけである(そのうち6名、およそ30時間にわたったインタビュー記録をちかく公刊予定)[赤嶺2017]。もっとも、個人史に着目するのは、捕鯨の花形ともいえる砲手さんの自伝や伝記をのぞけば、当事者の声が少ないことに気づいたからである。
戦後復興から高度成長にいたる過程の人びとの生活は、どのようなものであったのか? 高度成長やバブル経済が、わたしたちの生活のなにを、どう変えたのか? 捕鯨関係者の肉声をもとに、まずは、この2点を考察したいと考えている。
そうした一連の研究の端緒として、本稿では、肉ばかりが脚光をあびる捕鯨に、鯨油という別の角度から光をあててみたい。具体的には、(1)鯨油利用の世界史を略述し、戦前の日本の南氷洋捕鯨の目的も、油脂資源獲得にあったことをあきらかにする。そして、(2)戦後日本において粉食の浸透とともに「見えざるクジラ消費」としてマーガリンの利用が拡大し、さらに植物性油脂へと推移した経緯を跡づける。
最後に、(3)生産中止となった鯨油を代替したパーム油の生産の陰でオランウータンが絶滅の危機にあることを論じ、(4)わたしたちの生活様式を改めないかぎり、「クジラも、オランウータンも」保護することが困難な現実を指摘したい。
鯨油とマーガリン
鯨類の皮や脂肪、骨からとれる油を鯨油と呼ぶ。鯨類は、人間でいえば歯茎にあたる部分が伸びた鯨髭(baleen)をもつヒゲクジラ類と歯をもつハクジラ類の2種類に大別できる。通常、ヒゲクジラ類からとれた油をナガス油、ハクジラ類からとれた油をマッコウ油と呼び、区別している。ナガス油は植物油同様に食用できるものの、マッコウ油はワックス(蝋)を含むため食用とされないように、油の性質がことなるからである。
1820年に英国人捕鯨者のウィリアム・スコーズビー(William Scoresby)があらわした『北極圏――北極海捕鯨の歴史』によれば、鯨油の主要な用途は、(1)皮革・羊毛洗浄用の液体石鹸、(2)照明用燃料および蝋燭、(3)ワニスやペンキなどの原料、(4)精密機械の潤滑油などであった。毛織物工業は、まず刈りとった羊毛を洗浄しなければならず、その工程に大量の鯨油を必要とした[森田1994: 112-113]。
18世紀半ば、欧米社会の都市を照らしたのは鯨油を光源とする街灯であった。捕鯨史的に興味深いのは、その頃にマッコウ油が登場することである。マッコウ油は、それまで捕鯨対象種であったセミクジラの油よりも明るくて臭いも少なかったことから、優れた光源とされた。家庭用ランプや蝋燭の需要は19世紀にますます大きくなり、それだけマッコウ油の商品価値も高まった。米国の捕鯨船が日本近海で狙ったのは、マッコウクジラであった。
ところが、石炭からガスを精製することが可能となると、街灯は次第にガス燈にとってかわられた。米国東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリーが「鎖国」の扉をこじ開けようとしていた、まさにその頃、皮肉にも、光源としての鯨油の人気には陰りが見えはじめていた。それは、同時期に米国で生じた2つの出来事に起因する。1848年、カリフォルニアで金鉱が発見されると、一攫千金をもとめてゴールドラッシュに参入する捕鯨者が続出した。さらに開国後の1859年にはペンシルバニアで油田が開発され、石油の利用が可能となった。
こうして鯨油採取を目的とする捕鯨は終息していった。しかし、20世紀初頭には、スコーズビー時代には想定できなかった鯨油のあらたな利用法が発明されることになる。ドイツで液体油を固体化する「硬化油処理法」が開発されたのである。この方法により、鯨油は高次加工が可能な工業原料と化すことになった。
たとえば、アルフレッド・ノーベルが開発したダイナマイトの原料はニトログリセリンであるが、その原料となるグリセリンは、もともとは固形石鹸を製造する過程の副産物として誕生したものであった。やがて第一次世界大戦で爆薬需要が増大すると、鯨油はきわめて重要な戦略物資となった[森田1994: 346]。
硬化油処理法によって、鯨油特有の臭みを取りのぞくことが可能となったため、固体鯨油は、1870年代に実用化されたマーガリン製造と結びつくことになった。1920年代末には摂氏30度くらいで融ける硬化油の製造法も開発され[山下2004: 190]、鯨油100%のマーガリン製造が可能となった。
そして、第一次世界大戦後の急激なマーガリン需要の伸びは、南氷洋での母船式捕鯨の拡大という事態をむかえるにいたった。それは南鯨(南氷洋における母船式捕鯨)先進国であるノルウェーやイギリスだけのことではない。1934/35年から日本が南氷洋に進出したのも、そうした世界的需要にこたえるためであった。
鯨油生産が主目的だった戦前の南鯨
現在、捕鯨の賛否が問われる場合、食肉生産が前提とされている。だからこそ、「飽食国家の日本で、いまさら鯨を食べる必要があるのか」といった反対意見の一方で、「鯨食は日本の伝統文化」といった議論がなされることになる。たしかに調査補鯨の副産物が鯨肉のみで、鯨油生産がなされていない以上、そうした論争がおこるのも故なしとしない。しかし、巨視的に捕鯨の歴史をふりかえれば、捕鯨の中心は鯨油生産にあった。
たとえば、地域色豊かな鯨食文化を育んできた江戸時代の捕鯨においても、鯨肉生産と並行して鯨油が生産されていた。それは、捕鯨砲を装備した発動機つきの船で捕鯨するノルウェー式近代捕鯨を導入した明治期以降の沿岸捕鯨でも同様である。それらの沿岸捕鯨地では、鯨肉を生産するかたわら、鯨油も生産していたのである。灯りとしての用途以外にも、イネにつく害虫を駆除するために鯨油は重宝した。
くわえて注視すべきことがある。それは、戦前に南氷洋ではじめて日本の母船式捕鯨船団が操業した1934/35年から太平洋戦争の開戦で中止されるまでの7回にわたった南鯨では、鯨油生産が主目的とされていたことである。それは、鯨肉生産を主要目的として操業していた、30隻程度の国内の沿岸捕鯨者たちを保護するためでもあった。同時に、西日本を中心とした鯨肉の国内需要が、当時、すでに飽和状態にあったからでもあった。
そんな均衡が崩れるのは、1937年に勃発した支那事変が泥沼化する一方で、おりしも対米戦争不可避との気運も高まり、戦時体制が本格化する1938/39年漁期からである。それまでわずかばかりの塩蔵肉しか持ち帰られていなかったところに、鯨肉輸送用の冷凍船が別個に派遣されるようになった。このあたりの事情を、当時の新聞はつぎのように伝えている。
「軍國気分滿喫! 鯨のスキ焼 栄養価は牛肉と匹敵 鯨鍋もウマイねェ」 牛豚肉に代わるべき動物性食品として兎、羊、鯉、鰯などが奨励されているのに鯨が何故か閉脚されているのは不思議です。鯨は蛋白質20.95、脂肪7.62、灰分1.25というほぼ牛肉に匹敵する成分をもち、かつ羊や兎は全国民が10日か1か月も食い続ければ無くなってしまうほど少量であるのに較べて、鯨は無尽蔵であることを考えれば、何よりも先ず鯨を食はねばならぬ筈です。が、現在は、捕鯨の目的は鯨油を得ることが主で肉には重きをおいていないため、輸送方法が他の魚類、海産物ほど慎重でない傾向があり(後略)[『讀賣新聞』1937年10月21日、朝刊、9頁]
この記事から牛肉と豚肉の代わりに鯨肉が推奨されていることがわかる。ただし、都市民ならいざしらず、当時、大部分の人口が居住していた地方で、どれほどの畜肉が消費されていたかは疑問である。とはいえ、この記事からは、(1)鯨肉が全国的に消費されていなかったこと、南氷洋の豊富な鯨類資源を念頭に(2)鯨類資源が無尽蔵であり、かつ(3)鯨油生産にくわえ、鯨肉生産が急務の課題であったこと、の3点が看取できる。
「極光の海から代用品の寵児 鯨肉、皮の土産はふんだん タンカーを冷凍船に改造して 中秋 乗出す捕鯨船部隊」 (前略)昨年度の捕獲5,500頭、鯨油65,000トンだったのを今年は約2倍の10,000頭、鯨油122,000トンが目標とある。(中略)これまで海に捨て去って来た鯨肉や鯨皮はどうして日本に持ち帰るかが研究題目だ。鯨油本位に造られた従来の母船では手の施しようもなく、中積船などで腐敗し易い肉や皮を冷凍または塩漬けにして赤道直下を一月も費やして運ぶのでは、技術的にも採算的にも無謀に近い。さりとて国策上鯨体帰送は是非とも早急に実現したいとあって、日水、大洋、極洋三社間で今夏来農林省の指示を仰いで方法を練っていたところ。母船の構造を急に鯨体輸送本位に改造することは実際問題として不可能のため、これまで鯨油や重油の中積みに使っていた中積船(タンカー)を三社の協同出資で冷凍船に改造、これを12月から来春3月までの盛漁期に数回廻航。(後略)[『讀賣新聞』1938年8月28日、第2夕刊、2頁]
日中戦争の戦時下とはいえ、この記事からは、それほどの逼迫感は感じられない。それでも(4)鯨肉を持ち帰るには、専用の冷凍船が必要であり、その用意が資金的・技術的にも簡単ではなかったこと、つまり、(5)それほどに戦前の南鯨事業が鯨油生産に特化していたことも指摘できる。
マーガリンの戦後
わたしは、以前に鯨肉消費の一形態として魚肉ソーセージ・ハムがはたした役割を論じたことがある[赤嶺2012]。そこでは、鯨肉入りの魚肉ソーセージ・ハムの普及が、高度経済成長とともに「本当」のソーセージ・ハムの需要を喚起し、しいては牛肉や豚肉などの畜肉消費を全国的に拡大させたという仮説を提示した。当然ながら、ソーセージに練りこまれた鯨肉は見えない主役であった。同様に、「見えざるクジラ消費」のひとつがマーガリンである。
戦後、米国による食糧援助のおかげでパン食が普及したことは、周知のことである。食パンにしろ、コッペパンにしろ、バターなり、マーガリンなりを塗って食べる。ヨーロッパでのマーガリン原料としての鯨油需要について触れたように、日本でもマーガリンの主要原料は鯨油であった。しかし、アメリカの主要生産物である綿実油や大豆油などとの競合をはじめ、鯨油は、つねにほかの油脂原料との競争にさらされていた。価格は当然のこと、風味や食べやすさが勝敗を決する要因となった。
「食べる <40> 変身する食品5 バターをしのぐマーガリン 原料も魚鯨油から植物油に」 (前略)だいたい、マーガリンという名称が使われ出したのは戦後も(昭和)25年ごろからで、それまでは・・・・・・人造バターと称していたぐらいだ。(中略)わが国でマーガリンが作られるようになったのは明治末だが、そのことの主原料は牛脂であった。一般に、大豆油など常温で液状のものを油、牛脂など固体のものを脂と区別するが、当初は油を個体にする硬化油技術が開発されていなかったため、常温でも固体の牛脂を原料にした。その後、液状の油を固めて硬化油にすることができるようになり、牛脂のほか、魚鯨油、植物油も原料として使われるようになった。戦後も30年代までは魚鯨油がマーガリンの主原料であった。/人造バターと呼ばれていたころは、現在のように精製、脱臭技術も進歩していなかったので、ロウをかむようないやなにおいがした。硬くて、パンにぬるにもボロボロしてうまく塗れず、口どけもすこぶる悪かった。(中略)/牛脂から魚鯨油と変化してきたマーガリンの原料は、さらに(昭和)40年代にはいり植物油へと三転する。冷蔵庫の普及と共に、融点の低いマーガリンが作られるようになり、軟らかく、パンに塗りやすい、ソフトタイプのマーガリンが登場してきた。/「バターは冷蔵庫に入れておくと硬くて、パンに塗りにくい。この点をマーガリンが克服、液状の植物油の配合、硬化油技術の進歩で、低温でも軟らかく、高温でも溶けないものが作れるようになった。バターとは違う食品へという一つの脱皮がこのソフト化にある(後略)[『讀賣新聞』1977年10月28日、朝刊、13頁]
冷蔵庫の普及がソフトタイプのマーガリンの登場をうながし、主原料が鯨油から植物油へ転換を決定づけ、その結果、バターの代用品という地位を抜けだしたという指摘は興味深い。『内閣府消費動向調査・主要耐久消費財普及率』によると、(電気)冷蔵庫の普及が50%を越えたのは、1960(昭和40)年であった。
一般に「家庭用マーガリン」の原料が動物性油脂から植物性油脂に切り替えられるようになったのは1960年代半ばとされている。冷蔵庫の普及と無関係ではないだろう。しかし、家庭用とことなり、業務用マーガリンには1970年代半ばまで鯨油が使用されていたようである。1976年は、捕鯨産業をゆるがした大変革の年である。
一般に南氷洋の捕鯨の規制は1972年にスウェーデンで開催された国連人間環境会議で米国が提案して以来のことと理解されている。しかし、それは事実ではない。ゆるやかとはいえ暫時、捕獲枠は減少しつづけていたし、1960年代半ばにはザトウクジラとシロナガスクジラが禁漁となっていたからである。
そして、1976年からはナガスクジラも禁漁とされた。この決定をうけ、大手水産会社の大洋漁業、日本水産、極洋捕鯨は捕鯨から撤退することになった。三社は捕鯨部門を切り離し、日本捕鯨、東洋捕鯨・北洋捕鯨の大型捕鯨部門と統合させ、1976年2月に日本共同捕鯨株式会社を設立した。
1976/77漁期の捕獲枠は、イワシクジラ1,237頭とミンククジラ3,950、マッコウクジラ234頭であった。マッコウクジラは、(食用とされない)工業原料用のマッコウ油がおもな目的である。最大体長26メートル・最大重量80トンのナガスクジラとくらべるとイワシクジラは最大体長18メートル・最大重量30トン程度にすぎないし、ミンククジラにいたっては最大体長9メートル・最大重量9トンと小さい。その分、鯨油採取の効率がわるいため、鯨肉の生産が重視されたのは当然のことである。
つまり、商業捕鯨は1987年まで存続していたとはいえ、その実態は、1960年代と70年代、80年代では、ことなっていることに注意が必要だ。鯨油生産から鯨肉生産へとシフトしてきたのである。
クジラもオランウータンも?
おおざっぱな見立てにすぎないものの、世界の油脂事情を俯瞰するかぎり、1970年代以降に次第に姿を消していった鯨油を代替したものは、大豆油とパーム油であった。2012年に世界で生産されたパーム油は5,595万トンで、植物油生産量の36%を占め、植物油で第1位の生産量を誇っている。第2位は大豆油の4,214万トンで、このふたつで世界の植物油生産の63%を占めている。
2012年、パーム油の生産はインドネシアが50%、マレーシアが35%を占め、両国で世界の生産量の85%を占めている。西アフリカ原産のアブラヤシが、東南アジアで注目されるのは、なぜなのか? それは、アブラヤシが熱帯多雨林の伐採跡地利用に適した油脂植物だったからである。
生物多様性の豊かな熱帯地域では、単位面積あたりの種数はおおいものの、逆に単一種の量は少ないのが特徴である。通常、商業材として伐採されるフタバガキ科の樹種は、1ヘクタールあたり4〜5本しか存在しない。したがって、それらの有用樹種を搬出したあとの森も、素人眼にはジャングルそのものにみえる。だが、そうした伐採跡地の商業価値はゼロである。だから、その空間は、アブラヤシ園として再生されることになる。
![30年以上がたって樹の生産性がおちてくると、植え替えられる。[2016年4月、マレーシア・サバ州にて筆者撮影]](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2016/08/P4_Sabah_20160423.jpg)
![低湿地でも開発がすすむアブラヤシ林。[2009年11月、マレーシア・サバ州にて筆者撮影]](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2016/08/P5_Sandakan_20090326.jpg)
しかし、困ったことに、現在、アブラヤシの植えつけが進む、ボルネオ島とスマトラ島には、オランウータンが生息している。いや、オランウータンは、この両島にしか生息していない。オランウータンの生息地は、人類未踏の原生林にかぎらない。たとえ伐採跡地であろうとも、そこに「森」があるかぎり、オランウータンは生存できる。したがって、経済価値を失った伐採跡地がプランテーションに転換されれば、それだけオランウータンの生息地は狭まることになる。
![シンガポール動物園はマレーシアとインドネシアで保護されたオランウータンのほか、人工繁殖させたものもふくめ、世界最大のオランウータンの展示数をほこっている。[2008年3月、シンガポール動物園にて筆者撮影]](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2016/08/P6_Orang_SIN_20080327.jpg)
このシナリオが正しいとするならば、残念ながら、オランウータンの保護はむずかしいといわざるをえない。ましてや、オランウータンの場合は、二重の悲劇でもある。皮肉にも、「クジラを守る」という行為が、まわりまわって、アブラヤシ園の造林を刺激し、その結果、これまた環境保護のシンボルたるオランウータンの生息環境をおびやかしているからである。
では、パーム油をやめ、大豆油を利用すれば、問題は解決するのであろうか? ことは、そう単純ではない。2013年、大豆油生産の第1位は米国の910万トンで、以下、第2位のブラジルが720万トン、第3位のアルゼンチンが670万トンとつづいた。大豆はアジアを中心に豆腐や納豆、醬油など食用とされてきた植物であるが、近年は油脂食物としての生産が拡大し、とくにアマゾンの開拓が問題視されている。
本稿ではマーガリンを中心に議論したが、わたしたちが消費する油脂は、なにもマーガリンにかぎらない。インスタント麺や、カカオバターの代用品、ラクトアイスなど、目に見えない部分での消費も随分とある。食用以外の石鹸も洗剤も油脂製品である。自戒の念をこめてのことであるが、今日、わたしたちの生活は油脂なしにはなしえない。だが、こうしたわたしたちの生活様式こそが、「クジラも、オランウータンも」のみならず、アマゾンの原生林までも、その存続を危なかしいものにしているという現実を知る必要がある。
鯨類の乱獲は、たしかに問題である。それはアマゾンやボルネオの森を破壊、生物多様性を脅かすのと同様、糾弾されてしかるべきである。逆説的であるが、だからこそ、わたしたちは歴史と対峙し、その過ちを繰りかえさないように科学調査を積みあげ、持続可能なレベルで厳格に管理された鯨類の利用を推進すべきではないだろうか? それは、「蛮行」なのではなく、「かぎりある地球でわたしたちが生きる」術のひとつなのである。
「食足りている」いまこそ、自分のライフスタイルが許される陰で生じていることに眼をむけてみよう。瞬時に問題を解決してくれる魔法の杖など、残念ながら存在しない。わたしたちがなすべきことは、問題のつながりを知ったうえで、そのつながりを断ち切るべく、できることから行動していくことだけである。
謝辞
本稿は、わたしが研究代表をつとめる日本学術振興会・科学研究費補助金「近代産業遺産としての捕鯨の記憶――捕鯨問題と文化多様性」(挑戦的萌芽研究,#25570010)と「生物資源のエコ・アイコン化と生態資源の観光資源化をめぐるポリティクス」(基盤研究B,#25283008)の成果の一部です。なお、本稿を作成することができたのは、捕鯨史研究の古典ともいうべき『鯨と捕鯨の文化史』(1994年、名古屋大学出版会)が存在したからです。著者の森田勝昭先生に感謝いたします。
引用文献
赤嶺淳、2012、「食文化継承の不可視性――希少価値化時代の鯨食文化の動態」、岸上伸啓編、『捕鯨の文化人類学』、成山堂書店、207-224頁。
赤嶺淳、2017、『聞き書き 鯨人の個人史』、吉川弘文館、印刷中。
森田勝昭、1994、『鯨と捕鯨の文化史』、名古屋大学出版会。
山下渉登、2004、『捕鯨Ⅱ』、ものと人間の文化史120-Ⅱ、法政大学出版局。
ヴァンダーミーア、ジョン・H.、イヴェット・ペルフェクト(新島義昭 訳)、2010、『生物多様性〈喪失〉の真実――熱帯雨林破壊のポリティカル・エコロジー』、みすず書房。
Scoresby, William. 2011. An Account of the Arctic Regions: With a History and Description of the Northern Whale-Fishery. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press.
プロフィール
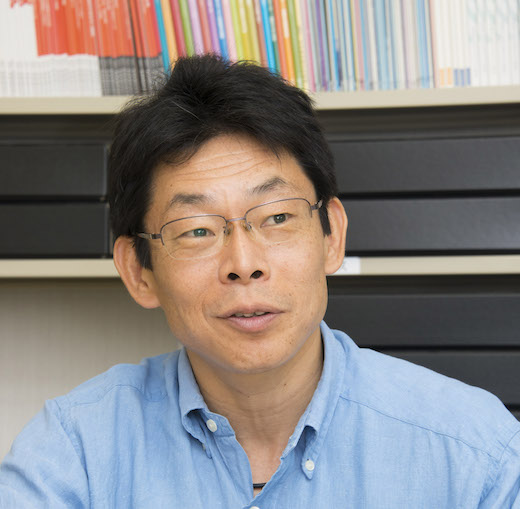
赤嶺淳
1967年、大分県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻・教授。2007年よりワシントン条約日本政府代表団顧問をつとめる。現在、高度経済成長期前後の生活様式の変容を鍵に「食の安全保障と捕鯨問題」に取り組んでいる。おもな著作に、『ナマコを歩く――現場から考える生物多様性と文化多様性』(新泉社,2010年)、『クジラを食べていたころ――聞き書き 高度経済成長期の食とくらし』(編著,グローバル社会を歩く研究会、2011年)、『バナナが高かったころ――聞き書き 高度経済成長期の食とくらし 2』(編著,グローバル社会を歩く研究会,2012年)、『グローバル社会を歩く――かかわりの人間文化学』(編著,新泉社,2013年)などがある。


