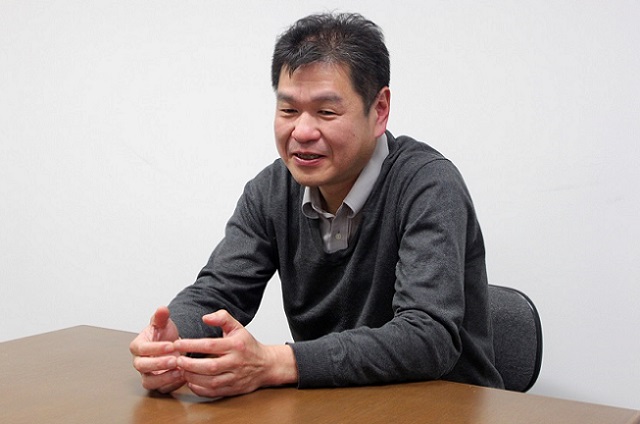2015.02.18
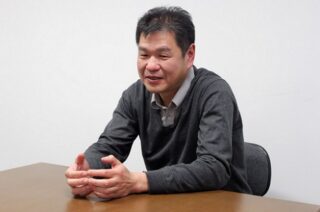
日本は死因究明における後進国だ
日本では「死因のウソ」がまかり通っている!?ずさんな死因究明制度が引き起こす、知られざる社会問題とは。話題の本『死体は今日も泣いている』著者・法医学者の岩瀬博太郎氏にお話を伺った。(聞き手・構成/山本菜々子)
もし自分が異状死したら
――本書を読んで、とても驚きました。現代の日本に生きていたら、異状死した場合、解剖されて死因を調べてくれるものだと思い込んでいたので。
皆さんそう思っているようですが、日本で解剖され死因が調べられることはまれです。外国では異状死の解剖率が9割近い国もありますが、日本は約1割です。
――非常に少ないですね。異状死した場合、どうやって死因が決められるんですか。
大抵の先進国では、死因が分からない場合、解剖して死因を特定しなければ犯罪性があるか判断できないので、司法解剖を実施します。ですが、日本は特殊で、解剖する前の段階、つまり警察による検視の段階で、犯罪性の有無を判断してしまい、犯罪性の疑われない死体を調べる「行政検視」と、犯罪性が疑われる死体に対してする「司法検視」に分けられます。
そして、警察官が犯罪性を疑った場合、司法解剖が行われます。簡単な初動捜査で、事件性が無いとされると、そのまま調べられることもなく火葬されます。
――1割しか解剖されないとしたら、残りの9割の死因はどのように特定されるのでしょうか。
犯罪性がないと判断された死体は、警察嘱託医が診察します。この警察嘱託医の先生の多くは、死体を診るために特別な訓練を受けているわけではありません。だいたいは、病気治療を専門にしている臨床医です。普段から病死ばかりを見ているから、どうしても診断は病死に引っ張られていく。
結局、死因がわからないので、えいっと適当な病名を付けざるを得ない。ふつうは、思いつく病名もないので、多くの異状死は、「心不全」という病名なんだかよくわからない診断名をつけられてきました。毒で死ぬときも、みんな心不全なんですが。
「あまりにも心不全が多すぎる」と法医学サイドから指摘があったのですが、1990年代に厚生労働省は死亡診断書に「心不全と書かないでください」と但し書きを入れるのみの対応をとりました。
――ブラックユーモアの世界ですね。
警察の方も忙しいですから、犯罪性がなければ早々に次の仕事をしたい。ですので、医者が病死にしてくれるのを歓迎する傾向があります。警察側の方で病死にしたいときは、そういう傾向の強い先生を選んだりもできる。これは実際に起きていることです。現場の人は、みんなおかしいと思っています。
――では、もし自分が殺されたとしても、事件性がないと判断されたら、もう調べられることはないと。
そうです。遺族が後から、何かの事件に巻き込まれたのではと疑っても、火葬されてしまったら後の祭りです。
実際に、きちんと死因を解明しなかった弊害は、多くのところで表れています。たとえば、パロマ製ガス機器に関連する一連の事件では、湯沸かし器の不具合が起こした一酸化炭素中毒なのにも関わらず「冷たいシャワーをあびて心臓麻痺を起こした」といったように死因が推定されました。事件は20年も放置され、少なくとも21名もの死亡者が出ました。
また、保険金殺人を見逃したせいで、第二、第三の被害者が出てしまった例が毎年のように報道されています。これらは、最初の被害者の段階で死因を特定していれば、防げたものです。
これはあくまで私の予想ですが、危険ドラッグも、もっと以前から死者がでていたと思います。その時、きちんと死因を解明し、危険性を周知していれば、こんなにも流行していなかったかもしれない。
また、交通事故で亡くなった際、解剖によって適切に得られた血液ではなく、事故現場に落ちていた汚染された可能性もある血液のアルコール濃度をもって、「飲酒運転」だったとされ、家族に保険が降りないようなケースもあります。死因を特定しない弊害は民事上の問題にもあらわれます。
ジャンボジェット機を一人で操縦するような
――そもそも、法医学とはどのようなものなのでしょうか。
法医学は、明治時代にドイツから入ってきた学問です。日本における法医学の始祖・片山国嘉教授は、法医学を「国家医学」に分類しました。
医学は、個人の病気を診る「各人医学」と、法医学や公衆衛生のような国を診る「国家医学」とがあります。法医学は、法律の適正な執行のために、医学的なアドバイスをする学問です。そのことで、国民の権利を守っていくことを目的としています。
適切に国民の権利を守るためには、解剖だけでなく、薬物検査など様々な検査を行って適切に死因を判断しなければなりません。薬物で殺害されていたのに、病死とされれば、また同じ殺人事件が起きますし、逆に薬物で殺害されたわけではないのに、噂話だけで人を罰してしまっては、冤罪がおきますから。
しかし、残念ながら今の日本の法医学は、「解剖だけやればいい」という風潮があります。本来ならば、死因を特定するために薬物検査やCT検査も積極的に取り入れていくべきです。
加えて、死んだ人だけではなく、生きている人も対象にする必要があります。虐待を受けた子ども、DVを受けた女性――そういう人たちを診察し、保護するようにアドバイスするのも、我々の仕事でしょう。
――全国に法医学者の医師は何人いらっしゃるんですか。
150人くらいしかいません。
――少ないですね。
全国でおよそ80の大学医学部があり、医学部には法医学教室が必ずあります。各大学に1人か2人ずつの計算です。
死因の解明は非常に難しいんです。解剖の時考えていたことが、検査をしてみてひっくり返ることもよくあります。正式な結果が出るまで全部で2ヶ月はかかりますね。それでやっと、死因がわかる。
本来ならば同僚同士で議論し合うべきですが、これくらいの人数しかいませんので、「同僚」というよりも「教授」と「助手」の関係で議論することも多く、そうなると、力関係がどうしても出てしまい、正しい議論ができないこともありえます。
他の医局だと例えば内科の医局に行けば100人以上の医師がいることがあります。これだけいれば診断の正しさについて議論することも可能です。一人の教授が倒れても、医局の業務にそれほど影響はでません。でも法医学の場合、もう目も当てられない感じになってしまいます。
ある意味で、ある裁判の被疑者の死刑が決まるかどうかという重要な問題に関わる死因究明という仕事に関与している人間が、県によってはたったの1人なんですから。これは、ジャンボジェット機を1人で操縦するくらいの無茶があります。場合によっては独善となってしまい、警察に迎合してしまうという可能性もあるのです。
そもそも今から8年ほど前までは、日本政府は全く死因究明に予算をかけてきませんでした。解剖すると最低でも30万円程度の費用がかかるはずなんですけど、以前はそうした経費は一切大学にいれず、解剖後に「謝金」と言って教授個人に数万円支払って終わってしまうという不思議な運営がされていました。
こうした謝金で一部の教授だけはホクホクということもありえましたが、善意で大学の設備投資などに全額使う奇特な教授が多くいました。しかし、仮に奇特な教授が全額設備投資などに使ったとしても、そもそもその金額では赤字採算ですから、ちゃんとした薬物検査の機械など買えるはずもなかったのです。
そうこうするうち「死因を適切に究明し、国民の権利を守る」という法医学のあるべき姿をすっかり見失い、解剖だけやっていればいいんだといったような、どんどん狭いところに追い込まれていったように感じます。
実際に、予算もまったくついていません。私が2003年に千葉大に赴任した時なんかは、法医学教室の解剖は台所にあるようなまな板と出刃包丁を使っていました。それくらいお金が無かったんです。
契機となったのは、2007年の時津風部屋事件です。新弟子として入門した少年が亡くなった痛ましい事件を覚えている方も多いのではないでしょうか。心不全と診断されましたが、解剖をしたことで集団暴行の事実が発覚しました。あの時をきっかけに、検死の重要性が注目され、その後解剖に付随して行う検査の経費がつくようになりました。
とはいえ、多少は改善しましたが、世界的に見て、まだまだ非常に貧相な状況です。他の国が、「法医学研究所」を持っているにもかかわらず、日本はいまだに持っていません。日本のほとんどの地域にあるのは、こじんまりとした「法医学教室」だけです。他の先進国は、システムとしてきちんと国や自治体が責任をもって運営しています。それなのに、日本はそれができておらず、各自治体で、たった1人か2人の法医学者の善意に極端に依存したシステムをいまだに続けています。法治国家として恥ずかしい事態だと思います。
先進的な取り組み
――海外にはどのような制度があるのでしょうか。先進的な取り組みをしている国を教えてください。
今は、オーストラリアとスウェーデンなどでしょう。
オーストラリアには「コロナー制度」と呼ばれるものがあります。日本には、刑事裁判と民事裁判の2種類がありますが、オーストラリアには3つ目に死因究明裁判があると考えてください。その死因究明裁判を行うのがコロナーという裁判官なのです。
病院以外で死亡した遺体があれば、コロナー裁判によって必ず死因を決めなければいけません。法医学研究所の解剖や薬物検査による医学的な調査と、警察の調査とを合わせて、コロナーたちが死因を決定します。
スウェーデンは、日本に近い法律なのですが、法医学庁という省庁があり先駆的です。法医学はどうしても人を集めづらいので、そのままにしておくと誰もやらなくなってしまうので、国が責任をもって、人員や設備を整備しています。
ですので、スウェーデンではトキ保護センターのように、法医学者の給料を上げるなど、法医学者を保護し、減らさないようにしている。実際、外科と同じ給料をもらうようで医学部生に人気がでているようです。
家族が解剖されるとき
――お話を聞くと、なぜ日本だけ死因究明が重要視されないのでしょうか。
不思議でなりません。たぶん、なんちゃって法治国家にしかなれていないからだと思います。警察の調査手法も自白が中心で、江戸時代の岡っ引きを引き継いでいます。国民自体もいまだにどこか、警察が捜査をすればなんでもわかる、と思っている節があるのではと感じますね。
僕は、死因究明を進めていく事で、プライバシーが守られると思っています。というのも、解剖して死因がわかってしまえば、そんなに周辺捜査をしなくても、多くが病死と判断できるにもかかわらず、解剖で死因の特定をすることなく、周りの状況の捜査のみで、犯罪性を見極めようとするので、死者の携帯電話を勝手にのぞくなどどうしてもプライバシーが侵害されがちになります。ほかの国のように、犯罪性の判断のまえに、解剖などによって科学的に死因を特定さきるようになれば、捜査をすることによるプライバシーの侵害が、最小限になります。
――法律で遺族の許可無く解剖できるようになったと聞きました。この意図はどこにあるのでしょうか。
日本では、「遺族が泣いていてかわいそう」というだけで解剖されなくなってしまいます。解剖は遺体を傷つける行為であるということばかり強調すれば、「解剖は悪」になりがちです。ですが、日本ではほとんどすべて死体は焼かれてしまうし、焼かれてしまったら、もう死因は分からない。死因がわかることで、救える命があるかもしれない。だから、それくらいは譲ってよいことなのではないかと思います。当然遺族によっては、抵抗を感じる人もいらっしゃるとは思います。
でも、それは世界的にそうなんです。家族が解剖されることが好きな人はどこにもいません。ユダヤ教もキリスト教も、日本人以上に解剖が嫌いです。嫌いだからこそ、法律で、きちんと決められているんですね。それが本当の法治国家なのだと思います。
法治国家とは言いがたい面のある日本では、解剖をする/しないの決定を、遺族がしないといけません。それは残酷です。時津風部屋の被害者の父親が、「自分で息子の遺体を解剖する判断をしたのが辛かった」とおっしゃっていました。辛いですよね。ただでさえ、悲しい状況なのに。制度がきちんと自動的に死因を究明してくれるようになれば、こんなに苦しまずに済んだはずです。
また現場の感覚からすると、殺人事件での加害者で多くは家族なんですよね。今のままでは、殺人を犯した遺族が上手に泣けば犯罪は見過ごされてしまうでしょう。素直に家族の話を鵜呑みにしてしまっては、別の人が被害者になってしまうかもしれない。次の被害者を出さないことも大事だと考えています。
一緒に戦う
――岩瀬先生はなぜこの仕事を始めたのですか。
学生時代、法医学教室の先生に「警察から差し入れられたお神酒があるから飲みにおいで」と誘われたのがきっかけです(笑)。それから、教授に法医学やらないか口説かれて。本当は嫌だったんです。内科や皮膚科とかに行きたかった。「臭いがちょっと」と逃げようとしたら、「臭いは慣れるから」と説得されて、断る理由が無くなってしまって。でも、臭いはいまだになれませんね。
法医学は3Kの仕事です。しかも、他の医者に比べて給料も安い。加えて、死因の分からない遺体を扱うわけですから、解剖中に感染症になってしまう可能性もあります。
こないだも、肝硬変の遺体の解剖中に針刺し事故を起こしてしまってヒヤッとしました。検査したらセーフだったのですが、もし遺体がC型肝炎にかかっていたらと思うと恐ろしいです。
最近、マスコミが注目しなくなった途端、すっかり政府もやる気をなくしてしまって、場合によっては予算を半分にする話まで出てきているんです。今まで大事に育ててきた人材はどうしたらよいのか。なんとか阻止しなきゃと思うのですが。
この国は、一部の善意ある方々の善意の上にあぐらをかいています。これでは善意ある人間は押しつぶされてしまうでしょう。非常に頭にきますよ。こんなに国がいい加減に我々のことを扱っているのに、なんで私たちはこんなに一生懸命やんなきゃいけないんだろうって思うこともあります。
よく、「法医学者は解剖が好きじゃないとなれない」と言う方もいます。ですが、ぼくは解剖が好きかと聞かれれば、好きとは言い切れません。そもそも、それっておかしいですよね。産婦人科の先生が女性の内診が大好きだったら、びっくりします。医師としての仕事は、いやな仕事であっても責任感や使命感でやっているのであって、好きという気持ちだけでやるものではないと思います。
ぼくは、解剖の前に手を合わせることに、抵抗があってやらないんですよ。ご遺体に言い訳するみたいな気がしてしまうんですよね。本来は、解剖をやって死因が分かって、それでようやくこの人が成仏できると思うんです。いつも一緒に戦っているような気持ちで、解剖をしています。
死因を究明することは、どうしても後ろ向きなイメージを持たれます。ですが、同じことを繰り返さないために何で死んだのかを知る必要がある。そして、今生きている人が安全に楽しく暮らせるようにしたい。本当はとても人の生に対して前向きな仕事なんだと思います。だから、我々も頑張れているのだと思います。
プロフィール

岩瀬博太郎
平成5年東京大学医学部卒業。博士号を取得後、東京大学大学院医学研究院法医学教室助手、講師、助教授を経て、平成15年から千葉大学大学院医学研究院法医学教室教授。平成26年4月から、東京大学大学院医学研究院法医学教室教授兼任。