2017.03.27

『政治の理論』――近代において共和主義を再考する
全体主義は否定すべき悪であるのか?
本書『政治の理論』に至るまでの私の仕事を振り返ってみるならば、まず1999年の『リベラリズムの存在証明』という本があった。あの本のライトモチーフはひとつには”Taking Libertarianism seriously”であり、直観的には荒唐無稽だが、すっきりと明快であるがゆえになかなか決定的な論駁が難しく、思考実験としては大いに魅力的であるリバタリアニズム、最小国家論に対して普通のリベラリズムをどこまで防御できるか、という問題意識がそこにはあった。
今一つのモチーフとしては、経済学における「ケインズ経済学のミクロ的基礎付け」とのアナロジーで言えば「全体主義のミクロ的基礎付け」とでもいうべきものであり、合理的選択理論を根底に置いた考え方で、どこまでいわゆる全体主義というものを理解できるか、またそれに抵抗する方途としてはどのようなものが考えられるのか、という問題意識であった。そこでは「理論的に完璧な全体主義というものがあったとして、そこから脱出することは可能か?」という問いが立てられたが、とりあえずの回答は否定的なものであった。
もしも「忘却の穴」が「原理的に不可能なものではない」のだとしたら、それを完全に防ぐことは「原理的に不可能」である。我々になしうることは、「忘却の穴」が「原理的に不可能ではなく」とも「現実的には」失敗する可能性もあるということに賭けて、「必ず誰か一人が生き残って見て来たことを語るだろう」ことに期待すること、ないしその「生き残り」になるべく努力することしかありえない。(『リベラリズムの存在証明』406頁)
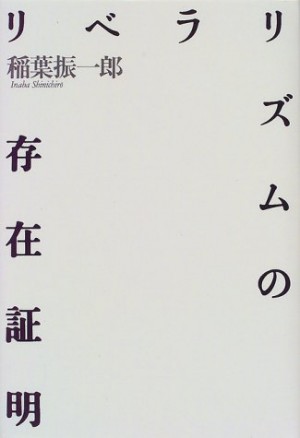
2008年の『「公共性」論』ではリバタリアニズムへの関心は後退し、かわってリベラリズム対コミュニタリアニズム、さらにコミュニタリアニズムの基盤としての徳倫理学への関心が前面に出てきている。ポイントの一つは「価値の多元性」へのコミットメントの問題である。
「リベラル-コミュニタリアン論争」と一口に言っても、そこで主役となっているのは、リベラル陣営の中ではロールズ、ロナルド・ドゥウォーキン、あるいはロバート・ノージックら、権利論的なタイプの論者であり、コミュニタリアン陣営においてはテイラーなどの多文化主義者でしょう。つまり、現代社会において社会的な価値の多元性、不可共約性が支配していること=「比較不能な価値の迷路」は事実として認め、かつそれを克服・変革できる/すべき対象とは見なさず、受け入れ是認する、つまりこの価値の多様性それ自体は望ましいことだ、と肯定的に評価する、という点において既に同意してしまっている者たちの間での「論争」が、舞台の中心を占めている。そこまでは既に見たとおりです。
では多文化主義的なコミュニタリアンがリベラルな多元論者をどのように批判するのか、を考えてみましょう。多文化主義の文脈から見た場合、批判の最大のポイントは「単に開かれた機会、機会の平等が与えられただけの世界においては、実際には価値の多様性は実現しないだろう」という危惧でしょう。(中略)
これはつまり言い換えれば、個人の自由な選択に任せた場合、じつは社会の中での価値の多様性は縮小し、衰退するだろう、という予想であるわけです。だから実際にはリベラルな多元主義者と多文化主義コミュニタリアンの間では「事実」認識が微妙に食い違っている、と言わなければならない。そしてこのずれは「評価」のレベルにおけるずれよりもおそらくは大きい。共約不能な諸価値の並立、という現状に対する「評価」は、リベラル、コミュニタリアン共に一応肯定的であるわけです。しかしこの現状が将来どのようになっていくか、という(希望的な期待ではなく)「事実」的、客観的な予想のレベルでは、リベラルの方はおそらくこの並立が続くだろうと予想しているのに対し、コミュニタリアンは、もし適切な手を打たなければ、とりわけ積極的な政治的アクションを起こさなければ、この諸価値の並立状況は崩れていくだろう、と考えているわけです。(『「公共性」論』150-151頁)
すなわち、そこでは「リベラルな寛容だけでは社会は存立できず、誰かが政治を引き受けなければならず、政治を引き受ける主体は一定の能力や資質=徳を備えねばならない。しかし人にそのような徳の涵養を強制するとリベラリズムは死ぬ。さてどうする?」との問いが立てられた。ではその問いにはどのような回答が与えられたか?
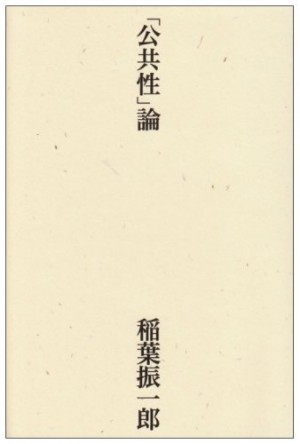
『「公共性」論』でも全体主義論の問題系は引き継がれているが、やや転形を経ている。すなわち『リベラリズムの存在証明』での「全体主義への抵抗は可能か?」という問題設定から「なぜ全体主義ではいけないのか?」という問題設定に移行している。すなわち「完璧な全体主義からは脱出不能である」として『リベラリズムの存在証明』での否定的な回答を受容したうえで、問いの立て方を変える。外側からやってくる災厄としての全体主義について考えるのではなく、我々自身が政治的に選択し実現してしまいかねないものとしての全体主義について考える、という方向に問いを転換するのである。
『「公共性」論』では藤田省三の「安楽への全体主義」などを参照しつつ「よき全体主義」が理論的には可能であることを強調した。実際ある種の功利主義の政策構想は、人々の自由意志を無視し、欺瞞を用いてまでその幸福を最大化することを容認するため、この「よき全体主義」の要件を満たしている。そこまでいかなくとも我々は公共政策やマーケティングにおいて、コミュニカティヴなやり取りを迂回して、人々を一方的に操作することを日常的になしている。全体主義とはそうした、『政治の理論』の用語法を用いるならばいわば「政治なしの統治・行政」の極限型に他ならない。
極限的に完璧な全体主義からは脱出不能である。しかしながら全体主義の可能性のスコープの中には、人々の幸福に奉仕する、少なくとも功利主義・厚生主義の観点からは必ずしも不正とは決めつけられない「よき全体主義」までもが含まれている。そのような全体主義までをも、全面否定する必要があるのだろうか?
すなわち『「公共性」論』では、『リベラリズムの存在証明』ではほぼ自明視されていた「全体主義は否定すべき悪である」という前提を疑問に付す。「よき全体主義」が可能でありその実現に意義があるのなら、『リベラリズムの存在証明』で論証された全体主義の脱出不能性も、必ずしも悪い報せであるとは限らないことになる。はたしてそれでも「全体主義は否定すべき悪である」と言えるのかどうか、我々にとって取りうる選択肢の中にそれがあるとして、それをあえて選ぶべきではない理由はあるのか?
『「公共性」論』では結局、「それでも全体主義を選ぶべきではない理由」としてまさに、その脱出不能性があげられる。いったん成立してしまえばそこから脱出できないのみならず、完璧な全体主義においては、とくに「よき全体主義」であればなおのこと、その下に生きる人々は、その体制自体に対して懐疑を抱くことさえもできなくなる。このように、人々を欺瞞の小世界に閉じ込めることになるがゆえに、たとえ完璧な「よき全体主義」であっても、我々はそれを目指すべきではない、とそこでは結論された。
そのような狭い世界の中に封じ込められた人々の不自由さを嘆くという立場は、あくまでも外在的なものかもしれない。しかしながら、そのような体制を意図的に構築し、管理する立場に立つ人々のことを考えてみよう。完璧な全体主義に対しては、その設計者・管理者は、徹頭徹尾超越的な立場から、一方的に振る舞うしかない。管理の対象たる体制下の人々に、その意図や存在を気取られようものなら、完璧な管理には隙ができてしまう。しかしそのような「政治なしの統治・行政」に徹するという生き方は、生きるに値する生であろうか?
そして今回の『政治の理論』は、「政治なしの統治・行政」とは何か、をもう少し厳密に論じたうえで、真正な意味での「政治」とは何かを論じようとしたものである。
市民社会を支えるインフラストラクチャー
本書で『政治の理論』想定されている古典的な共和主義のモデルは、ジョン・ロック『統治二論』やアリストテレス『政治学』のそれから大きく逸脱するものではない。市民社会の一人前の構成員=市民は財産と教養のある大人であり、それ以外の人々――女子供、無産者――は通常は家長たる大人の支配と保護を受ける。財産と教養ゆえに市民は他人に騙されず、強制からも自由に行動できる。そうした市民たちの自由な行動の場が市民社会である。そして、市民たちがその自由をあくまで保持したままで、共通の利益のために、共通の意志(合意)に基づいて作り上げるのが統治権力=政府である、というモデルである。
しかしこれだけでは足りない。アリストテレスの場合は当然視されてか、またロックの場合にはその歴史的条件故にか、市民社会を支えるインフラストラクチャーの話がそれほど立体的になされていない。ことにロック――そしてトマス・ホッブズ――的な、近代的なイメージでは統治権力は「法人」であり、それ自体は物理的実体を持たない抽象的存在であり、その抽象的存在が具体的に何事かをなすためにはその執行機関としての君主なり政務官なりといった身分の生身の人間が登場する、という感じであるが、物的インフラストラクチャーもまたじつは無視できない。具体的には都市の物理的構造――公道、公共広場、集会場、水道、水路――がそれにあたる。ことにアリストテレスにあっては「法人」の概念はないのだから、そこでイメージされるポリスは抽象的存在ではなく、生身の人々と都市構造物からなるもっと具体的な何かである。
もう少し踏み込むならば、ここでイメージされている共和主義の市民社会は、人間たちからのみなるわけではない。市民社会の正規のメンバーとしての市民は家長のみであるが、それを上回る数の従属民がいる。しかし重要なことは、それに加えて、市民たちの家は市民とその家人たちからのみなるのではなく、その保有する財産、家産もまたその構成要素だ、ということである。家人の一部もまた財産(奴隷)でありうるが、重要なのは土地建物であり、家畜であり、食糧などの貯えである。社会を構成しているのは人だけではなく、人とかかわりあう「物」たちもまたその構成要素である。そして同様のことが都市の物理的インフラ、公共財産についても言える。
もうひとつ、物の話をすると、物には少なくとも二種類ある。動産と不動産、ではない。同じく法学風の言い回しをするなら元物と果実、である。元物とは消費されてなくなってしまうものではない、耐久性がある物で、それを用いて果実を生み出せるものである。典型的にはまさに土地がそうだし、建物や固定資本設備として用いられる機械などもそうだ。それに対して果実とは、元物を用いて生産され、それ自体は消費される――用いられると消耗しなくなってしまうもの、だ。食糧など農作物の類、あるいは鉱物等がこれにあたる。
ついでに言うならば、果実はほとんどの場合個性を持たない「種類物」である。たとえば隣近所とお味噌やお醤油を貸し借りしたとして、同じものを返すだろうか? 何しろ消費してなくなってしまうのだから、本やCDや、あるいは車や農機具の貸し借りとは違って、具体的に同じ個体を返すということはなく、同じ種類の別のものを返すはずである。(金銭の貸借もそうだ。このような取引を消費貸借と言い、借りた当のものを返す賃貸借などとは区別する。)これに対して元物の場合には、しばしば個性が帰せられる。経済学風に言えばストックとフローの違い、と言ってもよい。
もちろん両者の区別は流動的で、たとえば倉庫に貯蔵された大量の農作物や鉱物などはフローを集積したまさしく「ストック」としての性質も持つ。あるいは建物や大型の固定資本設備なども大量のフローを投じてできたストックとしても解しうる。
それでも市民社会を大きな構造のレベルで見ていくならば、その構造を支える要となるのは、まずは市民権を有した人であり、そしてそのストックとしての財産、資産である。耐久性を帯びた固定的な資産に対して、フローとしての材料、水、燃料、種苗、肥料、そして労働を投入して、フローとしての果実を収穫する。果実の一部は貯蓄=投資されてストックに一体化するし、一部は消費される。この循環は基本的にそれぞれの市民の財産領域内で完結するが、フローは他の市民との間で取引される。
市民の自立は、この生産―消費の循環が大体において自己完結可能であること、やろうと思えばある程度までは自給自足できるということ、それゆえに、他者の干渉をはねつけることができるということによっている。もちろん市民社会においては、物をめぐっての市民同士の交流がないわけではない。しかしそれが他者への依存とはならず、自由を害さないために、市民社会では一定の条件が成り立っている。それはフローの流通がすべての市民に開かれた公共圏で行われているということ、潜在的な取引相手はたくさんいて、特定の相手に拘束されることがないということ、である。公道を通り、公共の広場に出かけて、好きな取引相手を探せるということ、取引する商品を好きに運搬できること、が重要である。川や海などへのアクセスもまた重要だ。この公共圏のインフラストラクチャーも当然ながら耐久性のあるストックたることを求められている。
現代の経済学ではストックをたかだかフローの集積としか見ず(つまり前者を後者に還元可能なものと見がち)、公共財と私的財との区別においてストック―フローの次元を無視しがちである。だが、私的財においては元物も果実もともに重要であるのに対して、公共財の本体は通常はストックである。学校での教育や病院でのケアはサービスというフローかもしれないが、それを行う施設は固定設備であり、ストックだ。それは事実として耐久性を備えているし、そのようなものとして維持されねばならないのが普通だ。
ここからさらに一歩踏み込むならば、私的に保有されている、私有財産であるような土地建物、固定設備についてはどうか? という問いが浮かび上がる。今日われわれが私有財産権の中心、その典型とみなしているものは所有権であるが、所有権には普通、「その所有の対象を意のままに処分してもよい権利」が含まれている。フロー、果実、種類物であれば、それを利用することは直ちにそれを消費し、消滅させてしまうこと、になるので、それらについて「自由な処分」が許されなければ誰でも困ってしまうだろうが、ストック性の高いものについてはどうだろうか? たとえば人は土地を消費してしまえるものだろうか? また仮にそれができたとして、それは許容されることだろうか?
むしろわかりやすいのは、広く価値を認められた芸術作品の場合であろう。我々は通常芸術作品の私有を認める。しかしながらそれが所有者による作品の自由な処分権までを含意するか、と言われれば悩むところだろう。
理念どおりの純粋な所有権、あるものを自由に使えて自由に処分できる権利、というのは案外と少なく、とくに耐久性のある物の所有権には、土地建物、不動産がわかりやすい例だが厳しい規制があるのが普通である。それでも我々が所有権の理念型、標準を「自由な使用権、自由な処分権、残余請求権」のセットに求めがちだ。「実態においては自由な使用も処分もできないが、それでも所有の本来型はそれであるし、ほとんどの場合残余請求権(*)は残る。」と。しかし、物を持つということの基本型、基準型が処分権を含む所有権ではないとしたら? 土地に対してはそもそも「処分」が考えづらいし、所有権思想が覇権を握った近代においても土地公有化論はデイヴィッド・リカードウのそれなど非社会主義的な立場からも出されている。
*「残余請求権」について簡単には以下のようにイメージしてほしい。たとえば会社の所有権たる株主の得る利益は、会社があげた収益の中から、原材料費や人件費などの費用を引き去り、さらに債権者に債務を支払った後で、それでもまだ手元に残る利益である。会社があげた収益に対しては、従業員や債権者も貢献しているわけだが、彼ら彼女らの取り分はあらかじめ決められた賃金や利息に限定されている。従業員や債権者は、そうやってリスクから保護されている反面、予想外の利益にあずかることはできない。それはもっぱら所有者たる株主の取り分である。
非常に極端な立場として、耐久性を備えた物については所有権が成り立たず、それを処分する――とりわけ毀損し破壊する権利は誰にもないのが基本で、例外的にのみ処分権が認められる、という体制について想像してみよう(ひょっとして現在のわれわれもここから思ったほどは遠くないのかもしれないが)。物に対する権利の基本型は所有ではなく占有ということになるのだろうか。この場合、人は通常、ある物を独占的に利用しそこからの利益を引き出せる権利はあっても、処分する、とりわけ破壊する権利はない。逆に言えばそれを維持する義務さえもそこに読み込める、ということにさえなりかねない。
我々の常識の中では公共財も普通は国なりその他の公共団体という法人の財産であり、その所有権者に処分権があることが多い。ある場合には行政の自由裁量により、また別の場合には議会の立法、決議によってそれが売り払われたり、破棄、破壊されたり、ということは普通にある。しかしながら公共財、公共の財産の基本型、理念型はどちらだろうか?
重要なことは、古代の都市国家においても、近代的な国家や会社などの法人においても、公共の財産は政治共同体みんなのものではあるが、その「みんな」とは現に生きていて等の国家なり共同体なりを今現実に構成するメンバーだけではなく、可能的なメンバーまでをも含んでしまう、ということだ。つまりはやがて生まれてくるかもしれない将来世代とか、他国から訪れて帰化して市民となる外国人とかまでをも。つまりそれは「みんな」のものだがみんなの恣意によって処分はできない、ということになる。
市民を含めて生身の人間は生まれてきては死んでいく、有限な存在である。永続的な構造として都市、市民社会、国家を支えるのは、短命な個人以上に家であり、その家が継承する財産であり、公共圏を支える都市インフラである。
ハンナ・アレントやカール・シュミットがやや大げさに言ったのは、ギリシアにおける法nomosとはまずはこうした構造、土地を中心とする私有財産が、公道や広場によって互いに隔てられつつも結び付けられる、という構造のことである、ということだ。境界とは、ひとつのものを二つ以上に分かち、分かたれたものたちを互いに隔てる構造である反面、分かたれたものたちを無関係なものとして切り離すのではなく、互いに結び付ける構造でもある。言葉による法はその上に、それを明確化し、それでは足りないものを補うというかたちで出来上がった、と。都市国家ではなくより広大な領域国家に生きる近代人ロックの場合には、都市インフラへの視点は欠けており、その分法は抽象的となり、政府・国家も観念的構築物としての法人として捉えられているが、財産の基本型が土地であることは明確に押さえられている。

近代において共和主義を再考する
さて、ここから近代に移り、近代的な共和主義というものを構想してみたときに、何が問題となるのか?
重要な問題は、市場経済が大規模となり、経済学風に言えば「競争的」となって、取引相手の具体的なアイデンティティが失われ、各市民はただ相場に受動的に適応するのが普通、という風になってしまう、ということだ。平の市民同士の交流、取引は「政治」とはみなされなくなり、明示的に共同的な意思決定である国家レベルの管理ばかりが「政治」とみなされるようになる。しかし実際には国家より下位レベルの地方自治体はもちろん、市民同士の組合や法人も、相対的に少人数で顔の見える関係の中、双方向的なコミュニケーションを通じて意思決定、運営がなされる限り、本当はそこもまた「政治」の場なのではあるが。だがいずれにせよ、大規模化に伴い、市民社会が脱政治化されていく傾向がある。
今一つの重要な問題は、産業革命以降の技術革新の常態化である。新しい技術が次々に生まれ、古い技術が陳腐化していく中で、フローとストック、単なる商品と資産、本来的な意味での財産との差異はどんどん見失われていく。ここで逆説的にも土地は強さを発揮するが、それでも昔日の農地としての存在感は薄れるばかりである。まして、直接に市場の取引から保護されるものであったはずの財産が、どんどん市場に引きずり出されていく。土地の生産物だけではなく、土地そのものが賃貸借の対象となり、時には丸ごと売り買いされる商品にさえなっていく。同様のことは資本についても言える。
このようなありよう、つまりは資本主義化は、悪いことばかりではない。商品化、市場化の波はほかならぬ労働にもどんどん及んでくる。これはどういうことかと言えば、雇用や小作というかたちで無産者も経済的自立をはかることが容易になる、ということだ。無産者も市民の家に丸抱えになることなく、市場を介して仕事をすれば、独立性を保つことができる。ただ問題は有産者の場合に比べて、やはりどうしても市場における交渉力が弱くなることだ。
有産者の場合、財産の蓄えがあるので、自給自足とはいかないまでも、短期的には市場から撤退して持ちこたえることもできるが、無産者の場合はそれが極めて困難となる。また無産者の場合、自己の能力を高める人的投資にせよ、あるいは資本財や土地を購入する物的投資にせよ、資本信用=長期借り入れに依存する度合が高くなる。長期的な取引は競争的市場を介した短期的なそれと比べて属人的となり、特定の取引相手への依存度がどうしても高くなってしまう。同様のことは小作や雇用関係の場合にもしばしば当てはまる。
身一つの雇用労働において、特定の雇い主に従属することなく、競争的市場の恩恵を存分に受けられるケースは、実質的に有産者と言える高度な――技術革新の先端と同レベルで付き合える――専門職(典型的には医師)か、あるいは単純労働の日雇い、パートタイムかの両極のケースであり、中間においては人的投資のために特定の職場、特定の雇い主へのコミットメントが避けがたくなる場合が多いのである。中途半端な専門職は技術革新によって技能が陳腐化する恐れが高い。
近代的な共和主義は、以上のような状況を踏まえて、自立した有産者の市民社会を目指すことになる。ここで我々が「リベラルな共和主義」と呼ぶのはその一バージョンである。
近代において共和主義を再考するとしたら、大まかに言って二通りの戦略が考えられる。第一は、古典的共和主義と同様に、有産者の寡頭的な合議政治の樹立を考えるエリート主義的構想。第二は、市場経済が社会全体を覆い、無産者までをも巻き込んだ現状を踏まえて、無産者の実質的(擬制的なそれも含む)有産者化を目指す構想であり、こちらが「リベラルな共和主義」である。
リベラルな共和主義は当然ながらリベラル・デモクラシーの一バージョンだが、リベラル・デモクラシー一般に比べて福祉国家的再分配を、単なるフローとしての所得保障ではなく、擬制的なストックとして機能するような支援を無産者に付与するようなかたちで行い、かつ能動的政治参加を促進するという点において異なる。またリベラルな共和主義は主権国家のみをターゲットとするのではなく、営利企業を含めたあらゆる法人における、自由な討議に基づくガバナンスを求める。コーポレートガバナンスと労使関係はとりわけ重要な意味を持つ。
みんなが資本家である資本主義
少し言い方を変えるならば、「リベラルな共和主義」が目指している市民社会のかたちは、「みんなが資本家である資本主義」である。この観点から、拙著『不平等との闘い』をいわば『政治の理論』における「リベラルな共和主義」の前提条件についての議論として読み替えることもできる。
『不平等との闘い』は直接には共和主義の問題を取り上げてはいない。それどころかそこではただ単に私的所有制度と市場経済が成り立っているだけではなく、その市場経済は十分に競争的である、つまりそこには政治の余地はないものとして議論が展開されている。もちろん『不平等との闘い』の議論が政治を否定するわけではない。後半では福祉国家的再分配の議論を提示しているし、のみならず競争的市場経済の外側に公共財が存在していて、その配分をめぐって「政治」が登場してくる可能性ももちろん排除してはいない。しかしその主題としての持続的経済成長の基盤は、あくまでも競争的市場メカニズムとして描かれている。
しかしながらそこでは、競争的市場の下での経済成長が、分配、しかもフローとしての所得だけではなく、ストックとしての資本の分配にどのような影響を及ぼすか、が論じられている。そしてそこでの議論は「みんなが資本家である資本主義」の可能性を排除してはいないのだ。
復習するならば、『不平等との闘い』ではスミス、リカードウ、そしてマルクスにいたるいわゆる「古典派経済学」の枠組みの下では、経済成長の主体はあくまでも資本家であり、所得分配が賃金労働者に対して有利に、資本家に対して不利になれば、投資の原資が減り、その分経済成長、長期的な総生産に対してマイナスとなると結論される、と論じられた。すなわち、分配と生産・成長とは不可分であり、分配が資本家にとって有利であればあるほど成長にも有利である、と。
それに対して我々の解釈では、19世紀末以降の新古典派経済学では、古典派とは異なり、(1)資本市場が発展する――銀行を媒介とした信用機構が長期的な資本信用にまで及ぶ、また株式市場も発展する――、(2)投資の対象が物的資本設備のみならず、人的資本、労働者の知識や技能にまで及ぶ、(3)労働者の所得水準が向上する、といった条件の成立が想定され、そこから賃金労働者もまた、金融機関に貯蓄を行うことによって、また教育を受けることによって、投資の主体となる、という可能性が射程に入ってくる。
こうした議論は、理論的に言えば、分配と生産・成長の切断を可能にする。十分に効率的な金融市場が存在すれば、所得・富の分配と生産力、成長とは無関係である。社会のなかの富、生産手段の分配が平等であろうが不平等であろうが、資本市場はそれを効率的に活用して、最大限可能な成長を実現できる。新古典派の議論にはそのような含意がある。
これは言ってみれば両義的な含意を持つ。一方では分配と成長は分離可能であるから、古典派の議論とは異なり、新古典派の枠組みに則れば、分配の平等化は何ら生産、成長を阻害しない。しかし逆に言うと、それは古典派の場合とは異なり、分配問題に対する関心を経済学者の間から奪う効果をも持ったとも考えられる。
しかしながらより精密に見ていくと、新古典派の枠組みの下でも、成長と分配との関係はじつは一筋縄ではいかない。新古典派の成長モデルにおいては、基本的な経済主体の時間の中でのありようを念頭において、大まかに言って二通りのタイプのモデルがある。ラムゼイ・モデルと呼ばれるものは、あたかも永遠に生きて、無限の寿命のなかでの自己利益の最大化を目指して長期的意思決定を行い、行動する主体を主人公とする。この場合、貯蓄=投資行動は永い生涯の中で時々刻々と変化していく。
それに対して、もう一つのモデルは重複世代(OLG)モデルと呼ばれ、有限な寿命を生き、世代交代していく主体たちを主人公とするモデルである。このモデルの特徴は、ラムゼイ・モデルの場合と異なり、第一に競争的市場の下での主体の合理的行動が、完全雇用、可能な最高の成長率を普通は下回ってしまう、ということであり、第二に、代表的な設定の下では、貯蓄率=投資率が世代を超え、長い時間の中でずっと一定不変のままとなる、という点である。念のために付言しておくならば、その解釈には注意が必要だが、従来の統計的研究の示唆するところでは、現実の経済における長期的な貯蓄率は、一定不変とは言わないまでもかなり安定している。
『不平等との闘い』における我々の作業の結果見えてきたのは、競争的市場、とりわけ資本市場がきちんと機能している市場経済を前提とすると、貯蓄率が時間の中で変動していくラムゼイ・モデルにおいては、経済成長の過程の中で、人々の間の富、資産の分配は不変である。手元に使いきれない資本を持ち合わせた人は、それを他人に貸し出し、資本が足りない人は他人から借り入れ、経済の中に存在するすべての資本は無駄なく利用される。しかしながら当然、貸し出される資本は、利子をつけて返却せねばならない。この利子の作用によって、富める者と貧しい者との間で、資本は貸し借りされつつも、結局その所有は移動せず、富める者は富めるまま、貧しい者は貧しいままである。ところがこれに対して、貯蓄率が長期的に一定のOLGモデルにおいては、世代を経るうちに資産格差がだんだんと縮小していく。
きわめて単純で抽象的なモデルの解釈には注意が必要だが、あえて踏み込んだ解釈を行うならば、不確実性のない(このモデルではそこが重要)市場経済においては、格差を縮小する力はとくにはたらいていない一方、増幅する力もはたらいていないように見える。その一方で世代を超えた貯蓄=遺産の力は、それを超えた格差の縮小効果を持つのかもしれない。というあたりだろうか。しかしいうまでもなく、ここに「不確実性」という要因を放り込むと、どうなるかはわからない。
それでも、古典派的な「分配が改善すると成長率は低下する」という展望は、新古典派の下では否定されたと言えるだろう。少なくとも「成長を維持しながら分配を改善する可能性はないわけではない」くらいまではいえるかもしれない。
もう少し踏み込むならば、古典派の、そしてとりわけマルクスの考えでは、本格的な資本主義経済はビジネスの、生産の単位としての企業の規模を大きくするため、その意味でも持てる資本家と持たざる労働者の間の格差の存在は、生産の拡大、成長にとってプラスになる、という議論に行かざるを得なかった。
しかしながらそのような発想は、リカードウやマルクスが産業革命以降の機械制大工業に注目し、のみならずそれが労働を代替し、失業を生み出す可能性まで指摘していたにもかかわらず、ある意味スミス的なマニュファクチャーの世界から彼らの想像力があまり外に出られなかったことを示しているのかもしれない。労働が機械によって代替されることは、労働需要を減らし、失業を増やすが、長期的にはそれに反応して労働供給、労働者人口をも減らしていく。その延長上に「みんなが資本家である資本主義」を展望することは、あながち無意味でもない。
興味深くも厄介なことはもちろん、『不平等との闘い』後半で説明したように、以上の考察はまだ技術変化と生産性上昇を考慮に入れず、長期的には最適水準で成長がストップしてしまうモデルをもちいてのものである、ということだ。技術革新による生産性向上、ひいては持続的な経済成長を組み込んだモデルはなかなか難しい。『不平等との闘い』で取り上げたのは一番素朴な、投資にネットワーク外部性が存在するケースである。典型的には知識や情報技術がその例としてあげられる。
たとえば技術的な知識は、それを体得して使いこなすことで、それを知らないライバルよりも生産性を上げ、抜きんでることを個別の経済主体にとって可能とします。そうであれば、個々人、個々の企業にしてみれば、自分だけが持っている知識、技術を自分だけのものとして秘匿しておきたくなるでしょう。しかしながらそうした知識、技術を独占し続けておくことができず、社会全体に知れ渡り共有されてしまったら、公益の観点からはともかく、元の独占者は損をするばかりでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。
もちろんライバルよりもぬきんでて相対的に有利なポジションを獲得することはもはやできないかもしれません。しかしその知識・技術が汎用性に富んでいて、自分の業界以外にも広く利用されうるようなものだった場合には、どうでしょうか? 知識を独占してライバルよりも良いものをより安く売りつけることはもはやできなくなったかもしれません。その場合、生産者・売り手としては元独占者は損をしたことになります。
しかし漏れ出た知識が狭い業界を超えて他の産業でも威力を発揮し、より良いものをより安く作ることに貢献していたとしましょう。そうなると生産者・売り手としては損をしていた元独占者も、消費者・買い手としては得をするわけです。そして知識・技術の汎用性がとても高ければ、得は損を上回るでしょう。こうしたスピルオーバー効果は、最も根本的なレベルでは「読み書きそろばん」、つまり初等中等教育レベルの識字能力、基礎学力について強調されますが、言うまでもなくさまざまな技術標準について考えると分かりやすいでしょう。(『不平等との闘い』174-175頁。)
ここではかつての古典派とも、標準的な新古典派とも異なり、資産の分配が平等であった方が生産性の上昇率、ひいては経済成長率が高くなる可能性が指摘されている。
単純にまとめるなら、古典派の想定する世界では、資本市場が不完全であるため、投資は資本家が主役になるしかなく、分配が平等化すれば資本家の投資が低下し、ひいては成長率も下がる。それに対して初期の新古典派においては、資本市場が発達し、また全体としての生産力が上がるため、労働者も投資の主役となりうる。そこでは分配がどうあろうと、市場が効率的にはたらいて最大限の生産と成長を実現する。
しかし20世紀末以降の新しい成長理論は、さらに異様な展望を示す。知識の交流が活発な社会においては、投資はネットワーク的外部性を発揮して、持続的な技術革新と経済成長を引き起こす。のみならずそこでは、資本の分配が平等であればあるほど、ネットワーク外部性の効果で生産性は上昇し、成長率は高くなる。論者によってはそこでの投資の主体はもはや物的投資よりも人的投資である、とさえ主張する。
以上をまとめるならば、『不平等との闘い』の立論は、「リベラルな共和主義」の基盤としての「みんなが資本家である資本主義」は自然にできあがるものではないが、実現不能と言うわけでもないし、またそれが成立することは望ましい程度のことは言える、となるだろう。
しかしながらそこで話を終わらせるわけにはいかない。『政治の理論』では、標準的な経済学の枠をあえて踏み越えないようにした『不平等との闘い』とは異なり、市場経済における不確実性や非対称性の議論にまで踏み込んでいるからだ。
市民社会にとって「諸刃の剣」である金融システム
「リベラルな共和主義」などという構想を提示するのは、「自由人による自由な政治」としての共和主義は、政治の主体として「財産と教養のある市民」を想定するので、その要件を満たさない人々はそこから排除されざるを得ないからである。これは狭い意味での「政治」、公共政策をめぐる決定への参加の問題に限定される話ではない。市民社会における私的な活動のレベルにおいても、「財産と教養」がなければ、人々に残された自由は、たかだか「他人にいいように操作されない自由」にとどまり(それも市場が競争的である限りにおいて)、自らのイニシャティブで事業を起こす自由はない。だから我々の「リベラルな共和主義」構想にとって「みんなが資本家である資本主義」の成否の可能性は死活問題である。
しかしながら「みんなが資本家である資本主義」の実現可能性は低くはあってもゼロではない、としたところで、それで問題が――とりわけ『不平等との闘い』が示唆するような、順調な経済成長の結果として(むろん「自然に」「成り行き」のままに)実現するなどとは思えないということを措いても――なくなるわけではない。
問題は「金融市場」「資本取引」にある。ここまであっさりと「資本市場」と書いてきたが、これがじつに曲者である。一口に「資本の取引」と言っても具体的な様態はさまざまである。たとえば土地建物を借りて、その対価として地代・家賃を払うような場合には、即金での売買とそれほど違いがあるわけではない。しかしながらこのような賃貸借取引がそのすべてではない。
人々はすでにある土地建物や固定資本設備を借りるだけではない。丸ごと買うこともあるし、あるいはいまだない固定資本設備を作り上げることも多い。問題はそこで、プランやアイディアはあっても金が――財産がない場合にはどうするか? いうまでもなく人々はここで、不足する資金を借り入れる。しかし『政治の理論』で散々論じたように、同じ「貸借」という言葉を用いてはいても、元物の賃貸借と、果実の消費貸借とは、じつは互いに極めて異質である。やや長くなるが、説明しよう。
経済学的な思考は、売買、より正確に言えば同時交換を基準として取引を考える、だから「雇用」という売買とは異なるカテゴリーの取引を「労働力商品の売買」だなどと言ってしまえるのである。この考え方だと前者、元物、土地や資本財などのまとまった資産の貸借は「土地や資本財を、一定の時間決めで利用する権利の売買」とイメージされる。この「賃貸借と売買の間に本質的な相違はない」というイメージを支えるのが、ひとつには賃料と利用の交換が同時――とは言わないまでも時差が少ないことである。
土地や家でもよいが、もっと気楽に、レンタルビデオ屋でビデオ、現在ならDVDやBDを借りることを考えよう。(これらは少額だが個性も耐久性もあり、「元物」としての性格が強い。)我々はビデオ屋で普通事前にレンタル料を払い、ディスクを持ち帰る。この支払と受け取りの同時性が「売買」イメージの基となる。もちろんこれはディスクそのものの売買ではなく、ディスクの所有権は移転しない。定められた期間内に、その同じディスクが返却されねばならない。だが、その期間が過ぎるまでは、借り手はディスクを占有して、それを破壊したり毀損したりしない限りで、それを使用する権利を持つ。小難しく言うとここには双務的関係がある。貸しても借りても、互いに義務を負い合い、互いの権利を保証し合っている。
これが消費貸借の場合は異なる。隣の家から味噌や醤油を「借りる」のであれ、消費者ローンからお金を「借りる」のであれ、そこではじつはレンタルビデオや家を「借りる」のとは質的に異なることが起きている。そこで貸し借りされているものは個性のない種類物であり、なおかつ、使用すると消えてしまう、消費の対象である。ストックではなくフローだ。だから味噌や醤油であれ、お金であれ、それを「返す」ときには、レンタルビデオや家とは異なり、厳密に同一のものを「返す」のではない。同じ種類のものを同じ量、そしてしばしば利息をつけたして「返す」のである。
この場合貸し手は、貸した後ではもう貸したものに対する使用権はおろか、所有権も失ってしまっている。これはビデオや家の場合のような賃貸借とは根本的に異なる。そして借り手の方は、借りたものをただ単に占有し使用するのではない。使えばなくなってしまうものだから、借り手は借りたものを(消費するまでは)所有しているのである。(自由な処分権があり、そして普通は処分してしまう。)そう考えるしかない。しかしいうまでもなくそれで話は終わらずに、同じ種類のものを同量(以上)返す義務が生じる。いわばその義務と引き換えに、所有権が移転されたのである。
ここでは元物の賃貸借とは異なり、片務的な関係が生じている。借金の取り立ての場合を考えるならば、むろん債権者、貸し手は、返済期限が来るまでは取り立てを差し控える義務がある、と言ってよいかもしれないし、債務者、借り手はその間催促を受けない権利がある、と言えるかもしれない。しかし返済期限を過ぎてしまえばどうなるか? そこではもはや貸し手は一方的に借り手に対して返済を迫る権利を有し、特段の義務は負わない。一方借り手は、返済する義務だけを負い、貸し手に対して特段の権利を有さない。
むろん元物の賃貸借の場合にも、期限までに貸したものを返さない延滞が生じれば、貸し手は一方的に返却を迫る権利を有し、借り手は借りたものを占有する権利を失ってただ返却義務を負うだけになるだろう。ただこちらの場合には、借りたものを毀損していない限り、とりあえず返却すれば、借り手は最低限の義務は果たしたことになる。貸し手の方でも、「借りたものを返せ」以上のことは言えないし、言う必要もない。貸したものは貸している間も、相変わらず貸し手の所有の基にあることははっきりしている、つまり貸し手の領分と借り手の領分との間の線引きは明確である。
しかしながら消費貸借においては、この線引きが不明確になってしまうのである。消費貸借においては、貸したものは消費し、消滅する。だからこうした消費財となる種類物においては、占有と所有の区別がなされないことが多い。ではそうやって、借りたものがすっかり借り手の所有物となるから、借り手の立場が強くなるかというとそうではない。その反対である。線引きのあいまいさが、かえって際限のない貸し手による介入を生む。
賃貸借においては、貸し手としては何を取り戻せばよいかがはっきりしており、反対に言えばそれ以上のことを求めるのは越権の疑いが強くなり、貸し手の自制も、借り手の抵抗も強固となる。しかし消費貸借の場合には関係が不透明となる。貸したものは借り手の領分に埋没して、その意に反して取り返すことは難しい。逆に言えば、消費貸借が安定的に行われるためには、貸し手の側が借り手の私的な領分に介入して、強制的にふるまうという仕組みがあった方が望ましいことになる。
これは今風に言えば「モラルハザード」の問題だ。自然環境のせいであれ、借り手の能力や誠意にのせいであれ、借り手がきちんと返済してくれるかどうか不確実な状況においては、貸し手は何らかの手段で以て借り手が誠実に債務を履行してくれるよう、誘導する仕組みを作りがちである。貸し手は借り手に対してある程度一方的な権力者としてふるまう仕組みが確立しなければ、安心して貸出取引に乗り出せない。
こうした関係、信用取引を通じた支配関係は、歴史上きわめて一般的によく見られるものであることは言うまでもない。狭い意味での金融機関を介したもののみならず、農業における地主小作関係、製造業・商業における問屋制、下請制においても、信用取引は本質的な機能を果たし、そこで地主や問屋は信用を与えることによって小生産者たちをコントロールしている。
確認しておくが、共和主義のヴィジョンはこのような信用取引に潜む権力性を克服するためのオルタナティブな仕組みとして、そもそも信用取引に過度に依存せずに済む程度に、人々が十分な財産を以て自立すること、そのような存在として互いに対等となること、を求めるわけである。
しかしその代価として、自立できない人々は取引から排除される。それでは無産者はいつまでたっても浮かばれない。ここで大規模な再分配政策による平等化などが期待できないとなったら、無産者が有産者になるためには、やはり危険を承知で大規模な資金借り入れに頼らざるを得ない。その意味で、「リベラルな共和主義」構想においては、信用取引に内在する危険にもかかわらず、それを全面否定することはできない。
とはいえ、やはり信用取引は極めて危険な仕組みである。債務者は、うまくいけば完済後でも財産が十分に残り、有産者に成り上がることができる一方で、いつまでも返済が終わらずに、債権者に従属し続ける可能性も無視できない。というより、我々が知る小作制度の歴史とは、後者のケースがむしろ多いことを示唆するのではないか。また、信用取引の世界では有産者もまた完全に安泰というわけではなく、借財を返済し損ねてもともとの資産自体を利子によって食いつぶされ、零落する危険にさらされることになる。
金融システムは市民社会にとって、「諸刃の剣」であり内在的なリスクとして考えられねばならない。無産者を再分配や資産形成支援を通じて有産者に転化させるのみならず、有産者の無産者への転落を防ぐためのインフラストラクチャーが重要となる。これはいわゆるプロセス憲法理論の発想を、国家レベルでの参政権を中軸とするものから、市民社会レベルの市民的権利を中軸とするものへと延長し組み替える発想として考えていただいてもよい。
現代憲法学というか、近代立憲主義においては、民主政治に対する憲法的制約の中核に人権という原理がある、とはよく言われるが、この「人権」とはそもそも何か、については諸説ある。有力な考え方の方向性としては、ひとつには、人権原理を民主主義とは別物、別個のものと考え、立憲的制約を「人権保障の法的メカニズムが民主政治に対して外側からタガをはめる」ようなものだ、と理解する考え方がある。
そしてもうひとつは、人権を民主主義に外在的なもの、民主主義とは別個のものとしては考えず、民主政治の基本的な構成要素、ビルディング・ブロックとして考える、という発想に立ち、立憲的制約を、民主主義の自己破壊、民主的決定が結果的に自己の存立基盤を掘り崩し、自壊してしまうことがないように防ぐ仕組みである、と考える。いわゆるプロセス的憲法理論はこれにあたる。
前者の考え方は、ホッブズ、ロック流の古典的な社会契約理論と馴染みやすい。国家に対して市民社会が先行していて、市民社会の基本ルールとして人権を捉え、国家は市民社会に奉仕する機関として捉えられ、その作動範囲は市民社会の基本原理としての人権によって限界づけられる、というヴィジョンである。そこでの人権は言ってみれば政治以前、国家以前のものとして考えられており、どちらかと言えば私的な自由がより基層のレベルに位置付けられて、その上に政治的権利が上乗せされる、という結構だ。このイメージは権力分立論、司法権の独立論との相性も良い。
それに対してプロセス憲法理論などの後者では、人権は民主的機関としての国家を運営する基本ルールとして捉えられ、その中心はむしろ政治的権利の方になる。前者がともすれば司法優位の憲法観になるのに対して、こちらはあくまで立法、政治的決定中心の憲法観である。
それに対して「リベラルな共和主義」の提示する構想は、あえて国家中心か市民社会中心かと言えば、市民社会中心の発想をとるが、そこでの権利観はプロセス的である。市民社会のなかでの自由な市民の行動は、結果的に自己破壊的な、市民的自由を掘り崩し、市民社会の秩序を崩壊させるような結果にも結び付きかねない。具体的には、市場での競争の中で、一部の市民が財産を失って零落する、といったかたちで。
それゆえ市民社会は、人々の市民的権利が掘り崩されないようなセーフガードを必要とする。リベラルな共和主義においてはそれは生存権保障に加えて、ある程度の財産までをも人々に割り当てる再分配政策を含まざるを得ない。しかしその本旨は自由な市場の活動を制限することであるよりは、市場の自由が万人によって十分に享受できるための条件を整えるところにある。
またそこでは、司法手続、裁判というものについての考え方も特徴的なものとなる。すなわち裁判という仕組みが裁判官中心にではなく、訴訟当事者中心にとらえられる。陪審制度までを含みこめば一層明らかとなるが、そこでは訴訟は裁判官による意思決定ではなく、訴訟当事者同士の闘争と交渉、つまりは一種の合議として理解されるのである。
「人間改造」という人的投資
ここまで『不平等の闘い』と『政治の理論』の接続についてみてきたが、今度は『宇宙倫理学入門』との接続についても考えてみたい。
『不平等との闘い』では「成長が格差をなくす」という楽観論は肯定されなかったが、「格差の主因は成長率の差であり、社会全体での成長の持続なしには格差の縮小は難しい」とまでは論じられた。そのような格差の解消――とは言えぬまでも、格差が縮小し、(失業して飢えて死ぬという「ジェノサイド」なしに)無産者が存在しなくなり、誰もが有産者となるような社会の成立が、我々が『政治の理論』で提示した「リベラルな共和主義」が成り立つための前提条件の一つである。
しかしながら、際限ない経済成長が一体何を意味するのか、それははたして可能なのかどうか? という疑問は、ローマ・クラブ以降、『成長の限界』以降の我々にとって、どうしようもなく避けがたい問題である。
この問題についてはすでに、『経済学という教養』の文庫増補版の補章で簡単に論じてあるが、そこでの暫定的結論は、いまとなってみれば『不平等との闘い』の煮え切らないそれと非常に似通ったものであった。すなわち、「成長なくしては技術革新はなく、技術革新なくしては環境に対してそれほど破壊的ではない技術の開発もできない。『経済成長が環境を守る』とは到底言えないが、(生産性上昇という意味での)経済成長なしには、自然環境を守ることはじつは難しい」と。
純然たる理屈でいえば、経済成長と環境破壊との間に必然的な関係はない、とさえ言える。そもそも我々が経済成長に求めるものは、人間の効用が増加することであって、貨幣の量が増えることではないのはもちろん、人間一人が利用できるエネルギーや物資の量やバラエティが増えることそれ自体でもない。理屈でいえば、経済成長の尺度は貨幣ではなく、さりとて消費されるエネルギーの量でもなく、人間が享受する効用である。
しかしながら現在の経済学などにおいて支配的な考え方の下では、効用はひどく個人的なもので、同じ個人のレベルで「昨日より今日が幸せ」ということはできても、「AさんよりBさんの方が幸せ」ということは厳密にはできない(異なる個人間での効用は比較できない)、と普通されている。だから我々は公共政策では「効用」という尺度は用いず、「GDP」といったお金で換算した尺度を用いるのだが、それでも通常我々は、厳密な意味での貨幣ベースでの「名目GDP」ではなく、物価の変化を考慮した数字である「実質GDP」を用いることで、少しでも「効用」に近づこうとする。
それでも、人間が生物学的、物理学的な存在である限り、生物学、物理学の影響を受ける。それは当然に、一定の環境の中でのみ生存していける、という意味で自然環境の保全を求めるということでもあるが、また生物学的な代謝を行い、エネルギー、物質を消費せずしては存続できない、ということでもある。効用を生み出すにはどうしてもエネルギー・物質が必要である。その利用をどんどん効率的にすることはできるだろうが、ゼロにすることはできない。どこかで、物理学の法則が制限をかけてくるのではないだろうか? となれば、地球という物理学的に見て閉鎖性が強い有限の系の中での存続を前提とする限り、人間の社会にとって経済成長には、超長期的に見れば限界があるのではないか?
『宇宙倫理学入門』は以上の難問に対して「宇宙というフロンティアがある!」という回答を提示したものでは全くない。この著作での暫定的回答は「少なくとも今までと同じ生物学的身体を備えたままでは、人間は宇宙、地球外の空間や他天体を生存圏とすることは極めて困難で割に合わないだろう」というものだ。むしろ問題はここでの「今までと同じ生物学的身体を備えたままでは」という但し書きにある。
古くは多くのSF作家たちが想像し、のちにはフリーマン・ダイソンをはじめとする科学者たちまでがまじめに検討の俎上に載せ始めたように、地球外の環境に適応可能なかたちに自己を改造した人間たち(もちろん人間だけではなく、改造人間の生存を支える改造生物からなる改造生態系も必要だが)ならば、地球外宇宙に植民していくことも可能なのではないか、と考えられる。
さらに言えばこの、改造人間の可能性は、何も宇宙進出、宇宙空間のためにのみ行われる、と考える必要はないのである。むしろ我々が想像すべきは、有限な地球環境の制約に適応すべく、より効率的な工業技術の開発に邁進する人々が、ついには人間の身体そのものの改造に乗り出し、より効率的にエネルギー・物質代謝を行い、より少ない資源で、より少ない地球環境への負荷で生存できる改造人間を作り出していく、という可能性であろう。
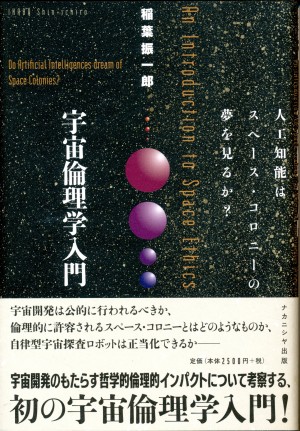
さて、このような人間改造は、経済学的に見て――というと口幅ったいが、我々のここまでの考察とどのように接続されうるだろうか? 「持続的経済成長が追求された挙句に行きつく果て」として、外部環境の改造のみならず、内部環境――人間的自然そのものの開発、改造に乗り出す、という方向性は、じつはすでにある程度は踏み出されている、というべきだろう。生命倫理学のいうところの「ヒューマンエンハンスメント」とはそういうことである。
ここで考えてみよう。こうした人間改造にも、当然にコストがかかるし、リスクもある。コスト、リスクとそこから得られる利益が、様々な立場から勘案されつつ、ものごとは進んでいくだろう。その意味ではこれもまた、人間の経済活動の延長線上にある。経済学の観点からは教育が人的投資とみなされるように、こうした人間改造もまた投資行為に他ならない。
さてそう考えるならば、いろいろと興味深い――しかし現実の課題として全面化すれば相当に厄介な問題系が浮上してくる。我々が教育を投資と考えることに対してなにがしかのためらいを覚えるのは、何も古典的なヒューマニズムからのみ来るのではない。人的投資の結果としての人間の知識や能力を「人的資本」とみなすことが誤りだと言いたいわけではない。
しかし少し考えてみればわかるように、「人的資本」は所有の対象ではない。その「持ち主」の人間から切り離せるものではない。物的資本ならば、先に小作制や問屋制に触れたときに示唆したごとく、あるいは現代の「ファイナンス・リース」といった業態に見る如く、賃貸借で取引することができるが、人的資本は賃貸借することはできない。資金を消費貸借のかたちで借り入れるしかない。同じ消費貸借による物的資本購入の場合には、住宅ローンが典型的に示すように、返済が滞れば当の資本財を差し押さえれば、取引の行き詰まりは解消できる。しかしながら、人的資本の場合にはそうはいかない。差し押さえるべきものがそこにはない。むろん、奴隷制度を容認すれば話は別だが。
教育訓練が開示するこうした問題系は、よりテクノロジカルにあからさまな人間改造をめぐる取引においては、はるかに厄介で興味深い問題を引き起こさずにはいまい。
我々は『不平等との闘い』において、近年の経済学において、格差を引き起こす主因としては物的資本の格差以上に人的資本の格差が重要になってきているのでは、という見解が影響力を持つようになってきたことを見た。『21世紀の資本』にいたるトマ・ピケティの仕事は、そうした見解に対して「いや、物的資本も今なお重要である」と実証を踏まえて提起したところにあるが、もはや教育とは呼び難い、よりあからさまな「人間改造」という人的投資は、従来の人的資本と物的資本の区別――それさえもじつは十分に明確なものではないのだが――をあっさりと踏み越える問題領域を切り開いてしまうかもしれない。
プロフィール

稲葉振一郎
1963年生まれ。明治学院大学社会学部社会学科教授。専門は社会哲学。著作『社会学入門』(NHK出版)、『オタクの遺伝子』(太田出版)など多数。


