2014.04.04

デザイン志向のサイエンスコミュニケーション――科学と社会を対話で繋げるSYNAPSE Lab.とは?
研究者を中心に、社会、環境、アート、デザイン、建築、メディアなど専門分野の枠組みを越え、イベントの開催やフリーペーパーの発行などを行っているSYNPASE Lab.。研究者、編集者、デザイナーが対等な立場となり、音楽家や建築家、フードデザイナーなど様々な他領域と融け合いながら、一方的に答えを押し付けるのではない科学の営みを伝えるSYNAPSE projectについて、メンバーであり研究者の飯島和樹さん、菅野康太さん、編集・ライターの塚田有那さんにお話をうかがった。(聞き手・構成/金子昂)
※本インタビューをきっかけに、SYNAPSE Lab.とコラボレーションすることになりました。詳細は記事末尾にて。
大学の研究や学問の魅力を伝える
―― 最初に簡単に自己紹介をお願いしたいいたします。また、SYNAPSE projectをご存じない読者のために、SYNAPSE Lab.がどういった団体なのか、どんな活動をされてきたのかをお話ください。
菅野 菅野康太です。日本学術振興会特別研究員PDで、専門は行動神経内分泌学です。いまは麻布大学で研究を行っています。
飯島 日本学術振興会特別研究員PDで、言語や道徳の認知神経科学や心の哲学を研究しています。飯島和樹です。2014年4月に玉川大学の研究室へ移籍したところです。
塚田 塚田有那です。編集やライター、イベントの企画などを行っています。
菅野 SYNAPSEは、研究者を中心として、大学の研究や学問をひとつのコンテンツとしてとらえ、その魅力を多くの人びとに届けるために、社会、環境、アート、メディアなどそれぞれの専門分野の枠組みをこえたイベントや出版を行っている任意団体です。一応、活動の総称をSYNAPSE project、団体名をSYNAPSE Lab.としています。これまでにフリーペーパーを2冊、イベントを6度ほど開いています。
たとえば最初にわれわれが制作した「SYNAPSE Vol.01」は、「パターン・カタチ・リズム」をテーマに、脳神経科学者の坂井克之さんと音楽家の高木正勝さんの対談や、神経科学を研究されている池谷裕二さん、他にも鉱物学や建築、科学技術史、発達遺伝学などさまざまな専門家の方に、「美しいカタチ」について語っていただいたフリーペーパーです。
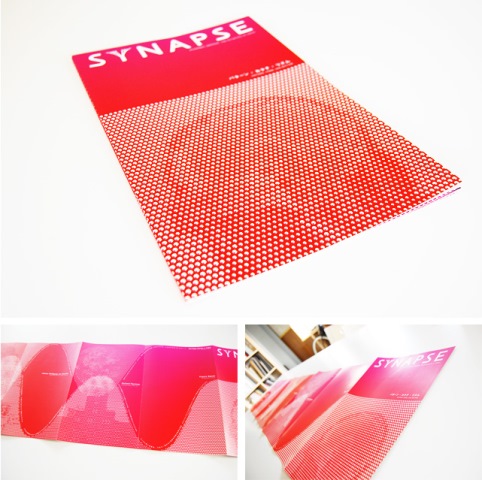
またフリーペーパー第2号となる「SYNAPSE Vol.02 -LIGHT-」は、テーマに「光」を掲げ、宇宙物質から生物の視覚世界、色彩の認知、光のアートから宗教分野まで、あらゆる分野へ横断的に光をあてたものとなっています。

SYNAPSEメンバーの塚田と福島がフリーのライター・編集者なのですが、この2冊を作る際はNOSIGNERさんという気鋭のデザイナーにアートディレクションをお願いしてチームを組みました。
ほかにも、音楽家の渋谷慶一郎さんと複雑系科学の研究者である池上高志さんなどにご出演いただいたトークイベントや、「学術は編集されるべきなのか?」をテーマにしたワークショップを開くなど、さまざまな活動をしてきました。ウェブサイト(http://synapse-academicgroove.com/)をご覧いただくと、これまでの活動を把握してもらえると思います。
科学に興味のない人まで届ける
―― SYNAPSEはどういった経緯で結成された団体なのでしょうか?
菅野 いろいろな流れが複雑に絡まっていて、お話するのがとても難しいんですが……。
日本では、科学技術基本法が施行された95年、そして「サイエンスカフェ元年」と呼ばれる05年くらいから、イギリスなどからサイエンスコミュニケーション活動を「輸入」する流れが始まりました。啓蒙活動よりも双方向的で、社会に対して科学側からの積極的なアプローチを行う機運がアカデミアで高められたと言えます。
その時期に、独立行政法人・科学技術振興機構(JST)の振興調整費によって、科学コミュニケーターを養成する部門として、北海道大学の科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)、早稲田大学の科学技術ジャーナリスト養成プログラム(MAJESTy)、そして東京大学の科学技術インタープリター養成プログラムがつくられました。ぼくはその東京大学の科学技術インタープリター養成プログラムの三期生にあたります。東大ではこのプラグラムを大学院の副専攻としていましたので、ぼくは生物学の研究をしながらSYNAPSEに繋がる活動をプログラムの修了研究として行うことになります。
三期生となって、いざ活動をはじめようとしたところ、サイエンスコミュニケーションとして大学が発行しているさまざまなパンフレットやウェブページがとにかくダサいことに気付いたんですね。
塚田 そうなんです。一般の人に手に取ってもらうことをまったく考慮していないように思えました。私だったら手に取らないかな、と。
菅野 たぶん業者も「大学のパンフレットは、幾何学模様で、青を使っていて……」とよくあるフォーマットにそって作っていたのだと思います。それって業者に限らず携わっている科学者も読者をバカにしているというか、かなり手抜きなように感じました。
サイエンスコミュニケーションがリーチすべきなのは、業界の内側ではなく外側にいる人たちです。パンフレットを作るなら、科学に興味のない人にも手に取ってもらえるようにしなくちゃいけない。それこそカフェに並んでいる情報誌と比べて遜色ないくらいに。
どうすればいいんだろう、と考えていたとき、理化学研究所が映像作家・音楽家の高木正勝さんを呼んでイベントを開いていたということを知りました。さらに理化学研究所は、高木さんに所内を見学してもらい、発生生物学にまつわる映像作品も一緒に製作していました。何故そんなことが可能になったのか、仕掛人は誰だったのかなど、そこにぼくの活動のヒントがあるように感じていました。そんな折り、アップルストア銀座で高木さんの対談が行われることを知り、そこに参加して高木さんにいろいろとお話を伺ったところ、芸術家の高木さんが、もともと科学に興味をお持ちだったということを知ったんです。
もしかしたら芸術に関心のある方の中には高木さんと同じように科学に興味のある方もいるのではないかと思い、東京大学で神経科学を研究している坂井克之さんと高木正勝さんをお呼びしてサイエンスアゴラ(http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/)でイベントを開くことにしたんです。イベントでは、お客さんにアンケートを取ったのですが、興味深い結果が複数とれました。たとえば、科学関係のイベントに初めてきた方が全体の6割で、この数字はサイエンスアゴラの来場者全体と比べると、異なった層をイベントに呼び込むことが出来たと言えるのですが、さらに同じく全体の6割の方が科学に対する好感度が上がったとお答えになっていました。
また、とくに興味深かったのは、「またこのような科学イベントに参加したいか」という質問に対して、「参加したい」と答えている多くの方は過去に科学関係のイベントに参加されている方で、そうでない方は「場合による」と答えていた点です。
これは科学に関するイベントに参加されている方の多くが常連だってことですよね。でもこのイベントで初めて科学イベントに来たという人の好感度が上がっていることを考えると、他にも常連になりうる潜在的なファンがいると言えると思います。寧ろ、そういう人たちにこそ科学のコンテンツを届けないといけないと、イベントを開いてから改めて思いました。
ただ、イベントを開いたりSYNAPSEの活動を始めたら「あいつは研究者の癖にちゃらちゃらしている」とも言われてしまったんですけど……(笑)。
飯島 アカデミズムの世界って、自分の専門一本に絞って研究するのがよしとされているところがあります。たとえば認知神経科学の研究者が哲学に手をだすとよろしくないとされているんですよね。仮に、学術的に本質的な結びつきがあったとしても。
菅野 それって飯島さんのことですよね(笑)。
「あるある大事典」が内容のねつ造をしていたことが明るみになって、繰り返し報道されたことがありましたが、そのときに、やっぱりアカデミズムとしても担保されたなにかをやらないといけないと思いました。
その際に、シノドスさんのように、アカデミック・ジャーナルを掲げたメディアのあり方というのも、ひとつの解だと思います。でもぼくらは研究者です。研究もしなくてはいけないし、資本も組織もない。さらに、いま科学雑誌は軒並み廃刊になって、残っているのは『Newton』や『日経サイエンス』、岩波書店の『科学』くらいしかありません。そういった厳しい現状を踏まえると、ぼくらはメディアになるのではなくて、たとえば『ブルータス』のような科学の専門誌ではない総合カルチャー誌に、科学について取り扱っているコーナーを増やしてもらうような働きかけをすることが現実的だと思いました。「気に留めてなかったけど科学のこと書いてあったな」くらいがちょうどいいと思うんです。
……でも気づいたら時代は変わっていて。震災以降、シノドスさんでも科学関係の記事を取り扱われる機会が増え、ワイヤードが日本で復活して良質な記事を載せている。ぼくらがやりたかったことが世の中に出てきて、いやあ、良い時代になってきたなあって思っています(笑)。

総長と学生のGrooveの合流点=SYNAPSE?
―― なるほど(笑)。それからSYNAPSEが生まれるまでのお話をお願いします。
塚田 最初に菅野がお話したように、すごく経緯が複雑なんです。SYNAPSEの誕生には「Academic Groove(http://academicgroove.net/)」という活動についてのお話がかかせません。
菅野 『Academic Groove』は、「学問はわくわくするほど面白い」というコンセプトを掲げた有志(東大構成員)が、東京大学創立130周年記念出版物として上梓したムック(書籍)です。このムックに登場されている研究者はそうそうたる顔ぶれですが、特に注目いただきたいのは、装丁がオシャレだということです(『Academic Groove』を制作した有志は、現在、SYNAPSE Lab.(およびSYNAPSE project)と密接な関係を持つ任意団体『Academic Groove』として活動している)。
塚田 わたしはこの本を、SYNAPSEが始まるよりずっと前に青山ブックセンターに並んでいるのをみて、装丁に惹かれて購入しました。ちょうど自分でフリーペーパーを作っていた時期だったので、こんな世界もあるのかと興奮したのを覚えています。
菅野 青山ブックセンターがチョイスするような本だったということがヒットのポイントだと思います。ダサいパンフレットじゃないんですね(笑)。科学コーナーに行こうという目的を持っていない人でも手に取ります。
サイエンスアゴラでのイベントを終え、副専攻での修了研究をまとめながら今後の方向性を模索していたぼくがイメージしていた理想的なかたちが東大からでていたことに驚いて、仕掛け人の一人であり、当時東大本部広報にいた清水修さんに藁をもすがる思いで電話をしたところ「ぜひお話をしよう」とおっしゃってくれたんです。そこで意気投合して清水さんと一緒になにかをやろうという話になったものの……。
飯島 なにかをやるには資金がいる。だけどぼくらにお金はない。どうやって資金を手に入れるか……と頭を悩ましていたら、東大が毎年開いている学生企画コンテストの受賞企画には賞金が出ることを知ったんです。そこで<東京大学を編集して魅せる>という企画書を書いて応募しました。
ぼくらはすでにイベントを開いていましたし、学者の仲間もたくさんいます。塚田のような雑誌の編集者も、『Academic Groove』を作った清水さんもいた。他の企画に比べて圧倒的に実現可能性がありました。
菅野 いま思うと大人げないことだったのかもしれません(笑)。ほとんどの企画は、学部生によるもので、ぼくらは博士課程の院生だったので。
ここからが面白くて。審査結果を待っている間に、東大の濱田純一総長が「オープンキャンパスやホームカミング・ディにあわせて、東大の学問を紹介するフリーペーパーを作りたい」と言い出したんですね。しかも清水さんに、「学生や職員でチームを結成して、作って欲しい」と仰っていた。
塚田 「それなら、すでにありますよ」と(笑)。
飯島 下からのぼくらの流れと上からの総長の流れが清水さんで合流したわけです。
菅野 そのとき生まれたのが「SYNAPSE vol.01」なんです。
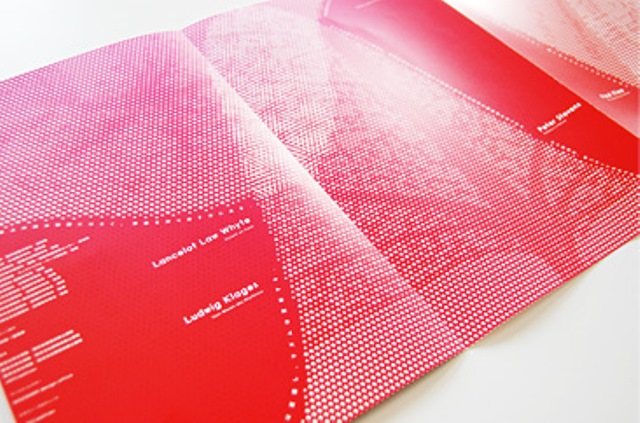
余談ですけどここでちょっとした問題が発生しました。「大学の予算で作ったSYNAPSEと同じような企画がコンテストに出ている。誰かが裏から手を引いているんじゃないか」って大学側が問題にしたんですよ。清水さんは大学から事情聴取まで受けてしまいました(笑)。が、総長からのフリーペーパー制作依頼より前にコンテストにエントリーしていましたから、すぐに潔白は証明されました(笑)。
科学と他分野の共通点:「観察と記述」
―― 学内のいろいろな流れがSYNAPSEの誕生で一つの形に結実したわけですね。SYNAPSEの活動を続けられるにあたって、特に意識されていることはありますか?
菅野 SYNAPSEは研究者が主体の活動です。編集者から取材を受けて、編集者が伝えたい内容にそって作られた原稿に承認の判を押すような、ウラ取りのための存在ではありません。
長々とインタビューを受けて、一部分をカットされて掲載されたものに「意図と違う」と文句を言うだけではいけないと思うんです。SYNAPSEは、科学者の口調も含めて、考えも癖も、科学者という生態や営みそのものを伝えられるメディアにしたかった。
なぜなら、たとえば原発事故のあとによく耳にした「可能性はゼロではない」といった科学者の発言がありましたが、あの発言って、科学者特有の言い方であることを知っているかいないかで、まったく受け取り方が変わってしまうんですよね。
でも何かを伝えるときには、かならずメディアを介することになります。そしてメディアは、紙媒体なら紙媒体の、ウェブ媒体ならウェブ媒体の伝え方があり、それによって伝わり方がかわる。そしてぼくら研究者が一方的に言いたいことを言っているだけじゃ伝えたい人たちに伝えられない。だからぼくらは企画の段階から、科学者も編集者もデザイナーも一緒になって考えています。実は、清水さんも東大に来る前はフリーのライターでいらっしゃいました。元はアカデミアではないところで仕事をされていた「外」の人だったんです。そんな方が、『Academic Groove』を作ったんです。
塚田 みんな同じ場所から始めたかったんですね。
菅野 一緒にやることが大事です。まあ、喧嘩になったり、お互いのバックグラウンドが違いすぎるので辛いんですけど(笑)。
―― 伝える内容だけでなく、伝え方も一緒に考えないといけないわけですね。最初にお話になられていた、「専門分野の枠組みを超える」は、科学者が編集者、デザイナーといった分野とも繋がることができるということなのでしょうか。
塚田 そうですね。それこそ科学者とは視点の異なる編集者やデザイナーが一緒に企画を考えることで、それぞれの専門分野を超えることができている。
菅野 芸術家だって、きっとそうです。高木正勝さんに制作活動に関して今後も「科学は興味をもつに値するものなのか」と質問をしたとき、反対に「科学ってなに?」と聞かれました。「現象の観察とその記述が過不足ない答えです」と答えたら「それは芸術も一緒だよ」っておっしゃった。
ぼくらのような自然科学者は、物質の定量、 紫外線のような電磁波の観測、脳活動の可視化等の手法を用いて、世界を記述しようとします。飯島さんならヘモグロビンの酸素化の状態を可視化することで脳の活動を観察しているし、ぼくは切断した脳を染色して脳の活動を見えるようにしている。音楽家の高木さんは、世界を絵と音で表現しようとしています。
飯島 「観察と記述」には受動的な印象があるかもしれませんが、観察は単純に受動的な行為ではなく、どの観点で世界を切り取るかという選択を行っている時点で既に能動的な営みなんです。アートと科学に共通する側面だと思います。
―― 科学は、他分野と共通する部分もたくさんあるということですね。とはいえ、やはり他分野とは違う、科学特有のものもあるわけですよね。
菅野 そうですね。抽象化された部分では共通点がありますが、それぞれの方法論に目を向ければ、似ていると言ってしまうと齟齬がたくさんあります。
それでもなぜ繋がることができたのかというと、ぼくらに協力してくださった方は、それぞれの分野が既存の体系のままではいけないと思っている方が多かったからだと思います。
いま、どの業界もお金がないので、自らのパイを広げるためには、他分野に対して、自分たちの分野の意義を伝える必要があると感じているように思います。そのときに「われわれは素晴らしいことをやっているから金をくれ!」ではいけません。一緒にやってくださる方にメリットを感じてもらうことが重要なのだと思います。
「子どもにもわかるように」ではない
―― 伝える側ではなく、伝えられる側はどういった層を想定されていらっしゃるのでしょうか。
菅野 ぼくらは、子どもにもわかるように噛み砕いた説明をするつもりはありません。
震災・原発事故以降、ミュージシャンやアーティスト、著名人の方々の中には、原発もしくはその背景にある科学技術に対して「反○○」という姿勢をとって、さまざまな運動をしたり、行き過ぎた発言をされた方がいました。おそらく、そういった姿勢をとるのは、(間接的にせよ)彼らに情報を提供している誰かがいるんだと思うんですよね。分析的であることよりも、イデオロギーによるバイアスが強い印象があります。一部の学者ですら、そうではありますが……。
世間の人々が何を議題にするのかも、多くの場合は、人々に情報を提供するマスメディアが左右しているように思います。そして、その議題に対して賛成をするか反対をするかは、もっとローカルな、コミュニティのカリスマ的な存在に強い影響を受ける。
先ほどお話したように、ぼくらにはマスメディアを動かせるほどの力はありません。たとえばサイエンスカフェのようなイベントには、毎回2、30人くらいの方が参加されます。ということは、何かを動かせるほど多くの方に伝えるためには、何度も何度もイベントを開かなくちゃいけない。
そうした状況でぼくらができることって、きっと最初にお話したようにカルチャー誌に小さな連載や特集を持つとか、1万人の読者をもつ人気ブロガーに対して情報を提供するといった活動だと思うんです。おそらくそういった人たちは、深みがないものは簡単に見透かしてしまうでしょう。だとしたら、安易にわかりやすいものを作るのではなくて、ある程度しっかりしたものを作りたい。そう考えています。

科学の営み全体を伝えるメディア
―― 波及効果のある人たちに伝えて、より多くの方に広めていくということですね。先ほど科学者の営みを伝えたいとお話になられていましたが、きっとそれは具体的な知識とは違う、別のなにかを伝えたいと考えているのだと思います。
飯島 もちろん、自然科学によって生産された知識は有用で、大事なものです。でも科学の本質は、知識そのものではなく、むしろその知識がどのようにして生み出されたかという生産行為にあります。そうした知識生産のノウハウは、日常において人々が直面するさまざまな問題に取り組む際にも、きっと有効なものであるはずだという確信があります。
菅野 そうです。方法、結果、そして考察という科学の営み全体を伝えたい。どういった方法でそのデータが取られて、そこからどのような結果が得られたのか、そしてその結果をどのように考察するか、それをトータルで伝えたいんです。そうでなければ、あるデータから得られる考察が、ひとつではなく複数あるということを納得してもらえないと思うんです。科学が嫌われる理由の一つは、一方的に答えを押し付ける存在であるかのようにとらえられがちだからだと思います。でも本来、科学はそのような存在ではありません。
シノドス編集長の荻上チキさんの『彼女たちの売春(ワリキリ)』(扶桑社)って、最後に統計データを書かれているじゃないですか。それをみて「もしかしたらシノドスさんも同じことをやろうとしているんじゃないか」と思いました。これからはデータから適切な<選択肢>を導くジャーナリズムをやらなくてはいけないと思います。小さなメディアとして活動するうえで、どういう方法があるのかを探り探りではありますが、ぼくたちなりに有用なカタチを見つけていきたいと思います。
これまでの活動を通して、普段あまり科学と接していない人たちの中にも潜在的な興味を持つ人たちがいることは分っています。そういった人たちとはゆるやかにコミュニティを形成しつつあり、このコミュニティを今後の具体的な活動に繋げていきたいと考えています。今回の連載企画でもその点の議論を深めたいと思います。ただ、そういう方々とは基本的に最初から協力的な関係がつくれるのですが、実際の社会問題では異なるコミュニティ間で何らかの意見対立が起こり、対話すら可能ではなくなってしまう場面もあります。その背景には科学技術に対する反感や嫌悪感などもあると思うのですが、そういった内容についても議論していきたいと思います。
シノドスさんのような大きな影響力を持っていないので活動の有用性に悩むこともありますが、研究者として、そして一般市民としてメディア活動をすることで、なにかがわかるのではないか。そうした一例として今後も活動を続けていきたいと思っています。また、この活動が、新しい学術領域を創ることにも繋がるようにしていきたいです。
―― シノドスとしてもぜひ応援させていただきたいと思います。今日はお忙しいところありがとうございました。
(2013年某日 渋谷にて)
【SYNAPSE Lab.×SYNODOS】
本インタビューをきっかけに、SYNAPSE Lab.とSYNODOSのコラボレーション企画として、SYNAPSE Lab.から「科学と社会をつなぐ」をテーマに様々な記事を提供いただくことになりました。
科学と社会をつなぐSYNAPSE project。様々なカルチャーやライフスタイルの側面から、現代社会と科学の関係を考察する連載シリーズ。科学研究に携わる人間自身が編集者と共にイベントやインタビューを通して人々と対話する。その先に見えるモノとは? 不定期更新(次回更新は5月予定)。ご注目ください!


