2012.08.24
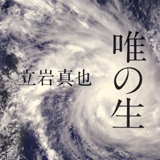
私には「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」はわからない
「尊厳死法制化を考える議員連盟」が今期国会での成立を目指している法――公表されているのは「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」で2案を同時に出すという話もある――がどんなもので、どんな報道がなされ、どんな意見があるかは以下を見ていただければだいたいわかる。
安楽死・尊厳死 euthanasia / death with dignity 2012
http://www.arsvi.com/d/et-2012.htm
そして私がこの主題についてどう思うか、何が起こってきたかは、次の2冊の拙著を読んでいただければと思う。
それからとくになにか新しいことが言われているわけではない。
長いものはまた、必要があったら、書かせてもらう。以下簡単に。
まず、すくなくとも、ほとんど誰も何も知らないこの状況で、なにがなんだかわからないまま、法律を通すようなせこいことはよしてくれ、いや、よしなさい。それが一つ。
脳死(・臓器移殖)法のときには、それなりに長い議論がなされた。今回問題にされている「ステージ」は脳死よりさらに「生」の側に近い。というか、実際生きている状態である。さらにより慎重な議論がなされるべきだが、そう考えない人たちがいるのは不思議であり、よくないことである。
「終末期」?
次に、単純に不思議なことを二つ。一つめ。この法案では「終末期」が以下のように「定義」されている。「この法律において、「終末期」とは、患者が、傷病について行い得る全ての適切な治療を受けた場合であっても回復の可能性がなく、かつ死期が間近であると判定された状態にある期間をいう。」(私が読んだものでは第5条1項)
第一に、「回復の可能性がな」い場合はたくさんある。障害者という人たちは、すくなくとも制度上はその身体の状態が固定された人たちを言うから、その限りでは、すべて「回復の可能性がない」。法律上の障害者の定義――それがよいものだと言っているのではない、よくないと私は考えている――などもってくる必要もない。回復の可能性のない障害・病を抱えている人はたくさんいる。すると、一つに、「当該」の――この法案では――「傷病」の治療という意味では手だてがないということであれば、それはしても無益であり、かつ治療は多く侵襲的であるから、加害的であさえありうる。それは行なう必要がない、あるいはすべきでない。だからそれはよい。もちろん法律的にも問題はない。
すると、「かつ」の次、つまり「死期が間近」という文言が問題になる。
もちろん、誰が何をもって判定するのかという疑問もある。複数の医療者が、というのがいちおうの回答のようだが、その複数の人とはほぼ同僚だろうから、どこまで有効かという疑問も当然出されている。その上で、医療者の「経験知」による「見立て」が「あと何時間」というレベルではかなり当たることは否定しない。そして「死期が間近」とはそのぐらいの時間を指すと考えるのが普通ではないか。
となると、停止するにせよ、開始するにせよ、その短い時間のあいだに何を新たにする必要があるのだろうかと思う。できるだけその人が楽であることに気を使いながら、維持し、看守ればよい。こうした時点で、新たに手術などしないことは、現行の法律からも、別に法律論にもっていかなくても、問題にされないだろう。とすると、なぜ新たな法律がいるのかということになる。
長く同様の法律の制定を主張し活動してきた日本尊厳死協会 http://www.songenshi-kyokai.com の(いまは前)理事長という方と、2人の副理事長という方と直接に話をさせていただく機会がこの数年の間にあった。いずれも率直なところ――しかし様々に私にはよくわからないところが残ったこと――を語ってくださった。最近では、7月3日に東京弁護士主催のシンポジウム http://www.toben.or.jp/know/iinkai/koureisyougai/news/20120528.html で副理事長の長尾和宏氏(医師)のお話をうかがったが、氏は「死期が間近」な「終末期」がどのぐらいの状態・時期のことを指すのか、決めることはできない、わからないととおっしゃった。それは正直な発言ではあるが、たいへん困る。「末期」と言われて今も生きている、あるいは長く生きた人をたくさん知っているが、そういう「誤診」の可能性のこと(だけ)を言いたいのではない。そもそも「わからない」のである。そして他方、繰り返すが、私のように(たぶん)普通な言葉の受け取り方をする人にとっての「間近」なのであれば、あらためて新しいきまりを作ることもない。
かつて、やはり尊厳死協会の人々は――これも人によって言うことが違うので困ってしまうのだが――「認知症」「植物状態」「(神経性)難病」等様々な状態について「尊厳死」の妥当性を言い、認知症を対象とすると言った時には認知症の人たちの家族の会から抗議を受けた(それでいったん引っ込めた)ということがあった。これらの人々が「間近」であることはない。そうして「間近」でない人を抜いていくと、さきほど私が述べた「正しい」意味での「間近」な人だけが残り、そこに新しいきまりは不要である。とすれば、この法律がなにか実際的な効果をもたらすのは、文案に書いてあるのと違い、「末期」でない人に対してなされる場合だということになる。これは、もう説明の用はないと思うが、よくない。
「延命措置」?
同じ第5条では「延命措置」の「定義」もある。「この法律において「延命措置」とは、終末期にある患者の傷病の治療または疼痛等の緩和ではなく、単に当該患者の生存期間の延長を目的とする治療上の措置(栄養又は水分の補給のための措置を含む。)をいう。」とある。
前半はここでは飛ばそう。「ではなく」とあるし、「疼痛等の緩和」は――意識をなくさせてそれをもって「緩和」とし、そのまま逝ってもらうといったことになるとまた話が別だが――基本的にはよいことである。そして「治療」はこの第5条2項の前の第1項で既に無効であることになっていた。
すると問題は「単に当該患者の生存期間の延長を目的とする治療上の措置(栄養又は水分の補給のための措置を含む。)」ということになる。まず「単に」がわからない。この言葉が使われているということは、「生存期間を延長」すること「以上」に「よいこと」があることが想定されているのだか、それは何か。言ってもらわないと法文としては成立しない。
そして例えば()内の「栄養又は水分の補給」だが、まず、長くその状態に置かれれば、その人は喉が乾いたり腹が減ったりするだろう。それはどのようにいけないことなのか。(仮にその人にまったく意識・感覚がないとしても、その本人にとってすくなくともわるいことではない。)そして他方、さきほどのように「間近」を普通の意味に受け取れば、その短い時間の間になにかすることを変える理由も思いつかない。「胃ろう」はこのごろ最初からよろしくないものであるかのように言われることがあるのだが、それもすこし冷静に考えたらよい。ほとんど運動がない人に多くの栄養はいらない。それを過剰に供給すれば、身体がおかしくなる。その調整は微妙だが可能であり、それをきちんと行なわないと本人にとって苦しいことにもなる。それはやめた方がよい。しかしそれはその「措置」を行なわない方がよいことを意味しない。
答えてもらってから、することしてもらってから
このように逐条的にみていくと、まだいろいろとあるが、それはここではよすことにする。2004年からしばらく同様の法案が上程されようとした時(この時のことについては前掲の拙著『唯の生』の第2章・第4章)以来、私は文章を書き(文章はそれ以前から書いてきた)、そして多くの場に呼び出されて、自らも話し、また直接にこうした法案の作成・法の制定をしようとしている方々に質問をしてきたが、ともかく、一度も、理解することのできる回答をいただいたことがない。最低、この小学生にもわかる問いに、小学生でもわかる答をもらいたい。でないと議論にもならない。
私だけでない。多くの人が様々な懸念を呈してきた。例えば「経済」がここに絡んでしまっていること。尊厳死協会の前理事長である井形明弘 http://www.arsvi.com/w/ia04.htm 氏は、日本宗教連盟主催のシンポジウム http://www.arsvi.com//ts/20100012.htm (2010年)で、医療や福祉のお金を削るために(膨張を抑制するために)法を作ろうなどと毛頭思っていないとおっしゃった。そのようにたしかに信じておられるとして、しかし、お金(と人手)の事情があって少なからぬ人々が死を選んでいることは、「つもり」がどうであろうと、「事実」である→拙著『ALS』(2006、医学書院)。そして今度新たに理事長になられた方は、ことが「医療経済」の問題で(も)あることを、すっきりと認めているとも聞く。「話は生きられる社会にしてからだ」という多くの人々の主張はもっともである。
最後に。それにしても、以上のようにすこし考えていくとわからなくなってしまうことを含めて、このかんずいぶん多くのことが語られ書かれた。本がたくさん出されている。そうしたものを紹介する本を出す企画がずいぶん前からあって、一冊分の分量にはなっているのだが、しょうじき気が進まないということもあり、まとめの作業を怠ってきた。そこで、まず前文(の下書き)、そして既にある文章と文章のあいだにはさみこむ短文を書いて、下記の生活書院のウェブサイトで、短期集中かつ不定期の連載?させていただいて、なんとかまとめようと思っている。よろしかったらご覧ください。
【Web連載】 『生死本』(仮)の準備・1
プロフィール

立岩真也
1960年、佐渡島生。専攻は社会学。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。千葉大学、信州大学医療技術短期大学部を経て現在立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『生の技法――家と施設を出て暮らす障害者の社会学』(共著、藤原書店、1990、増補・改訂版1995)『私的所有論』(勁草書房、1997)『弱くある自由へ――自己決定・介護・生死の技術』(青土社、2000)『自由の平等――簡単で別な姿の世界』(岩波書店、 2004)『ALS――不動の身体と息する機械』(医学書院、2004)『希望について』(青土社、2006)『所有と国家のゆくえ』(共著、NHK出版、2006)『良い死』(筑摩書房、2008)『流儀』(共著、生活書院、2008)『唯の生』(筑摩書房、2009)『税を直す』(共著、青土社、 2009)『ベーシックインカム――分配する最小国家の可能性』(共著、青土社、2010)『人間の条件――そんなものない』(イースト・プレス、 2010)『家族性分業論前哨』(共著、生活書院、2011)『差異と平等――障害とケア/有償と無償』(共著、青土社、2012)等。


