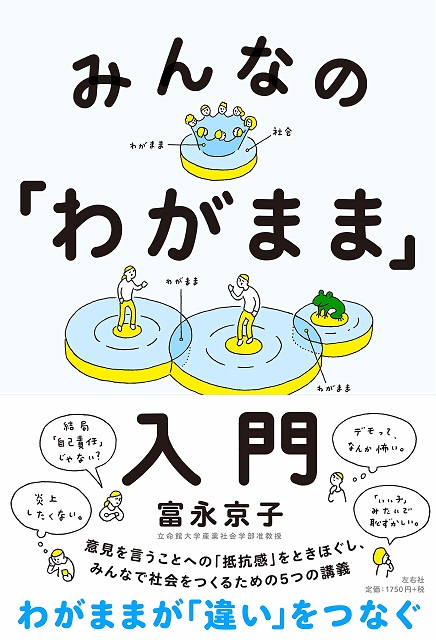2019.06.17
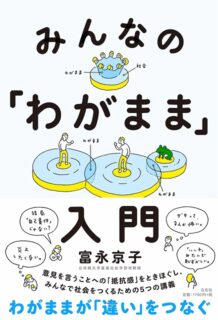
「わがまま」の背景に思いをいたす想像力を
――今回、若者に向けて社会運動についてお書きになろうと思った理由を教えていただけますか。
直接的なきっかけとしては、ある中高一貫校で講演をした経験があります。生徒さんからいただいた質問の多くは、「政治のこと、社会のことに関心がある。でも、どうやって関わればいいのかわからない」というものでした。
学校の授業で社会科を学んでいるんだからそれで十分じゃないかとも思うけれども、彼らの中に「それでは足りない」という感じがあった。自分の周りの大学生を見ていても思うのですが、もっと社会の当事者になりたいのかなと。そういう、何か関わり方みたいなものを非常に強く欲する態度に接して衝撃を受けたというのが、一番のきっかけだったかもしれません。このへんは18歳選挙権の影響もあるのかもしれませんが……
もちろん子どもだから、多くの場合、労働も納税もしていないわけで、ある程度社会に関わるやり方は制限されている。ただ、その中でできることというか、「じゃあ、どうやれば関われるだろうか」ということを、中高生の方と一緒に考えてみたいな、というところがありました。
――若者のあいだに政治や社会に関わりたい、という思いがあるんですね。でも、そこでなぜ「わがまま」なのでしょうか?
「わがまま」という言葉を思い浮かんだのは本当に偶然ですが(笑)、「社会運動ってようは個人のわがままでしょ」「社会のせいにするな」といった、忌避感や抵抗感、近寄りがたさから社会運動を読み解きつつ、その重要性を主張するという試みは、どこかでする必要があると思っていました。
社会運動をやっている人の前でこういうことをいうと、どうしても拒否反応を示されてしまうし、おそらく社会運動研究でもそれほどメジャーにはなりえない。ただ、現実的に、社会運動への抵抗感や忌避感は拭い難いものとしてあると思います。
だから、そうしたネガティブな感情をとっかかりに、じゃあなんでそういう感情を抱いてしまうのか考えてみようか、というところから議論をスタートさせたいというのが、ねらいといえばねらいになるでしょうか。
――たしかに、社会運動への忌避感や抵抗感は、根強いものがありますね。日本はほかの国に比べて「わがまま」に厳しいという調査結果があるとのことですが。
著書の中では、「わがまま」に対する許容度を示したデータとして、山本英弘さん(筑波大学)による調査を紹介しています。こちらはドイツと韓国と日本の三カ国において、「署名」「請願・陳情」「デモ」「座り込み」という社会運動のそれぞれの手法について、回答者に「行ってもよい」「まあ行ってもよい」「あまり行うべきではない」「行うべきではない」「分からない」のいずれかを選んでもらったというものです。
日本に住む人々は、署名や請願・陳情に対してはまあまあ肯定的なのですが、デモに肯定的な人は45.3%と低く、座り込みを支持する人は21.5%と非常に低い。ドイツだと、いずれの手法に関しても7-8割くらいの人が肯定的な回答をしているので、そこが興味深いところです。
山本さんはさらに、社会運動へのイメージに関しても、社会運動の「有効性」(社会運動に意味があるかどうか)、「代表性」(自分たちの意見を代表しているかどうか)、「秩序不安」(社会運動は危険、怖い、暴力的)という3つの軸から明らかにしています。日本の場合、半数くらいの人が「有効性」を認めている。ただいっぽうで、半分くらいの人が社会運動に対して「秩序不安」を、つまり怖いとか危険だとか感じているわけですね。
――意外に、ある程度、意味は認められているんですね。しかし、同時に怖くて危険。なぜなのでしょうか?
なぜ「社会運動は、怖くて危険」なのか。これはお答えが難しいところですが、ひとつには、1968年の学生運動や、その後の新左翼運動といったラディカルな運動がマスメディアによって報道され、未だにそのイメージが残っているからというのはよくいわれるところです。
あとは実際、質問紙調査で「社会運動、意味あるじゃん」とか「俺たちのいいたいことを代弁してくれてる!」と答えはするんだけど、実際に目にしたら引いちゃうというのもあるのかもしれない。インパクトのある表現を使う分、頭の中のイメージと現実に目にしたときのイメージのずれがあるのかなと思います。
――ご著書を読んでいて、なるほどと感じたのですが、野球チームの優勝パレードとかマラソン大会で道路が通行止めになるのは、さほど気にならない。なのに、それがデモによるものだと、なぜか多くのひとは迷惑に感じてしまう。これはいったいなぜなのでしょうか?
生活や労働に直結した利害と強い結びつきがあり、それが想定しやすい、というのはありますよね。
「原発を廃炉にしてほしい」「女性専用車両を導入して欲しい」というと、「いや、私のおじさん原発で働いてるんですけど」とか、「男性でも痴漢にあう人はいるでしょう」という反対意見は存在するし、それは例えば、私が「マラソン嫌いなんで、そういうイベントで交通遮断されるのは納得いきません」というのと切実さが違うだろうと思います。みんなにとって「どうでもいい」ことじゃないからこそ、激しい反応を招きうる。
みんな、自分のことだから、真面目に関わらなければならないのは分かっている。ただそれに対してセンシティブにならざるを得ない中で、声を上げている人に対して、「価値観の押しつけ」と感じる人がいるのではないかと思います。
――かつてのように運動への共感を調達するのが難しくなっているんですね。
はい。社会がグローバル化し、個人化するなかで、社会運動の性格もかつてとは違ってきています。
近年の代表的なものだと、#MeToo運動や安保法制に対する抗議行動ということになるでしょうが、どちらも非常に強い「個」の語りがあった。「私はこういう理由で、安保法制に反対します」「私はこうした事情から、ハラスメントに強く抗議します」といったような。そして、それが多くの人に対して、強い共感や衝撃を与えている。
こうした運動では、「私」の体験や背景が重要で、おそらくあまり「20代だから」とか「女だから」といわない。それはなぜかというと、低学歴だから低賃金だとか、女性だからハラスメントされる(男性でもハラスメントはされる)とか、生まれつきの属性や世代によってある特定の苦しみがある、という前提が崩れてきているからでしょう。
実態としてはもちろん、生まれ持った属性による苦しみというのは未だにあるわけですけれども、人々の生き方も多様化したので、それが実態として感じられづらくなっている。
――属性や世代による共感によって運動が成立しないとなると、個人にかかってくる負担も大きなものになりそうです。
私の最初の研究は、2008年に行われた北海道洞爺湖G8サミット(現G7サミット)に対する抗議行動の研究でした。その研究をしようと思って、実際に活動に携わっていた人に話を聞きに行ったのです。そのうちお一人に一度、面会を断られてしまって。
少し間を置いてお会いいただけるというときに、一度お断りされた経緯を伺ってみると、「あれは本当に大規模な運動で、とても大変だった。疲れたから、しばらく社会運動についてはお話したくなかったという気持ちがあって・・・」とお話されていました。
抗議行動が2008年、取材が2010年でしたから、外部の人に対してであれ、語れるようになるまでに2年を要したということになる。多分そういう社会運動の傷みたいなものを、きちんと見なくてはならないなと思ったのです。社会運動は、周囲のためにも自分のためにもなる「いいこと」ですから、当然やりがいもあるし、魅力的な人が多く集まっている。
私はたまにデモなどを見ているだけですが、見る側としても感動したり、高揚感があるから、きっとやっている人はその比ではないでしょう。ただ、それだけに、負の面は見えにくい、あるいは見せにくい。「いいこと」だからこそ、そこに伴う責任感や宿命感もあり、ネガティブな気持ちを吐露しにくい局面もあるのではないかと感じました。
端的に「社会運動、やりすぎるとよくないぞ」というのではなくて、社会に「いいこと」がつねに個人にとって「いいこと」とは限らない。熱中したり、責任感を持って取り組むことが生み出すネガティブな面を、どこかで言葉にしたり打ち明ける、そういう仕組みづくりが必要なのではないかと。それは社会運動に限らず、どういった活動でもそうかと思います。
――そうしたなかで、「アクティヴィスト・トラウマ・サポート」という団体の活動が興味深かったです。
「アクティヴィスト・トラウマ・サポート」は英国で2004年にできたボランタリー・グループで、社会運動に対する弾圧(警察からの攻撃やいやがらせ)や社会運動組織内部でのハラスメントを解決するためにできた団体です(https://www.activist-trauma.net/)。
現在は表立っては活動していないのですが、多くの取り組みが世界中の社会運動の中で紹介されました。先程申し上げたような、社会運動による燃え尽き(アクティヴィスト・バーンアウトといったりします)や、運動内部の人間関係で困っている人に対して相談窓口を開いたり、各国で大きな社会運動があるときは、燃え尽きやハラスメントをどう防ぐかというワークショップを開いたりしていました。
アクティヴィスト・トラウマ・サポートの方の取材の中で、「社会運動がマッチョ(男性優位主義)になる」という言葉が印象的でした。路上に出て、ときには機動隊と激しい衝突になったりする。そうすると、機動隊と戦ったひとが偉い、デモに出ている人がすごい、という「参加」そのものを高く評価してしまう傾向があるといいます。
機動隊と戦えて、デモで前面に出られるような人は、女性や障害を持った人や子ども、あるいは「身バレ」したくない人よりも、名前を表に出しても問題ない成人の男性のほうが多い。そうなれば、社会運動の中で誰が「すごい」かというヒエラルキーを作ってしまう。それがしばしば男性主体になってしまうことに対して、彼女たちは強い危惧を抱いていました。
アクティヴィスト・トラウマ・サポートでの体験は、おそらく自分が社会運動に参加できない、あるいはしてもあまり重要な立場にはなれないことと共鳴しているような気がして、個人的にも印象深いことのひとつです。
――ラディカルさの競い合いが運動の内部にもたらす病弊がある一方で、運動に参加するひとたちが振り回す「正義」に辟易する外部の人たちもいます。
この本では「わがまま」をいう側だけでなく、聞く側のあり方についてもそれなりの紙幅をとってお話しています。それはまさに、正義を「振り回す」ように感じる、あるいは運動の主張に「辟易」するという人びとの態度に疑問を持ったからです。
私もポリティカル・コレクトネスの観点から問題のある振る舞いをしてしまうことは当然あって、そういうときに攻撃的な物言いや皮肉めいた言い方をされるとイラッとしてしまうというか、いま流通している言い回しを使うなら、「そういうとこだぞ」と思わないわけでもない。
ただ、そういう言い方しかできないのには必ずなにか理由がある。穏健な言い方をしていても誰も聞かないとか、あまりに傷ついたり怒ったりしていて攻撃的にならざるを得ないとか。だから、イラッとするのはしょうがないとしても、必ずきちんと聞くようにします。
ご質問に戻りますが、活動をしている人、声を上げている人が「(正義を)振り回す」と感じるなら、なぜその人たちが振り回すまでに至ったのかを考えるということも、聞く側の作法として必要ではないかなと思うのです。
――ご著書を読んでいて浮かんでくる現代の若者像にちょっと驚きました。中高生と親のあいだに意見の相違がなくなってきているとか。異なる意見をもつ「他者」に対する警戒心が強いとか。「はみ出しちゃいけない」「間違っちゃいけない」とか。
本書で提示しているのは、土井隆義さんの調査データです。この調査だと、中高生の親が「子供と意見が合わない」と感じる10項目をあげる調査で、1982年以降には1項目を除くすべての割合が下がったといいます。
それに対する土井さんの解釈がとても印象的で、「親や教師が『共通の敵』ではなくなった」と論じている。実際に、1968年の社会運動は親世代や大学に対する反逆だったわけですが、おそらく現代の若者で、親に対してあえて反抗しようという人はそれほどいないかもしれない。
――なぜでしょうか?
なぜ、というのは簡単には議論しにくいところですが、私が少し驚いた点として、学生が「親に学費を払ってもらっている」「親にお世話になっている」といっていたのが印象的でした。
学費や教育費の観点から、保護者に対する負担感や庇護されている感覚が強いというのが、対抗心を形成しにくい理由としてあるのかと思ったりもします。それを「返さなければならない」という感覚も強くなりますから、自ずと親であれほかの大人であれ、先を行っている人々が良いという道を辿らなければという重圧が生まれてくるのかもしれません。
ただ一方で、この本を書いている中でお話を伺った中高生や大学生の話を聞いていると、むしろ多様な価値観とともに生きようという感覚は、むしろ親世代よりも強いのではないかと感じたりもします。
例えば、保護者の方のどういうところと価値観が合わないと思う?と聞いたら、「他人の結婚や恋愛に対して口出しするような報道を好むのが理解できない」「LGBTや外国の人たちに対して、なんで嫌悪感を示すのかわからない」という意見がありました。
高校でも何か社会や学校に対する不満はないかということで聞いてみると、学校の先生や制度に対して、おそらくふだんはいえないようなことをたくさん伝えてくれたりする。
そういうことを聞いていると、彼らは親や教師に遠慮して表立っていわないだけで、自らの意見があるし、こうしたいという気持ちがきちんとある。政治的・社会的ことがらに対する関心についても同じで、強いけれどもいろいろな事情や制約から遠慮してしまっていえない、という感覚が強いのではないでしょうか。
――冒頭のお話に戻るわけですね。政治や社会に関わりたいという意欲自体は強いと。その制約をはずすための「わがまま」のすすめ。
ところで、富永さん自身は直接、社会運動に関わることはないとのことですが、富永さんにとって社会運動とはどのような意味をもつものなのでしょうか?
私が社会運動の研究をしようと決めたのは、関わっていた選挙運動が失敗して、じゃあ「負けた」私たちの思いはどういうふうに政治に反映すればいいのか、と思ったからでした。つまり、政治的意義という点から社会運動は大事だし、やってみるかと思ったのです。
ただ、社会運動の世界を垣間見てみると、関わっている人々の言葉遣いや服装など、なかなか独特の文化があるな――もちろん社会運動といっても組織や課題によって非常に多様であることは後で気づくわけですが――ただ、少なくとも自分の側に「やりたい」という気持ちがあるだけではいづらいままだろうな、と感じたのです。
でも、それが政治であれ信仰であれ趣味であれ、集団が何かをしようとする限り必ずそうした作法や規範はつきものになるし、それこそが文化的な価値やオリジナリティでもあると思います。私はそうした文化を体現するという意味では、社会運動家にはなれなかったし、これからもなれない。ただ、社会運動を研究しつづけたのは、その政治的意義も重要ですが、社会運動の文化的価値に本当に強く惹かれたからだと思います。
――最後に、本書がターゲットにしている若者と、それから社会運動に冷ややかな視線を向けている大人にメッセージをいただけますか。
私は、「何か社会に不満があるなら、社会運動しようよ」というふうにはいえません。そして、この本も、そういう本ではまったくないです。なぜなら、私もやっていないし、今後もおそらくデモや陳情といったかたちでは関わらないのではないかと思います。
ただ、社会運動がやってきたことに、私たちの生がずいぶんのところ支えられているのは事実ですし、いま困っている、これから困るかもしれない私たちを救う選択肢としても大いに重要でしょう。
実際に人々が思っていること、感じていることを、「こう思え」というのは無理だと思います。私だって社会運動をする人の物の言い方に対してイラッとしたり、ずいぶん上からくるなと思ったことはいくらでもあります。社会運動、意味あんのかな?と思う気持ちも、過去にそう考えていた経験のある者として、わからなくもないです。
ただ、重要なのはイラッとしたり、ギョッとした後なんだと思います。自分たちとは違う人として分けて考えてしまうのではなく、じゃあちょっと聞いてみるか、考えてみるかと思って欲しい。一見無茶な要求をしている人、自分勝手に見える人、「わがまま」と感じられる人がなぜそういうことをいっているのか、その背景を考えてもいいんじゃないか、私から呼びかけられることがあるとしたら、控えめですがそれくらいでしょうか。
「社会運動をやらない社会運動研究者」である私に対して、
そして、研究者として、自分が面白がっているものを人に伝えたいと思うのはやはり、当たり前のことです。『みんなの「わがまま」入門』を通じて、そういう面白さが伝わればいいなと思います。【聞き手・構成 / 芹沢一也】
プロフィール
富永京子
1986 年生まれ、立命館大学産業社会学部准教授、シノドス国際社会動向研究所理事。専攻は社会運動論・国際社会学。社会運動・政治参加とサブカルチャーの関係を通じて、現代社会における人々の意識や行動のあり方を考究する。