2012.01.10
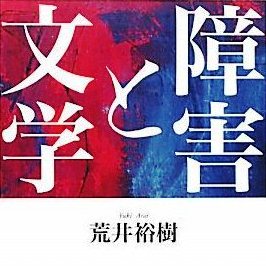
「障害者運動史」のなかに「文学」をいかに位置づけるか?
失われつつある「運動」の記憶
避けようのないひとつの物理的な時間切れを、ひりひりと肌を刺すような焦りと苛立ちのなかで感じている。戦後日本の障害者運動の現場で、文字通り体を張って「人間とは何か」という問いに立ち向かった人々の記憶と記録が、今まさに失われつつあるのである。
日本の障害者運動は1950年代にその萌芽があり、70年代に花開く、というのが通説である。もちろん、障害者運動(に類するもの)はそれ以前にも存在したし、また現在進行形で継続されてもいる。しかしながら70年代の運動は、ふたつの点で特異であったように思われる。ひとつは、たんに福祉制度の充実を求めるだけではなく、(学生運動の波とも相俟って)障害者差別に対する厳しい告発・糾弾へのエネルギーが異様な高まりを見せた点であり、もうひとつは、一見「過激」に見える主張の奥底に、「人間」や「生命」の意義を根源から問い直す哲学的な深みが潜在していた点である。
70年代の運動にたずさわった闘士たちの多くは戦前もしくは戦中生まれであり、運動の最盛期に30~40歳代を迎えた世代であった。現在、これらの人々は70歳代後半から80歳代となり、高齢化による障害の重度化や、それに伴う事故や病気の発症により、ここ数年、立てつづけに鬼籍に入っている。また、個々の運動団体や運動家たちが残した資料も本格的にアーカイブ化されることはなく、多くは個人の蔵書として秘蔵(死蔵)され、当事者の逝去や施設への転居に伴って散逸してしまう。障害者たちが社会を変えようとした苦闘の記録とも言うべきこれらの資料は文化遺産といっても過言ではないのだが、その貴重さが認識されることは(関係者のあいだでも)意外なほどに少ない。資料の保存や関係者への聞き取りなど、歴史を語り継ぐための作業が急がれる。
文学を媒介とした共同体の存在
拙書『障害と文学―「しののめ」から「青い芝の会」へ』は、この風化し、摩耗しつつある記憶と記録の痕跡を、もう一度この手でなぞろうとするささやかな試みである。具体的には、日本の障害者運動の先駆けである文芸同人団体「しののめ」と、「日本脳性マヒ者協会青い芝の会」を中心的な分析対象としている。
「青い芝の会」は、1957年に東京で結成された脳性マヒ者の団体である。結成当初はサロン的な雰囲気の漂う穏健な親睦団体であったが、60年代後半から福祉制度の拡充を求めて行政交渉を進めるようになる。70年代に至ると全国各地に支部が立ち上がり、ときに実力行使も辞さない過激な差別糾弾闘争を繰り広げ、日本の障害者運動の中心的な部分を形成していくことになる。
もうひとつの分析対象である「しののめ」は、上記「青い芝の会」の母体となった文芸同人団体である。同会は「社会保障」の制度はおろか、その概念自体が存在しなかった1947年に結成され、同名の文芸同人誌『しののめ』はおもに在宅で親の介護を受ける障害者たちのあいだに広まって行った。家庭の奥深くに閉じ込められていた障害者たちにとって、『しののめ』誌は、親にも打ち明けられない私的な感情を表現する貴重な場であり、同時に、家庭の外界(社会)と繋がる唯一の場でもあった。「青い芝の会」のような社会運動が湧き上がる土台に、文学を媒介にした共同体が存在していたことは特記されてよい。「しののめ」同人たちは、そのような共同体のなかで、障害を持つ自分が生きる意味について思索をめぐらせていたのである。
拙書ではとくに、「青い芝の会」に関しては神奈川県連合会代表で詩人の横田弘氏に、「しののめ」に関しては同会主宰で俳人の花田春兆氏をとりあげて検討した。両者とも文学を重要な自己表現の手段とし、障害者運動の現場でも中心的な役割を果してきた人物である。詳細は拙書を参照して頂きたいが、「青い芝の会」および「しののめ」は、日本の障害者運動の歴史を考える上で非常に重要な役割を果たした団体である。そして両会ともに文学を重要な核としていたことを勘案すれば、日本の障害者運動の起源には、重要な水脈のひとつとして、文学活動が潜在していたと言っても過言ではないのである。
社会運動の論理だけでは掬い切れないパトス
近年、とくに「青い芝の会」に関しては、社会学や障害学の若手研究者のあいだで歴史の再検討がさかんに進められている。このこと自体は非常に歓迎すべき事柄ではあるが、ただ、少しばかりの違和感を覚えることも事実である。
「青い芝の会」の歴史を検討・記述することは、日本の戦後史のなかで厳しく抑圧されてきたマイノリティたちの言葉を掬い上げる貴重な作業であることに間違いはない。そのことに異論はないのだが、その検討の俎上に上る資料が、運動の機関誌類に記された声明文や議事録、あるいは個々の運動家の著作などが中心となり、機関誌の文芸欄に掲載された文学作品や、個人の文学的著作などがほとんど無視されている点に漠然とした違和感を覚えるのである。
「しののめ」や「青い芝の会」にかぎらず、敗戦直後のハンセン病患者や日患同盟による人権闘争、あるいは70年代のウーマン・リブの戦いに至るまで、日本の社会運動の現場では数多くの機関誌類やミニコミ誌などが発行されたのだが、興味深いことに、それらのなかには無視しえない量の文学作品が掲載されているのである。
社会運動は被抑圧者のおかれた境遇の不当性を訴え、生存権を獲得し、生活の向上を図るものであるから、その主張の表明は世論の支持が得られるよう合理的で論理的であることが求められる。したがって「大衆」への浸透性が高い文学がプロパガンダとして機関誌類に登場することは想像に難くない。
しかしながら、実際にそれらの誌面に現れた文学作品には、政治的主張を展開するわけでもなく、何らかの問題の解決を求めるわけでもなく、ただ個人の心情が(しばしば極端に象徴化されたかたちで)吐露され、はなはだ解釈に困却せざるを得ない作品も少なくない(容易に解釈し得ないプロパガンダなどプロパガンダ足り得ない)。そこには、文学が生み出される何らかの必要性が存在したのであろう。
70年代の障害者運動は、それまで抑圧されていた障害者たちのルサンチマンが大きなエネルギー源になっていた。これらの運動が「福祉関係者」「障害児教育関係者」「障害者の家族」といった、障害者(問題)に近く、また理解のある人々に対してことさらに強く反発したのも、それらの人々の「善意」の前に飲みこんできた個々人の感情が爆発したためであろう。前述した通り、社会運動の主張は論理的で合理的であることが求められるが、個人の内的な感情は決して合理的でも論理的でもない。個性も生育環境も千差万別の障害者たちが共闘して運動を進めるためには、自らの心の奥底に押し込めなければならない私的な感情も少なくなかったことだろう。
おそらく、社会運動の論理だけでは掬い切れないそのようなパトスのはけ口が文学だったのだと思われるのだが、障害者運動の思想を本当の意味で解き明かすためには、このパトスの部分をいかにくみ上げるかが重要な鍵になるのだろう。
「自分は生きるに値する人間である」という根源的な自己肯定感
拙書の目的は、障害者自身によって描かれた文学作品の分析を通じて、上記のようなパトスの痕跡を掘り起こし、戦後日本の障害者運動に潜在した内的なエネルギーの根源を解き明かしていくことにある。試みに「青い芝の会」を引き合いに拙書の意図を説明すれば、同会が「過激」な言動を通じて社会に潜む障害者差別を告発・糾弾していたとして、そのような言動を「過激」に発せずにはおられなかった個々人の深層に、いかなる内的衝動が孕まれていたのかを、具体的な文学表現から解明していくことに主眼がある。
言うまでもなく、障害者運動は障害者たちが生きていくために引き起こされたものである。しかしながら、「生きるための主張」をするためには、前提条件として「自分は生きるに値する人間である」という根源的な自己肯定感が不可欠である。70年代の熱く激しい障害者運動の基層部分には、障害者たちが文学を通じて「そもそも自分は生きるに値する人間なのか?」「障害者が生きる意味とは何か?」という内省的な問いを繰り広げた思索の蓄積があったのだ。
現在の感覚からはあまり想像しにくいが、おそらく「しののめ」や「青い芝の会」に属した障害者たちにとって、文学は「生きること」と根源的な次元で結びついた営みであったのだと思われる。それらの文学と向き合うことを通じて、「人間にとって表現とは何か?」「人は何故に表現せずには生きられないのか?」といった普遍的(でおそらく解答不可能)な問いに思いをめぐらすことは、かつての障害者運動の闘士たちから託された大きな課題なのかもしれない。
拙なる本書が、この尊大な思索への道筋の一端を示すことができれば幸いである。
プロフィール

荒井裕樹
2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二松学舎大学文学部専任講師。東京精神科病院協会「心のアート展」実行委員会特別委員。専門は障害者文化論。著書『障害と文学』(現代書館)、『隔離の文学』(書肆アルス)、『生きていく絵』(亜紀書房)。


