2014.01.23
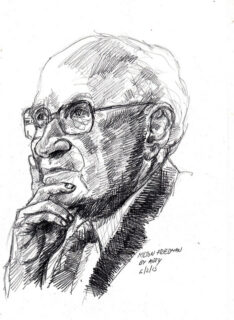
反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと「予想」
さてこの連載では、国家が経済のことにいろいろ管理介入する1970年代までの体制が、80年代以降世界中で崩れている転換を、「転換X」と呼び、その正体は何だったのかを探っています。
それは「小さな政府」への転換だ──こう言って、企業が利潤をもとめて活動するのを自由にして、みんな競争させようという「新自由主義」や、それをマイルドにした「ブレア=クリントン=日本民主党路線」が80年代以降今日に至るまでとられてきました。しかしそれは誤解だったというのが、この連載で言いたいことです。
そこで、70年代までのやり方が行き詰まった原因がどこにあって、それを解決するためにはどうしなければならないのか──それを、この転換を提唱した経済学者たちの言っていたことを振り返る中から探ってきました。
まず、国家が管理介入する体制の中でも一番典型的なソ連型システムが行き詰まった原因を、ハンガリーの共産党体制批判派の経済学者であったコルナイさんの言っていたことにそくして見てみました。さらに、やはり長年ソ連型システム批判を続けてきた、自由主義の巨匠ハイエクが言っていたことも検討しました。二人とも言っていたことをまとめると、リスクと決定と責任は一致しなければならない、これがズレていたのがソ連型システムの根本的な問題だったのだということになります。
ハイエクによれば、この批判があてはまるのは、ソ連型システムだけでなくて、国家が経済のことにいろいろ管理介入する体制全部に言えることです。リスクのあることは、それにかかわる情報を持つ現場の人々に決定と責任をまかせるべきである。それに対して、国家はリスクのあることには手を出さず、人々の予想を確定する役割に徹するべきである──こういうわけです。
そして、このように見ると、この転換にのっとったと称して新自由主義政策がやってきたことは、しばしば、コルナイさんやハイエクが言ってきたこととは、逆行することだったということもわかりました。
今回は、世界が新自由主義政策へ転換するにあたって、一番影響力があった経済学者として、誰もが筆頭にあげるミルトン・フリードマンの言っていたことを検討します。そして、彼の切り開いた経済学の「反ケインズ革命」の道を徹底し、その後の主流派マクロ経済学の源流を築いた「合理的期待形成学派」のルーカスさんの経済理論も見てみます。
その結果は、ここでもやはり、前回見たものと同じ命題にたどりつきます──予想は大事! ということです。
※1月23日朝掲載しました原稿には、ルーカスモデルの説明に関して間違いがありましたので、訂正いたしました。お詫びいたします。松尾匡(1月24日)
連載『リスク・責任・決定、そして自由!』
第一回:「『小さな政府』という誤解」
第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」
第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」
第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」
第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」
第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」
第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」
第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」
反ケインズ革命の旗手フリードマン
ミルトン・フリードマン(1912-2006)は、ケインズ政策全盛時代からケインズ理論を批判して、民間企業の自由な活動に任せて「小さな政府」にしたら、市場メカニズムが働いてうまくいくと大声で提唱し続けたことで有名です。
ケインズ経済学はそれとは逆で、資本主義の市場メカニズムは放っておいてはうまく働かなくて、ときどき不況になって失業者がたくさん出てしまうことがあるから、そんなときには政府や中央銀行がおカネをつぎ込んで景気をよくしなければならない。そうやって雇用を増やさないといけないと主張します。第二次世界大戦後の先進資本主義諸国では、この理屈に基づいて、政府が経済全体の需要を拡大して、完全雇用の実現を目指すようになっていきました。
アメリカではとくに1960年代、ケネディ大統領の元で「ニュー・エコノミクス」と銘打ち、積極的な財政政策で経済成長が図られました。その後のジョンソン政権も「偉大な社会」というスローガンでこの路線を推進し、60年代の半ばにはほぼ完全雇用が実現されるという、輝かしい成果をあげていました。
フリードマンはこんな頃、孤立無援の少数派になりながら、ブレることなく現実のケインズ政策を批判していました。やがて1970年代に、本連載第1回にも書いた「スタグフレーション」が起こり、ケインズ政策が景気停滞を解決できずに、ただインフレだけを悪化させるに及んで、フリードマンは俄然攻勢に出ることになります。講演や評論を精力的に行い、1980年には彼の監修するテレビの十回シリーズが放映されて反響を呼びました。同年これを書籍化したのが、有名な世界的ベストセラー『選択の自由』です。
こうした活動がどの程度あずかったことかわかりませんが、同年にはアメリカ大統領選挙で、「小さな政府」と市場規制の緩和を掲げる、共和党のレーガン候補が勝利しました。前年のイギリスでのサッチャー政権の成立とも合わせ、この後、新自由主義政策が世界を席巻していくことになります。そして学術的にもこれ以降、反ケインズ派が破竹の勢いで学界を制覇していきました。
……読者のみなさんは、フリードマンはお嫌いですか。たしかに、それもごもっともなことです。
この連載の主題の一つは、フリードマンも含め、70年代までの国家介入体制行き詰まりの本質を分析した学者たちが言ったことを、新自由主義政策は、しばしば非常に歪めてきたということです。その中にはフリードマン学説の真意に反した政策もたくさんあったと思います。しかし、フリードマン自身は学者であるにとどまらず、非常に政治的な動きをしてきた人です。新自由主義の政治家を応援し、世界に新自由主義政策が広まっていったことを、自説が受け入れられていったストーリーとして自慢しています。新自由主義政策がもたらした様々な犠牲や混乱に対する個人的な責任はたしかに免れないと思います。
とはいえ、理論の検討は、それとはまた別問題として重要なことだと思います。あとで申しますように、経済理論としても、フリードマンの理論の想定には大いに異論があるのですが、それはそれとして、それまでのケインズ派の理論や政策の弱点を突いた点で、大きな貢献があると思います。
そもそも新しい説が既存の学説を打ち負かし、人々に受け入れられて一世を風靡したならば、それは何か理由があることです。テクノロジーとか人々の生活のあり方など──流行りの言い方では「ファンダメンタルズ」、古風な言い方をすれば「物質的生産諸力」──の条件に、何かフィットしなくなったから既存の学説は負け、ベストでなくても何らかの適応をしたからこそ、新学説は人々に受け入れられたわけです。思想堅固であれば負けなかったなどという総括は最悪の観念論です。勝った学説のどこにその適応があったのかを見極めて、自分の側のブラッシュ・アップに活かしていく姿勢こそが必要なことでしょう。
ケインズ派とフリードマンの主張の違い
と、まあこんなことをわざわざ書いたのも、フリードマンと言えば、左派系の人たちの間では怨嗟の的で、世界に新自由主義の惨禍をもたらした悪魔の学説の教祖みたいな扱いですので、ちょっとでもその学説の中にプラスのものを見いだそうとしたらボコボコ叩かれそうだからなのですが、さて、では念のためにケインズ派の人たちと、フリードマンでは、どんな主張の対立があったのか、ちょっとまとめておきましょうか。
ケインズ派と言えば、欧米では労働組合側に支持されているものです。ヨーロッパではイギリス労働党やドイツ社会民主党などの左派政党、アメリカではアメリカリベラル派の民主党が取入れてきました。資本主義経済とは欠陥のあるものだから、働く大衆や社会的弱者のために公的な責任で適切な介入がなされるべきだと考える人たちです。
それに対してフリードマンの考えは、世界の財界に支持されて、イギリス保守党、アメリカ共和党などの保守派の政党が取入れてきたものです。資本主義の市場経済はすばらしいものだから、原則として役所は口出しせずに、民間人の自由なビジネスにまかせなさいという立場ですね。
はいでは、次の二つの主張のうち、どちらがケインズ派の主張で、どちらがフリードマンの主張でしょうか。
A.不況になったら、中央銀行がおカネをどんどん発行すること(金融緩和)や、政府が財政支出の拡大をするべきである。そうすると、経済全体のモノやサービスを買おうとする力(総需要)が増えて、景気がよくなる。
B.金融緩和や財政支出拡大をしたら、一時的には生産や雇用が増えるが、それは長続きせず、やがては元の木阿弥になってしまう。結局、インフレや財政赤字が悪化するだけ損で、有害無益だ。
もちろん、Aがケインズ派、Bがフリードマンの主張です。最近の日本にいると勘違いしそうですが、間違えないで下さいよ。Bは、左翼の怨嗟の的で、世界に新自由主義の惨禍をもたらしたとして悪魔の学説の教祖扱いされているフリードマンの主張です。胸に手を当てて近頃の自分の言動を思い返してほしい人が左派系にもたくさんいるのですが……。心当たりのある人は、少なくとも、フリードマンから何かプラスの論点を引き出そうとしたカドだけでヒトを叩いたりすることは、できれば遠慮してほしいと思います。
(ちなみに余談ついでに言えば、社会民主主義みたいなヘタレじゃダメと言うならば、もっと急進的な共産主義は、中央銀行を国有化して労働者政権がコントロールすることを主張するものなのです。例えばマルクスの『フランスにおける内乱』を読んでみて下さい)
ケインズ政策批判の要点=インフレ予想を加速させる
もちろん、私たちがフリードマンから取入れるべきものは、こんな論点なのではありません。フリードマンがBのような主張をするにあたっては、そもそも、働きたいのに働き口がなくて働けない失業者なんていないことが、お話の前提になっています。もっとも、技能と求人のミスマッチで人手不足と失業が同時にある事態は認識しているのですが、世の中の総需要が不足して大半の職種で人が余る事態は最初から考えていないのです[*1]。
実は、ケインズ登場以前の、古いタイプの新古典派経済学でも同じように考えられていました。フリードマンがただの先祖返りではなくて、そこに新しいものを付け加えた点は、一時的には景気対策が効くことを表現できたことにあります。古いタイプの新古典派の想定では、人手がみんな雇われてしまっているので、総需要拡大政策をとってももう雇用は増やせません。だから生産も増えない。生産が増えないのに需要だけ増えるのですから、いろんなものがみんな品不足になって値上がりします。つまり、最初からただインフレになるだけで、何の効果もありません。
それに対してフリードマンの想定の場合は、総需要拡大政策の結果、さしあたり人手不足になって名目賃金が上がったら、人々が実質賃金も上がったものと勘違いして、これはもうかるぞと、いままで働こうとしなかった人も働きに出るようになるとされているのです。本当は物価も同じくらい上がっているので、実質賃金は変わっていないのですが、人々はそれを正確には認識できず、当初そんなには物価が上昇しない予想をしているというわけです。
こうして労働需要が増えるのに追いついて労働供給も増えるので、生産も増えます。雇用量も増えます。これが、一時的に景気対策が効いた状態です。
しかしやがて、実は物価が予想以上に上がっていて実質賃金が増えていないことに人々が気づき出します。すると、働くのがばかばかしくなって働きに出るのをやめる人が出ます。結局最終的にはもとの雇用量と生産量に戻り、ただインフレがひどくなっているだけ。古いタイプの新古典派の見立てと同じ結末になります。
フリードマンに言わせれば、ケインズ派の人たちは、雇用がまた減ってしまったのを見て、景気対策が足りなかったと判断して、ますます総需要を拡大する政策をとってしまう。そうすると、人々のインフレ予想を上回るインフレになってはじめて、実質賃金が増えたと勘違いして労働供給が増えて生産が増える効果が復活しますが、それもまた人々のインフレ予想が現実に追いついて高まることで、元の木阿弥になってしまう。そしてますます総需要を拡大する政策がとられ……と悪循環が続き、インフレがどんどん悪化していくのだということになります。
私は、景気の拡大というのは、働きたい人が増えて生産が増えるというよりは、働きたいのに働き口がなかった人が新たに雇われて生産が増えるものだと思いますので、以上解説したフリードマンの議論はそもそも想定が間違っていると思います。しかし、ここで重要なことは、人々の予想が経済の動きに影響することが指摘されたことです。人々の予想を超えるインフレを起こし続けて、人々のインフレ予想がどんどん上がっていくからこそ、現実のインフレも歯止めなく加速していく。生産は長期的には停滞したまま増やせないのに。こう言って、スタグフレーションのメカニズムを説明したわけです。
だからフリードマンによれば、ケインズ政策の何が悪いのかと言えば、人々のインフレ予想を不安定にする(どんどん上がっていく)ところがダメだということになります。それに対してフリードマンがインフレを抑えるために提唱したことは、人々のインフレ予想を抑え込むことです。一時的に失業が増えるかもしれないけど、焦らずブレず、中央銀行のおカネの発行を引き締め続ければいいのだということです。
不況では金融緩和の景気対策は必要
したがって、フリードマン理論の革新点もまた、前回見たハイエクの議論と同じということになります。政府は民間の人々の予想を不確実にすることに手を出してはならない。人々の予想を確実ならしめるのがその役割でなければならない。──こういうわけです。
ですから、これは、「不況になっても景気対策も何もせずほったらかしておくべきだ」という主張ではないわけです。
実際、フリードマンは、1930年代の「大不況」が長くてひどいものになった原因を、中央銀行がとるべき政策をとらなかったことに見ています。アメリカの中央銀行である連邦準備制度理事会は、本来、もっと大胆におカネを出すべきだったにもかかわらずそれをせず、かえっておカネの発行を減らしてしまったと言って批判しているのです[*2]。
では、どんな政策をとればいいのか。これもやはりハイエクと同じです。人々の予想を確定させる政策、すなわち政策担当者のその都度その都度の胸先三寸の判断で左右されることのない「ルール」です。フリードマンが提唱した有名なルールは、世の中に出回っているおカネの量を一定の率で増やしていく政策です。世に言う「k%ルール」ですね。フリードマンの一般向けの主著である『資本主義と自由』では、Xを記号に使っていますので、「X%ルール」とも言ってもいいです[*3]。
これは、何も考えずに機械的にX%でおカネを出し続けるというお話ではありません。『資本主義と自由』でも、ここで言っている、世の中に出回っているおカネの定義は、民間の銀行の外にある現金と、民間の銀行にある預金の合計のことだとされています[*4]。銀行がおカネを貸すときには、現金で貸すことはほとんどなくて、貸し出す相手の預金を作って口座に数字を書くだけですよね。借りた人がそのおカネを使うときも、支払先の預金口座に振り込むだけです。だから預金というのはおカネの一部なのです。
ということは、景気がいいときには、銀行は貸出を増やしますので、世の中で出回るおカネの量は増えます。不況のときは逆で、銀行は貸出を減らしますので、世の中で出回るおカネの量は減ります。世の中に出回るおカネの量というものは、景気に合わせて自動的に変動するものなのです。
だから、フリードマンは「預金準備率100%」という、どう考えても無理なことも理想としていたようですが[*5]、現実にはそういうわけにはいきません。一定の率X%で世の中に出回るおカネの量を増やしつづけるためには、景気がよすぎて貸出の伸び率が高いときには、中央銀行はおカネの発行を引き締めなければならないことになります。景気が悪くて貸出が減っているときには、中央銀行はおカネの発行を増やさなければなりません。景気の状況に合わせた金融政策は必要だということになります。フリードマンが、1930年代のアメリカの中央銀行が本来とるべきだったとしているのは、明らかにそのような姿勢です。
つまり、一旦ルールを決めたならば、それを守るために、政策当局者によるその都度その都度の状況を見た機敏な判断が必要になるということです。
ハイエクの場合も、判決が繰り返される中で形成される不文のルールたる「ノモスとしての法」は、それがあるというだけではダメで、その都度その都度の状況に合わせた権力機関の判断による「テシスとしての法」によって守らせなければならないということでした。ただ、あくまで後者が前者に下位のものとして従属するという点が重要なのです。それと同じで、その都度その都度の状況に合わせて金融政策の加減をする判断は、現実には必要なんだけど、それはあくまで、一定のX%というルールを守るためなんだということです。
とはいえ、中央銀行がおカネを出す量をコントロールしても、世の中に出回っているおカネの量が思った通りに増減できるかというと、そう簡単にはいかないです。フリードマンは、両者の関係をわりとリジッドに考えて楽観的だったかもしれませんが、実際にはその関係はかなりルーズです。結局、世の中に出回るおカネを一定率で伸ばそうとしても、中央銀行の判断に委ねられる部分はかなり大きくなり、民間人にとっての政策の不確実性はたいしてなくならないじゃないか……ということになってしまいます。だから、今日ではこのフリードマンの提案自体は、ほぼダメだということになっています。
[*1]以下の総需要拡大政策についての議論は、主に置塩信雄がフリードマンの議論を数学モデルにして分析しているものに基づいている。置塩信雄『現代経済学II』(筑摩書房, 1988年)第6章。
[*2]フリードマン『資本主義と自由』村井章子訳、日経BP社、2008年、103-110ページ。もっと詳しくは、フリードマン、シュウォーツ『大収縮1929-1933「米国金融史」第7章』久保恵美子訳、日経BP社、2009年。
[*3]前掲『資本主義と自由』116-118ページ。
[*4]同上書116ページ。
[*5]Bennett T. McCallum, “Monetarism”(The Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty)、voxwatcher訳「マネタリズムの経済学」、2012年6月19日、「VOXを訳す!」サイト内。http://voxwatcher.blogspot.jp/2012/06/bennett-mccallum.html
ルーカスの「合理的期待」革命
さて、前回も触れましたように、シカゴ大学というところは、一時ハイエクもいたくらいで、もともとシカゴ学派と呼ばれる自由主義経済学の伝統があったところですが、フリードマンが同大学で教鞭をとって、同僚や教え子に多くの市場自由主義の経済学者が育ってくることになります。その中で、フリードマンに続く世代のロバート・ルーカスさん(1937-)が、経済学の歴史に一時代を画することを言い出しました。「合理的期待」という考え方です。
「合理的期待」というのは、人々が将来の価格などを、現在の情報から得られる確率的期待値に一致するように予想するという意味です。まあ、おおざっぱに言えば、平均的に見たらだいたい当たるように予想するということです。
ルーカスさんは、この合理的期待を話の前提にした理論モデルを使って、驚きの結論を導き出しました。さすがのフリードマンも、総需要拡大政策は短期的にだけなら効果があると言っていたのに、それをも否定したのです。人々の意表をついてやるならば効果があるが、人々が平均的に見てそれを予想するならば、総需要拡大政策は短期的にも無効になる。ただインフレになるだけだと言うのです。ですからここからは、フリードマン以上に、政府による経済への介入を否定し、自由な市場の調和性を強調する立場が導かれました。
このルーカスさんの議論がセンセーションを巻き起こし、やがてこの手法を使うことが経済学の主流の作法になっていったのです。
この議論が最初に広まっていった頃は、この理論モデルの総需要拡大政策を無効にする性質やバッチリ市場均衡がなされる性質は、合理的期待という前提に原因があると思われていました。だから、こうした結論が気に入らないケインズ派や、その他の左派系の経済学の人たちは、「合理的期待なんて前提は非現実的な絵空事だ」という批判をやっきになってしていたわけです。
ところが実はこれは誤解でした。
そもそもの出発点になったルーカスさんの1972年の最初の合理的期待モデル[*6]は、今日「ルーカスモデル」と呼ばれていますが、計算の都合のために、たしかにとんでもなく非現実的なおとぎ話のような想定をおいています。こうした想定の非現実性をあげつらったり、「合理的期待」という前提が「絵空事」だと言ったりするのは簡単なことです。
しかしその後続々と明らかになったのは、このルーカスモデルの想定をそっくりそのまま使い、合理的期待の前提もおいたままで、このモデル自体にルーカスさんが気づいていなかった別の均衡がいくつもあるということでした。そしてそれらの別均衡のもとでは、政府がおカネの発行を増やしたとき、ただインフレになって終わりというわけではなく、ちゃんと生産が増えることが明らかにされたのでした。
このことは、もうずいぶん早くから指摘されていたことなのですが、最近では松井宗也さんが詳しく研究されていますので、ここでは松井さんの論文[*7]にしたがってそのことをご紹介しましょう。
Lucas(1972)の島モデル
ルーカスモデルそのものの詳しい説明は日本語でもたくさんあって、どれも正確なのですが、私の読んだ限りでは、大瀧雅之さんの『景気循環の理論』[*8]第1章第3節の説明が、モデルの仮定の経済的意味やタネの「仕込み」に踏み込んだ説明をしていて圧倒的にわかりやすいので、詳しくはそちらをご覧下さい。ここではその大瀧さんの解釈にそって、数学的展開にはまったく触れずに、言葉で概要だけお話しします。
ルーカスモデルで想定されている人たちは、現役の頃と引退してからの二期間生きます。人口は永久に一定なのですが、現役時代は出鱈目に二つの島に分かれます。そこで「財」というものを生産するのですが、これは期間を超えて保存することができません。なので、その期のうちに自分で消費するか、同じ島に住む引退世代の人に売るかします。売ったら「貨幣」が手に入り、これは次の期に持ち越すことができます。
次の期になったら、現役世代だった人は引退して、両島の総貨幣量が等しくなるように島の間を移住します。これはとてもご都合主義的な仮定なのですが、計算が複雑にならないために必要な工夫だと思って下さい。そして、引退した人たちの持っている貨幣に対して、政府が新たに貨幣を発行して、ランダムな利率の利子をあげます。彼らは、こうやって増えた貨幣をその期の内に費やして、住んでいる島の現役世代から財を買って、それを消費して一生を終えます。……とまあ、こんな想定のモデルです。
そうすると、引退してしまった人は、ただ持っている貨幣で財を買うだけですので何も決めることはありませんけど、現役世代の人は決めなければいけないことがあります。どれだけ働いて財を生産するか、現役のうちにどれだけ消費するかということです。これを決めるためには引退後の生活のことも考えなければいけません。すると、引退後に財をどんな価格で買えるかが気になります。このモデルの中の人はこれを合理的に予想して必要な決定を行います。
ここで、現時点の物価が上がったとしましょう。モデルの中の人はこれを手がかりにして将来の物価を予想します。現時点の物価が上がるには、二つの原因が考えられます。一つは、この島に振り分けられた現役人口がたまたま少なかったせいで、財の供給が少なくなっているということです。もう一つは、引退世代に政府から渡された利子が多くて、彼らの手元に貨幣がたくさんあって、財の需要が多くなっているということです。
前者は、生産条件の変動の不確実性を、後者は、政策の変動についての民間人の不確実性を、それぞれ象徴する「おとぎ話」だと思って下さい。ルーカスのタネの「仕込み」は、この二つの原因を人々がその期のうちには区別することができず、次の期になってはじめてわかるという想定になっていることにあります。
もし物価上昇が全部現役人口の変動のせいならば、それは次期の現役人口には関係のないことです。次期には平均的には物価が元に戻ると予想されます。つまり、いまより物価は下がるということです。これは貨幣を持ち越せば将来買える財が増えるということで、実質的に利子がつくことといっしょです。ならばたくさん稼いで貨幣を将来に持ち越して引退人生を楽しもうと思います。だから、生産が増えます。
ところが物価上昇が全部、貨幣が増えたせいならば、その貨幣が次期にも持ち越されますので、平均的に見て物価は高くなったまま変わらないと予想されます。貨幣を持ち越すごリヤクは変わりませんので、生産も増えません。
しかしこのモデルの中の人は、この両者を今期中は区別できませんから、物価が高くなった理由が、本当は政府が人々の意表をついて貨幣発行を増やしただけのことだったとしても、人々は自分の島への現役人口の割り振りが少なかったせいである可能性を否定できません。その可能性の分は、人々は財の生産を増やして貨幣の持ち越しを増やそうとします。だから、人々に予期されざる金融緩和政策は、生産を増やすという意味で有効ということになります。
ところが政府の貨幣供給がバッチリ人々によって認識されるならば、人々はただ現役人口の割り振りに反応するだけで、貨幣の変動の方に反応して生産を増やすことはしません。だから、予想された金融政策は無効ということになります。
[*6]R. E. Lucas, Jr., “Expectations and the neutrality of money,” Journal of Economic Theory, Vol. 4, 1972.
[*7]松井宗也「Lucas (1972)モデルにおける複数均衡」(2012)http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/MCENTER/pdf/wp1202.pdf
[*8]東京大学出版会、1994年。
政策無効になる前提は合理的期待以外にある
さてここで注意してほしいのですが、このモデルでは最初から失業というものがありません。そもそも雇うとか雇われるとかいう労働市場というものがなく、各自が自営業者として「財」を生産しているイメージを持つべきです。そして、この財の需要と供給は、価格がスムーズに動いて毎期きれいにバランスすることが最初から想定されています。だから、政策が有効とか無効とか言っても、財の売れ行きが増して失業が減るかどうかという話は、最初から想定していないのです。
ここで景気の拡大のようにみなされている事態は、人々が自らたくさん働くようになって財の生産が増えることです。総需要の拡大に合わせて、売れる分だけ生産が増えることではありません。総需要拡大政策の有効性など、そもそもの初めからあり得ないモデルの想定になっているのです[*9]。この点には、合理的期待の想定などまったく関係ありません。
そしてその上に後年みんなわかってきたことは、ルーカスさんは、つじつまのあった物価の決まり方の式として、特定の式を、天降り的に持ち込んでいるということです。それが「貨幣数量説」型の式、つまり、貨幣の量が二倍になったら物価も二倍になるというように、貨幣の量と物価が比例するとみなす式です。
ルーカスさんが難しい数学を使って証明しているのは、こういう物価の決まり方の式を使えば、モデル全体とつじつまが合うということです。つまり、人々がある将来価格の予想のもとで各自最適に行動したら、それが合成されて決まる将来の価格が、平均的に当初人々が予想していた価格とホントに一致する、そのような物価の決まり方の式が存在するということです。
その証明はともかく、このような物価の決まり方を前提すれば、貨幣をどれだけ増やそうが、実際の生産や消費に関係なくなるのはあたりまえです。なぜなら、人々が生産や消費の計画を決めるにあたって、貨幣が影響するのは、それでどれだけ財が買えるかということですから、人々の行動を決める式の中に、貨幣は必ず「実質量」の形で入ってきます。つまり、貨幣が財何個分にあたるかを表すために、名目貨幣量を物価でわった形で入っているわけです。ところが、その割る数である物価が貨幣に比例していたならば、貨幣は割る数と割られる数の両方に出てきて約分されて消えてなくなり、人々の行動を決める式の中には名目貨幣量は出てこないことになります。これではそもそも貨幣が生産や消費に影響できるはずはありません。
ルーカスモデルに発見された複数均衡
だから、ルーカスさんの論文の政策無効の結論は、実は「合理的期待」という新しい手法に原因があったわけではなかったのです。
このことが認識されたのは、ルーカスモデルでつじつまの合った物価の決まり方の式は、ルーカスさんが使った貨幣数量説型の式だけでなく、いろんな式があり得るということが発見されていったからです。松井さんの論文によれば、1990年代の初めには、ルーカスモデルの中に出てくるいろいろな式を、計算のしやすい簡単な式に特定化した上で、貨幣が生産や消費に影響するような解が無限に出てくることが示されている[*10]そうです。
松井さん自身のされたことは、計算のしやすいように特定化したりせず、ルーカスさんのもとのモデルとまったく同じ一般的な式のもとで、貨幣数量説型以外の物価の決まり方の式を持ち込んでみて、それがちゃんとモデル全体とつじつまが合うことを証明されたことです。その式というのは、価格と貨幣量はきれいに正比例するわけではないけど、何かの関係はあるという式です(きれいに正比例する貨幣数量説は、一特殊ケースとして扱えます)。きれいに正比例するのでなければ、人々の行動を決める式の中に貨幣量が変数として残ります。つまり、金融政策は生産や消費に影響を与えるということです。
また、ルーカスモデルにおいては、政府による貨幣発行ルールの式を変えても、貨幣を出す量が生産や消費に影響するようにモデルを作ることができることが指摘されています。松井さんによれば、1985年にすでに小谷清さんがこれを見つけていた[*11]そうです。
ルーカスモデルでは、何らかの利率の利子を政府が貨幣発行して配ることになっていましたから、当然それは各自の持ち越した貨幣量に比例してもらえるわけです。ところが、小谷さんは、そうした利子に加えて、引退世代一人頭一定のベーシックインカムのような貨幣をばらまくことにしても、モデルはつじつまが合って成り立ち、しかも貨幣は生産や消費に影響するようになることを見つけました。この場合、各自の持ち越した貨幣量に引退後使える貨幣量が比例しないために、きれいに割り算されずに貨幣量が式に残ってしまう効果が出るわけです。
注意すべきは、これらはすべて合理的期待による予想形成を前提して成り立っているということです。たしかに、これらの研究はルーカスモデルの設定をそのまま使って分析していますので、「政策有効になった」と言っても、もともと総需要不足の失業があったわけではなく、人々がもっと働きたくなって働くことを増やしたら生産が増えたというだけです。現実の不況対策に役に立つことを言っているわけではありません。ですけれども、合理的期待で予想形成するかどうかと政策無効命題とは関係がないということが、これらによってはっきりと示されたわけです。
なおルーカスモデルの枠組みを引き継ぎながら、雇い雇われるの関係をモデルに盛り込み、合理的期待による予想形成を前提しても、総需要不足で失業が発生し得るようにすることはできます。そのときには、政府が貨幣発行を増やすことで総需要が拡大して失業を減らせることが示せます。大瀧雅之さんの『貨幣・雇用理論の基礎』[*12]第1章のモデルはその試みと言えます。これは、不確実性がないモデルで、万事キッチリ決まることが前提されていますので、合理的期待どころか、人々は将来の価格を完全予見することになっているのですが、それでもこのような結論が導けるわけです。このモデルに、貨幣数量説的な物価決定と、ルーカス型の貨幣発行ルールを持ち込めば、完全雇用のもとで本質的にルーカスモデルと同じものが再現されることが示されています。
[*9]むしろルーカスの真意は、誰もが政策無効になると確信するような前提でモデルを立てておいて、しかし、予期されざる政策が取られれば実体経済に影響するということを示すことの方に目的があったと言える。「1972年論文でルーカスが目指したのも、一般の理解のように貨幣の短期的・長期的な中立性を示すということではなく、むしろ、それがどのような現実的条件の下で破れるかを考えることであったのだと見なされうる。」山崎好裕「ルーカスの始源から──マクロ合理的期待モデルの誕生と屈折するシカゴ」『経済学史研究』第54巻第2号、2013年。
[*10]P. A. Chiappori and R. Guesnerie, “The Lucas equation, indeterminancy, and non-neutrality: an example,” Economic Analysis of Mardets and Games, ed. P. Dasgupta, D. Gale, O. Hart and E. Maskin, The MIT Press, Cambridge, 1992.
[*11]K. Otani, “Rational Expectations and Non-Neutrality of Money,” Weltwirtschaftliches Archiev, Vol. 121, 1985.http://download.springer.com/static/pdf/594/art%253A10.1007%252FBF02705820.pdf?auth66=1390480040_8bd2ae38c8d30d57eec25a69c315ecb1&ext=.pdf
[*12]勁草書房、2011年。
[*13]この二つの前提を、大瀧は「デノミ」と解釈している。手持ち貨幣の額が比例的に増え、それで買えるものが不変ということは、これまでの千円を新二千円と呼ぶことにすることと同じだというわけである。何事も起こらないのは当然だとされる。同上書38ページ。
合理的期待で予想される「バブル」
さてその後、合理的期待や完全予見による将来予想形成を前提することは、市場メカニズム万歳論とは関係なく、それによって市場の不安定性を示すこともできるとする研究が普通に生み出されていくことになります。
それがはっきりと示された最初の研究の一つは、「合理的バブル」のモデルだったと思います[*14]。
株を持っていたら、その株の会社が利益を上げたらそれが配当としてもらえます。土地を持っていたら、それを誰かに貸して事業に使ってもらったら、地代がもらえます。そしたら、株の価格や土地の価格は、本来だったらどうやって決まるかと言うと、そうやってもらえる配当や地代が、あたかもなんらかの資金を銀行に預けたときにもらえる利子とみなしたときの、その預ける元手の資金額と同じになるように決まります。このような価格を「ファンダメンタルズ」と言います。
ところが、株や土地は値上がりすることがあります。値上がりして、買ったときの価格よりも高く売れたら、その差額分は配当や地代にプラスするもうけになります。そうすると、値上がり分もプラスしたもうけを、あたかも利子と見立てた元手の資金額で、株や土地の価格が決まります。これは当然、「ファンダメンタルズ」よりも高くなります。このファンダメンタルズよりも高くなった分が「バブル」と呼ばれます。
さてそうすると、人々が株なり土地なりの何らかの資産について、価格がファンダメンタルズを離れて一定率で上昇し続けるという予想を持ったとしましょう。その値上がり分を含めたもうけから計算される毎期の資産価格が、ちょうどこの一定率で上昇する価格の予想とつじつまが合っていたら[*15]どうなるでしょうか。
仮に一時的に資産価格がこの予想の価格よりも下がったとしましょう。たとえ自分では、それはファンダメンタルズに近づく正常化の動きだと思っていたとしても、他の人々がいままでどおりの値上がり予想をしていると思うならば、それを売ってしまうことは得策ではありません。人々はその資産を、安値の買いときだと判断するでしょう。同じおカネをかけるならば、銀行に預けるよりそれを買った方がもうかると判断し、自分もそれを買いに走ります。実はみんな同じことを考えて買いに走るので、結局その資産の価格は、もとの予想された価格に戻ります。「バブル」が一種の均衡になるのです。
つまり、人々がバブルを予想して、それに基づいて各自自分が最適になるように行動すると、その合成結果が予想通りのバブルを生み出してつじつまが合ってしまい、そこからはずれることができなくなるということです。
でも、本来社会的ニーズのあまりない事業だったのに、その会社の株がバブってどんどん値上がりしちゃったら、会社はそれで簡単に資金調達してしまい、労働や生産手段などの生産資源を、本来の社会的ニーズ以上に過剰に吸収してしまうかもしれません。主流派経済学者の好きな言い方で言えば、「資源配分の効率性」が壊れちゃうということです。こんなことはいつまでも続くことはなく、いつかはバブルははじけちゃうのですが、でも誰もそれを止めることができないということになります。
私が昔大学院時代に最初に「合理的バブル」という言葉を聞いたときには、「なんちゅうクダラナい概念や」と思ったものです。「バブル」というものは、合理的期待や完全予見で予想されるものではなくて、何かもっと非合理な思い込みだというところに問題点の本質があるように思ったわけです。
ところがそれは違ったわけです。単なる非合理な思い込みでバブルが起こるものならば、人々が賢くなってそんな思い込みをしなくなればバブルは起こらないことになります。いざバブルが起こっても、「これはバブルだよー」と経済学者が叫べば、バブルはたちまちストップするはずです。
しかし、「合理的バブル」の理論が示しているのは、もっと深刻な事態です。みんなこれはおかしいと思いながら、しかし、自分が少しでもマシになるように、みすみすチャンスを棒に振らないように、冷静合理的に振る舞ったならば、その結果としてバブルを推進するということになる。しかもそれが予想通り当たっているわけだからはずれることができないということです。どんなに頭のいい合理的な人たちであっても、個々人の努力やモラルに任せるかぎりは、ここから逃れることができないという事態です。
勘のいい読者はおわかりのとおり、これは、「ゲーム理論」で説明されている事態と同じです。
今回は、主に1980年代以降、マクロ経済学の分野で隆盛した、フリードマンやルーカスさんの理論を見ました。その要点は、「予想は大事」ということでした。
一方、その同じ1980年代、ミクロ経済学の分野では、「ゲーム理論」と呼ばれる手法が爆発的に発展を始めていました。そしてやがてこの手法によって、制度や慣習など、従来は社会学や法学の分野に扱いがまかされていたようなものが分析されるようになります。
そしてここでもキーワードは、「予想は大事」ということになります。次回はこのことを見ていきましょう。
[*14]解説は、Brunnermeier, “Bubbles,” The New Palgrave Dictionary of Economics, 2008.http://www.princeton.edu/~markus/research/papers/bubbles_survey.pdf
[*15]資産価格(のバブル部分)の上昇率がちょうど利子率に等しければそうなる。これは期待値が利子率に等しければいいので、実現した上昇率が利子率よりも高いことはあり得る。
連載『リスク・責任・決定、そして自由!』
第一回:「『小さな政府』という誤解」
第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」
第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」
第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」
第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」
第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」
第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」
第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」
サムネイル「Milton Friedman for PIFAL」Arturo Espinosa
プロフィール

松尾匡
1964年、石川県生まれ。1992年、神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。1992年から久留米大学に奉職。2008年から立命館大学経済学部教授。


