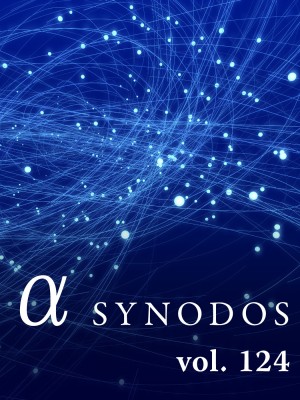2013.10.17

「第三者による検証」という言葉をとらえ直す――事故や災害の検証を行うべきは「誰」なのか
事故や災害の検証を行うべきは「誰」なのか
事故や災害が発生する。そしてその再発防止のためには、責任追及とは切り離した形での検証(調査)を行うことが必要である、という主張がなされる。またこの再発防止のための検証は、「中立的な」もしくは「第三者的な」立場から行われることが肝要であるとされる。
これまでこの第三者的視点は、「専門家」の側から提示されることが常であった。そしてその対となる「被害者(遺族や負傷者やその家族など)」の言葉は、専門知識をもたない素人の意見として、怒りや悲しみの感情が先に立つ人々の主張として受け止められがちであった(*1)。
(*1)柳田邦男「この解説書の大きな意義 納得感のある開かれた事故調査への一歩」http://www.mlit.go.jp/jtsb/kaisetsu/nikkou123-kikou.pdf (2013.9.24現在)
また場合によっては、被害者の言葉は、客観性や科学性を重視すべき検証を妨げるものとして位置づけられ、検証の場から排除される傾向が強かった。しかしそうなのだろうか。被害者の声は「素人の」「感情的な」ものばかりなのだろうか。
「2.5人称の視点」をもつ専門家
作家の柳田邦男氏は、フランスの哲学者ジャンケレヴィッチの「死の人称性」という概念をもとに、被害者視点にたった上で検証(事故調査や対策立案)を行うことの重要性を「2.5人称の視点」という言葉で表現している。
柳田氏は、検証を行う上で「もし自分が事故にあっていたら」と考えるのは1人称の視点、「もし自分の家族や大切な人が事故にあっていたら」と考えるのは2人称の視点、専門的な知識だけに基づいて判断するのは3人称の視点。そして1人称、2人称の視点をいれつつ、専門家として冷静に判断するのが「2.5人称の視点」であるとしている。
また、航空・鉄道事故調査委員会の委員であった黒田勲氏は生前、「学識経験者(専門家)というのは、『有』学識『無』経験者なんだよね。その事故を経験していない。だから常に事故調査や再発防止策の立案に、経験をどう役立てることができるかを考えなければならない」と語っていた。
この二人の専門家の主張は、専門的な知識に裏打ちされ、真実を知る者と認識されやすい専門家の「力」に対するいさめであるとも言えよう。第三者の視点で専門家が十分に配慮して検討したとしても、そこに見落としの可能性は残る。それを少しでも埋めるための方法として、被害者だからこその気づき、被害者が苦悩の末にこだわり抜く要素も含めた形で、専門家が検証に臨むことこそが、事故の再発防止や被害軽減につながるという主張でもある。
「被害者の社会的責任」という考え方
筆者は、2005年に発生したJR西日本福知山線事故の被害者らをはじめとして、国内で発生したさまざまな事故、特に公共交通事故の被害者の方々と活動をともにし、また研究の一環としてインタビューを行っている。
その中で、公の場での強い言葉としては語られることは少ないが、『被害者としての責任』『被害者だからできること、言うべきこと』『よりよい被害者でありたい』というような言葉で、「被害者の社会的責任」とも呼べるようなことがらに、被害者自らが言及する場面に居合わせたいくつかの経験がある。
筆者がここで「被害者の社会的責任」と表現するものは、被害者(すべて)が行うべきことという意味ではない。被害者という立場になった人の心身の痛み、平穏な日常を破壊されたことの影響力を考慮すれば、それらの人々はさまざまな社会的支援を受け、自らの回復を最優先する立場にある。
一方で、被害者の想いや状況はひとつに収斂するものでもない。おかれた状況によっては、自らが遭遇してしまった事故の原因究明や再発防止策の立案に積極的にかかわり、「被害者の社会的責任」とも呼べるものを全うしたい、そう考える被害者も存在するのである(*2)。
(*2)被害者の考え方も一様ではない。本稿で述べるように被害者の社会的責任を強く自覚し、積極的に活動する被害者もいる一方で、活動に係わっていても強く社会的責任を自覚しているわけではないと話す被害者も存在する。また、当然のことながら、被害者自身の人称も異なる。その意味で被害者がもつ「2.5人称の視点」の背景や実態はさまざまである。本稿では、被害者としての責任を意識し、発信しようとする強い想いを持つ人々を中心に記述していることを付記する。
1985年に発生した日本航空機墜落事故の遺族である美谷島邦子さんは、『遺族である私にできること、遺族だからできること』があるとその著書に綴っている(*3)。
(*3)美谷島邦子、御巣鷹山と生きる 日航機墜落事故遺族の25年 新潮社 2010
その上で、社会的には注目されにくい事故(多くの場合は、被害者数が少ない事故)の被害者と比較して、『私たち遺族は、大事故だったが故に、こうして発言の場をいただいた』という言葉とともに、加害企業や報道機関、規制機関がその声に耳を傾けやすい立場だからこそ、個人の感情を超えて、発言するべきことがあると語っている。これは、社会的に注目をあびることになってしまった事故や災害の被害者の中に存在する、あるひとつの想いである。自らの事故の原因究明を求めるだけではなく、自らの生活を破壊した事故を社会の「負」の共有財産としてとらえ直し、二度と同じような事故を起こさせないという強い想いである。
このように被害者としての社会的責任を果たそうとする人々は、専門家とは別の仕方で「2.5人称」の視点から、事故の再発防止に寄与しようとする人々であるとも言えよう。そのような被害者の声は、事故や災害の検証において、被害者の声というデータとして位置づけられるだけで十分なのであろうか。もう一歩踏み込んだ形で検証にかかわる仕方がありうるのではないだろうか。
見守り続ける被害者として
事故や災害の検証にあたって、データに裏打ちされた専門家の知見は不可欠である。その一方で、専門家はさまざまな事故に横断的にかかわる存在である。その意味で、「事故」とは一定の距離をとらざるを得ないし、検証の後の時間も含めた形で、あるひとつの事故だけに深くかかわり続けることには物理的な限界がある。
それと対置される被害者は、事故の後の時間を「自分たちに降りかかった事故」とともに生き続ける人達であるように筆者には見える。被害者も24時間常に、事故のことを考え続けているわけではないだろう。しかし同時に、忘れたいという気持と、忘れない、忘れられないという気持のはざまを揺れ動きながら、その事故は被害者の日常生活の傍らにある。そしてふとしたきっかけで、事故の記憶が浮かび上がる。
そのような日常の中で被害者と呼ばれる人々は、再発防止策はどのように実行されるのだろうか、その対策は時間の流れにより形骸化しないのだろうか、新しい知見が発見されたときそれが反映されるような枠組になっているのだろうか、という形で検証を見つめ、そして検証の「後」にも想いを馳せている。
私たち社会の一人一人は、いつか自分自身や自分の家族が同じような事故に巻き込まれるかもしれないという意味で、潜在的な被害者であると筆者は考えている。そうした視点からみれば被害者と呼ばれる人々は、検証から得られた知見が、適切に反映され続けることを見守る役割を、社会の代表として担っているとも言い換えることができるのではないだろうか。
検証や再発防止策よりも、まず被害者が求めていること
しかし、そのように被害者の社会的な立場というものに目をむけ、さまざまな活動や発信をする人々も、最初から「2.5人称」の視点で事故と向き合っているわけではない。
事故原因を追及したいという想いも、それを再発防止に役立てて欲しいという想いもそこには存在する。しかしそれより目の前にあるのは、ごく当たり前の個人的な想い。自分の大切な人を襲った悲劇の詳細を知りたい。その時、何がどのように起こって、その瞬間に自分の大切な人が何を感じたのか、その時の周りには誰がいて、どのような状況だったのかを知りたい。そういう想いなのだろう。
遺族の著作では、この「自分の最愛の人の最期を知りたい」という記述を数多く見つけることができる。そこで求められているのは、事故調査報告書で求められるような客観的事実やデータだけではない。その時に、自らの大切な人に起こったことがらのすべてを、事故や災害に出逢ってしまった被害者の側から見つめ直し、その状況に同化したいという強い想いである。
JR西日本福知山線事故は、その事故の凄惨さから、亡くなった家族の乗車位置はおろか、亡くなった家族の乗車していた車両すらわからない遺族が存在した。そのような中で『私は娘が最後に座っていた同じ座席に座ってあげたいんです。最後に握っていたであろうつり革につかまってあげたいんです』というある遺族の言葉に後押しされて、被害者(遺族と負傷者)が協力して自主的に乗車位置を確認するための情報交換会が開催された(*4)。
(*4)JR福知山線脱線事故被害者有志 JR福知山線脱線事故 2005年4月25日の記憶 神戸新聞総合出版センター 2007
この情報交換会には、身体の傷をおして、また事故の惨状を語るという心の負担を引き受けて、数多くの負傷者が参加し、遺族と協働で乗車位置の確認につとめたと言う。
大切な人が事故にあってしまった状況を知りたいという想いは、遺族だけのものではない。負傷者の家族も、事故で受けた心身の傷とともに懸命に回復しようとする家族のために、その時に何があったのかを知りたいと語る。
JR西日本福知山線事故の負傷者の家族である三井ハルコさんは、『私はいまだに事故当時のことをもっと知りたい。映像もみたい。(中略)我が子がどんなところにいて、どんな格好で、どうやって助け出されて、だからここが痛くて、だからこういうところが不自由で、だからこうなっているのというのは知りたい。(中略)あの子のことはあの子にしか分からないんだけど、でも分からないから、せめてその事実の断片みたいなところを共有したい』と語っている。
前述の美谷島邦子さんが『亡き人を思い、その面影を心にしまう、そうした場所が必要だと思う。そこで自分の過去を整理しながら、自分の人生と、その人の物語を紡ぎ直していくことができる。それが、二度と繰り返させないという思いにつながっていく』と著書の中で語るように、まずは一人称、二人称の視点で事故を見つめ直す。どんな些細なことでも可能な限りの事実の断片を拾い集める。そして被害者それぞれが自分にとっての事故を語り直す。それができるようになってこそ初めて、「2.5人称」の視点をもつ被害者が生まれてくるのだろう。
専門的な検討と、被害者の視点の「交点」
被害者自らが事故や災害について語る言葉は、この個人的な想いという文脈でクローズアップされることが少なくない。その言葉はどちらかといえば、被害者の感情的なものとして切り取られがちである。そして事故調査や再発防止策の立案という、客観性や科学性が求められる場面とは棲み分けたかたちで取り扱われる。本当にそれらは全く別のものなのだろうか。そこに接点はないのだろうか。筆者は、そこにある種の落ち着きの悪さを感じ続けている。
現代社会は高度に発達した科学技術社会でもある。筆者が出逢ってきたさまざまな事故は、そのどれもが専門的・科学的知見の粋をあつめて「安全に運用されている」と思われていた、そういう科学技術の産物である。
その科学技術によって、ある日突然、事故が引き起こされる。そしてそこには、心身の傷もさることながら、その生活のすべてを根こそぎ変えてしまうような暴力的な被害が現れる。その被害のあり様を見せつけられたとき、私たちはこのようにも感じるのではないか。客観的な第三者が、専門的な科学的な知識が「正解」を導き出してくれるのなら、なぜ、いまここにあるこの状況は生まれているのだろうと。どうして専門的な知識は、この事故を未然に防ぐことができなかったのだろうと。この再発防止を考えるときに、専門的な知識だけを重視することが、「正解」にたどり着く道なのだろうかと。
加えて事故や災害の検証は、どうして自分の大切な人がこの事故や災害で命を失わなければならなかったのか、どうして自分が、自分の大切な人がこの事故や災害で心身の傷を負わなければならなかったのか、という被害者の問いに応える役割を担うことも求められる。その意味で事故や災害の検証は、専門的検討と被害者視点の交点を見つけていくプロセスを通じて、被害者一人一人が自分にとっての答えを探し出すためのもの、と言えるのではないだろうか。
事故や災害の検証を行うべきは「誰」なのか、改めて
筆者はここまで、被害者が検証にかかわることの意味について、記述してきた。その一方で、被害者が常に事故や災害の検証にかかわるべきとは言い切れない、とも考えている。
筆者がさまざまな被害者の話を聴く限り、被害者とよばれる人々が自らの強い想いをいったん脇におき、「2.5人称」の視点をもつことはそれほど容易ではない。事故や災害からの時間、被害者自身が一定程度の心身の回復に至るまでの十分な社会的支援、同じような経験をもつ被害者との出逢い、それらを通じて自らの経験を客体化する機会、その他にもさまざまな状況が整うことが不可欠である。また状況が整ったとしても、そのプロセスには相当の葛藤を伴う。その意味で、すべてのタイミング、すべての事故で「2.5人称」の視点をもつ被害者がうまれるとは言えないのである。
しかし一方で、その事故や災害の検証がおかれた文脈によっては、被害者の直接的な参加が重要な意味をもつ場合もある。
JR福知山線事故では、この事故の調査にあたっていた航空・鉄道事故調査委員会(当時)の委員からJR西日本社長に対して情報の提供がなされ、また同社長の依頼により、委員会において委員が事故調査報告書案の一部修正を求める発言をするといういわゆる情報漏洩問題が2007年に発覚した。
この情報漏洩問題の検証委員会(「運輸安全委員会福知山線脱線事故(情報漏洩問題に係る)調査報告書の検証委員会」)(*5)には、専門家のみならず、遺族や負傷者、その家族といった被害者自らも委員として、その検証に参加した。
(*5)福知山線脱線事故調査報告書の検証等について http://www.mlit.go.jp/jtsb/fukuchiyama/fukuchiyama.html(2013.9.24現在)
これは、第三者性をもって事故調査に当たる公的機関(専門家機関)である「航空・鉄道事故調査委員会」の委員による情報漏洩という事態の深刻さの裏返しでもある。航空・鉄道事故の「専門家」に対する極端な信頼低下という文脈では、別の第三者(専門家)による検証のみならず、この問題について最も厳しい目をむける被害者自らが、その検証に参画するしかなかったのである。
結果として、情報漏洩問題の検証委員会は、「(この情報の漏洩やそれを受けた委員の発言により)報告書の当該部分が修正されることはなかった」との結論を出した。被害者自らが、丹念に検証作業にかかわり、それでもなお、情報漏洩そのものは深刻な問題であったが、問題とされた委員の行為が報告書の内容を歪めることはなかったと判断したのである。
事故や災害の検証は、無条件に第三者(専門家)が行うべきであるという前提にたつのではなく、まずはその検証がどのような文脈で、どのような目的で行われるのか、ということから問い直されなければならない。その結果として、即時性がもとめられる検証や、専門的・技術的な内容が中心となる検証の場合は、専門家主導で行うことが適切であると判断されるだろう。
その一方で福知山線事故のケースのように、そもそも検証のあり様や専門家に対する不信感が根強い場合には、被害者自らが直接的に検証にかかわるという方法もあり得るだろう。事故をとりまく状況によっては、直接的な被害者(遺族や負傷者やその家族)のみならず、間接的な被害者(鉄道事故で言えば、沿線住民の方や、被害者以外の鉄道利用者など)の声を取り入れることが必要となる場合もあるだろう。
この筆者の主張は、「検証する人として誰がふさわしいのか」を誰が選ぶのか、という問いにもつながり、その答えにたどり着くのは容易ではない。しかし、あってはならない事故や災害を目の前にして、私たちの社会に求められることは、既存の価値観や知識の中で「回答に近い」処方箋を探す力ではなく、まだ見たこともない処方箋を自ら書く力なのだと思う。
謝辞
本原稿の執筆にあたっては、JR福知山線事故・負傷者と家族等の会(空色の会)の三井ハルコさん、坂井信行さん、津久井進さんから示唆に富む意見を頂戴しました。改めてここに御礼申し上げます。
(本稿は、「α-Synodos vol.124(2013/05/15) 基本に戻って問い直す(https://synodos.jp/a-synodos)」に掲載された原稿を一部加筆・修正したものです。)
サムネイル「JR福知山線脱線事故」Jun Otani
http://www.flickr.com/photos/snapman/177204591/
湯浅誠×大西連「社会的な綱引きを超えて――これからの生活困窮者支援」
根本敬「政治家アウンサンスーチーをどう見るか」
大野更紗「さらさら。」
標葉隆馬「東日本大震災――いま、もう一度確認したいこと/目を向けたいこと」
八木絵香「『第三者による検証』という言葉をとらえ直す――事故や災害の検証を行うべきは「誰」なのか」
プロフィール
八木絵香
1972年生まれ。大阪大学コミュニケーションデザイン・センター准教授。社会的にコンフリクトがある科学技術の問題について、意見や利害の異なる人同士が対話・恊働する場づくりを主な研究テーマとしている。関連する著作に,「科学的根拠をめぐる苦悩——被害当事者の語りから」中村征樹(編)「ポスト3.11の科学と政治」ナカニシヤ出版