2015.11.20
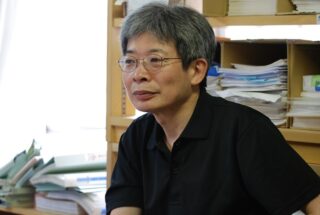
演劇と民主主義――青年団という冒険
平田オリザ氏は、青年団を率いる劇作家・演出家であると同時に、こまばアゴラ劇場のオーナーでもある。こまばアゴラ劇場はたった60席の小さな劇場である。しかし関東の小劇場ファンなら訪れたことのない人はいないかもしれないほど、現代演劇の発信地として機能している。1983年の青年団旗揚げから30年あまり。青年団からは多くの劇作家・演出家・俳優が輩出し、ごまばアゴラ劇場は多くの観客を育ててきた。小さな劇場が大きな存在感を持つのはなぜなのか。今回は「集団」と「場」についてを中心に話をうかがった。(聞き手・構成/島﨑今日子)
民主主義とは何かをずっと考えてきている
――9月19日、安保法案が可決されたあとに、国会前でSEALDsのマイクを握ってスピーチされました。「私は東アジアの未来に悲観していない。安倍首相がアジア存立の危機になっている。安倍さんを替えればいいのだ」と。
この7月、8月はアジアツアーに出ていて日本にいなかったので、たまたまあの日になったんです。うちの劇団(青年団)の若手の演出家がSEALDsの映像記録を撮る手伝いをしていて、あの場で奥田(愛基)さんに紹介されたら、ちょっとしゃべってくれと言われて。
韓国や中国で芝居を上演すると、新聞記者のインタビューも毎日のように受けます。そうすると、安倍さんが海外ではレイシストだと思われていることをひしひしと感じるんですね。それはイメージの問題なので、払拭するのは難しい。日本国内と海外でのイメージのずれがここまで大きくなっているのは危険な状況だと思って、そういう話をしました。
――ずっと演劇の力について考えてこられたと思います。代表作の「東京ノート」をはじめ、平田作品を串刺すものは民主主義です。
民主主義とは何か、あるいは民主主義を壊すものは何かということをずっと考えてきているのだと思います。演劇は、哲学とともに、2500年前に民主制が生まれたと同時にできてきたものです。哲学と演劇が、民主制や熟議を支えるひとつの訓練方法、ある種の思考実験だと思っているんですね。演劇をやったり、見たり、そこにかかわったりすることによって、異なる感性を持った人たちがどうやって集団を、共同体を形成していくかという仮想実験が行われる。演劇というのは民主主義を支えるもっとも重要なファクターのひとつで、逆に言うと日本がダメなのは演劇をやらないからだというのが僕の考えです。
民主主義って、ひとつには個が確立されているということだと思うんです。ひとりひとりが自分の意見を持ち、それを表明することが保証されていること。もうひとつは、たぶん場だと思う。その個が集まれる場があること。SEALDsのコールで「民主主義ってなんだ、これだ」があるんですが、「民主主義ってなんだ、ここだ」と言ったほうが盛り上がると思うんです。あそこに民主主義はあったわけだから。今度、奥田君に会ったら言います。
――オリザとは、ラテン語で稲の意味だとか。珍しい名前ですが、日本でお一人ですか?
僕の知ってる範囲であと二人います。このくらい変わった名前だと、教えてくれる人がいるんですね。他の二人は女性で、ひとりはお父様がどこか北海道の大学の農学部の先生で、娘さんにオリザとつけたと聞いています。
――オリザという特殊な名前を背負ったことに何か意味は、ありました?
今思えば、あるでしょうね。オリザという名前をつけるような両親に育てられたという意味で。特に父親が変わっていて、もうひとつの僕の名前の候補は栄でした。大杉栄の栄です。こまばアゴラ劇場をつくったのも父で、名前だけではなくて、「それは何が人と違うの?」ということを、子どものときからずっと言われて育てられてきたので。
――幼稚園のときから、何がほしいのかをお父さんに伝えるために企画書を書いたとか。
ユニークネスがないとダメなんです。僕は高校もあんまり行ってなかったんです。これも今思えばですけど、プレッシャーが強かったんですよね。この町(東京大学駒場キャンパスのある目黒区駒場周辺)は、子どものころにちょっと成績がいいとその子は東大に行くものだと思って育てられるんですよ。で、このまま行けば東大に行けるだろうけど、ずっとこんな競争を続けるのかと思って、子ども心にしんどかったですね。まだ僕たちの世代は競争の世代ですから。
――高校を休学して16歳で世界一周の旅に出られたのも、人と違う人生を選んでいかなければいけないという呪縛があったからでは。
それで、もっと競争の激しい世界にいってしまい、もっとしんどい人生になってしまいました(笑)。
――そうですね(笑)。23歳で、1億1000万円の借金を背負って、アゴラ劇場の支配人になられた。お父様は、息子に借金を背負わすことに抵抗はなかったのでしょうか。
父親は私以上に楽観的な人間だったので、返せると思ってたんじゃないですか。母親からはときどき感謝の言葉を聞くんですけど、父親からは聞いたことがない。父は、息子にこの劇場をとられたという意識の方が強いぐらいじゃないですか。僕をライバルだと思っていた。
熱狂とどう距離をとるか
――著書に「演劇だけが自分を興奮させてくれた」「孤独だ」とありますが、鈴木忠志さんも同じことを言われていました。
演劇人だけじゃなくて、芸術家全般がそうだと思います。赤ん坊は、最初の言葉がだいたい「ママ」でしょ。それは、自分と母親は違うものだということに気がついた瞬間だと思うんです。そのとき、赤ん坊はものすごい孤独を感じているはず。僕はそういうことが感覚として残っている人間が芸術家になると思っているので、ある種の絶望みたいなものがあるでしょうね。現実にも、わかってもらえないということがよく起こります。
僕の場合は劇作家と演出家と両方なので、そこでバランスをとっているようなところがあります。劇作家はひとりの作業ですが、設計図だけ書いて渡しちゃうっていう、小説家とも違う作業です。一方、演出家は人のまんなかにいます。ただ、人といるのに誰にも理解してもらえない瞬間があるので、より孤独だという言い方もできます。新しいことをやろうとすればするほど、基本的にはわかってもらえません。
――鈴木さんは、孤独だからこそ演劇という共同作業に興奮し、熱狂したと。平田さんもそうなのでしょうか。
それは、もちろんあります。ただ、世代が違うので、逆に言うと、その熱狂からどれだけ距離を置くかというところで、戦ってきたところがあります。今の時代に、これだけの集団を持続させるのはとても大変なことです。
僕たちの世代では、小劇場で若い人たちが持続的に入ってくる劇団は他にほとんどありません。で、それは新しい革袋みたいなものがないとできない作業でしたから、まさに熱狂とどう距離をとるかというのがいちばんのパラダイムシフトでした。
――演劇はずっと政治と密接な関係にありましたが、平田さんの世代ではもうそれはなかった。むしろ冷めていたというか。
少なくとも集団に政治性を持ち込まないというのは、最初からあったと思います。前の世代の野田(秀樹)さんとかだと、意識してどうするかというのはあったと思うんですね。
あるイベントで、竹内銃一郎さんと野田さんがモメたという話があります。集団とか演劇に対する考え方にずれがあり、野田さんは、「政治性とか、理想論でやってるわけじゃない」と、竹内さんよりもクールなわけですよ。そこらへんからやっぱり変わってきたと思うんですけど、それをわざわざ言わなきゃいけなかった世代と、もうそういうことは前提だっていう僕たち世代とは、また大きく違う。
――思想や理想がないと集団の継続は難しいでしょう。その熱狂に代わるもの、鰯の頭のようなものが必要になるのでは。
もちろん経済的に成り立てばいいんですが、それはもう無理なので、そうすると、劇団を維持するため何か、架空のものをつくらなければいけないわけですよね、普通は。僕らはそれをつくらないでやるってことを、ずっとずっと考えてきた30年ということです。だから、文化大革命みたいなものだと言っているんです(笑)。途中にオウム事件がありましたから、より一層、集団を維持するのが難しくなった。
当時、劇団を主宰していた人間で、まともな人間はみんな、自分たちとオウムがどこが違うのかを考えたと思うんです。明らかに違うんだけど、ほんとにどこが違うのか。そのなかで劇団のあり方や劇場のあり方を考えざるを得なかったところはあると思います。オウムと前後して新国立劇場の問題があり、その後に文化芸術振興基本法などの制度をつくる時代になってきた。偶然と言えば偶然なんですが、僕の演劇にかかわる時間帯と、そういう時代が重なってしまったということはあると思います。
――オウムの前から平田さんは現代口語演劇をやり、いわばずっと前衛です。愚問ですが、コマーシャリズムに行こうとは?
あまりなかったですね。性格的なこともあります。研究者タイプというか、理論的なものが好きだというのがまずひとつ。それから、先程話に出たように借金があったので、中途半端に儲けても全然意味がなくて(笑)。若い作家が生活が楽になるから商業的なものをやるというのはわかるんですが、僕の借金は非効率な演劇では解決しません。だったらもっとほんとに他の、株とかやった方が儲かる(笑)。
ただね、今思うと借金があってよかったこともある。最近、若手によく言うのは、「借金はスランプ脱出を待ってくれない」ってことです。銀行は、書けないとか理由にならないんで。それだけはよかったかなと思います。
――1億1000万の借金は、新しい演劇をつくっていくための守護神だったという言い方もできます。
まあねえ、これがない人生が想定できないからわかんないですけどね。ただ、矛盾しているんですが、ときどき自分は頭がおかしいんじゃないかと心配になります。普通こんなに借金があったら、演劇なんて変なことはしないでしょ。
――そうかもしれないですね(笑)。話、戻します。集団の維持について、です。
現代口語演劇理論が89年から90年ぐらいにできていく過程で、やめていった人もいますが、残った人たちの間には、「集団でねばり強くやっていくしかないんじゃないか」というコンセンサスはありました。僕たちは電気の発見のようなすごくベーシックなものを発見したけれど、あまりにも地味だ、と。すごくたくさんの人がいっぺんに見に来ることが理論上、物理的に無理だったし、発見したものが熱狂しない芝居なわけだから、かつてのアングラの劇団のような熱狂でも維持できない。それで、集団の持続可能なシステムっていうのは相当考えましたね。
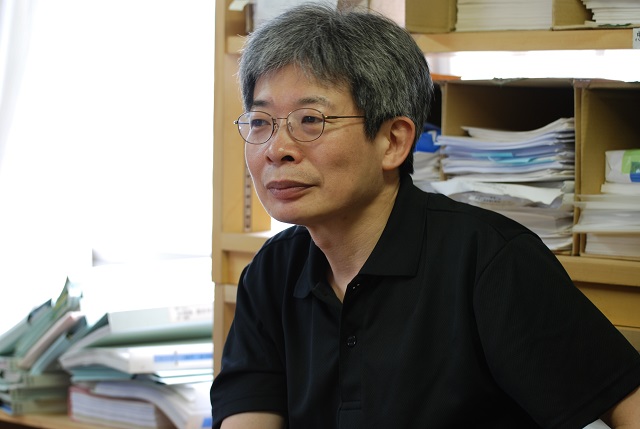
「鰯の頭」の代わりに、多様性を確保する
――具体的には?
当時は、主宰者がどんな端役の人にも「おまえの役はかけがえのない役だから」みたいなことを普通に言ってたんですよね。今も言うんだろうけど。でも、それは嘘なので、それは嘘だってことをまず認めようよと。そう言うことによって、ある女優さんがひとつの役を離さなかったりする弊害もあるわけです。だからそういう嘘はやめて、役が交換可能になっていくシステムをつくっていくことは、ある程度意識はしていたし、公言もしていた。
もうひとつ意識したのは規模です。現在、団員は、名簿上は百数十人います。海外にいたり、子育て中だったりいろいろいるので、実際にコアで活動しているのは50人ぐらいですが。ある程度規模が大きいと、いろんなやつがいても大丈夫なんですよ。
10人、15人だとみんなが一定の方向を向いてないときつくて、そこには何かの旗印や鰯の頭みたいなものが必要になるんですが、それがなくてもやれるようにするためには、ある程度組織を大きくして、多様性を確保しなきゃダメだということは最初から考えていたことなんです。
――スターシステムはとっておられませんね。
作風がそうだということもあります。青年団は30年やってて、役者の降板で上演中止は一回もないんですよ。結婚している人間も多くて、劇団員の子どもを合わせたら20人以上います。要するに、子どもを生んでも持続可能にする。育ててるあいだ2、3年休んでも戻ってこられる。20代で漠然と考えていた集団論が、40歳を過ぎてから機能し、ほんとに役に立っているという感じはありますね。
――俳優は喝采を求める生き物です。平田さんは「役者は駒だ」と公言されていますが、そう言われてよく耐えていられると思います。
そうですね。何が楽しいんだろう(笑)。ただ韓国でもフランスでもオーディションをやると、過去に僕の作品に出た俳優たちもみんなきてくれるということは、何か楽しいんでしょうね。
「演劇1」「演劇2」を撮った想田和弘監督に聞かれたことがあるんです。「僕が俳優に『0.1秒ゆっくり』とか指示するときの0.1秒って、どう決めてるんですか」って。もちろん、それは感覚的に決めるんだけれども、もうひとつは、「その俳優がしゃべりたい方向にしゃべらせてるんだ」という話をしたんです。
たぶん、武満(徹)さんの言葉だと思うんだけど、「その音が伸びたい方に伸ばす」という言葉があります。その俳優の身体が欲している間(ま)は、本当はその俳優にはわからないというのが僕の基本的な考えです。
Aという俳優にとってはこの瞬間のその台詞とその台詞の間は0.1秒でも、他の俳優が言ったらそれは変わるということです。だから僕の感覚でなく、実は俳優たちの感覚でやっているから、俳優たちは納得する。基本的にすぐれた演出家というのは、そういう要素を持っていると思うんですね。
――すみません。私、型でつくっていらっしゃるのかと誤解していました。
もちろん、もうひとつの理論として、言語構造で規定される部分はあります。でも、それは大きな部分であって、0.1秒とかの部分は俳優の身体によるんです。その両方の組み合わせで間が決まっていきます。
利賀村で合宿をして、鈴木さんの演出を見た若手の演出家が驚くのは、僕と鈴木さんの演出が驚くほど似ていることでした。しゃべり方は全然違うんだけど、もし字に起こしたらほとんど同じ、みたいな。鈴木さんもものすごく具体的な指示を出し、「もっと悲しそうに」とかいうことは絶対言わない。僕は、演出家というのは基本的にそういう仕事だと思っているんです。
――青年団のホームページには俳優の名前はなく、平田さんの顔写真しか載っていませんが、ヒエラルキーのない集団を目指しておられるわけではないのですね。
ええ、青年団は僕が絶対的な権力を持っているので。ただ、うちは、天皇制社会主義と呼んでいるんですが、一君万民と言ってもいいですけど、私に権力を集中させて、私が無私なら、平等なんですよ。
――(笑)でも、無私って難しいですよ。
とっても難しい。完全に実現しているとは思っていませんが、いちおうそういう理屈でやってるわけです。うちの演出部からたくさんの演出家が育ってきているのは、明らかに、そういう環境のなかで俳優と演出家がある程度対等な作業ができているからだと思っています。
ヨーロッパの劇場にはプロデューサーと芸術監督がいて、若手の演出家と俳優をマッチングさせて、演出家がそのなかで育っていく。それに近いシステムを日本で唯一持っているのが青年団だと思っています。次の世代からは、僕みたいなものを必要としなくても、劇場のシステムがきちんと機能すればそうなっていくと思っているんですけれども。
――権力って腐りますが、権力がなければ動かせないこともあります。
集団でやる芸術は、権力性を伴います。権力性を伴うんだということにどれだけ意識的かということの方が問題であって、権力性を伴っちゃダメだとなったら、たぶん、芸術ではなくなってしまう。学芸会のひとりひと台詞みたいな、そういうつまらないものになってしまう。だから権力性を伴うことを前提にしながら、たとえば俳優やスタッフ個々人の人格を損なわないようにするにはどうすればいいかということの方が大事だと思う。
――そのためのシステムをつくってこられた。
ある程度、ルールが必要だと思います。青年団の根源的なルールは、ルールはできるだけ少ない方がいいというルール(笑)。劇団をやりたくて、作品に対するロイヤリティーをもって集まってきているわけだから、基本的にはルールは要らないはずなんです。でも、問題も起こる。劇団の力がいちばん弱くなるのは、団員が不平等感を持つときなんですね。
だから不平等感を持たせないようなシステムをどうつくっていくかということを、ずっと考えてきて、そのために必要なルールをつくってきました。普通にセクハラ、パワハラの規定もあって、パワハラでやめてもらった人もいます。
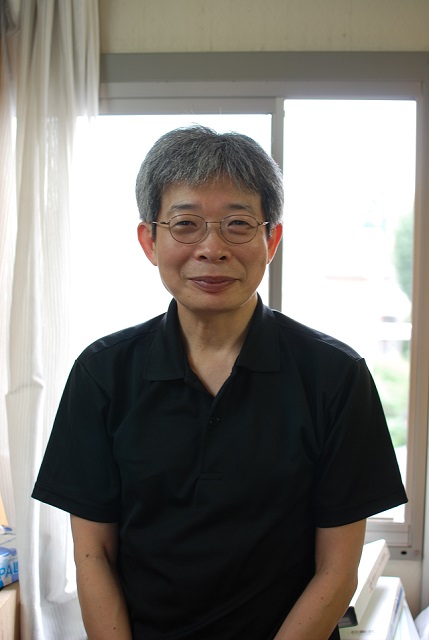
算盤がはじける人間も、政治家と話せる人間も必要
――劇団の他に、大学の教員をやり、地方自治体と組んでワークショップもやり、一時官邸にもいらした。それはすべては演劇のため、「演劇人がバイトしなくても食える状態を作るため」と発言されていますけれど。
厳密に言うと、僕は選ばれた俳優だけが食えればいいと思っているんです。要するに不平等なのが嫌なんですね。厳しい言い方をすると、才能がないのにずっと続けてるやつも嫌なんです。才能があるやつがとてつもない努力をして生き残って行く世界だと思っているので、そのことがちゃんと評価されるような演劇界でありたいというのがまずあります。
だからある種の競争のシステムはどうしても必要で、それが古い層からは反感を買うときもあります。劇場法なんていうのは、まさにある種の競争のシステムを導入することになりますから。
でも、少なくとも公的なお金で芸術活動をするからには、選ばれた者であるべきですし、選ぶ過程に透明性がなければいけないということを、僕は言ってきました。でも、世のため人のためにやっているつもりはなくて、基本的に自分の演劇のためにやっていることです。
――鳩山内閣の内閣官房参与に就任したときは、スピーチライターもされました。演劇人として、政治や行政にかかわる役目を一人で背負っておられるようにも映ります。
僕はヨーロッパで仕事をしていたので、それは当たり前だと思っていました。それに、文句だけ言ってるとか、泣き言だけ言ってるとか、ルサンチマンみたいなのは嫌なんですよ。
日本の文化政策にかんして、演劇、特に新劇は「貧乏だからお金をくれ」「ヨーロッパではこんなにもらってる」としか言ってこなくて、なぜ自分たちが社会のなかで必要なのか、自分たちにもっとお金がくればどういう社会をつくれるのかという提言はまったくしなかった。それはダメだろうというのがまずあるんです。
その上で、たまたまそういう役回りを背負った以上は、照れたり斜に構えること自体がかっこ悪いと思っているので、そういう態度はなしにしようというのもあります。
それから、これも本やいろんなところに書いてきたことですが、僕は18歳のときに大学検定試験を受けて、非常にひどい制度だと思い、それについて書き続けてきたら、20年後に改革がなされて高卒認定制度に変わった。20年間僕が言ってきたことが法的にもほぼ実現したというある種の成功体験があり、それは明らかに世の中のためになったんです。やりたいことをきちんと法律化したり予算化していくことは僕にとって、政治というイメージすらないぐらいで、当たり前のことなんです。
――「演劇1」に、平田さんがレシートを1枚1枚チェックしている場面があります(笑)。
あれはね、たまたま半年に1回ぐらいの作業を撮られたんです(笑)。でも、嫌いじゃないんで。たとえばよく言われることですが、明治維新のときに、坂本竜馬だけが経済的観念があるんですよね。商売人だから。
革命をするときには、算盤がはじける人間がたぶん必要なんだと思うんです。政治家と話せる人間も必要。演劇の場合には、鈴木さんがいて、鈴木さんと僕は24歳ぐらい違う。四半世紀に一人ぐらいこういうのがいないと、たぶん困るんだと思うんです。
――平田さん以降は、いらっしゃいますか?
そういう人間は、きっと出てくると思っています。ただ、最近ベテランの新聞記者と話しても、僕より下の世代の演劇人で、新聞に評論が書けたり、何か事件があったりしたときにコメントしたり、そういう人間が演劇界から出てきていないという話になる。僕の前には、井上ひさしさんや別役実さんらが連綿といました。本来劇作家には「この事象は演劇的にはこう見える」とか、そういう発言をする役割も社会のなかにあるので、そっちの方が心配です。
――一平田さんは海外での活動される時間も長い。でも、世界を舞台に仕事をする醍醐味は、さぞや大きいのでは。
単純に行きたいというのはありますよね。特に若いときには。今は、毎年向こうの劇場から依頼がきて作品を書くという大変恵まれたポジションにありますが、評価がはっきりしているので、やっぱりやりがいがある。フランスでは15年続けていますが、15年間、毎年作品を書いている海外の劇作家はフランスでもほとんどいません。向こうの作家は40代半ばで半分引退ですから。だから、メジャーリーグに似ていますね。毎年1軍でちゃんと試合に出られるか。それに伴って、お金も、全然違うので。
――いくらとは聞きませんけど、何倍ぐらい違いますか。
仕事によって違いますが、今度ハンブルグでオペラをやるんですね。オペラの演出ってほんとに「えっ!?」っていうぐらい高い。今年の2月に公演1年前の最終打ち合わせがあって、僕、人生ではじめて、ギャラを提示されたときに顔がにやけそうになりました。我慢して、「まあ、いいんじゃない」って、ちょっと不満げなぐらいの顔をしましたけど(笑)。
――あははは。最後に。平田オリザ55歳引退説がありますが本気ですか? あと2年です。
はははは。別に演出家や劇作家として引退するわけではなくて、劇団の座長を、55歳前後ぐらいにやめたいということは劇団員には言ってきました。天皇制社会主義みたいなものはほんとに体力がいるので、もう無理だろうと。一君万民の君が狂っちゃったら、大変なことになりますから。あまり迷惑をかけないうちに、一芸術家に戻ります。
公演情報
平田オリザ演劇展 vol.5
東京公演 2015年11月5日(木)〜11月18日(水)
こまばアゴラ劇場
プロフィール
島﨑今日子
ノンフィクションライター。京都府出身。新聞・雑誌等に数多く執筆。著書に『安井かずみがいた時代』(2013年、集英社)など。

平田オリザ
1962年東京生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。16歳で自転車で世界一周旅行を果たし、大学1年生で初の戯曲を執筆。大学在学中の1983年に劇団青年団を結成。1990年代に「現代口語演劇理論」を提唱し、多くの演劇人に影響を与える。1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。ヨーロッパ、アジア各国に活動の場を広げている。2003年日韓合同公演『その河をこえて、五月』で、第2回朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。近年はヨーロッパ、アジアの各国との国際共同製作作品を多数上演している。2008年から青年団+大阪大学ロボット演劇プロジェクトとしてロボット演劇『働く私』『さようなら』などを上演。著書に『演劇入門』(1998年、講談社現代新書)、『芸術立国論』(2002年、集英社新書)『わかりあえないことからーコミュニケーション能力とは何か』(2012年、講談社現代新書)など多数。


