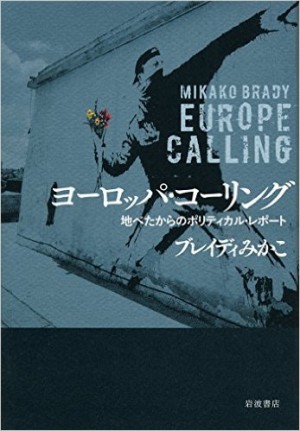2016.09.17
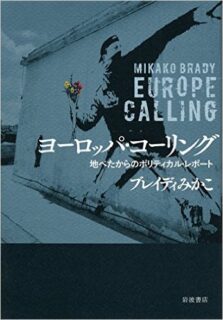
「もしもし、ヨーロッパです」「こちらは日本です」――階級の時代の回帰に寄せて
在英20年のライターで保育士のブレイディみかこさん。ブログでの発信や、著書『アナキズム・イン・ザ・UK――壊れた英国とパンク保育士』『ザ・レフト UK左翼セレブ列伝』(いずれもPヴァイン)は、音楽好きや英国に関心がある人びとを中心に熱く支持されていましたが、欧州の政治を鋭く捉えたYahoo!ニュースの記事により、さらに多くの読者がその文章の魅力と出会うこととなりました。
ブレイディさんの生活に根ざした視点、英国から日本社会を問う切り口、そして、読む人の心を打つ表現は、今、ますます注目を集めています。
6月には『ヨーロッパ・コーリング――地べたからのポリティカル・レポート』(岩波書店)が、8月には『THIS IS JAPAN――英国保育士が見た日本』(太田出版)が刊行されました。この新刊2冊を、著者であるブレイディさんご自身に読み解いていただきました。(岩波書店編集部)
EU離脱決定から1か月半が過ぎた8月8日、BBC2は国民投票までの離脱派・残留派双方の(ウソだらけの)PR戦、出来の悪いコメディのような政治家たちの権力闘争を総括した『Brexit—The Battle For Britain』というドキュメンタリー番組を放映した。狐と狸の馬鹿し合いのようなエリートたちのバトルを横糸にしながら、同ドキュメンタリーが縦糸として淡々と追い続けたのは、離脱に走っていく北部の労働者階級の人々のリアルな姿だった。
それらを対比させながら描いたドキュメンタリーのエンディングで、BBCの政治記者、ローラ・クンスバーグはこう言った。
「実のところ、ブレグジットとは秩序ある革命だったのです」。
◆ ◆ ◆
6月に刊行された『ヨーロッパ・コーリング』は、2014年から書き始めたYahoo!ニュース個人などの記事をまとめたものである。原稿整理のために2年前に書いた文章を久々に読んで驚いたのは、英国版こども食堂の話題から始まり、格差社会が国家にもたらすコスト、アンチホームレス建築の話へと続く拙著の冒頭部分は、まるで現在の日本のニュースを読んでいるみたいだということだった。
2014年の英国には政治的・社会的な閉塞感と、このまま保守党独裁が未来永劫に続くのではないかという諦念が蔓延していた。保守党政権がゴリ推しする緊縮財政のため、生活保護を打ち切られて餓死した人のニュースがあったり、ゼロ時間雇用契約の話があったり、暗い話題が続くのだが、スコットランド独立投票の話題でトーンが一変する。
ウエストミンスターは「彼らにそんな勇気があるわけがない」と直前までタカを括っていたのだが、独立派が勝利しかねないことが判明すると、首相、野党第一党党首、元首相など政界の要人たちがパニックしてスコットランド入りし、メディアは「為政者たちは粗相をしそうなほど焦っている」と書きたてた。
「もしかしたら政治というものは変えられるのかもしれない」
という英国民の意識の小さな萌芽は、あのときに芽生えたのではなかったか。実際、EU離脱が決まったとき、「スコットランドができなかったことを俺たちがやった」とパブや路上で口にした人を何人も目にした。
反緊縮と市民的ナショナリズムを掲げて独立派を率いたSNP(スコットランド国民党)は、2015年の英国総選挙でも台風の目になる。女性党首ニコラ・スタージョンが一躍選挙戦のスターになり、労働党とSNPの連立の可能性もささやかれ始める。
思えば、このときの選挙に勝ちたい一心で「EU離脱の是非を問う国民投票を行う」と口走ったのがキャメロン前首相だった。人間というものは、ビビると墓穴を掘るものである。その効果もあってか総選挙では保守党が大勝するのだが、時を同じくしてギリシャでは債務危機が持ち上がる。英国の「ピープル」(セレーナ・トッド著『ザ・ピープル イギリス労働者階級の盛衰』(みすず書房)によれば、英国英語のPEOPLEは単なる「人々」や「民衆」ではなく、「労働者階級」を意味するという)もギリシャ国民のように緊縮に痛めつけられていた。
だから「ピープル」はEUが強制する緊縮財政にギリシャ国民がNOを突きつけたことに共感し、それでも執拗にギリシャに緊縮を強いるドイツ主導のEUに対して「だいたい、俺らがあいつらを選んだわけでもないのに、どうしてあいつらはああも独裁的に俺らの生活を支配しているんだ?」と憤り、「EUにデモクラシーはない」と言うようになる。
この流れに乗って、労働党党首選でまさかの大勝を果たしたのが、反緊縮派の泡沫候補ジェレミー・コービンだった(彼は党首候補討論で堂々とEU批判さえした)。若者や労働者たちが彼を熱く支持し、ブレア派を筆頭とする労働党議員たちはまたもやパニックに陥る。
一方、スペインでは、やはり反緊縮を政策の柱とするポデモスが急激に勢力を伸ばし、「左翼は『ピープル』のツールにならなければいけない」と吠える党首パブロ・イグレシアスのカリスマも相まって、結党2年にしてスペインの第3勢党に躍り出る。
このように2015年は、欧州で新左派と呼ばれる勢力が思わぬ躍進を見せた年だったが、忘れてはならないのは、彼らは大前提として反緊縮派であり、現在のEUの在り方と、EUが強制する緊縮という病に反旗を翻したということだ。
この過去2年間の経緯を知れば、英国のEU離脱投票の結果を、単なる「右傾化の現れ」と呼ぶことはあまりにも一方的だ。そしてそこに至るまでの「もう一つの流れ」が、拙著『ヨーロッパ・コーリング』には期せずして記録されているように思う。
さて、このような英国や欧州の国々の動きを受け、わが祖国はいったいどうなっているのだろう。
スコットランド独立問題、反緊縮派たちの台頭、EU離脱。欧州では政治に再び「ピープル」が影響を与え始めた。これは下側に溜まったマグマの表出である。日本にも、同様の兆しはあるのだろうか。
そうした好奇心から日本に飛び、取材して書いた本が『THIS IS JAPAN』だった。
キャバクラ・ユニオンの労働争議では、150万円の賃金未払いを訴えているキャバクラ嬢に向かって、周辺の店のキャッチや黒服、界隈では有名人らしいホームレスの男性が、「働けっ」「働けっ」と執拗に罵声を浴びせる様子を見た。
日本の「働け」とはどういう意味なのだろう。と考えた。
貧困・格差の問題に特化した運動団体エキタスのメンバーにも会った。そこで感じたのはコービン現象につながる若者たちのマグマは日本にも溜まっているということだった。が、同時にこのエネルギーを吸い上げる経済政策をオファーする政治勢力が日本にあるのだろうかと疑問に思った。
いくつかの保育園も見学した。そこで目の当たりにした保育士配置基準は、保育士として働くわたしには衝撃的だった。1人の保育士が20人の3歳児を見ているという(英国は1人の保育士につき8人だ。帰国して英国人の同僚に話すと、「1対20って、何それ。羊飼いかよ」と言われた)。
そしてあらゆる園で見た、先生たちが作っておられるという牛乳パックの家具や備品。靴箱から部屋の間仕切りまであった。「Austerity measures!(緊縮措置!)」という英国の緊縮ジョークを叫びたくなった。手作りのこころも倹約の精神も素晴らしいが、それをしなければならない理由もまたあるということだ。欧州では行き過ぎた緊縮財政のために死人が出ているが、保育に十分な投資をしていない国は自らの未来を殺しているように見えた。
反安部政権デモを見に行ったときには、あまりにも整然と並んで絶え間なくラップコールを続ける規律正しいデモ隊に驚き、欧州のデモのような流動性や躍動感がないことに戸惑った。雲のように人が集まって散っていく「クラウド」型のデモが祖国では注目されているというが、ならば、日本の「グラスルーツ」はどうなっているのだろう(「グラスルーツ」型の運動とは文字通り、地域コミュニティーに根を張り、平素からどっしりとそこにあって、そう簡単に消えたり現れたりしない)。スペインのポデモスはグラスルーツの連合体だが、そうした動きは日本にはないのだろうかと思った。
山谷で80年代から日雇い労働者・野宿者支援に携わってきたグラスルーツの御大、共同組合あうんの中村光男さんに会いに行った。彼は反貧困ネットワークをこう総括していた。
「標語としては、垣根を越えよう、だったんです。労働運動も、社会運動も、自分たちの中に垣根を作ってしまっているから、それを越えていこうよ、と」
「越えられましたか?」とわたしが訊くと彼は答えた。
「いやだから、それが越えられなかった、っていう総括なんですよ」
「どうして越えられないんですか?」
「なんというか、……学び合わないんですよねえ。……はたと立ち止まって考える、学び合う、という習慣が日本の運動体の中にない」
NPOもやい、つくろいファンド東京では、困窮者の生活相談ボランティアに参加した。まるで支払い能力(税金、家賃、食費、ショッピング)のない人間は尊厳を認められていないのかのように力なく折れてしまった困窮者たちを目の前にし、日本の人権とは、払えない人間には認められない特殊な概念ではないかと思った。日本の教育の人権課題が知りたくて、法務省の「人権教育・啓発に関する基本計画」の「第4章 人権教育・啓発の推進方策」を読んでみると、ジェンダーや人種差別、高齢者、障害者などのいわゆる「アイデンティティ」課題は組み込まれていても、「貧困」という大項目が抜け落ちていた。
アイデンティティ政治と階級政治。
それはブレグジットが英国に突きつけたテーマでもある。
政治思想を分けるものは「オープンな世界を望むか、閉じられた世界を望むか」だと思っていた左派は、離脱に票を投じた労働者階級を「右傾化している」と単純に理解した。彼らは、長いことアイデンティティ政治にのみこだわり過ぎ、欧州の政治イデオロギーを分けるクラシックな概念であったはずの「上」と「下」、すなわち階級のコンセプトを忘れてしまっていたのである。
だが、それは好むと好まざるに拘らず、明らかに回帰している。
ガーディアン紙のライター、オーウェン・ジョーンズは先月、こう書いていた。
「左派は、本気でいま再び階級に焦点を合わせなければならない。1980年代以降(労働運動が潰され、旧産業が崩壊し、冷戦が終結した)、階級が表舞台に出ることはなかった。ジェンダーや人種、性的指向のほうがより重要で、現代的な問題のように見えた。だが、実のところ、それはどちらを取るかというような問題ではないのだ。例えば、階級を理解せずにどうやってジェンダーを理解するんだ?」
◆ ◆ ◆
「Europe calling(もしもし、ヨーロッパです)」
「This is Japan(こちらは日本です)」。
前者は劇的に動く時代の暴風に晒され、迷いながら変動を続けている。
後者だって前者の混迷を笑いながら傍観している場合ではない。
『ヨーロッパ・コーリング』と『THIS IS JAPAN』は、まったく別の地平の話のようであり、実は呼応している。