2013.07.09

自由と平等の攻防 ―― アメリカでの同性婚合法化の波を理解するために
米最高裁が伝統的な男女の結婚しか本当の結婚と認めないとした連邦法の結婚防衛法(DOMA=Defence Of Marriage Act)を違憲と判断したというニュースは日本でも大きく報道されました。それに付随して新聞各紙やテレビも、たとえば米国でのゲイの認知度の高まりや様々な社会的な変化を、さらには世界ではすでに15カ国で同性婚が認められていることなどを紹介しています。
ところが半年ぶりに帰国しているこの日本国内で、そういう事情が一般にどれだけ理解されているのだろうかというと、なんだかみなさん、きょとんとしているというか、うーんと唸ったきり思考停止になっているような感じなのです。ニュースを伝える各メディアのアメリカ特派員たちも、限られた紙面や放送時間の中で何をどう伝えればよいのか、いまひとつ決めかねて米国での報道をそのまま受け売りしたような、結果的にとても断片的な、あるいは断面的なリポートになってしまいました。
そこで気づきました。若者を中心に欧米でも日本でもゲイのこと、あるいはもっと広げてLGBT(性的少数者)一般のことを本や映画やテレビなどから、あるいは実生活上でもどんどん知ってきている層がある一方で、そういうことをまったく知らない、LGBTの当事者などとも会ったことのない、というか(たとえば日本では)知っていることと言えばマツコやミッツやはるな愛やのことだけという人たちがどっかりと身動きせずに控えているのです。
すると、そういう人たちにとってはゲイっていうのはいまでもなんかおかしな人たち、奇妙な連中、ヘンタイ、オカマ、異常者、性的倒錯者なんだな、と。「だって同性愛とかって、言ってみればエッチなシュミの問題でしょ? そういうのがシュミで結婚して社会的にも認知してほしいだなんて、おかしくね?」みたいな、これはどう考えても反語なのです(欧米の場合はそこに宗教的な断罪が付随します)。
「性のバケモノ」から「隣の生活者」への変身
1969年6月にニューヨークのストーンウォール・インというゲイバーでゲイやレズビアンたちが暴動を起こしたとき(後に近代ゲイ解放運動のきっかけとなった出来事でした)も、米国のマスメディアはそれを地域的な「一部層の」ごくまれな特異事案として報道すらしませんでした。1週間後にやっと報じた際も新聞の見出しは「Homo Nest Raided, Queen Bees Are Stinging Mad(ホモの巣を摘発 狂い刺す女王蜂たち)」でした。そう、このころ「ホモ」たちは、ニュースにすら値しない狂気の倒錯者、セックスのバケモノだったのです。
そして日本の大多数の人々もまた、いまでもその段階の情報のまま取り残されている、置き去りになっている状態です。それは性的少数者の問題をずっとキワモノ扱いにして報道を避けてきた日本の旧態依然のメディアの怠慢の結果でもあります。そんな状況で突然「同性婚」の話をされても、「はあっ?」となるのは無理もありません。
はてそういう人たちにいったいどう説明すればよいのでしょうか?――「70年代から欧米の大都市部ではゲイたちのカミングアウトによる可視化が進み、80年代のエイズ禍を経験して『理想のアメリカ男性像』だった俳優ロック・ハドソンがゲイだとわかったりしてその悲劇に社会的な同情も急速に拡大し……云々」と説明したところで、それもどうせ外国の話です、例によって「日本は外国とは違うよ」という常套句の壁に阻まれてしまうのがオチでしょう。
ストーンウォールから44年かかって、欧米などではLGBTたちはやっと「セックスのバケモノ」という偏見から解放され、やがてほんとうにすぐ隣にいる「身近な生活者」なのだということが徐々に徐々に理解されてきました。そういうものすごく長い時間をかけていまやっと、アメリカでは「自分の周囲の親しい友人や家族親戚にLGBTの人がいる」と答える人が57%いて、しかも同性婚を支持する人が55%という状況になったのです(ともにCNN調べ)。でも、そんな環境も下地も何もない日本で、同性婚がどうしてかくも重大な社会的な課題として扱われるのかを理解するには何をどう考えればよいのでしょうか。
正体見たり枯れ尾花
「同性愛は異常でも倒錯でも何でもない」という言説はすでにちまたに溢れています。しかし知識、頭ではわかっていても、日本人の多くにとっては実感が伴わないのです。カムアウトの運動が大々的に起きたことのない日本では、「周りにだれもLGBTがいない」のと同じことですから。
「だからこそLGBT当事者のカムアウト運動を!」というのもすでにありふれた呼びかけです。でも、もうひとつ同時に、逆にカムアウトされる側、つまり圧倒的多数者の側の、こんな思考実験も有効かもしれません。それはたとえば学校なり職場なりで自分の同僚や友人全員がゲイやレズビアンだと仮想してみることです。
「えー!」と思われるかもしれません。しかしそこで戸惑ったり疑心暗鬼になったりしている自分がいるとすれば、その自分こそが問題なのだ、と気づくことができます。なぜなら、同僚・友人全員はいままでと何ひとつまったく変わらずにそこにいてそこで仕事をしているのです。女装/男装もせずシナを作るわけでも自分を襲うそぶりを見せるわけでもなくそこにいままでと変わらずに存在している。なのにただ彼らがゲイだレズビアンだと知って不意にうろたえている自分がいる。
じつは欧米で44年かけて気づかれてきたことはそういうことなのです。「正体見たり枯れ尾花」。問題は枯れ尾花ではなく、それを幽霊だと見ていた自分だった。だとすれば、オバケでも何でもなかった「彼ら」を、そうと知ってもなお結婚もできない二級市民の地位におとしめているのは大変な間違いなのではないか。これはかつて女性問題や奴隷制度で犯したと同じ公民権に関係する過ちなのではないか。その気づきが現在、同性婚への支持が過半数に逆転した背景なのです。
本来ならば44年かかるその気づきを即製で導いてくれる上記の思考実験を経なければ、日本では多く、世界の人権先進国での同性婚合法化の気運を理解できないかもしれません。
連邦最高裁は同性婚の是非を判断せず
さてその上で説明を進めましょう。今回の最高裁判断で最も注目されたのは、2つの訴訟の判決をとおしてアメリカの司法制度が連邦として、つまり1つの国家として同性婚を認めるかどうか、ということでした。日本の報道では「同性婚を支持」とか「容認」となっているのですが、ところが厳密に言えば、連邦最高裁はその判断を避けているのです。
2つの訴訟の1つは、長年連れ添ってきたレズビアンのカップルが、一方が他界したことで36万ドル(1ドル=100円換算で3600万円)以上の相続税を支払うように命じられたのがきっかけでした。
原告のイーディス・ウインザーさん(84)はいまから51年前の1962年にテア・スパイヤーさんと出会い、間もなく「エンゲージ(婚約)」し、同性婚に踏み込めないでいたニューヨーク州での「結婚」を見切ってすでに同性婚を合法化していたカナダで2007年に正式に結婚しました。それも長年にわたって多発性硬化症を患っていたスパイヤーさんが、余命一年と告げられたのがきっかけでした。2人は2人が共に生きたことの証しに公的に結婚をしたのです。
2年後、スパイヤーさんは亡くなり、政府は傷心のウィンザーさんに追徴課税の知らせを送ってきたのでした。ウィンザーさんたちのカナダでの結婚は外国での結婚も結婚と認めるニューヨーク州法によって認知されていました。ところが連邦政府は同性パートナーと彼女の「結婚」を認めず、(異性間の結婚では必要のない)追加の遺産相続税の支払いを強制しました。それは法の下での平等を保障した合衆国憲法に違反している、と訴えたのです。
この経緯は「Edie & Thea: A Very Long Engagement(『イーディー&テア:とても長い婚約』)」というドキュメンタリー映画になり、数々の映画賞を受けています。
連邦政府が彼女たちの「結婚」を認めないのは、結婚を「伝統的な男女間のものに限る」とした連邦法「結婚防衛法(DOMA=Defence Of Marriage Act)」があるからでした。なぜこんな法律ができたかというと、1990年代初め、ハワイ州を初めとして当時の先進的なゲイ団体やグループが結婚の権利を自分たちにも平等に与えよと同性婚に関する訴訟を起こしたのが背景です。
ハワイ州最高裁は93年、米国内で初めて「同性婚を認めないのは法の下の平等を謳う州憲法に違反する」と判断しさえしました(後にこれは激しい世論と議会の反対で取り消されます)。こうした気運に危機感を持った保守派が、連邦レベルで網羅的に同性婚を認めない法律を作ろうと画策して96年に成立したのがこの「結婚防衛法」でした。
ちなみに日本のメディアではこのDOMA(ドウマと発音します)を「結婚保護法」だとか「擁護法」だとかと訳す向きもありますが、そうした攻防の末に出てきた「Defence」という軍事用語は、まさに「防衛」と訳す以外は間違いです。
この結婚防衛法によって、連邦政府の管轄である、たとえば連邦所得税に関する夫婦合算納税の優遇税率が同性の結婚カップルには適用されませんでした。また配偶者としての遺族年金の受給資格も同性カップルにはありませんでした。あるいは一方がアメリカ市民である場合にその配偶者に「婚姻による永住権」が出せる移民法上の特典も同性カップルには与えられません。その他同性カップルの享受できない連邦法上の権利・恩恵は計約1100項目にも上ります。
さて今回、連邦最高裁が下した判断というのは、9人の判事で5対4の僅差ながら、この結婚防衛法がやはり連邦憲法修正第5条(法の下の平等保護)に違反しているというものでした。すなわち、イーディスさんの結婚は、連邦法上でも男女間の結婚と同等に認められるということを間接的に認めたのです。
アンソニー・ケネディ判事は次のように書いています。
DOMA undermines both the public and private significance of state-sanctioned same-sex marriages; for it tells those couples, and all the world, that their otherwise valid marriages are unworthy of federal recognition. This places same-sex couples in an unstable position of being in a second-tier marriage. The differentiation demeans the couple, whose moral and sexual choices the Constitution protects, see Lawrence, 539 U. S. 558, and whose relationship the State has sought to dignify. And it humiliates tens of thousands of children now being raised by same-sex couples. The law in question makes it even more difficult for the children to understand the integrity and closeness of their own family and its concord with other families in their community and in their daily lives.
結婚防衛法は州が是認した同性婚の公的および私的な意味の双方を損なうものである:というのもそれはそうしたカップルに対し、そして世界中に対し、それ以外では合法的な結婚が、連邦の認知には値しないものだと告げているからである。これは同性カップルを第二級の結婚関係にあるという不安定な立場に置くものである。この差別化は、その道徳的および性的選択を合衆国憲法が保護している、またその関係性に州が尊厳を与えようとしてきたカップルを貶めるものである。前者に関してはローレンス対テキサス州判決(ソドミー法への違憲判断)を参照せよ。また、それは現在同性カップルによって育てられている数万人もの子供たちに屈辱を与えるものである。問題の法は、そうした子供たちが自分たちの家庭の絆の強さや親密さを、そして自分たちのコミュニティの中で、および自分たちの毎日の生活の中で、自分たちの家庭が他の家庭と協和しているのだと理解するのをよりいっそう困難にしてしまうものなのである。
ここで注目したいのは「(the couple,) whose relationship the State has sought to dignify(その関係性に州が尊厳を与えようとしてきたカップル)」という文言です。同性婚の尊厳を認めてきたのはここでは「the State」、つまり特定の州政府です。その州の決定を、連邦法であるDOMAが毀損している、というのがこの判決文の論旨なのです。
すなわちここで示されているものは、連邦として同性婚をdignifyするという行為ではなく、連邦としては同性婚をdignifyした州の行為を尊重する、という態度なのです。具体的かつ直接的に同性婚をdignifyするのはそれぞれの州であり、最高裁は、州の専権事項である「結婚」の是非には踏み込んではいません。
余談ですが、この訴訟で勝訴した原告のウィンザーさんは6月30日に行われたニューヨーク市のプライド・パレード(ストーンウォールの暴動を記念して毎年6月最終日曜日に世界中で行われるLGBTの可視化啓発パレード)でグランドマーシャルと呼ばれる式典代表を務めました。彼女は「50年前に、84歳になったらあなたはニューヨークのゲイパレードで先導役を務めることになるよと告げられていたとしても、もちろん信じなんかしなかったわ」と笑顔で話していました。
リベラルなカリフォルニア州での攻防
同性婚の是非に踏み込まなかったのはもう1つの判決、カリフォルニア州憲法修正提案8号(プロップ8)に関するものでも同じでした。
ゲイの聖都とされるサンフランシスコを有するリベラルなカリフォルニア州は、2008年6月から同性婚を合法化しました。ところがこれに反対する住民グループが提案8号なる同性婚禁止の住民投票を提起し、同年11月の大統領選挙と同時に行われた住民投票の結果、禁止支持が52%対48%と過半数となっていったん合法化された同性婚が取りやめになったという経緯があったのです。
リベラルで知られるカリフォルニア州でどうしてそんなことになったのかというと、人口の36%を占めるヒスパニック系のカトリック教会、アフリカ系黒人層に影響力を持つバプティスト教会、さらにユダヤ教やアルメニア正教会などの宗教界が大々的な同性婚反対キャンペーンを展開したのが要因と言われています。とくにテレビ広告を中心としたモルモン教の反対キャンペーンは凄まじく、一説で2000万ドル(20億円)が投じられたとされています。これは反対キャンペーンの資金の75%に相当したとも言われます。
これに対し、2組の同性カップルがこの提案8号可決による州憲法修正(同性婚の禁止)はやはり法の下での平等を保障する州憲法に違反しているとして提訴し、一、二審ともに「禁止は違憲」と勝訴したのでした。そこで提案8号支持派の上告となったわけです。
ところが最高裁の判断は、上告した提案8号賛成者たちには「当事者の資格がない」というものでした。資格がないのですから上告自体が無効なわけで、つまりはそれを門前払いで却下したわけです。
こちらは最高裁長官のジョン・ロバーツ判事が書いています。
For there to be such a case or controversy, it is not enough that the party invoking the power of the court have a keen interest in the issue. That party must also have “standing,” which requires, among other things, that it have suffered a concrete and particularized injury. Because we find that petitioners do not have standing, we have no authority to decide this case on the merits, and neither did the Ninth Circuit.
このような事案あるいは議論のためには、裁判所の権限を発動する関係者はその問題に強烈な関心があるというのでは不十分である。その関係者は「当事者適格」をもまた有しなくてはならない。その資格は、とりわけ、その関係者が具体的かつ個別的な損害を被っていることを必要とする。我々は上告の申立人たちには当事者適格がないと判断するが故に、我々は、そして(元々の控訴審の)第9巡回裁判所も、本案を判断する権威を有しない。
どうして上告者たちに「当事者適格がないと判断する」のか? ここに書かれてあるのは「具体的かつ個別的な損害を被っている」わけではない、ということです。それはつまり、同性婚が禁じられなくとも、「あなたがたはべつに傷つくわけでも法的不利益を被るわけでもないでしょう? 同性婚によって異性婚が破壊されるわけではないでしょう?」ということなのです。それなのに他の人の余計なことに口を出す必要も資格もないのだ、ということなのです。
もしこれが州憲法を修正した当事者であるカリフォルニア州による控訴、上告だったら「当事者適格」があったかもしれません。しかしカリフォルニア州は途中で控訴することをやめて、同性婚合法化の流れに身を寄せたのでした。なので代わって提案8号の推進派の人たちが控訴しなくてはならなくなったわけで、その彼らに当事者資格がないと判断された……かくして「同性婚の禁止は違憲」とした下級審の判決がめぐりめぐって自動的に有効になる、という論理なのです。
ここでも最高裁は同性婚そのものの是非を論じていません。これはとてもよく考えられたものだと言えます。というのも、もし最高裁が「同性婚は正しい。認めるべきだ」などと判断したら、これは同性婚を禁止している34もの州で大混乱が起きてしまうでしょう。そう、同性婚合法化の流れが加速しているといっても全米50州中34州ではこうした流れを前もって予想して90年代から続々と先手を打ってきたのでした。
なお続くアメリカの試行錯誤
私たち日本人が「アメリカは自由の国だ、平等の国だ」と言うのには少々誤解があります。なぜならアメリカにおいて「自由」と「平等」はしばしば対立概念となるからです。
アメリカにおいて「自由」という言葉は、しばしば連邦政府の干渉からの「自由」を指します。連邦政府(連邦最高裁もその一部です)がなにかと個人の生活や慣習や伝統に口出ししてくることから自由でありたい、自分たちは「自由」に自分たちの規則で生きてゆく、ということなのです。この場合は、結婚に関しては連邦政府に「同性婚は正しい」などと強制されたくないのです。その背景には、この国が独立独歩の開拓者たちによって成立してきた自助の歴史があります。そして彼らを支えてきた唯一かつ全てのものが聖書、教会であったというキリスト教の「正義」があります。
一方で「平等」はそんなあるがままの自然(不平等で弱肉強食の社会)を矯正して人工的に成立したものです。奴隷制度然り、女性解放然り、そしてLGBTの人権運動然り。そこには政府や制度の強力な率先がありました。それは「干渉」だったのです。
同性婚や妊娠中絶に関して裁判所が革新的な判決を出すたびに、米国では「過激派の裁判所判事たちが勝手に規則を作っている」という批判が渦巻いてきました。それは自由と平等の相克でした。妊娠中絶に関しては、ここ最近、中絶禁止法を復活させようという不穏な動きも顕在化しています。
もちろん今回の最高裁判断に関しても、全米各地で反対派がそれこそ「狂い刺す蜂」のように一斉に反撃の狼煙を上げています。カリフォルニア州で直後に再開された同性カップルの婚姻届受理に関しても、反対派が裁判所に差し止め請求を行って即座に却下される事態も起きました。中にはファミリー・リサーチ・カウンセルという保守団体が6月の「ゲイ・プライド月間」に対抗して、「同性愛を治していまでは異性愛者に変身した」と言う人たちのための「元ゲイ・プライド月間」を宣言するなどという不思議な事態にもなっています。いやそれだけでなく、具体的に各地のプライド・パレードなどで、LGBTの人々を狙う暴力事件も頻発しているのです。
「欧米先進国」とひとくくりに捉えがちですが、アメリカはいまもとても保守的です。前述のように全米50州中34州で同性婚はいまも州憲法あるいは州法で「敢えて」禁止されています。つまりこれは今回復活したカリフォルニア州を加え計13州(ミネソタ州は8月1日からの施行)+ワシントンDCとなった同性婚合法化(人口でみると米国全体のちょうど30%に相当します)の余地が、あとはニューメキシコ州とニュージャージー州とイリノイ州ほどしかないという計算になります。
自身の、あるいは友人や家族の同性婚を認められて歓喜する人々が増えているのは確かですが、そういう人々が増えれば増えるほど、それを自身の信仰への脅威、神への冒涜だとして心底、ほんとうに心の底から怒りに震える「正義の人々」も先鋭化しています。彼らにとってそれはとても正しい公憤なのです。
いま心配されているのは、かつて起きた中絶クリニックへの爆破事件や医師殺害事件などと同様の狂信の犯罪が、ふたたびLGBTを標的に吹き上がることです。LGBTコミュニティにはすでに、ハーヴィー・ミルク(1978年に暗殺されたサンフランシスコのゲイの市会議員)やマシュー・シェパード(1998年に厳寒の牧場の柵に磔にされる形で殺害されたワイオミングのゲイの大学生)など、多すぎる殉教者が存在しているのですから。
はたして州憲法や州法を改正してまでして同性婚の波は米国全体に拡がってゆくのでしょうか。私は、連邦制をとっている米国で連邦全体として同性婚を認知するのはなかなか難しいと思っています。州はそれぞれに独立国家であり、その風土的、歴史的、宗教的差異は今後も維持されてゆくでしょう。その意味で、今回の最高裁判断は現実的なものだったと思います。それは、州で認めた同性婚は連邦としても認知するし、州で認めない同性婚は連邦としては認知する立場にない、というものです。
そうしてこの問題の解決は全米各州の各地の各人の問題に下りてきている。それは自治をモットーとする、ある意味とてもアメリカらしい試行錯誤が、つまりは自由と平等の攻防が、これからもまた続いてゆくということなのだと思います。
サムネイル:『Supreme Court』Mark Fischer
プロフィール
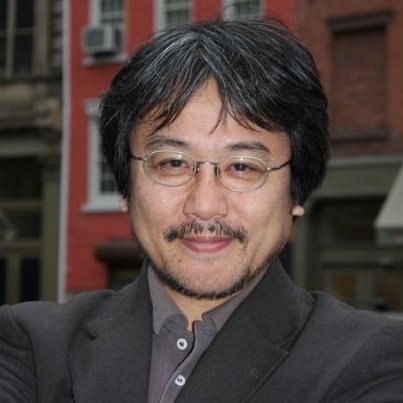
北丸雄二
毎日新聞、東京新聞(中日新聞)ニューヨーク支局長を経て1996年に独立。ニューヨーク在住。日米を軸とした社会、政治報道に関わる一方で、20年以上前から日本でただひとり継続的・体系的に世界のLGBT関連ニュースを提供してきたジャーナリスト。現在は活字媒体だけでなくTBSやMBS、ニッポン放送などのラジオ番組でも米国関連のニュース報道・解説を行うかたわら、政治・文学・ブロードウェイ関連の著作や台本の翻訳も手がけている。


