2021.09.06
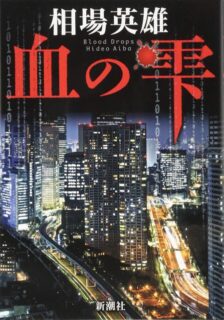
「福島」は他人事か――作家・相場英雄氏が『血の雫』に込めた思い
食品偽装問題、粉飾決算、汚職事件など、数々の社会問題に鋭くきり込む人気作家・相場英雄氏が、原発事故後の福島に残る課題を描いた。2017年に週刊新潮で連載を開始した『血の雫』(2018年)が、2021年10月、幻冬舎から文庫化される。
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故に見舞われ、深く傷ついた福島県民を、さらに心ない誹謗中傷が襲った。この問題を真正面から扱った作品は、これまでにほとんどなかった。
相場さんに、作品に込めた思いと共に、福島との関わりについて伺った。

いつどこで起きてもおかしくない
「震災と原発事故からわずか6年で、早くも福島の苦難が忘れ去られようとしていた」と、相場さんは『血の雫』の連載開始当時を振り返る。
千年に一度ともいわれる2011年3月の震災は、福島の地形を変え、多くの犠牲者を出し、街を破壊した。そして続く原発事故は、突然の避難や家族の離散をはじめ、あまりにも多くの大切なものを奪った。
その福島の苦難を、他人事と思わず、親身に寄り添ってほしい。そう語る相場さんの印象に残るのは、家族が離散を強いられたケースだ。原発事故後、住民に強いられた避難は長すぎた。就職や子供の通学など、とりわけ若い世代では、避難先での定住を選ばざるを得ないケースも多かった。一方、「生まれ育った故郷で最期を迎えたい」と望む高齢者の思いも切実だった。本来対立する必要のない家族が、怒鳴りあう――。誰にもどうしようもない悲しいぶつかり合いは、しかし、自然災害など、いつどこで起きてもおかしくない、と相場さんはいう。
報道を通じて知った状況はほかにもある。原発事故後、葛尾村から避難所に一時身を寄せていた住民が、怒りを発した様子がテレビで報じられた。相場さんは、休校で家にいた当時小学5年生の息子さんと共にそれを見た。菅直人首相(当時)が、避難所の通路で待つ葛尾の住民を一顧だにせず、避難所を出ていこうとする。その背中に向かって、怒りの声があがった。震災と原発事故の苛酷さと、国の対応のまずさを象徴しているかのような出来事だった。
その様子を見ていた息子さんが、「福島の人も怒るんだね」と呟いた。幼い頃から、彼は相場さんと共に、頻繁に福島を訪ねていた。「彼が知る福島県民は、皆優しい人ばかり。国道脇の果樹園で買い物をすれば、買った物以上の土産を持たせてくれる。優しいおばちゃんたちを肌で知っていた。その優しい福島人が怒鳴っている姿に素直に仰天したのだと思う」と相場さんは言う。
避難指示が出なかった県内地域も、苦難に見舞われた。農林水産物を放射能から守るための除染作業や、それにも関わらず起きた風評被害もそのひとつだった。
田畑では、表土の剥ぎ取りや反転耕(表土と汚染のない土壌とを反転させること)、放射性セシウムの作物への移行を防ぐための塩化カリウムの散布が徹底された。そして桃などの果樹の幹を、凍てつくような空の下、高圧洗浄機を使って一本ずつ洗うという苛酷な作業も行われた。農家の高齢化による農作業の簡便化が課題となる中、突然待ったなしで必要となったこれらの除染作業は、きわめて大きな負担だった。果樹からの落下事故も起きた。苦労の結果、福島の農林水産物の安全性は保たれた。しかし、それにも関わらず、風評被害は起きた。初年度、市場で値がつかず、苦難を乗り越えて熟れた桃が大量に捨てられる光景が広がっていた。
震災と原発事故により、福島県民は筆舌に尽くしがたい苦難に見舞われた。世間はそれを忘れていく。それだけではない。これほどの苦難を生き延びた福島県民への、誹謗中傷が始まっていた。
「福島県産でもいいですか?」
相場さんは、『共震』(小学館文庫)で宮城、岩手の沿岸地域を扱い、『リバース』(双葉文庫)で福島の浜通り(沿岸部)を舞台にした作品を発表している。『みちのく麺食い記者 宮沢賢一郎』シリーズは、震災前、福島の会津地方から始まった。縁のはじまりは、少年時代に遡る。
小学生の頃から、父に連れられて何度も福島を訪れた。ドライブ好きの父親は、会津や中通り、ときには浜通りにも車を走らせた。「蕎麦が格段にうまく、野菜や果物がふんだんにあり、魚介類がめっぽう美味という体験は幼少期から体に擦り込まれてきた」と語る。
福島の蕎麦はおいしい。野菜も果物も魚もおいしい。米も肉もおいしい。だから、福島県産品にこだわった料理を売りにする料亭や宿は県内に多かった。相場さんが、2012年に浜通りの取材後に立ち寄った飯坂温泉(福島市)の宿もそのひとつである。
だからこそ、相場さんは、宿の女将さんの言葉にショックを受けた。「うちの食べ物は全部福島産だけど、それでもかまいませんか?」。その頃、世間の一部では、福島の農林水産物に対する過剰な拒絶があった。自慢だった「福島県産」を、おそるおそる出さなければならないのか。無性に腹が立った。「もちろん、全然平気だし、好きだから全部いただく」と即答した。以来、この宿は定宿となった。毎年欠かさず訪れているという。
2014年、大阪に出張した。仕事を終えて関係者と同行した北新地(大阪市北区)のクラブに、いわき市(福島県)出身の女性が働いていた。店で浜通りの話に花をさかせた半年後の深夜、突然相場さんの携帯が鳴った。出てみると、その女性だった。電話口で号泣している。「浜通り出身者だから一生妊娠できないだろう」と酔客に絡まれたのだという。絶句した。相場さんは、たった一度、半年前に店で話しただけの客である。その客に深夜に電話をかける以外に手段がない。浜通りを知る人間だという確信がなければ安心して言えない愚痴だからだろう。彼女のおかれた環境の惨さを思った。
さらにその数年後、西宮のある大学で講演を頼まれた。取材に訪れた新聞記者から聞いた西宮の話に驚いた。西宮はいわゆる「意識の高い」インテリ層が多く住む街だが、「琵琶湖より東の産物は絶対に子供たちに食べさせない」と主張する人が結構いる、というのである。
福島県民への誹謗中傷を幾度も目の当たりにし、「小説ならば、福島県民の苦しみを世間に訴えることができるのではないか」との思いを強くした。
今なお続く福島の苦しみを伝える術はないか――。一方で、原発事故後の福島を繰り返し訪れる中で、艱難辛苦を黙々と耐え忍ぶ福島県民の我慢強さに、もどかしい思いを抱きもした。他県で同じことが起きれば暴動が起きてもおかしくないはずだ。福島を忘れ去ろうとしている人々に、「とても他人事じゃないだろう」と、本気の怒りを示さなければならない、と思った。
「私は福島で米をつくります」
「本当に私のつくっている米に毒がはいっているなら、警察がつかまえにくるでしょ。それまでは、私はここで米を作ります」
小さな神社を囲む雑木林に蝉が鳴く。連なる桃林は春、愛らしい花を咲かせる。フルーツラインに近い福島市の庭坂地域で、夫と共に米農家を営む加藤絵美さん。大きなトラクタを操り、田んぼを耕す。4人の子どもを育てる母でもある。
単行本になった『血の雫』を読み、相場さんにお話を伺って、加藤さんの顔が浮かんだ。おそらく相場さんが『血の雫』の執筆を始めたのと同時期に、私は加藤さんをはじめて取材していた。連想した理由は、「怒り」だった。
加藤さんを思い出すとき、いつも朗らかな笑顔が浮かぶ。しかし、加藤さんも原発事故と当然無縁ではなかった。原発事故後、彼女が暮らしを営む福島市には、避難指示が出なかった。それでも周囲の、とりわけ子育てをする家族の場合、避難を選択する人も少なくなかった。
加藤さんも当時、幼い子どもを育てていた。夫と何度も話し合い、福島に留まること、そして農業を続けることを決めた。土壌中の放射性物質を稲に移行させないための塩化カリウムを撒き、作った米は全量、放射能濃度の検査で安全を確認した上で市場に出す(2015年以降、通算5年間基準値超過がないことから、2020年度米より一部市町村を除き、全量全袋検査からモニタリング検査に移行した)。
もともと有機肥料を工夫し、手間のかかる米作りをしていた。塩化カリウムの大袋をいくつも担ぎ、広大な田んぼに撒く。売り先に自ら営業してまわり、原発事故の年も取引きしてくれる都内の米穀店を探し当てた。
ある夜、疲れてネットを見ていたとき、「毒入りの米を作る福島の農家はテロリストだ」という文言が目を射た。血の気が引いた。指が冷たく震えて、スマートフォンのスクロールができなかった。固まったように文字列をじっと見つめているうち、引いていた血が逆流して、頭の奥で沸騰するような感覚に襲われた。「そうか」と思った。福島市には米の出荷制限がかかっていない。基準値を超える米も一度も出ていない。それでもこの米を毒入りと呼ぶのか。
「本当に私のつくっている米に毒がはいっているなら、警察が私をつかまえに来るでしょう?じゃあ警察に取り押さえられるまではやりますよ。この手に手錠をかけられるまで、ここで米をつくってやろうじゃないか。そう思ったんです」日焼けした手を見せて、加藤さんは笑った。
加藤さんのつくる「天のつぶ」は全国的に人気を博す。新型コロナ感染症が流行する前は、何度も海外でのイベントも開催した。ベトナムでおむすびをつくり、絶賛された。福島の米のうまさを、国内外で証明してきた。近年はクラフトビールの醸造も始めた。
米農家の仕事は、米をつくることだ。丹精こめてつくった米を「おいしい」と喜ぶ人がいる。米をつくり、新しいことにチャレンジし、子どもを育て、家族が皆元気に笑えている。5年前、加藤さんにみた怒りは本気のものだった。しかし、だからこそ、食べた人の健康を願い、笑顔を思い浮かべ、おいしい米をつくることに邁進した。
「生きる」という抵抗
「死ぬな」――。
『血の雫』作中で、ある福島県民に向けられた言葉だ。
綿密な取材と繊細な人物の描写によって、いつしか読者も「福島県民の怒り」に飲み込まれてゆく。相場さん自身も「福島県民の本気の怒りを伝えるべきだ」と語る。しかし、それは決して「怒りと復讐に人生を捧げろ」という意味ではないだろうと思う。
ある海外の文学者が、原発事故に触れた上で、「日本人には抵抗の文化がない」と評した。違う、と私は思う。違う。抵抗のあり方が違うだけだ。
「生きる」。
それが、福島県民の抵抗のあり方だ。福島の農家に、住民に取材し、『血の雫』を読み、相場さんにお話を伺う中で、それは確信に変わった。生きること、ただただ、生きること。この理不尽を、生きること。それは並大抵の努力ではない。でもそれをやり遂げること。これほど誇り高い「抵抗」があるだろうか。
2021年7月、相場さんはふたたび福島を訪れた。「半日というわずかな時間ながら浪江、小高、双葉、大熊を周った。震災後の復旧が未だに済んでいない地域がある一方、復旧から復興のフェーズにようやく達した地域があり、市区町村ごとの格差を感じた。また、復興の名の下に、東京の大資本が進出し、除染からインフラ整備、住宅建設、流通など、様々な分野で、いくつもの利権が生まれているようにも感じた。先に大手ゼネコンの幹部が逮捕されたように、復興しようとする地元の意欲、気力を削ぐような事態が頻発しないか、強く懸念している」と語る。
相場さんが福島に向ける眼差しは鋭く、そしてあたたかい。これからも、相場さんと福島の縁は続いてゆくのだ、と強く感じた。
プロフィール

服部美咲
慶應義塾大学卒。ライター。2018年からはsynodos「福島レポート」(http://fukushima-report.jp/)で、東京電力福島第一原子力発電所事故後の福島の状況についての取材・執筆活動を行う。2021年に著書『東京電力福島第一原発事故から10年の知見 復興する福島の科学と倫理』(丸善出版)を刊行。



