2022.09.20

「見守り」と「疫学調査」は両立しない――福島の甲状腺検査の構造的問題 稲葉俊哉氏インタビュー
右足でアクセルを踏みながら、左足でブレーキをかける
東京電力福島第一原子力発電所(以下福島第一原発)事故後、子どもの甲状腺がんの増加を不安に思う福島県民の声が多く上がった。
福島県は、県民の不安を解消する目的(以下、「見守り」と呼ぶ)で、甲状腺がんやその疑いの有無を超音波機器でふるいわける検査(甲状腺がんスクリーニング。以下、甲状腺検査)を開始した。加えて県は、原発事故による放射線被ばくの子どもの甲状腺への影響を調べることを、甲状腺検査の目的として掲げた。
県民健康調査のあり方の議論および結果の分析については、これを検討する専門家会合(「県民健康調査」検討委員会。以下、検討委員会)が設置され、議論が続けられてきた。
今回、2013年から2022年まで、検討委員会の委員を務めた稲葉俊哉氏にお話を伺った。稲葉氏は、広島大学原爆放射線医科学研究所がん分子病態研究分野教授であり、専門は放射線医学、腫瘍学、小児科学である。
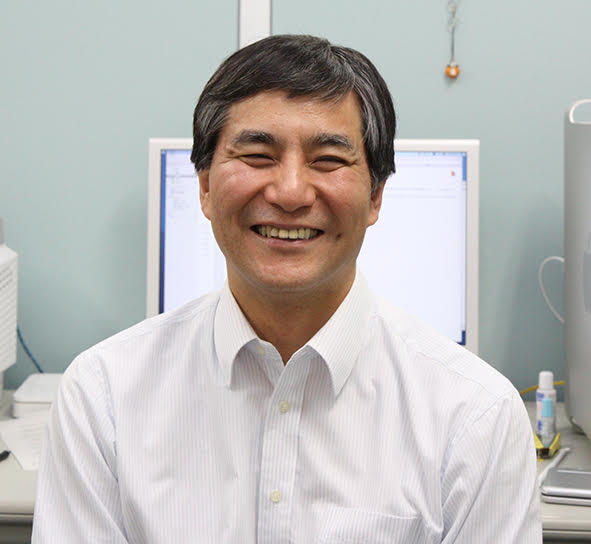
今回、稲葉氏は福島県の甲状腺検査の抱える構造的な問題を指摘した。以下にポイントを挙げる。
01.原発事故による福島県民の甲状腺被ばく量は非常に低かった。したがって、原発事故前や他県と比べても、被ばくの影響は見えない、すなわち解析不可能であると予想される。このことは原爆調査と比較するとわかりやすい。広島や長崎では、放射線被ばくの健康影響を調べるために、強引とも言える徹底的な調査が行われた。その結果、高線量被ばくによる健康への影響については明確な結果が得られた。しかしその調査でも、低線量被ばくによる健康への影響は解明できなかった。まして広島・長崎に比較して調査の条件が格段に悪い原発事故後の福島で、低線量被ばくによる健康への影響を明らかにすることは不可能であろう。
02.調査態勢を構築する際の失敗が、調査の見通しをさらに暗いものにしている。甲状腺検査の主な目的は「見守り」であった。この目的が達成されて、不安が解消されれば、検査希望者は必然的に減る。しかし一方で、県は「放射線被ばくによる甲状腺への影響を調べる」と、疫学調査を検査目的としてつけ加えた。疫学調査を実りあるものにするためには、県および検査実施主体である福島県立医科大学(以下、福島医大)は、受診率を高く保つ必要がある。すなわち、「見守り」と疫学調査は両立しない。
たとえるならば、重装備のサファリラリー仕様車でも走破できなかった悪路に、普通の車で挑み、しかも右足でアクセルを踏みながら、左足でブレーキをかけ続けるようなもの、ということになるだろう。(※重装備のサファリラリー仕様車=強引かつ徹底的な調査、悪路=低線量被ばくによる健康影響の解明、普通の車=任意性のある検査、アクセル=受診率向上、ブレーキ=不安解消による受診率低下)
福島県の甲状腺検査には、成り立ちそのものに欠陥がある――。もしそれだけであれば、成果を望めない公共事業が継続されることに伴う問題を考えればすんだかもしれない。しかし、検査の孕む問題は、残念ながらそれだけではなかった。
稲葉氏は、検査について「過剰診断が起きている」と指摘する。UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)も、2020/2021年報告書で、過剰診断が起きている可能性を指摘している。過剰診断とは、検査で見つかりさえしなければ、生涯にわたって症状を出したり生命に影響したりしなかっただろうがんを見つけてしまうことである。
2022年8月現在、284 人の子どもや若者ががんまたはがんの疑いと診断されている。福島県の甲状腺検査は、検査さえなければ健康に成長し、青春を謳歌できたはずの数百人の子どもたちを、がん患者にしてしまった。
そもそもの構造的欠陥と子どもたちへの有害性が指摘される福島県の甲状腺検査は、今後どのような形になるべきなのだろうか。
原発事故後の福島における被ばく線量の低さ
2019年6月、甲状腺検査評価部会は、本格検査について「現時点において、甲状腺検査本格検査(検査 2 回目)に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」とするとりまとめ案を提出した。これを受け、2019年7月8日の検討委員会で、稲葉氏は以下のようにコメントしている。
(以下抄録)
もし「福島第一原発事故による甲状腺被ばく線量が高かった」と仮定すると、UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の、原発事故後の生態系への影響など他の分野の報告と矛盾する。このことからも、「福島第一原発事故による放射線の甲状腺被ばく線量は低かった」と考えられる。
福島第一原発事故による放射線の甲状腺被ばく線量は、非常に少なかった。被ばく線量がこれほど低い状況で、無理やり線量をさらに細かく区分していっても差は出ない。それを明らかにするためにも、「福島第一原発事故による放射線の甲状腺被ばく線量はそもそも低かった」ということには、報告のどこかで触れたほうがよい。
「現時点において、甲状腺検査本格検査で発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間に関連はみられない」という結論には賛成である。
加えて、福島の甲状腺検査は「定常状態」(放射線被ばく量が平常時と変わらない状態)をみているというコメントがあってもよい。
つまり、甲状腺への放射線被ばくがなくても、この年齢の集団を対象に甲状腺検査を行えば、一定の確率で「甲状腺がん」と診断がつくようなものがみつかる。しかし、検査で見つかった甲状腺がんが全部どんどん大きくなると仮定すると、それはこれまでの疫学の知見と矛盾する。したがって、たくさん甲状腺がんが見つかったとしても、それはそのまま全部が大きくなっていくのではなく、自然とおさまっていくのだと考えられる。それが定常状態であり、福島の甲状腺検査における状況もまた定常状態であるというコメントがあってもよいのではないか。

――放射線被ばくの健康影響を調べるという目的において、原爆投下後の広島、長崎での調査と、原発事故後の福島での調査とでは、どのような違いがありますか。
広島と長崎の場合、ほぼ被ばくしなかった人から数シーベルトの高線量の放射線を受けた人まで、被曝線量の幅が広がっていました。このため、被爆者を線量の高低によって分類し、発がん頻度を比較する方法で、その影響を調べることができました。
一方福島では、95%の人が5ミリシーベルト以下、これはゼロに限りなく近いとすら言えるほど低い値です。最大値は、数人の受けた数十ミリシーベルトです。ダイナミックレンジ(被ばく線量の最大値と最小値の幅)が極端に狭い。
線量の最大と最小の差がこれほど小さく、また被ばく線量そのものが非常に低かった福島で、その影響を疫学的に検出することはまず不可能でしょう。
――原爆投下後の広島と長崎では、放射線の健康影響について、多くの知見が得られています。
まず、広島・長崎への原爆投下では、20万人の市民が亡くなりました。生き延びた被爆者にも、がんを含むさまざまな後遺症が残りました。現在我々が知る放射線の健康影響についての基礎データは、この方々の血と涙の上に成り立っています。
その上で、ABCC(アメリカが設置した原爆傷害調査委員会。Atomic Bomb Casualty Commission)による調査の強行についても言及しなければならないでしょう。
当時のアメリカは、旧ソ連との全面核戦争を強く恐れていました。そのため、放射線の健康影響について、少しでも詳しい情報を得ようと真剣でした。そのためもあってか、ABCCは、「有用なデータを集めるため」として、どんなことでもやりました。たとえば、女学生を裸にして校庭に並ばせて身体検査をしたり、大量の血を何度も無理やり取ったり、と、そういったことです。さらに被爆者から被爆時の状況を聞き出し、爆心地の街並みを再現した「リトルヒロシマ」をニューメキシコ州の砂漠に作り、被爆者のいた位置に線量計を置き、そこに本物の原爆を落として、線量計の値(≒被爆者の個人線量)を実測するということまでしました。
ABCCのなりふり構わない調査でも解明できなかったのが、低線量放射線被ばくによる健康への影響でした。
福島第一原発事故が起きたとき、専門家の中から、「100 mSv以下の低線量放射線被ばくによる健康影響を解明すべきである」という声が上がりました。「これは人類史における日本の責務である」という意見すらありました。
――当時のそういった意見について、どのようにお考えですか。
原爆投下後の広島、長崎と、原発事故後の福島とでは、放射線被ばくの影響を調べるための条件が、多くの点で異なります。
まず、先述の通り、そもそもの放射線被ばく線量が非常に低く、ダイナミックレンジが極端に狭いこと。
次に、正確な個人線量の推定が困難であること。原爆の場合、被爆状況の把握は簡単です。原爆投下は一瞬の出来事ですから、被爆者に、その瞬間にどこにいて、どういう遮蔽状況だったかを聞き、それを計算式に入れれば、個人線量がはじき出される。ところが福島の場合、数日にわたる行動記録から個人線量を推計しなければなりません。何日の何時から何時まで外にいたか、その記憶はどの程度正確か。風速・風向・にわか雨など、気象条件のちょっとした局地的変化で受けた放射線の量は大きく変わります。甲状腺など臓器の被ばく線量は内部被ばくを含むので、推計する際の個人差が大きく、それでなくても大きな誤差が、さらに拡大します。
もうひとつ、原爆の疫学調査では、死亡診断書が主な指標として用いられました。死亡診断書に優る正確さと信頼性を持つものはそうありません。極論すれば、正確な個人線量付きの被爆者リストと死亡診断書から、被爆者の死亡とその死因とを漏らさず把握し、さらに線量と照合することにより、疫学調査は成り立ちます。
原発事故後の福島では、放射線被ばくによる死亡者は、がん死を含めてもほぼゼロでしょう。したがって、死亡診断書に基づいた確実性の高い調査はできません。
これほど条件が揃わない中で、低線量被ばくの健康影響を解明することなど、土台無理な話なのです。ABCCや、その後継ながら「被爆者に寄り添う」という組織に転身した放射線影響研究所(1975年から日米共同機関)ですら解明できなかったのですから。それにもかかわらず、放射線被ばくによる甲状腺への影響を調べるといい、福島医大からはそれが可能であるかのようなプロトコル(手法)が論文として発表され、県は県民に調査をすると宣言してしまった。これが第一の失敗です。
「見守り」と疫学調査の目的の矛盾
さらなる失敗は、「見守り」のための検査、つまり県民の過度な不安を解消するための検査集団を、そのまま疫学調査集団(コホート)として設定してしまったことです。
ひとつの集団にふたつの目的を持たせると、それぞれの目的遂行のための方策が矛盾した場合に、行き詰まります。福島の甲状腺検査において、それは現実になりました。
「見守り」の目的である、県民の過度な不安解消が達成されれば、受診率は落ちてしかるべきです。一方で、受診率が落ちればコホートの維持はできず、疫学調査は不可能になります。ふたつの目的は初めから矛盾していました。
「見守り」が目的であるならば、受診の自発性・任意性が最大限に尊重されるべきです。特に甲状腺がん検診は、検査を受けることによる受診者へのメリットがあるかどうか疑わしい検診です。「見守り」、すなわち受診者の利益を主たる目的とするのであれば、けっして強く受診を推奨してはいけません。実際に、県の出した検査対象者への「お知らせ文」では、検診のデメリットを列挙して、慎重な判断を求めています。
ところが、疫学調査を目的とした場合、これが真逆になります。受診率を高く保たなければ、データの信頼性が失われます。調査する側の利益を主たる目的とするのであれば、受診を強く推奨しなければならないということになります。
県は県民に対して「甲状腺検査を通じて放射線被ばくによる影響を調べる」と公言しました。県の宣言を正面から受け止め、「それならば」と協力した県民も多くいらっしゃることでしょう。
「見守り」が成功したことで、予想通り、特に学校で検査を受けなくなった年齢の対象者の受診率は年々低下し、コホートの維持そのものができなくなり、甲状腺検査のふたつの目的の矛盾が露呈してきています。しかしそのことを、県は県民に対して今も何ら説明をしていません。県民に対する背信行為にも等しいと思います。
少なくとも、「現行の甲状腺検査では、原発事故後の放射線被ばくによる健康影響が明確になる見通しは立ちません」と明言することは、県の最低限の義務だと思います。
――検査の「見守り」の成果についてはどのように評価されていますか。
甲状腺検査の「見守り」機能について、私は高く評価しています。
ご存知のように、原発事故直後、状況は混乱を極めていました。チョルノービリ原発事故後に子どもの甲状腺がんが増えた、という印象は強く、このために不安を募らせた県民はたくさんいました。
不安をマスメディアが過剰に煽った、という側面もあると思います。
直接的ではないにせよ印象的だったのは、ガスマスクの写真とともに、「放射能がくる」というキャッチコピーを表紙にした雑誌(『AERA』, 2011.3.28)でした。悪ふざけにも程があるでしょう。こういった報道に対して直接申し入れをしたこともありました。しかし、「国民の不安を記事にした。科学的事実はともかく、不安があったこと自体は事実だ」と繰り返すばかりで、話になりませんでした。マスメディアの一斉砲火による破壊力は凄まじいものがあります。
そういった混沌とした状況の下、甲状腺検査は始まりました。2011年7月に決めて10月から実施という短期間に態勢を整え、検査は県民の不安に的確に対応しました。緊急避難的措置として、百点満点だったと評価しています。今からなら何でも言えるでしょうが、当時の状況を鑑みれば、おそらくこれ以外の方法はなかったでしょう。
小児神経芽腫マススクリーニングの「過剰診断」
――2012年1月に、稲葉先生は「検診による「見かけ上」の増加も」という記事で、福島の甲状腺検査で過剰診断が起きる可能性を指摘していらっしゃいます。(https://www.blog.crn.or.jp/lab/06/41.html)
これは韓国からの甲状腺がん過剰診断についての論文が公開される2年も前であり、甲状腺検査の過剰診断について指摘した論考としては相当早い時期のものだったのではないかと認識しております。なぜ、これほど早く、福島の甲状腺検査で過剰診断が問題になるだろうことを予見されたのでしょうか。
私は1986年から1990年まで埼玉県立小児医療センターに勤務していました。ここは大変熱心に神経芽腫のマススクリーニング(大規模検診)を行なっていた施設で、私もそのお手伝いをしました。ところが、その後、「小児神経芽腫マススクリーニングをしても、神経芽腫を発症する子どもは減っていない。したがってこの検診は無効である」という結論が出たのです。
――神経芽腫のマススクリーニングとは何ですか。
赤ちゃんが6ヵ月健診を受けるとき、尿検査を同時に実施して、神経芽腫というがんを見つけるというスクリーニング検査です。
神経芽腫は、体幹の交換神経節や、腎臓のすぐ上の副腎髄質などにできる小児のがんです。0歳に最も多く、10万人に2人の割合でかかります。15歳未満でかかりますが、5歳以上でかかるのはまれでしょう。尿検査といっても尿一滴で検査はできるので、おむつに脱脂綿をあてて採尿すればすむ、負担の少ない検査でした。
――神経芽腫のマススクリーニングはどのように始まったのでしょうか。
神経芽腫の治療成績が年齢により大きく違うのがポイントです。
1歳を過ぎた子どもが神経芽腫を発症した場合、現在でも治療は非常に難しいものになります。ところが1歳以下の赤ちゃんに見つかった神経芽腫の場合、比較的容易に治るのです。腫瘍がすごく大きかったり、あちこちに転移して、ステージ4とされるような状態であったりしても、1歳以下の子に見つかったものであれば、薬の効きも良く、ちゃんと治ります。自然に小さくなったり消えてしまったりするものすらありました。治療への反応や予後をみると、これらはまるで別の病気のようでした。
こういった状況から、「生後半年から1年の間に神経芽腫をスクリーニングして、早期に発見して治療することができれば、この病気で亡くなる子どもを減らせるのではないか」と、当時の小児科医は考えました。幸い日本では、赤ちゃん全員を対象にした6ヶ月健診がある。このときに同時に尿を採って、神経芽腫をスクリーニングすればよいのではないか――。
こうして小児神経芽腫のマススクリーニングは始まりました。
――小児神経芽腫マススクリーニングは2004年に中止されています。これはなぜなのでしょうか。
実際にスクリーニングを始めてみると、想定した数の何倍もの子どもに神経芽腫が見つかりました。そして見つかった腫瘍を切除し、抗がん剤で治療すると、みんな治っていきました。
これで、幼い我が子が悲惨な病気で苦しみ、悲嘆に暮れる親はいなくなるはず、だったのです。ところが、1歳以上の神経芽腫の患者は、スクリーニング開始前と変わらぬペースで病院にやってきました。しかも、この子たちはみんな、過去に6ヶ月健診で、神経芽腫のスクリーニング検査を受けており、その際には陰性だったのです。
私たちは、腫瘍をすりつぶして、染色体分析や遺伝子検査を行いました。その結果、腫瘍には予後の良いパターンAと悪性で治療の難しいパターンBがあることがわかりました。
そして、悪性のパターンBを早期に発見して治療しようとして始めたはずのマススクリーニングで見つかった神経芽腫の、ほとんど全部が、予後の良いパターンAだったのです。失敗は明白でした。
小児の神経芽腫の場合は、調べたいのは「6ヵ月健診の際の1回のマススクリーニングの効果」ですから、その結果は死亡率のほか、信頼性の高い小児がん登録でも見ることができました。いずれにしても、小児神経芽腫マススクリーニングをしても、神経芽腫で亡くなる子どもは減らなかった。したがってこの検診は無効で、受診者への不利益の方が大きい、という結論に至り、事業は中止になりました。
――予後の良いパターンAを早期に発見して治療しても、悪性のパターンBを減らすことはできなかったということですね。マススクリーニングで見つかった、おそらく予後の良いパターンAの神経芽腫の切除手術で亡くなる例もあったと聞きます。
実は、がん検診を行なって、当初の想定以上にがんが見つかり、検診で見つけたがんの治療がうまくいっても、そのがんの死亡率は減らない、というのは、子どもの神経芽腫のケースが初めてではありません。
当時からすでに、肺がんをはじめ、いくつものがんで、こういった報告が相次いでいました。
がん検診で見つかったがんの治療成績は一般に良好です。しかし、がん検診の有効性をはかる上で最も肝心なのは、そのがんによる死亡率の低減があるかどうか、です。神経芽腫や甲状腺がんでは、がん検診をしても、そのがんで亡くなる人が減らないことが既に立証されています。その上、がんと診断されることによる精神的なダメージや、治療にともなう身体的なダメージなどの不利益があるわけです。
「過剰診断」は臨床医にとって苦しい言葉
――「過剰診断」という用語は、臨床医にとって「医療過誤」と似た意味を持つのでしょうか。
30年前にマススクリーニングで見つけた神経芽腫の赤ちゃんのことを、今でもにがく思い出します。「あの子たちには余計なことをしてしまったな」と。赤ちゃんの小さなお腹を開けて、小さな体に抗がん剤まで投与したのですから。
一方で、たまたま神経芽腫(おそらくは予後の良いパターンA)が見つかることがあります。赤ちゃんのお腹は柔らかいので、できものがあれば、親がオムツを替えるときに気づくことがよくあります。「お腹にできものを触れた」といって病院に連れてきたり、あるいは肺炎など別の病気でX線写真を撮ったらたまたま腫瘍が写っていたり、そうして見つかった神経芽腫を治療して、それがうまくゆけば、親も医者も大満足です。誰も後悔などしないでしょう。
――同じ月齢の子どもに神経芽腫を見つけたとして、たまたま見つかった場合と、スクリーニングで見つけた場合とで、何が違うのでしょうか。
難しい質問です。つまるところは、「正当な」医療ではない、という引け目かもしれません。医者によっては「どちらも治療としては同じことをしているのだから、引け目を感じる必要はない」と言うかもしれません。このことを、他の医者と議論したことはありません。
過剰診断が起きているとわかっているスクリーニングで見つけたがんを治療することは、臨床医にとって「正当な」医療ではないと思うのです。いくら「医療過誤ではない」と言われたとしても、私と同じように、苦しく思う医者はいるでしょう。
――甲状腺がんについても、小児神経芽腫と同じ状況がおきていると考えられますか。
私は、ある福島医大の医師が感情を吐露されるのを、耳にしたことがあります。福島の甲状腺検査で発見された甲状腺がんを数多く手術した方でした。
「手術適応を慎重に考え、大きいものしか取らないようにしています。むやみに多くの人を手術対象にしないように心がけているし、甲状腺の一部を残して、後遺症を残さないようにもしています(※甲状腺を全部摘出した場合、甲状腺機能が低下するため、一生甲状腺ホルモン剤を内服する必要がある)。傷も最小限に、かつ目立たないように工夫しています」と言ったあとで、「過剰治療という人に私は問いたい。この治療のいったいどこが『やりすぎ』なんだ」、と続けたのです。
個々の症例に応じた、細やかな配慮がなされていることは、素晴らしいことだと思います。しかし、論点はそこではありません。福島の甲状腺検査というシステム全体を見通した時に、過剰診断・過剰治療が起きていることは、まぎれもない事実だ、という点なのです。
親の「安心」の代わりに子どもが引き受けるもの
小児科の臨床医をしていた頃、親子の意見の食い違いは気にせず、利益・不利益の相反、つまり親にとって利益となる選択が、子どもに害をもたらさないように、ということを注意していました。もちろん親子の意見が一致していればなお良いのでしょうが、なかなかそうもいきません。
たとえば小さな子どもは注射を嫌がるものです。それでも、いくら子どもが「嫌だ」と言ったところで、親が注射の必要性を理解している場合、子どもの意見を聞き入れることは通常ありません。それは親の利益のためではなく、子どもの利益(命や健康)を護るための判断です。ここでは親子間の意見の不一致が起きていますが、利益・不利益の相反は起きていませんね。
――親にとっての利益が子どもにとっての害となるケースとは、たとえばどのようなものでしょうか。
よくあるのは、親の極端に偏った思想信条を貫くために、子どもが適切な医療を受けられない、といったケースです。宗教上の理由により、親が子供の輸血を拒否し、白血病の治療や先天性心疾患の手術などに支障をきたすような場合が典型的でしょう。私も、宗教上の理由ではなかったものの、親が理解し難い理由で子どもの手術を拒絶し、子どもに障害が残ってしまったという辛いケースを経験しました。
――福島の甲状腺検査には、子どもを対象とした疫学調査という側面があります。疫学調査では、よく調査する側・される側の利益・不利益の相反が課題として挙げられます。
小児科医を経験した上で、私が懸念していたのは、調査する側・される側の間での課題よりはむしろ、同じ調査される側であっても、親の利益が子どもの害をもたらさないかという点です。
――子どもが甲状腺検査を受けることによって、その親が得られる利益とはなんでしょうか。
まず、子どもが「異常なし」と言われれば、親は安心を得ることができます。検査を受けた99%以上の方は「異常なし」と言われますので、安心を得られる確率も高いでしょう。
また、1%以下の確率ではあっても、甲状腺がんと診断されることはあります。その場合でも、ほとんどの親は、甲状腺がんについて、「早期発見・早期治療」が良いことだと誤解していますので、「早く見つけてもらえてよかった」と考えるでしょう。この場合も利益があったといえそうです。甲状腺がんについては、早期に発見して治療することで治りやすくなるといえる科学的根拠はないわけですが、その知識はあまり浸透していないようですね。
そういうわけで、結果がどちらであるにせよ、甲状腺検査は、ほとんどの親にとっては利益だけを受ける検査です。とにかく受けた方が良い、と判断する親が多いのは普通のことでしょう。
――検査を受ける子ども自身の利益はなんでしょうか。
まず、子どもや若者には、学業や進路、職場に部活、友人関係に恋愛、差し迫った心配事が山のようにあります。したがって、そもそも「自分が放射線によって甲状腺がんになるかもしれない」「それを検査で調べてもらっているんだ」という切迫した感覚が、特に今となっては希薄です。「異常なし」と言われても、もともと心配していないので、特段の安心も得られません。つまり、子ども自身にとっての利益はありません。
一方で、もし甲状腺がんと診断された場合、子どもはとんでもなく大きな害を被ります。子どもや若者にとって最も大切なこと――学業、進路、部活、友人関係に恋愛、就職、結婚――すべてに影を落とし、彼らのその後の人生が左右されてしまうわけですから。
甲状腺検査の結果が「異常なし」の場合は、どちらにも害はないので、取り立てて利益・不利益の不一致はありません。
では、「甲状腺がん」と診断された場合はどうでしょうか。「早期に発見して早期に治療できたから、甲状腺がんが治りやすい」というのは誤解です。親は、誤解に基づく安心を得られるかもしれません。しかし、実際に子どもの身の上に起きるのは、検査さえ受けなければ受けなくてよかっただろう苦しみです。がんの治療の苦しみ、そして自分ががん患者だという感覚による苦しみは、その後の人生に長い影を落とします。もし子ども自身も親と同じように誤解し、そうと知らずに過ごしたとしても、実際に害を被ることに違いはありません。ここに私は親子間の利益・不利益の相反を見ています。
原発事故後の福島での被ばく線量は非常に低く、したがって被ばくによる健康影響は心配いらないということは、既に国際的なコンセンサスです。これを知った上でもなお、もし我が子に甲状腺検査を受けてほしいと思うお母さんがいるのであれば、どうか考えていただきたい。ご自身の安心と引き換えに、我が子が引き受けるものの恐ろしさを考えていただきたいと思います。
疫学調査はそもそも要らなかった
――福島の甲状腺検査に関係する三者(県・医大・検討委員会)の姿勢について、委員を退かれた今、どのように評価していらっしゃいますか。
滑り出しは上々でした。大混乱をあざやかに収拾し、検討委員会も今とは比較にならないほど緊張感に満ちたものでした。検討委員会終了後、新幹線を乗り継ぎ、何時間もかけて家にたどり着いても、なお緊張が残っていて、妻から心配されたのが懐かしい思い出です。県、なにより福島医大に、「委員から意見を拝聴したい」という、謙虚な姿勢がうかがえました。
その後、福島県民の放射線被ばく線量が非常に低かったことが確実になってきた2016年頃から、少しずつ状況が変わりました。県も安心したのでしょう。検討委員会の議論を軽視するような印象を持つことが増えていきました。一方、検討委員会も「言いっぱなし」が増え、議論の形骸化が進んでいきました。
近年では、「福島県民の放射線被ばく線量が低かったことを示すためにも、福島で甲状腺がんが増えていないことを確認する必要がある」という、因果関係が逆転した意見すら耳にするようになりました。こうなるともう支離滅裂です。
県は、「一度始めると止まらない公共事業」のように、ただただ甲状腺検査の継続だけに注力しているように見えます。
疫学調査としての検査は、そもそもの放射線被ばく線量が低いという時点で不要です。初めから不要でしたし、今もこれからも、全てが蛇足、まさに有害にして無益です。10年前、「見守り」として検査を始め、あれほど見事に混乱を鎮めた県が、今や自ら災禍の種をまいているように見えます。
私は2016年に、日本放射線影響学会の第59回大会長を務めました。「福島から5年、放射線影響学は今」をテーマに掲げ、さまざまな分野の専門家をお呼びし、シンポジウムを開きました。環境への影響、野生動物や植物への影響、人体への影響、どの側面からどう調べても、福島県民の放射線被ばく線量は少なかった、というのが結論でした。
この結論は、しかし甲状腺検査の運用の改善には活かされませんでした。
そもそもの放射線被ばくが少なければ、被ばくを原因とする甲状腺がんは増えようがありません。それが自然の摂理、それが科学です。したがって甲状腺がんと放射線被ばくとの関連をみる疫学調査など不要なのです。
ただし不安がおさまらない県民のための、医療サービスとしての「見守り」はしっかり残す。しかし、私の意見は、検査そのものをやめようという「甲状腺検査縮小論」と同じものであるかのように誤解され、一蹴されてしまいました。
ひとつには、「見守り」集団と、疫学調査のためのコホートが同じであったため、「疫学調査をやめるべきだ」という意見が、「甲状腺検査そのものをやめるべきだ」という意見であると止めるように誤解されたということもあるでしょう。
しかし誤解されようが批判されようが、「福島県民の放射線被ばく線量は低かった。だから、福島の子どもに甲状腺がんは増えない」という科学的事実を、もっと、もっと言い続けるべきだった。私は今それを大いに悔やんでいます。
本当に今「見守り」が必要な人のための検査に
――福島の甲状腺検査は、今後どのような形になることが望まれるでしょうか。
6年後(2028年)、原発事故の年に生まれた子が高校を卒業すれば、学校での検査実施は終わります。その後、甲状腺検査は数パーセントの方々の不安解消、すなわり「見守り」の機能を残すのみになるでしょう。もちろん、この機能は必要不可欠なもの、大切なものです。受診対象者が成人すれば、親子間の利益・不利益の相反も解消されていくでしょう。しかしできることならば、6年先と言わず、今すぐ、明日からでも、この状態になってくれないかなあ、と思います。学校の授業時間で検査することをやめ、学校以外の施設での検査に変更することで、この状態に若干近づけることはできるかもしれません。
県民を「見守る」ために始まった甲状腺検査が、本当に今それを必要とする人たちだけのためのものとなっていくことが、私の希望です。
プロフィール

服部美咲
慶應義塾大学卒。ライター。2018年からはsynodos「福島レポート」(http://fukushima-report.jp/)で、東京電力福島第一原子力発電所事故後の福島の状況についての取材・執筆活動を行う。2021年に著書『東京電力福島第一原発事故から10年の知見 復興する福島の科学と倫理』(丸善出版)を刊行。



