2018.05.25

みえない人道支援をみる――アフリカ遊牧社会の現場から
シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今回は「最前線のアフリカ」です。
なぜ東アフリカ遊牧民の人道支援の問題に取り組むのか
おそらく、この記事をご覧になっている現代日本の読者の方々の大多数は、人道支援を必要とするような毎日を生きているわけではないであろう。私たちが暮らす日本の社会にも多くの課題が山積しており、その中には人道的な危機と呼ぶべきものもある。たとえば、東日本大震災は私たちの国家を襲った人道的な危機として記憶に新しい。それなのに、なぜ、私たちは、遠い東アフリカ遊牧民の人道支援の問題を考えようとしているのだろうか。
本来の人道支援は、経済的、社会的、文化的な違いにかかわらず、そして人種や国籍にかかわらず、同じ人間である以上、なされるような支援でなければならない。緊急医療のトリアージが、あくまで治療の緊急度や重症度のみによって判断されるように、本来、考慮されるべきは、それが生命にかかわる深刻な問題かどうかだけなのである。
私たちも多くの問題を抱えていて、日々を生きるのに精一杯だ。しかし、今まさに生命にかかわるより深刻な問題を抱えている人がもしどこかにいるならば、─たとえそれがここで扱う東アフリカ遊牧民のような私たちと遠い人たちであったとしても─その人たちのことを優先的に考える必要がある。それが人道支援の根本を貫く基本的な考えのはずだ。
ここでご紹介する私たちのプロジェクトでは、東アフリカ遊牧社会で人道支援の問題を考え続けてきた。彼らの社会は、近年「ラスト・マイル(援助や支援が世界中で最も届きにくい地域)」と呼ばれるようになった世界の最貧困層の一部であり、現在、飢饉と飢餓、低強度紛争、気候変動等に関連する人道的危機と、それにともなう人道的支援が常態化しつつある。彼らは、人道支援のなんらかの影響を受けながら人道支援とともに暮らしているのである。

少年の脚に残る銃弾の跡
同じ人間として、ただし、実際には大きく異なる多様な人間として
同じ人間といえども、人道危機や人道支援の現場は、ありとあらゆる差異と格差に満ちた現場でもある。政治的、あるいは軍事的な意図が外部から介入し、人道的危機に陥った人々が利用されることも決して珍しくはない。東アフリカ遊牧民の人道危機や人道支援の現場では、過酷な現実と絶望を突きつけられる。
私も、銃撃音を耳にしながら調査をしたこともあれば、夫を殺されて、乳児とともにナイロン袋一枚を唯一の持ち物として暮らす女性に衝撃を受けて絶句したこともある。言うまでもなく、東アフリカ遊牧民と私たちの間には、経済的裕福さにおいても、言語や文化においても、住んでいる環境においても、ありとあらゆる意味での隔たりがある。そしてその隔たりは、相手が究極の弱者であるだけに、知らず知らずのうちに私たちを圧倒的な優位に置いてしまう。
逆説的だが、同じ人間としての人道支援は、実際の現場では、異なる人間の間に存在する見えない隔たりの間で行われざるをえない。それでも、私たち地域研究者は、現地調査を通じて、その地域の住民に少しでも近づこうと努めてきた。その土地の言葉を話し、同じ場所で寝て、同じ食事をとってきた。その地域の住民と同じように考えたりふるまったりできるようになろうと愚直に努めてきた。
通常、日本に暮らす私たちの多くは、支援の向こう側にある世界を十分に想像することなく、いつの間にか当たり前のように支援する側に立ち、支援する側からしかものごとをみなくなってしまう。かくいう私も、恥ずかしながら現場に身を置く以前はそうであった。しかし、それとは反対側の、支援を受ける側の地域住民の側から、人道支援をもう一度捉え直してみることはできないだろうか。
人間のことを考えるに当たって、私たち地域研究者は、無色透明な人間ではなく、つねにある特定の地域の特定の環境の中で生きる具体的な人間を想定し、さまざまな顔を思い浮かべる。特定の地域の脈絡の中で特定の生を営んできた人々の観点から、人道支援にかかわる私たちのものの見方の前提を問い直すことはできないだろうか。
地域研究の立場から、同じ人間として、ただし、実際には大きく異なる多様な人間の問題として、人道支援の問題に新たな光を当てること。これが、私たちが取り組んできたプロジェクトのねらいである。
配給食糧を自分達の論理で再配分する遊牧民
このプロジェクトのおもな研究成果は、すでに英文学術誌の特集号(S. Konaka & X. Sun (eds.), 2017. Localization of Humanitarian Assistance Frameworks for East African Pastoralists. African Study Monographs, Supplementary Issue, 53)として刊行されているが、この度、その日本語訳書籍が刊行された(湖中真哉・太田至・孫暁剛(編)『地域研究からみた人道支援』昭和堂、2018年)。
同書は、東アフリカ遊牧社会をおもな対象として、地域研究からみた新しい人道支援の在り方を追求している。第Ⅰ部では、食料・物資・医療・教育といった人道支援の基本的構成要素を網羅しつつ、第Ⅱ部では、政治的・文化的・社会的文脈に即して問題を掘り下げている。その内容は多岐にわたるため、ここではすべてを紹介しきれないが、第1章の孫によるケニア北部のレンディーレ社会の事例を紹介しよう。
レンディーレは、北部ケニアのカイスト砂漠を本拠地とし、ラクダ、ヤギ、ヒツジ、少数のウシを飼養する遊牧民である。カイスト砂漠は、年間降水量が200mm程度で、東アフリカのなかでもっとも乾燥が厳しい地域のひとつである。2011年には1年間にわたり、国連世界食糧計画が1カ月半おきに救援食料の配給を行なった。配給の内容はトウモロコシの粒、米、豆類などの主食と、調理用油、そして栄養不良の子供向けのUnimixと呼ばれる栄養食であった。
配給は、世界食糧計画の委託をうけたケニア赤十字が担当した。ただし、配給対象は集落全員ではなく、世界食糧計画の基準にもとづいて認定されたいわゆる「脆弱世帯」だけであった。これは、弱者に対して優先的に食料を援助する世界食糧計画の基本方針に基づいたものである。対象世帯の選定は、ケニア赤十字のスタッフと各集落の長老代表者によって組織された救援委員会が担当し、高齢者と乳幼児、そして寡婦など社会的弱者がいる世帯が認定された。救援食料はトラックで集落まで運ばれ、担当スタッフが脆弱世帯の名簿に沿って配給を行なった。
しかし集落の人びとは、援助機関のスタッフが帰った後、受け取った食料を一カ所に集めて、集落にいる全世帯に再分配した。なぜ彼らはそのような再配分を行ったのだろうか。
干ばつのため、人々は厳しい暮らしを強いられ、みんな助け合って暮らしている。高齢者や寡婦ほどまわりの人たちに助けられている。もし彼(彼女)らがもらった食料を自分の家だけで消費するなら、食料がなくなって彼らが困った時、まわりの誰も助けないだろう。集落の人びとにとって、慢性的な食料不足と不確実な自然災害の脅威のなかで生活を維持するには、相互扶助の社会関係がもっとも重要である。そのため、救援食料の配給から生じる不均衡によって相互扶助関係が崩れないように自ら再調整したのである。

国連世界食糧計画が配付したトウモロコシの穀物袋
遊牧民は人道支援物資をいかに利用しているか
つぎに、第三章で湖中が明らかにしている支援物資利用の事例を紹介しよう。2011年に政治家の扇動による紛争に巻き込まれ、新聞報道によると1万人の国内避難民が発生した。紛争発生直後の2011年11月に赤十字は、国内避難民に対して、緊急支援物資としてテント、水容器、食器、調理器具、毛布、トウモロコシの粉等を配給した。このうち、ここでは国内避難民による配給されたテントの活用法をとりあげる。
第一の事例では、摩耗してしまったテントを定住型家屋の建材として用いていた 。摩耗したテントは、住居の屋根部分の建材として部分的に利用されていた。第二の事例では、幼いヤギ・ヒツジ用の家畜囲いとしてテントを活用していた。第三の事例では、放牧キャンプ用の建築技術が応用され、その屋根部分として摩耗したテントが使用されていた。

テントを活用した国内避難民の家屋

テントを活用したヤギの幼獣用家畜囲い

テントを活用した放牧キャンプ式の簡易住居
もちろん、テントは、国内避難民に一時的な簡易住居を提供するために人道支援機関から配給されたものである。しかしながら、ほぼ三ヶ月以内に摩耗してしまったため、それより長期にわたる避難生活を余儀なくされている国内避難民は、なんらかの手段でテント以外の住居をすでに獲得している。遊牧民の多くは、彼らの居住地に自生している植物を中心とした自然の素材を用いて、住居を自力で建築する技術をもっているからである。
つまり、配給されたテントは、遊牧民の住居を完全に代替するような支援物資としては必ずしも有意義ではない。しかしながら、ここで示した事例は、配給されたテントの建材が配給側の意図とは異なる用途で用いられていることを示している。遊牧民が用いる自然の素材では、家屋への浸水を十分に防ぐことができない。国内避難民は、テントがもつ耐水性をよく認識しており、おもに家屋や家畜小屋の屋根の素材として、摩耗したテントを利用している。
つまり、遊牧民出身の国内避難民は、人道支援機関が配給した生活物資を、もともとの彼らの建築技術にうまく取り入れながら組み合わせることで、人道支援機関が予想しなかった方法で、彼らの避難生活に活用していることが明らかになった。
このように、現地調査によって人道支援の現場では、私たちが思ってもみなかったような事態が起こっていることが明らかになった。こうした問題は、グローバルな支援とローカルな伝統文化の対立として受けとめられるかも知れない。しかし、ここで問題なのは、伝統的な意味での文化とは異なり、グローバルな人道支援の影響をすでに受け、「変化が生じた後」に起こったさまざまな現象である。つまり、人道支援に際してより注意を払わなければならないのは、地域の伝統文化そのものの独自性ではなく、グローバルとローカルの組み合わさり方の独自性なのであり、こうしたアプローチを、私たちは「接合領域接近法」と呼んでいる。
みえない人道支援
さて、それでは、こうした現地調査の成果から導かれる人道支援のありかたとは、どのようなものだろうか。私たちのプロジェクトが明らかにしたのは、先に挙げたふたつの事例が示すように、人道的危機に直面した遊牧民は、彼ら自身による自助努力の仕組みを創りあげてきたということである。これは、人道的危機の被災者に対する保護の概念そのものを問い直すことが必要なことを意味している。
保護の物語は、人道的危機の被災者が、無力で、脆弱で、悲惨であり、依存的であるというステレオタイプ・イメージを前提としている。しかしながら、このプロジェクトが明らかにしたのは、人道的危機の被災者に対する保護は、外部からの回路にのみ限定されてしまうわけではなく、遊牧共同体の内部、あるいは共同体間に、「不可視の保護」の領域が存在することである。
自らも難民となった経験をもつ考古学者サダ・マイヤーは、このプロジェクトの国際会議で重要な指摘を行った(第8章参照)。遊牧生活では人々の手元に残るものは非常に少ないが、その代わりに、無形の知識として保存される。家の建造方法や生活用品の作り方についての知識は実践を通じて保存され、彼女が難民になった際に生き延びることができたのは、まさにそうした知識によってであった。
遊牧民の生活では、生活物資はいつか消失しうるので、それを必要な時には、また作り直せる知識を保存する必要があったのである。つまり、国際機関が実施する人道支援の領域とは別に、人道的危機に瀕した人々自身が地域住民とともに創り出した「みえない人道支援」の領域が存在することが明らかになった。
内的シェルター
救援食糧のトウモロコシやテントや緊急医薬品のように、共同体の外部からもちこまれる目に見える保護の領域に対して、共同体レヴェルの保護の領域は、「内的シェルター」と呼ぶことができる。この内的シェルターは、救援食糧のトウモロコシやテントや緊急医薬品のようにはっきりと目に見えるわけではない。
ここでいう内的シェルターは、非常に儚く、壊れやすく、柔軟な特徴を持っているが、その一方で危機には強い。それは、伝統的な文化や社会それ自体ではなく、それらが被災後の変化によって産みだした変異体であり、私たちの接合領域接近法はまさにそこに注目している。この領域は、開発や人道支援にたずさわる実務家からも、現地調査を行う地域研究者からも見過ごされてきた。
一方、人道的危機によって共同体が危機に瀕している以上、外部からの介入にまったく頼らずに、共同体のみが独力で行う人道支援のモデルを考えることは、あまり現実的とは言えない。「力強く逞しい難民」といった彼らを無責任に讃えるような避難民像は、先に指摘した脆弱な避難民像のたんなる裏返しに過ぎない。
ここで私たちが提唱するのは、遊牧共同体が創り上げてきた内なるシェルターと、外部介入による外からのシェルターを相補的に組み合わせていく方向性である。接合領域接近法は、こうした方向性を追求するためのアプローチと言って良い。
新しい普遍主義にもとづく人道支援に向けて
このようにしてみると、私たちが注目してこなかっただけで、世界のさまざまな地域には、それぞれの地域なりのみえない人道支援のありかたがあるはずだ。私たちが現在慣れ親しんでいる人道主義や人道支援が前提としている普遍主義は、西洋社会流の人道主義や人道支援を唯一の正しい規範とし、それを非西洋世界に押しつけるようなタイプの普遍主義に過ぎないことがわかる。
私たちは、決して、各地域の伝統文化に回帰することを主張しているのではない。私たちのプロジェクトが試みたことは、人道支援という従来普遍的とされてきたものを検討することによって、西洋的な規範を唯一正しい規範とみるような現在の普遍主義のあり方を、非西洋地域も包摂できるような、真の意味で普遍的な普遍主義のあり方へと解き放っていくことなのである。西洋的な規範ももちろんあってよいが、それは、あくまで世界各地に存在する多様な規範のひとつとして理解されなければならない。
私たちは、唯一正しい人道主義の規範が西洋社会にしか存在せず、それを非西洋社会にひろめていくことこそが正しいと考えるのではなく、西洋社会と非西洋社会のさまざまな接続によって、多様な規範が生みだされる可能性があり得ることに目を向け直す必要がある。
地域研究の立場からみた人道支援を提唱するこのプロジェクトは、地域的多様性に満ちたこの世界において、その多様性をそのまま肯定しえるような新しい普遍主義に向けてのひとつのステップとなるだろう。地域研究は、これまで顧みられなかった地域住民の声に耳を傾けることによって、強者の論理の押しつけによってできあがった現在あるような普遍主義を乗り越えて、地域的多様性がぶつかり合うなかで生みだされる未来の普遍性へ向けて、道を少しずつ拓きつつある。
地域研究からみた人道支援を提示したこのプロジェクトの試みは、ささやかながら、その歩みの一歩となるだろう。
プロフィール
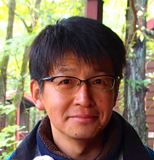
湖中真哉
1965年生まれ。筑波大学大学院博士課程単位取得退学。京都大学博士(地域研究)。現在、静岡県立大学 国際関係学部 教授。おもに、東アフリカ遊牧社会のグローバリゼーションを対象とした調査研究を行う。主要著書: 『牧畜二重経済の人類学─ケニア・サンブルの民族誌的研究』(2006年、世界思想社)など。


