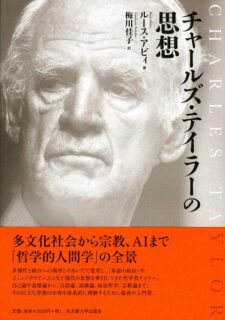2021.09.24
多様性と統一性のあいだ――『チャールズ・テイラーの思想』ルース・アビィ(名古屋大学出版会)
はじめに
テイラーは、現代の英語圏において、もっとも多産な哲学者の一人であり、哲学、歴史、言語から人工知能まで、きわめて多様な分野についての研究を蓄積してきた。そのためもあって、各分野におけるテイラーの議論を扱う研究は、世界的に膨大なものになっている。
その中でもテイラーの思想の全体像を示そうとした簡潔な研究として定評があるのが、ここに翻訳したRuth Abbey, Charles Taylor(Acumen, 2000)である。著者のルース・アビィは、カナダのマギル大学でテイラーに師事した政治思想家であり、政治理論や政治思想史、フェミニストの政治思想に精通している。
アビィの著書Charles Taylorは、2000年に出版されており、邦訳されるまでに長い期間を経ているものの、現在でもよく読まれている。これは、ケンブリッジ大学出版会より「今日の哲学」Philosophy Nowシリーズの一冊として出版されたものである。本シリーズは「今日においてもっとも広く読まれ議論されている重要な哲学者に関する新たな入門書」として位置づけられている。この中でテイラーの哲学について執筆したアビィは、同じくケンブリッジ大学出版会が出している「現代思想」シリーズの一冊である論文集『チャールズ・テイラー』Charles Taylor(Cambridge University Press, 2004)の編集者も務めている。
さらにアビィは2016年の7月にベルギーのアントワープ大学で行われたテイラーに関する学会「倫理学と存在論:チャールズ・テイラーの道徳的現象学」において基調報告をしている。これらの点からもわかるように、アビィは、テイラーの思想に関する総合的な研究について国際的にも数少ない研究者の中で、中軸的役割を果たしている。
日本においては、テイラーの思想については、すでに日本においても多くの翻訳が行われている。たとえば、田中智彦訳『「ほんもの」という倫理:近代とその不安』(産業図書、2004年)、伊藤邦武・佐々木崇・三宅岳史訳『今日の宗教の諸相』(岩波書店、2009年)、下川潔・桜井徹・田中智彦訳『自我の源泉』(名古屋大学出版会、2010年)、上野成利訳『近代:想像された社会の系譜』(岩波書店、2011年)、などがある。
このようにテイラー自身の著作については、これまで多くの邦訳書が刊行されてきたが、2019年の時点では、彼の思想に関する研究書の邦訳書は出版されておらず、この点が日本におけるテイラー研究の課題の一つになっていた。
本書は、アビィ自身によっても、テイラーの思想に関する入門書として位置付けられているが、その内容はテイラーの思想の全体をカバーしている。具体的には、道徳論、自己論、政治論、知識論、世俗論を扱っており、それぞれアビィの独自の理解が示されている。
以下では、説明の便宜上、テイラーの思想における、知識論、政治論、自己論、道徳論、宗教論の順に、その内容について簡潔に述べる。
知識論
まず知識論に関しては、第4章で扱われる。テイラーを哲学の中で特定の学派に位置付けることは難しいが、彼は、分析哲学と大陸哲学のあいだを架橋しようとした哲学者と評されている。テイラーは、社会について研究する際に解釈学的アプローチを採用するが、その際、彼は、人間が自らの行為に与える意味こそが、社会科学によって考慮されなければならないと主張する。
テイラーが解釈学の伝統を重視する理由は、17世紀の科学革命と、その革命が残した永続的な遺産が、認識論をこえて哲学一般に広まり、近代西洋の文化全体に影響を与えていると考えるからである。この認識論的な遺産を乗りこえるために、本書の第4章で述べられるように、テイラーは、関与的主体と身体化された主体をめぐる理論を展開している。
政治論
テイラーは、人間が自らの行為に与える意味の重要性を強調することによって、その意味が、時と場所によって変化するということを鋭く認識せざるをえなくなった。本書の第3章で扱われる彼の政治論で示されるように、テイラーがコミュニタリアンと呼ばれる所以は、彼が人間の社会的性質を強調し、自己がその内部で生活するコミュニティから与えられる意味と、そのコミュニティに対して個人が負う義務を強調している点にある。
たしかにテイラーは、消極的自由論と原子論的個人論を長年にわたって批判し、西洋の政治における共和主義的な伝統を復活させようとしてきた。しかし他方で、彼は個人の自由と権利を擁護し、市民社会の価値を高く評価し、国家の中立性の理念を批判してきた。アビィは、テイラーにおけるコミュニタリアンとしての要素だけでなく、リベラリズムに対するテイラーの複雑な関係についても指摘している。
自己論
前に述べたように、人間が自己の行為に与える意味は、自らの属する社会やコミュニティによって変化する。しかしながら、このように異なるコミュニティのあいだで考え方や価値観の差異があるからといって、彼は、普遍的で永続的な人間の性質があるという考え方を拒否するわけではない。彼は、人間存在に必然的に付随する一定の特徴があると考えており、その特徴は、時間、場所、文化、そして言語をこえると考える。
たとえば、本書の第2章のテーマである自己論で述べられるように、人間が自己解釈的である――人間が自己を解釈する仕方が自らのアイデンティティの重要な部分を形成する――という特徴、および、アイデンティティが他者との対話を通じて形成されるという特徴は、人間にとって普遍的な特徴であると彼は考える。テイラーによれば、自分自身についての人間の感覚、すなわちアイデンティティは、自分一人だけで形成できるものではない。アイデンティティを構築するためには、他者からの承認が必要不可欠となる。逆に、他者から正当に認められた自己のアイデンティティを持つことができなければ、自己のアイデンティティは歪められ、傷つけられることになる。
道徳論
さらに、すべての人間に共通するその他の特徴として、何らかの目的を持つことが、人間のアイデンティティ形成において重要な役割を果たしている点が挙げられる。本書の第1章の道徳論において示されるように、個人は、道徳的フレームワークの中に位置づけられることによって、自己がもっとも高く評価している善に方向づけられ、自己の生活が、それらの善に近づいているのか遠のいているのかについての感覚が形成される。このような感覚を通じて、人は、テイラーのいう「強評価者」になっていくのである。
強評価とは、自己の善を、他の欲望や目標などよりも質的に高次のものとして、より価値のあるものとして、意味のあるものとして位置づけ、他の欲望や目標などを序列づけるための評価基準にすることを指している。テイラーにとって、人が強評価を行うという事実は、人間が、複数の選好を単に比較考慮しているわけではないことを意味している。そうではなく、人びとが自らの行動を選択する際には、自己が評価し求める諸善のあいだで質的な区別をしているのである。
宗教論
本書では、道徳論、自己論、政治論、知識論に加えて、最終章である第5章「結び」で宗教論が論じられる。ルース・アビィの原著が刊行された2000年の段階では、テイラーが2007年に出版することになる大著『世俗の時代』A Secular Age (2007)(邦訳、名古屋大学出版会、2020年)は出版されていなかった。しかしアビィの本書第5章は、その概要を先取りした章となっている。テイラーの宗教的見解は、すでに『自我の源泉』の最後の部分にも発見できるが、『自我の源泉』の刊行後、彼は、このテーマについて、より明示的に述べるようになっていく。たとえばテイラーは『世俗の時代』において、現代西洋社会におけるキリスト教信仰の変遷を歴史的に辿っている。
アビィがすでに本書で指摘していたように、テイラーの関心は、現代の個人が、自分自身、自己が関わる社会、そして自然の世界を、神聖なるものや超越的な領域に言及せずに、どのようにして純粋に世俗的な方法で理解することが可能になってきたかという点に向けられている。しかしながら、アビィの見解では、時とともに宗教の内容が変化しているにもかかわらず、テイラーは、人間が、彼のいう「超越的なるもの」に向かって必然的に方向づけられていると考え、人間をこえたところにある何らかの意味を渇望しているのだと示唆している。
まとめ
これまで、本書の各章の内容について述べてきたが、本書全体を貫くテイラーの思想の中心的な特徴は、「統一性と多様性のあいだを調停」しようとする点にあると、アビィは主張する。言い換えれば、テイラーは、互いに孤立しているものたちを和解させようとしているのである。このような彼の特徴は、彼の経歴からも説明することができる。
テイラーは、カナダにおいて、イギリス系文化とフランス系文化が競合するとともに調和を模索しているケベック州で、イギリス系の父とフランス系の母によって育てられた。ケベック州モントリオールのマギル大学を卒業してイギリスのオックスフォード大学で博士号をとり、世界の多くの大学で研究と教育に従事しながら、イギリスやカナダでは、政治活動にも関与する。
このように、テイラーは、複数の異なる文化やネイションの緊張と相互承認の間で生きてきた。したがって特定の文化については、たとえそれがイギリス系文化であろうとヨーロッパ文明であろうと、それらを単純に肯定あるいは否定することをつねに拒否してきた。こうしたテイラーの態度について、アビィは、彼が理論的な体系を構築することを拒否し、「問題を単純化してまとめようとするよりも複雑化」しようとしている、と説明している。
テイラーがさまざまな分野で提出してきた多くの主張のあいだで、その中の矛盾や理論的なほころびを指摘するのは、難しいことではないだろう。しかしアビィは、最初はテイラーの元指導生として、次に友人として、つねにテイラーの哲学に寄り添い、その内在的な理解に努めてきた。したがって本書は、テイラーの思想を批判的に検討するというよりは、彼のさまざまな理論のあいだの全体的な関連性を示すものとなっている。
また、テイラーの抽象的な哲学を親しみやすいものにするために、アビィがおそらく自らの経験をもとにした具体的事例が散りばめられている。本書は、彼女が、テイラーの巨大な哲学を理解しようとした努力の痕跡である。アビィは、このような作業を通じて、本書が示すような総合的なテイラー理解を作りあげたと思われる。
プロフィール

梅川佳子
中部大学人文学部講師。名古屋大学大学院法学研究科修了。博士(法学)。専門は政治学。とくにチャールズ・テイラーの政治思想についての研究>。日本カナダ学会研究奨励賞受賞。訳書に『チャールズ・テイラーの思想』(名古屋大学出版会、2019年)、共訳書に『世俗の時代』(千葉眞監訳、名古屋大学出版会、2020年、日本翻訳出版文化賞)