2010.09.13
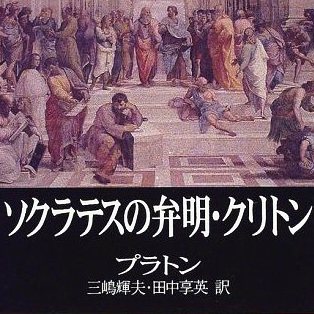
法を守る理由
なぜわれわれは法を守らなければならないか。
この質問は一般的に、たんに法の命ずるところに反する行動を取らないこと(遵守compliance)だけではなく、たとえその内容が自らの信念に反しているとしても、それを尊重すること(服従obedience)の問題として理解されている。
たとえばアテネの民会から死刑を命じられたソクラテスは、亡命を選ぶことなく従容と死を選んだといわれている。法に反したときに国家から加えられる制裁を恐れて法を遵守するのであれば、すでに死刑が命じられている場合になお法にしたがう理由はないだろう。亡命を企てて失敗しても、何もせずにいても死刑がまっているならば、成功する可能性にかけて法に反するのではないだろうか。
ソクラテスがそうしなかったとき、彼は単に法に《従わされた》のではなく、自発的に《従った》のである。だが、それは何故なのだろうか。
愛に基づく議論、公正による議論
この問題に答えるひとつの典型的な方法は、家族愛ないし同胞愛に訴えることである。
ソクラテスがまさにそう述べたように、国家なくして個人は存在しないのだからそれは親のごときものであり、親の命令を子が聞くように、自らを生み出した国家の命令に個人はしたがわなくてはならないというわけだ。
だが個人が集まって国家をつくったという古代とは、逆の観念をもっている近代以降の国家において、ソクラテスの議論はそれほど説得的ではないだろうし、多民族国家や人工国家のように「国家は家族である」というシンパシー自体に違和感を覚える場合もあるだろう(もちろん日本でも抵抗感のある人はいるだろう)。
そこで次にでてくるのが、公正fairnessにもとづく正当化である。
たとえば野党の支持者にも、現在の政権がつくった法を守るように要求できるのは、政権交代が実現したあかつきには彼らもまた、その時点の野党の支持者に法に服従することを求めるからだ。
自分たちが求めるだろうものは自らも引き受けなくてはならない、それが「公正」だと、そういうことになろう。
だが問題は、第一に、そのような逆転の可能性がない絶対的な少数者にも、この議論で服従を求めることができるかという点にあるし、第二に、これで求められるのはあくまでも、「遵守」であり「服従」ではないのではないかという問題もある。
《きちんとした》統治
すると結局、被治者に服従を求めることができるのは、統治者が《きちんとした統治》を行なっているからではないか、自分が普通に判断するよりも、そのような《きちんとした統治者》の意見を尊重したほうがよさそうだと、個々の市民に思わせるような条件が整っている場合に、人びとは「服従」するのだという可能性が残る。
たとえば生活を改善しなさいという医師の指示と自分の意見が違ったり、反発を覚えることもあるだろうが、しかしその医師のふるまいが《きちんとして》いれば、われわれはとりあえず自分の勝手な判断を差し控えて、彼の意見を尊重するのではないか。そのようなことが法の場合にも起きるのではないかというわけだ。
だがもちろん問題は、法をつくる統治者のふるまいが《きちんとしている》とはどういうことかという点にあるだろう。
医師の場合それは、教育や資格試験を通じた専門能力の認定が基礎となるだろう。だがそれだけでなく、挙措動作におかしな点がないとか(嘘かまことか「人は見た目が九割」という話もあった)、言動が一貫しているかといった要素もあるだろう。いい大学を出てちゃんと免許を持った医者のいうことでも、その内容が朝令暮改されるようなら、やはりわれわれは従いたくなくなってしまうのではないだろうか。
一貫性による正統性
法の場合、同じ統治側の人びとでも、主に専門性を担当する官僚と、民主的な正統性を担当する政治家とでは、《きちんとしている》ことの内容は異なるかもしれない。
しかしどちらにせよ、ふるまいが首尾一貫していること、時間を通じた言動に矛盾や自己撞着がないこと、別の言い方をすれば、そのときどきの利害に応じて、主張や立脚点を変えて、たんに利益を最大化することを狙っているのではなく、特定の立場を維持していることが、「服従」の対象として尊重されるためには求められるだろう。
またそれは、服従の根拠を公正におく場合でも、立場の交換可能性を保障する価値として要求される。要するに、統治者(の一員)として自らのつくりだす法を尊重し、服従することを人民に求めるのならば、統治者として《きちんとして》いること、過去の言動と現在の主張の一貫性を保つことが必要になるのだ。
立法府の一員として自分たちもコミットしたはずの制度改正が、不利な結果をもたらしそうになるや、「あれは素人判断だ」といいだすとか(そういう側面はたしかにあるが、ではなぜ過去にそのような改革を行なったのか)、国会議員という統治者=権力者でありながら、自分がその立場から追われそうになるや、国家権力の横暴を言い立ててみるといった姿勢は、《きちんとした》統治を放棄することによって、人民が法に服従する理由自体を掘り崩してしまう。
その意味で、特定の政治家の評価の問題にとどまらず、国家・権力の正統性に影響が及ぶ問題だと、この観点からはいわなくてはならないだろう。
もうひとつの選択肢
念のためにいえば、しかし、最初からこの問題構成を拒否する選択もある。
国家が国民に要求できる・すべきなのは、あくまで外形的な行為が法の範囲内に収まっているという意味での「遵守」であり、内心に関する「服従」など扱うべきではないし、また扱えないという立場だ。
この場合、結局国家によって重要なのは外形的な「遵守」を確保できるかどうかなので、それを人民に強制する効率的な手段を確保できているかどうかだけが問題になる。価値や理念の問題をさておいて、純粋に実力の問題として統治を考えるリアル・ポリティクス的な視点ということができよう。
だがこの場合、正当かどうかにかかわらず、相手に対して何かを強制できるだけの実力を形成することに成功した側の勝ち、という、ある観点では国際政治の現実のようなものが国内法秩序においても全面的に通用することになるだろうから、人民裁判だろうが何だろうが、現実的である以上理性的だということになろうし、現に裁判という国家の権力装置が動作してしまった以上はその動機がいずこにあったか、国策だったかどうかといったようなことを問題にする意義はないということになろう。
実力に裏づけられた厳然たる国家権力の作動に対して、そのようなリアル・ポリティクス的な視点の持ち主ができるのは、せいぜいおとなしく牽かれていくことくらいではないかと、そういう話である。
推薦図書
アテネがスパルタに敗北した戦争ののち、青少年を惑わせた罪で民会に告発されたソクラテスが、いかに自らの行為を正当化したか(ソクラテスの弁明)、また待ち受ける死刑から彼を救いだそうとする友人クリトンに対し、ソクラテスがどのような理由でそれを拒否し、死を受け入れることを選んだか(クリトン)を描いた、有名な対話篇。「法に従う義務」という問題を考える際の出発点として、しばしば参照される古典である。
プロフィール

大屋雄裕
1974年生まれ。慶應義塾大学法学部教授。法哲学。著書に『法解釈の言語哲学』(勁草書房)、『自由とは何か』(ちくま新書)、『自由か、さもなくば幸福か』(筑摩選書)、『裁判の原点』(河出ブックス)、共著に『法哲学と法哲学の対話』(有斐閣)など。


