2016.02.16

「自然保護」を本気でやるには何が必要か――CEPAツールキットの紹介を中心に
地球サミットで生まれた2つの条約
昨年の12月、気候変動枠組条約の第21回締約国会議(COP21)がパリで行われた。温暖化に対する危機感が共有され、アメリカや中国も加えた多くの国で「パリ協定」が締結された。日本でも比較的大きく報道されたのは、気候変動問題が現在最も重要な地球環境問題と認識されているからだろう。
気候変動枠組条約は、1992年のいわゆる「地球サミット」で生み出された条約だが、同じ会議でもう一つ、世界規模の環境条約が誕生している。それが「生物多様性条約」である。この条約は、自然保護に関する条約としては最も広い範囲をカバーし、また194もの国と地域が加盟しているという点でも重要な条約である。2010年には、この条約の第10回締約国会議(COP10)が名古屋市で開催され、話題を集めた。しかしそれから6年が経ち、名古屋会議について話題にされることは少なくなった。
全般的に、生物多様性問題は、気候変動問題に比べて注目度がうすい。それは一つには、言葉やコミュニケーションの問題がある。気候変動問題が、「温暖化」というキーワードを通じて五感に訴えかけるのに対し、生物多様性問題は、「生きもの」の保護の問題と考えられ、人間の生活に密着したものとは感じられなくなっている。しかし、後で述べるように、生物多様性の減少は人間の生活に大きな影響を与えるものなのだ。
気候変動対策のネックになっているのは、対策が経済発展の妨げになることへの懸念である。同様に、生物多様性保全、いわゆる自然保護のネックになっているのも、それが経済発展の妨げになるという論点である。自然保護の主張を採用すると、端的には「開発」が抑制されるわけだが、生きものの保護のために経済活動が抑制されることに対して反発を感じる人も多い。そこから自然保護は経済発展と対立関係にあると考えられてきた。
生物多様性をめぐる国際的議論の成熟:自然保護 対 経済発展 を超えて
しかし生物多様性をめぐる国際的議論において、「自然保護をとるか経済発展をとるか」といった対立軸は過去のものになりつつある。そこでは、自然(生物多様性・生態系)を守ることは経済発展の基盤であるという認識が進んでいる。それを示す典型的な用語として「生態系サービス」がある。これは自然環境が人間にもたらすさまざまな恵みの総称である。
その中では「基盤サービス」(大気・水・土壌)、「供給サービス」(食糧・資源・エネルギー)、「調整サービス」(気候調整・洪水制御・廃棄物分解)、「文化的サービス」(科学・レクリエーション)といった、人間にもたらされるさまざまな恵みが掲げられている。生物多様性の減少は生態系サービスの減少をもたらし、人間の暮らしも貧しくなるというわけだ。それに関連して、生態系や生物多様性に対する経済的評価も進んでおり、「生態系と生物多様性の経済学」(TEEB)という報告書もつくられている。
さらに近年では「自然資本」という言葉も登場している。企業にとって、物的・人的な資本を維持しなければならないのと同様に、経済活動を持続的に行うためにはその基盤となっている自然(生物多様性)を維持しなければならない、という考え方だ。
現在の生物多様性保全論ではこのような考え方が主流となっている。自然保護と経済発展をいたずらに対立させるのではなく、経済発展の基盤に自然保護を位置づけている点で、現在の国際的な自然保護の議論は成熟の段階に入っているといえよう。
「思い」だけでは自然は守れない
このように経済の論理で自然保護を語ることに対して、従来の自然保護運動家は眉をひそめるかもしれない。確かに、自然保護を訴える人々の動機としては、経済的な計算によるものよりも、自然を失いたくない、大切な場所を奪われたくない、といった直観的な「思い」のほうが大きいだろう(私がこの分野の研究をしているのもそのような動機に基づいている)。
しかし、自然保護の現場においては利害対立が生じる。そのときに、自分の「思い」が伝われば、相手が納得し、合意が形成され、対立が解消するというのは、楽観的すぎる見方であろう。そうではなく、第三者的な土俵で語り合うための共通言語がなければならない。そこで必要になるのは、それぞれの「思い」とは別の、より客観的な自然保護のための論理である。「生態系サービス」や「自然資本」は、多くの人々が納得できる論理であり、そこから利害関係者間の共通の土俵になりうると考えられる。
これは、自然保護に対する個々人の「思い」を、経済的・生態学的な論理に翻訳すべきであるということではない。「思い」の強さ、真摯さはそれ自体に価値がある。時にはそれが人を動かすこともある。しかし、「思い」の強さや動機の純粋さを訴えるだけでは、自然保護を広めることは難しいだろう。自然保護に対する「思い」は、経済的・生態学的な共通言語とともに示されることで、多くの人に理解される力をもつようになるだろう。
自然保護は愛好家の趣味の問題ではない
また、自然保護を具体的に遂行するためには、人間か自然かという二者択一的議論はかえって有害であり、自然保護運動を行っている人々を社会から孤立させることになるだろう。自然保護は、一部の人々の趣味の問題ではない。生物多様性条約の会議に集まっている人々は、自分が「自然愛好家」だから来ているわけではない。そこで議論されているのは、例えば遺伝資源から得られる利益の配分といった、国や地域の資源や経済に関わる議題も多いのである。そこは南北問題の最前線ともいえる。
こういったことは、生物多様性をめぐる国際的議論においては半ば常識になっているように思われる。しかし、このことが日本の多くの人々にきちんと伝わっているかは疑わしい。自然保護は学者や登山家の浮世離れしたご高説、というのは遠い昔の、しかも間違った理解である。“自然を守るなんて、霞みを食べて暮らせというのか”という反感は見当違いだ。このような理解だと、生物多様性条約の締約国会議で論じられていることがまったく分からないだろう。政策決定者や企業の意思決定者は、自然保護をめぐる国際的議論について知っておかないと、ふとしたことで国際的非難を浴びかねないだろう。
CEPAツールキットとは
日本の現状と国際的議論とのギャップは、〈環境教育〉においても顕著である。ここでの〈環境教育〉とは、学問分野としての環境教育や、個々の具体的な取り組みについてではなく、日本で環境教育として漠然とイメージされているもの(例えば環境意識を高める、環境保全活動を促すなど)を指している。
先にも述べたように、生物多様性問題が気候変動問題よりも注目度が低いのは、言葉やコミュニケーションの問題が一つの原因といえる。それを打開するために、CEPAツールキットという、生物多様性の教育や普及啓発活動を行う際の手順や留意事項が体系的に書かれたマニュアルが作成されている(http://www.cepatoolkit.org/ 日本語訳はhttp://cepajapan.org/newsevent/1831/)。
CEPAとはCommunication, Education, and Public Awarenessの頭文字をつなげた言葉である。教育・普及啓発というと、お説教じみたことがたくさん書かれているような印象を受けるが、このツールキットの中心にあるのは、コミュニケーションの方法論である。ここには、生物多様性にとどまらず、何らかのプロジェクトを実行する際には読んでおくと必ず役に立つ内容が盛り込まれている。
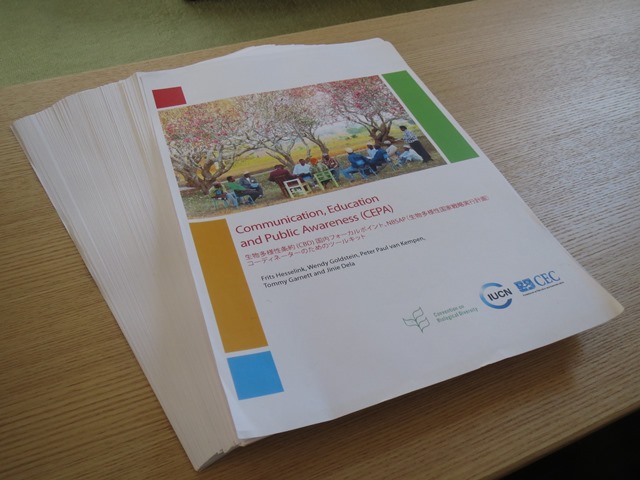
なぜCEPAが重要なのか
CEPAツールキットは、「問題を解決するにあたって、なぜコミュニケーションや教育、普及啓発が必要か」という問いからスタートする。そこでは、生物多様性について知ってもらうだけでなく、人々に行動を変えてもらうことが目的とされている。そのためにはコミュニケーション上の工夫が必要となる。
そもそもコミュニケーションとは伝達であり、確実に伝えることが必要なので、伝わったかどうかの確認が重要なはずである。CEPAツールキットでは、「言った」ことを「実行」してもらうためにコミュニケーションをしているので、本当に言ったことが実行されるかどうかを細かく確認している。その間には多くのハードルがある。
「言ったことは、必ずしも聞かれるとは限らない」。
「聞かれたことは、必ずしも理解されるとは限らない」。
「理解されたことは、必ずしも同意されるとは限らない」。
「同意されたことは、必ずしも行動に結びつくとは限らない」。
「行動に結びついたことも、繰り返し行われるとは限らない」。
言いっぱなしではコミュニケーションが成立していないということだろう。この執拗な確認の要求からも分かるように、このツールキットの製作者たちは、徹底した結果主義に立ち、問題解決を志向している。そしてここにこそ、製作者たちの自然保護に対する「思い」を感じる。何が何でも生物多様性の損失を食い止めなければならないという熱意がここにはある。
ステークホルダーの関与について
その上で、生物多様性保全のための効果的な普及啓発として、(1)関係者間のネットワークを構築すること、(2)多くのステークホルダーを関与させること、(3)戦略的にコミュニケーションのやり方を計画することが必要になる、とされている。まるで企業の経営戦略のような文言である。
例えば、ステークホルダーの関与というテーマならば、保護地域を拡大する場合のステークホルダーとして、通常は、(1)許認可権者(環境省、林野庁など)、(2)直接的に影響を受ける人(土地所有者、居住者、木材会社、旅行会社など)、(3)間接的に影響を受ける人(地元企業、保護区の外の土地所有者・居住者、環境NGOなど)、(4)人々の意見に影響を与える人(地域のオピニオンリーダー、生態学者、メディア)などがリストアップされ、この人たちとのコミュニケーションが重視される。
ここでCEPAツールキットは、それ以外にも「忘れられたステークホルダー」がいることを指摘する。それは「内部のステークホルダー」すなわち「直属の上司や、他の部局を担当するスタッフ」であり、彼らとのコミュニケーションが第一に必要なのだと説く。外部のステークホルダーよりも先に、内部のステークホルダーとのコミュニケーションを確実にとっておくことが大切なのだ(Communicate internally first before externally)。
コミュニケーション戦略について
コミュニケーション戦略について書かれた箇所では、(1)「計画を失敗することは、失敗に向けた計画をすることだ」(Failing to plan is planning to fail.)という名文句や、(2)コミュニケーションの相手を特定することによって、コミュニケーションの役割が決まってくるという洞察が登場する。
また(3)コミュニケーションの目的はSMARTに(Specific 具体的、Measurable測定可能、Acceptable受け入れられる、Realistic現実的、Time-related期限を定めた)という命題が示され、単に「公園をきれいに」という目標ではなく、「公園の訪問者の95%がゴミを捨てないようになることを3年以内に達成する」という目標を立てることが求められる。最後に(4)事業評価のモニタリングや評価とは別個に、事業のコミュニケーション過程についても「モニタリング」し「評価」することを計画に組み込むべきとされる。ここで、コミュニケーション自体についても反省とフィードバックを求めているあたりに、CEPAツールキットの特徴がよく表れている。
具体的かつ詳細な指示
さらに興味深いのは、細かい指示がたくさんあることだ。参加型コミュニケーションを実現するには、ワークショップを工夫する必要がある。講演者が長話をし、多くのパネリストの話が続き、質疑応答の時間が短く、1人の質問者が時間を独占するといったシンポジウムは避けるべきだ。情報公開は、単に情報を出せばよいという問題ではなく、情報を一括管理した上で公開すること(窓口の一本化)がポイントであり、それをクリアリングハウスメカニズムという。
ウェブサイトをつくる際には、最も基本的なセクションは情報豊かで変更を少なくすること、そして全ての情報が3クリック未満でアクセスできることが肝要である。プレスリリースの際には、身近な地域の話題(1km先で1人死ぬことと、1000km先で1000人死ぬことの注目度は等しい)や、自分自身の問題と感じられる話題、そして新しく、驚きのある話題(イヌが人を噛んでもニュースにはならないが、人がイヌを噛むとニュースになる)、ストーリー性のある話題を中心にする。そしてプレスリリースは最大400語(英単語を想定しているのであろう)、7段落に収めるべきである。
このような事細かな技術的な議論は、日本では〈環境教育〉としてはイメージされにくい。しかし、環境意識を高め、環境保全活動への参加を促すことを本気で追求するならば、こういった細かい技術的議論を大いに参考にすべきだろう。
「自然保護」を本気でやるには
生物多様性をめぐる国際的な議論においては、自然保護と経済学、および自然保護と教育論が、実践的・技術的なレベルで結びついているといえよう。「自然保護」を本気でやるには、「思い」を訴えるだけでなく、こういった実践的・技術的な智慧を総動員するべきだ。
そして、国際的な議論をきちんとフォローすることと、コミュニケーションの技術論を軽んじないこと、具体的な行動内容や目標を提示することなどが必要だろう(「自然に優しく」とか「一人一人の心がけ」といった呼びかけではなく)。それらを通して、日本の自然保護運動もより洗練され、自然保護に対する社会の見方も変わっていくと思われる。
プロフィール

吉永明弘
法政大学人間環境学部教授。専門は環境倫理学。著書『


