2013.11.18
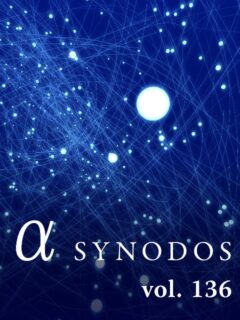
「当事者研究」の可能性について語る
「研究してみようか」――自身の「障害」を分析し、研究する「当事者研究」。当事者は研究にどう関われるのか、その可能性について語り合う
当事者研究の広がり
荒井 最近、「当事者研究」という言葉が、あちこちで使われるようになりました。この広がり方の背景には、おそらく、それだけ「当事者が主体となって何かをする」「新しい価値や枠組みをつくっていく」ということに対する潜在的な需要があるのだと思います。その需要の具体像を言い当てることは難しいのですが、今日のお話の流れの中で、その糸口だけでも掴むことが出来たらいいかな、と思っています。
もともと、「当事者研究」という言葉は、北海道の浦河町で活動している「べてるの家」の試みから生まれてきたものですね。熊谷さんも、綾屋紗月さんと共著で「当事者研究」と冠した著作を出されていますし(『発達障害当事者研究――ゆっくりていねいにつながりたい』医学書院、2008年)、あえてその言葉は使わなくとも、内実は「当事者研究」といってよいご本も出されています(『リハビリの夜』医学書院、2009年)。こういう言い方が正しいかどうかわかりませんが、熊谷さんや綾屋さんのご著書と、「べてるの家」の人たちの著書を読み比べてみると、「べてる」の人たちのほうが「文学的」な感じがします。もちろん「当事者研究」の「当事者」の中身が違うので、やり方が違うのは当たり前なのですが。
熊谷 そうかもしれませんね。
荒井 「べてる」の人たちがやっているのは、「研究」と銘打ってはあるけれども、実際は、「自分という人生の語り直し」に近いように思います。それに比べると、綾屋さんのご本などは特にそうなのですが、自分の身体的な特徴を限界まで言語化しようとする試みですね。「当事者研究」という言葉自体はいろいろなところで目にするのですが、その言葉を使う人たちの中で、ちょっとずつ中身が違っているようにも思います。熊谷さんご自身は、「当事者研究」という言葉について、具体的に、どのようなイメージをお持ちですか?
熊谷 「障害」という括りが適切かどうかわからないのですが、なにか困りごとを抱えている人がいたとして、その困りごとに対して「研究してみようか」という呼びかけがなされたときにピンときた人たちが、各々で自分たちについての研究をはじめている、というのが、当事者研究という実践を説明する一番広いくくりと言えると思います。「べてるの家」をつくった向谷地生良さんも、当事者研究の定義について具体的な内包とか外延とかは規定しているわけではありません。研究方法もかなりマチマチです。
大切なのは、「研究してみようか」という呼びかけが何を意味するのかという点ですね。「研究」にもいろいろな効果があります。たとえば「べてる」で「当事者研究」が最初に明示的にはじまったエピソードというのが象徴的かもしれません。有名な方なのでお名前を出してもいいと思いますけど、河崎寛さんという方がいて、大変な問題を抱えていらっしゃった。親を殴る、学生を殴る、食事中に茶碗を投げる、親の大事なものを壊して親を困らせる、住宅ローンが払い終わったばかりの自宅に放火するなど、いわば「問題行動」をたくさん起こしていたのです。
そういう誰も手を付けられないような状態で、担当のソーシャル・ワーカーだった向谷地さんが面接することになった。仲間も、医療関係者も、支援者もさじを投げかけていて、万事休すじゃないけど、打つ手なしというような状況にあって、向谷地さんもなかば破れかぶれに、「研究でもするか」と言った。そのときに、急に河崎さんの眼の色が変わって、「研究、したいです」というふうに言ったんだそうです(『べてるの家の「当事者研究」』)。このエピソードは、研究とはなんであるかを考える上で、とても象徴的な何かだと思ってるんです。その瞬間、何が起きたんだろうということですよね。
いろんなことが考えられると思うのですけど、一つは「免責」っていうんでしょうか。それまで本人は、爆発をしてしまった後にどこかで自分を責めるという回路がすぐにやってきて、その責める回路が次の爆発の燃料になるみたいな悪循環の内にいたんだということが、河崎さん自身の当事者研究で明らかになった。
そして、その循環というのは、ある種の常識的な価値判断みたいなものを前提にした回路だと思うんです。物を壊してはいけないとか、自分や他人を傷つけてはいけないとか、そういう常識的なものを当事者も内面化していて、それがベースになって、ある種のサイクルを作り上げてしまう。そういう人に対して、「研究してみようか」という呼びかけをすることは、一度その常識的な価値判断をカッコに入れる効果があると思うんですよね。まずは他人事のように、自分のしでかしたことを分析対象にしていく。研究対象にしていく、という掛け声ですね。
荒井 「他人事のように」という距離感が面白いですね。
熊谷 このエピソードを聞いたときに、ある編集者さんが、「なんて無責任な」と言ったらしいんですね。つまり「研究してみよう」と呼びかけることは、常識的なことを棚上げするというか、規範に沿わない自分のふるまいを他人事のように観察するということなので、市民的な常識では「責任の自覚がない」という風に見られがちな、リスキーなことなんです。でも、実は「免責」されてはじめて「引責」できるという構造がどこかにあるような気がするんです。それは自分の経験に照らし合わせても実感があります。
たとえばいつも引き合いに出すのは「失禁」ですね。「おもらし」です。自立生活運動に関わる前までは、私も「おもらし」を私秘化していたというか、恥ずかしいこと、禁じられたこと、端的に悪いことだと思っていたんですけど、自立生活運動の中ではオープンになっていました。「エルドラド(黄金郷)問題」って言われていて(笑)。いわば失禁が公共化しているような空間に出会って、ある種、ものすごく「免責」されたんですが、同時に全然違う角度から重たい「引責」が加わってきたんです。
具体的に言うと、失禁の仕方ですよね(笑)。失禁を公共的なものにしていくときに、無制限にしていいかというと、そうでもない。「失禁スタイル」みたいなコードが別のところからやってきて、自分でコントロールできる領域とできない領域の線引きが変わるんです。コントロールできる選択の幅が残されている領域は「引責」できるんだけれども、選択の幅がない、必然的に、機械論的にそれが起きてしまう領域というのは「引責」できるわけがない。だから「引責」と「免責」の境界ラインというのは、自分で変えられる部分と変えられない部分の境界ラインでもあると思う。
ところが、私たちはいつの間にか常識的な境界ラインを内面化しているので、その境界ラインが自分の体に合っていないということがしばしば起きるんですね。その線の引き直しが、「研究してみよう」という呼びかけの基本的な機能だと思うんですよ。
ハイブリッドとしての「当事者研究」
荒井 向谷地さんが出されたという「研究してみよう」という一言は、ソーシャル・ワーカーの「職人技」ですね。ベテランのソーシャル・ワーカーさんの中には、現場で鍛え上げられた「職人技」としか言いようがない技術を持っている人がいます。
熊谷 そうですね。
荒井 「べてるの家」の人たちの研究っていうのは、いままで奪われてきた「自分物語」みたいなものを、もう一回自分の言葉で語りなおそうというところがあるんだと思います。「精神科」が扱う症状って、すごく難しいところがあって、「統合失調症」の幻聴や幻覚の現れ方一つとってみても、当人の人生の積み重ねと切っても切れない部分があるように思います。みんな同じように幻聴が現れるかっていうとそうでもなくて、いままでの人生の積み重ねがあって、そのうえで幻聴がある。
病院の診察室では、その幻聴の部分だけ切り取られて、「あなた幻聴がありますね。幻聴があるから精神障害者ですね」という言われ方をしてしまう。「べてる」の試みには、医療がきちんと相手にしてくれなかった「自分物語」の部分を、もう一回自分の言葉で積み上げてみようという部分があると思うんです。だから向谷地さんの「当事者研究」のご著書を読んだときに、私は「これは物語論だ」って思いました。医療にいままで奪われてきた言葉を取り戻す試みなんだと。
熊谷 確かに、そうかもしれません。
荒井 医療って、ある程度客観化できで、数値化できて、測量できる問題を取り扱うわけですよね。たとえば腕が30度しか曲がらない人と、50度まで曲がる人がいて、二人の腕の可動範囲は測定できるじゃないですか。で、その結果として30度しか曲がらない人のほうが客観的に「障害が重い」ですよね。医療的な観点からすると、そうなってしまいます。
でも、その二人比べて「人生どちらが幸せか」っていうのは、それとは基本的には関係がない。それは自分の人生という「自分物語」を、どちらがより豊饒なものとして持っているかという問題です。向谷地さんたちのやっている「当事者研究」というのは、今まで医療が見てこなかった、客観的には測定できない「自分物語」を編みなおして行こうという試みなのかなと思います。それは、私の感覚からすると、すごく「文学的」なんです。それに比べると、熊谷さんや綾屋さんがやっている「研究」は、本当にアカデミックに近い「研究」のような気がします。
熊谷 大まかにわけると、そういうところがあるかもしれませんね。正しいと思います。ただ一方で、向谷地さんって、すごく「メカ好き」なんですよ。車とかパソコンとかが好きだったり、基本的には機械論的な発想の人という印象があります。当事者研究の中でも、苦労の「メカニズム」という言い方をよくします。石原孝二先生と『当事者研究の研究』(医学書院)という本を共著で出したんですけど、そこで向谷地さんにインタビューしたときに、いろんなものが合流して「当事者研究」が出来上がってきた様子が伺えて興味深かったです。
荒井 いろんなものが合流、というところに興味があります。「当事者研究」はハイブリッドなものなのですね。
熊谷 既存のいくつかの実践が源流となって、それが合流して、現在の「当事者研究」という潮流が出来上がっています。
一つ目は、いま荒井さんがおっしゃった「語りの文化」ですね。実はアルコール依存症の自助グループであるAA(アルコホリック・アノニマス)の語りと分かち合いの文化を、統合失調症の自助活動に取り入れたSA(スキゾフレニック・アノニマス)という試みを、日本で初めてやったのが「べてるの家」らしいんですね。当時、海外ではすでにSAはあったんですが、日本ではAAや、薬物依存症のNA(ナルコティック・アノニマス)しかなく、AAと同じものをやってみたいと「べてる」メンバーが提案して、当事者だけのグループでSAをやってみた。
それから二つ目の源流は、1980年代の自立生活運動の流れです。向谷地さんは、北海道の小山内さんの「いちごの会」にずっと関わってこられたので、そのあたりの流れがもつ思想も合流している。
三つ目は、SST(social skills training 生活技能訓練)とか認知行動療法などの流れです。これらは問題を機械論的な枠組みでとらえ返し、仮説検証的に生活を組み替えていくという部分で当事者研究に方法論的な枠組みを与えている源流ですが、どちらかというと自助というよりもセラピスト―クライアント間の治療の枠組みとしてとらえられがちです。しかし、「べてる」での取り入れられ方っていうのは、かなりアレンジしているようですね。
たとえば診察室の中で行うのではなく、現場やコミュニティーの中で行うわけです。ある意味、安全じゃない場所で行うといいますか、まさにトラブルを目の前にして、ケンカしている相手と一緒にSSTをやったりするんですね。診察室の中で、クライアントとセラピストの間でやるんじゃないという点が、「べてる」でのエッセンスなんじゃないかって思います。ですので当事者研究は、物語的なナラティブの文化を持ちつつも、機械論的な観察と解釈、検証の発想も合わさった部分があると思います。
そのような整理をした上で、あえて違いに注目するとすれば、いま荒井さんがおっしゃったとおり、「べてる」に比べると、綾屋さんや自分がやっているのは、ちょっと機械論の比重が大きい、という感じですかね。これは比率の違いであって、本質的なものではないと考えています。
「異なる部分」をどう語るのか
荒井 綾屋さんの文章を拝読していると、下手すると誤解されてしまうんじゃないかと思うことがあります。なかなか上手く表現できないんで、少し遠回りしながら説明したいんですけど。先日、朝日新聞の記事で、日本ではADHDが成人の「1.65パーセント」というような記事が出ていました。なんでそんなことを数値化できるんだろうって、そのことも疑問だったんですけど、とにかく記事を読んでみたら、ADHDの紹介が「脳の機能に何らかの障害を持っていて…」という解説からはじまるんです。私はこの「何らかの障害を…」っていう表現が気になるんです。
というのは、脳の機能というか、もっとざっくりと言ってしまうと、人間の個性ってツルツルしたまん丸じゃあり得ないですよね。どこかが凹んでいたり、出っ張っていたりして。たとえばレーダーチャートで人間の個性を測れるとして、測れないと思うけど仮に測れるとして、きれいな円形になる人はほとんどいないはずです。みんな個性があるわけですから、それぞれデコボコしているはずです。で、その凹みや出っ張りの部分を、何の注釈もつけずに「障害」と呼んでしまっていいのかな、という気がするんです。そんなこといったら、「涙もろい」は障害なのか。「笑い上戸」は障害なのか。ということになりかねない。
熊谷 確かに。
荒井 人より動いちゃうとか、人より集中するのが苦手とか。何をもってその部分を「障害」と呼ぶのか。安易に「障害」と呼んでしまう想像力が、すごく気になっているんです。みんなそれぞれの形にデコボコしたレーダーチャートも、10万人分とか100万人分集めて平均をとれば、きっとキレイな円形に近づきます。でも、それが「平均的な個性」だと思われてしまうと大変なんですよね。計算上は平均値なのかもしれないけど、でもそれは実体のないゴーストです。人口層が一番厚いわけじゃなくて、むしろ存在しないんです。
今「発達障害」とか「ADHD」といった障害を医療的にくくって行こうという立場の人たちは、その「平均」が実体的に存在していると思っているのかな、と考えさせられてしまう節があります。その「平均」から突き出たり、凹んだりしている部分をとらえて、何の注釈も付けずに「障害」と言ってしまったいいのかなって・・・。
大切なのは、それを「障害」と呼んでしまうのは、きっと社会側の要請があるからなんですよね。だから私は、綾屋さんのお仕事は、そのデコボコの部分をきちんと言葉にして、それを一気に「障害」と呼んでしまうんじゃなくて、そこに注釈をつけていきましょう、というお仕事だと受け取りました。
熊谷 そうですね。そうかもしれない。綾屋さんに聞いてみないとわからないですけど、たしかにあるかもしれません。綾屋さんのナラティブを聞いてみると、こんな感じです。
つまり、最初物心ついたころから「何かずれてる」と感じていて、でも何がずれているのかということもよくわからない。「どうも自分は他人と繋がれていない」という表現からはじまって、自分の違和感を言語化できないモヤモヤ状態を30年間くらいずっと経験していた。精神科にいって薬が出されるんだけど、飲んだら眠くなるだけで、全然変わらない。なんでこんなことを感じるんだろうということを、いろんな本を読んだりして考えるんだけれど、どれもピンと来ない。
それで、ある日「自閉症」とされる人の手記を偶然読んで、そこに書かれている違和感のディテールが、あまりにも自分とぴったり合うということで、不思議な感傷にいたるんですね。それまでも「自閉症」とか「アスペルガー」とかの教科書的な知識はあったみたいなんですが、それは医学的な記述っていうんですかね。それを読んでも自分には関係ないことだと思っていたんだけど、当事者が書いたものにはピンとくる。そこで、名状しがたいしんどさに、もしかしたら名前が付くかもしれない、ということに思い至るわけです。
そして、それはすごく「生きやすさ」に繋がるんじゃないかと。それで、自分の職場の先輩が専門医だったので、そこに紹介して診てもらうというようなことをしたわけです。
でも、晴れて診断名をもらって、それによって自分の違和感が全部解決したのかというと、むしろスタートだったというか。そして綾屋さんは、三つの問いにぶつかるんですよね。一つは、なんで当事者の手記を読むと「おお」っと身体が反応するのか。もう一つは、でも専門家の記述にはピクリとも身体が動かないのはなぜか。三つ目が、それなのに、なんで専門家の診断書が自分の物語的な構造の中で意味を持つのか。この三つの問いからスタートするんです。特に三つ目ですよね。三つ目が一番誤解されやすいんですけど。なぜ権威ある他者の診断書が必要なのか、っていうところが一番言語化に時間がかかる場所なんです。
とりあえず、ここでは二つ目について私なりに言葉を足しておくと、専門家の言説を読んでみると、納得できない部分があるんです。たとえば「自閉症」の概念にしても、それこそディスアビリティのレベルをインペアメント化している。他者関係とか、社会との相互作用の場で生じるレベルのディスアビリティであるにも関わらず、本人の脳の中になにか特定のインペアメントがあって、それによって社会性に何か障害が生じるという流れが出来つつあるんです。
最近よく聞く言葉だと、「ソーシャル・ブレイン研究」とかですね。脳の中に「ソーシャル」なんてあるわけがないのに(笑)。でも、ソーシャル・ブレイン研究でも、わかっている人たちは、一個の脳の中にソーシャルはないということくらいはわかっているんですよね。そういったことをわかっている人たちは「ソーシャル・ブレインズ」って言っています。Sを付けるか付けないかがすごく重要なんです。複数の脳、あるいは複数の身体の相互作用でソーシャルという現象が起きるということがわかっている人と、一個の脳の中にソーシャルがあるって思っている人とでは、全然方向性が変わるんです。
こういった専門的な研究が、いざ実践の中に翻訳される瞬間に、すごく矮小化されてしまうことを危惧しています。一個のブレインの中にソーシャルなものがあるという理解の仕方になってしまう。でも、これはちょっとおかしい。綾屋さんと自分の関心は、そもそも定義がおかしいっていうところからはじまって、そのディスアビリティのインペアメント化という現象を、どう捉えていったらいいのか、という方向に移って行ったところがあります。
「インペアメントのディスアビリティ化」でもなく、「ディスアビリティのインペアメント化」でもなく
荒井 「コミュニケーション障害」っていう言われ方がされるんですけど、コミュニケーションってそもそも二人いないと成り立たないですよね。私いま子育てしているんでよくわかるんですけど、祖父母が遊びに来て、4人くらいで子どもを見ていると、何やってもかわいいんですよね。茶碗ひっくり返そうが、机の上に載って踊りだそうが・・・
熊谷 余裕がある(笑)。
荒井 はい(笑)。でも1対1だと、「お前いい加減にしろよ!!」って(笑)。私たち夫婦は共働きなので、朝は戦場になるんです。NHKのEテレの「いないいないばあ」ってご存知ですか?
熊谷 知ってます(笑)。
荒井 あれを見せておくと、15分間くらい魔法がかかったように止まってくれるんですよ(笑)。
熊谷 大したもんですね(笑)。
荒井 すごいんです(笑)。そうすると、私たち夫婦は、戦場の15分間の中で全力を尽くすんです。
熊谷 なるほど(笑)。
荒井 でも、変な話ですが、「いないいないばあ」に食いつかない子どもだったら、もしかしたら「発達障害」といわれてしまうかもしれません。「両親をパンクさせてしまう子」になってしまうわけですから。
私たち夫婦が共働きで余裕がない、というのは社会の縮図なわけです。その余裕のない中で、「いないいないばあ」にきちんと食いついてくれるのがモデルケースとしての発達で、食いつかないというモデルケースからずれた人たちが、結局「医療のサポートが必要なんじゃないか」という形でくくられていってしまう、という気がするんですよね。
熊谷 まさにそうです。
荒井 私たち夫婦の仕事の量だとか、朝の出勤時間とか、お互いの体調とか、いろんな相互関係の中で、子どもが「いい子」か「いい子じゃない」かが決まってくるんですよね。子どもが「いい子」かどうかは、その子自身に問題があるよりは――もちろんその子自身の問題も重要なのかもしれないけれども――、まずはそれを受け入れる環境との相関関係なのではないでしょうか。そこをすっ飛ばして、その子個人の問題として語ってしまう語り口が、すごく気になるんです。「人と異なる」「標準とずれる」という点を、あまりにも安易に、個人の医療的な問題に還元してしまう発想は、社会のありようを不問に付してしまう危うさがあります。
以前、シノドスに「できないことを許さない社会」(生き延びるための「障害」――「できないこと」を許さない社会)というのを書かせて頂いて、そこにも書いたことですが、「発達障害は」、ここ十数年で疫学的に増えてきたという話ではないと思うんです。やっぱり、いまの社会のありようの中ではじかれていく人がいる、という風に理解した方がいいわけですよね。
熊谷 いいと思いますね。
荒井 でも気になるのは、それでも医療や福祉のサポートが必要な層が出てくるということです。
熊谷 そうですね。ディスアビリティのインペアメント化も怖いし、インペアメントのディスアビリティ化も怖いです。何が怖いかっていうと、「全部社会のせいだ」といったときに、個々人の多様性がごっそりと無視されてしまう可能性です。多様性が無視されたときに、「では、どんな社会がいいのか」という構想の拠点が失われます。社会に目が向く方向と、自分に目が向く方向と、循環する必要がある。自分を鏡の前に映して、価値中立的にそのままを見る、ということが、翻って社会に向きなおしたときに戦ううえでの価値基盤を与えるというような気がしています。
「ディスアビリティが悪い」「社会が悪い」っていうのは、それだけではイマイチ切れ味が悪い。むしろ、「発達障害」という立ち位置から何を言うかとか、もっと極論すれば、「私」という立ち位置から社会を逆照射するためには、その「私」が何者なのかっていうことを見つめる必要がある。それを1980年代以降、さぼってきたんじゃないかっていうことを自分は感じています。当事者研究と当事者運動が相互循環するためには、そういった作業が必要なんです。
荒井 なるほど。でも、障害者運動の現場などでは、これまで「自分を見つめる」ということが、ある種の語りにくさを帯びていたように思います。
熊谷 そうです。確かに自分語りはネガティブにとらえられてきた経緯があります。「それはインペアメントの記述じゃないか」とか、「医療化なんじゃないか」とか、「自分を見つめて社会は変えられるのか」言われてきたわけですね。でも、実は社会をするどく逆照射するためには、その作業が必要なんじゃないかなと思うんです。自分と綾屋さんがやろうとしたことは、上手くいっているかどうかわかりませんが、まずは「他人とのかかわりに難がある」という既存の定義を一旦脇に置いて、他人が登場しない場面での記述から始めようとしたんです。
「自閉症」において、他人が登場しない場面での記述というのは、実は専門家が一番怠ってきたところです。なぜなら、「他人が登場しない場面の記述」というのは、当事者本人しかできないことだからです。「他人が登場する場面での障害」というふうに定義する背景には、本人と専門家がいる場面で顕在化する問題だけを取り上げようとする発想があって、それは多くの場合、「本人が語れない」という前提からスタートしているんです。
だから『発達障害当事者研究』という本の目次も、他人が出てくるのはなるべく後の章に回しました。第一章は「身体」、つまり自分の身体とのつきあい。第二章は「もの」、他人はまだ出さない。で、第三章は「夢」、まだ他人が本格的には出てきていないかもしれない。これは突っ込みどころがあるんですけど。で、第四章で本格的に「他人」が出てくる、という構成にしたんです。この本のこだわりというのは、ディスアビリティをなるべく出さないということなんですよね。じゃあ、それがインペアメントなのかっていうと、わからないけれども。
荒井 実は、私はそこがすごく気になったんです。綾屋さんのご著書を読んでいて、「ものとつき合うのにこんなに苦労するのは、やっぱり医療モデル的なインペアメントがあるからじゃないか」って理解というか誤解する人が、きっとでてくるような気がするんです。でもそうじゃなくて、「インペアメント」という前に、もっと他の言葉があるんじゃないかっていう気がするんですね。さっきのレーダーチャートの話じゃないですけど、出っ張ったり凹んだりしている個性みたいな部分とか、自分の身体の特徴みたいなものを、出っ張ったりへこんだりしているから障害だよ、インペアメントだよ、っていう前に、もう少し言葉を詰めて、注釈を付けていったほうがいいんじゃないか、と。
熊谷 その辺は確かにそうです。実はインペアメントという言葉は、最近は禁句になっていて、body function and structureって言い換える流れもあります。つまり価値中立的な言い方をしようというわけですよね。自分は、それは「障害」の「害」の字をひらがなにするのと同じような感じがして、あまりしっくり来ていないので、相変わらずインペアメントで通してしまっているんですけど。「そんなの折り込み済みじゃないの…」という気がしてしまう。
インペアメントという言葉にすでにネガティブな価値判断が入っているという批判であれば、じゃあbody function and structureでいいです、みたいなことはありますが……。それは最近のICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)とかにも見て取れますよね。つまり「障害分類」さえ言葉が適切じゃなくて、「生活機能分類」にしようと。そういうことの議論の背景にあるのは、まさにデコボコというか、先ほどのレーダーチャートを価値中立的に、多様性を差異として記述しようというニュアンスなのでしょう。
(つづきは「α-Synodos vol.136」で! → https://synodos.jp/a-synodos)
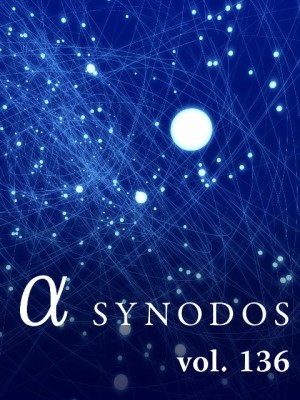
α-synodos vol.136 「異なる部分」と向き合って
荒井裕樹×熊谷晋一郎「『当事者研究』の可能性について語る」
渡邉琢「障害者介助を担う人たち〔バイク屋からの転職篇〕」
坂爪真吾インタビュー「射精介助を考える――『障害者の性』とどう向き合うのか」
松本ハウス×荻上チキ「焦らずに受け入れて――『統合失調症がやってきた』トークショー」
大野更紗「さらさら。」
プロフィール

熊谷晋一郎
新生児仮死の後遺症で、脳性麻痺に。2001年に東京大学医学部医学科卒業。その後、千葉西病院小児科、埼玉医科大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究科博士課程での研究生活を経て、2015年より現職。障害や病気を持った本人が、仲間の力を借りながら、症状や日常生活上の苦労など、自らの『困りごと』について研究する「当事者研究」が専門。著書に「発達障害当事者研究」(綾屋紗月との共著)、「リハビリの夜」(いずれも医学書院)など多数。

荒井裕樹
2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二松学舎大学文学部専任講師。東京精神科病院協会「心のアート展」実行委員会特別委員。専門は障害者文化論。著書『障害と文学』(現代書館)、『隔離の文学』(書肆アルス)、『生きていく絵』(亜紀書房)。


